日本神話に登場する、重要ワード、重要エピソードをディープに掘り下げる「日本神話解説シリーズ」。
今回は、
「天磐櫲樟船」「鳥磐櫲樟船」「鳥之石楠船神」
をテーマにお届けします。
『日本書紀』では、「天磐櫲樟船」「鳥磐櫲樟船」と伝え、蛭児を流棄するための「特別な船」として登場。
『古事記』では、神生みの中で「鳥之石楠船神(亦の名は天之鳥船)」と伝え、のちに国譲りの交渉役として活躍します。
今回は、流すために使われたり、神となって交渉役として活躍したりするスペシャルな船について、日本神話をもとにディープに掘り下げます。
『古事記』の鳥之石楠船神
目次
『古事記』では、神生みの中で伝えてます。
次に生んだ神の名は、鳥之石楠船神、亦の名は天之鳥船という。次に大宜都比売神を生んだ。次に火之夜芸速男神を生んだ。亦の名は火之炫毘古神と謂う、亦の名は火之迦具土神という。
ということで。
石のように固い楠材の船の神。
「鳥」を冠するのは、天空を飛翔する鳥と海洋を航行する船とが結びつくほか、天と海とが水平線で一続きになるから。万葉集でも「天の海に雲の波立ち月の船 星の林に榜ぎ隠る見ゆ」(詠天1068番)とあります。
天磐櫲樟船、鳥磐櫲樟船 とは
まずは『日本書紀』からご紹介。
『日本書紀』では、「天磐櫲樟船」「鳥磐櫲樟船」と伝え、蛭児を流棄するための「特別な船」として位置づけられてます。
『日本書紀』神代巻一第五段、本伝と〔一書2〕の2箇所に登場。
| 本伝 | 天磐櫲樟船 | 風の順に放棄 | 天、風が運んでいく |
| 一書2 | 鳥磐櫲樟船 | 流の順に放棄 | 鳥、流で水鳥が運んでいく |
いずれも、
放棄用として「流れ」を生み出すものとして、天=風→風の流れ、水鳥=流→水の流れ といった対応関係が設定されている。
「天磐櫲樟船」「鳥磐櫲樟船」の原義
①「天」「鳥」・・・流棄用の船として、「流れ」を生み出すものとして冠されてます。
- 天=風 →風の流れ
- 水鳥=流 →水の流れ
といった対応関係が設定されてます。
②「磐」・・・立派なの意味。
③「櫲樟」・・・クスノキの別称。常緑樹。
独特な香があり「臭き木(くすしき)」が語源。防虫剤である樟脳の原料。古代より、その独特の香りから邪気を払う呪力があるとされてきました。
また、〔一書5〕で、素戔嗚尊が「杉と櫲樟とを「浮宝=船」にすべし」と伝え、船の建造用材としてクスノキがあったことが分かります、また、考古学的調査からは、実際にクスが古代船の船材として多用された発掘も相次いでいます。
天磐櫲樟船の登場箇所『日本書紀』巻第一(神代)第五段 本伝
最初に登場するのは、「天磐櫲樟船」として。『日本書紀』巻一(神代紀)第五段〔本伝〕です。
伊奘諾尊と伊奘冉尊の協議により「天下之主者(地上世界の統治者)」を生む流れへ。尊の側として位置づけられる日神と月神、卑の側として位置づけられる蛭児と素戔嗚尊。
以下、蛭児誕生の箇所より抜粋。
次に蛭児を産んだが、三歳になっても脚が立たなかった。それゆえ天磐櫲樟船に乗せ、風のまにまに棄てた。
次生蛭兒 雖已三歳 脚猶不立 故載之於天磐櫲樟船 而順風放棄 (引用:『日本書紀』巻一(神代紀)第五段〔本伝〕より)
ということで。
神生みのなかで生んだ「蛭児」は三歳になっても脚が立たなかったので、これを理由として放棄した。その際に使用したのが「天磐櫲樟船」です。
鳥磐櫲樟船の登場箇所『日本書紀』巻第一(神代)第五段〔一書2〕
次に登場するのは、「鳥磐櫲樟船」として。神代紀の、同じく第五段〔一書2〕から。
第五段〔一書2〕は、第四段〔本伝〕の一部要約からスタート。柱巡りの際に、原理を違えて陰神が先唱。これが原因で、蛭子や素戔嗚尊が生まれたとしてます。
ある書はこう伝えている。日と月は既に生まれた。次に蛭児を産んだ。この子は三年経っても脚が立たなかった。
これは初めに、伊奘諾・伊奘冉尊が御柱を巡った時に、陰神が先に喜びの声を発したからである。陰陽の原理に背いてしまったのだ。そのせいで今蛭児が生まれた。ー中略ー
次に鳥磐櫲樟橡船を産んだ。この船に蛭児を乗せ、流れにまかせ棄てた。
一書曰。日月既生。次生蛭児。此児年満三歳、脚尚不立。初伊奘諾・伊奘冉尊、巡柱之時。陰神先発喜言。既違陰陽之理。所以今生蛭児。ー中略ー 次生鳥磐櫲樟橡船。輙以此船載蛭児、順流放棄。 (引用:『日本書紀』巻一(神代紀)第五段〔一書2〕より)
ということで。
第五段〔本伝〕同様、三年経っても脚が立たない障害をもつ児であったので「鳥磐櫲樟橡船」を生んで、この船に載せ流したと伝えます。
天磐櫲樟船、鳥磐櫲樟船 のポイント
天磐櫲樟船、鳥磐櫲樟船は、
なぜ流すのか?
という理由理解が不可欠。この理由が分かれば、そのためのツールとして船が使用されたことが見えてきます。
結論から。
「不祥」の結果というのは「穢悪」な存在であり、
本来的に「濯除」など、水による濯滌・除去を必要とするものだから。そんな考え方があるから。
蛭児とは、「不祥の子」なんです。
第四段〔本伝〕で、伊奘諾尊が「吾是男子、理当 先唱 。如何婦人反先 言乎。事既不祥。」と述べてましたが、まさにコレ。「陰神先唱」にかなりキレてました。
この「不祥」については、類例があって、
ただし、伊奘諾尊は自ら泉国を見てしまった。これはまったく良くないことであった。それで、その穢れを濯ぎ除こうと思った。
但親見 泉国 。此既不祥。故欲 濯除 其穢悪 。 (引用:『日本書紀』巻一(神代上)第五段〔一書10〕より)
つまり、
「不祥」の結果というのは「穢悪」な存在であり、
本来的に、水による濯滌・除去を必要とする、という考えがあるんです。
コレ、大事。
不祥=穢れてる、だから水で流す、除去する。
そういう概念があるからこそ、
流れにまかせて棄てた「順 流放棄」という表現になってる。
そこには水による穢れの除去、祓いの意味が込められてるってこと。
周到な処分を行ったと解釈すべきというのも合わせてチェックです。




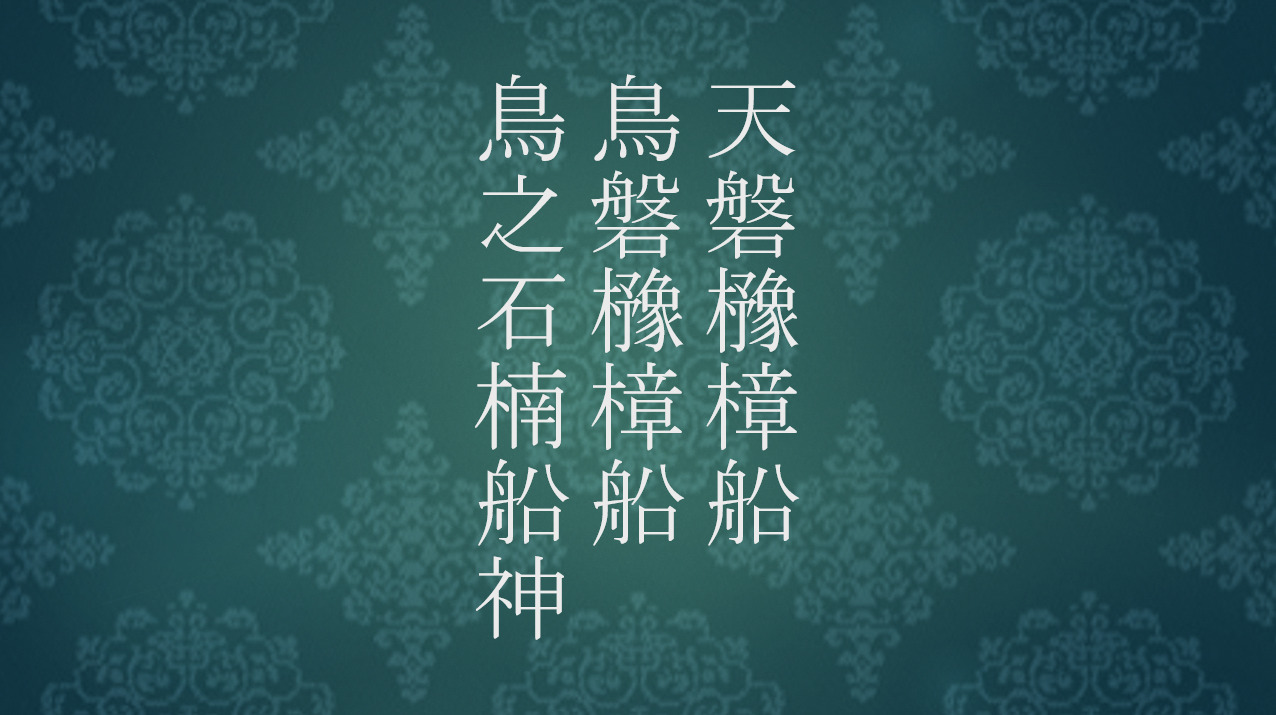








最後までお読みいただきありがとうございます。お気軽にコメントされてくださいませ。お待ちしております!