多彩で豊かな日本神話の世界へようこそ!
日本最古の書『古事記』をもとに、
最新の文献学的学術成果も取り入れながら、どこよりも分かりやすい解説をお届けします。
今回は、『古事記』上巻から、
天地開闢
天地初発から次々に神が誕生し、神世七代まで続く『古事記』版「天地創生神話」を分かりやすく、ディープに解説。
概要で全体像をつかみ、ポイント把握してから本文へ。最後に、解説をお届けしてまとめ。
現代の私たちにも多くの学びをもらえる内容。日本神話から学ぶ。日本の神髄がここにあります。それでは行ってみましょう!
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
『古事記』天地開闢|原文と現代語訳|神名を連ねて物語る古事記の天地開闢を分かりやすく解説!
目次
『古事記』天地開闢のポイント
『古事記』版天地開闢。
上巻・中巻・下巻と、全部で3巻ある『古事記』の「上巻」本文がここから始まる。。
って、その前に、序文はしっかりチェック。
その上で、、天に5柱の「別天神」、次いで12柱の「神世七代」という神々の出現を、神名を連ねる手法で物語ります。
で、『古事記』については、、当サイトとしては、是非、
正史『日本書紀』と比較しながら、読み進めていただきたいド━(゚Д゚)━ン!!
その方が、『古事記』の注力しているポイントがとっても分かりやすくなる。コチラ!
『日本書紀』の方は、天地開闢に始まる神々の誕生を、陰陽や易といった原理的思想をもとに物語ってます。
そして、「本伝」のほかにも多くの「異伝」を併載、列挙して、神話を多面的・多角的に伝えようとしてる。ココがポイント。
天地開闢については、『日本書紀』では本伝と異伝(一書)の計7種類の伝承が共存しながら、ああだこうだと多様な世界を繰り広げているわけです。
それに対して、
『古事記』は本文は一つ。終始一貫して統一的な世界を構築してます。異伝など存在せず、あっても本文を説明するための「注」にすぎません。
書紀のようにああだこうだと言わない分、洗練された「物語」として完成度も高いと言えます。
そして、「天地開闢」については、『古事記』では、神々の誕生と、その尊貴さを示すことに注力してる。もう、コレだけ分かってくれればそれでいいんだよ、と言わんばかりの、格付け(カテゴリ分け)の嵐であります。
と、こういうことも、
『日本書紀』との比較のなかで初めて分かる。何度も言いますが、『日本書紀』との比較を通じて『古事記』を解釈するのが激しくおススメ!
ということで、早速、現場をチェックです。
『古事記』天地開闢の原文と現代語訳
古事記 : 国宝真福寺本 上 国立国会図書館デジタルコレクションより 天地が初めて發った時に、高天原に成った神の名は、天之御中主神。次に、高御産巣日神。次に、神産巣日神。この三柱の神は、みな独神と成りまして、身を隠した。
次に、国が稚く浮いている脂のように海月なすただよえる時に、葦牙のように萌え騰る物に因って成った神の名は、宇摩志阿斯訶備比古遅神。次に、天之常立神。この二柱の神も、みな独神と成りまして、身を隠した。
上の件の五柱の神は、別天神である。
次に、成った神の名は、国之常立神。次に、豊雲野神。この二柱の神も、独神と成りまして、身を隱した。
次に成った神の名は、宇比地邇神、次いで妹 須比智邇神。次に、角杙神、次いで妹 活杙神。次に、意富斗能地神、次いで妹 大斗乃辨神。次に、於母陀流神、次いで妹 阿夜訶志古泥神。次に、伊耶那岐神、次いで妹 伊耶那美神。
上の件の、国之常立神より下、伊耶那美神より前を、あわせて神世七代という。上の二柱の独神は、おのおのも一代という。次に双へる十柱の神は、おのおのも二柱の神を合わせて一代という。
※音指定の「注」は、訳出を分かりやすくするため割愛。
天地初發之時、於高天原成神名、天之御中主神訓高下天、云阿麻。下效此、次高御產巢日神、次神產巢日神。此三柱神者、並獨神成坐而、隱身也。
次、國稚如浮脂而久羅下那州多陀用幣流之時流字以上十字以音、如葦牙、因萌騰之物而成神名、宇摩志阿斯訶備比古遲神此神名以音、次天之常立神。訓常云登許、訓立云多知。此二柱神亦、獨神成坐而、隱身也。
上件五柱神者、別天神。
次成神名、國之常立神訓常立亦如上、次豐雲上野神。此二柱神亦、獨神成坐而、隱身也。
次成神名、宇比地邇上神、次妹須比智邇去神此二神名以音、次角杙神、次妹活杙神二柱、次意富斗能地神、次妹大斗乃辨神此二神名亦以音、次於母陀流神、次妹阿夜上訶志古泥神此二神名皆以音、次伊邪那岐神、次妹伊邪那美神。此二神名亦以音如上。
上件、自國之常立神以下伊邪那美神以前、幷稱神世七代。上二柱獨神、各云一代。次雙十神、各合二神云一代也。 (『古事記』上巻より一部抜粋)
『古事記』天地開闢の解説
『古事記』版天地開闢(正確には、天地初発)いかがでしたでしょうか?
物語が一本なので、非常に分かりやすいですよね。「物語」として洗練されており、完成度が高い。
ただ、、単線なので、なんでそうなってるのか?みたいなところが分かりにくい。
例えば、冒頭の「天地が初めて發った時に、、」というところ、コレ、天と地が初めてできた時のことを伝えてる、、、くらいしか言いようがない。比較するものがないと、そうなってしまいがち。
そこで登場するのが、『日本書紀』。
先ほど触れたとおり、『古事記』は『日本書紀』との比較を通じて解釈すると、注力ポイントがめっちゃ分かりやすくなる。
天と地ができた時のことを伝えてる、くらいしか言いようがない、という所も、
『日本書紀』では天と地ができる前の状態から描いている、てことは、『古事記』はその部分は端折られてる。つまり、重要感をおいてないんだな、つまり、天地の形成プロセスより、神々の誕生の方が伝えたいんだな、と、『古事記』独自の、『古事記』ならではの注力ポイントが分かるようになってくるんです。ツウとしては、こういう楽しみ方がオススメ。
てことで、
以下そんなテイストで解説を。

次!
→ここまでの神様が独神。単独で誕生した尊い神という位置づけです。
神の詳細はコチラで。
⇒「国之常立神|国土神として最初に化成し、独神として身を隠す神世七代の第一代」
⇒「豊雲野神|国土神として化成し独神で身を隠している神世七代の第二代」
いずれも、独神として成り、すぐに身を隠す、つまり、この後に誕生する双神に活躍の場を譲る。非常に奥ゆかしいスタンスであります。
次!
- 次に成った神の名は、宇比地邇神、次いで妹 須比智邇神。次に、角杙神、次いで妹 活杙神。次に、意富斗能地神、次いで妹 大斗乃辨神。次に、於母陀流神、次いで妹 阿夜訶志古泥神。次に、伊耶那岐神、次いで妹 伊耶那美神。
- 次成神名、宇比地邇上神、次妹須比智邇去神此二神名以音、次角杙神、次妹活杙神二柱、次意富斗能地神、次妹大斗乃辨神此二神名亦以音、次於母陀流神、次妹阿夜上訶志古泥神此二神名皆以音、次伊邪那岐神、次妹伊邪那美神。此二神名亦以音如上。
→いっぱい出てきました、、、男女ペアで誕生する神様たち。5世代。
「妹」は女性の意味。なので「妹」の接頭語がついていない神名が男性神ということになります。誕生した神様の概要はコチラ↓
神世七代の双神のみなさん
| 第3世代 | |
| 第4世代 | |
| 第5世代 | |
| 第6世代 | |
| 第7世代 |
まー、いっぱい。豊かな感じになってきました。
ちなみに、、
「神世七代」における男女ペア神は、『日本書紀』では4世代です。伝えるのは、『日本書紀』第二段本伝と、第三段一書1の2箇所。
ちょっと抜粋列挙してみます。
- 第二段本伝:次に神があった。泥土煑尊、沙土煑尊である。次に神があった。大戸之道尊、大苫辺尊である。次に神があった。面足尊・惶根尊である。次に神があった。伊奘諾尊・伊奘冉尊である。
- 第三段一書1:まず泥土煮尊、沙土煮尊があった。次に角樴尊、活樴尊があった。次に面足尊、惶根尊があった。次に伊奘諾尊、伊奘冉尊があった。
ということで、
何が言いたいかというと、『古事記』の男女ペア神=双神はこれらを結びつけた神名列挙になってるってこと。
『日本書紀』第二段本伝「大戸之道尊、大苫辺尊」と、第三段一書1「角樴尊・活樴尊」を合体!盛り込んで、全5世代としてるわけです。
当てられてる漢字は違いますが、『古事記』では、意味的には、最初は泥砂状態の土台に杙を打ち込んで固め、その上に構造物を建造するという展開。『日本書紀』と比べて一世代増えてるので、そのぶん、その後のお互いの賛美、誘い合い、、、の流れはナチュラルになってます。
コレはこれで記紀先後論争に入るのですが、ここから見ても、神代紀をもとに古事記が成り立ってるとみる方が自然なんですよね。神代紀の本伝と一書をつなげてできたのが『古事記』、、補足でした。
次!
- 上の件の、国之常立神より下、伊耶那美神より前を、あわせて神世七代という。(上の二柱の独神は、おのおのも一代という。次に双へる十柱の神は、おのおのも二柱の神を合わせて一代という。)
- 上件、自國之常立神以下伊耶那美神以前、幷稱神世七代。上二柱獨神、各云一代。次雙十神、各合二神云一代也。
→5柱の「別天神」が誕生した後、続いて誕生する「独神」2柱と、「双神」10柱の計12柱。
これらの神々の総称。「神世七代」という神様カテゴリ。
「神世七代」については、神名に注目。
コレ、実は、
世界が次から次へと形をとって展開するさま
を表象してると考えられるんです。新しく、次々に形作られていく様子を、神名が表現していると。
ただ、その意味については、様々な説があり、いまだに決着をみていません。
こんな感じ。
| 代 | 神 | 説① | 説② | 説③ |
| 1 | 国之常 | 国の恒常的確立 | 国土の根源 | 神々の生成の場としてのトコの出現 |
| 2 | 豊雲野 | 雲の覆う原野 | 原野の形成 | 神々の生成を具現化している二元的な場 |
| 3 | 宇比地&須比智 | 男女一対の盛土(地鎮) | 土砂の発生 | 神の原質としての泥と砂 |
| 4 | 角杙&活杙 | 棒杙(境界の形成) | 杙の打ち込み | 現れ出ようとする最初の形 |
| 5 | 意富斗&大斗乃 | 門棒(住居の防塞) | 居住の完成 | 男女神の性が形態として表面化したこと |
| 6 | 淤母陀&阿夜訶 | 男根・女陰の神像(生産豊穣の霊能) | 人体の完備・意識の発生 | 形態の完備を体と用の両面から言ったもの |
| 7 | 伊耶那岐&伊耶那美 | 交歓の2面像(媾合生産) | 夫婦の発生 | 完全体としての神の身体的出現の次第を表すもの |
まーいろいろある訳です。
ただ、
神世七代の神名の要点をまとめると、以下になります。
| 神名 | 表象するもの |
| 国常立 | 天の常立神に続き、それと対応して成る国の恒常的確立(予祝) |
| 豊雲野 | 地上世界に豊かな雲のわき立つ野が出現したこと、地上世界の豊穣(予祝) |
| 宇比地&須比地 | 天→国、雲野→泥砂という対応に即した、地上世界の土台 |
| 角杙&活杙 | 土台としての大地に標識となる杙を打ち込む |
| 意富斗&大斗乃 | 打ち込んだところに(外と内を隔てる)戸(門)を造立 |
| 於母陀&阿夜訶 | 男と女をそれぞれ「面足る」「あや畏ね」と称える |
| 伊耶那岐&伊耶那美 | 男と女とが互いに誘いあう |
これ、ホントによくできた神名になっていて。
表象しているのは、神の世に、新しく世界が次々に具体的な形をとって展開するさまであり、以下のような物語展開。
- 先ずは、国(国土)が恒久的に(永久に)確立することを予祝
- その国(国土)に、豊穣を約束する「雲のわき立つ野」が出現することを予祝
- そのうえで、双神により具体的な表れとして、大地の土台ができ、そこに標識となる杙を打ち込み、戸を造立する
- そして、その中で結婚に向け、男女の神により、互いに全き性を具有することを称えあい、誘い合う、、
ステキですね。ゾクゾクします。
日本的な、極めて日本的な、世界創生の物語。
特に大きいのは、伊耶那岐&伊耶那美の誕生です。
この2柱の神が誕生する前は、国や野が誕生したり、土台とか杙とか、表象内容は外観・外見にとどまっているのですが、
伊耶那岐&伊耶那美の登場によって、男と女が互いに誘い合い、心を交わせ、お互いの存在を認め合うようになります。
これは、つまり、男女が一体化しようと声を掛け合っているという事。
ポイントはまさにここで。
要は、
日本神話的世界創生は「最終的に収斂していく事」にあります。
一体のものとして収れんするのです。
国→野→土台→男と女の誕生、そして一体化。
男と女という、本来的にあい異なる性が、異なればこそ、互いに誘いあって一体化しようとする本質的・根源的なありようを表象している。。
って、こんな世界創生を描いているところが他にあるのでしょうか。。いや、ない!
神の世の最後に、男女が互いに誘いあう本来的なあり方を表象する神が出現したことにより、神世七代という世界も完成をみる、とも言えて。
だからこそ、そのあとに、いよいよ具体的な国や神々が誕生していく流れができてくる訳です。
神世七代、その位置づけを全体の文脈から見るととても奥ゆかしい内容になっていることが分かります。ココ、しっかりチェック。
『古事記』天地開闢まとめ
『古事記』天地開闢
天地の初発から次々に神が誕生し、神世七代まで続く『古事記』版「天地創生神話」。いかでしたでしょうか?
天に5柱の「別天神」、地には7代の「神世七代」という神々の出現を、神名を連ねる手法で物語ってます。
以下、ポイントまとめ。
- 『古事記』的には、世界の生成過程や陰陽理論よりも、天地が初めてできたときの高天原に生まれた神のほうを伝えたい。
- 高天原とは、天地開闢の最初から存在し、非常に尊貴な神々が誕生した、めちゃくちゃ尊い場所である。
- 最初に誕生するのは「造化三神」。「造化」とは形づくられること。神の場合、「化す」という運動の中で、造形物として成る。
- 三神のポイントは関係性。一番大事なのは、天之御中主神。高天原系の神の代表である高御産巣日神と、出雲系の神の代表の神産巣日神を融和的に止揚する立ち位置。
- 続けて登場する神カテゴリは「別天神」。『日本書紀』で設定されてる「神世七代」に先立って、それよりも尊貴な神として位置づける。
- 続けて登場する神カテゴリは「神世七代」。神名を通じて、世界が次から次へと形をとって展開するさまを表象。
- 最後の世代、伊耶那岐&伊耶那美の登場によって、男と女が互いに誘い合い、心を交わせ、お互いの存在を認め合うようになる。つまり、日本神話的世界創生は「最終的に収斂していく事」にある。
- だからこそ、そのあとに、いよいよ具体的な国や神々が誕生していく流れになっていく。
以上、是非チェックされてください。
当サイトとしては、是非『日本書紀』と比較しながら読み進めていただければと思います。そうすることで『古事記』の独自性や注力ポイントが見えてくる。コレ、激しくおススメです。
続けて、国生み神話!コチラ↓で分かりやすくディープに解説!
天地開闢を『日本書紀』と比べて楽しむツウな方はコチラ!
『古事記』版天地開闢を知るには神を知れ!!
「造化三神」「別天神」「独神」「神世七代」についてはコチラで解説中!
●必読→「造化三神|天と地ができたその原初の時に、高天原に成りました三柱の神神。」
●必読→「別天神(ことあまつかみ)|神世七代に先立って特別に誕生した5柱の神々。」
●必読→「独神(ひとりがみ)|単独で誕生し、男女の対偶神「双神」と対応する神。」
造化三神&別天つ神
●必読→「天之御中主神|高天の原の神聖な中央に位置する主君」
●必読→「高御産巣日神|2番目に化成した独神で別天つ神」
●必読→「神産巣日神|3番目に高天の原に化成した独神」
別天つ神
●必読→「宇摩志阿斯訶備比古遅神|葦芽のように勢いよく芽生え伸びてゆくものを依代として化成した独神」
●必読→「天之常立神|国土浮漂のとき、葦芽に依って化成した独神」
神世七代
●第1世代→ 国之常立神:国が恒常的に(永久に)立ち続ける神
●第2世代→ 豊雲野神:豊かな、雲の覆う野の神
●第3世代(男→ 宇比地邇神:最初の泥土の神
●第3世代(女→ 妹 須比智邇神:砂と泥土の神
●第4世代(男→ 角杙神:角状の棒杙の神
●第4世代(女→ 妹 活杙神:活きいきとした棒杙の神
●第5世代(男→ 意富斗能地神:偉大な戸の男神
●第5世代(女→ 妹 大斗乃辨神:偉大な戸の女神
●第6世代(男→ 於母陀流神:顔つきが整って美しいと称える神
●第6世代(女→ 妹 阿夜訶志古泥神:まあ何と恐れ多いことよと畏まる神
●第7世代(男→ 伊耶那岐神:いざなう男の神
●第7世代(女→ 妹 伊耶那美神:いざなう女の神
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
[itemlink post_id=”13035″] [itemlink post_id=”13037″] [itemlink post_id=”13038″] [itemlink post_id=”13039″]
よくある質問(FAQ)
Q:天地初発とは?
A:天と地ができた世界のはじまりのこと。『古事記』では、「天地が初めて發おこった時に(天地初發之時)」と記し、天と地が發る、つまり、世界が始まるという出発的な意味で表現されてます。また、『古事記』の天地初発の特徴は、最初から高天原が用意され、造化三神が誕生する点。世界の生成過程や陰陽理論よりも、天地が初めて發おこったときの高天原に生まれた神を伝えることに注力しています。
Q:天地の始まりはいつ?
A:『古事記』では天と地ができた世界のはじまりがいつなのか?は伝えてませんが、例えていえば、宇宙の「始まり」とされる「ビッグバン」と同じく気の遠くなるような遥か昔のことです。『古事記』では、いつだったのか?よりも、どんな神が誕生したのか?のほうが重要であり、神々の誕生を通じて天地の始まりを描写しています。
Q:天地開闢の地とは?
A:『古事記』では、天と地ができた場所がどこなのか?は伝えていません。特定の場所で発生したわけではなく、世界のはじまりとして、より広く大きな概念で想像する必要があります。唯一、『古事記』が伝えてるのは高天原という場ですが、これも天空に想定されているため、地上世界における特定の場所を伝えている訳ではありません。
Q:天地開闢の三柱とは?
A:天之御中主神、高御産巣日神、神産巣日神の三柱の神をいいます。三神のポイントは関係性です。天之御中主神は、高天原の中央に主として座す神として、他の二神の中央に位置します。一方、高御産巣日神は高天原系の神の代表、一方の神産巣日神は出雲系の神の代表として位置づけられています。
Q:アメノミナカヌシ様 なんの神様?
A:天之御中主神は、はじまりの神ですが、役割としては、高御産巣日神、神産巣日神の二神を融和的に止揚する神です。高天原系と出雲系は対立的関係でありつつ、高天原系の神が出雲系の神を支配する関係でもあるので、両神を融和的に止揚する必要があります。この、神話的要請に応える存在が、天之御中主神です。
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




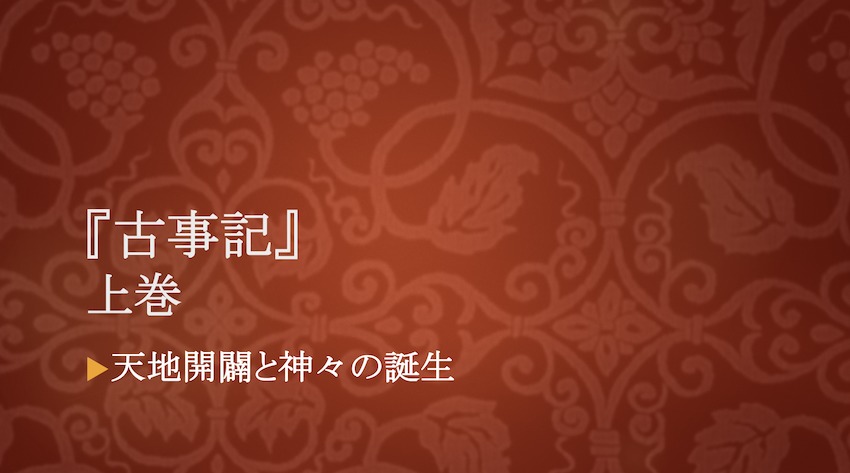



















→ 『古事記』版の天地開闢。。厳かな雰囲気を感じて。
先に細かいところを。「天地が初めて發った時に(天地初發之時)」とありますが、この中で「発」の訓みには諸説あり。
近世以後は「ひらけし」など「ひらく」系で訓むのが多く、だとすると「天地が初めて發いた時に」となります。コレは『古事記』序文でも「乾坤初分」や「天地開闢」とあり、世界の始まりを天と地が分かれていく形で表現してる、というのが根拠。
一方、『古事記』の他の箇所では、「発」は「おこる」「たつ」と訓まれてるので、用例重視の本エントリではこれを採用。「ひらく」だったとしたら、それこそ「開」とか「分」などの文字が使われていたはず。ココでは、コレから『古事記』的神話世界が始まる、つまり、出発的な意味合いで使われてるとしています。
その他、チェックしておきたいポイントは4つ。
①『古事記』は、天と地が誕生するところから始まってる。
「天地が初めて發った時に」とあり、天と地ありきの天地開闢。コレ、結構重要なポイントで。
なんで誕生したの?とか、どうやって誕生したの?っていう質問は受け付けておりません。天と地ができたところからのスタート。
これに対して、『日本書紀』では、その前の段階の「混沌」から始まり、陽の気が天へ、陰の気が地へ、、といった天地の形成プロセスを伝えてます。
参考として、『日本書紀』の冒頭がコチラ。
ということで。
全然違いますよね。 スゴイ、、説明臭いというか、理論ガチガチというか。。。これが『日本書紀』の世界。
一方の『古事記』は、こういう天地の形成プロセスは省かれてる。
「天地が初めて發った時に、高天原に成った神の名は」と、天地ありき。なんなら高天原ありきで伝えてる訳です。
このことから、
『古事記』的には、そんな世界の生成過程や陰陽理論がどうのよりも、天地が初めて發ったときの高天原に生まれた神のほうを伝えたい、ということが分かります。
コレ、『日本書紀』と比較することで初めて浮かび上がってくる。比較によって『古事記』の独自性とか、『古事記』が注力したいポイントが見えてくるんです。
ちなみに、『古事記』的には、「天」は「高天原」に繋がり、「地」は「国」を経て葦原中国へと繋がっていきます。後ほど再チェック。
次!
②『古事記』は、高天原という至高の場がすでに用意されている。
コレも、超重要ポイント。
すでにあるんすよ、高天原。
どうやってできたのか?なんて関係なく。あるの高天原。
ポイントは、高天原とは、天地初發から存在し、非常に尊貴な神々が誕生した、めちゃくちゃ尊い場所であるってこと。
誕生経緯や理由はいいから!とにかくコレだけ理解してくれればそれでいいの! とでも言わんばかりの『古事記』。
高天原について、突っ込んだ解説はコチラから↓
高天原とは、「天原」という広大な天空の広がりをもとに、それより一段と高い領域の、非常~に尊い場所であり、至尊神が都を造営して世界を統治するに相応しい場所。ってことで。この、「場の尊さ」が非常に重要なんです。
ちなみに、高天原には「安の河」も流れていますし、八百万神が集い神事も行います。いわば、古代人の理想的な至高の世界観をぎゅっと凝縮した場、それが高天原。とも言えますね。
次!
③『古事記』は、造化三神とよばれる神が誕生している。
『古事記』は、天地が初めてできたときの高天原に生まれた神を伝えたい、てことで。さっそく誕生するのが「造化三神」。
コレ、元は、『古事記』「序」に記載されております。『古事記』序文とは、『古事記』の概要をまとめた箇所。本文の前、冒頭部分にあり。
そこから「造化三神」を抜粋します。
ということで。
「乾坤」とは、ココでは、天と地のこと。「陰陽」とは、男女の両性のこと。「群品」とは、万物のこと。
で、一番大事なのは「造化」。
「造化」とは形づくられること。神の場合、「化す」という運動の中で、造形物として「成る」。他にも、「化成」「化生」と言った言葉が神の誕生に使用される。日本神話的な、特別な表現であります。後ほど再解説。
なので、「造化三神」という言葉は、『古事記』本文ではなく序文に伝える内容をもとにしてる。そして、三神をひとつのカテゴリとし、それが最初に出現した、至尊の神としてること、チェックです。
誕生した神の詳細はコチラ↓で!
⇒「天之御中主神|高天の原の神聖な中央に位置する主君。天地初発の時に高天の原に化成した最初の神」
⇒「高御産巣日神|造化三神の一柱で、天之御中主神に次いで二番目に化成した独神で別天つ神。」
⇒「神産巣日神|造化三神の一柱で3番目に高天の原に化成した独神。生命体の蘇生復活を掌る至上神。」
で、ココからが大事。
三神のポイント、それは「関係性」です。
一番大事なのは、やっぱり、天之御中主神。
天、高天原の中央に主として座す神として、同じく高天原に化成した高御産巣日神と神産巣日神とのちょうど真ん中に当たる神として位置付けられます。
高御産巣日神は高天原系の神の代表、一方の神産巣日神は出雲系の神の代表として、それぞれ活躍。『古事記』ではそういう設定になってる。
一方で、
高天原系と出雲系は対立的関係でもあり、とは言え、高天原系の神が出雲系の神を支配する関係でもあるので、それゆえに、両神を融和的に止揚する必要があります。アウフヘーベン!
この、神話的要請に応える存在が、天之御中主神。
この関係性が激しく重要なので、しっかりチェックされてください。アウフヘーベン!
最後に4つめ。
④最初に誕生した三神は、独神。そしてすぐに身を隠す。
「みな独神と成りまして、身を隠した」とあります。成ってすぐに身を隠した、、、って、YOUは何しにこの世界へ?そして、どこ行った、、?? まさに、「なにごとの おはしますかは 知らねども かたじけなさに 涙こぼるる (作:西行)」の境地。よー分からんのであります。それがなんかスゴい。。この奥ゆかしいスタンスを念頭に。。。
「独神」について、突っ込んだ解説はコチラから↓
ポイントは、『古事記』では、「独神」は全て「隠身」と組み合わせてるってこと。「独神成坐而、隠身也(独神と成りまして、身を隠した)」
まず、「独神」とは、単独で誕生し、男女の対偶神を指す「双神」と対応する神のことを言います。先に「独神」が誕生し、続いて、その後に「双神」が誕生するという流れ・順番。
それを受けての、「身を隠す」という内容。組み合わせ。で、「隠身」といえば、国譲りを迫られた大国主神が執った処身方法で。
天孫に国を譲り、わが身は表の世界から立ち退くこと。コレが「隠身」。
つまり、
「独神」として身を隠すとは、「双神」に彼らの活躍するこの世界を譲り、立ち退くことをいいます。
言い方を変えると、
独神が身を隠すことで、双神の活躍に道を拓いた。身を隠しながらも、双神が生みなしたこの世界と神々とに関わり、その活躍を導き、あるいは助力する存在であり続ける。。
ってことで、、俄然、スゴイ神のような気がしてきましたね!?
実際、「双神」の代表格は、伊耶那岐と伊耶那美神で。コレ、まさに世界を創生する2神。国生みも神生みも、この世界を形作ったのは双神の御業な訳です。それだけでも十分すぎるほど尊い話なんですが、こうした「双神」の活躍も、「独神」が身を隠しながらも陰ながらサポートしていたからこそ、とも言えて。。
『古事記』の独自な世界を、この独神が担っているといっても過言ではない、非常に奥ゆかしく、それゆえ尊い存在であることチェックです。
ちなみに、、
『古事記』の「独神」は、『日本書紀』巻第一(神代上)第一段 本伝の「純男神」に相当するものとみるのが自然です。
こちらも合わせてチェックされてください。
次!
→「造化三神」のあとに続けて誕生する二神。
詳細コチラで。
●必読→「宇摩志阿斯訶備比古遅神|立派な、萌え出る葦の芽の男神」
●必読→「天之常立神|国土浮漂のとき、葦芽に依って化成した独神」
なんか、、尊いですよね。雰囲気からして。スゴイです。
ポイントは「国が稚く浮いている脂のように海月なすただよえる時に」のところ。コレ、『日本書紀』がベースになってる表現で。。参考として、『日本書紀』巻第一(神代上)第一段〔本伝〕では以下のように伝えてます。
ロマンやー。。。古代日本人が構想し想像した世界のはじまりの描写。。。
特に、「海月なすただよえる時に」原文「久羅下那州多陀用幣流之時流字以上十字以音」のところ。「流字以上十字以音」とあり「流」以上10文字を音読み指定付き。なので「久羅下那州多陀用幣流」は、「海月なすただよえる」、つまり「クラゲのようにただよっている」という訳になる次第。この「ただよへ(え)る」という音の響きを古代日本人が持っていたことが伺えて、ロマンをかきたててくれますよね ←私だけ?
そんなことより、こっち↓が大事。
『日本書紀』版天地開闢では、「洲」と「国」は使い分けがされていて、「洲」は国土的なもの。なんなら巨大な土のカタマリくらいの勢いで。当然、統治者も人民もおらず、領域も確定しておりません。一方、「国」とは国家のこと。当然、統治者も人民もいて、支配のおよぶ領域がある。『日本書紀』では、「洲」からはじまり「国」へ移行し「葦原中国」へつながっていきます。
これをもとに考えると、『古事記』の「国が稚く」と伝える「国」って、、、??いきなり登場?? なんですが、、「稚く」とあるので、それこそ『日本書紀』が伝える「洲」と同じで、のちに国になっていく前段階の状態を言ってると考えられる訳です。いわば、『古事記』的意訳であり、『日本書紀』的な「洲」を「国」へ。使い分けとか、理論理屈にのっとった段階(プロセス)とかはいいから、国にしときます。的なスタンス。
なお、冒頭の「天地初発」のところで解説したとおり、「天」は「高天原」に繋がり、「地」は「国」を経て「葦原中国」へと繋がっていく訳で。今、その、地→国(稚い)が登場した局面。
その他、状態表現としては同じイメージを共有してますよね。『日本書紀』『古事記』いずれにしても、天地開闢時は、未成熟な「洲」とか「国」とかが、水に浮かぶ脂のようにぷかぷか浮き漂っていたと。コレはこれでロマンやー。
最後に、「葦牙のように萌え騰る物に因って成った」というところもチェック。
先ほど、造化三神のところで「造化」とは形づくられること。神の場合、「化す」という運動の中で、造形物として成る。他にも、「化成」「化生」と言った言葉が神の誕生に使用される。日本神話的な、特別な表現、とお伝えしましたが、それをより具体的に表現したものがコレ。
『日本書紀』でも、このあたりは「葦の芽のような物から化す」と具体的に伝えてます。
西洋をはじめ、外国の神様は最初から「ある」「(完全体として)存在する」ものとして描かれることが多いですが、日本の場合は違います。神様は最初から完璧な状態で生まれるのではなく、「化す」という運動のなかで、そのプロセスを通じて「成る」のです。コレ、「化ける」的な感じで、形を変え、姿を現すイメージ。コレ、激しく重要なポイントなのでしっかりチェック。
次!
→造化三神+二神=五神をまとめて「別天神」として位置づけてます。
意味合いとしては、尊いよと。ほかの神々とは別だよ、違うよと。そういうための神様カテゴリ。
要は、別天神とは、『日本書紀』で設定されてる「神世七代」に先立って、それよりも尊貴な神として位置づけるための神様カテゴリってこと。そんな『古事記』であります。
このあたりで、神様がごちゃごちゃになってくると思うので、いったん整理。
コチラ!
こ、コレ、、分かりやすい!
『古事記』はやけに神カテゴリを作りたがる雰囲気あり。「造化三神」「別天神」「独神」などなど、、、
コレは、『古事記』がめざす「国内向けの、天皇家の歴史を伝える書物」という目的から。いろんな神様カテゴリをつくって、いろんな神様を当て込んで、いろんな豪族、氏族のご先祖様を位置付けることで、序列やら体系やらを示してる訳です。コレ、神話と歴史が交錯するロマン発生地帯。