多彩で豊かな日本神話の世界へようこそ!
正史『日本書紀』をもとに、
最新の文献学的学術成果も取り入れながら、どこよりも分かりやすい解説をお届けします。題して、おもしろ日本神話シリーズ。
今回は、『日本書紀』巻第一、第一段 本伝より、
「天地開闢と三柱の神の化生」
世界の成り立ち、その始まりである天地開闢から、三柱の神が誕生する神話をお届けします。
概要で物語の全体像をつかんで、ポイントを把握してから本文へ。最後に、解説をお届けしてまとめ。
現代の私たちにも多くの学びをもらえる内容。日本神話から学ぶ。日本の神髄がここにあります。それでは行ってみましょう!
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
『日本書紀』巻第一(神代上) 第一段 本伝 ~天地開闢と三柱の神の化生~
目次
『日本書紀』巻第一(神代上)第一段 本伝の概要と位置づけ
初回なので、そもそも論や背景含め、『日本書紀』に記されている日本神話全体像からチェック。
まずは、『日本書紀』編纂の背景から。かいつまんで。
契機は、壬申の乱(672年)に勝利した大海人皇子、改め「天武天皇」としての即位。
ココから、天皇中心の中央集権国家ビルディングがスタート。日本マッチョ化計画です。
律令整備と歴史書編纂。
この2つを両輪として、ムキムキのジャパンビルディング。
天武天皇から持統天皇へ、そして以降の天皇に引き継がれながら、天皇中心とした国家づくりが進む進む。
『飛鳥浄御原律令』(689年)施行、藤原京遷都(694年)、『大宝律令』(701年)施行、平城京遷都(710年)、『風土記』(全国の国情や古老の伝承などを記録して国に報告した地誌)編纂などなど。
●必読→ 【保存版】飛鳥浄御原宮|日本神話編纂のふるさと!歴史書の編纂がスタートした超重要スポット
●必読→ 【保存版】藤原宮跡|藤原京の中心施設「藤原宮」の跡地!歴史書の編纂が進んだコレまた重要スポット!
そして!
律令整備とあわせて、国を挙げて取り組んだのが「歴史書編纂事業」。これが、『日本書紀』『古事記』の編纂です。
対内・対外的にも主張できる「国家のアイデンティティ」を、「己の正当性」を、歴史書にして構築しようと目論んだ訳で。
スゴくないすか?このモチベーション。
川島皇子、忍壁皇子の2人の皇子を中心とする12人の皇族・豪族・官吏により編纂されたのが『日本書紀』。当時の精鋭集団、スーパーエリートの皆さんによる、「国家事業としての歴史書編纂」という訳です。
議論し、取捨選択し、創造し、世界の成りたちからはじまって、日本の歴史書を作っていく。。。
途方もない企てですよね。
日本てスゴイぜ!こんなに豊かで多様な伝承、神話があるぜ!マジやばいぜ。
そんな主張を、自負を。そして、そのための根拠、ロジックを随所にちりばめていく訳で。
この世界の原初にまで遡ってしまう日本という国の、その歴史の凄さ&多彩さ、国家統治の正当さ、を示すのが目的なんで、そのためのロジック構築には最高の頭脳による最大の力が注ぎ込まれている訳です。言葉一つ一つに意味がある。
●必読→ 『日本書紀』と『古事記』の違いに見る「日本神話」の豊かさとか奥ゆかしさとか
ま、それを私たちが今、こうして読み解こうとするわけで、並大抵の作業ではございません。分からないことだらけ。だからこそ学会学術の世界でもいまだに議論が続けられてるんです。
と、そんなこんなの背景をもとに、
今回、解説していくのが『日本書紀』の巻一(神代上)。
下図、赤枠部分。

『日本書紀』は全30巻。日本神話が記載されてるのは、巻一、二、三の計3巻で。3/30。
今回は、その1巻目。「巻第一」と呼ばれ、全部で8段構成。その一番最初、第一段からスタート。
ポイントは、
神話全体の流れの中で読み解くこと。
詳細は今後順次解説、大きな流れ、枠組みは以下の通り。
| 大テーマ | 小テーマ | 内容 | 段 |
| 誕生の物語 | 道による化生 | 乾による純男神 | 第一段 |
| 乾と坤による男女対耦神 | 第二段 | ||
| 神世七代として一括化 | 第三段 | ||
| 男女の性の営みによる出産 | 国生み | 第四段 | |
| 神生み | 第五段 |
第一段から第五段までは、大きく「誕生」がテーマ。
誕生には2つあって、一つが「道による化生」、そしてもう一つが「男女の性の営みによる出産」。
「道による化生」は、第一段、第二段、第三段がひとまとめ。神世七代という最も尊い神さまカテゴリ誕生を伝えます。
そんな大きな流れの中で、
第一段 は、天地開闢と合わせて、道による化生、中でも、乾道という万物の根源の働きにより純粋な男の神様が誕生。
構成は、〔本伝〕と、〔一書〕と呼ばれる異伝6個。計7つの伝承。今回は、その中で〔本伝〕をお届けします。
参考:第一段の〔一書〕はコチラで解説→『日本書紀』巻第一(神代上)第一段 一書第1~6 〜体系性を持つ一書群が本伝をもとに展開〜。
『日本書紀』巻第一 第一段 本伝の概要とポイント
ということで、日本神話の現場にお連れする前に、最終のご案内。概要とポイント解説。
日本神話における、世界の創生。
壮大なスケールとガッチガチに組まれたロジックをお楽しみあれ。古代日本人がこんなスゴイ神話を構想していたことに感動です。
日本神話的には、あらゆる事物事象に先立つ「混沌」からスタート。
その中から、①まず天が形成され、そのあと、②地が成り立ち、そのあと、③天と地の間に三柱の神=純粋な男の神が生まれると伝えます。ホップ・ステップ・ジャンプ。この順番が大事。
ポイント3つ。
①万物の根源が持つ自律的&自動的な働きによって世界ができ、神もできた
いきなり、、ナニですが、、、でも、これから日本神話を読み解いていくうえで、一番の基本。超絶重要事項なので激しくチェック。
日本神話は、とどのつまり、その根底には「易」の思想があるんす。なので、その思想とか考え方をある程度理解しておかないと読み解けない。。
ただ、
易のすべてを理解する必要は無く、最低限ここで押さえておきたいのは、
- 万物の根源に「道」があり、乾道や坤道など二項対立の関係がある。
- そして、それぞれの根源(乾道や坤道)は、自律的、自動的な働きを持っていて、この働きによって世界ができあがり、神も誕生した。
ってこと。
例えば、本文中の「清く明るいものが薄くたなびいて天となり重く濁ったものがよどみ滞って地となる」といった内容も、
- 清く明るいもの=乾・陽 →軽いので上へ、そして天になる
- 重く濁ったもの=坤・陰 →重いので下へ、そして地になる
といった、二項対立の根源とその働きにより世界が創生されていきます。コレ、やっぱり易がもと。
さらに!
この、天になったり、地になったり、もっというと神ができたりする展開は、乾や坤、陽や陰といった世界の根源がもつ自律的・自動的働きであるぞと。。それはスゴイぞと。。コレ、思想なんで、そういうものとしてご理解ください。詳しくは後ほど。
次!
②世界の形成過程や神の誕生には「原理」がある
二項対立の根源(乾坤、陽と陰など)で世界や神ができあがった訳なんで、その出来上がった世界には「この世界を成り立たせる原理」が存在することになります。
その「原理」とは、先後、尊卑などの順番、順序のこと。
陽に対して陰、天に対して地、尊に対して卑、男に対して女など、易をベースにした順番・順序といった鉄の掟・ルールがあるよと。
なので、
読み解きにあたっては、順番とか順序に着目してみるといろいろ見えてくる。コチラも念頭に。
次!
③最先端知識・知恵の体系をフル活用しながらも、新しく独自の言葉や世界観を創造
第一段、とにもかくにも根源!とか原理!推しの嵐。そのガッチガチな雰囲気を堪能するのが〇なんですが、それだけじゃない!
当サイトとして一番推したいところは、古代日本人が創造性を発揮したところ。その創意工夫の痕跡で。
日本書紀編纂チームは、漢籍をもとにした最先端知識とか知恵の体系を駆使はするんだが、単に真似で終わるのではなく、日本独自に組み合わせ、工夫し、新しく生み出しているんです。
ココ激しく重要なポイント。日本人らしいところ、超絶クリエイティブ発揮の巻。こちらも後ほど。
まとめます
- 万物の根源があり、その自律的&自動的な働きによって世界ができ、神もできた
- 世界の形成や、神の誕生には「この世界を成り立たせる原理」が働いている
- 『日本書紀』編纂当時の、最先端知識を駆使して天地開闢や神誕生を創造。だけど、単に真似で終わるのではなく、日本独自に組み合わせ新しく生み出している!
以上の3点、つまり、「基本(根源とか原理)と応用(創意工夫)」をチェックしたうえで、以下本文をどうぞ!
『日本書紀』第一段 本伝
▲国立国会図書館デジタルライブラリより引用。慶長4(1599)刊版 昔々、天と地は未だ断ち割れておらず、陰と陽も分かれていなかった。混沌として、まるで鶏の卵のようであり、ほの暗くぼんやりとして事象が芽生えようとする兆しを内に含んでいた。その清く明るいものが薄くたなびいて天となり重く濁ったものがよどみ滞って地となるに及んでは、軽やかで妙なるものは集まりやすく重く濁ったものは凝り固まりにくい、だから、天がまず成りそして地は後で定まったのである。しかるのち、神が天地の中に生まれた。
それゆえに、天と地が開かれる初めには、のちに洲となる土壌が浮かび漂っていた。その様は、まるで水に遊ぶ魚が水面に浮いているようなものだった。まさにその時、天地の中に一つの物が生まれた。それは萌え出る葦の芽のようであった。そして、化して神と成った。この神を国常立尊と言う。次に国狭槌尊。さらに豊斟渟尊。あわせて三柱の神である。天の道は単独で変化する。だから、この(男女対ではない)純粋な男神に成ったのである。
古、天地未剖、陰陽不分。渾沌如鶏子、溟涬而含牙。及其清陽者薄靡而為天、重濁者淹滞而為地、精妙之合搏易、重濁之凝竭難。故、天先成而地後定。然後、神聖生其中焉。
故曰、開闢之初、洲譲浮漂。譬猶游魚之浮水上也。于時、天地之中生一物。状如葦牙。便化為神。号国常立尊。次国狭槌尊。次豊斟渟尊。凡三神矣。乾道独化。所以、成此純男。※号国常立尊。の後の、注〈至貴曰尊、自余曰命。並訓美挙等也。下皆倣此。〉は割愛 (引用:『日本書紀』第一段〈本伝〉より抜粋)
『日本書紀』巻第一 第一段 本伝 解説
第一段 本伝の構成
『日本書紀』第一段の本伝は、構成上、大きく二つの部分から成りたってます。
前段、後段、二つに分ける語が「故曰」→訳出「それゆえに、」。本伝の中間に位置。
この語「故曰」を境に、前半は、「万物の根源の働きと原理の提示」がテーマ。この「根源」「働き」「原理」については後程詳しく。神話全体を貫く超重要テーマです。
そして後段は、より具体的な様子を伝えながら、三柱の神の化生を伝えます。
上記を押さえつつ、以下詳細解説!

第一段 本伝 前半部分詳細概説
ココからは、前半後半に分けて解説。特に重要なポイントをピックアップ。
ということで、
前半は全体として、「宇宙論」として全体を規定するというより、天地や陰陽の未分化な「古」まで溯った上で、神聖の誕生に到る経緯を伝えつつ、、万物の根源の存在とその働きによる継起的な展開は原理に基づくものであると伝えてる、と。ココがポイント!
続けて後半!

第一段 本伝 後半部分詳細概説
- それゆえに、天と地が開かれる初めには、のちに洲となる土壌が浮かび漂っていた。その様は、まるで水に遊ぶ魚が水面に浮いているようなものだった。
- 故曰、開闢之初、洲譲浮漂。譬猶游魚之浮水上也。
→「故曰」という言葉を使う事で、後半も天地神の生成が原理にのっとる事を明示しつつ、、
「開闢」の「闢」について。「門」と「辟」の形声文字。「辟」は主に「ひらく・あける」という意味で、「開闢」のように世界の始まりや、土地や分野などを「切り開く・設ける」という意味でも用いられます。そんな「辟」と「門」が合わさってる訳なんで、イメージとしては重々しい門が開くことで道が開かれる、新しい世界が開かれるといったダイナミズムをビシビシ感じていただきたい!
で、「開闢之初」→訳「天と地が開かれる初めには」。天と地が開かれる初めという「時」を設定。
そのうえで、この時の「洲壌」(のちに「洲」となる土壌)や、天地の中に生じた「物」の状態を、比喩を使って具体的に表現してます。
「のちに洲となる土壌が浮かび漂っていた。その様は、まるで水に遊ぶ魚が水面に浮いているようなものだった。」とあり、なんか、、良いですよね。この描写。とても想像力をかきたてられます。
前段で、「重く濁ったものがよどみ滞って地となる」とありましたが、開闢当初はまだ固まってなかったってこと。「洲譲」という、のちに洲となる土壌がふわふわ漂っている状態だった訳です。コレ、原始地球のドロドロっとしたイメージと重なる??
次!
- まさにその時、天地の中に一つの物が生まれた。それは萌え出る葦の芽のようであった。そして、化して神と成った。
- 于時、天地之中生一物。状如葦牙。便化為神。
→天地の中に、萌え出る葦の芽(原文:葦牙)のような物が生まれ、それが変化して神と成ったと。。
ココで、突然登場する「物」ですが、、、どっから来た??? って、でも、このころは万物の根源が働きまくって宇宙や世界や天地やらを形づくってる訳で、、、そのなかで、ある「物」が誕生していたとしても何ら不思議ではありませぬ!! ←と、解釈する。
で、そんなことより注目は、「神の生まれ方」であります。
神は、完全な形では生まれません。
神は、まず物として、葦の芽のような形をして生まれる。それが神に化す!
化すというのは、運動です。「化=化ける」「生=生まれる、なる」。つまり、元の姿を変えて別の姿になる、別の姿として生まれる、という事。
葦の芽のような物が、神様の形に変化。。。これまた、、、超絶ジャパーン的。アニミズムの国だからこその神生成イメージ。非常に奥ゆかしい。。
ちなみに、、西洋をはじめ、外国の神様は、最初から「ある」「(完全体として)存在する」ものとして描かれることが多く、これとは対照的。
日本の神様は、最初から完璧な状態で生まれるのではなく、「化す」という運動のなかで、そのプロセスを通じて神になる。コレ、「化ける」的な感じで、形を変え、姿を現すイメージ。非常に重要なポイントなのでしっかりチェック。
なお、ここで誕生した神は恐らく、人間のような形をしていたと想定されます。なぜなら「神世七代」という一連の神カテゴリの最後、伊奘諾尊、伊奘冉尊の結婚のところで互いに形状確認してて、それは人間そっくりだから。
ちなみに、「神をモデルにして人間ができている」というのが日本神話の基本スタンス。これも要チェック。
次!
→3神が誕生したとあります。
ココにも、二項対立がベースの易思想・理論あり。奇数は「陽数」であり、偶数は「陰数」。なので、3は奇数で陽数、乾の側。付け足すとすれば、「3」は奇数の最初の数。すごいパワーをもった数字なんだと。
繰り返しになりますが、なんせ、このころは万物の根源が働きまくって宇宙や世界や天地やらを形づくってる訳ですから、、ここで最初に誕生する神は「3神」でなければならなかった。ということで、チェック。
次!
- 天の道は単独で変化する。だから、この(男女対ではない)純粋な男神に成ったのである。
- 乾道独化。所以、成此純男。
→天の道は単独で変化するからこそ、純粋な男性神となった、と。
これまで解説してきた易思想がモロ出しになってる箇所。
まずは「乾道」から。
「乾道」とは、万物の根源たる「道」の天側、陽側のやつ。天の道。天の徳、道理、本体、といったところ。対になるのは「坤道」。ちなみに「乾坤」は天地の事、陰陽の事。
易思想そのものであり、例えば、『説卦伝』では「乾を天と為し」とあります。『説卦伝』とは、儒教の経典である『易経』の「十翼」と呼ばれる主要解説書の一つ。
つまり、「乾=陽=天」ということで、「乾道」→訳出「天の道」というのが多く用いられます。コチラ↓でも詳しく。
そのうえで、
「乾道独化。所以、成此純男。」
コレ、『周易』の卦(易で占った結果あらわれる象)で伝える内容を組み合わせて作られてます。『周易』とは、古代中国の易の書物。周代に生まれた易。
この中で、
- 「乾」卦の「乾道変化」(彖伝)、
- この卦を説明する「大乾哉、剛健中正、純粋精也」(第五節)
- 「乾道成男」(繫辞上伝)
といった「乾」に関連したこれらの記述を取り込んで、組み合わせて構成されてるんです。
「乾」という卦はそもそも変化する、その性質は剛健中正・純粋精であり、男を成すと。。。すごい男性優位というか、、現代でこそドン引き確定ですが、ま、古代の、というか易の思想ってことで、、、
で、大事なのは、こうした思想をもとに組み合わせるだけでなく、新しく生み出してるってこと。
それが「純男」。
「純男」は、「乾道」(天の道)だけによって成る男の神のこと。「男」じたいの、「乾道」との本質的な不可分の繋がりを強調する独創的な表現であります。
要は、陰陽の結合によらず、乾=天の道のみで男神が生まれたことを言ってるんですが、、。
易はじめ編纂当時の最先端漢籍や思想に「純男」という言葉はでてきません。
最先端知識(易) × 創意工夫 = 純男
ということで、乾坤とか陰陽とか易の概念を導入しつつも、独自に創造したジャパーン的なるものとして、是非チェックされてください。
ちなみに、
「乾道独化、所以成此純男」は、このあと第三段〔本伝〕がつたえる「乾坤之道」の混交によって化成する「男女」を予定し、それと対応させてます。
まず「乾道」だけで化成した「純男」を先行登場させてること、あわせてチェックされたし。
ということで、
後半部分の重要テーマは、やはり
最初に生まれた神が、天を体現する、あるいは本質とする、三柱の「純粋な男の神」であった、というところ。
その意図、理由はやはり「尊卑先後の序」。はじめに男性神が誕生するのは、普遍的な原理に基づいていることを伝えているのです。
こうして見てくると、「第一段の本伝(天地開闢と三柱の神の化成)」においては、
混沌から、天→地が誕生する先後の順番、男性神が先に誕生、など、根源のもつ働きをもとに「尊卑先後の序」を伝えようとしてる、とも言える訳で。
で、この、
書紀全体を貫く「普遍原理の存在」を最初に持ってくることで、以後の流れを原理の中で伝えることができるようにしている訳です。
このロジックは、最終的に「天照大神」を頂点とする神話世界の序列、そして「天皇」を頂点とする現実世界の序列を支える根拠につながっていく。。。
世界中の神話を読んでも、こうした普遍原理をもとに神話を構築している例は無く、まさに書紀独自の、いや、日本独自の超ユニークな世界観であると言えますよね。スゴイよほんと。
『日本書紀』巻第一(神代上)第一段〔本伝〕まとめ
『日本書紀』巻第一(神代上)第一段〔本伝〕
だーっと解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
大きくは、
日本神話全体のなかで、第一段、第二段、第三段がひとまとめで、神世七代という最も尊い神さまカテゴリ誕生を伝えます。その大きな流れを意識しつつ、、
今回の、「天地開闢と神の化生」は、
- 万物の根源があり、その自律的&自動的な働きによって世界ができ、神もできた
- 世界の形成や、神の誕生には「この世界を成り立たせる原理」が働いている
ってことを、易の思想をベースに、これでもか!というくらいゴリゴリに推してる訳です。
この世界の創生当初から「原理=尊卑先後の序」が存在し、この原理により、天→地→神という成りたちが導かれた、そして、「乾道」(天の道)だけによって、つまり、陰陽の結合によらず、陽=天の道のみで最初の神、男神が生まれた、、、と。
で、だからと言って漢籍知識だけかというとそうではなく、当サイトとして一番推したいところでもある、古代日本人が創造性を発揮したところ。その創意工夫が重要で。例えば、
最先端知識(易) × 創意工夫 = 純男
なんて、ほんと究極ですよね。自在に組み合わせていく。
膨大な知の体系、宇宙論を取り込みながら、私たち日本人のご先祖様は、そこに創意工夫を巧妙かつ大胆に交えながら、新しい宇宙論として展開している訳です!
日本のスゴイところ。先端の知識を学びとして取り入れながら独自のものにしてしまう。現代の私たちにもたくさんの気づきと学びをいただける内容かと思います。日本神話から学ぶ。日本の神髄がここにあります。
続けて、『日本書紀』第一段 一書の解説です。が、その前に、まずコチラをチェック!
続きはコチラ↓で!本伝に対する異伝のみなさん!!!
『古事記』版の天地開闢はコチラで!
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
天地開闢まとめ、関連エントリはコチラで!
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




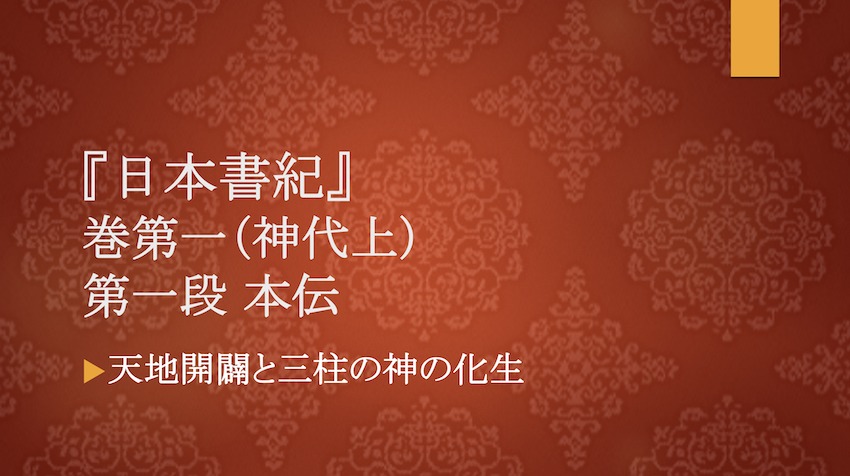






















→日本の、いや、世界のはじまり、その原初の状態描写。厳かな雰囲気を感じて、、、
原文「天地未剖、陰陽不分。渾沌如鶏子。溟涬而含牙。」について。
「天地未剖」の「剖」は、まん中から二つにたち割る。わける。さく意。「分ける」というより、「二つに断ち割る」といった動的な、ダイナミックな意味に近いので、訳出は「天と地は未だ断ち割れておらず」としてます。
一方、「陰陽不分」の「分」は、「分ける」の意。陰の気、陽の気が混沌として分かれてない、分離してない、といった意味なので、訳出は「陰と陽も分かれていなかった」。
で、実はこの一文、古代の漢籍である『淮南子』(巻二)俶真訓の「天地未剖、陰陽未判」と、『三五暦紀』の「未有天地之時、混沌状如鶏子、溟始牙」とを結合させて作られてるんです。
『淮南子』とは、前漢時代に淮南王の劉安が編纂させた、道家思想を基調とする百科全書的な思想書。
『三五暦紀』は、3世紀の呉の徐整による神話集。「盤古」の天地開闢神話を伝えます。
と、いきなりディープな漢籍たちが登場しましたが、このように、『日本書紀』自体が当時の最先端知識とか知恵の体系とか宇宙論みたいなのを色々組み合わせながら作られていて。最初のころは特にモーレツゥ。。。
今回も、『淮南子』『三五暦紀』に記述されてる世界の始まりの様子を組み合わせ天地開闢を描いている、、、という次第で。ま、パクリと言えばパクリなんだけど、でも、それで終わりかというとそうでもない。ちゃんと創意工夫が入っていて、中でも、当サイト的にイチ推しは、一番最初の文字「古(いにしへ)」!
コレ、非常に日本的な表現で。。
例えば、『文選』巻三四「七啓八首」には「夫太極之初、渾沌未分」とあり、当時の宇宙論には「太極」という「根源」「一番最初の状態(点)」を表す言葉が存在する訳です。しかし、『日本書紀』はそれを使用していない。
これは、推測するに、国の歴史書の中で「太極」という言葉を使うと、「太極」とは何か?それっていつなの?とかが問題となり、別の説明が必要になってくるから。そうすると、本来伝えたい内容ではなくなってしまうから。
天と地が断ち割れる前の、陰と陽の要素があって、それらが混沌としてるころを、単に「古=むか~し昔」と定義するだけで良しとしてる、ってことで。ココに、神代紀独自の世界観が凝縮されていると言える訳です。
別の言い方をすると、「全ての始まり」という「点」を定義しない、とも言えて。『日本書紀』(神代紀)では、現代の私たちが考えるような直線的時間概念で世界を描いていないんですね。
曖昧なんだけど、なんか奥ゆかしい。日本ならではの精神性や価値観が、日本神話の一番最初の言葉に埋め込まれてる、ってことでチェック。
でも、、一応、『日本書紀』、正史=国の歴史書なんすけど。。。大丈夫でしょうか?むか~し昔、って、、、
、、、と、このように、基本は漢籍ベースなんだが、至るところにローカライズというか、、日本独自の価値観とか世界観が埋め込まれていて、、そういうのを探していく作業も日本神話の楽しみ方だったりします。
あともう一つ。
「混沌として、まるで鶏の卵のようであり、ほの暗くぼんやりとして事象が芽生えようとする兆しを内に含んでいた。(原文:渾沌如鶏子。溟涬而含牙。)」のところ。
「古」の天地開闢の状態を「鶏子=鶏の卵」に例えてる訳ですが、単に、混沌(原文:渾沌)としている訳ではなく、事象が芽生えようとする「兆し(原文:牙)」を内に含んでいる、予定されているものがあると、、。
コレ、受精卵のことで、一見、ただの卵にしか見えませんが、実は、中では、将来どの部分が、頭になる、翅になるなど、分化する部分が決まっている、つまりプログラムされている!ってことで。理科の時間、勉強しましたよね。
今でこそ、科学の力で明らかになってきたことを、引用とはいえ、天地開闢の状態表現に使ってることは注目に値します。コチラもチェック。
次!
→やけに説明臭い、、、
って、この「臭さ」、実はめっちゃ大事で。この臭いの中身を考えていくことが重要。
この部分、やはり『淮南子』(巻三)天文訓や『三五暦紀』がベースになってますが、それよりも、ポイントは「根源のもつ働き」と「順番(序列)の存在」を伝えてるってこと。
まず、「根源のもつ働き」について。
この根源、いわゆる「万物の根源=道」であり、宇宙、世界、ありとあらゆるものの根源ということなんですが、、そのベースにあるのが「易」であります。
まずは、一旦コチラ↓の記事をチェックいただき、
そのうえで、
ポイント2つ。
ってことで、
ここで伝える「清く明るいものが薄くたなびいて天となり重く濁ったものがよどみ滞って地となる」といった内容も、
といった、易をもとにした二項対立の根源とその働きによって世界が創生されてる訳です。
そしてこの、天になったり、地になったり、もっというと神ができたりする展開は、乾や坤、陽や陰といった万物の根源がもつ自律的・自動的働きによるものだ!と。これ、思想なんで、そういうものとしてご理解ください。
逆に、易思想が分かってる人からすると、何の違和感もなく読み解ける箇所であり、もっというと、「分かっておるじゃないか!」「流石じゃ!」となる箇所であったりします。多分。
これはやはり、『日本書紀』編纂当時の背景を踏まえる必要があって、対内以上に対外的にもしっかりアピールできる歴史とか文化の厚みとかスゴさとか、、みたいのを示す必要があったから、ガッチガチのムッキムキになっていく訳ですよ。。
ということで、まずは1つめ、万物の根源とその働きによって天と地に分かれていった、ということでチェック。
次、2つ目は、「順番(序列)の存在」について。
改めて、ここでの流れとしては、
混沌があり、その中に兆したものがあり、そこから天へ、そのあと地へ展開していく、、といった内容。この、何々が起こって、何々が起こって、と続く形式を「継起性」といいますが、単に継起的に展開していくのではなく、軽いものは天、重いものは地、さらに、天が先に成り地は後、という順番(序列)が存在する、としてる訳です。そういう風に読み解きます。
これを「尊卑先後の序」と言います。つまり、尊いものは卑なるものに先立つということ。
「尊卑先後の序」は書紀神話全体を規定する最も重要な考え方であり、普遍的な原理として位置づけられています。
第一段では、
様々な事象が発生していくのは全て、原理に基づく順番(序列)があり、その原理こそが最も重要であることを表現している。やけに説明臭い展開もそれによるもの。
天=先、地=後。その順番が大事。しかもそこには原理があるよ、という事。ココ、しっかりチェック。