多彩で豊かな日本神話の世界へようこそ!
正史『日本書紀』をもとに、最新の文献学的学術成果も取り入れながら、どこよりも分かりやすい解説をお届けします。
今回は、『日本書紀』巻第一(神代上)第四段の本伝。
新しい時代の幕開け。
第一段~第三段の「道の働きによる神々の誕生」から、伊奘諾尊・伊奘冉尊の「男女神の営み、行為による誕生」へ。まさに新時代到来!!
概要で全体像をつかみ、ポイント把握してから本文へ。最後に、解説をお届けしてまとめ。
現代の私たちにも多くの学びをもらえる内容。日本神話から学ぶ。日本の神髄がここにあります。それでは行ってみましょう!
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
国生み『日本書紀』巻第一(神代上)第四段 本伝 ~聖婚、洲国生み~
目次
国生み『日本書紀』巻第一(神代上)第四段 本伝の位置づけ
前回はコチラ。
今回お届けするのは、下図、赤枠部分。

ポイントは、神話全体の流れの中で読み解くこと。
詳細は順次解説、大きな流れ、枠組みは以下の通り。
| 大テーマ | 小テーマ | 内容 | 段 |
| 誕生の物語 | 道による化生 | 乾による純男神 | 第一段 |
| 乾と坤による男女対耦神 | 第二段 | ||
| 神世七代として一括化 | 第三段 | ||
| 男女の性の営みによる出産 | 国生み | 第四段 | |
| 神生み | 第五段 |
第一段から第五段までは、大きく「誕生」がテーマ。
この中で、第四段のテーマは
「男女の性の営みによる出産」国生み編!!
第二段本伝で、「乾坤の道」がお互いに参じて混ざって誕生(化成)した男女ペア神、その最終世代が伊奘諾尊、伊奘冉尊で。その男女の、最初のはたらきが、洲国生み。位置づけとか意味が超重要。
これまでとは違う、
新しい時代の幕開けを感じていただきたい!
第四段からは、いよいよ物語チックな雰囲気が濃くなってきます。豊かで奥ゆかしい神話世界をたっぷりご堪能あれ。
国生み『日本書紀』巻第一(神代上)第四段 本伝の概要とポイント
ポイント4つ。
①新時代の幕開け。道の働き→男女の営みへの大転換
改めて、経緯確認。第一段から第三段は、「神世七代」という至尊の神々が誕生。その「尊さ」の実態根拠は、乾坤の道から、道の働きによって誕生(化成)する、ってこと。
宇宙、または万物の根源から化成。最初は、乾のみで純男神が化成。続いて、乾坤の両方から男女神が化成、、
これ、尊すぎるやつっ!
こうした流れ(継起的展開)を承けつつ、第四段からは「乾と坤の道」が、その実質を引き継ぎながら「男と女の性」へ転換!
道(乾・坤)→継承・転換→性(男・女)
第四段は、性を内在した男女神がその属性の働きとか導きを「かたち」にする段とも言えて。それが洲国生みの実態、男女の営みの実態であり、これによって
「子を生む」という全く新しい時代へ大転換!新時代キタ━(゚∀゚)━!
この「誕生」をテーマにした壮大な転換、その違いをチェック。
次!
②第四段は三部構成。協議→結婚→出産。日本的な麗しいウェディングストーリー
そんな新時代の幕開け第四段は、全体として三部構成。以下。
| 第一部 | |
| 第二部 |
|
| 第三部 |
|
ということで、
「協議→結婚→出産」という、男女による日本的な麗しいウェディングストーリー。
協議からスタートする男女の物語。神が主体ながら、人間の行為に通じる内容で描かれてます。
新時代の到来を織り込み、話し合って、結婚して、子を生んでいく。。。って、いいじゃないですか、この優しいジャパーン的なる雰囲気。
次!
③結婚=儀礼なんで、手順やルールに則らないとダメよ
そんな麗しきウェディングストーリー、実は、ポイントは、
結婚=儀礼
であること。儀礼ってのはきちんとした手順やルールがある。
道をひき継ぐ性に根ざす営みでもあるわけで。道理にのっとるのは当然。道理=原理原則。手順やルールがあるのだよ。
で、この手順やルールを間違えると、、、とんでもない結果を生んでしまう。なぜなら、儀礼を間違える=道理を違える、てことだから。
つまり、
表側のストーリー展開では、結婚、洲国生みといった華やかなイベントが進行してるのですが、その裏側では、絶対的な原理原則が働いていて、手順やルールを間違えると相応の結果を受ける、代償を払わなければならない、という仕掛けになってるんす。これも事前にチェック。
次!
④産んだ子=大八州国を神聖化。儀礼手順は全てそのためでした
ウェディングイベントの結果、全部で八つの洲国+αが生まれます。
第四段は、最終的に、男女二神が大八州国を生みました、それはとっても神聖な洲国なんです、てところに持って行きたい。
大八州国の神聖化
それは、日本の神聖化と同じであって、そのための仕掛けや設定が随所に。
結婚=儀礼を経て誕生する、というのも神聖化の仕掛け。
きちんとした手順を踏んだわけで、そりゃスゴイねと、分かってるじゃないかと。神でさえ従うべき手順、ルールがあるし、それを支える原理があるんだと。ますますよく分かってるじゃないかと。そう、それは尊卑先後の序!
後程詳細。ちなみに、これまでの流れも再確認。
純男神三代(3)→男女神四代(4)→神世七代(7)→大八州国(8)
といった設定で、第一段から広がりをもった数字の設定、その世界線上にあります。
まとめます。
- 新時代の幕開け。道の働き→男女の営みへの大転換
- 三段構成。協議→結婚→出産
- 結婚=儀礼なんで、手順やルールに則らないとダメよ
- 産んだ子=大八州国を神聖化!儀礼手順は全てそのためでした
以上4点を踏まえて以下、本伝をどうぞ!

国生み『日本書紀』巻第一(神代上)第四段 本伝
国立国会図書館デジタルライブラリより慶長4(1599)刊版 伊奘諾尊と伊奘冉尊は天浮橋に立って、共に計り「底の下に、どうして国がないだろうか(きっと国があるはずだ)」と言った。そこで、天之瓊矛(瓊とは玉である。ここでは努という)を指し下ろし探ると、蒼く深く広がる海があった。その矛の先から滴り落ちた潮が凝り固まり一つの嶋と成った。これを名付けて「磤馭慮嶋」という。
二柱の神は、ここにおいて、かの嶋に降り居た。よって共に夫婦となり国を産もうとした。そこで、磤馭慮嶋を国の中心である柱とした。そして、陽神は左から巡り、陰神は右から巡った。分かれて国の柱を巡り、同じ所であい会した。その時、陰神が先に唱え、「ああ嬉しい、いい少男に会ったことよ。(少男、ここでは烏等孤という。)」と言った。陽神はそれを悦ばず、「私が男だ。理の上ではまず私から唱えるべきなのだ。どうして女が理に反して先に言葉を発したのだ。事はすでに不吉になってしまった。改めて巡るのがよい。」と言った。
ここに、二柱の神はもう一度やり直してあい会した。今度は陽神が先に唱え、「ああ嬉しい。可愛い少女に会ったことよ。」と言った。(少女、ここでは烏等咩という)。そこで陰神に「お前の身体には、なにか形を成しているところがあるか。」と問うた。それに対し、陰神が「私の身体には女の元のところがあります。」と答えた。陽神は「私の身体にもまた、男の元のところがある。私の身体の元のところを、お前の身体の元のところに合わせようと思う。」と言った。ここで陰陽(男女)が始めて交合し、夫婦となったのである。
産む時になって、まず淡路洲を胞としたが、それは意に不快なものであった。そのため「淡路洲」と名付けた。そこで、大日本豊秋津洲(日本、日本では耶麻騰という。以下すべてこれにならえ)を産んだ。次に、伊予二名洲を産んだ。次に、筑紫洲を産んだ。そして億歧洲と佐渡洲を双児で産んだ。世の人に双児を産むことがあるのは、これにならうのである。次に、越洲を産んだ。次に、大洲を産んだ。そして吉備子洲を産んだ。これにより、はじめて「大八洲国」の名が起こった。そして、対馬嶋、壱岐嶋、及び所々の小島は、全て潮の泡が凝り固まってできたものである。または、水の泡が凝り固まってできたともいう。
伊奘諾尊・伊奘冉尊、立於天浮橋之上、共計曰、底下豈無国歟。廼以天之瓊〈瓊〉玉也。此云努。〉矛、指下而探之。是獲滄溟。其矛鋒滴瀝之潮、凝成一嶋。名之曰磤馭慮嶋。
二神於是降居彼嶋。因欲共為夫婦、産生洲国。便以磤馭慮嶋、為国中之柱。〈柱、此云美簸旨邏。〉而陽神左旋、陰神右旋。分巡国柱、同会一面。時、陰神先唱曰、憙哉、遇可美少男焉。〈少男、此云烏等孤。〉陽神不悦、曰、吾是男子。理当先唱。如何婦人反先言乎。事既不祥。宜以改旋。
於是、二神却更相遇。是行也、陽神先唱曰、憙哉、遇可美少女焉〈少女、此云烏等咩。〉。因問陰神曰、汝身有何成耶。対曰、吾身有一雌元之処。陽神曰、吾身亦有雄元之処。思欲以吾身元処、合汝身之元処。於是、陰陽始遘合、為夫婦。
及至産時、先以淡路洲為胞。意所不快。故、名之曰淡路洲。廼生大日本〈日本、此云耶麻騰。下皆效此。〉豊秋津洲。次生伊予二名洲。次生筑紫洲。次双生億岐洲与佐度洲。世人或有双生者、象此也。次生越洲。次生大洲。次生吉備子洲。由是、始起大八洲国之号焉。即対馬嶋、壱岐嶋及処処小嶋、皆是潮沫凝成者矣。亦曰、水沫凝而成也。 (『日本書紀』巻第一(神代上)第四段 本伝より引用)
国生み『日本書紀』巻第一(神代上)第四段 本伝解説
改めて、ココ第四段は、これまでの「乾坤の道の働き」から「男女の性の営み」への大転換発生中。超重要事項なので再確認。
- これまで:
乾と坤の道をもとに、道の働きによる、化生という自動詞的、自律的誕生。つまり「自己完結型」。 - ココから:
男と女の結婚をもとに、性の営みによる、出産という他動詞的誕生。つまり「関係性発展型」。
てことで、第四段〔本伝〕の位置づけとして
時代の大きな転換が発生中!!コレ、猛烈にチェック
そんな背景認識の上で、
第四段は全部で三部構成。少々長いですが、頑張ってお付き合いください。
第一部解説
- 伊奘諾尊と伊奘冉尊は天浮橋に立って、共に計り「底の下に、どうして国がないだろうか(きっと国があるはずだ)」と言った。
- 伊奘諾尊・伊奘冉尊、立於天浮橋之上、共計曰、底下豈無国歟。
→神世七代の後を引き継ぐ時代が「共計(協議)」から始まる。。。
以下、環境と行為の2つに分けて解説。
まずは、環境認識から。
「伊奘諾尊と伊奘冉尊は天浮橋に立って」とあります。これ、既に天空にいて、天空にある天浮橋に立ってる設定。。。って、YOUたちいつからそこに??
神が化成する「場所」として、第一段では、天と地の間、中空が設定されてました。そこに葦の芽のような「物」が生まれ、神に化成したと。それを承けての第二段なので、男女ペア神も同様に、中空に誕生したと考えられ。それが、ココ第四段、いつの間にやら天空にいらっしゃるとのことで、乾坤の道は軽いのでふよふよ上に昇っていった??
これまでの経緯を踏まえると、
混沌から天と地ができ、その頃は「のちに洲となる土壌が浮かび漂っていた。その様は、まるで水に遊ぶ魚が水面に浮いているようなものだった。(第一段本伝より)」と伝えてるので、地は洲壤(洲となる土壌)が浮び漂ってた訳で、この浮かび漂っていたのが海(あるいはのちに海となる液体のようなもの??)だったのではないかと推測されます。で、神世七代が誕生してる間に、ある程度、世界が具体的な現れを見せ始めていた。。
その上で、ここでは、より具体化が進んだ天と地があって、伊奘諾尊・伊奘冉尊が下界を探って獲た海(原文「滄溟」)があったと、、まさに天、地、海という基本要素が具現化していた模様で。
これ、言い方を変えると、これまでの洲壤みたいなレベルではなく、世界がいよいよ国の誕生にむけた準備に入ってるとも言えて。そんな環境認識をもとに、、
「天浮橋」について。
コレ、天にあって下界全体が見渡せる橋のこと。
天上から地上へ降りてくる途中にある、あくまで天上にある橋で。ここから地上世界の様子がまー良く見えるらしい。
ちなみに、第九段〔一書1〕の天孫降臨でも登場。天忍穂耳尊が天浮橋から葦原中国を見下ろします。
天浮橋=天と地をつなぐ梯子説、というのがあるのですが、天と地をつなぐのは、日本神話的に言えば「柱」です。第五段で「天柱」として登場。
天浮橋は、あくまで天空にあり、天神が天上から下界の様子を察知する場合のみに登場。尊いお方はまず、これから向かう先について状況確認できるナイスビュースポットに立つもんなんす。
細かいついでに、「天」の読み方について。一応ルールがありまして、、、
- 独立した意味であれば「あめ」
- 修飾関連の意味であれば「あま」
と読みます。
ここでは、「天の浮橋」という形で「天」は「浮橋」を修飾するので「あまの」と読ませます。逆に、「天地」のように、独立した意味であれば「あめつち」と読ませます。
次!
行為について。
「共に計り」とあります。原文「共計」。
第四段は、性を内在した男女神がその属性の働きや導きを「かたち」にする段。とも言えて。
男女の性の営みゆえに、その最初は「共計(協議)」からスタート。神世七代の後を引き継ぐ時代が協議から始まる。。。この深い意味を全身で感じていただきたい!
外国のように超越的な絶対神が、その意志のままに天地を創造するのとは全く違うスタイル。
性を異にする。だからこそ、必然的に伴う個性の異なりや意見の対立。でも、それを前提として、「協議」によって乗り越えるってことなんすよ皆さん!
異質が互いを認め合い、すりあわせ、共に一つの方向を目指し、実現を図っていく。「共計(協議)」はそういったことを如実に物語る訳で。超絶ジャパーン的なるものとして激しくチェック。
ちなみに、コレは、最終的に、第五段〔一書10〕へつながって行きます。いわば「わたり」として。男女の物語は、協議にはじまり協議で終わる。。。深淵なテーマが横たわってるのだ!
以上、環境認識と行為の意味はしっかりチェック。
そのほか、細かいところで2点。
①きっと国があるはずだ=予祝
「どうして国がないだろうか(きっと国があるはずだ)(原文:豈無国歟)」とあります。日本神話史上、初めて神が発した言葉、、、 (゚A゚;)ゴクリ。。
「豈無国歟」は反語表現。意味として強調。「どうして国がないだろうか?ないわけないやん!いや、きっとあるはずだ」。
しかも、先ほどの「共計」、つまり共に計る、計画する意味あいもあって。諾冉二神が計画としての意味合いで「きっと国があるはずだ。」としてることも踏まえると、ココでいう「国」とは、
予祝
としてチェック。
国家成立の三要件というのがあって、①領土(国土)、②人民(国民)、③主権(国権)。
諾冉二神による国生みの段階では、いずれの要件も無い状態(これから生もうとしてる所)なんだが、この時点で「きっと国があるはずだ!」と強い表現(反語表現)で、計る文脈で言ってる訳で。
つまり、将来、国家、つまり、領土あり人民あり主権ありの三要件が整った国となるべきものがある!!!と、極めて予祝感あふれる意味があること、しっかりチェック。
日本神話が最終的に日本建国へつながって行くことを踏まえると、諾冉二神はこの時点でそうした将来を予定していた、または、これから日本神話が展開していく全ての起点がココにあるってことで、超絶に、猛烈に、激しく重要事項としてしっかり胸に刻め。
次!
②言表して行為に及ぶ=神の行動にはパターンがある
言表とは、言葉で言い表すこと。神はまず、言表し、そして行為に及ぶ。
「底の下のほうに、きっと国があるはずだ。」まず言表。言い表す。その上で、矛を指し下ろす行為へ、そして国生みの起点となる嶋が実際に形成される。
コレ、「言興」とも通じる内容で、言霊信仰が背景にあります。言葉そのものに霊力が宿っている、ある言葉を口に出すとその内容が実現する、という考え方や信仰。
ちょいちょい登場するこの神様行動特性、チェックです。
次!
- そこで、天之瓊矛を指し下ろし探ると、蒼く深く広がる海があった。その矛の先から滴り落ちた潮が凝り固まり一つの嶋と成った。これを名付けて「磤馭慮嶋」という。
- 廼以天之瓊矛、指下而探之。是獲滄溟。其矛鋒滴瀝之潮、凝成一嶋。名之曰磤馭慮嶋
→天浮橋から瓊矛を地上に指し降ろした、と。それどんだけ長い矛やねん、、というのはさておき、
「天之瓊矛」について。
「天之」は美称。「瓊」は玉飾りのこと。なので、「麗しい玉飾りのついた矛」。めっちゃ長いやつ。
「矛」については、特別な力をもつパワーツールとしてチェック。
なんせ、矛の先から滴り落ちた潮が凝り固まって嶋と成った訳で、、、これを矛パワーと言わずしてなんと言おう。
矛については、他にも第九段で登場。葦原中国平定の際、大己貴神が経津主神と武甕槌神に「広矛」を授けます。そのとき、大己貴神は、その「広矛」を「平国(国を平定する)」に功があり、さらに「治国(国を治める)」にも効果を発揮すると。コレ、「矛の功」というもので。
矛を使うことで功を収める、矛を使うことで平定や統治という功績をあげることができる。つまり、矛にはそうした特別な力があると神話的に位置付けられてる訳です。
諾冉二神が国の存在を想定した上で、矛を使って嶋をあらしめるのも同じこと。ここでは矛の功は「磤馭慮嶋」そのものになります。矛の持つ特別な力、矛の功、しっかりチェック。
次!
「蒼く深く広がる海があった。(原文:是獲滄溟)」とあります。
「滄溟」の「滄」は、「あおい色」「広い海」「青い海」の意。「溟」は「くらい(薄暗い)」または「うみ/大海」を意味。いずれも、蒼い海の意味なんですが、暗さ=深さを含む海としてチェック。
つづいて、「その矛の先から滴り落ちた潮が凝り固まり一つの嶋と成った。(原文:其矛鋒滴瀝之潮、凝成一嶋。)」と。
先ほどの「滄溟」とあわせて、とっても映像的な表現ですよね。蒼く深緑色の「滄溟」と、白い潮の色彩コントラスト。からの、矛の先から滴瀝=ぽたりぽたりと滴り落ちた潮が、凝成=凝り固まり一つの嶋を成した。それが、「磤馭慮嶋」。
「磤馭慮嶋」については、いくつかポイントあり。
1つ目は、名前に注目。
まず、名辞の「磤馭慮」のあらわす「おのずから」という意味自体が、国をあらしめるための実質的な「行為」を始めるべき適当な時期や状態に達してることを示唆。
これから国として成立するための様々なイベントが発生していく訳で。それこそ、国家成立の三要件である「領土、人民(国民)、主権」のうち、第四段では、領土に相当するものとして、「大八州国」が誕生。人民も、後の段で生まれてることになってるし、主権は、日本神話の最後に日本建国、橿原即位により成立、、、と、
こうした「ちゃんとした国」にしていくためには、やっぱり環境や条件が整ってないとできない訳です。その「整ってる感」あるいは「整ってきてる感」を、「磤馭慮≒おのずから」という言葉が示唆してるってことでまずチェック。
その上で、
2つ目のポイントは、「磤馭慮嶋」の誕生方法。
実はコレ、第一段の「神の誕生(化成)方法」に通じます。2つを並べてみます。
- 天地の中に一つの物が生まれた。それは萌え出る葦の芽のような形状であった。そして、変化して神と成った。「天地之中生一物。状如葦牙。便化為神」(第一段 本伝)
- 矛の先から滴った潮が凝り固まって一つの嶋と成った。「矛鋒滴瀝之潮、凝成一嶋」(第四段 本伝)
と。いずれも、自ずから、という生成方法が共通してる訳です。
自ずから成った「磤馭慮嶋」の誕生方法=道の働きにより自ずから成った「神」の誕生方法
てことで、これ、実は、ちゃんと意味や理由があってのことなんす。
その意味や理由とは、「磤馭慮嶋」は諾冉二神の聖婚が行われる場所なので、神聖化が必要、ってこと。
神の誕生方法と同じようにする、神の誕生方法をトレースすることで、神聖な嶋であることを伝えてるんですね。
なので、これまでのポイントをまとめると、
嶋の名前に込められた「自ずから」という意味、そして、神と同じ形成プロセスの2つをもって、聖婚に相応しい聖なる嶋へと位置づけようとしてるってことでチェック。
そして最後のポイント。
「これを名付けて「磤馭慮嶋」という。(原文:名之曰磤馭慮嶋)」とあり、「名」=名付けた、としてます。これ、
名付け=親権の発生
ってことで、諾冉二神がわざわざ名付けしてる、って結構重要事項。
私たちも、子供ができたときには名前をつけますよね。それと同じ行為を、、、いや、神様の行為に倣って私たちも子に名前をつける、という言い方のほうが正しくて。
矛を使って成した嶋であるとは言え、男女二神の共同作業による結果ですよね。磤馭慮嶋って。
なので、名付けして認知する。または、名前を付すことで存在を確定させる。これ、親としての最初の責任。親権ってそういうことで。これ、新しい時代ならではの超重要イベントとしてしっかりチェック。

続けて第二部へ。
第二部解説
- 二柱の神は、ここにおいて、かの嶋に降り居た。よって共に夫婦となり国を産もうとした。
- 二神於是降居彼嶋。因欲共為夫婦、産生洲国。
→嶋に降居し柱巡りを始める男女二神。
これ、ふつーに夫婦になり国を産もうとしたと伝えてますが、さらっと流すの禁止。
解釈としては、
伊奘諾尊と伊奘冉尊は、乾と坤の道を、その実質と働きを引き継いでいるからこそ、「男性」と「女性」は互いに惹きつけ合い交わり合う。だから、夫婦になろうとする。
ってことで。実際、第二段では「天の道と地の道が互いに参じて化した。それゆえ男と女に成った。(原文:乾坤之道、相参而化。)」と伝えてましたよね。男の性、女の性は、そもそも参ずる働きとか性質を内在してるんです。、、って、深い、深すぎるぞ日本神話。
その上での柱巡りですが、ココで、大前提としておさえておきたいポイントをチェック。それは、
結婚=儀礼である
てこと。ココ激しく重要。儀礼というのはきちんとした手順、ルールがあるってことで、具体的には、
- 左旋右旋
- 先唱後和
- 身体問答
- 交合結婚
の手順。そして、これらの手順を支える道理とは「陽主導」であること。道理=「尊卑先後の序」。
なので、先ほどの手順に当て込むと、
- 左旋右旋・・・陽が左旋、陰が右旋
- 先唱後和・・・陽が先、陰が後
- 身体問答・・・陽が先、陰が後
- 交合結婚・・・ここは、、、特になし。二人で交合だから。
となるわけで、この、道理が絶対的に存在する、というのをしっかりチェック。
で、それ以上に大事なのは、2つあって。
①道理にもとづく手順に則している=神聖であること
儀礼化=神聖化
てことで、最終的には、日本の国土たる「大八州国」を神聖化したい訳です。そのためには、道理に基づく神聖な儀礼によって誕生した、ということを言っておきたい。やけに手続き臭いのは、そのためで。。意味があってわざわざやってるんす。
2つめは、
②この道理や手順を間違えると、、、とんでもない結果を生んでしまう
なぜなら、儀礼手順を間違える=道理を違える、てことだから。道理を違えるというのは相当なことなんす、、、
表側のストーリー展開では、結婚、洲国生みといった華やかなイベントが進行してるのですが、その裏側には、絶対的な原理原則が働いている。
で、その手順やルールを間違えると相応の結果(代償)を受けるという仕掛け。特に、先唱後和のところで明確に伝えてます。これは後ほど詳細を。
ということで、本文解説にはいるまえに、まず大前提として
- 結婚=儀礼。なので、手順やルールが決まってる。
- 儀礼化の目的は、「大八州国」神聖化である。
- 道理や手順を間違えると、、、とんでもない結果を生んでしまう。緊張感!
以上、
3つ踏まえたうえで、以下どうぞ!
- そこで、磤馭慮嶋を国の中心である柱とした。
- 便以磤馭慮嶋、為国中之柱。
→嶋を柱とする謎の行動、、、しかも国の中心だと??
実は、この「嶋を柱とする設定」は、神仙の山として名高い崑崙山を天柱とみなす思想の応用だったりします。
国の中心である柱=地の中央であり天と通う場所=崑崙山思想がベース
例を挙げれば、
- 「崑崙山、天中柱也」(『芸文類聚』巻七「崑崙山」所引「龍魚河図」)
- 「崑崙山為天柱」(『初学記』巻五「総戴地第一」所引「河図括地象」)
など。①②ともに、「天」を「国」という文字に変えれば本文のようになりますよね。特に、②の背景設定は、天柱の崑崙山から気が上昇して天に通い、そこが地の中央に当たると。
要は、これから結婚しようとしてるわけで、その聖なる儀式に相応しい場所として、地の中央であり天と通う場所としての「国中柱」が設定されてる訳です。
分かってる人には分かる、そういう設定。当時の先端知識体系である漢籍をベースにした創意工夫の痕跡であります。
次!
- そして、陽神は左から巡り、陰神は右から巡った。分かれて国の柱を巡り、同じ所であい会した。
- 而陽神左旋、陰神右旋。分巡国柱、同会一面。
→国の中心である柱=聖なる場所で展開される柱巡り。イメージコチラ!

実は、この左旋・右旋運動は、北の空、北極星を中心とした天と地の運動がトレースされてます。天文学!!

北極星を中心に、星(天)は左回り、対して、大地(地)は右回りに動くように見えますよね。
第一段でもお伝えしたように、日本神話は易の二項対立がベースなので、
- 乾・天・陽・男・奇数・・・伊奘諾尊
- 坤・地・陰・女・偶数・・・伊奘冉尊
といった、そもそも設定があるんです。なので、
- 陽であり、天の側の伊奘諾尊は左旋
- 陰であり、地の側の伊奘冉尊は右旋
根拠となる漢籍は、
- 「天ハ左旋シ、地ハ右動ス」(春秋緯・元命包)
- 「北斗ノ神二雌雄有り、・・・雄ハ左行シ、雌ハ右行ス」(淮南子・天文訓)
- 「天ハ左旋シ、地ハ右周ス。猶シ君臣陰陽相対向スルガゴトシ」(『芸文類衆』天部所引『白虎通』
といったところ。他にも細かいのがあるので詳細はコチラ↓で!
それにしても、、、天文学をベースに二神の神聖な儀式へと応用展開する構想力が超絶。古代日本人の創意工夫の凄さに震えが止まりません。。
次!
- その時、陰神が先に唱え、「ああ嬉しい、いい少男に会ったことよ。」と言った。陽神はそれを悦ばず、「私が男だ。理の上ではまず私から唱えるべきなのだ。どうして女が理に反して先に言葉を発したのだ。事はすでに不吉になってしまった。改めて巡るのがよい。」と言った。
- 時、陰神先唱曰、憙哉、遇可美少男焉。陽神不悦、曰、吾是男子。理当先唱。如何婦人反先言乎。事既不祥。宜以改旋。
→これ、学術用語で、「先唱後和」と呼ばれる箇所。先に唱して、後に和して唱する。
大事なのはその先後、順番。先ほどの易の二項対立より
- 乾・天・陽・男・奇数・・・伊奘諾尊(陽神) →先
- 坤・地・陰・女・偶数・・・伊奘冉尊(陰神) →後
という設定で。
なので、本来であれば、陽神(男)が先に唱して、陰神(女)が後に和して唱する、という手順を踏むべきなんだが。。。
「陰神が先に唱え、「ああ嬉しい、いい少男に会ったことよ。」と言った。」とあり、つまり、最初から順番間違えた!あかんやつ!!
だからこそ、伊奘諾尊が「陽神はそれを悦ばず、「私が男だ。理の上ではまず私から唱えるべきなのだ。どうして女が理に反して先に言葉を発したのだ。」というイラッと発言になる訳です。。。って内容がスゴいけど、、、(゚A゚;)ゴクリゴクリ。。
ポイントは、「理の上ではまず私から唱えるべきなのだ。どうして女が理に反して先に言葉を発したのだ。事はすでに不吉になってしまった。」のところ。
原文でも、「理当先唱。如何婦人反先言乎。事既不祥。」とあり、「理」という言葉が使われてます。この理=道理は「尊卑先後の序」。
「尊卑先後の序」をもとに、道理上は「陽主導」であるべきで、先に唱えるべき。というロジックが明確に伝えられてる。これ、激しく緊張感のある内容ですよね。。
むしろ陽神は分かってる。神様ですら従わないといけない道理=鉄の掟があり。これを違えると、とんでもないことになる。。。
ちなみに、第四段本伝ではやり直しするので大丈夫なんですが、〔一書1〕とかになると儀礼を間違える=原理を違えることで障がいのある子が生まれる、といった伝承に差異化されていきます。ここでは、その前兆として「事はすでに不吉になってしまった。(原文:事既不祥。)」と、「不祥」めでたくないこと、不吉なこととしてますよね。(すみません、ココ、あくまで神話伝承としてそうなってるってだけですのでご理解くださいまし)。
また、この問題は、結果としての子の良し悪しだけでなく、違える、間違えることは、儀礼としての神聖さが無くなってしまうって事に。それは、結婚の神聖さ、結婚によってうまれる大八州国の神聖さが失われるということで。
これはあきまへんな。
と。だからオコ入れる訳です。この道理の存在を前提とした発言の意味、しっかりチェック。
ということで、「事はすでに不吉になってしまった。改めて巡るのがよい。」として、やり直しにつながっていきます。
次!
- ここに、二柱の神はもう一度やり直してあい会した。今度は陽神が先に唱え、「ああ嬉しい。可愛い少女に会ったことよ。」と言った。
- 於是、二神却更相遇。是行也、陽神先唱曰、憙哉、遇可美少女焉。
→やり直す二神。今度は正しい手順で。。
ポイントは、陽神主導であり、「理」に則った結婚であることを強調してる、ってこと。
道理にのっとった儀礼だから正式な結婚といえる。その結果は、まさに神聖なる国=大八洲国!!
次!
- そこで陰神に「お前の身体には、なにか形を成しているところがあるか。」と問うた。それに対し、陰神が「私の身体には女の元のところがあります。」と答えた。陽神は「私の身体にもまた、男の元のところがある。私の身体の元のところを、お前の身体の元のところに合わせようと思う。」と言った。ここで陰陽(男女)が始めて交合し、夫婦となったのである。
- 因問陰神曰、汝身有何成耶。対曰、吾身有一雌元之処。陽神曰、吾身亦有雄元之処。思欲以吾身元処、合汝身之元処。於是、陰陽始遘合、為夫婦。
→ココ、学術用語で「身体問答」と呼ばれる個所。
身体問答とは、性別による男女のありかたの違いを、それぞれの形状をたがいに言表することによって、確めあうことをいいます。
言表とは、言い表すこと。言表し行為に及ぶ。神様行動特性(神コン)。
ポイントは、
神のかたち=人のかたち
神様の形状は、人間そっくり。てか、日本神話では「神様をモデルにして人間ができてる」という奥ゆかしいスタンス。神先人後。
余談ですが、、、この聖婚やってるころって、、、世界に光はあったのでしょうか?
天照大神はまだ誕生してません。てことは、、、世界に光はなかった?つまり真っ暗だった??? そうか、、だから二神は身体問答したんだね。真っ暗で見えないから。触り合って確かめる男女の巻???余談でした!

第三部解説
- 産む時になって、まず淡路洲を胞としたが、それは意に不快なものであった。そのため「淡路洲」と名付けた。
- 及至産時、先以淡路洲為胞。意所不快。故、名之曰淡路洲。
→交合して即出産???それにしても早過ぎじゃないかい!??
「産む時になって、まず淡路洲を胞としたが、」とあり、いきなり登場した淡路洲。。。しかも淡路洲を胞となす??「胞」というのは出産時に胎児が包まれてでてくる膜のことで、、
ちなみに、ココ、説としては、「第一子は生み損ないをするという思想の反映であろう。」とか、「生み損ないだからうれしくない。それで、吾恥。あはじ。自分は恥をかいたの意で淡路洲と名付けた。地名起源説話の一種。」といった説があるのですが、そんなこと書いてないし勝手な解釈です。まず、産んでないし。原文「及至産時(産むときになって)」って伝えてるだけ。しかも、淡路の「ぢ」は「し」に濁点の「じ」ではないので恥とか関係ない!別の言葉!ってことで、原文に忠実に解釈すべきです。
神話で伝えるコトを、文献を忠実に読み解くと、、、さーこれから産むよ-!というときになって、まず、淡路洲というのが既にあって、それを胞(膜)としたと。これってつまり、出てくる胎児(ここでは洲国のこと)を膜で包もうとした、ということになる。。
てことは、どうやら、神の出産は、胎児が「胞(膜)」に包まれて出てくるのではなく、胎児が出てくるときに「胞(膜)」を使う、という方法のようで。
これは恐らく、交合即出産と関連してると考えられ、、十月十日不要。てことは、胎盤でゆっくり育むのが不要、つまり、胎盤とあわせてできる「胎児を包む膜」も不要、てか、できない。膜ができないから、外部にある膜を用意して使うスタイル、、、と推測される訳です。
ちなみに、、第四段の遺伝である〔一書6、8、9〕でも同様のスタイルで出産。
- 〔一書6〕二神は交合して夫婦となった。まず淡路洲・淡洲を胞として、大日本豊秋津洲を生んだ。
- 〔一書8〕磤馭慮嶋を胞として淡路洲を生んだ。
- 〔一書9〕淡路洲を胞として大日本豊秋津洲を生んだ。
現代の私たちが近代合理や科学の力によって分かってるコトと、『日本書紀』編纂当時の人たちが分かってたコトには、大きなギャップがあって。。。出産は神秘そのもの。むしろ、神様スタイルと人間スタイルの出産の違いは、そういったロマンの中で考えて見るとオモシロくなると思います。
話を戻します。
その胞とした淡路洲なんですが、「それは意に不快なものであった。そのため淡路洲と名付けた(原文:意所不快。故、名之曰淡路洲。)」と。名辞の「淡路」は「あわぢ=あわない」。
「それは意に不快なものであった。」とあり、意図した=胞としようとしたのとは違う感じだったと。その不快感はきっと「淡」の文字に表れていて、淡い感じでふわーっとしていたのがダメだった??
なお、突然出現したように見える淡路洲なんですが、実際には、第四段最後のところで、「所々の小島は全て、潮の泡が凝り固まってできたものである。」とも伝えているので、そういう一環で形成された嶋だったと推測されます。
これまでの経緯のなかで、唯一、洲ができるところといえば、、、磤馭慮嶋ができるところ以外あり得ず、、つまり、磤馭慮嶋ができたときに付随して潮の泡や水の泡が凝り固まって「淡路洲」もできていた、それを胞として使おうとしたけど合わなかったと。そういう解釈に。
いずれにしても、少なくとも「淡路洲」は産んでないので、産み損ない説とかは違います!
次!
- そこで、大日本豊秋津洲(日本、日本では耶麻騰という。以下すべてこれにならえ)を産んだ。
- 廼生大日本〈日本、此云耶麻騰。下皆效此。〉豊秋津洲。
→そして始まる国産み。日本神話における日本という国土の起源説話個所!その最初は、本州たる「大日本豊秋津洲」!!
ま、本州といっても、今私たちが認識してるような本州全域というよりは、本州の一部、または畿内を中心とした本州といった感じで。
ポイント2つ。
①「日本」=国名の起源であり、独自性や独立性の宣言
日本神話史上初!「日本」という国号が登場。しかも、「耶麻騰(やまと)」と読む訓注がつけられてます。
まず、「日本」について。
ちょっと歴史の話になりますが、お付き合いください。
「日本」という言葉の源流は、それこそ607年(推古天皇代)、聖徳太子が隋に送った国書に「日出ずる処の天子」と称したところから。これ、日本が大陸側に従属する存在ではないことを示し、独立性を主張するものだった訳ですが、やっぱココからなんですよね。
この自覚というか自負というかマインドが時代をへて、日出ずる処=日の本=「日本」という国号として公式に使用され始めたのは、701年(大宝元年)に制定された大宝律令から。ここで、「明神御宇日本天皇詔旨」という、主に外国使に大事を宣する詔書が公式に整備され、「日本」の国名が明記されたことが、その最初とされてます。
それまでの「倭」に代わる正式な呼称として、「日本」を自称するようになった訳で。だって、「倭」って例えば、『漢書』地理志に日本の呼称として「倭」の字が使われたり、大陸側が日本を呼ぶときに使われてた言葉であって、、自分たちの言葉じゃないし。
一方で「やまと」について。
もともと「やまと」は、畿内、とくに奈良盆地を中心とした地域をさす言葉でしたが、7世紀前後には「倭」を「やまと」と読ませていたようで、国をさす言葉と「やまと」が結びついていた模様。
で、そうした経緯を経ての720年『日本書紀』編纂。
からの、ココ第四段で「日本」という国号を「やまと」とよませる形で伝えてる。コレ、やはり日本としての独立性を持ち、自国を東方で日が昇る「日出ずる国」と位置づける意識や自覚や自負をビシビシ感じる訳です。
もちろん、ここ国産みでは、国の正式名称としてではなくあくまで畿内を中心とする本州の名称で伝えてますが、そうは言っても「日本」という言葉の、神話史上初の登場シーンなんで、激しく重要事項としてチェック。
そして!
②「豊秋津洲」=豊かな実りのある国を予祝。東征神話の最終で再登場
この「豊秋津洲」、神武天皇が橿原即位して30年後、国見をしたときのシーンで再び登場します。
「国状」をはるかに望み見た神武天皇が、「妍哉、国を獲つること。内木綿の真迮国と雖も猶し蜻蛉の臀呫せるが如もあるかも。」と言い、これにより「秋津洲」の名が生じたと伝えています。
蜻蛉=トンボが交尾してつながり飛ぶ五穀豊饒の国を「秋津洲」の名が象徴的に表現している訳ですね。
いや、ほんと、、、ここでつながるのかーーー!!!というくらい、日本神話全体を貫き張られた壮大な「わたり」。ココ、国産みで誕生した「大日本豊秋津洲」は、最終、神武天皇が建国した国の歌につながっていく、、、この構想力、このスゴさを激しくチェック。
次!
- 次に、伊予二名洲を産んだ。次に、筑紫洲を産んだ。そして億歧洲と佐渡洲を双児で産んだ。世の人に双児を産むことがあるのは、これにならうのである。次に、越洲を産んだ。次に、大洲を産んだ。そして吉備子洲を産んだ。これにより、はじめて「大八洲国」の名が起こった。
- 廼生大日本〈日本、此云耶麻騰。下皆效此。〉豊秋津洲。次生伊予二名洲。次生筑紫洲。次双生億岐洲与佐度洲。世人或有双生者、象此也。次生越洲。次生大洲。次生吉備子洲。由是、始起大八洲国之号焉。
→次々に産んでいく継起的展開。
ポイントはたくさんあるぞー!ってところ。以下一覧。
| 1 | 大日本豊秋津洲 | 本州 |
| 2 | 伊予二名洲 | 四国 |
| 3 | 筑紫洲 | 九州 |
| 4 | 億歧洲 | 隠岐島 |
| 5 | 佐渡洲 | 佐渡 |
| 6 | 越洲 | 北陸道 |
| 7 | 大洲 | 周防国大島(山口県屋代島) |
| 8 | 吉備子洲 | 備前児島半島(岡山県) |
こうして産んだ「大日本豊秋津洲」以下の八洲をまとめて「大八洲国」と号する訳です。
ポイント3つ。
①産み方、順番はおおよそですがルールがある!
産み方、その順番は、直前の柱巡りの運動を踏まえて、おおよそ左回りに生んでいく!というもの。

を踏まえ、陽の動きをベースに、、、

(あくまで現場目線で)左回りで産んでいく訳です。
国中柱を左旋・右旋していた流れを踏襲。聖なる洲国の誕生ですから当然、陽神主導の左旋が利用されてる。
そして!
②「大八洲国」で国土が確立!しかも「八」は、多数を表す聖なる数!
「はじめて「大八洲国」の名が起こった。(始起大八洲国之号焉。)」とあります。
これ、国土が確立した瞬間として激しく重要事項であります。また、「八」は、意味としては、数が多い、めっちゃあるぞー!ってことで。誇らしげに、高らかに宣言してる感じを。。
ちなみに、八という数字について、神代紀に散見する例を他に挙げると、、
「八雷(八色雷公)」「八十万神」「八箇少女」「八丘八谷」「八十木種」「八日八夜」「八重雲」「百不足之八十隈」、またあるいは「八咫鏡」「八坂瓊曲玉」など、いずれも、「八」にちなむ例は「大八洲國」より後に登場。実は、ココからスタート、ここが起点になってるってことですね。
そして!
③「洲壌」と諾冉二神が生んだ「洲国」とは全然違う!責任の有無がポイント
「洲壌」は、第一段の本伝で登場。
「天と地ができる初めには、のちに洲となる土壌が浮かび漂う様は、まるで水に遊ぶ魚が水面にぷかりぷかり浮いているようなものなのである。(第一段 本伝)」とありました。天地開闢のはじめ、地上世界は固まっておらずドロドロ状態、、、土壌=土の固まりのようなもの、後に「洲」となる原料のようなもの=「洲壌」が、ぷかりぷかり浮いてる状態だったわけです。
そこから、男→男女と世代が下り、今、こうして国生みをしている。ココでのポイントは、
- 土壌が固まってできた「洲壌」と
- 伊奘諾尊、伊奘冉尊の二神が生んだ「洲国」とは
全然違う。それは、バラバラな「洲壌」に対して、まとまりをもち領土たる「洲国」との違い、のみならず、(自然発生的に)できた「洲壌」と、男女二神が(意志をもって)生んだ「洲国」との違いでもあり。
たしかに、なんか知らんけど勝手にできてたのと、意志をもって生んだのとでは、意味あいが全然違いますよね。
で、それは
無責任と責任発生の違い
でもあって、
二神による国生みは、男女の営みの結果として、でもそこには責任が発生してくるわけで。なので、コレを承けて次の第五段、国の主者を生む流れへつながって行く。
生みっぱなしにしない。国を生んだら、国を統治する「主者」を生む。これも責任を果たす枠組みのなかでの営みであります。
あと、細かい補足。
- そして、対馬嶋、壱岐嶋、及び所々の小島は、全て潮の泡が凝り固まってできたものである。または、水の泡が凝り固まってできたともいう。
- 即対馬嶋、壱岐嶋及処処小嶋、皆是潮沫凝成者矣。亦曰、水沫凝而成也。
→「大八洲国」をメインの国土としつつ、周辺の島々もしっかり参入。
ただし、ここでは洲と嶋は明確に使い分けがされてます。
- 洲・・・諾冉二神で産んだもの。最終的に国として一括される大きさをもつ
- 嶋・・・産んでない。潮の泡が凝り固まってできたもの。小島くらいの大きさ
ということで、生成プロセスの違いをチェックです。
最後に2点。
①第四段は、国をめぐるハードの整備とソフトの予定
第四段の〔本伝〕と異伝たる〔一書〕を通じて、基本は、国としての土台、ハードが整備されますが、それだけでなく、〔一書〕ではソフト面も予定されます。コレ、本伝と一書の役割分担の話でもあって。
〔本伝〕では、国のハード面重視。伊奘諾・伊奘冉尊を主体とし、「どうして国がないだろうか(きっと国があるはずだ)」と予祝し大八洲国を産む。ハードとしての国土形成。
〔一書1〕では、国のソフト面重視。天神を主体とし、「豊葦原千五百秋瑞穂之地」と予祝し大八洲国を生む。これは、本伝でハードたる国土形成を前提として、その中身の充実を伝えてる訳です。
それぞれ、本伝と異伝で「1伝承1メッセージ」のルールをもとに、ハード・ソフト両方から国の整いを伝えてるってことでチェック。
2つ目は、
②ステージを用意するのが第四段、ステージの主を登場させるのが第五段
第四段(国産み)は、続く第五段(神生み)とセットで捉えるのがポイントで。
洲国を生んだよと。で、そのあとは、国(号)が起こり、今度は、その国を統治する主、主者を生むことだよと。これが神生みにつながっていく。
ステージを用意するのが第四段、ステージの主を登場させるのが第五段、「生む」という行為を通じた大きな流れを「継起的に展開」してる。
ってことで、日本神話のダイナミックな展開を激しくチェックです!
国生み まとめ
『日本書紀』巻第一(神代上)第四段 本伝 ~聖婚、洲国生み~
再度、第四段本伝の位置づけ確認。
新しい時代の幕開け。
第一段~第三段の「道の働きによる神の誕生」から、伊奘諾尊・伊奘冉尊の「男女神の営み、行為による誕生」へ。まさに新時代到来。
ここでは、最終的に生まれる「大八洲国」を神聖化したいという動機を、そのための理論やロジックをしっかりチェック。
第四段のポイントとしては
第一部
- 「天浮橋」=天にあって地上世界全体が見渡せる橋
- 「国」=予祝&尊い
- 言表と行為=神様の行動パターン
- 天之瓊矛=矛の功、矛を使うことで特別なパワー発動!
- 磤馭慮嶋の誕生方法と名付けの意味
第二部
- 結婚=儀礼。儀礼化=神聖化である
- 国の中心である柱=地の中央であり天と通う場所=崑崙山思想をもとに応用
- 左旋右旋=北極星を中心とした天と地の動きをもとに展開
- 先唱後和 尊卑先後の序の大原則、物事の先後、順番という鉄板ルール
- 陽神主導、「理」に則った結婚と出産
- 身体問答 神のかたち=人のかたち
第三部
- 神様の出産方法 淡路洲を胞となす
- 「大日本豊秋津洲」は日本という国号の初出。秋津洲は予祝であり建国神話で結実
- 「大八洲国」=国土の確立 左回りに生んでいく
- 「洲壌」と諾冉二神が生んだ「洲国」とは全然違う!
と、まー盛りだくさん。。。
乾坤の道から道の働きによって誕生(化成)した男女神、その最後の世代である伊奘諾尊と伊奘冉尊による営みによって誕生した洲国、それは尊卑先後の序をベースにした正しい儀礼によって、手続きによって誕生したんだよと。それが大八州国。神聖さあふれる、なんてスゴイ洲国なんや!
要はこれが言いたい。
編纂当時の先端理論や知識の体系を取り込みつつ、単なる真似で終わるのでは無く、創意工夫し、自在に組み合わせ、独自の世界として構築展開してる。それが国産み神話の実態なのです。
日本のご先祖様がつくったスーパートレビアンな神話世界、是非すみずみまでご堪能くださいませ。
次は、第四段の一書を解説!
続きはコチラ↓第四段〔一書1〕天神登場!
『古事記』版国生みはコチラ↓で!
神話を持って旅に出よう!
国生み神話のもう一つの楽しみ方、それが伝承地を巡る旅です。以下いくつかご紹介!
●上立神岩:伊奘諾尊と伊奘冉尊が柱巡りをした伝承地
●自凝神社(おのころ神社):伊奘諾尊と伊奘冉尊の聖婚の地??
●絵島:国生み神話の舞台と伝えられるすっごい小さい島。。
●神島:国生み神話の舞台と伝えられるこちらも小さな島。。
こちらの記事も!補足解説!!
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




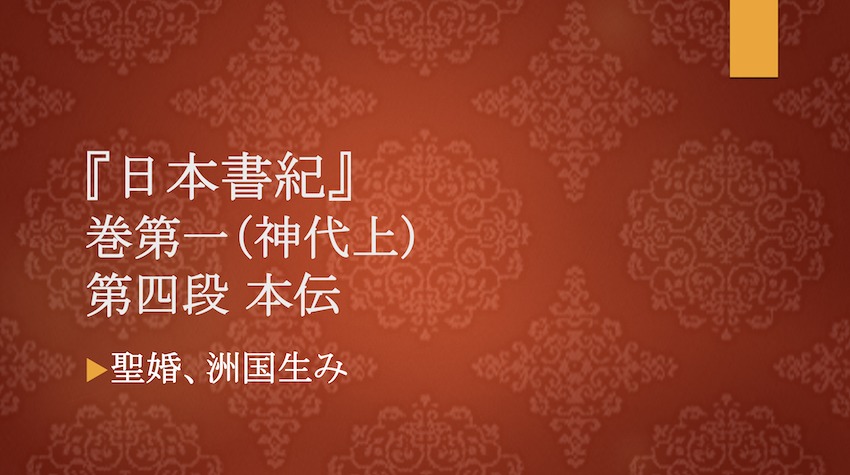






























大変面白く読ませていただいています。巻第一(神代上)第一段から第四段本伝までたどり着いたところです。
第四段本伝の内容につて質問があるのですが、ご教授いただけると大変うれしく思います。
①陽神は左から巡り、陰神は右から巡った。(而陽神左旋、陰神右旋)という部分について
「左から巡り」だと右回り(右旋)になる様な気がします。ここは、
「陽神は右回りに巡り、陰神は左回りに巡った。」みたいな言い方が妥当なのでは?
②淡路州について
淡路州は、磤馭慮島の別名ということはないのでしょうか?
③大八州国について
大八州国には、東北・北海道が含まれていませんよね?もしかして関東も含まれていないのかな?
この点はどういった解釈になるんでしょうか?
素人のたわ言で的外れでしたら申し訳ありません。ご教授いただけると大変うれしく思います。
宜しくお願い致します。
すいません。
質問①で記載間違いしてしまいました。
誤:陽神は右回りに巡り、陰神は左回りに巡った。
正:陽神は左回りに巡り、陰神は右回りに巡った。