多彩で豊かな日本神話の世界へようこそ!
正史『日本書紀』をもとに、
最新の文献学的学術成果も取り入れながら、どこよりも分かりやすい解説をお届けします。
今回は、『日本書紀』巻第一(神代上)第五段の一書の第2~5。
少々長いですが、まとまりのある一書群なので、せーのでお届け。
概要で全体像をつかみ、ポイント把握してから本文へ。最後に解説をお届けしてまとめ。
現代の私たちにも多くの学びをもらえる内容。日本神話から学ぶ。日本の神髄がここにあります。それでは行ってみましょう!
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
『日本書紀』巻第一(神代上)第五段 一書第2,3,4,5 ~卑の極まりと祭祀による鎮魂~
目次
『日本書紀』巻第一(神代上)第五段 一書第2,3,4,5の概要
からの続き。
下図、赤枠部分。本伝の下、一書2,3,4,5。

上図を見てのとおり、
第五段は、『日本書紀』神代の中で、最も異伝が多い段。こんな伝承もある、あんな伝承もある、と計11パターン。
『日本書紀』最大の特徴である、一書の存在。本伝と一書の関係についてはコチラ↓をチェック。
- 本伝の内容をもとに多角的、多面的に展開する異伝、それが一書。
- 本伝があっての一書であり、一書あっての本伝というように、お互いにつながり合って、関連し合って、踏まえ合って、多様で豊かな日本神話世界を構築している。
で、
それもそのはず。第五段は超重要テーマが目白押し。
特に、天下之主者生み、三貴神の誕生と分治、そして生と死の断絶など。今後の日本神話展開の起点となる設定がたくさん埋め込まれてる。
神ならではのワザ(神業)連発、神ならではの極端な振れ幅、基本的に意味不明。でも、ご安心を。当サイトならではの分かりやすいガイドがあれば迷うことはございません!
ということでコチラ

全11もある異伝も、大別すれば2通り。整理しながら読み進めるのが〇。
- 本伝踏襲 差違化型・・・〔一書1~5〕
- 書6踏襲 差違化型・・・〔一書6~11〕
※踏襲・・・踏まえるってこと。前段の内容、枠組みを。
※差違化・・・(踏まえながら)変えていくこと、違いを生んでいくこと。神話に新たな展開をもたらし、多彩で豊かな世界観を創出する。
で、今回お届けする〔一書2~5〕は、本伝踏襲差違化型。本伝の枠組みを踏まえつつも差違化によって変化を取り入れてる伝承の皆さんです。
『日本書紀』巻第一(神代上)第五段一書第2,3,4,5のポイント
ポイント3つ。
①尊をメインとした神生み〔一書1〕から、卑を中心とした神生みへ一転。極まっていく。
第五段〔一書1〕は、伊奘諾尊という陽神単独での神生み。しかも、「大日孁尊」「月弓尊」という尊の側に位置づけられる神々の誕生を中心に伝えてました。
それが、〔一書2〕からは一転。卑を中心とした神生みへ転換します。具体的には、
- 〔一書2〕:「卑」の誕生、最後に火神生み。伊奘冉尊焼死し臨終に神生み
- 〔一書3〕:伊奘冉尊の死をめぐる展開に特化。臨終に神生み
- 〔一書4〕:伊奘冉尊の死に際にフォーカス、その排泄物から神誕生
- 〔一書5〕:伊奘冉尊の死後、葬と祭により鎮魂、幕引き
といった流れ。
全体的に伊奘冉系の陰なる雰囲気が漂ってることチェック。このダークな感じは続く〔一書6〕で黄泉訪問へとつながっていきます。
次!
②卑へ転換したのは、あの時、原理に背いたから。その幕引きは葬と祭による鎮魂で。
尊から卑へ。真逆へ転換したのにはちゃんと理由があるんです。それが、なんと、第四段〔本伝〕、国生みの先唱後和での順番間違い。
え? そこ・・・???
実際、原理を違えたところから蛭子、素戔嗚尊、さらに〔一書2〕からは火神の軻遇突智と、、、「卑」なる子の誕生が続く流れに。。陰神先唱からすべてが狂い始めた。。。((((;゚Д゚))ガクブル
そして、このダークなモメンタムは、〔一書5〕の有馬村での葬と鎮魂の花祭りで収束する形になってます。
卑なる展開、負の連鎖、その幕引きは葬と祭で。
コレも、神話世界ならではの設定としてチェックしておきましょう。
次!
③火を通じて衣・食など生活に必要なものが生まれている
火神の誕生をきっかけに、伊奘冉尊の臨終を通じて神が誕生していきます。
| 〔一書2〕 | 土神埴山姫、水神罔象女、稚産霊 |
| 〔一書3〕 | 水神罔象女、土神埴山姫、天吉葛 |
| 〔一書4〕 | 金山彦、罔象女、埴山媛 |
で、
〔一書2〕では、火神が土神を娶り、稚産霊を生む。さらに、稚産霊によって「衣」と「食」が発生します。これ、意味は「生活の発生」。日本神話的に長重要事項。
また、〔一書3〕以降も、葛=薬や、金山=製鉄といった、人間生活に不可欠なものが発生していきます。
まとめます。
- 尊をメインとした神生み〔一書1〕から、卑を中心とした神生みへ一転する。極まっていく。
- 卑へ転換したのは、あの時、原理に背いたから。その幕引きは葬と祭による鎮魂で。
- 火を通じて衣・食など生活に必要なものが生まれている
以上、3つしっかりチェックして本文へゴー!

『日本書紀』巻第一(神代上)第五段 一書2,3,4,5の本文と解説
今回は複数の〔一書〕をせーのでお届け。なので、それぞれの伝承ごとに解説する流れで。伝承→解説、の順番。
第五段〔一書2〕の本文と解説
国立国会図書館デジタルコレクションより慶長4(1599)刊版 ある書はこう伝えている。日と月は既に生まれた。次に、蛭児を生んだ。この子は三歳になっても脚が立たなかった。初めに、伊奘諾・伊奘冉尊が柱を巡った時に、陰神が先に喜びの言葉を発したことで陰陽の原理を違えた。それにより今、蛭児が生まれた。
次に、素戔鳴尊を生んだ。この神は、神としての性質が悪く、いつも哭き叫び怒り恨んでいた。それで国の民が多く死に、青々とした山が枯れた。そのため、父母は勅して「もしお前がこの国を治めたならば、必ず多くをむごたらしく傷つけるだろう。だからお前は、はるか遠くの根国を治めよ」と命じた。
次に、鳥磐櫲樟橡船を生んだ。この船に蛭児を乗せ、流れにまかせ棄てた。
次に、火神の軻遇突智を生んだ。この時、伊奘冉尊は軻遇突智によって焼かれ終った。その臨終する間、倒れ臥し土神の埴山姫と水神の罔象女を生んだ。
そこで、軻遇突智は埴山姫を娶って稚産霊を生んだ。この神の頭の上に蚕と桑が生じ、臍の中に五穀が生じた。
罔象、これを「みつは」という。
一書曰。日月既生。次生蛭児。此児年満三歳、脚尚不立。初伊奘諾・伊奘冉尊、巡柱之時。陰神先発喜言。既違陰陽之理。所以今生蛭児。次生素戔鳴尊。此神性悪。常好哭恚。国民多死。青山為枯。故其父母勅曰。仮使汝治此国。必多所残傷。故汝可以馭極遠之根国。次生鳥磐櫲樟橡船。輙以此船載蛭児、順流放棄。次生火神軻遇突智。時伊奘冉尊、為軻遇突智、所焦而終矣。其且終之間。臥生土神埴山姫及水神罔象女。即軻遇突智娶埴山姫、生稚産霊。此神頭上生蚕与桑。臍中生五穀。罔象。此云美都波。 (『日本書紀』巻第一(神代上)第五段〔一書2〕より)
ということで。
第五段〔一書1〕から一転。「日月既生」が「尊」に当たるほかは、蛭児、素戔嗚尊、軻遇突智と、卑なる存在が次々に誕生。この流れは伊奘冉が焦かれ終ることでようやく止まった。。全体が「卑」を中心に展開。ダークなモメンタム。
以下詳細解説。
- ある書はこう伝えている。日と月は既に生まれた。次に、蛭児を生んだ。この子は三年経っても脚が立たなかった。
- 一書曰。日月既生。次生蛭児。此児年満三歳、脚尚不立。
→第五段〔本伝〕以来の登場、蛭児!
「日と月は既に生まれた(原文:日月既生)」とあります。コレ〔本伝〕の内容、日神・月神誕生のこと。そこからスタートしてるので、本伝踏襲の意味としてチェック。
その後に伝える「次に、蛭児を生んだ。この子は三歳になっても脚が立たなかった。(原文:次生蛭児。此児年満三歳、脚尚不立。)」も、第五段〔本伝〕と対応。以下。
次に、蛭児を生んだ。しかし三歳になっても脚が立たなかった。それゆえ天磐櫲樟船に乗せ、風のまにまに放棄した。
次生蛭兒 雖已三歳 脚猶不立 故載之於天磐櫲樟船 而順風放棄(『日本書紀』巻一(神代上)第五段〔本伝〕より)
蛭児の容態については、ほぼ同じ内容で伝えてますよね。放棄方法に若干の違いがありますが、コレは後ほど。
ということで、まずは、〔一書2〕は〔本伝〕踏襲、特に蛭児以後の卑をフィーチャーしてるってことでチェック。
次!
- 初めに、伊奘諾・伊奘冉尊が柱を巡った時に、陰神が先に喜びの言葉を発したことで陰陽の原理を違えた。それにより今、蛭児が生まれた。
- 初伊奘諾・伊奘冉尊、巡柱之時。陰神先発喜言。既違陰陽之理。所以今生蛭児。
→突然登場する謎の種明かし、、、え??そうだったの??
ポイント2つ。
①原理を違えることで招来する「卑」の誕生
蛭児を生んだが、三年経っても足腰立たず、、、この理由が、国生みの柱巡りの時に、陰神、つまり伊奘冉尊が先に声をあげてしまったからだ、と伝えてます。
コレ、実は第四段〔本伝〕のことで。覚えてますか、あの時のこと、、
その時、陰神が先に唱え、「ああ嬉しい、いい少男に会ったことよ。(少男、ここでは烏等孤という。)」と言った。陽神はそれを悦ばず、「私が男だ。理の上ではまず私から唱えるべきなのだ。どうして女が理に反して先に言葉を発したのだ。事はすでに不吉になってしまった。改めて巡るのがよい。」と言った。
時、陰神先唱曰、憙哉、遇可美少男焉。〈少男、此云烏等孤。〉陽神不悦、曰、吾是男子。理当先唱。如何婦人反先言乎。事既不祥。宜以改旋。(『日本書紀』巻一(神代上)第四段〔本伝〕より)
確かに、「伊奘諾・伊奘冉尊が柱を巡った時に、陰神が先に喜びの言葉を発したことで陰陽の原理を違え」てましたね。陽神がそれを指摘し、やり直しをしてました。
で、ここ第五段〔一書2〕で「それにより今、蛭児が生まれた。」とあるので、伝えたいメッセージとは、
原理を違えると卑なる結果を招いてしまう
てことで。。結構、恐ろしいことを伝えてますよね。。でも、実際、原理を違えたところから、蛭子、素戔嗚尊、さらに〔一書2〕からは火神の軻遇突智と、、、「卑」なる子の誕生が続く訳で。
陰神先唱からすべてが狂い始めた。。。((((;゚Д゚)))ガクブル
てことで、神世界的には原理を違えることは「卑」の誕生を招く、身震いとともにチェック。
次!
②負の連鎖は、母体たる伊奘冉の死を引き寄せる
国生みで、原理を違え陰神先唱したことをきっかけに続くダーク展開は、結果、伊奘冉自身の焦死を引き寄せます。これつまり、原理を違えると原因を作った自分自身に跳ね返ってくる、、、ってことで、かなりダークなブーメラン。
解釈として、乾坤の道から、原理によって誕生した神は、原理に規定され、原理そのものを内在しているわけで、そうした存在が原理を違えてしまうって事は自己否定そのものであり、結果として火神による焼死を招くのもむしろ当然と考えるべきなんだと、それが原理というものなのだ、ってこと、、、なのかい!??
いずれにせよ、日本神話史上初のブーメラン。こんなところで発生してましたってことでチェック。
次!
- 次に、素戔鳴尊を生んだ。この神は、神としての性質が悪く、いつも哭き叫び怒り恨んでいた。それで国の民が多く死に、青々とした山が枯れた。そのため、父母は勅して「もしお前がこの国を治めたならば、必ず多くをむごたらしく傷つけるだろう。だからお前は、はるか遠くの根国を治めよ」と命じた。
- 次生素戔鳴尊。此神性悪。常好哭恚。国民多死。青山為枯。故其父母勅曰。仮使汝治此国。必多所残傷。故汝可以馭極遠之根国。
→蛭子の次は素戔鳴尊。この神、かなりの困ったちゃんで。。。
ここで伝える素戔嗚尊の性質も、蛭子同様、第五段〔本伝〕と対応。以下。
この神は勇ましく強く残忍であって、いつも哭き泣くことを行いとしていた。このため、国内の人民の多くを早死にさせ、また青々とした山を枯らしてしまった。
此神 有勇悍以安忍 且常以哭泣爲行 故令國内人民 多以夭折 復使青山變枯(『日本書紀』巻一(神代上)第五段〔本伝〕より)
ということで、〔本伝〕と同じような内容。〔一書2〕は〔本伝〕踏襲型ってのを再確認しつつ、、
「この神は、神としての性質が悪く、いつも哭き叫び怒り恨んでいた。それで国の民が多く死に、青々とした山が枯れた(原文:此神性悪。常好哭恚。国民多死。青山為枯。)」とあります。
「哭き叫び怒り恨んでいた」=「哭恚」について。
「哭」は、大声で泣き叫ぶこと。単に泣くのではなくそれこそ「泣き叫ぶ」「号泣する」など激しい感情の表現。特に、古代の葬送儀礼として、死を深く悲しんで大声をあげて哭くといったことが行われてました。
用例として、同じく第五段〔一書6〕で、伊奘冉尊の死を嘆く伊奘諾尊が
そこで伊奘冉尊の頭の辺りを腹ばい、脚の辺りを腹ばいして、哭いて激しく涕を流した。
則匍匐頭邊 匍匐脚邊 而哭泣流涕焉 (『日本書紀』巻一(神代上)第五段〔一書6〕より)
ということで、死を深く悲しんで大声をあげてのたうちまわりながら哭くということを葬送儀礼的に行ってます。哭くとはそういう泣き方。
話を戻して、
残忍な神が哭き叫ぶ訳ですから、その凄まじさは想像を絶するものだったに違いない。空も山も海も大地もことごとく鳴動、ビリビリ世界が震える壮絶さ。。
「恚」について。これ、古訓で「ふつくむ」と読み、「いかる」「うらむ」という意味。主に「心に怒りや恨みを抱くこと」。
ポイント2つ。
①素戔嗚尊の神性!?哭くことで「命」を奪う恐るべき神
本伝同様、ポイントは、この素戔嗚尊の凶暴性は、素戔嗚尊が本来「神性」として持っている性質である、ってこと。生まれながらの無垢凶暴。外的要因によって怒る訳でもなく、不満がある訳でもない。ここでの素戔嗚尊はそういう神として描かれてます。
イメージとして、台風、地震、津波など自然の持つ猛威、それは人間側の事情とか生活とか関係なく根こそぎ破壊していくような、自然とはそういう性質・性格を持つ。
ちなみに、、
異伝である〔一書6〕以降の素戔嗚尊は、不公平な処遇に対する怒り、不服を根拠とした凶暴性発揮なので、別の描かれ方をしてます。
次!
②民を死なせ青山を枯らすのは、卑=陰の働きである「殺」によるもの
国の民がたくさん死んでしまうし、青々とした山は枯れてまうし。。。って、なんて恐ろしい((((;゚Д゚))))
て、、、いつのまにやら国の民がいることになっとる。。??ま、それはいいか。
大事なのは、この「民が死ぬ」のも「青山が枯れる」のも、いずれも、素戔嗚尊=卑=陰の働きである「殺」によるもの。だってこと。詳細はコチラ↓で。
日本神話のベースにあるのは易の思想。乾坤や陰陽など二項対立の根源から世界はできていて、特に、陽や陰が持つ自律的かつ自動的な働きとして、
- 陽の働き=徳を謀る=成長させていく、
- 陰の働き=刑を謀る=殺していく、枯らしていく
というものがある訳です。四季があるのもこの働きによるもの。この陽と陰は、そのまま尊と卑であり、つまり、「卑」は、そもそも陰の働きである「殺」というのを内在してる、ってことで。素戔嗚尊により「民が死ぬ」のも「青山が枯れる」のこうした「殺」の働きによるものとして伝えてるってことなんす。
次!
「そのため、父母は勅して「もしお前がこの国を治めたならば、必ず多くをむごたらしく傷つけるだろう。だからお前は、はるか遠くの根国を治めよ」と命じた(原文:故其父母勅曰。仮使汝治此国。必多所残傷。故汝可以馭極遠之根国)」とあります。
「むごたらしく傷つける」=「残傷」について。「残」は、残忍の意で、むごたらしいこと。なので、「むごたらしく傷つける」。
「治めよ」=「馭」について。読みは「馭らす」、意味は、馬をあやつる。馬に乗る。そこから転じて、おさめる。統治する。
「馭」は、結構大事な漢字。元々は、馬を制御する様子を表す会意文字で、左側の「馬」+右側の 「又」。「又」は語源的に「右手を伸ばして物を取ろうとする象形文字」で「持つ」「進める」の意味。なので、手で馬を操る、馬をてなずける、乗りこなす、からの、支配する、管理する。
なので、「馭極遠之根国」は、極遠の根国を統治する、という意味になります。
で、「馭」については実は、日本神話の最終、神武東征神話の最後で橿原即位した神武天皇が、自らを「始馭天下之天皇」としています。意味は、「初めて国を治めた天皇」ということで。ここでも、統治する・治める意味で「馭らす」という言葉が使われてるんです。
ポイント2つ。
①勅=国家意志の発動になぞらえた超重要命令
「勅(ちょく)」は、天皇の命令、またはその命令が記された文書のこと。絶対命令、NO無し。全員起立!
「勅して〜(勅)」とあり、突然ですがコレ、「本朝」の権威を前提として、国家意志の発動になぞらえる形で、超重要命令として使われてます。
いつから勅発動する権威をゲットしたの?という疑問は置いといて、なんせ〔一書2〕は本伝踏襲。〔本伝〕では「天下之主者」生みをテーマに、統治領域設定の根拠として「勅」という言葉が使われてました。統治には権威が大事。
「根国を治めよ」とあり、統治領域を設定する場面だからこそ、権威を持った絶対命令として「勅」が使われてる、ってことでチェック。
次!
②追放する根国の位置づけ=遙か彼方の僻遠の地
勅命追放処分となった素戔嗚尊ですが、その追放先は根国。〔一書2〕では、遙か彼方にある異界として位置付けられてます。
「極遠之根国」とあるように、これまでの「遠い所」(本伝)から「遙か彼方の世界の端っこくらいの勢いのめちゃくちゃ遠い所」へ差異化。それこそ、遠すぎて見えませーん!
ちなみに、『日本書紀』で伝える「根の国」関連トピックまとめると、、、
| 本伝 | 遠適之於根國 | 水平方向+遠い |
| 一書1 | 令下治根國 | 下方向 |
| 一書2 | 馭極遠之根国 | 水平方向+極遠・世界の果て |
| 一書6 | 從母於根國 | 下方向+母:伊奘冉に従う |
といった感じに差異化されてることもチェック。
さらに、位置的に、日本神話的地上世界マップはこんな感じになってます。

根国については、コチラ↓で詳しく。
実は、根国には、「四裔」=国の四方の果て、鬼の住む場所。というモデル、背景設定があったりします。是非チェックされてください。
次!
- 次に、鳥磐櫲樟橡船を生んだ。この船に蛭児を乗せ、流れにまかせ放棄した。
- 次生鳥磐櫲樟橡船。輙以此船載蛭児、順流放棄。
→船を生んで、流す、、だと??!
「鳥磐櫲樟橡船」の解説の前に、この流し放棄するについて解説。ポイント2つ。
①不祥の結果は「穢悪」にまみれた存在。そんな時は水による濯滌・除去でスッキリ♪
先ほど解説した通り、「初めに、伊奘諾・伊奘冉尊が柱を巡った時に、陰神が先に喜びの言葉を発したことで陰陽の原理を違えた。それにより今、蛭児が生まれた。」とありました。
なので、蛭児は第四段本伝を継承してるとみるべきで。要は、「不祥の子」。
この「不祥」については類例があって、
ただし、伊奘諾尊は自ら泉国を見てしまった。これはまったく良くないことであった。それで、その穢れを濯ぎ除こうとした。 (原文:但親見 泉国 。此既不祥。故欲 濯除 其穢悪 。(『日本書紀』巻一(神代上)第五段〔書十〕)
ということで、
ポイントは、「不祥」の結果というのは「穢悪」な存在であり、本来的に「濯除」など、水による濯滌・除去を必要とするものなんす。
不祥=穢れてる、だから水で流す、除去する。
そういう概念があるからこそ、流れにまかせて棄てた「順 流放棄」という表現になってる。
蛭児の放棄は、共同体の存立を損ないかねない存在を、異物として排除する習俗、あるいは慣行の起源を物語っている(と、見るほかなく、、、)。
その意味で、本件は、始原における神世界の生存原理に根差してる、とも言えて。この時点では、神ワールドといえど「神聖の保持」に心砕く、、、といった感じで。なかなかな雰囲気であります。
いずれにせよ、そこには水による穢れの除去、祓いの意味が込められてるってこと。子を放棄する船まで生んで!周到な処分を行ったと解釈すべきというのも合わせてチェック。
次!
②鳥磐櫲樟船。不祥=穢れてる、だから水で流す、除去する、そのための船
「鳥」は水鳥のことで、「順流」と対応し、鳥(水鳥)=流→水鳥が泳ぐことでできる流れ。で、流棄用の船として「流れ」を生み出すものとして冠されてます。「磐」は立派な。「櫲樟」は、クスノキの別称。常緑樹。
「櫲樟」の別称であるクスノキは、独特な香があることから「臭き木(くすしき)」が語源。防虫剤である樟脳の原料。古代より、その香りの強さから邪気を払う呪力があるとされてきました。
ちなみに、後段で、素戔嗚尊が「杉と櫲樟とを「浮宝=船」にすべし」と伝え、船の建造用材としてクスノキがあったことも分かります、また、考古学的調査からは、実際にクスが古代船の船材として多用された発掘も相次いでたりします。
不祥=穢れてる、だから水で流す、除去する訳で、「鳥磐櫲樟船」の登場は、こうしたコンテクストから。その他詳細はコチラ↓で
次!
- 次に、火神の軻遇突智を生んだ。この時、伊奘冉尊は軻遇突智によって焼かれ終った。その臨終する間、倒れ臥し土神の埴山姫と水神の罔象女を生んだ。
- 次生火神軻遇突智。時伊奘冉尊、為軻遇突智、所焦而終矣。其且終之間。臥生土神埴山姫及水神罔象女。
→ついに登場!火の神・カグツチ!!!
ポイント2つ。
①卑の連続誕生は、母体である伊奘冉の死によってでしか止められなかった
蛭児、素戔嗚以上に「卑」!非道の極み火神「軻遇突智」初登場!
って、生まれた瞬間に、生んでくれた母を、おのが火によって、死に至らしめる!という、、
日本神話史上初の、神殺し&親殺しをやってのける。
ものスゴい神として伝えてます。ポイントは、
- 蛭児、素戔嗚と、卑の誕生が続いていた中での誕生だった
- 卑の連続誕生は、母体である伊奘冉の死によってでしか止められなかった
の2点。軻遇突智は、ここ第五段〔一書2〕で誕生し、第五段〔一書3〕〔一書4〕〔一書6〕〔一書7〕〔一書8〕と伝承をまたがって活動。
軻遇突智について詳細はコチラ↓で
主な役目としては、神殺し&親殺しをもやってのける猛烈な神、という設定をもとに、
- 卑の連続出産という悪循環を止める
- 人間の生活必需品誕生のきっかけをつくる
- 猛烈な神を化成させる元となる
といった3点。
特に、2つ目と3つ目。火神ならではの役目であり、そこには古代日本人の世界観や精神性が表れてるように思います。この後の展開を要チェック。
次!
「(伊奘冉尊は)その臨終する間、倒れ臥し土神の埴山姫と水神の罔象女を生んだ(原文:其且終之間。臥生土神埴山姫及水神罔象女)」とあります。
ポイント1つ。
①時代に逆行?だからこそ、生み方の違いには意味がある!
これまでの道が持つ働きによって化生する展開から、男女神の結婚と出産によって国や神が誕生する展開へ。大きな時代変化のただ中にあって、本来であれば出産による神誕生であるべきなんですが、
- よほどのスゴイ神が化出させる場合
- よほどのスゴイ事件が発生した場合
- よほどのスゴイ儀式が行われる場合
この3つに限って、単独による神化成イベントが発生。
時代と逆行してるんだけど、、、
①の場合は、化出させる神自身の神威を根拠として。②の場合は、その事件の激烈さ・劇的さを根拠として。③の場合は、その儀式の神聖さを根拠として、それぞれ単独神化成。
要は、それだけ特別で重要だということを強調してる、ってことでチェック。
ココで言えば、②に該当。で、よほどのスゴイ事件とは、やはり、「日本神話史上初の神殺し」ってやつ。。やっぱり、コレ、とてつもない殺神事件で。その強烈さを根拠として「土神の埴山姫」「水神の罔象女」が誕生してます。そしてこの土と水をもとに人間の生活必需品誕生に繋がっていきます。
次!
- そこで、軻遇突智は埴山姫を娶って稚産霊を生んだ。この神の頭の上に蚕と桑が生じ、臍の中に五穀が生じた。
- 即軻遇突智娶埴山姫、生稚産霊。此神頭上生蚕与桑。臍中生五穀。
→火神が土神を娶って稚産霊を生む、、、って、どいうこと??
ポイント2つ。
①火神が土神を選び取り結婚=焼畑農業、農の起源譚?
「軻遇突智は埴山姫を娶って」とは、火神が土神を選び取り結婚したってことで。それが「稚産霊」の誕生につながる。さらに水神のはたらきにより桑や五穀といった農産物の発生に至る、、、
この「火神が土神を選び取り結婚」とは、焼畑農業と考えられます。焼畑により、植物の生育に必要な肥沃な土壌が形成される、それが桑や五穀発生に繋がっていく訳です。
次!
②「稚産霊」を通じた、人間の生活必需品たる「衣・食」の起源譚
「稚産霊」について。「稚」は若々しい、「産霊」は生成を意味。穀物の生育を司る神。
「この神の頭の上に蚕と桑が生じ、臍の中に五穀が生じた。」とあり、意味としては、「蚕と桑」は衣食住の「衣」を、「五穀」は「食」の発生ってことであり、重要なのはつまり「生活の発生」ってことであります。
「住」は、、、ま、いいじゃないですか、そんなもん。住もうと思えばどこでも住めるし。住めば(どこでも)都だし。
、、、て、コレって、、人間が生まれていることが前提になってますよね。。。人間、いつ生まれてた??
人間にまつわるこれまでの伝承としては、
- 本伝では、素戔嗚が国の民を若殺し
- 〔一書2〕でも、同じく素戔嗚尊が民を殺し
ってことで、殺す民がいたってことは人間が生まれてるってことで、コレまでの経緯を踏まえて推測するに、どうやら、、、国生みをして山川草木生みしてるうちに人間さんも生まれてたみたいです、。。
だからこそ、ここで、衣食住を用意。つまり「生活の発生環境を整備した」ってことなんす。
人類すでに誕生。なので、衣食住のうち「衣」「食」が用意され、「生活」が発生する。。。
この流れ、是非チェック。
次!
③母の生んだ土台に桑や五穀=農が発生。それを承けて農業発生へ繋がっていく
伊奘冉尊が生んだのは土神、水神。この土・水という土台に桑や五穀が発生する。イメージ的には、大地母的存在として「農」発生への道を拓いた感じで。
それを承けて、同じ第五段の〔一書11〕では、天照大神による養蚕開始&農業開始へつながっていきます。
↑「業」なんで、反復継続して社会的な規模で行うわけで。〔一書11〕では、村長も誕生してるし、養蚕の道も拓けてます。
つまり、ここで「農の発生」は、〔一書11〕の「養蚕&農業の発生」へ向けた「わたり」として組み込まれてる、ってこと。非常に練りに練られた神話構造。素晴らしすぎます。
ということで、
「卑」に当たる子の出産と、火をめぐる五穀等の起源をつたえる〔一書2〕でした。

第五段〔一書3、4〕の本文と解説
続けてご紹介する〔一書3〕と〔一書4〕。
内容的には、伊奘冉尊の死にフォーカスしつつ生活必需品の発生を伝えてます。
ポイント2つ。
- 「間際」のお話。〔一書3〕で伊奘冉尊の死ぬ間際を、〔一書4〕で火神を生む間際を。
- 〔一書2〕をもとにした差違化伝承。形式、枠組み踏襲。表現変化。
詳細後ほど解説。まずは本文をご確認ください。

<一書3>
ある書はこう伝えている。伊奘冉尊は火産霊を生む時に、子のために焼かれ神退った。又は神避ると言う。その神退る時に、水神 罔象女と土神 埴山姫を生み、また天吉葛を生んだ。
天吉葛は「あまのよさづら」と言う。又は「よそづら」とも言う。
一書曰。伊奘冉尊生火産霊時。為子所焦而神退矣。亦云神避矣。其且神退之時。則生水神罔象女及土神埴山姫。又生天吉葛。天吉葛。此云阿摩能与佐図羅。一云、与曾豆羅。 (『日本書紀』巻第一(神代上)第五段〔一書3〕より)
<一書4>
ある書はこう伝えている。伊奘冉尊は火神 軻遇突智を生む時に、熱に悶え懊悩し、そのため嘔吐した。これが神に化した。名を金山彦と言う。次に、小便した。これが化して神となった。名を罔象女と言う。次に、大便した。これが化して神となった。名を埴山媛と言う。
一書曰。伊奘冉尊且生火神軻遇突智之時。悶熱懊悩。因為吐。此化為神。名曰金山彦。次小便。化為神。名曰罔象女。次大便。化為神。名曰埴山媛。 (『日本書紀』巻第一(神代上)第五段〔一書4〕より)
ということで。以下書3,4まとめて詳細解説。
伊奘冉尊の死にフォーカスした2つの異伝。
〔一書2〕をもとに差違化。形式や枠組みを踏襲しながら表現を変化させてます。
- 〔一書2〕
其且 終 之間、
→臥生 土神埴山姫及水神罔象女 。 - 〔一書3〕
其且 神退 之時、
→則生 水神罔象女及土神埴山姫 。又生 天吉葛 。 - 〔一書4〕
且生火神軻遇突智之時、悶熱懊悩。
→因為 吐。此化為 神。名曰 金山彦 。次小便。化為 神。名曰 罔象女 。次大便。化為 神。名曰 埴山媛 。
「~時、+ 生まれる神たち」といった形式で揃えつつ、表現変化させてますよね。
内容的にも、
- 伊奘冉の死ぬ間際を〔一書3〕で、
- 火神を生む間際を〔一書4〕で、
それぞれ振り分けながら伝えてます。
ここで、生まれた神を確認。
| 一書2 | 土神埴山姫、水神罔象女、稚産霊 |
| 一書3 | 水神罔象女、土神埴山姫、天吉葛 |
| 一書4 | 金山彦、罔象女、埴山媛 |
埴山姫(媛)、罔象女は共通で、 稚産霊、天吉葛、金山彦が一書ごとに独自。
〔一書2〕をもとに〔一書3〕〔一書4〕を考えると、ここでも人間の生活に必要な神として解釈できます。
天吉葛の「葛」は、用途がホントに色々あって、、食用や薬用(葛粉、葛根)はたまた、葛布(くずふ)など、、特に、「葛粉」は食用として利用するほか、滋養強壮のための葛湯や、葛餅などの和菓子の原料になったり。また、葛の根を乾燥させた「葛根」は生薬として用いられ、現代でも広く知られてる漢方薬の「葛根湯」の主原料となったり。コレ、発汗作用、解熱作用、鎮痛作用などがあり、風邪の初期症状、頭痛、肩こり、下痢などに効果があるとされてました。
金山彦=鉱石を火で熔とかしたさま。それが嘔吐に似ていることからの連想と考えられます。
ちなみに、金属加工の歴史で言うと、古墳時代に朝鮮半島から製鉄職人の一団が日本にやってきて「たたら吹き製鉄」を広めたといわれていて、当初は鉄製の刀や斧など鉄製品だったのが、大和朝廷になると古墳の副葬品に鉄の甲冑や鉄刀、剣、鉄板、鉄斧、鉄鎌など武器が多くなっていく。それが飛鳥時代に入ると、仏像の製作や寺院装厳具などにうつり、天武天皇代に貨幣経済の先駆けとして、日本列島最古の銅銭「富本銭」が鋳造されてます。
いずれにしても、
〔一書2、3、4〕を通じて、伊奘冉尊が生んだ土神・水神という土台に桑や五穀が発生、さらに、葛=薬?や金山=製鉄・鋳造など、人間生活に不可欠なものが誕生していて、いずれも、大地からいただく恵み的な感じで、まさに大地母的神格の獲得としての意味がある。。。「母なる大地」「母なる自然」と言われるように、日本神話でも大地や自然の豊かな生命力、多産、豊穣を神格化した女神として伊奘冉尊が描かれてるのかもしれません。
次!
第五段〔一書5〕の本文と解説
国立国会図書館デジタルコレクションより慶長4(1599)刊版 ある書はこう伝えている。伊奘冉尊は火神を生む時に焼かれ神退去った。故に、紀伊国の熊野の有馬村に葬った。その土地の習俗としてこの神の魂を祭る時には、花の時期には花をもって祭り、また鼓や笛や旗を用いて歌い舞って祭るのである。
一書曰。伊奘冉尊生火神時。被灼而神退去矣。故葬於紀伊国熊野之有馬村焉。土俗祭此神之魂者。花時亦以花祭。又用鼓・吹・幡旗、歌舞而祭矣。(『日本書紀』巻第一(神代上)第五段〔一書5〕より)
ということで。以下詳細解説。
- 伊奘冉尊は火神を生む時に焼かれ神退去った。
- 伊奘冉尊生火神時。被灼而神退去矣。
「神退去った(原文:神退去)」は超重要ワード。コレまでの伊奘冉尊の焼死ワードをまとめてみます。
- 〔一書2〕終った
- 〔一書3〕神退った
- 〔一書5〕神退去った
火神に焼かれ臨終する際の表現を少しずつ差異化してきた訳ですが、ここ〔一書5〕ではついに「去」という言葉が追加されました。これ、ただ単に死滅する以上に、この世界からの退去としての意味があるんです。
つまり、
卑としての伊奘冉がこの世界から退去する
逆に言うと、
尊としての伊奘諾中心の世界へ移行する
ということでもあるんですよね。この後の、鎮魂によって幕引き、決着をつけた、という意味だけでなく、卑は退去、尊がメインとなる世界へ移行するという意味があるってこと、激しく重要なのでしっかりチェック。
次!
- 故に、紀伊国の熊野の有馬村に葬った。その土地の習俗としてこの神の魂を祭る時には、花の時期には花をもって祭り、また鼓や笛や旗を用いて歌い舞って祭るのである。
- 故葬於紀伊国熊野之有馬村焉。土俗祭此神之魂者。花時亦以花祭。又用鼓・吹・幡旗、歌舞而祭矣。
→突然登場するリアル地名。、、どういうこと???
ポイント3つ。
①伊奘冉尊を葬った「紀伊国の熊野の有馬村」の伝承地が、三重県熊野市にある「花窟神社」
日本神話では重要イベント、重要スポットについては今回のようにいきなりリアル地名が登場します。解釈としては、それだけ重要だってことで。
今回の「紀伊国の熊野の有馬村」も、伊奘冉尊を葬った場所として超絶重要。なので、あえて記載されてます。これ、現在の三重県熊野市とされ、ここに日本神話ファンとしては鉄板のビジットスポットである「花窟神社」があります。
「花窟神社」には高さ約45メートルの巨大な「磐座」があり、この巨岩を「伊奘冉尊の御神体」としてお祭りをしてきました。

黄泉譚の顛末もふまえ、なんせ伊奘冉尊を鎮める訳ですから、これくらいの巨岩がないととてもじゃないか鎮められません!
ちなみに、三重県熊野市と伊奘冉尊は、神武東征神話でも登場。神武一行を襲った暴風雨の正体が実は、、コチラもあわせてチェックされてください。
次!
②有馬村の花祭り伝承は、亡き伊奘冉尊の魂を祭り鎮める目的の重要なお祭り
「その土地の習俗としてこの神の魂を祭る時には、花の時期には花をもって祭り、また鼓や笛や旗を用いて歌い舞って祭るのである。(原文:土俗祭此神之魂者。花時亦以花祭。又用鼓・吹・幡旗、歌舞而祭矣)」とあります。
原文にある「土俗」というのは、伊奘冉尊を埋葬した有馬村の習俗のことを言います。その土地の人々は、この神の魂を祭る時には、花をもって祭り、鼓や笛や旗を用いて歌い舞って祭ったと。
コレ、類例があって、2つご紹介します。
1つが、神功皇后の新羅親征。
新羅から無事帰国した後、これに従軍した「住吉三神」が皇后に「我が荒魂を穴門(長門=現在の山口県)の山田邑で祭れ(我荒魂 令祭 於穴門 山田邑也)」と誨えます。この神の誨えをうけて、穴門の直の祖、践立を「為祭荒魂之神主」とし、さらに「仍祠立」と伝えます。(以上、神功皇后摂政、仲哀天皇九年十二月)
この「祠」と同様のものを立て、有馬村の習俗として祭ったと考えられます。
2つ目は、天武天皇の崩後の殯宮儀礼。
天武天皇崩後の際、殯宮儀礼が行われたのですが、「次に国々の造たちが参り出てそれぞれが誄をして種々の歌舞を奏じた。(次国々造等、随参赴各誄之。仍奏種々歌舞)」(天武天皇朱鳥元年九月)という内容。
この「歌舞」に通じるのが今回の「歌舞而祭」。亡き伊奘冉尊の魂を祭り、鎮めることが目的のお祭りであります。
次!
③〔一書2〕から「卑」をめぐって展開してきた所伝に幕引き。伊奘冉尊の鎮魂を果たす。
伊奘冉尊を葬ってお祭りをする、これにより、〔一書2〕から「卑」をめぐって展開してきた所伝に幕引き。伊奘冉尊の鎮魂を果たします。
また、先ほどの、「神退去った(原文:神退去)」のところで解説したとおり、卑としての伊奘冉がこの世界から退去し、尊としての伊奘諾中心の世界へ移行する、てことも超重要。このあとの〔一書6〕以降、伊奘諾中心に神話が展開し、それが天照大神に引き継がれていくことになります。
こちらも是非チェックされてください。
まとめ
『日本書紀』巻第一(神代上)第五段 一書第2,3,4,5
だーっと解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
内容としては、伊奘冉という卑を中心とした物語。
蛭子、素戔嗚尊、さらに火神の軻遇突智と、、、「卑」に当たる子が次々に誕生。卑が極まっていく感じの展開は、火神に焦かれて伊奘冉が死ぬことでようやく終息を迎えます。
当の伊奘冉尊は、その死(神退去)により現世(うつし世)から姿を消す、そうして「卑」を世界から消し去って「尊」に道を拓く、ということで一貫したストーリー展開。日本書紀編纂チームは周到に演出してる。最終的には有馬邑の祭祀による鎮魂で一応決着。素晴らしいフィナーレ。
こういう構想を物語としてカタチにした古代日本人の叡智とか創意工夫がやっぱりスゴイ。多くの学びをいただけます。
次からはいよいよ、書6踏襲差違化パターンの一書群へ入っていきます。
続きはコチラ↓で!
神話を持って旅に出よう!
本エントリに関連するおススメスポットはコチラです!
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




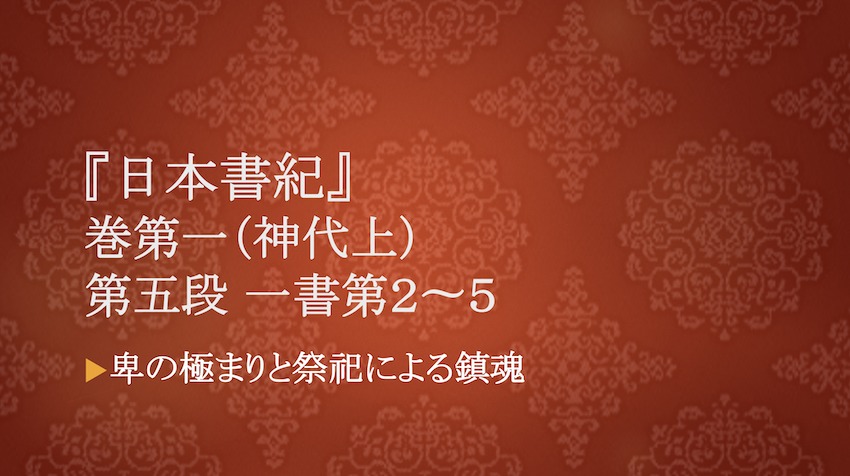































続きが読みたくてたまりません!
遅くなりまして申し訳ございません。日本神話.comをお読みいただきありがとうございます。
続き更新いたしました。ご確認くださいませ!4万文字超の超大作になっております。今後ともよろしくお願いします。
https://nihonshinwa.com/archives/11697