多彩で豊かな日本神話の世界へようこそ!
正史『日本書紀』をもとに、
最新の学術成果も取り入れながら、どこよりも分かりやすい解説をお届けします。
今回は、『日本書紀』巻第一(神代上)第五段の本伝。
第四段から続く新時代。
伊奘諾尊と伊奘冉尊という男女ペア神。その性の営みによる出産の物語。
国生みから神生みへ、「生む」という行為の第二章であります。
概要で全体像をつかみ、ポイント把握してから本文へ。最後に、解説をお届けしてまとめ。
現代の私たちにも多くの学びをもらえる内容。日本神話から学ぶ。日本の神髄がここにあります。それでは行ってみましょう!
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
『日本書紀』巻第一(神代上)第五段 本伝 天下之主者生み(神生み)
目次
『日本書紀』巻第一(神代上)第五段 本伝の概要
前回、『日本書紀』巻第一(神代上)第四段の一書10、
からの続き。
下図、赤枠部分。

ポイントは、神話全体の流れの中で読み解くこと。
詳細は順次解説、大きな流れ、枠組みは以下の通り。
| 大テーマ | 小テーマ | 内容 | 段 |
| 誕生の物語 | 道による化生 | 乾による純男神 | 第一段 |
| 乾と坤による男女対耦神 | 第二段 | ||
| 神世七代として一括化 | 第三段 | ||
| 男女の性の営みによる出産 | 国生み | 第四段 | |
| 神生み | 第五段 |
第一段から第五段までは、大きく「誕生」がテーマ。
この中で、
第五段は、第四段から続く新時代の第二章。
男女の性の営みによる出産〜神生み編〜
引き続き、メインプレイヤーは伊奘諾尊と伊奘冉尊。男女ペア神。
大八洲国という国の土台ができたので(第四段)、いよいよ統治者を生んでいく(第五段)。コレ「天下之主者」。
男女の性の営みによる神生みだからこそ、そこには責任が発生。生んだ子に対しては、その性質に応じた「処遇」を与える。コレ「親の責任」。新時代ならではの概念。
この中で、
皆様おなじみ、日神(天照大神)や素戔嗚尊が誕生。今後の神話展開における最重要神!
全体の流れは大きく三部構成
| 1. | 前段引き継ぎ 大自然生み |
| 2. | 協議 |
| 3. | 神生み |
今回もめっちゃ重要テーマが登場する段。ポイントをしっかり押さえながら読み進めましょう。

『日本書紀』巻第一(神代上)第五段 本伝のポイント
ポイント3つ。
①前段からの流れを踏襲し大自然を生む!これは国土充実化の他にも人が住める環境整備という意味が??
前段、第四段で、国の土台たる大八洲国の誕生を承け、ココ第五段では、海、川、山、木、草を生んでいきます。これ、意味としては、国の土台→大自然へ、継起的に国の有り様が具体化していく。てことなんですが、その他にも、人が住める環境整備という意味もあるってことでチェック。
実際、後段では、いつの間にやら人間が誕生してたことになってるので、そのためには特に動植物の生育環境が揃ってないと無理なんで、、
で、その上で再度、協議して「天下之主者」を生んでいく展開へ。
次!
②実はムズい!?天下之主者生み。どうにも、、極端に振れてしまって、結果、主者生まれない??
二神が生もうとするのは「天下之主者」。
「天下」とは、天の下、すなわち地上すべてのこと。「主者」とは主たる者。統治者のこと。要は「地上世界の統治者」のことで。コイツを生んでいこうぜ、って話なんだが、、
でもね、、、
難しいんすよコレが!
これまでの洲生みや大自然生みとは訳が違う。何が違うって「統治」の概念が入るってとこ。統治者として相応しい人柄、もとい、神柄、能力、血統、、、等々、あらゆる点で理想スペックが求められる訳で。。極度にプレッシャーのかかる局面。。。なにぶん初めてなもんで。。
で、結果、生まれたのは、
とんでもなくスゴイ子と、とんでもなくあかんたれな子、、って、神様極端!!
とんでもなくすごい子は、日神であり、月神。そのスゴさ、ヤバさは本文をご確認。二神びっくり。
で、あんまりにも素晴らしいので、地上に置いておくのは良くないと、天上送致!
てことで、天下之主者生み、再チャレンジ。
って生まれたのが、蛭児と素戔嗚尊。今度の子は、、、逆に酷すぎた。。。酷すぎてヤバい、、、二神びっくり。その2。
で、あんまりにも酷すぎるので、放棄&追放!!
結局、、、天下之主者生み、、、
コンプリートならず!残念!
と、この不思議展開、、これでいいのか???と貧乏ゆすりが止まりませんが、、
でもね、、これがあるから、つまり、天下の統治者不在のままで終わったからこそ、後の、国造り・譲り&天孫降臨へとつながって行く訳で、逆に言うと、大きな神話展開の仕掛けとして、あえて不在になってるってこと、しっかりチェック。
次!
③現れまくる尊卑先後の序。枠組みをもとに神の誕生を読み解くのが◯
地上世界の統治者を生もうと、実際生んだ神は、日神、月神、蛭兒、素戔嗚尊だったんだが、大事なのは、ココ、尊と卑という二項対立の枠組みが設定されてるってこと。
- 尊・・・日神、月神
- 卑・・・蛭児、素戔嗚尊
これ、後付け結果論かもしれんが、、、尊卑先後の序がそのまま現出した!といっても過言ではない!そんなテンションをチェックです。
まとめます
- 前段からの流れを踏襲し大自然を生む!これは国土充実化の他にも人が住める環境整備という意味が??
- 実はムズい!?天下之主者生み。どうにも、、極端に振れてしまって、結果、主者生まれない??
- 現れまくる尊卑先後の序。枠組みをもとに神の誕生を読み解くのが◯
以上、3点を踏まえて以下、本伝をチェック。
『日本書紀』巻第一(神代上)第五段 本伝
国立国会図書館デジタルコレクションより『日本書紀』慶長4(1599)刊版 次に、海を生んだ。次に、川を生んだ。次に、山を生んだ。次に、木の祖、句句廼馳を生んだ。次に、草の祖、草野姫を生んだ。またの名を野槌と言う。
ここまで生むと、伊奘諾尊・伊奘冉尊は共に議り「我々はすでに大八洲国をはじめ山川草木まで生んだ。どうして地上世界の統治者を生まないでいようか」と言った。
そこで、共に日神を生んだ。名を大日孁貴と言う。(大日孁貴、ここでは於保比屢咩能武智と言う。孁は、音は力丁の反である。ある書には、天照大神と言う。ある書には、天照大日孁尊と言う。)この子は、光り輝くこと明るく色とりどりで、世界の内を隅々まで照らした。故に、二神は喜び「我々の子供は多いけれども、未だこのように霊妙な子はいない。長くこの国に留め置くのはよくない。すぐに天に送り、天上の事を授けるべきだ」と言った。この時、天と地はたがいに遠く離れていなかった。それで天柱をもって天上に送り挙げた。
次に、月神を生んだ。(ある書には、月弓尊、月夜見尊、月読尊と言う。)その光りの色どりは日神に次ぐものであった。日神とならべて天上を治めさせるのがよいとして、また天に送った。
次に、蛭児を生んだ。しかし三歳になっても脚が立たなかった。それゆえ天磐櫲樟船に乗せ、風のまにまに放棄した。
次に、素戔鳴尊を生んだ。(ある書には、神素戔鳴尊、速素戔鳴尊と言う。)この神は勇ましく残忍であって、いつも哭き泣くことを行いとしていた。このため、国内の人民の多くを早死にさせ、また青々とした山を枯らしてしまった。それゆえ、父母の二神は素戔嗚尊に勅して「お前は、甚だ道に外れている。この世界に君臨してはならない。必ず、遠く根国へ行かなければならない」と言い、遂に追放した。
次生海 次生川 次生山 次生木祖句句廼馳 次生草祖草野姫 亦名野槌 既而伊奘諾尊伊奘冉尊 共議曰 吾已生大八洲國及山川草木 何不生天下之主者歟 於是 共生日神 號大日孁貴 【大日孁貴 此云於保比屢咩能武智 孁音力丁反 一書云 天照大神 一書云 天照大日孁尊】 此子光華明彩 照徹於六合之内 故二神喜曰 吾息雖多 未有若此靈異之兒 不宜久留此國 自當早送于天 而授以天上之事 是時 天地相去未遠 故以天柱 擧於天上也 次生月神 【一書云 月弓尊 月夜見尊 月讀尊】 其光彩亞日 可以配日而治 故亦送之于天 次生蛭兒 雖已三歳 脚猶不立 故載之於天磐櫲樟船 而順風放棄 次生素戔嗚尊 【一書云 神素戔嗚尊 速素戔嗚尊】 此神 有勇悍以安忍 且常以哭泣爲行 故令國内人民 多以夭折 復使青山變枯 故其父母二神 勅素戔嗚尊 汝甚無道 不可以君臨宇宙 固当遠適之於根國矣 遂逐之 (『日本書紀』巻第一(神代上)第五段 本伝より)
『日本書紀』巻第一(神代上)第五段 本伝解説
あらためて、第五段は、第四段から続く新時代の第二章。テーマは、男女の性の営みによる出産。
第四段の国生みから、第五段は神生みへ。
大八洲国という国の土台ができたので、まずは自然物を生み、いよいよ「統治者」を生んでいく。コレが「天下之主者」。
男女の性の営みによる神生み、だからこそ、そこには責任が発生。生んだ子に対してはそれぞれに「処遇」を与える。コレ「親の責任」。新時代ならではの概念としてチェック。
大きく三部構成。
| 1. | 大自然生み |
| 2. | 協議 |
| 3. | 神生み |
ということで、各部ごとに解説していきます。
1.大自然生み

2.協議
- ここまで生むと、伊奘諾尊・伊奘冉尊は共に議り「我々はすでに大八洲国をはじめ山川草木まで生んだ。どうして地上世界の統治者を生まないでいようか」と言った。
- 既而伊奘諾尊伊奘冉尊 共議曰 吾已生大八洲國及山川草木 何不生天下之主者歟
→第四段から続く新時代の風。
テーマは、性を内在した男女神がその属性の働きや導きを「かたち」にする段。その現場は、男女の協議からスタートしてました。第四段「共計」。
第五段でも、大自然生みが一段落したところで再度協議。話し合って決めてく優しいジャパニーズスタイル。
ポイント1つ。
①言表と行為、ここでは言表は「共議」という形式表現
言表と行為、という神様行動特性(通称、神様コンピテンシー)。神様は、まず言表、つまり、言い表す。そして行為に及ぶ。背景にあるのは言霊信仰。言葉にすることで実現する、予祝的な意味あいもあり。
ココでの言表は、「共議(協議)」という形式で伝えてます。
第四段でもお伝えしましたが、協議からスタートする、って結構深い意味があって。。外国の神々のように超越的な絶対神がその意志のままに天地を創造するのとは全く違うスタイル。
それは、性を異にするからこそ必然的に伴う個性の異なりや意見の対立を前提として、だからこそ「協議」によって乗り越えるってことで。異質が互いを認め合い、すりあわせ、共に一つの方向を目指し、実現を図っていく。そういう意味を持つ重要ワードとしてチェック。
次!
「どうして地上世界の統治者を生まないでいようか(原文:何不生天下之主者歟)」とあります。「何〜歟」は反語表現。どうして生まないでいようか?いや生むのだ!
第四段で大八洲国が誕生、つまり日本という国の土台ができたと。さー次は統治者だと。そういう流れの中での「天下之主者」。
「天下」とは、天の下、すなわち地上のこと。「主者」とは主たる者。統治者のこと。要は「地上世界の統治者」のこと。
ポイント2つ。
①主者生みから、いよいよ、生む子に「性質」が現れ始める!これ、日本神話的革命。
コレまでの出産は、洲とか大自然とかで、そこに性質みたいなのって無かった訳です。無機質。洲は洲だし自然は自然。でも、この主者生みから、いよいよ、生む子に光り輝くとか脚が立たないとか暴虐武人といった性質が現出する訳で。
これ、日本神話的革命大事件であって、、大きな構造としては、この性質誕生というのは第五段〔一書6〕で誕生する「人間モデル神」への布石。いわゆる「わたり」としての意味があります。
第五段〔本伝〕で、生んだ子が初めて性質というものを持ち始め、さらに〔一書6〕で情(感情)を持ち始める、、以後、神々がさながら人間のように喜怒哀楽し、それが原動力となって日本神話を展開させるようになっていく。
その意味で、ここ第五段〔本伝〕はその起点となる場所であるってことで、しっかりチェック。
次!
②「天下之主者」は日本神話を貫く最重要テーマ
「天下之主者」、これ、この後の展開、いや、もっというと、日本神話全体の展開における起点となる言葉でもあって。いろんなすったもんだがありつつ、、最終的に、神武天皇が即位誕生することでこの「天下之主者」誰だ問題は解決を見る訳です。
この、日本神話全体を貫く重要テーマが「天下之主者」であること、その意味で、今後の神話展開の起点になる言葉でもあること、しっかりチェック。その上で、当初の狙いや意図がどうなっていくのか?その後の神生みをチェックです。

3.神生み
とは言いつつ、、「天下之主者」生み、コレ、かなり難しくて、、、
伊奘諾尊・伊奘冉尊といえど、最初からちょうどいいスペックに当てていくのは至難の業。。「主者」って簡単には生めないし、生まれない。なんなら、子供を生むってそれくらい大変なことなんですよ皆さん!
「大日本豊秋津洲」をはじめとする「大八洲国」を構成する「洲」や「山川草木」は、次々に、難なく生んでましたが、ここへ来て大きな転換に差し掛かっている。「なかなか生まれない」とか「生み損ない」がそんな状況を暗示。残念ながら、当事者たちはなかなか気付かない、、、
そんなところを読み取りつつ、、
- そこで、共に日神を生んだ。名を大日孁貴と言う。(大日孁貴、ここでは於保比屢咩能武智と言う。孁は、音は力丁の反である。ある書には、天照大神と言う。ある書には、天照大日孁尊と言う。)この子は、光り輝くこと明るく色とりどりで、世界の内を隅々まで照らした。
- 於是 共生日神 號大日孁貴 【大日孁貴 此云於保比屢咩能武智 孁音力丁反 一書云 天照大神 一書云 天照大日孁尊】 此子光華明彩 照徹於六合之内
→「天下之主者」生み、一発目は日神!!
日神について、ポイント2つ。
- 本文では、あくまで日神。名は「大日孁貴」。
- 異伝的な位置づけの「注」で「天照大神」。
日本神話ファンとしては、天照の印象が強いかと思いますが、その最初の誕生、第五段本伝の段階では、あくまで「日神」。で、神名が「大日孁貴」。
コレ、実は、めっちゃマニアックな名前の作りになってて、、。読み解きのカギは「孁」。
従来、これは「巫女の意で用いた文字」(岩波日本古典文学大系の頭中)と解釈するのが通例で。かつ、例えば、小学館新編日本古典文学全集の頭注では「神代紀の撰者は「孁」をメ(女)の訓にあて、しかも女神とした」といった説明になってるのですが、、、ある意味当たり前のことを言ってるだけ。説明になってない。。。
細かい考証は省きますが、そもそも「孁」は「霝」と「女」を組み合わせた会意文字です。
会意文字とは、二つ以上の漢字を意味の上で組み合わせ、新しい意味を持たせた漢字のこと。例えば、「人」と「木」を組み合わせて「休」(人が木に寄りかかる様子)、「木」を二つ組み合わせて「林」など。漢字の造字法のことで。
「孁」は、「霝」と「女」を組み合わせた会意文字なので、合成する前の「霝」が本来持っている意味はどんなか?が重要になります。それがコチラ
昔に一を得る者は、天は一を得て以て清く、地は一を得て以て寧く、神は一を得て以て霝になる
昔之得一者 天得一以清 地得一以寧 神得一以霝
馬王堆漢墓出土「帛書甲本『老子道徳経』(法本第三十九) 漢語大詞典「霝」
これ、『老子』の言葉で、万物の根源である「一(道)」を得ることで、自然界や精神の原理がその本来のあり方に戻ることを言ってるんですが、
- 天得一以清 → 天が「一」を得ることで、万物を清浄に保つことができる。
- 地得一以寧 →地が「一」を得ることで、万物が安定し、落ち着くことができる。
- 神得一以霝 →神が「一」を得ることで、神秘的な霊妙さを発揮する。
といった感じで、、「一」とは、万物の根源である「道」や「無」を指し、その「一」を得ることで、本来の秩序や力が回復するという思想が背景にある。
特に、最後の「神得一以霝」。つまり、神は「一」を得て「霊妙」という無上最高の霊格になる、としており、そもそも論として、「霝」にはこうした非常に尊貴な「霊格」という意味があるんです。
その上で、特にそれが女性であることを明示したのが「孁」。「霝」と「女」を組み合わせた会意文字。
なので、「大日孁貴」とは、
大いなる+お日様の+最高の霊格で+非常に尊貴な存在であるといった意味が込められてる。しかも、特に激しく推すわけではないですが、サラッと女性であることを匂わせてる訳です。
この女性の匂わせ方は、〔一書6〕の素戔嗚尊の反抗、第七段の「姉」といった言葉へ繋がっていったりします。
他にも、ココで押さえておきたいのは、
- 日神=天照大神なんですが、第五段本伝では、あくまで日神である。
- 「天照大神」として、高天原の統治者として位置づけられるのは、第五段一書第六から。
- 天照=女性神といった、余計な先入観や予備知識は、ココでは一旦置いとくこと!
ということでチェック。
その上で、
異伝的な位置づけの「注」で「天照大神」を伝えていますが、この神名については、以下。
- 本伝で日神として伝える。まずココで基本概念を打ち立てる。
- その上で、一書第6以降で、天照大神として伝え、高天原の統治者とする。
- さらに、次の第六段以降、一書6の「天照大神」が本伝へ乗っ取りをかけ、以後、天照大神として神話が展開。日神はフェードアウト。
本伝の、原型としての日神が、一書で天照大神へと引き継がれ、さらに第六段で本伝へ。以後、天照大神が神話展開の本流をつくっていく。非常に大きな仕掛けが動いていること、チェックです。詳しくは今後のエントリで順次解説していきます。
で、
「この子は、光り輝くこと明るく色とりどりで、世界の内を隅々まで照らした(原文:此子光華明彩 照徹於六合之内)」とあります。
ついに登場、子の性質!!!ここに激しく注目。「光華明彩」。光り輝くこと明るく色とりどりに、すっげーまぶしい。。って、そういう性質を持って生まれた訳です!!
それで「照徹於六合之内」。世界の内を照らし倒したと。「六合」とは、天地(上下)+四方(東西南北)、つまり世界全体のこと。「照徹」とありますので、訳出は「隅々まで照らした」。
第五段本伝の段階では、性別不祥。男か女かも分かりません。余計な先入観や予備知識は一旦置いといて、性別不詳の光輝く性質を持つ日の神が誕生した、ということでチェック。
次!
- 故に、二神は喜び「我々の子供は多いけれども、未だこのように霊妙な子はいない。長くこの国に留め置くのはよくない。すぐに天に送り、天上の事を授けるべきだ」と言った。この時、天と地はたがいに遠く離れていなかった。それで天柱をもって天上に送り挙げた。
- 故二神喜曰 吾息雖多 未有若此靈異之兒 不宜久留此國 自當早送于天 而授以天上之事 是時 天地相去未遠 故以天柱 擧於天上也
→霊妙スゴすぎなんで地上無理!だから天上送致!??
ポイント2つ。
①新時代ならではの親の責任として、子の性質に応じた処遇を行なってる
「長くこの国に留め置くのはよくない。すぐに天に送り、天上の事を授けるべきだ(原文:不宜久留此國 自當早送于天 而授以天上之事)」とあります。
冒頭に解説した通り、男女の性の営みによる神生み中。だからこそ、そこには親としての責任が発生。生んだ子に対してそれぞれ「処遇」を与える。コレ、新時代ならでは。
ココでは、日神の「光華明彩照徹於六合之内」という「性質」、生まれながらにして持つ「霊異」を根拠として、「長くこの国に留め置くのはよくない」と。なので、「すぐに天に送り、天上の事を授けるべきだ(原文:授以天上之事)」と天に送る「処遇」を行ってるのです。
なお、「天上の事を授ける」とは「天上世界の統治委任」のこと。第五段〔一書6〕ではより具体的に統治領域を指定する形に展開していきます。
いずれも、新時代ならでは、親の責任として子の性質に応じた処遇を行なってるってことでチェック。
次!
②天柱=第四段一書1で登場した天柱。天と地をつなぐ役割
「天柱」は第四段一書1で既に登場。
二柱の神はその島に降り居て、八尋之殿を作った。そして天柱を立てた。
二神降居彼嶋、化作八尋之殿。又化竪天柱。(『日本書紀』巻一(神代上)第四段〔一書1〕より)
と。この天柱、エレベーターみたいな感じで、神の転送、いや、天送用として位置づけ。
「天柱」は、神仙の山として名高い崑崙山思想が背景にあります。例を挙げれば、
- 「崑崙山、天中柱也」(『芸文類聚』巻七「崑崙山」所引「龍魚河図」)
- 「崑崙山為天柱」(『初学記』巻五「総戴地第一」所引「河図括地象」)
など。
特に、②の背景設定は、天柱である崑崙山から気が上昇して天に通い、そこが地の中央に当たる、とするもの。まさに、日神・月神を天に送るための柱そのものですよね。
次!
- 次に、月神を生んだ。(ある書には、月弓尊、月夜見尊、月読尊と言う。)その光りの色どりは日神に次ぐものであった。日とならべて天上を治めさせるのがよいとして、また天に送った。
- 次生月神 【一書云 月弓尊 月夜見尊 月讀尊】 其光彩亞日 可以配日而治 故亦送之于天
→ココでも日神同様、月神の性質に応じた処遇実施。
「日とならべて天上を治めさせるのがよい」とあり、天空に太陽と月があることの起源譚的内容を伝えてます。なお、昼と夜を分けることになるのは第五段〔一書11〕です。
↑「この時、天照大神は激怒し、「汝は悪い神だ。もう顔など見たくもない。」と言った。こうして、天照大神は月夜見尊と、日と夜と時を隔てて住んだ。」第五段〔一書11〕。
ということで、最終的に兄弟喧嘩?いや、姉ちゃんの一方的ブチギレで別れることになります。。。いつの時代も姉強し。。??
それはさておき、
日本神話的月神について。月神は伊奘諾ファミリーにおける長男なんだけど「間っ子」。兎にも角にも影が薄い、、月の神、ということで、異伝の神名には「(ある書には、月弓尊、月夜見尊、月読尊と言う。)」とあり、意味内容としては以下。
- 月弓・・・弦を張って曲がった弓のような形をした月にちなむ名称。上弦・下弦が該当。弓張月、弦月ともいう。
- 月夜見・・・月は夜に見える。月にわざわざ「夜見」という漢字を設定したのは、後の〔一書11〕で昼と夜の断絶・隔離の起源譚を予定した名称。
- 月読・・・古代は月の満ち欠けをもとにした太陰暦がベース。月齢(月の満ち欠けを表す日数。新月が零、満月はほぼ十五日)や暦と関連するので読むという漢字。
といった具合で、これはこれで月の多様なあり方に即した表現が設定されてます。
それにしても、、日本神話の中で、月神(月夜見尊)はホント存在感が薄い。。。活動するといっても、「月夜見尊」だけ。。強烈モーレツな姉と弟の間に挟まれて、、、??
それはさておき、
ココで確認しておきたいのが、「天下之主者」生みは、この時点で成功してないってこと。性質が素晴らしすぎたので天送したので、引き続き不在状態、、そこで二神、コレじゃダメだと切り替えたんだと推測。そんなに力まずに生んだところ、、、
- 次に、蛭児を生んだ。しかし三歳になっても脚が立たなかった。それゆえ天磐櫲樟船に乗せ、風のまにまに放棄した。
- 次生蛭兒 雖已三歳 脚猶不立 故載之於天磐櫲樟船 而順風放棄
→コレまでの性質と一変。脚が立たない子が誕生、、、しかも船に乗せて放棄だと?
なんでそんな極端???
それはさておき、
蛭子は第四段〔一書1〕で誕生してました。
ついに夫婦となり、まず、蛭児を生んだ。そこで葦船に載せて流した。
遂為夫婦、先生蛭児。便載葦船而流之。(『日本書紀』巻一(神代上)第四段〔一書1〕より)
第四段〔一書1〕では蛭子の具体的な性質は伝えてませんでしたが、「不祥の子」として位置付けられてましたよね。背景設定として、結婚儀礼は「陽主導」であるべきで、先に唱えるべき。なんだが、陰神が先に声を上げた。これは道理を違えることであり、不祥=不吉だと。
それを承けての、ココ第五段〔本伝〕。
「三歳になっても脚が立たなかった(原文:已三歳脚猶不立)」と、具体的な性質を伝え、その上で「天磐櫲樟船に乗せ、風のまにまに放棄した(原文:故載之於天磐櫲樟船 而順風放棄)」という処遇実施。
「天磐櫲樟船」について。
「天」は、「順風」と対応し、流棄用の船として「流れ」を生み出すものとして冠されてます。天=風→風の流れ。「磐」は立派な。「櫲樟」は、クスノキの別称。常緑樹。
「櫲樟」の別称であるクスノキは、独特な香があることから「臭き木(くすしき)」が語源。防虫剤である樟脳の原料。古代より、その香りの強さから邪気を払う呪力があるとされてきました。
ちなみに、後段で、素戔嗚尊が「杉と櫲樟とを「浮宝=船」にすべし」と伝え、船の建造用材としてクスノキがあったことも分かります、また、考古学的調査からは、実際にクスが古代船の船材として多用された発掘も相次いでたりします。
なので、邪気を払う+船の建造用ということで、「櫲樟」が使われてる次第。
いずれにしても、「流す」とか「放棄」といった対応の意味が重要で。日本神話的に、「不祥」の結果というのは「穢悪」な存在であり、水による穢れの除去や祓を必要とする。という考え方がある、てこと、改めてチェック。
蛭児の放棄は、共同体の存立を損ないかねない存在を、異物として排除する習俗、あるいは慣行の起源を物語っている(と、見るほかなく、、、)。
その意味で、本件は、始原における神世界の生存原理に根差してる、とも言えて。この時点では、神ワールドといえど「神聖の保持」に心砕く、、、といった感じで。なかなかな雰囲気であります。
次!
- 次に、素戔鳴尊を生んだ。(ある書には、神素戔鳴尊、速素戔鳴尊と言う。)この神は勇ましく強く残忍であって、いつも哭き泣くことを行いとしていた。このため、国内の人民の多くを早死にさせ、また青々とした山を枯らしてしまった。それゆえ、父母の二神は素戔嗚尊に勅して「お前は、甚だ道に外れている。この世界に君臨してはならない。必ず、遠く根国へ行かなければならない」と言い、遂に追放した。
- 次生素戔嗚尊 【一書云 神素戔嗚尊 速素戔嗚尊】 此神 有勇悍以安忍 且常以哭泣爲行 故令國内人民 多以夭折 復使青山變枯 故其父母二神 勅素戔嗚尊 汝甚無道 不可以君臨宇宙 固当遠適之於根國矣 遂逐之
→素戔嗚尊もヒドいが父母も追放て、、なんでそんな極端???
「この神は勇ましく強く残忍であって、いつも哭き泣くことを行いとしていた(原文:此神 有勇悍以安忍 且常以哭泣爲行)」とあります。
「勇悍」は、勇ましく強いこと。「安忍」は、普通ならするに忍びない残忍なことを平気ですること。特に、「安忍」は唐律の名例律にも登場する非常に重たい重罪ワード。
「哭泣」は、哭き泣くこと。特に、「哭く」とはフツーの泣くとは違い、慟哭といった感じで、叫ぶニュアンス。残忍な神が哭き叫ぶ訳ですから、その凄まじさは想像を絶するものだったに違いない。空も山も海も大地もことごとく鳴動、ビリビリ世界が震える壮絶さ。
ポイント1つ。
①素戔嗚尊の性質=本来もってる神性としての凶暴性
「勇悍」や「哭泣」といった凶暴性は、実は、素戔嗚尊が本来、神性として持つ生まれながらの性質として描かれてます。外的要因によって怒ってる訳でもなく、不満がある訳でもなく、生まれつき凶暴な性質をもってた。無垢。ナチュラルボーン。第五段本伝の素戔嗚尊はそういう神として描かれてます。ここしっかりチェック。
ちなみに、、
異伝である〔一書6〕以降の素戔嗚尊は、不公平な処遇に対する怒り、不服を根拠とした凶暴性発揮なので、別の描かれ方をしてます。
次!
「国内の人民の多くを早死にさせ、また青々とした山を枯らしてしまった(原文:故令國内人民 多以夭折 復使青山變枯)」とあります。
「夭折」について。意味は、年が若くて死ぬこと。若死に・早死に。
「夭」は、「わかい」「みずみずしい」といった意味と、「若死に」という2つの意味がある漢字です。
ポイント1つ。
①際立つ素戔嗚尊の悪行。これは卑=陰の働きである「殺」によるもの。
「夭折」や「變枯」などの、人民を早死にさせ青山を枯らしたという意味は、
- 早死に=本来もってる寿命を全うさせない、命を奪う
- 枯らす=植物が持ってる生命力を奪う
てことで、いずれも「殺」という言葉に集約される恐ろしい行為であります。
イメージとして、自然の持つ猛威、それは人間側の事情とか生活とか関係なく根こそぎ破壊していくような、、台風、地震、津波、、、だからこそ、父母二神が「無道」という言葉で表現。訳は「甚だ道に外れている。」としましたが、もっと強烈な意味としてチェック。外れてるどころの騒ぎではなく、そもそも道が無いのであります。
大事なのは、この「民を若死にさせる」のも「青山を枯らす」のも、いずれも、卑=陰の働きである「殺」によるもの。だってこと。詳細はコチラ↓で。
日本神話のベースにあるのは易の思想。乾坤や陰陽など二項対立の根源から世界はできていて、特に、陽や陰が持つ自律的かつ自動的な働きとして、
- 陽の働き=徳を謀る=成長させていく、
- 陰の働き=刑を謀る=殺していく、枯らしていく
というものがある訳です。四季があるのもこの働きによるもの。この陽と陰は、そのまま尊と卑であり、つまり、「卑」は、そもそも陰の働きである「殺」というのを内在してる、ってことで。素戔嗚尊が「民を若死にさせる」のも「青山を枯らす」のも、こうした「殺」の働きによると伝えてるんです。これも合わせてチェック。
次!
「父母の二神は素戔嗚尊に勅して「お前は、甚だ道に外れている。この世界に君臨してはならない。必ず、遠く根国へ行かなければならない」と言い、遂に追放した。(原文:故其父母二神 勅素戔嗚尊 汝甚無道 不可以君臨宇宙 固当遠適之於根國矣 遂逐之)」とあります。
「君臨」について。
「君臨」は、「君」=君主と「臨」=のぞむ、臨むという2つの漢字が組み合わさったもの。「君として臨む、統治する」という意味。『春秋』の解説書(注釈書)である『春秋左氏伝』に登場。
「宇宙」について。
「宇」は、部首の「宀(うかんむり)」と、音符の「于(ウ)」が組み合わさった形声文字。もともとは「屋根」や「家」を意味。そこから「軒」「家屋」「屋根のように覆うもの」といった意味に。
「宙」は、「宀(うかんむり)」と「由」を組み合わせた形声文字。元の意味は「棟木」で、建物を支える屋根の中心部分を指しましたが、そこから転じて「空間」「大空」「時間」などの意味を持つようになりました。
なので、「宇宙」は、覆うように広がりのある空間といった感じで、現代でいう宇宙ではなく、訳出では(国生みが終わった直後の)世界といった意味になります。
ポイント2つ。
①勅=国家意志の発動になぞらえた超重要命令
「勅(ちょく)」は、天皇の命令、またはその命令が記された文書のこと。絶対命令、NO無し。全員起立!
「勅して〜(勅)」とあり、突然ですがコレ、「本朝」の権威を前提として、国家意志の発動になぞらえる形で、超重要命令として使われてます。
いつから勅発動する権威をゲットしたの?という疑問はさておき、なんせ第五段〔本伝〕は「天下之主者」生みで、統治をテーマにしてるわけで、当然、統治領域設定には根拠となる権威が必要になってくる訳です。なので、ここで「勅」という言葉が使われてるんです。神はいつだって唐突です。
次!
②追放する根国の位置づけ=遙か彼方の僻遠の地
追放処分となった素戔嗚尊ですが、その追放先は根国。コレ、遙か彼方にある「異界」として設定されてます。
「根国」は、ここ本伝だけでなく、異伝も含めて全部で4つ伝えてます。まとめてみると、
| 本伝 | 遠適之於根國 | 水平方向+遠い |
| 一書1 | 令下治根國 | 下方向 |
| 一書2 | 馭極遠之根国 | 水平方向+極遠・世界の果て |
| 一書6 | 從母於根國 | 下方向+母:伊奘冉に従う |
といった感じに差異化されてます。
さらに、位置的に、日本神話的地上世界マップはこんな感じになってます。

根国については、コチラ↓で詳しく。
実は、根国には、「四裔」=国の四方の果て、鬼の住む場所。というモデル、背景設定があることをご紹介してます。是非チェックされてください。
ということで、
最後に、全体のまとめとして3つ。
①尊卑先後の序の現出。神の誕生は、尊と卑、先と後という枠組みで整理
第五段の「神生み」は、新時代の第二章。男女の性の営みなんで、そこには2つ新規発生。
- 営みの結果である子の「性質」
- 営みの結果に対する親の「責任」
第一章の「国生み」には「性質」無し。同じ「生む」という行為なんだが、生んだのは「洲」だったんで。
でも、第二章の「神生み」には「性質」が入る。いよいよ「子供」なので、性格とか性質とか、子が本来的に持ってる「多様さ」が生まれてきますよね。
この本来的に持ってる性質の多様さが、神話に大きな展開を与えていくことになります。いつの時代も未来を創っていくのは子供らニュージェネレーション。
また、営みの結果には「責任」が発生。第二章では、それを「処遇」として表現。生んだ子に対しては、その子の持つ性質に応じた処遇を与えます。
| 段 | 生んだもの | 性質 | 責任 |
| 第四段 | 洲(大八洲国) | 無し | 名付け |
| 第五段 | 神(山川草木) 神(主者ならざる四神) |
有り | 名付け、処遇 |
なので、
子の性質と、その性質に応じた処遇、という2軸で整理すると分かりやすい。
また、生まれる子をめぐっては、「尊卑先後の序」が具体的な現れとして設定されてます。
| 尊卑 | 誕生する神 | 性質 | 順番 | 処遇 |
| 尊 | 日神、月神 | 光華明彩照徹於六合之内、其光彩亜日 | 先 | 天送 |
| 卑 | 蛭児、素戔嗚尊 | 雖已三歳脚猶不立、有勇悍以安忍 | 後 | 放棄、追放 |
「尊」を体現し、「先」に誕生する日神と月神。なので、その「性質」も輝いている。
この「性質」や「霊異」を根拠として、ともに天上のことを授ける&天に送るという「処遇」にな流。
一方、
「卑」を体現し、「後」に誕生する蛭児と素戔嗚尊。なので、その「性質」もヒドい、、日神・月神とは著しく対照的です。
いずれも過度に卑なる「性質」ゆえに、蛭児は葦船にのせて放棄。素戔嗚尊は根国へ追放。という処遇に。散々だ。。。
このように、第五段の神生みは、「尊」と「卑」との対応が「先」と「後」との対応に重なり、この「尊・先」「卑・後」の序をもとに本伝全体が成りたつ構成になってる訳ですね。
ちなみに、、、
神武東征神話では、この「日神」としての性格、性質をもとに、神武が東征発議で「我天神」として位置づけてます。つながりチェック。
次!
②過度な性質、からの処遇により、天下は統治者不在のまま。コレ、神話展開上の大きな仕掛け
過度にスゴすぎても、過度にダメすぎても、結局ダメ。
多分、神様的には、日神・月神が良くて、蛭児・素戔嗚尊が悪い、といった価値判断はないと思うんですよね。どっちにしても、過度であると天下(地上世界)には置いておけないんです。
こうして、伊奘諾尊・伊奘冉尊の当初の企図(天下之主者を生む)が、結局は破綻するに至る。。。
もうちょい程よい生み方なかったの???
極端なんす。。。神。
で、天下は統治者不在のまま。。。
なんですが、
「統治者不在」だからこそ、神話は展開する。
つまり、地上世界は悪いものが跋扈するダークワールドになっていくんですよね。これは後に、八岐大蛇や悪神たちの登場として語られます。
ポイント2点。
- 統治者がいないとどうなるか?という事を伝えてる
- 神話展開上の仕掛けである
1つめ。
統治者がいないとどうなるか?という事を伝えてる件。
統治者不在=管理者不在
例えば、家を管理する人がいないとどうなるか?
きっとその家は、埃だらけ虫だらけ、ボロボロになって朽ちていく、、、のは当たり前。
地上世界、もっと言うと、国というものも同じなんです。統治者がいないと、その世界は汚れていく、悪い奴らがのさばるようになる。だから統治者というのは必要なんだという話。
2つめ。
神話展開上の仕掛け
統治者不在だからこそ、その後の、国造り・譲り&天孫降臨へとつながっていく。
あえて地上世界のことは空けておいたんすね。きっと。天上世界と地上世界をつなげること、天上世界の統治者が地上世界の統治者を降臨させる・送り込む形で関連付ける、そういうゴールに向けて、ココでいきなり天下之主者を誕生させるより、まず天上世界を固めてから地上世界へ繋げていった方が縦のラインがしっかりできるので効果的。会社とかの組織づくりもそうですが、まずは上からつくっていく、固めていくのがセオリー。
そう考えると、コレはこれで、大きな神話展開上の仕掛けとして位置づけられる訳で。このあたりもポイントとしてチェックです。
次!
③伊奘諾尊→日神、伊奘冉尊→素戔嗚尊。陽と陰の働きをそれぞれが引き継いでいく
大きく見ると、次の世代へのバトンタッチ。
陽や陰が本来的にもってる働きを、伊奘諾尊と伊奘冉尊という男女神によって表現し、今、それを日神と素戔嗚尊が引き継ごうとしている。。。
参考:日本神話的時間発生起源|伊奘諾尊・伊奘冉尊の柱巡りが時間の推移や季節を生みだした件
つまり、
根源の働きとしてプログラムされてる2項対立の構図。
- 陽の働き=徳を謀る=成長させていく
- 陰の働き=刑を謀る=殺していく、枯らしていく
この概念をもとに、
| 陰陽 | 働き | 具体例 | 国生み | 神生み |
| 陽 | 徳を謀る | 成長させていく | 伊奘諾尊(左旋回) | 日神(照徹於六合之内) |
| 陰 | 刑を謀る | 殺していく、枯らしていく | 伊奘冉尊(右旋回) | 素戔嗚尊(有勇悍以安忍) |
といった形で、整理しながら対応させてるんです。まー、よくできてる。
特に、ココ、素戔嗚尊の凶暴性とは、陰の道がもつ「刑・殺」そのものであり、伊奘冉に代わって素戔嗚尊が引き継いでいるという形になってる。コレをチェック。
最後に、
第五段本伝で誕生する神様たちをまとめておきます。
| 尊 | 日神(大日孁貴、天照大神) 月神(月弓、月夜見、月読尊) |
| 卑 | 蛭児 素戔嗚尊(神素戔鳴尊、速素戔鳴尊) |
まとめ
『日本書紀』巻第一(神代上)第五段 本伝
だーっと解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
第五段は、第四段から続く新時代の第二章。テーマは、男女の性の営みによる出産。第四段の国生みから、第五段は神生みへ展開。
大八洲国という国の土台ができた(第四段)ので、いよいよ統治者を生んでいく(第五段)。
男女の性の営みによる神生み、なので、そこには2つの事項が発生。
- 営みの結果である子の性質
- 営みの結果に対する親の責任
「神生み」には「性質」という概念が入ります。二神の「子供」なので、性格とか性質とか、子が本来的に持ってる「多様さ」が生まれ、この多様さが、今後の神話展開に大きな影響を与えていく。
また、営みの結果には「責任」が発生。第五段では、それを「処遇」として表現。生んだ子に対しては、その子の持つ性質に応じた処遇を与えます。コレ、「親の責任」。新時代ならではの概念です。
また、第五段の神生みは、「尊」と「卑」との対応が「先」と「後」との対応に重なり、この「尊・先」「卑・後」の序をもとに本伝全体が成りたつ構成。いずれも、過度な性質であるがゆえに、天下、つまり地上世界にはいられない結末に。
世界は主者不在のまま。統治者不在であるがゆえに、悪神が跋扈するダークワールドへ。これは第八段の八岐大蛇へとつながって行きます。
次は、いよいよ第五段、天下の主者誕生です!
続きはコチラ↓で!
神話を持って旅に出よう!
本エントリに関連するおススメスポットはコチラです!
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




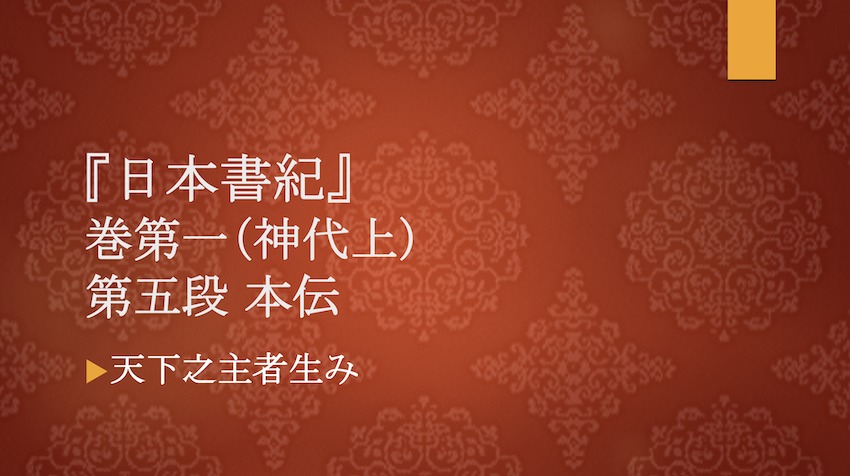






























→「次」を先頭に立てることで、前段継承を明示。
この形式、既に登場してましたよね。第二段本伝。「次に~」というのは、前段踏襲、前段からの流れを承けてまっせ、という意味でした。
第四段の大八洲国を生んだ流れを承けて、海、川、山、木、草を生んでいったと。さらに、生むごとに「次」という言葉で繋いでいく継起的展開。次々に生んでいった感をチェック。
コレら大八洲国の国土にうまれた大自然シリーズ、ポイント以下4つ。
①海は、国土と対になる意味での「海」
海について、前段、第四段〔本伝〕で二神が天浮橋から天之瓊矛を指し下ろしたときに「滄溟を獲た」とありました。滄溟=青海原。
海ってあったんとちゃうんかい???
となりますが、ココでは、国土と対比される海、としてチェック。
大八洲国が誕生してる訳で、これは後の日本であり、国土。日本は海に囲まれてるので、そのときのイメージとして、まず国土、そして取り囲む海、といった感じで。それは「滄溟」という広漠たる青海原とは違う位置づけなんす。「滄溟」は領海の概念がない、国という概念がない、単にどこまでも広がってる海。だからこそ、大八洲国の誕生の意味は大きくて。漠然と広い海→国土と対比される海へ。国の概念が生まれることで、さまざまな輪郭が明確になっていくのだ!
そして!
②神のヒエラルキー??天神→地祇(国神)→ち(精霊)ってのがあるらしい
「次に、木の祖、句句廼馳を生んだ。次に、草の祖、草野姫を生んだ。またの名を野槌と言う(原文:次生木祖句句廼馳 次生草祖草野姫 亦名野槌)」とあります。
日本神話的に、海や山は神格化され「地祇」になります。天神に対する地祇。国土を守護する代表的な国神として位置づけられていて。表記上の通例として、「わたつみ」には「海神」を、「やまつみ」には「山祇」という漢字があてられます。
一方、木や草は、「精霊」といったニュアンス。「神」や「祇」という言葉は使用されません。古語「ち」は、「おろち(蛇)」、「いかづち(雷)」など、霊威や霊力をもつ神を表しますが、ココでは、木の祖=くくのち、草の祖=のつち、という、むしろ精霊に近い表現になってます。
この、天神→地祇(国神)→ち(精霊)といった神世界の階層、ヒエラルキー。一応チェック。
ちなみに、、
草が姫になってるのはオモロー!ですよね。「象徴表現」なのですが、山裾の広い傾斜地、高原地帯に生息する茅(かや)が風にそよぐ姿からか、女神としての表現になってるのもポイントです。
そして!
③海、川、山、木、草は、大八洲国の国土に生まれたありとあらゆるもの、と言った意味
まず、海、川、山、木、草の順番は、イメージとして、海から川伝いに山へ、山の木があって草があって、、、といった流れ。で、この後に、二神が「我々はすでに大八洲国をはじめ山川草木まで生んだ。」と言い、直後に主者生みに言及してることから、これら海、川、山、木、草は、大八洲国の国土に生まれたありとあらゆるもの(大自然系)といったニュアンスとして列挙されてることチェック。
ちなみに、『古事記』は具体的な神名を詳細に記載することで伝えてます。
④実は、人も生まれてた??だからこその大自然生み
大自然生みのもう一つの意味。むしろこっちの方が重要。それが、人類誕生!コソッとね。
このあと、素戔嗚尊が生まれるのですが、その暴虐武人っぷりを伝えるところで「国内の人民をたくさん早死にさせ(原文:故令國内人民 多以夭折)」だと!?
人、いつの間に生まれてたの!!???
という謎展開。。。でも、振り返ってみれば、確かにココで、大自然生まれてたよねと。てことは、植物を食する動物や人類の一つや二つ生まれててもおかしくない、、??
日本神話的必殺後出しジャンケンではありつつも、海、川、山、木、草に代表される大自然生みましたシリーズのもう一つの意味として、人類コソッと誕生す、ってのがあること、こっそりチェック。