日本神話に登場する、重要ワード、重要エピソードをディープに掘り下げる「日本神話解説シリーズ」。
今回は、『古事記』をもとに
「造化三神」
天と地ができたその原初の時に、高天原に成りました神が「天御中主神」「高御産巣日神」「神産巣日神」。この三柱の神を、古事記の序文では、「造化三神」と称しています。
で、「造化三神」については、これ以上は何も伝えていません。なので、正直よく分からないのが実際の所であります。
なので、その理解には『古事記』本文に即して
- 誕生した「高天の原」についての解釈
- 「三神」それぞれの解釈
- 「独神」の解釈
- 「身を隠す」についての解釈
- その後の活動から解釈
の5つを組み合わせて総合的に解釈していく必要があります。
今回はそんな謎に包まれた「造化三神」について、文献学的アプローチをもとに最新の学術成果も採り入れながら徹底解説いたします。
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
造化三神とは?|天と地ができた原初の時に、初めて高天原に成りました三柱の神々。あとに誕生する神に世界を譲り自らは立ち退くという奥ゆかしいスタンス。
目次
「造化三神」とは?
まずは、「造化三神」が登場する箇所と内容をチェック。
「造化三神」、コチラ『古事記』序文に登場。
「序文」とは、『古事記』の概要をまとめたもの。本文の前、冒頭部分。『古事記』編者である太安万侶が、元明天皇に言上する上表文という形式を採ってます。「臣、万侶が言さく、、、」。
そう、実は「造化三神」という言葉は、『古事記』本文には登場しないんです。本文は「造化三神」に相当する三柱の神の誕生を伝えるのみ。
ということで、
『古事記』序文から、「造化三神」部分を抜粋します。
乾坤初めて分かれて、参神造化の首となり、陰陽ここに開けて、二霊群品の祖となりき。 (※『古事記』序文より一部抜粋)
「乾坤」とは、ここでは天と地のこと。「陰陽」とは、男女の両性のこと。「群品」とは、万物のこと。
なので、訳出すると、
天と地が初めて分かれて、三神が化成して出現した最初の神であり、男女両性がここに開かれ、伊耶那岐・伊耶那美神が万物の祖となった。
といった意味になります。
大事なのは、「造化」という言葉。
「造化」とは形づくられること。
神の場合、「化す」という運動の中で、造形物として成る。他にも、「化成」「化生」と言った言葉が神の誕生に使用されます。コレ、日本神話的な、非常に特別な表現。
『日本書紀』では、このあたりは「葦の芽のような物から化す」(第一段 本伝)と、より具体的に伝えてます。
西洋をはじめ、外国の神様は最初から「ある」「(完全体として)存在する」ものとして描かれますが、日本の場合は違います。神様は最初から完璧な状態で生まれるのではなく、「化す」という運動のなかで、そのプロセスを通じて造形物として「成る」のです。「化ける」的な感じで、形を変え、姿を現すイメージ。コレ、かなり重要なポイントなのでしっかりチェック。
さて、
序文を受けて、実際の内容は『古事記』上巻の本文で登場。
特に、「造化三神」に関する部分を抽出。
天地が初めて發った時に、高天原に成った神の名は、天之御中主神。次に、高御産巣日神。次に、神産巣日神。この三柱の神は、みな独神と成りまして、身を隠した。 (『古事記』上巻より一部抜粋)
つまり、高天原に成りました神で、三柱の神であり、独神であり、身を隠したと。
で、「造化三神」については、これ以上は何も伝えていません。
なので、その理解には本文に即して
- 誕生した「高天の原」についての解釈
- 「三神」それぞれの解釈
- 「独神」の解釈
- 「身を隠す」についての解釈
- その後の活動から解釈
の5つを組み合わせて総合的に解釈していく必要があるんです。
なお、⑤について。④の身を隠したにも関わらずその後に活動してる、というのは、実際は、活動してるのは三神のうち、「高御産巣日の神」「神産巣日の神」の2神。こちら、⑤のところで詳しく解説。
ということで、いったんまとめます。
- 「造化三神」という言葉は、『古事記』序文に登場。本文では「造化三神」に相当する三柱の神の誕生を伝えるのみ。
- 「序文」では、天と地が初めて分かれて、三神が化成して出現した最初の神であると伝える。「化す」は、超日本的な表現。
- 「本文」では、三柱の神について、高天原に成りました神で、独神であり、身を隠した、と伝える。
- 「造化三神」については、これ以上は伝えてないので、本文に即して、5つのポイントをもとに総合的に解釈する必要あり。
てことで、
以下、①~⑤の順番で解説していきます。

「造化三神」のポイント① 誕生した「高天の原」を解釈する
まずは、1つめ、
「造化三神」の属性、伝えてる内容として、「高天原に成りませる」というところを深堀りチェック。
「高天原」についてはコチラで詳細を。
ポイントは、
天の原よりさらに高い場所・領域である
てことで。「高 天の原」とは、その字のごとく、「天の原」という、天空にある非常に広く尊い場所よりも、さらに高いところにある場所。
コレ、日本神話的には、至尊神が都を造営し世界を統治するに相応しい場所として位置づけてます。
このことから、要は、
「造化三神」は、高天原という一番尊い場所で誕生したから、一番尊い神々である、
ってことが言いたい。そういう位置づけにしたい訳ですね。
参考として、『古事記』版天地開闢で誕生する神々を整理した表をチェック。
結構たくさんいらっしゃるのですが、造化三神だけが唯一「高天原に誕生した」と位置づけられてるのが分かります。

造化三神だけ高天原。そのほかは文脈上、天→国。
造化三神は天空の非常に尊い場所、そのほかは下。
この明確に分けてる感じをしっかりチェック。それくらい、造化三神は尊いんだよと、特別なんだよと、つまりコレが言いたい。
次!
「造化三神」のポイント② 三神それぞれを解釈する
造化三神が誕生した場を通じて、その尊さとかスペシャルな感じが理解できたところで、次は、三神それぞれを解釈していきます。
記載順に以下。
「天」は、「天神」の住む天上界、またその天上界を賛美する美称。「御中」は、同一平面の中央ではなく、あれこれ対立するもののその真ん中の意味。
ポイントは、
「御中主」の位置が、同じく高天原に成りました「高御産巣日神」「神産巣日の神」とのちょうど真ん中に当たる
てこと。わざわざ「中の主」という神名を冠してることは要チェック。後ほど再度触れます。
続いて、
「高御産巣日神」は、天之御中主神に次いで二番目に高天の原に成りました独神で、身を隠している別天神。
「神産巣日神」は、3番目に高天の原に成りました独神で、身を隠している別天神。
で、
ポイントは、両神名に共通する「産巣日」という言葉。
「産巣」は「苔が生す」などの「むす」で、「生成する」意味の自動詞。「日」は「霊的なはたらき」を意味する語で、神名の接尾語としてよく用いられます。
この、自動生成した、という意味と、霊的なはたらきをする(もちろん、超強力)、という意味、超重要。
特に、「産(むす)」についてはしっかりチェック。
まず、用例としては、『万葉集』に大伴家持が「陸奥の国に金を出いだす詔書を賀く歌」。
「海行かば 水漬く屍、 山行かば草生す屍、 大君の辺にこそ死なめ、 かへり見はせじと 言立て」(4094番)と歌う「草生す屍」の例。
そして、『古今集』には、
「わが君は 千代に八千代に、細れ石の巌となりて、苔の生すまで」(賀)」という、「苔生す」の例、などがあります。
死体が腐ってそこに草が生えるのも、また苔が生えるのも、自然であり、条件や環境が整えばおのずから生じるもの、と考えられてた訳です。
なので、
「産巣」には、「おのずから生じる」といった意味があり、2神はそうしたイメージを共有しているってことをチェック。
ま、この「生じる」条件や環境を提供しているのが、「高天原」という場だったりするわけですが。
もっと言うと、
高天原に自然に誕生した神でもあって、その霊威、神威は抜群!
と言うこともできます。イヤ、実はそういうことが言いたいんだろう。
本件、⑤で再度まとめますので、いったん続けて解説。
次!
「造化三神」のポイント ③「独神」と④「身を隠す」について解釈する
続けて、「造化三神」の属性、伝えてる内容として「独神」と「身を隠す」についてチェック。
「独神」については詳細コチラで。
ポイントは、
『古事記』では、「独神」は、全て「隠身」と組み合わせている
ってこと。「独神成坐而隠身也(独り神と成りまして、身を隠したまひき)」
まず、「独神」については、単独で誕生し、男女の対偶神を指す「双神」と対応する神のこと。
まず「独神」が誕生し、続いてその後に「独神」が誕生するという流れ・順番。
それを受けての、「身を隠す」という内容です。
「隠身」といえば、国譲りを迫られた大国主神が執った処身方法で。
天孫に国を譲り、わが身は表の世界から立ち退くこと。コレが「隠身」。
つまり、
「独神」として身を隠すとは、「双神」に彼らの活躍するこの世界を譲り、立ち退くことをいいます。
「双神」の代表格は、伊耶那岐神と伊耶那美神であります。まさに世界を創生する2神ですね。
ここから、「造化三神」についても同じことが言えて、
三神のあとに続けて誕生する神神に、彼らが活躍する世界を譲り、自らは立ち退く立場を取っている
という訳です。このとてつもなく奥ゆかしいスタンスをチェック。
次!
「造化三神」のポイント ⑤その後の活動から解釈
その後の活動からも造化三神を解釈する手がかりを探ります。

やっぱり、最重要なのは「天之御中主神」なんですが、こちらの神様、実は単独で解釈することはできないので、まずは「高御産巣日神」「神産巣日神」の概要をチェックしてから「天之御中主神」を通じて「造化三神」をまとめてみます。
高天原を統治する天照大御神が「天の石屋」に籠り、「高天原皆暗く、葦原中つ国悉に闇し。これによりて常夜往きき。」という危機に際して、八百万の神がこぞって打開策を練りますが、このときに打開するための神事を統括するのが「高御産巣日の神」の子の「思金神」です。
「高御産巣日神」自身は、天孫降臨に際して、子の「思金神」とともに葦原中国の平定に尽力する一方、天照大御神とともに降臨を命じてもいる。尚、降臨する天孫の「日子番能邇邇芸命」は、「高御産巣日神」の外孫。
このあたりが、「高御産巣日神」が高天原系代表と言われる所以です。身を退いたにも関わらず活動してるというのは矛盾してるかもしれませんが、逆に言うと、それくらい重要な局面だったということも言えて。天孫降臨。そんな観点から整理しておきましょう。
いずれにしても、
国や神々が誕生したあとの世界で、
として、それぞれ活躍します。この構図をしっかりチェック。
そのうえで、、、
神名の「御中」にもあるように「真ん中=あれこれ対立するもののその真ん中」ということなので、「高御産巣日神」「神産巣日神」との関係性の中で解きほぐす必要あり。
なので、
神話的には、この両神が対立的関係のもとに、それぞれ役割を分担し、
一方で、対立的な関係とは言え、実質的には、高天原系の神が出雲系の神を支配する関係でもあるので、
それゆえに、両神を融和的に止揚する必要があるんです。
要は、役割は分担してるけどそれぞれ代表しているものがあるので、二つの関係を取り持つ存在が必要だってこと。
この
両神を融和的に止揚するという神話的要請に応える存在が「天之御中主神」
対立関係があるんだけど、一応、役割分担の体裁はとっており、でも、融和的にまとめあげていく必要があって。このために「天御中主の神」がいる。神名の「御中」にもあるように「真ん中=あれこれ対立するもののその真ん中」という意味を冠してるのはそういうこと。
存在そのものにこそ、この神の意義があると言えます。

次!
「造化三神」とは?全部まとめるとこうなる
以上、すべてまとめると
高天原という天界よりさらに高く尊い場所に、初めて誕生した三柱の神神。それは神名が表す通り、自然と誕生=そもそもが尊い存在であるということ。
それゆえ、三神のあとに続けて誕生する神神に、彼らが活躍する世界を譲り、自らは立ち退く立場を取っている。尊すぎる存在は表には出ない?
それでも「高御産巣日神」「神産巣日神」は重要局面で表にでて活躍。高天原系を代表する「高御産巣日神」と出雲系を代表する「神産巣日神」でそれぞれ役割分担。
ただし、両神は分担してると言っても、政治的には対立的な関係にあり、かつ、実質的には高天原系の神が出雲系の神を支配する関係でもあるので、それゆえに、両神を融和的に止揚する必要がある。この神話的要請から生まれた神が「天之御中主神」。
これら三柱の神が、一体となって高天原の最高神として位置づけられている。
ということです。やはり、一言でまとめるのは難しい。。。
あえて言うなら、、、
とにかく尊いんだ、他とは別格なんだ。と。
つまりはコレに尽きますよね。。
造化三神 まとめ
「造化三神」
『古事記』序文、本文をもとに「造化三神」を解説してきましたがいかがでしたでしょうか?
天と地ができたその原初の時に、高天原に成りました神が「天御中主神」「高御産巣日神」「神産巣日神」。この三柱の神を、古事記の序文では、「造化三神」と称しています。
で、「造化三神」については、これ以上は何も伝えていません。なので、その解釈は本文に即して整理していく必要があります。
「造化三神」。当サイトとしては、
高天原という天界よりさらに高く尊い場所に、初めて誕生した三柱の神神であり、それは神名が表す通り、自然と誕生=そもそもが尊い存在であるということ。
それゆえ、三神のあとに続けて誕生する神神に、彼らが活躍する世界を譲り、自らは立ち退く立場を取っている。
活躍する神神は、高天原系を代表する「高御産巣日の神」と出雲系を代表する「神産巣日の神」でそれぞれ役割分担している。
ただし、この両神は役割分担してるとは言え、対立的な関係にあり、かつ、実質的には高天原系の神が出雲系の神を支配する関係でもあるので、それゆえに、両神を融和的に止揚する必要がある。この神話的要請から生まれた神が「天御中主の神」。
これら三柱の神が、一体となって高天原の最高神として位置づけられている
ということでチェックいただければと思います。
ま、いずれにしても、古代日本人が構想したこの壮大な世界観が素晴らしくて。非常に日本的な概念も盛り込まれてますし、当時の政治状況等も連想させるロマンみたいなのもあります。是非ご自身で日本神話ロマンをひろげて自分なりの解釈を形作っていただければと思います。
造化三神をお祭りする神社
「造化三神」としてまとめているところは数が少なく、三神がそれぞれで祀られてるところが多いです。
● 天津神社:大津大神=造化三神の一柱としてお祭り中!
●サムハラ神社
大阪府大阪市西区立売堀2丁目5−26
「造化三神」としてまとめてお祭りしてる神社。昭和36年(1961年)に遷宮鎮座したかなり若い神社で、、いろいろ曰くあり。
●サムハラ神社 奥の宮
岡山県津山市加茂町中原900−3
大阪のサムハラ神社の起源となる地。ココからサムハラ信仰は始まった、、、
●出雲大社
幽界を統治する訳なので、当然のことながら造化三神もここに祀られておられます。
●水天宮(久留米)
「天御中主神」をお祭りする神社といえば水天宮。久留米の水天宮は全国にある水天宮の総本社です。
●高御産巣日の神・・高木神社、高皇産霊神社の社名で全国に
●神産巣日の神・・・全国の各社
是非お近くの神社をチェックされてください。
コチラも是非!日本神話の流れに沿って分かりやすくまとめてます!
天地開闢まとめはコチラで!必読!
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
[itemlink post_id=”13035″] [itemlink post_id=”13037″] [itemlink post_id=”13038″] [itemlink post_id=”13039″]
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




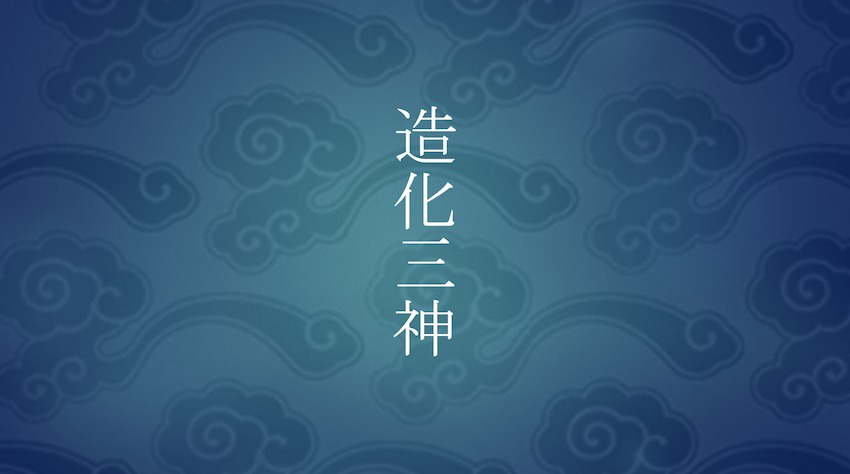






















素晴らしいですね✨