日本神話に登場する、重要ワード、重要エピソードをディープに掘り下げる「日本神話解説シリーズ」。
今回は、
饗
をテーマにお届けいたします。
饗応、饗とは、酒や食事を出して人(神)をもてなすこと。
日本神話の中でもちょいちょい登場。
コレ、結構大事なイベントで。背景には、礼をめぐる思想があったりします。
私たちも、日常生活やお仕事の中で、いろんなおもてなし場面ってあったりしますよね。そんな時にも使える神様流おもてなし作法。
これを読めば、神おもてなしができるようになる!?日本神話から学ぶ極上のノウハウをご紹介します。
神様流おもてなし作法|「饗」ってのは惜しみなくもてなすもんだ。そうすることで礼を重んずる心が尽くされるのだ
目次
神様流おもてなし事例① 保食神の月夜見尊への饗応
まずは、日本神話の現場から、神様流おもてなし事例をいくつかご紹介。神対応のリアルをチェックです。
1つめは、『日本書紀』巻一(神代上)第五段〔一書11〕から。
天神・月夜見尊に対する国神・保食神のおもてなしケース。
経緯は以下の通り。
天照大神の指令(地上にいる保食神の様子を偵察)を受けて地上に降下した月夜見尊に対して、保食神は国の飯、海の魚、山の獣をもって饗とし、激しくもてなします。
月夜見尊が(天照大神の)勅命を受けて降り、保食神のもとに到ると、保食神はさっそく首を巡めぐらし、国に向かえば口から飯を出し、また海に向かえば大小さまざまな魚を口から出し、また山に向かえば大小さまざま獣を口から出した。それらのありとあらゆる品物を備え、数え切れないほどたくさんの机に積み上げて饗応した。
月夜見尊受勅而降。已到于保食神許。保食神乃廻首、嚮国。則自口出飯。又嚮海則鰭広・鰭狭亦自口出。又嚮山。則毛麁毛柔亦自口出。夫品物悉備。貯之百机而饗之。 (引用:『日本書紀』巻第一(神代上)第五段〔一書11〕より一部抜粋)
詳細の解説はこちら↓で
●必読→ 『日本書紀』巻第一(神代上)第五段〔一書11〕 天照大神の天上統治と農業開始
月夜見尊をもてなす保食神。
コレ、状況としては、天上からエラい神様(天神)が降りて来た、ってことで。下々の、、国神としては当然、饗宴をひらいて最高のおもてなしで対応すべき局面であります。
保食神のもてなした内容。実は、非常にロジカルに組まれてます。整理すると以下の通り。
| 場所 | 国 | 海 | 山 |
| 口出したもの | 飯 | 鰭広 | 毛麁 |
| 鰭狭 | 毛柔 |
まず、国。
コレは、領域・人民・主権の3要件が揃ったいわゆる「国家」ではなく、その前段的な「国」のイメージ。もちろん、ゆくゆくは統治者のもとで人民が豊かな実りのもとで生活する国になることは想定されてます。
だからこその、飯。ご飯ですよね。
次に、海。
鰭が広い魚、鰭が狭い魚、ということで、「大小さまざまな魚」という意味になります。神様的には魚は「鰭」で分類するのがいいみたいです。オモロー!ですよね。
最後に、山。
毛が麁い動物、毛が柔らかい動物、ということで、「大小さまざまな動物」という意味に。こちらも、神様的には動物の分類整理には、毛並みを重視されるようです。
これら含め、
ありとあらゆる品物を揃えて、数え切れないほどたくさんの机に積み上げておもてなしするのが神様的流儀。
ご飯、山の幸、海の幸が、数え切れないほどたくさんの机に積み上げられ、ズラーっと並んでいる、果てが見えないくらいの光景、、、スゴイっす。しっかりチェック。
ちなみに、、、
保食神、あなた、なぜ口から出した?ってことについて補足。
コレ、実は、重要な意味があって。2つ。
1つ目。
魚や鳥獣も飯と同じ「食」に当てるものだと示すねらい。口から吐き出すことによって、食用であることを、むしろ月夜見尊に演じてみせた、ということです。
2つ目。
つまり、この時点では、葦原中国には「業」としての農や漁と言ったものが成立してなかった、ってこと。
農業や漁業が成立していなければ、文化的な営みである饗宴もひらけるはずがなく。。仕方ないので、てか、地上世界の未成熟さを表象しているものとして、口から出してもてなした、ってこと、
以上、2点、補足チェックしておきましょう。
いずれにしても、「品物悉備、貯之百机而饗之。」は御馳走の限りを尽くしてもてなした。この神様的はからいをチェックです。
神様流おもてなし事例② 海神の天神之孫への饗応
次にご紹介するのは、
2つめは、『日本書紀』巻第二(神代下)第十段〔一書3〕から。
天神之孫(彦火火出見尊)に対する海神のおもてなしケース。
海神のもとに来臨した彦火火出見尊(天神之孫)を、海神自ら厚くもてなします。
すると、海神(わたつみ)が自ら迎えて招き入れ、多くの海驢(みち)の皮を重ね敷いてその上に座らせ、さらに多くの品々を載せた机を用意し、主人としての礼を尽くした。
是時、海神自迎延入、乃鋪設海驢皮八重、使坐其上。兼設饌百机以尽主人之礼。(引用:『日本書紀』巻第二(神代上)第十段〔一書3〕より一部抜粋)
彦火火出見尊をもてなす海神。
コレ、状況としては、「天神之孫」であるエラい神様が来臨された、ってことで。海神としては当然、最高のおもてなしで対応すべき局面であります。
海神のもてなした内容。ポイント3つ。
- 海神が自ら迎えて招き入れる。
- たくさんの海驢の皮を重ね敷き、その上に座っていただく。
- 多くの品々を載せた机をたくさんご用意申し上げた。
ということで、
これが文中にある「主人之礼」。非常に厚くおもてなししてますよね。
ちなみに、、、
「海驢」とは、今でいうアシカのこと。アシカの皮を重ね敷くことが海神流のおもてなしのようです。
以上、2つ、神話の現場からお届けいたしました。神様たちも結構必死。とにかく御馳走、おもてなしの限りを尽くしてる感じをチェックです。
おもてなしで大事なのは礼を重んずる「心」
ここからご紹介するのは、これらの神様流おもてなしの拠り所、背景となる思想について。
日本神話、より具体的に言うと、『日本書紀』が編纂された当時の、膨大な知の体系を探ることで、どういった思想が背景、根拠となってるのかが見えてくるのです。
今回の、おもてなし根拠は、、、
『礼記』
来ました。礼記、、、
『礼記』とは、儒教の基本経典である「経書」の一つで全49篇。周から漢にかけて、儒学者たちがまとめた「礼」に関する記述を、前漢の戴聖が編纂したもの。
もともとは、礼に関する注記という意味で、「礼」あるいは「礼経」に関係する論議・注釈を指す言葉でした。
『礼記』では、賓客をもてなす「礼」について、まー細かく定めているんですが、そのなかに今回の神様流おもてなしに通じる記述があります。
それがコチラ。
まずは、賓客をまず迎えるときの内容。
「主人拝迎賓于庠門之外入、三揖而后至階、三譲而后升、所以致尊譲也。」(郷飲酒義第四十五)
→意訳: 主人が案内して廟に至り、門に入って揖すること三度ののち堂下に至り、辞譲すること三度ののち、まず主人から登るが、これは主客が互いに相手を尊びかつ譲ろうとする心を表明するからである。
※揖とは、中国式の会釈のこと。胸の前に両手を組み合わせて行う礼法。
そのあと賓客の座について
「主人者尊賓、故坐賓於西北。」(郷飲酒義第四十五)
→意訳: 主人は賓客を尊ぶので、賓客が座る場所を西北に設ける。
※西北は、冬初の始まる方角で、漢代の陰陽五行説にもとづく考え方。
他にも、
「壹食再饗、燕与時賜、無数。所以厚重礼也。(中略)然而用財如此厚者、言尽之於礼也。」(聘義第四十八)
→意訳: 使節に食事を供する酒宴一回と、主客献酬する饗宴二回、制限もなくいくたびも賜与がなされる。これらは礼を重んじるからこそである。(中略)財物が惜しみなく多く用いられるのは、真に礼を重んじる心が尽くされる。
と。
いずれも、賓客をもてなす「礼」について、ホント細かく定めてるんです。とくに「壹食再饗」など、酒宴や賜与も無数とあり、これはまさに神様流のおもてなしに通じますよね。
そして、
ココが一番大事なのですが、
慇懃ともいえる礼式の数々、無数の酒宴や賜与は、それこそが礼を厚く重じることをあらわす考え方だということ。
財物を惜しみなく用いることは「真に礼を重んずる心が尽くされる、と言うべきである。」ってことなんす。
なので、
天神・月夜見尊に対する国神・保食神のおもてなしも、
天神之孫(彦火火出見尊)に対する海神のおもてなしも、
いずれも、御馳走をならべてみんなで楽しみました、ではなくて、その本質は、礼を重んじる心を尽くしている、その現れと解釈すべきなんですね。とても重要な考え方だと思います。
まとめ
神様流おもてなし作法
日本神話に登場する、重要ワードをディープに掘り下げる「日本神話解説シリーズ」。今回は、
饗
をテーマにお届けしましたがいかがでしたでしょうか?
天神・月夜見尊に対する国神・保食神のおもてなし。
天神之孫(彦火火出見尊)に対する海神のおもてなし。
いずれも、
慇懃ともいえる礼式の数々、無数の酒宴や賜与は、礼を厚く重じる考え方や価値観があり、惜しみなくおもてなしすることは、真に礼を重んずる心が尽くされるということとしてチェックです。
私たちも、日常生活やお仕事の中で、いろんなおもてなし場面ってあったりしますよね。そんな時にも使える神様流おもてなし作法。ぜひ活用してみてください。
こちらも参考に。
日本神話をシリーズ解説!多彩な神話世界をチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




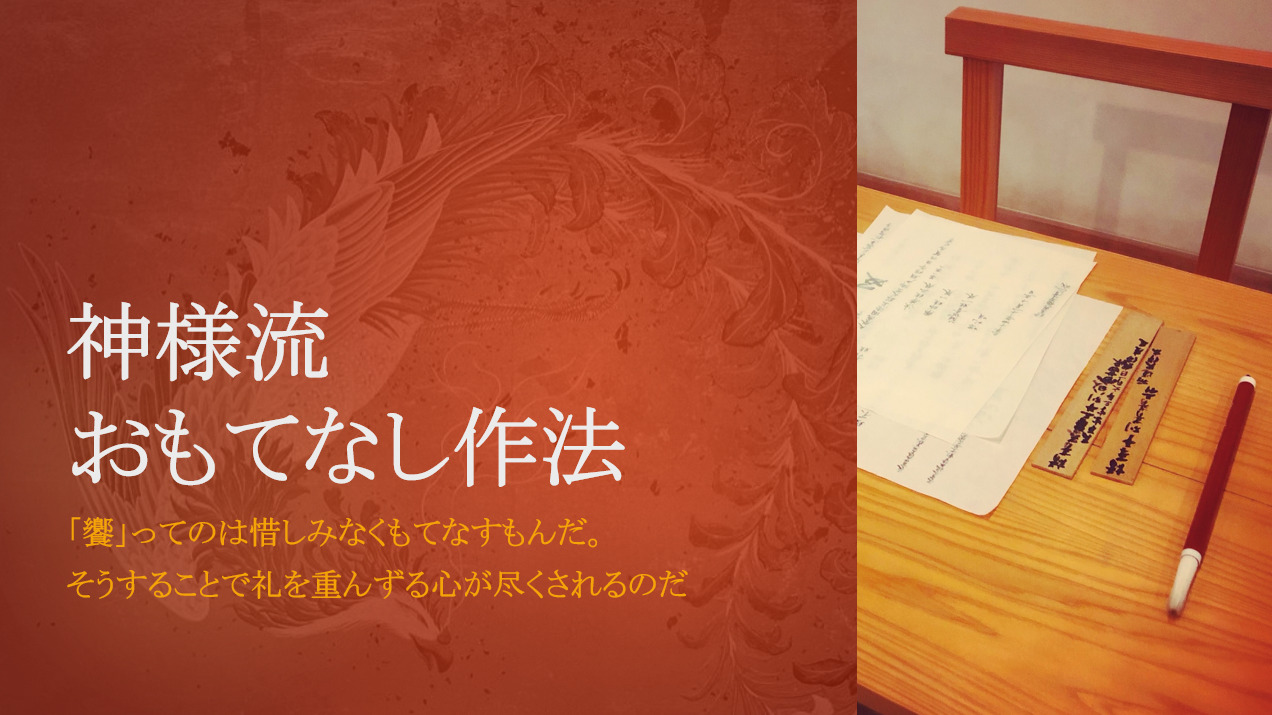












最後までお読みいただきありがとうございます。お気軽にコメントされてくださいませ。お待ちしております!