日本神話に登場する様々な神様を、どこよりもディープに、分かりやすく解説します。
今回は
「神世七代」
です。
「神世七代」は、『日本書紀』にも『古事記』にも登場する神々のカテゴリ。
『日本書紀』では、天地の始まりに伴って最初に誕生した「純男」と、続いて誕生した「対偶神(男神と女神の一組)」とを、一括して「神世七代」と称しています。
一方、『古事記』では、5柱の「別天神」が誕生した後、続いて誕生する「独神」2柱と「双神」10柱の計12柱の神々の総称。
どちらも同じ「神世七代」という言葉が使われているのですが、ビミョーに位置付けが違うのです。
今回は、その辺りも含めて、『日本書紀』『古事記』の本文を元に、文献学的学術成果も取り入れながら詳しく解説します!
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
神世七代(かみよななよ)とは? 天地開闢に次々と誕生した尊貴な神様カテゴリ!『日本書紀』『古事記』をもとに神世七代を徹底解説!!
目次
『日本書紀』の神世七代
まずは、正史『日本書紀』からご紹介。
「神世七代」が登場するのは、『日本書紀』巻第一。「神代紀」と呼ばれる箇所で、具体的には、第一段と第二段で登場、そして第三段で総括して「神世七代」としています。
具体的な神の誕生がコチラ!
で、それらを一括する第三段がコチラ!
合わせて八柱の神である。これは陰の道と陽の道が入り混じって現れた。それゆえ男と女の性となったのである。そして、国常立尊から、伊奘諾尊・伊奘冉尊に至るまでを、神世七代と言う。
凡八神矣。乾坤之道、相参而化。所以、成此男女。自国常立尊、迄伊奘諾尊・伊奘冉尊、是謂神世七代者矣。 (『日本書紀』巻一(神代上)第三段 本伝より)
ということで。
「国常立尊から、伊奘諾尊・伊奘冉尊に至るまでを、神世七代と言う。」とあるように、第一段と第二段で登場した神々を総括して「神世七代」と位置付けてる訳です。
これら、登場する神々をまとめると、、、
『日本書紀』の神世七代一覧
| 神世 | 神名 | 誕生方法 | 登場場所 |
| 一代 | 国常立尊 | 乾道独化 (純男の神) |
第一段 |
| 二代 | 国狭槌尊 | ||
| 三代 | 豊斟渟尊 | ||
| 四代 | 泥土煑尊 | 乾坤之道、相参而化 (男女一対の神) |
第二段 |
| 沙土煑尊 | |||
| 五代 | 大戸之道尊 | ||
| 大苫辺尊 | |||
| 六代 | 面足尊 | ||
| 惶根尊 | |||
| 七代 | 伊奘諾尊 | ||
| 伊奘冉尊 |
って、、
コレ、すごくないですか!???
3+4=計7世代を、「神世七代」として位置づけ。まさかの、、こんなガチガチ設定が用意されてたなんて、、、天地開闢、世界創世という原初に誕生した、非常に尊い神様ジェネレーション、神様カテゴリとして「神世七代」が登場してるんです。
で、
その詳細としては、、ちょっと、専門的になりますが、、
- 「乾道独化」した「純男の神」は、最も尊い存在。なので「3」という陽数設定。
- 一方の「男女ペアの神」は、次順の存在。なので「4」という陰数設定。
- 全体を括る数字として、奇数の「7」という陽数設定。合理的で数学的にも美しい世界、それが天地開闢にまつわる神世七代誕生の神話観です。
てことで。
なお、「乾道独化」とか、「純男神」とか「男女ペア神」とか、突然出てきて意味不明な方々はコチラ↓をチェック。詳しく、分かりやすくまとめてます。
●必読→ 『日本書紀』巻第一(神代上)第一段 本伝 ~天地開闢と三柱の神の化生~
そのうえで、、、
『日本書紀』の神世七代、その絶対押さえとくべきポイントが3つあります
- 「神世七代」のカテゴリ分け=「尊卑先後の序」にもとづく区別!
- 「神の化生方法」には「乾道独化」と「乾坤之道、相参而化」の2つがあって、全然違う!
- 「神世七代」は、天地開闢、世界創世という原初に誕生した、非常に尊貴な神様カテゴリ
ということで、
詳細は以下。
次、2つ目。
②「神の化生方法」には「乾道独化」と「乾坤之道、相参而化」の2つがあって、全然違う!
神様の誕生の仕方、神話的には「化生」という言葉なんですが、それには2種類あり、全然違いまっせ、ということ。これもチェック。
コレ、そもそも、「道」や「易」の概念を理解しないと読み解けない、、、詳細コチラ↓で
●必読→:日本神話的易の概念|二項対立の根源とその働きによって宇宙はつくられ動いている
ここでは簡単に、以下。
「道(みち、タオ)」は、乾坤、天地、のように
- 2項対立の概念で構成され、
- 「働き」がある、または運動するものである
乾の道・坤の道、といった感じで、「2項対立の関係」と「働き」があるとされます。
具体例としては、、、
- 乾、陽、天、男、、、
- 坤、陰、地、女、、、
と、2項対立の対応関係。これを理解してないと何のことやらサッパリ。。。
乾の道は「乾の道として働き」があり、坤の道は「坤の道としての働き」があるんです。男女もそうですよね。男は男としての働きがあり、女は女としての働きがある。
●必読→ 日本神話的時間発生起源|伊奘諾尊・伊奘冉尊の柱巡りが時間の推移や季節を生みだした件
で、
「日本神話的 乾坤の働き」として重要なのが、
「神を化生させる」
というもの。コレ、激しくチェック。
第一段で伝える「乾道独化」とは、「乾の道は単独で化す」という意味。コレ、乾道の単独の働きによる化生の結果が「純男神」ということ。純粋な男の神様。
まー、とにかくスゴイ野郎(♂)推し、、、現代の価値観からすると相容れない感たっぷりですが、『日本書紀』編纂当時の思想的なものとしてご理解いただければと。。。汗
乾の道の働きにより、純粋な男の神様が誕生
それに対して、
第二段で誕生した「男女ペアの神」は、「乾坤之道、相参而化」。
要は、乾道単独の働きでは無く、乾と坤の、両方の道の働きによるものだ、ということ。乾坤が互いに参じて、集まって、混じり合って、それによって化生したのが男女ペアだと。
乾と坤の道がお互いに集まって混じり合うと男女ペアの神様が誕生
と、明確に分けてるんですね。この「区別したいしたい感」を支えているのも「尊卑先後の序」。
「神の化生方法」には「乾道独化」と「乾坤之道、相参而化」の2つがあって、全然違う!てこと、しっかりチェックください。
次!
③「神世七代」は、天地開闢、世界創世という原初に誕生した、非常に尊貴な神様カテゴリ
ということで最後の3つ目のポイント。結論部分。コレまで見てきた通り、
3+4=計7世代を、「神世七代」として位置づけてました。
全体を括る数字(7)として奇数=陽数で設定。非常に合理的に、ロジックガチガチで構成。
天地開闢、世界創世という原初に誕生した、とっても尊い神様ジェネレーション、神様カテゴリ。
だからこそ、理解としては、
「神世七代」という神ジェネは、後の伊奘諾尊・伊奘冉尊の神生みによって誕生する神様たちとは違う、むしろ別格の、いや、超絶別格の神様たち、として位置付けられてる、明確に区別されてる、ってこと。
道の働きによって道から誕生した神様たちと、二神の結婚と神生みによって誕生した神様たちとでは、尊貴さにおいて、格が違います、てこと。この点もチェックされてください。
ということで、
『日本書紀』の「神世七代」をまとめると以下。
- 「神世七代」=「尊卑先後の序」にもとづく区別!
- 「神の化生方法」には「乾道独化」と「乾坤之道、相参而化」の2つがあって全然違う!「乾道独化」した「純男の神」は、最も尊い存在。なので「3」という陽数設定。一方の「男女ペアの神」は、次順の存在。なので「4」という陰数設定。合理的で数学的にも美しい世界、それが神世七代誕生の神話観。
- 「神世七代」は、天地開闢、世界創世という原初に誕生した、非常に尊貴な神様カテゴリ。この後に続く神生みによって誕生する神様たちとは違う、むしろ別格の、いや、超絶別格の神様たち、として位置付けられてる、明確に区別されてる。
以上、『日本書紀』の伝える「神世七代」でした。
次は『古事記』です!

『古事記』の神世七代
続けて『古事記』版「天地創生神話」。
まずは、「神代七代」について伝えてる箇所をチェック☟
次に、成った神の名は、国之常立神。次に、豊雲野神。この二柱の神も、独神と成りまして、身を隱した。
次に、成った神の名は、宇比地邇神。次に、妹 須比智邇神。次に、角杙神。次に、妹 活杙神(二柱)。次に、意富斗能地神。次に妹 大斗乃辨神。次に、於母陀流神。次に、妹 阿夜訶志古泥神。次に、伊耶那岐神。次に、妹 伊耶那美神。
上の件の、国之常立神より下、伊耶那美神より前を、あわせて神世七代という。上の二柱の独神は、おのおのも一代という。次に双へる十柱の神は、おのおのも二柱の神を合わせて一代という。
次成神名、國之常立神訓常立亦如上、次豐雲上野神。此二柱神亦、獨神成坐而、隱身也。 次成神名、宇比地邇上神、次妹須比智邇去神此二神名以音、次角杙神、次妹活杙神二柱、次意富斗能地神、次妹大斗乃辨神此二神名亦以音、次於母陀流神、次妹阿夜上訶志古泥神此二神名皆以音、次伊邪那岐神、次妹伊邪那美神。此二神名亦以音如上。 上件、自國之常立神以下伊邪那美神以前、幷稱神世七代。上二柱獨神、各云一代。次雙十神、各合二神云一代也。 (『古事記』上巻より一部抜粋)
ということで。
『古事記』では、天地初発に天之御中主神をはじめとして次々に神が誕生するのですが、その途中以降、「別天神」のあとに誕生する、國之常立神から伊耶那美神までを「神世七代」として位置づけてます。
分かりやすく、『古事記』冒頭で誕生する神様は、以下の通りです。
『古事記』の神世七代一覧

ということで、、、コチラも、、、スゴイ。。。
- 『日本書紀』と異なり、『古事記』の「神世七代」は、造化三神、別天神の次に位置付けられる神様カテゴリである。
- 『日本書紀』と異なり、2+5=計7世代を「神世七代」として位置づけ。
- 『日本書紀』のような乾坤の道による働きと言ったロジックガチガチの雰囲気無し。「純男神」に相当する「独神」、「男女ペア神」に相当する「双神」という分類があるようだが、、、
と言った設定になってます。
ポイント大きく2つ。
- 『古事記』の「神世七代」は次順の位置付け。「神世七代」よりも尊貴な神々の存在を伝えている
- 神の名前は、この地上世界の成り立ちを表象している
ということで、
詳細は以下。
①『古事記』の「神世七代」は次順の位置付け。「神世七代」よりも尊貴な神々の存在を伝えている
『日本書紀』では、「神世七代」とは、天地開闢、世界創世という原初に誕生した、非常に、なんなら最も尊い神様、という立ち位置でした。で、そのためのロジックをガッツリ組み上げてる感じ。ムキムキの『日本書紀』。
一方、『古事記』では、こうした立ち位置を「造化三神」や「別天神」に譲ってる感じなんです。あるいはランクを落とされてる。
コレは、そもそも『日本書紀』『古事記』の編纂目的や過程が関わってくるお話で。詳細はコチラ↓で。
●必読→ 『日本書紀』と『古事記』の違いに見る「日本神話」の豊かさとか奥ゆかしさとか
要は、『日本書紀』は国の歴史書、目線は外国に向いてるので、そのためのロジックをガッツリ組みあげて編纂されてる。一方の、『古事記』は天皇家の私的な歴史書なので、天皇家にとっての内容になってる。
こうした違いが、結果的に、「神世七代」の位置付けの違いを生んでいるんです。
『古事記』は神世七代よりも尊貴な神神を設定することに注力していて、道の働きがどうのと言った事は重要視してない。むしろ、天皇家と出雲、天皇家と各豪族との関係の方が重要で。
それが表れてるのが「造化三神」や「別天神」といったカテゴリ。
●必読→ 造化三神(ぞうかさんしん)|天と地ができた原初の時に、初めて高天原に成りました三柱の神々。
●必読→ 別天神(ことあまつかみ)|天地のはじまりに誕生した独神で身を隠す五柱の神々。『古事記』をもとに別天神をディープに解説!
特に、
「造化三神」は、「天御中主神」と「高御産巣日神」「神産巣日神」なのですが、
で、
「高御産巣日神」「神産巣日神」がそれぞれ、高天原系、出雲系として役割を分担してる設定になってます。しかしながら、それぞれ代表しているものがあるので、二つの関係を取り持つ存在が必要だということで、そんな神話的要請から誕生してるのが、「天御中主神」だったりします。
このように、神世七代では解決しきれない天皇家ならではの、諸勢力との関係取り持ちのために誕生している神々がいるわけで、結果的に、神世七代はランクが下がってるように見える訳です。
次!
②神の名前は、この地上世界の成り立ちを表象しています。
さて、そんな編纂背景とかはともかく、『古事記』の神世七代については、神名に注目です。
神世七代
●第1世代→ 国之常立神:国が恒常的に(永久に)立ち続ける神
●第2世代→ 豊雲野神:豊かな、雲の覆う野の神
●第3世代(男→ 宇比地邇神:最初の泥土の神
●第3世代(女→ 妹 須比智邇神:砂と泥土の神
●第4世代(男→ 角杙神:角状の棒杙の神
●第4世代(女→ 妹 活杙神:活きいきとした棒杙の神
●第5世代(男→ 意富斗能地神:偉大な戸の男神
●第5世代(女→ 妹 大斗乃辨神:偉大な戸の女神
●第6世代(男→ 於母陀流神:顔つきが整って美しいと称える神
●第6世代(女→ 妹 阿夜訶志古泥神:まあ何と恐れ多いことよと畏まる神
●第7世代(男→ 伊耶那岐神:結婚に向けて誘いあう男の神
●第7世代(女→ 妹 伊耶那美神:結婚に向けて誘いあう女の神
改めて、
表象するのは、神の世に、新しく世界が次々に具体的な形をとって展開するさま。
ただ、その意味については、様々な説があり、いまだに決着をみていません。
こんな感じ。
| 代 | 神 | 説① | 説② | 説③ |
| 1 | 国之常 | 国の恒常的確立 | 国土の根源 | 神々の生成の場としてのトコの出現 |
| 2 | 豊雲野 | 雲の覆う原野 | 原野の形成 | 神々の生成を具現化している二元的な場 |
| 3 | 宇比地&須比智 | 男女一対の盛土(地鎮) | 土砂の発生 | 神の原質としての泥と砂 |
| 4 | 角杙&活杙 | 棒杙(境界の形成) | 杙の打ち込み | 現れ出ようとする最初の形 |
| 5 | 意富斗&大斗乃 | 門棒(住居の防塞) | 居住の完成 | 男女神の性が形態として表面化したこと |
| 6 | 淤母陀&阿夜訶 | 男根・女陰の神像(生産豊穣の霊能) | 人体の完備・意識の発生 | 形態の完備を体と用の両面から言ったもの |
| 7 | 伊耶那岐&伊耶那美 | 交歓の2面像(媾合生産) | 夫婦の発生 | 完全体としての神の身体的出現の次第を表すもの |
まーいろいろある訳です。
ただ、
神世七代の神名の要点をまとめると、以下になります。テーマは男女の結婚へ向けたストーリー♡
| 神名 | 表象するもの |
| 国常立 | 天の常立神に続き、それと対応して成る国の恒常的確立(予祝) |
| 豊雲野 | 地上世界に豊かな雲のわき立つ野が出現したこと、地上世界の豊穣(予祝) |
| 宇比地&須比地 | 天→国、雲野→泥砂という対応に即した、地上世界の土台 |
| 角杙&活杙 | 土台としての大地に標識となる杙を打ち込む |
| 意富斗&大斗乃 | 打ち込んだところに(外と内を隔てる)戸(門)を造立 |
| 於母陀&阿夜訶 | 男と女をそれぞれ「面足る」「あや畏ね」と称える |
| 伊耶那岐&伊耶那美 | 男と女とが互いに誘いあう |
これ、ホントによくできた神名になっていて。
表象しているのは、神の世に、新しく世界が次々に具体的な形をとって展開するさまであり、以下のような物語展開。
- 先ずは、国(国土)が恒久的に(永久に)確立することを予祝
- その国(国土)に、豊穣を約束する「雲のわき立つ野」が出現することを予祝
- そのうえで、双神により具体的な表れとして、大地の土台ができ、そこに標識となる杙を打ち込み、戸を造立する
- そして、その中で結婚に向け、男女の神により、互いに全き性を具有することを称えあい、誘い合う、、
という、日本的な、極めて日本的な世界創生の物語。。。ステキすぎる!
ということで、
『古事記』の「神世七代」をまとめると以下。
- 『古事記』の「神世七代」は、造化三神、別天神の次に位置付けられる神様カテゴリ。2+5=計7世代を「神世七代」として位置づけ。
- 神の名前は、この地上世界の成り立ちを表象。日本的な、極めて日本的な世界創生の物語が込められている。
以上、『古事記』の伝える「神世七代」でした。
神代七代の日本神話的位置づけ
『日本書紀』『古事記』の「神世七代」をチェックしてきましたが、最後に、共通する部分を抽出し、日本神話全体における「神世七代」の位置づけをチェックです。
いずれも、天地開闢に誕生する非常に尊貴な神様カテゴリですが、やっぱり大きいのは、伊奘諾尊(伊耶那岐命)&伊奘冉尊(伊耶那美命)の誕生です。
この2柱の神が誕生する前は、乾坤の道が、道本来がもつ働きによって動いていた。あるいは、国や野が誕生したり、土台とか杙とか、表象内容は外観・外見にとどまっているのですが、伊奘諾尊(伊耶那岐命)&伊奘冉尊(伊耶那美命)の登場によって、男と女が互いに誘い合い、心を交わせ、お互いの存在を認め合うようになります。
これは、つまり、男女が一体化しようと声を掛け合っているという事。ポイントはまさにここで。
要は、
日本神話的世界創生は「最終的に収斂していく事」にあります。一体のものとして収れんする。
国→野→土台→男と女の誕生、そして一体化。
男と女という、本来的にあい異なる性が、異なればこそ互いに誘いあって一体化しようとする本質的・根源的なありようを表象している。
神の世の最後に、男女が互いに誘いあう本来的なあり方を表象する神が出現したことにより、神世七代という世界も完成をみる、とも言えて。
だからこそ、そのあとに、いよいよ具体的な国や神々が誕生していく流れが出来上がる訳です。
こんな世界創生を描いている神話が他にあるのでしょうか。。。神世七代、その位置づけを日本神話全体の文脈から見ると、とても奥ゆかしい内容になっていることが分かりますよね。ココ、是非チェックいただければと思います。
神世七代 まとめ
「神世七代」
『日本書紀』にも『古事記』にも登場する神々のカテゴリ。
『日本書紀』では、天地の始まりに伴って最初に誕生した「純男」と、続いて誕生した「対偶神(男神と女神の一組)」とを、一括して「神世七代」と称しています。
『日本書紀』の「神世七代」ポイント3つ。
- 「神世七代」=「尊卑先後の序」にもとづく区別!
- 「神の化生方法」には「乾道独化」と「乾坤之道、相参而化」の2つがあって全然違う!「乾道独化」した「純男の神」は、最も尊い存在。なので「3」という陽数設定。一方の「男女ペアの神」は、次順の存在。なので「4」という陰数設定。合理的で数学的にも美しい世界、それが神世七代誕生の神話観。
- 「神世七代」は、天地開闢、世界創世という原初に誕生した、非常に尊貴な神様カテゴリ。この後に続く神生みによって誕生する神様たちとは違う、むしろ別格の、いや、超絶別格の神様たち、として位置付けられてる、明確に区別されてる。
一方、『古事記』では、5柱の「別天神」が誕生した後、続いて誕生する「独神」2柱と「対偶神」10柱の計12柱の神々の総称。
『古事記』の「神世七代」をまとめると以下。
- 『古事記』の「神世七代」は、造化三神、別天神の次に位置付けられる神様カテゴリ。2+5=計7世代を「神世七代」として位置づけ。
- 神の名前は、この地上世界の成り立ちを表象。日本的な、極めて日本的な世界創生の物語が込められている。
いずれも、天地開闢に誕生する非常に尊貴な神様カテゴリ。
ですが、、
やっぱり大きいのは、最後の世代、伊奘諾尊(伊耶那岐命)&伊奘冉尊(伊耶那美命)の誕生。
2神の誕生により、男(陽)と女(陰)が互いに誘い合い、心を交わせ、お互いの存在を認め合うようになる。つまり、
日本神話的世界創生は「最終的に収斂していく事」にある。一体のものとして収れんする。
国→野→土台→男と女の誕生、そして一体化。
男と女という、本来的にあい異なる性が、異なればこそ、互いに誘いあって一体化しようとする本質的・根源的なありようを表象している。
だからこそ、そのあとに結婚し、いよいよ具体的な国や神々が誕生していく流れが出来上がる訳です。
日本神話全体の流れの中でその位置づけ、重要性をチェックされてください。
神世七代の神様詳細解説はコチラで!
●第1世代→ 国之常立神:国が恒常的に(永久に)立ち続ける神
●第2世代→ 豊雲野神:豊かな、雲の覆う野の神
●第3世代(男→ 宇比地邇神:最初の泥土の神
●第3世代(女→ 妹 須比智邇神:砂と泥土の神
●第4世代(男→ 角杙神:角状の棒杙の神
●第4世代(女→ 妹 活杙神:活きいきとした棒杙の神
●第5世代(男→ 意富斗能地神:偉大な戸の男神
●第5世代(女→ 妹 大斗乃辨神:偉大な戸の女神
●第6世代(男→ 於母陀流神:顔つきが整って美しいと称える神
●第6世代(女→ 妹 阿夜訶志古泥神:まあ何と恐れ多いことよと畏まる神
●第7世代(男→ 伊耶那岐神:いざなう男の神
●第7世代(女→ 妹 伊耶那美神:いざなう女の神
コチラも是非!日本神話の流れに沿って分かりやすくまとめてます!
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。参考:運営者プロフィール | 日本神話.com (nihonshinwa.com)
参考文献:『古事記』(新潮日本古典集成)、『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
[itemlink post_id=”13035″] [itemlink post_id=”13037″] [itemlink post_id=”13038″] [itemlink post_id=”13039″]どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




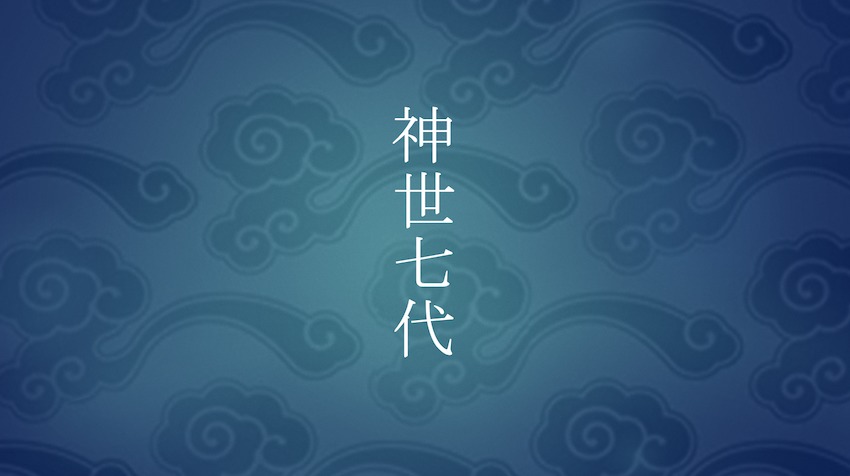
















①「神世七代」のカテゴリ分け=「尊卑先後の序」にもとづく区別!
そもそも、『日本書紀』の中で「神世七代」という神様カテゴリを設定してるのは結構特別なんです。他にそう言ったネーミング・カテゴリを設定している例が無い。
そこには、
この世界の始まりの時代を、
それ以降とは区別して「理想の世(聖代)」とする歴史観があるんです。
区別!
区別=尊と卑の別、優と劣の別
と言った感じで。コレを図示するとコチラ!
「神世七代」を理解しようとするとき、それ単体で捉えるのは難しい。
背景にある、天地開闢からの時代の変遷、それは「乾坤の道による化生」から「男女の営みによる出産」への大きな流れ、もっというと、大きな大きな誕生の物語であることを押さえる必要があります。
●必読→ 『日本書紀』巻第一(神代上)第一段 本伝 ~天地開闢と三柱の神の化生~
で、重要なのは、ココにある「スゲー区別したいぜ感」を支えている「尊卑先後の序」の存在。
「尊卑先後の序」は、日本神話を貫く超重要な原理原則。
やわらかく言うと、物事には優先順位があるよ、ということ。この根底概念をもとに神話世界が構成されてるんです。
●必読→ 尊卑先後の序|日本神話を貫く超重要な原理原則!世界の創生当初から存在する原理的次序で、天→地→神という成りたちを導きます。荘子(外篇、天道第十三)
ということで、
神世七代に込められた根本概念として、
原理原則をもとにした神様カテゴリ。そこには、この世界の始まりの時代を、それ以降とは区別して「理想の世(聖代)」とする歴史観がある。
まずはチェックです。