「天地開闢」とは、はじめて世界が生まれた時のこと。
「開闢」の「開」は開くこと、「闢」も左右に押し開くことをいいますので、「天地開闢」とは、文字通り、天と地が開かれること、を言います。
日本神話のみならず、おおむね世界の神話伝承は「天と地が分かれる、開かれる、できる」といったところから始まるので、世界のはじまりのことを「天地開闢」というようになってます。
天地開闢
そもそも日本神話の中で天地開闢を伝えてるのは『日本書紀』と『古事記』という日本最古の歴史書。実は、この時点で天地開闢は2種類あります。
しかも、『日本書紀』には〔本伝〕と呼ばれる基本ストーリーの他、〔一書〕と呼ばれる異伝を併載するスタイル。これにより、伝承はさらに増えるんです。
日本神話的な天地開闢を知ろうとするとき、まずは、この種類の多さ、それは「多彩で豊かな世界が広がってる」ってことなんですが、そこから入る必要があるんです。
今回は、そんな多彩で豊かな世界を、『日本書紀』が伝える天地開闢、『古事記』が伝える天地開闢、と分けて、ディープにご紹介していきます。
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
天地開闢とは? 日本神話が伝える天地開闢を日本書紀や古事記から徹底解説!
目次
『日本書紀』と『古事記』の伝える天地開闢の範囲
『日本書紀』、『古事記』における天地開闢の詳細に入る前に、まずは全体像を確認。
最初に地図。そのあと現場です。
まず、「天地開闢として扱う範囲」。
| 『日本書紀』 | 『古事記』 |
| 巻第一(神代上) 第一段 本伝、一書1,2,3,4,5,6 第二段 本伝、一書1,2 第三段 本伝、一書1 |
上巻の一番最初 |
『日本書紀』は全30巻あるなかで、最初の1巻目。の、1段から3段まで。
『古事記』は全3巻あるなかで、最初の1巻目。の、一番最初の箇所。
いずれも、内容的には、天地がはじめて分かれ、いろいろあって、伊奘諾尊・伊奘冉尊が誕生するところまで、です。
改めて、、、
「多彩」ですよね。
単純に、伝承の数だけでいうと、『日本書紀』本伝3+一書9+『古事記』1=13
13の伝承があって、それぞれ違ってるわけです。この時点で、「何がホントなのか?」なんて意味なくて、多彩さ、多様さを大きく捉えて理解する必要があるんです。
そのうえで、その豊かさを楽しみましょう。

『日本書紀』と『古事記』の伝える天地開闢の違いと共通点
さて、以下簡単に。『日本書紀』と『古事記』の天地開闢神話の違いと共通点です。
まずは「違い」から。
①目的、狙いが違う
まとめると以下。
| 『日本書紀』 | 『古事記』 |
| 国の歴史書。対外向けに日本という国のスゴさを伝えることが目的。 →最先端理論をもとに創意工夫によって独自の神話を構築。 |
天皇家の私的歴史書。皇太子教育用のテキストとして編纂。天皇家がこの地を統治する正当性を示すことが目的。 →一本の物語として分かりやすく神話を構築。 |
そうなんす。
『日本書紀』と『古事記』の編纂動機、目的が違うので、同じ天地開闢なんですが違うところが出てくる訳です。
『日本書紀』がたくさんの異伝を併載してるのも、目的が「対外的に日本という国のスゴさを示すこと」であり、そのためにたくさんの伝承があったほうがいいから。多くの神話伝承がある=文化の厚み、国のスゴさ、なので。
まず、そもそもの、目的が違うところから編纂された日本神話的天地開闢なんだということをチェック。
次!
②天地のつくられ方が違う
| 『日本書紀』 | 『古事記』 |
| 混沌から始まる天地開闢。混沌のなかから、軽い気は上へ、重い気は下へ、それぞれ天と地を形成、、、といった流れ。 | 天地が発生したところから始まる天地開闢。さらに高天原がすでにできていて、神の誕生をメインテーマに展開する流れ。 |
と。
天地のつくられ方が違うんすね。てか、『古事記』なんて天地は最初からあるし。なんなら高天原も既にあるし。
『古事記』としては、世界が、天地が、どう誕生したかなんて問題ではないんです。それよりも神とその系譜の方が大事。力の入れ方も全然違います。
一方、『日本書紀』は国の歴史書なんで、世界、天地、の誕生プロセスもしっかり伝えてます。整合性がとれてないと諸外国からツッコまれるしね、ナメられるしね。理論武装してガッチガチに構築。
次!
③誕生する神様が違う
| 『日本書紀』 | 『古事記』 |
| 純男神3神(三代) 男女神8神(四代) 計11神 (神世七代) ※本伝伝承のみ。一書も入れると増えます 神分類用の枠組みは、性別、世代の2つ |
造化三神 3神 別天神 5神(造化重複除外すると2神) 独神 7神(造化、別天重複除外すると2神) 双神10神(五代) 計17神 神分類用の枠組みは、場所、尊さ、単複(男女)の3つ |
と、
だんだん細かくなってきてるので迷わないように。
ココでのポイントは、神様を分類する枠組み、カテゴリ、軸の設定。
『日本書紀』は、2つだけ。男女の別、世代の別のみです。男女の軸と世代の軸は一致してるので、なんなら分類軸は1つだけとも言えます。
『古事記』は、3つ。場所、尊さ、単複(男女)。どこで生まれたか?尊さはどれくらいスゴイか?単数形か複数形か。
軸をしっかりチェックしておけば神様の分類は簡単です。
以下、『日本書紀』『古事記』の天地開闢時の誕生神様を記載します。
『日本書紀』
| 神世 | 神名 | 誕生方法 | 登場場所 |
| 一代 | 国常立尊 | 乾道独化 (純男の神) |
第一段 |
| 二代 | 国狭槌尊 | ||
| 三代 | 豊斟渟尊 | ||
| 四代 | 泥土煑尊 | 乾坤之道、相参而化 (男女一対の神) |
第二段 |
| 沙土煑尊 | |||
| 五代 | 大戸之道尊 | ||
| 大苫辺尊 | |||
| 六代 | 面足尊 | ||
| 惶根尊 | |||
| 七代 | 伊奘諾尊 | ||
| 伊奘冉尊 |
と、、まースゴイ合理的に組まれてる。
『古事記』

まーコチラもすごいガッチガチじゃないですか。天地開闢の神様設定に、こんな細かい分類・区別が存在していたなんて!
逆に、共通するところは以下の通り
①「神世七代」という尊い神様カテゴリ、枠組みは同じ
『日本書紀』版天地開闢も、『古事記』版天地開闢も、「神世七代」という尊い神様カテゴリを設定しているのは同じです。
『日本書紀』は「神世七代」を最も尊い神様として位置づけ。これ以上はありません。
しかし、『古事記』は「神世七代」以上に尊い神様を設定。「別天神(ことあまつかみ)」がその典型。これ、要は「別格で尊い天神」という意味なので。
そういった位置づけの違いはありますが、いずれも「神世七代」というカテゴリを使用しているのは共通しているのです。
②『日本書紀』純男神→男女神、『古事記』独神→双神、という1→2という展開は同じ
『日本書紀』版天地開闢では、まず「純男神」が単独で誕生。次いで「男女神」がペアで誕生。1→2です。
『古事記』版天地開闢も同様で、言葉は違いますが、まず「独神」が独りで誕生。次いで「双神」がペアで誕生。やはり1→2ですね。
単独神の誕生からペア神の誕生へ。これが同じなのは、最終的に、イザナギ・イザナミによる国生み、神生みへ繋げていく必要があるからです。
つまり、男女のペアは必ず誕生させないといけないんですね。
で、男女ペアをいきなり誕生させるわけではなく、まず単独で誕生する神を設定したわけですね。
ということで、
まとめます。
| 相違点 | ①目的、狙い ②天地のつくられ方 ③誕生する神様 |
| 共通点 | ①「神世七代」という尊い神様カテゴリ、枠組み ②『日本書紀』純男神→男女神、『古事記』独神→双神、という1→2という展開 |
要は、
『日本書紀』は、天地開闢に始まる神々の誕生を、陰陽や易といった原理的思想をもとに物語っていて、特に、本伝以外にも多くの異伝を併載、列挙して、神話を多面的・多角的に伝えようとしているところがポイント。
それに対して、
『古事記』は異伝など存在せず、あっても本文を説明するための「注」にすぎません。本文は終始一貫して統一的な世界を構築しています。書紀のようにああだこうだと言わない分、洗練された「物語」として完成度も高い。
ということで、以下、『日本書紀』『古事記』の伝える天地開闢伝承をそれぞれご紹介します。
『日本書紀』が伝える天地開闢

『日本書紀』版天地開闢。
テーマは、、
「天地開闢と神世七代」
はじめて世界がうまれ、天と地がひらかれます。その時に最も尊い神様カテゴリである「神世七代」が誕生する。この流れを是非チェック。
本エントリでは、本伝を中心にお伝えします。一書についてはリンクを設置しておきますので、より詳しくはリンク先でチェックされてください。
まずは、天地開闢の大きな流れを確認。要所要所のポイントを確認されてください。
『日本書紀』巻第一 第一段 本伝
テーマは、「天地開闢と三柱の神の化生」。
神話的には、あらゆる事物に先立つ「混沌」からスタート。その中から、まず天が形成され、そのあと、地が成り立ち、そのあと、天と地の間に三柱の神=純粋な男の神が生まれると伝えます。
昔むかし、天と地はまだ分れず、陰と陽も分れていなかった。その様は混沌として、まるで鶏の卵のようであり、ほの暗くぼんやりとして、事象が芽生えようとする兆しを内に含んでいた。
その中で、清く明るいものが薄くたなびいて天となり、重く濁ったものがよどみ滞って地となった。その清妙なるものは集まりやすく、重く濁ったものは凝り固まりにくい。これは原理に則った現象であり、だから、まず天ができあがり、その後で地が定まったのだ。
こうして天と地が成り立った後に、天地の中に神が生まれた。
だから、具体的にいえばこういうことになる。天と地ができる初めには、のちに洲(国)となる土壌が浮かび漂う様は、まるで水に遊ぶ魚が水面にぷかぷか浮いているようなものだった。
まさにその時、天地の中に一つの物が生まれたのだ。それは萌え出づる葦の芽のような形であった。そして、変化して神と成った。この神を「国常立尊」と言う。次に「国狭槌尊」。さらに「豊斟渟尊」。あわせて三柱の神である。天の道は、単独で変化する。だからこの純男、つまり男女対ではない「純粋な男神」となったのだ。
古、天地未剖、陰陽不分。渾沌如鶏子、溟涬而含牙。及其清陽者、薄靡而為天、重濁者、淹滞而為地、精妙之合搏易、重濁之凝竭難。故、天先成而地後定。然後、神聖生其中焉。故曰、開闢之初、洲壞浮漂。譬猶游魚之浮水上也。于時、天地之中生一物。状如葦牙。便化為神。号国常立尊。次国狭槌尊。次豊斟渟尊。凡三神矣。乾道独化。所以、成此純男。 (『日本書紀』巻第一 第一段 本伝より抜粋)
ということで、
ポイント2つ。
- 世界の形成や神の誕生には「原理」がある!
- 当時の、東アジアの最先端宇宙論に基づきながら、新しく独自の言葉や世界観を創造してる!
1つ目。
次!
②当時の、東アジアの最先端宇宙論に基づきながら、新しく独自の言葉や世界観を創造
さらにさらに、『日本書紀』編纂チーム。当時の精鋭集団、スーパーエリートの皆さんは、実は、東アジアの最先端知識、宇宙理論をもとに、単に真似で終わるのではなく、日本独自に組み合わせ、工夫し、新しく生み出しているんです。
物語の展開自体もそうですが、天地開闢でいえば、神の誕生方法、純男神がその典型です。
神の誕生方法で言えば、
「まさにその時、天地の中に一つの物が生まれたのだ。それは萌え出づる葦の芽のような形であった。そして、変化して神と成った。」とあるように、つまり、、
神は、完全な形では生まれない
ってこと。神は、まず物として、葦の芽のような形をして生まれる。それが神に化す。コレ、すごくない??
化すというのは、運動です。
「化=化ける」「生=生まれる、なる」。つまり、元の姿を変えて別の姿になる、別の姿として生まれる、という事。
物があった。それは葦の芽のような形であった、それが、神様の形に変わったんです。これがまさに、超絶ジャパーン的!な概念、考え方。まじ奥ゆかしすぎ。
西洋をはじめ、外国の神様は、最初から「ある」「(完全体として)存在する」ものとして描かれることが多く、これとは対照的。日本の神様は、最初から完璧な状態で生まれるのではなく、「化す」という運動のなかで、そのプロセスを通じて神になる。コレ、「化ける」的な感じで、形を変え、姿を現すイメージ。非常に重要なポイントなのでしっかりチェック。
他にも、
「純男神」も同様で。「純男」というのは、日本独自の言葉。
これも易の思想、「乾道成男」という考えにもとづき、「乾道」(天の道)だけによって成る神のこと。「男」じたいの「乾道」との、本質的な、不可分の繋がりを強調する神代紀の独創的な表現であります。
要は、陰陽の結合によらず、陽=天の道のみで男神が生まれたことを言ってる訳です。
コレ、易から借りてきて組み合わせている日本オリジナルワード。
宇宙論の最先端知識 × 易の知識 = 純男
ということで、陰陽の概念を導入しつつも、独自に創造したジャパーン的なるもの。こちらも是非チェック。
ということで、まとめます。
- 世界の形成や神の誕生には「原理」がある!
- 当時の、東アジアの最先端宇宙論に基づきながら、新しく独自の言葉や世界観を創造してる!
コレが、天地開闢の基本形、一番最初の場面の最重要ポイントであります。
詳細はコチラで!
なお、『日本書紀』第一段については異伝が全部で6つあります。この詳細はコチラで↓
●必読→「『日本書紀』巻第一(神代上)第一段 一書第1~6 体系性を持つ一書群が本伝をもとに展開」
●必読→「『日本書紀』の「一書」とは?『日本書紀』本伝と一書の読み解き方法を徹底解説!」
『日本書紀』巻第一 第二段 本伝
続けて、天地開闢の第二段階。
テーマは、「男女耦生の八神」
「耦生」とは、一緒に生まれること。ペアで生まれること。
前段の第一段では、「純粋な男の神様」が誕生するだけでしたが、今回、第二段ではここから展開して「男女ペアの神様」が登場。コレ、神話的に初、ニュージェネレーション。この大転換発生スポットが第二段ということで、大きなうねりを感じながら読み進めてください
次に現れた神は、泥土煑尊※1、沙土煑尊※2。次に現れた神は、大戸之道尊※3、大苫辺尊※4。次に現れた神は、面足尊・惶根尊※5。次に現れた神は、伊奘諾尊・伊奘冉尊。
次有神。泥土煑尊・沙土煑尊。次有神。大戸之道尊・大苫辺尊。次有神。面足尊・惶根尊。次有神。伊奘諾尊・伊奘冉尊。 (『日本書紀』巻第一 第二段〔本伝〕より一部抜粋。亦曰以下の神名は省略)
ということで、
ポイント2つ。
- 初めて、男女神が誕生する
- 神の名前にストーリーらしきものがある
1つめ。
次!
②神の名前にストーリーらしきものがある!
誕生する男女ペアの神神には、どうやらストーリーらしきものが存在します。それが
土台→家→互いに賛美→誘い合う
という「結婚の物語」。「進化の物語」とも言える。これが神名に付与されてるようなんです。
最初に、「泥土」と「沙土」を名に組み込んだ「泥土煑尊、沙土煑尊」が、まず土壌の出現を表象。
このあと、「大戸之道尊、大苫辺尊」。自然の土壌をかたどる表象から、人文の建造物、工作物をかたどる表象に転じます。要はお家を建てたわけです。
そして、「面足尊・惶根尊」。こちらは、「おもだる(りっぱなお顔ね)」、「あやかしこね(かわいいね)」、と、たがいに称えあう関係にある訳です。盛り上がってきました。
そして最後の、「伊奘諾尊・伊奘冉尊」。これは、「いざなふ」の語をもとに成りたつ神名とみるのが通例。要はベッドインへ向けて誘いあってるということです。
「土台→戸(家)→互いに賛美→誘い合う」結婚ストーリー。
すごいよくできた神話、、、((((;゚Д゚))))ガクブル
第四段でいよいよ国生みが登場する訳で、その前段として神名を通じて結婚ストーリーを表現したという訳ですね。ココも激しく重要なのでしっかりチェック。
まとめます。
- 純男神→男女ペア神への転換。初めて、男女神が誕生する!
- 神の名前にストーリーらしきものがある!土台→家→互いに賛美→誘い合うという結婚ストーリー!
その他、詳細はコチラで!
なお、『日本書紀』巻第一 第二段については異伝が全部で2つあります。この詳細はコチラで。
●必読→「『日本書紀』巻第一(神代上)第二段 一書第1,2 親が子を生みなすニュージェネレーション登場」
『日本書紀』巻第一(神代上)第三段 本伝
続けて、第三段はまさに、第一段、第二段の内容を踏まえた締めくくり、総括。
テーマは、「神世七代」。
分かりやすく
- 第一段:三世代(=三神)。純男神
- 第二段:四世代。男女で一対の神様が四世代、合計8神。
- 第三段:解説部分。3(純男神)+4(男女神)=7代(神世七代)
といった流れ。
「神世七代」。コレ、とっても尊い神様ジェネレーション、神様カテゴリです。コチラ!
合わせて八柱の神である。これは陰の道と陽の道が入り混じって現れた。それゆえ男と女の性となったのである。そして、国常立尊から、伊奘諾尊・伊奘冉尊に至るまでを、神世七代と言う。
凡八神矣。乾坤之道、相参而化。所以、成此男女。自国常立尊、迄伊奘諾尊・伊奘冉尊、是謂神世七代者矣。 (『日本書紀』巻第一 第三段 本伝より一部抜粋)
ということで、
ポイント2つ。
- 「純男」三神を三代、「男女」八神を四代と算出、全部で「神世七代」としてカテゴリ化
- 「神世七代」というカテゴリそのものが「尊卑先後の序」にもとづく
まず1つめ。
①「純男」三神を三代、「男女」八神を四代と算出、全部で「神世七代」としてカテゴリ化
要は、3+4=7の計算式。世代=ジェネレーション、という概念で理解OK
天地開闢の原初に誕生した、最も尊い神が、三世代。
次いで誕生した男女ペア四組(ペア2×4組=計8神)の神が、四世代。
で、3+4=計7世代を、「神世七代」として位置づけます。
天地開闢、世界創世という原初に誕生した、非常に尊い神様ジェネレーション、神様カテゴリ。その全体を括る数字として奇数の7(=陽数)が設定されてます。
非常に合理的に、ロジックガチガチで構成されてる感を堪能あれ。
次!
③「神世七代」というカテゴリそのものが「尊卑先後の序」にもとづく
わざわざ一段まるごと使用して「神世七代」という神様カテゴリを解説する第三段。
そこには、この世界の始まりの時代を、それ以降とは区別して「理想の世(聖代)」とする歴史観があります。
この概念をベースに、
- まずは、「神世七代」という神ジェネを、それ以降の神々、世代と区別
- そして、「神世七代」の中でも、純男三代と男女四代を区別

区別=尊と卑の別、優と劣の別
ってことで、ココにある根本の概念が「尊卑先後の序」。
「尊卑先後の序」は、日本神話を貫く超重要な原理原則。
やわらかく言うと、物事には優先順位があるよ、ということ。
この根底概念をもとに歴史観、神話世界が構成されてる、と、まーデカい仕掛けが存在しているのです。
まとめます。
- 「純男」三神を三代、「男女」八神を四代と算出、全部で「神世七代」としてカテゴリ化
- 「神世七代」というカテゴリそのものが「尊卑先後の序」にもとづく
その他、詳細解説はコチラで!
そして、『日本書紀』巻第一 第三段については異伝が1つあります。この詳細はコチラで。
●必読→「『日本書紀』巻第一(神代上)第三段 一書第1 新しい時代へ向けた準備」
と、いうことで、
以上が『日本書紀』版天地開闢の流れ。
全部まとめると以下の通り。
- 世界の形成や神の誕生には「原理」がある!
- 当時の、東アジアの最先端宇宙論に基づきながら、新しく独自の言葉や世界観を創造してる!
- 純男神→男女ペア神への転換。初めて、男女神が誕生する!
- 神の名前にストーリーらしきものがある!土台→家→互いに賛美→誘い合うという結婚ストーリー!
- 「純男」三神を三代、「男女」八神を四代と算出、全部で「神世七代」としてカテゴリ化
- 「神世七代」というカテゴリそのものが「尊卑先後の序」にもとづく
ということで、、、
かなり壮大な仕掛け、設定があって、理論をもとに天地開闢を伝えてることがご理解いただけたかと思います。このロジックガチガチ感は、やはり日本の国としての歴史書、という位置づけが関係してます。
目線は外。諸外国に向けて日本という国のスゴさを示す、この目的があるからこそ、漢籍の最先端知識を駆使、創意工夫によってジャパンオリジナルの神話を創り上げているのです。この創意工夫のスゴさ、すばらしさを是非。

『古事記』が伝える天地開闢
つづけて、『古事記』が伝える「天地開闢」。
天地の初発から次々に神が誕生し、神世七代まで続く『古事記』版「天地創生神話」。
天に5柱の「別天つ神」、地には7代の神々の出現を、神名を連ねる手法で物語っています。どちらかというと、『古事記』は神々の誕生と、その尊貴さを示すことに注力してる。
異伝なども存在せず、あっても本文を説明するための「注」にすぎません。本文は終始一貫して統一的な世界を構築。書紀のようにああだこうだと言わない分、洗練された「物語」として完成度も高いと言えます。
『古事記』上巻「天地開闢」別天神五柱~神世七代
天地が初めて發った時に、高天原に成った神の名は、天之御中主神。次に、高御産巣日神。次に、神産巣日神。この三柱の神は、みな独神と成りまして、身を隠した。
次に、国が稚く浮いている脂のように海月なすただよえる時に、葦牙のように萌え騰る物に因って成った神の名は、宇摩志阿斯訶備比古遅神。次に、天之常立神。この二柱の神も、みな独神と成りまして、身を隠した。
上の件の五柱の神は、別天神である。
次に、成った神の名は、国之常立神。次に、豊雲野神。この二柱の神も、独神と成りまして、身を隱した。
次に、成った神の名は、宇比地邇神。次に、妹 須比智邇神。次に、角杙神。次に、妹 活杙神(二柱)。次に、意富斗能地神。次に妹 大斗乃辨神。次に、於母陀流神。次に、妹 阿夜訶志古泥神。次に、伊耶那岐神。次に、妹 伊耶那美神。
上の件の、国之常立神より下、伊耶那美神より前を、あわせて神世七代という。上の二柱の独神は、おのおのも一代という。次に双へる十柱の神は、おのおのも二柱の神を合わせて一代という。
※「妹」は女性の意味。なので「妹」の接頭語がついていない神名が男性神ということになります。
天地初發之時、於高天原成神名、天之御中主神。次高御產巢日神、次神產巢日神。此三柱神者、並獨神成坐而、隱身也。次、國稚如浮脂而久羅下那州多陀用幣流之時、如葦牙、因萌騰之物而成神名、宇摩志阿斯訶備比古遲神、次天之常立神。此二柱神亦、獨神成坐而、隱身也。上件五柱神者、別天神。次成神名、國之常立神、次豐雲上野神。此二柱神亦、獨神成坐而、隱身也。次成神名、宇比地邇上神、次妹須比智邇去神、次角杙神、次妹活杙神二柱、次意富斗能地神、次妹大斗乃辨神、次於母陀流神、次妹阿夜上訶志古泥神、次伊耶那岐神、次妹伊耶那美神。上件、自國之常立神以下伊耶那美神以前、幷稱神世七代。上二柱獨神、各云一代。次雙十神、各合二神云一代也。 (『古事記』上巻より一部抜粋)
ということで、
『日本書紀』ではあんなにあったのに、『古事記』では以上。終了。
『古事記』版天地開闢のポイントは3つ。
- 『古事記』は、天と地が誕生するところから始まってる。
- 『古事記』は、高天原という至高の場がすでに用意されている。
- 『古事記』は、造化三神とよばれる神が誕生している。
ということで、
『日本書紀』とは違って、天地形成プロセスなんてものはなく、最初から高天原があって、造化三神がいて、、という形。つまり、神々の誕生と、その尊貴さを示すことに注力してる、ってこと。
と、ココで、誕生する神々を整理してみる。

と、、まースゴイ。
「造化三神」「別天神」「独神」「神世七代」についてはコチラで解説しています。
●必読→「造化三神|天と地ができたその原初の時に、高天原に成りました三柱の神神。」
●必読→「別天神(ことあまつかみ)|神世七代に先立って特別に誕生した5柱の神々。」
●必読→「独神(ひとりがみ)|単独で誕生し、男女の対偶神「双神」と対応する神。」
個別神々の意味合いは以下の通りです。
造化三神&別天つ神
●必読→「天之御中主神|高天の原の神聖な中央に位置する主君。天地初発の時に高天の原に化成した最初の神」
●必読→「高御産巣日神|2番目に化成した独神で別天つ神。「産霊」ならびに「産日」の霊能を発動。」
●必読→「神産巣日神|3番目に高天の原に化成した独神。生命体の蘇生復活を掌る至上神。」
別天つ神
●必読→「宇摩志阿斯訶備比古遅神|葦芽のように勢いよく芽生え伸びてゆくものを依代として化成した独神」
●必読→「天之常立神|国土浮漂のとき、葦芽に依って化成した独神」
神世七代
●第1世代→ 国之常立神:国が恒常的に(永久に)立ち続ける神
●第2世代→ 豊雲野神:豊かな、雲の覆う野の神
●第3世代(男→ 宇比地邇神:最初の泥土の神
●第3世代(女→ 妹 須比智邇神:砂と泥土の神
●第4世代(男→ 角杙神:角状の棒杙の神
●第4世代(女→ 妹 活杙神:活きいきとした棒杙の神
●第5世代(男→ 意富斗能地神:偉大な戸の男神
●第5世代(女→ 妹 大斗乃辨神:偉大な戸の女神
●第6世代(男→ 於母陀流神:顔つきが整って美しいと称える神
●第6世代(女→ 妹 阿夜訶志古泥神:まあ何と恐れ多いことよと畏まる神
●第7世代(男→ 伊耶那岐神:いざなう男の神
●第7世代(女→ 妹 伊耶那美神:いざなう女の神
改めて、
『古事記』としては、世界が、天地が、どう誕生したかなんて問題ではなく、それよりも神々の誕生と、その尊貴さを示すことに注力してる。
特に、『古事記』は「神世七代」以上に尊い神様を設定。「造化三神」や「別天神」がその典型。これ、要は「別格で尊い天神」という意味です。『日本書紀』を意識した設定であり、神々の系譜や上下関係的なものを打ち出そうとしているからです。
一方、「神世七代」については、『日本書紀』と同様、神名にストーリーらしきものがある。
『古事記』の場合は、表象しているのは、神の世に、世界が次々に形づくられ展開するさまであり、以下のような物語展開。
- 先ずは、国(国土)が恒久的に(永久に)確立することを予祝
- その国(国土)に、豊穣を約束する「雲のわき立つ野」が出現することを予祝
- そのうえで、双神により具体的な表れとして、大地の土台ができ、そこに標識となる杙を打ち込み、戸を造立する
- そして、その中で結婚に向け、男女の神により、互いに全き性を具有することを称えあい、誘い合う、、
、、、
ステキですね。ゾクゾクします。
日本的な、極めて日本的な、世界創生の物語。
特に大きいのは、伊耶那岐&伊耶那美の誕生です。
この2柱の神が誕生する前は、国や野が誕生したり、土台とか杙とか、表象内容は外観・外見にとどまっているのですが、
伊耶那岐&伊耶那美の登場によって、男と女が互いに誘い合い、心を交わせ、お互いの存在を認め合うようになります。
これは、つまり、男女が一体化しようと声を掛け合っているという事。
ポイントはまさにここで。
要は、
日本神話的天地開闢は「最終的に収斂していく事」にあります。
一体のものとして収れんするのです。
国→野→土台→男と女の誕生、そして一体化。
男と女という、本来的にあい異なる性が、異なればこそ互いに誘いあって一体化しようとする本質的・根源的なありようを表象している。
こんな世界創生を描いているところが他にあるのでしょうか。
神の世の最後に、男女が互いに誘いあう本来的なあり方を表象する神が出現したことにより、神世七代という世界も完成をみる、とも言えて。
だからこそ、そのあとに、いよいよ具体的な国や神々が誕生していく流れが出来上がる訳ですね。
神世七代、その位置づけを全体の文脈から見るととても奥ゆかしい内容になっていることが分かります。ココの部分、是非チェック。
その他、詳細はコチラで↓
天地開闢まとめ
天地開闢
日本神話が伝える世界の始まり、いかがでしたでしょうか?
日本神話版天地開闢の特徴は、一言で言うと「多様で豊かな世界のはじまり」ということ。
天地開闢を知ろうとするとき、まずは、この「多様で豊かな世界が広がってる」というところから入る必要あり。
前提で「多様さ」を認識しておかないと、迷ってしまいますし、もうやだー!ってなりますよね。
注意点は、「どれが本当の伝承なのか?」「どれを信じればいいのか?」という問いはNG。
そもそも目的が違います。編者は「正しい神話を伝えよう」なんて思ってません。編者が伝えようとしているのは、「多様で豊かな神話伝承を持つ日本のスゴさ」です。コレ、編纂当時の歴史や背景も踏まえて是非チェックください。
天地開闢を入口として、より深く、日本神話の世界へお越しいただければと思います。スゴイぞー
『日本書紀』『古事記』、どちらの天地開闢から入っても良し!
天地開闢を知るには神を知れ!!
「造化三神」「別天神」「独神」「神世七代」についてはコチラで解説中!
●必読→「造化三神|天地初発に高天原に成りました3柱の神々」
●必読→「別天神|神世七代に先立って特別に誕生した5柱の神々」
●必読→「独神|単独で誕生し身を隠す神々」
造化三神&別天つ神
●必読→「天之御中主神|高天原の中央に位置する主たる神」
●必読→「高御産巣日神|2番目に高天原に成りました独神」
●必読→「神産巣日神|3番目に高天原に成りました独神」
別天つ神
●必読→「宇摩志阿斯訶備比古遅神|立派な、萌え出る葦の芽の男神」
●必読→「天之常立神|国土浮漂のとき、葦芽に依って化成した独神」
神世七代
●第1世代→ 国之常立神:国が恒常的に(永久に)立ち続ける神
●第2世代→ 豊雲野神:豊かな、雲の覆う野の神
●第3世代(男→ 宇比地邇神:最初の泥土の神
●第3世代(女→ 妹 須比智邇神:砂と泥土の神
●第4世代(男→ 角杙神:角状の棒杙の神
●第4世代(女→ 妹 活杙神:活きいきとした棒杙の神
●第5世代(男→ 意富斗能地神:偉大な戸の男神
●第5世代(女→ 妹 大斗乃辨神:偉大な戸の女神
●第6世代(男→ 於母陀流神:顔つきが整って美しいと称える神
●第6世代(女→ 妹 阿夜訶志古泥神:まあ何と恐れ多いことよと畏まる神
●第7世代(男→ 伊耶那岐神:いざなう男の神
●第7世代(女→ 妹 伊耶那美神:いざなう女の神
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
[itemlink post_id=”13035″] [itemlink post_id=”13037″] [itemlink post_id=”13038″] [itemlink post_id=”13039″]
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




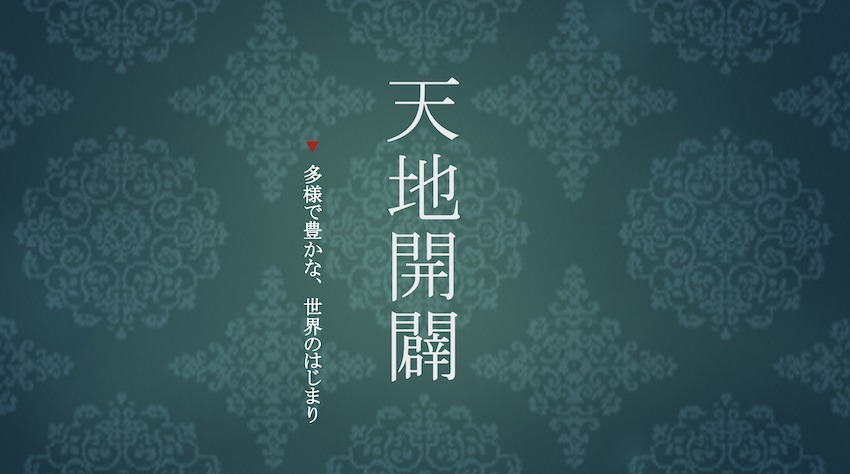


















①世界の形成や神の誕生には「原理」がある!
本文の、「だから、まず天ができあがり、その後で地が定まったのだ。」とか、「天と地が成り立った後に、天地の中に神が生まれた。」とか!「天の道は、単独で変化する。だからこの純男、つまり男女対ではない「純粋な男神」となったのだ。」とか!! がソレ。やけに説明くさいですよね。
この説明臭さの「臭いの元」は、、「易」×「この世界を成り立たせる原理」。
まず「易」でいうと、、
というように、実は、日本神話世界では、易にもとづく二項対立が設定されてるんです。
さらに、
「この世界を成り立たせる原理」とは、先後、尊卑などの順番、順序のこと。
つまり、乾坤であれば、乾が先、坤が後。陽陰であれば、陽が先、陰が後。天地であれば、天が先、地が後。というような順番、順序のことです。
この「易」×「この世界を成り立たせる原理」が臭いの元となり、やけに鼻につく説明臭さを出してる訳です。
日本神話的天地開闢を理解しようとするとき、この概念、考え方を理解しておく必要があるんです!全ては原理に基づくのだ!!