多彩で豊かな日本神話の世界へようこそ!
正史『日本書紀』をもとに、
最新の学術成果も取り入れながら、どこよりも分かりやすい解説をお届けします。
今回は、
『日本書紀』巻第一(神代上)第五段、一書の第11
テーマは
「天照大神の高天原統治と農業開始」
伊奘諾尊による三子への分治により、高天原統治を命じられた天照大神がいよいよ活動開始。
構成は、第五段〔一書6〕を踏襲しつつ大きく差違化。次の、第六段以降へ繋げる伝承として位置付けられてます。
今回も、概要で全体像をつかみ、ポイント把握してから本文へ。最後に、解説をお届けしてまとめ。
現代の私たちにも多くの学びをもらえる内容。日本神話から学ぶ。日本の神髄がここにあります。それでは行ってみましょう!
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
『日本書紀』巻第一(神代上)第五段〔一書11〕天照大神の天上統治と農業開始
目次
『日本書紀』巻第一(神代上)第五段〔一書11〕の位置づけ
前回、『日本書紀』巻第一(神代上)第五段〔一書10〕からの続き。
下図、赤枠部分。第五段〔一書11〕。

上図を見てのとおり、
第五段は、『日本書紀』神代の中で、最も異伝が多い段。こんな伝承もある、あんな伝承もある、と計11パターン。
『日本書紀』最大の特徴である、一書の存在。本伝と一書の関係についてはコチラ↓をチェック。
- 本伝の内容をもとに多角的、多面的に展開する異伝、それが一書。
- 本伝があっての一書であり、一書あっての本伝というように、お互いにつながり合って、関連し合って、踏まえ合って、多様で豊かな日本神話世界を構築している。
で、
それもそのはず。第五段は超重要テーマが目白押し。
特に、天下之主者生み、三貴子の誕生と分治、そして生と死の断絶など。今後の日本神話展開の起点となる設定がたくさん埋め込まれてる。
神ならではのワザ(神業)連発、神ならではの極端な振れ幅、基本的に意味不明。でも、ご安心を。当サイトならではの分かりやすいガイドがあれば迷うことはございません!
ということでコチラ

全11もある異伝も、大別すれば2通り。整理しながら読み進めるのが〇。
- 本伝踏襲 差違化型・・・〔一書1~5〕
- 書6踏襲 差違化型・・・〔一書6~11〕
※踏襲・・・踏まえるってこと。前段の内容、枠組みを。
※差違化・・・(踏まえながら)変えていくこと、違いを生んでいくこと。神話に新たな展開をもたらし、多彩で豊かな世界観を創出する。
で、今回お届けするのは、〔一書6〕踏襲差違化型の〔一書11〕。
〔一書11〕の展開を通して、
主人公が、伊奘諾尊から「天照大神」へ移り替わると共に、場も、地上世界から「高天原」へ転換していく。。
このダイナミズムを楽しむのが○!

『日本書紀』巻第一(神代上)第五段〔一書11〕の概要とポイント
〔一書11〕は、第五段〔一書6〕を踏襲しつつ、大きく差違化。次の、「第六段以降へ繋げるための伝承」としても位置付けられてます。
ポイント4つ。
①ついに主役交代!物語の展開ステージも、地から天へ大きく転換!
第五段〔一書11〕は、第一段から続く「誕生の物語」最終章。
〔一書11〕を通して、
物語のメインプレイヤーは伊奘諾尊から天照大神へ。また、メインステージも地上(葦原中国)から高天原へ大きく転換します。
| これまで | 〔一書11〕 | これから | |
| 主役 | 伊奘諾尊 | 伊奘諾尊→天照大神 | 天照大神 |
| 舞台 | 地上 | 地上→高天原 | 高天原 |
主役の天照は、そもそもは、第五段本伝で「日神」として誕生。「天照大神」としては〔一書6〕。それを承けての〔一書11〕。
日本神話の主役。メインプレーヤー。大役ですから、誰でもいいって訳じゃない!
もっと言うと、至高の世代「神世七代」の伊奘諾尊の存在の大きさ、果たした役割の大きさを引き継げる神は、相当スペシャルな要素を持ってないと無理。
主役交代は、実は念入りに準備される必要があって。
で、実は、準備されていたんです。後ほど解説。その上で、メインステージを一気に高天原へとぶち上げる!壮大な「神話ステージ」の転換!!
次!
②天照大神による高天原の統治スタート!まずは勅命を出して地上偵察!
伊奘諾尊による勅任により、高天原を統治することになった天照大神。その最初のお仕事が、月夜見尊を地上世界(葦原中国)に派遣して、食の神「保食神」の様子を探らせること。
コレ、もちろん、天照的には「食の確保」が念頭にあり。この辺りの優先順位付けも流石。天照は分かってる。
天子は人民の腹を満たしてこそ天子足りうる。
重要なのは、この月夜見尊派遣の時に「月夜見尊受勅降。」と、「勅」という漢字使われてるってこと。
天照大神が勅を出した。それはつまり、天照大神が「高天原の統治者」になってるって事とイコールなんです。
勅は、誰でも出せるわけではありません。統治者、それは、地上であれば天皇が、高天原であれば天照が出せる絶対命令だから。「勅」から読み取る高天原統治の確立。これも、しっかりチェック。
次!
③牛馬のほか、五穀・繭などの農産物が化生!喜んだ天照大神が意味を与える!
食の神「保食神」なんですが、、いろいろやらかしてしまい、月夜見に殺されてしまう、、ですが!食の神としての本領発揮?なんと!保食神の屍体に、牛馬のほか、五穀や繭といった農産物が化生!!!
五穀キタ━(゚∀゚)━!
流石!腐っても国神!いや、死んでも国神!五穀を生むなんて!ナイスです!
で、これを天熊人が採取して天照大神に奉る。すると、大いに喜んだ天照大神、「これは人民が食べて活きるためのものであるぞ〜」と、
五穀を「食物」として指定。
これ、超重要事項。天照大神が人民の食物として五穀を、特に稲を指定した訳なので。
保食神の屍体に発生した色々な物たち。実は、この時点ではその辺の雑草と同じレベルだった訳です。天熊人だって、よー分からんもんが生えてたから、とりあえず持って帰った。で、天照大神がそれを見て、「コレは食べ物だよ」と指定した。ココで初めて、それに意味や価値が生まれた訳です。
つまり、今、私たちがこうしてご飯を食べられるのもココで天照大神が指定してくれたから、ってことで。なんてありがたい話なんだ。。。
次!
④高天原と葦原中国はつながってる!天照大神が農を介してつながりをつけた深〜い意味
人民の食べ物として指定、意味づけしたのち、早速、高天原で稲作・農業を開始する天照。で、この農業開始は、第五段〔一書11〕の隠れたテーマである、
高天原と葦原中国の二つの世界が一体であることを示す
という意味を持ってます。天照大神が農を介して、そのつながりをつけたところがポイント。
コレまで、国生みや神生み、その舞台は大八洲国でした。地上世界だった訳で。ところが、ここ〔一書11〕で、月夜見尊降下の勅命、さらに、地上で発生した五穀を天上に持ち帰り農業開始、と言ったエピソードを通じて、天照大神の統治のもとに高天原と葦原中国を一元的に組み込んだんです!
高天原と葦原中国の二つの世界は、繋がってるよと。しかも、二つの世界は天照大神の統治のもとで実は一体であるという壮大な世界観。
これをもとに、次の第六段以降の展開や神話の礎地が築かれた、という事で。激しく重要事項であります。
まとめます。
- ついに主役交代!物語の展開ステージも、地から天へと大きく転換!
- 天照大神による高天原の統治スタート!まずは勅命を出して地上偵察!
- 牛馬のほか、五穀・繭などの農産物が化生!喜んだ天照大神が意味を与える!
- 天上と地上はつながってる!天照大神が農を介してつながりをつけた深〜い意味
以上4点。しっかりチェックした上で、本文をどうぞ!
『日本書紀』巻第一(神代上)第五段〔一書11〕の本文と現代語訳
『日本書紀』国立国会図書館デジタルコレクションより慶長4(1599)刊版 ある書はこう伝えている。伊奘諾尊は三子に勅任し「天照大神は高天原を治めよ。月夜見尊は日と並んで天を治めよ。素戔嗚尊は海原を治めよ」と言った。
こうしてすでに天照大神は天上にあり、「葦原中国に保食神がいると聞く。月夜見尊よ、そこに行き様子をうかがってきなさい」と言った。
月夜見尊が勅命を受けて降り、保食神のもとに到ると、保食神はさっそく首を巡めぐらし、国に向かえば口から飯を出し、また海に向かえば大小さまざまな魚を口から出し、また山に向かえば大小さまざま獣を口から出した。それらの品物をことごとく備え、たくさんの机に積み上げて饗応した。この時、月夜見尊は怒り顔を真っ赤にして「穢らわしい、卑しいことだ。どうして口から吐いた物でもって私をもてなすことできるのか」と言い、たちまち剣を抜いて打ち殺した。
そうして後に復命して詳しくこの事を報告した。この時、天照大神は激怒し「お前は悪い神だ。もはや顔も見たくない」と言い、月夜見尊とは日と夜とを隔てて住んだ。
この後に、天照大神はまた天熊人を遣わし見に行かせた。この時、保食神はすでに死んでいた。しかし、その神の頭には牛馬と化し、額に粟が生え、眉に繭が生え、眼に稗が生え、腹に稲が生え、陰には麦と大豆・小豆が生えてあった。天熊人はそれを全て取って持ち去り、天照大神に奉った。
時に天照大神は喜び、「この物は、この世に生を営む人民が食べて活きるべきものである。」と言って、粟・稗・麦・豆を陸田(畑)の種とし、稲を水田の種とした。またこれにより天邑君(村長)を定めた。そこでその稲の種を天狭田と長田に植えることを始めた。その秋には、垂れた稲穂が握り拳八つにたわむほど茂り、たいへん爽快であった。また、口の中に繭を含み糸を抽き出すことができた。これにより養蚕の道ができたのである。
保食神、ここでは「うけもちのかみ」と言う。顕見蒼生、ここでは「うつしきあをひとくさ」と言う。
一書曰。伊奘諾尊勅任三子曰。天照大神者、可以御高天之原也。月夜見尊者可以配日而知天事也。素戔鳴尊者可以御滄海之原也。
既而天照大神在於天上曰。聞葦原中国有保食神。宜爾月夜見尊、就候之。月夜見尊受勅而降。已到于保食神許。保食神乃廻首、嚮国。則自口出飯。又嚮海則鰭広・鰭狭亦自口出。又嚮山。則毛麁毛柔亦自口出。夫品物悉備。貯之百机而饗之。是時月夜見尊忿然作色曰。穢哉。鄙矣。寧可以口吐之物、敢養我乎。廼抜剣撃殺。然後復命。具言其事。時天照大神怒甚之曰。汝是悪神。不須相見。乃与月夜見尊、一日一夜隔離而住。
是後天照大神、復遣天熊人往看之。是時、保食神実已死矣。唯有其神之頂、化為牛馬。顱上生粟。眉上生繭。眼中生稗。腹中生稲。陰生麦及大豆・小豆。天熊人悉取持去而奉進之。于時天照大神喜之曰。是物者則顕見蒼生可食而活之也。乃以粟・稗・麦・豆為陸田種子。以稲為水田種子。又因定天邑君。即以其稲種、始殖于天狭田及長田。其秋垂穎八握莫莫然。甚快也。又口裏含繭。便得抽糸。自此始有養蚕之道焉。
保食神。此云宇気母知能加微。顕見蒼生。此云宇都志枳阿鳥比等久佐。 (『日本書紀』巻第一(神代上)第五段〔一書11〕より)
『日本書紀』巻第一(神代上)第五段〔一書11〕の解説
第五段の最後の異伝、〔一書11〕いかがでしたでしょうか?
神話全体の流れの中で、第五段〔一書11〕は
- 「誕生をめぐる神話」を締め括る伝承として位置づけられ、
- 第五段までの世界から第六段以降へ繋げる「ブリッジ(橋渡し)」的な役目があります。
大きなテーマは、
- 神話展開の原動力が「原理(道の働き)」から「情動(人間モデル神)」へ転換、
- さらに、世界秩序やルールも「尊卑先後の序」から「天照大神を中心とした秩序」へ転換する!
てことで。
天地開闢(第一段)から第五段までは、「道の働き」が神話展開の原動力となってました。世界の組成、神の化成は「道の働き」によるものだと。そして、神々の行動や事象には「尊卑先後の序」が関わり、それによって神々も動かされていた。。。
それが、〔一書6〕で革命的に誕生した「人間モデル神」と、めっちゃ人間的な、情動を契機とする行動により、原理を外れた多様な展開が生まれるようになりました。そして最終、ココ、第五段〔一書11〕からは、オレたちの天照大神を中心とした秩序へと移行する。。
この、大きな時代の転換が〔一書11〕を読み解く核心であります。
〔一書11〕は2部構成、
- 天照大神の高天原統治
- 天照大神による農業開始
前半と後半に分けて解説していきます。

前半: 天照大神の高天原統治
続いて後半へ!

後半:天照大神による農業の開始
- この後に、天照大神はまた天熊人を遣わし見に行かせた。
- 是後天照大神、復遣天熊人往看之。
→神を代えて、再度派遣の巻。
天照大神としては、これで終わるわけにはいきません。再度、天熊人を使として派遣、様子を見に行かせます。きっとスゲーゴツイ感じだった?熊人。
次!
- この時、保食神はすでに死んでいた。しかし、その神の頭には牛馬と化し、額に粟が生え、眉に繭が生え、眼に稗が生え、腹に稲が生え、陰には麦と大豆・小豆が生えてあった。
- 是時、保食神実已死矣。唯有其神之頂、化為牛馬。顱上生粟。眉上生繭。眼中生稗。腹中生稲。陰生麦及大豆・小豆。
→保食神の本領発揮?
なんと!保食神の屍体に、牛馬のほか、五穀や繭といった農産物が化生!!!
牛馬キタ━(゚∀゚)━!
これで田んぼ、耕せるよ!
五穀キタ━(゚∀゚)━!
これでみんな飢えずにすむよ!
流石!腐っても国神!いや、死んでも国神!農業セットを化成してくれるなんて、ナイスだぜ!
でもちょっと待って。この時点では、「五穀」と言っても何も意味を持ってない!この後で、天照大神による意味づけがあってこそなんで!今は、単に、そういう植物的なものが生じてましたレベルでチェック。
次!
- 天熊人はそれを全て取って持ち去り、天照大神に奉った。
- 天熊人悉取持去而奉進之。
→持って帰って奉る。使者としての基本です。
「悉」という文字が使われてます。全て、残さず、悉くかっさらってきた絵。牛とか馬とか持つの大変だったんじゃないか??そうか、だからゴツイ熊人か!
次!
- このとき天照大神は喜び、「この物は、この世に生を営む人民が食べて活きるべきものである。」と言って、粟・稗・麦・豆を陸田(畑)の種とし、稲を水田の種とした。またこれにより天邑君を定めた。
- 于時天照大神喜之曰。是物者則顕見蒼生可食而活之也。乃以粟・稗・麦・豆為陸田種子。以稲為水田種子。又因定天邑君。
→天熊人が持ち帰ったものを見て、大いに喜ぶ天照大神。
ポイント3つ。
①「顕見蒼生」は、この世界に生きるたくさんの人々・民衆・人間。だけど、もっと深い意味がある
詳しくはコチラ↓で。
ポイントは、
- 「顕見」を冠することで、(神幽の世界の対比として)この現世に生きる存在であることを明示する(だから食を必要とする)
- 「蒼生」として、 天下の隅々に生きる全人民を強調する
ってことで、考え抜かれた言葉のチョイスになってるんです。
天照大神が自らの本質を「日神」とする以上、葦原中国(顕見)の「蒼生」すべてを対象とすることは当然で。
天照大神を統治者として、その統治対象が葦原中国の民衆であることを、恩恵の意味と合わせて「顕見蒼生」に込めた、ということなんです。深い、、深すぎるぞ日本神話。。
そして!
②食物としての五穀を指定。これによって食べられるものになった
先程も少し触れましたが、保食神の屍体に発生した色々な物たち。実は、この時点ではその辺の雑草と同じレベルだった訳です。天熊人だって、よー分からんもんが生えてきたから、取り敢えず持って帰った。
天照大神がそれを見て、コレは食べ物だよ、と指定して初めて、それに意味や価値が生まれた訳です。
最後!
③管理体制も構築。統治者主導により高天原で農業が開始された
「粟・稗・麦・豆を陸田(畑)の種とし、稲を水田の種とした。またこれにより天邑君を定めた。(原文:以粟・稗・麦・豆為陸田種子。以稲為水田種子。又因定天邑君。)」とあります。
整理としては以下
| 陸田 | 粟・稗・麦・豆 |
| 水田 | 稲 |
なんだけど、もっと大事なのは、
「天邑君」と呼ばれる田畑を管理する村長さん的な存在を定め、管理運営体制も構築した、ってこと。
これ、超重要事項。意味としては、統治者主導により高天原で農業が開始された。ってことで、、これにより、ゆくゆくは地上である「葦原中国」で農業が始まり、たわわに稔った稲が穫れる豊かな国への道筋がつけられた、ということになるんです。
この意味、価値を全身に感じていただきたい!
次!
- そこでその稲の種を天狭田と長田に植えることを始めた。その秋には、垂れた稲穂が握り拳八つにたわむほど茂り、たいへん爽快であった。
- 即以其稲種始殖于天狭田及長田。其秋垂穎八握莫莫然。甚快也。
→管理運営体制が整ったので業としての稲作開始!!
言葉の解説を少し。
「天狭田及長田」は、狭い田んぼと長い田んぼのことで、いろんな田んぼという意味。網羅的全面的な意。
「垂穎」は、垂れた稲穂。穎=穂。
「莫莫然」は、稲穂が茂ってしなやかな状態。「莫莫」は茂ること。
ポイント2つ。
① 天子の超重要なお仕事。民に先駆けて率先垂範。親耕・親蚕の伝統あり。
「その稲の種を天狭田と長田に植えることを始めた(原文:以其稲種始殖于天狭田及長田)」とあります。これ、主語は文脈からして天照大神。つまり、天照大神が自ら稲の種を田んぼに植えた、ということであります。
コレ、非常に重要なポイントで。
背景には、天子の模範である親耕・親蚕の伝統があります。率先垂範の姿。(親耕・親蚕の「親」というのは、親から、自ら行う、という意味。)
『礼記』(月令第六)の、次の一節はかなり有名な例。
この月(初春)や、天子乃ち元日を以って、穀を上帝に祈る。 乃ち元辰を擇びて、天子親ら耒耜を載せ、これを參保介の御の閒に措き、三公・九卿・諸侯・大夫を帥い、躬ら帝藉を耕す。 ー中略ー 善く丘・陵・阪・險・原・隰、土地の宜しき所、五穀の殖する所を相て、以って民を教道す。
是月(孟春)也、天子乃以 元日 祈 穀于上帝 。乃択 元辰 、天子親載 耒耜 、措 之于参保介之御間 、帥 三公・九卿・諸侯・大夫 、躬耕 帝籍 。(中略)善相 丘陵阪険原濕、土地所 宜、五穀所 殖、以教 導民 。 (『礼記』(月令第六)より一部抜粋)
ポイントは、「天子親ら耒耜を載せ、(中略)躬ら帝藉を耕す。」の箇所。
コレ、つまり、初春の月に、
天子が人民に率先して親ら耕す儀式を行ってた
ってこと。これを、
親耕
といいます。古代における理想の天子像。これはつまり、
天下に、農耕のはじまりを告げる。つまり、時を告げる儀式
だってことで、激しく重要。
2点。
- 民に先駆けて自ら田んぼを耕す=率先垂範する理想の天子像であること
- 農耕の始まりを告げる=時を告げる=時間を司る=天子の専権事項であること
率先垂範。まさに理想の上司像、いや、天子像。自ら率先して行うことで民に教示する。民はその姿を見てついていく。超重要概念です。
さらに、この先んじて行うことで、春の到来を告げる役割を担ってるってこと。大きく言うと、それは時を告げるということで。天子にだけできて、一般ピープルに唯一できないこと。
それが、時を司る、時を握るということです。
日本では、その象徴が改元。つまり、天皇が代わるごと、または、天皇が思い立つごと、改元が行われる。これができるのは天皇しかおりません。
これもまた、超重要事項ですのでしっかりチェック。
以上2点、まずは理想の天子像ということで、土台となる概念としてチェックです。
そして!
② 私たちがお腹いっぱいご飯をいただけるのは、天照大神が高天原にて農業への道筋をつけていただいたからこそ。その最初のとっかかりがこの場面。
日本神話的に、稲の位置付けは非常に重要で、稲の行方を追いかけることで、神話の大筋が掴める、と言っても過言ではないくらい、超重要。大きくは、
① 『日本書紀』第四段〔一書1〕で、天神により「豊葦原千五百秋瑞穂之地」と予祝されるところから。コレ、日本の美称として。
全11文字熟語の長~い言葉ですが、、
- 「葦原」には稲が生育。つまり、豊かな葦原=豊かな稲がみのる場所。
- 「千五百」とは稲の収穫がめちゃめちゃたくさん、そんな秋。秋=1年の収穫の時でもあるので、千五百とかけて、めっちゃ長い間、年という意味も。
- 「瑞穂」はみずみずしい稲穂、みずみずしく豊かな、という意味。
まとめると、豊かな葦の茂る広大な原でめっちゃ大量になんなら永遠に豊かな稲穂が収穫できるみずみずしくすばらしい地、の意味。つまり、天神によって予祝された土台があって。
② その上で、第五段で伊奘諾尊・伊奘冉尊により、国生み、神生み、万物生みがなされ、そこで誕生したと思われる食物神。
③ 月夜見尊による想定外の惨殺はありつつも、その屍体から生えた穀物が天上にもたらされる。
④ 天上で、統治者・天照大神の主導により、農業が開始される。中でも、稲作は絶好調。豊作。
⑤ これを持って、第九段〔一書2〕の天孫降臨の時に、天照大神が「斎庭の穂(聖なる田んぼで育った稲穂)」を授ける。皇孫がそれを持って葦原中国に降臨する。稲がもたらされる。
⑥ さらに、第九段〔一書3〕では、占いによって定めた特別な田んぼ(卜定田)を、「狭名田」と名付け、そこで収穫した稲を天甜酒に醸して嘗し、また渟浪田の稲を飯に炊いて嘗として催した。。。要は、新嘗のお祭りが催されていることを伝えます。
⑦ そして、、神武東征神話の最後には、東征を果たした神武天皇が、国見をするシーンがあり、ココで、「国状」をはるかに望みみて「蜻蛉が交尾している形のようだ」(原文:猶如蜻蛉之臀呫焉)と伝えます。
「蜻蛉」=トンボであり、トンボと言えば、水田に飛んでいる秋の実りを象徴する虫ですよね。
トンボが交尾して飛ぶ=たくさんのトンボが連なり飛ぶ=豊かな稲の実りがあるという意味で、ココにも「稲」を通じた豊かな日本を称える、あるいは予祝する思想がある訳です。
以上、①~⑦までまとめると、
神代で天神が予祝した「豊葦原千五百秋瑞穂之地」は、天照大神による農業開始、天孫降臨により地上へもたらされ、神武天皇の東征と建国によって「秋津洲」として結実した。とも言えて、
壮大な神話展開の中に、稲が誕生し地上で豊かに実るようになった物語が組み込まれていること、稲に寄せた古代日本人の格別な想いを、その信仰をチェックです。
今、私たちがお腹いっぱいにご飯をいただけるのは、天照大神が高天原にて農業への道筋をつけていただいたからこそなんですね。
次!
- また、口の中に繭を含み糸を抽き出すことができた。これにより養蚕の道ができたのである。
- 又口裏含繭。便得抽糸。自此始有養蚕之道焉。
→先程の、天子の「親耕」に対する「親蚕」という枠組みでチェック。
天子の「親耕」に対して、皇后は「親蚕」。つまり、蚕を飼うこと。蚕(幼虫)の繭から糸をつむいで機織りをすることがお仕事とされてます。
これ、現在も宮中で行われてますよね。毎年、地味にニュースになってます。
衣食住のうち、「衣」と「食」については特別な思想があることをしっかりチェック。
どうやら古代の人にとっては「住」はそれほど大きな問題ではなかったようで。。。ま、住めればどこでもいい?
最後に。
第五段〔一書11〕の隠れたテーマについて解説。
ココ、〔一書11〕を通じて伝えたかったこと。それは、
高天原と葦原中国の二つの世界が、実は一体である!
ってこと。
天照大神が農を介して、そのつながりをつけたところがポイント。
コレまで、国生みや神生み、その舞台は大八洲国でした。地上世界だった訳です。
ところが、ここ〔一書11〕で、月夜見尊降下の勅命、さらに、地上で発生した五穀を天上に持ち帰り農業開始、と言ったエピソードを通じて、天照大神の統治のもとに高天原と葦原中国を一元的に組み込まれることとなりました。
高天原と葦原中国の二つの世界は、実は繋がってるよ、と。だからこそ、行き来ができるわけで。しかも、二つの世界は天照大神の統治のもとで、実は一体であるという壮大な世界観。
これを元に、次の第六段以降に展開する礎地がここで築かれ、例えば第七段、天照大神の天石窟幽居で、天照大神が閉じこもると葦原中国も真っ暗になる、というところに繋がっていくのです。
天照大神が農を介して二つの世界がつながってるということ、一体であることを示した。ここ、激しくチェックされてください。
〔一書11〕で登場した神々
伊奘諾尊、天照大神、月夜見尊、素戔嗚尊、保食神、天熊人
まとめ
『日本書紀』巻第一(神代上)第五段、一書の第11
だーっと解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
- 天照大神の高天原統治
- 天照大神による農業開始
の2部構成で展開。伊奘諾尊による勅任を根拠として高天原統治を確立し、その最初のお仕事として、五穀の意味づけと農業開始。つまり、人民にとって最も重要な「食」の確保を、成果としたわけです。
また、〔一書11〕の表側のストーリーとは別にチェックしておきたいのは3つ。
- 伊奘諾尊から天照大神への主役交代
- 葦原中国から高天原への舞台転換
- 高天原と葦原中国の二つの世界は繋がってる。しかも、二つの世界は天照大神の統治のもとで、実は一体であるという壮大な世界観。
この意味をしっかり確認されてください。
また、神話全体の流れの中で、第五段〔一書11〕は前半を締め括る伝承として位置づけられ、第五段までの世界から、第六段以降へ繋げる「ブリッジ(橋渡し)」的な役目があります。
その主な内容は、
- 神話展開の原動力が「原理(道の働き)」から「情動(人間モデル神)」へ転換、
- さらに、世界秩序やルールも「尊卑先後の序」から「天照大神を中心とした秩序」へ転換する!
てことで。
世界を動かすルールが変わった
ってことでもあって。まさに革命。この、大きな時代の転換を、全身に感じていただきたい!それが〔一書11〕を読み解く核心であります。
ほんと、、古代日本人の叡智、構想力がほんとスゴイ。そして、それを物語として落とし込む力というか、実現力も超絶であります。現代の私たちにも多くの学びになるかと思います。
ということで、次回はいよいよ第六段に突入!お楽しみに!!
神話を持って旅に出よう!
本エントリに関連するおススメスポットはコチラです!
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




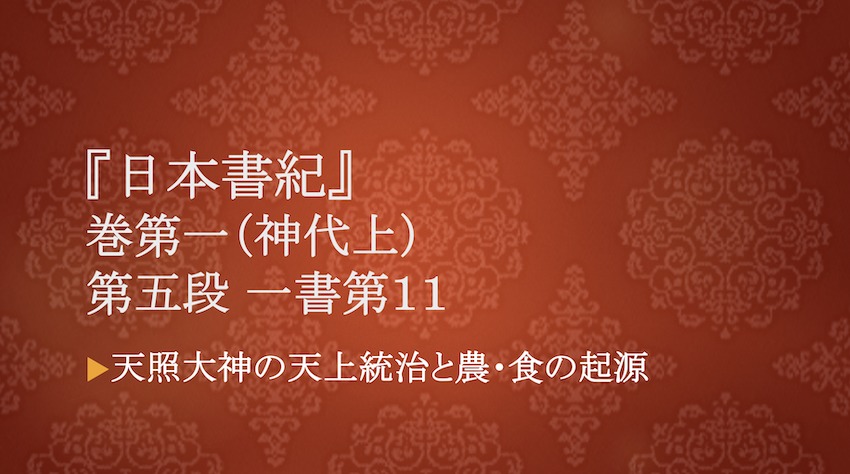






















→伊奘諾尊による三子への勅任。これ〔一書6〕を踏襲。
言葉の解説を少し。
「治めよ」の「御」。「彳」と「午」を組み合わせた会意文字で、もともとは「馬を操り、車を動かす人」の意。それが、後に「治める」「司る」といった意味に。ここでは「統治する、治める」の意で、天照大神と素戔鳴尊に対して使われてます。
「治めよ」の「知」。こちらは、統治者が物事の道理(あるいは国の状況)を「知る」ことが国を「治める」ことにつながる、という古代の統治理念が背景に。月夜見尊に対しては「知」が使われてます。
同じ「治める」という意味の「御」と「知」ですが、使い分けがされてる訳で。これは、天照との対比においての使い分けと考えられて。つまり、天あるいは高天原の統治者はやはり天照だから。メインの統治者は「御」、サブとまでは言わないがメインでないので「知」。
その上で、ポイント4つ。
① 統治領域は〔一書6〕からの差異化。日本神話的世界構造と合わせてチェック
元を辿ると、そもそもは第五段〔本伝〕の「天下之主者」を産もうぜ、からの着地・結論部分。
その上で、、
統治領域設定は以下。
まず、〔一書11〕では、
の、二項対立で世界が構成されてます。いずれも「原」という高貴な漢字を使用。
これは〔一書6〕で設定されていた
という3つの領域から、天と海の2つを切り出してる(差異化)。
「天下」が無くなっているのは、「天下之主者」として任命した素戔嗚尊が職務放棄&反抗、からの、放逐された経緯があるから。神話的には、天下の統治者は、天孫降臨までは空席のまま置いておく必要があって、。なぜなら、天照系の統治者に引き継がせたいから。
なので、ココでは「天下」は脇に置いといて、「天」と「海」が統治領域として設定されてるんす。
海を目の前にした時、そこに広がるのは、天であり、海。そして、踏みしめる大地。
このあたり、古代の人々が目の前に広がる世界をどう捉えていたのか、ロマンをバシバシ感じるところですよね。追いかけていくとそれはそれでオモロー!な世界が見えてきます。
次!
②「高天原」の起源は天地開闢まで遡る、それくらい尊い場である
〔一書11〕からは、いよいよ高天原がメインステージに。でもちょっと待って、この「高天原」、そもそもどっから出てきた?ってことなんすが、改めて、その起源は天地開闢まで遡る訳です。
初めて登場したのは、第一段〔一書4〕。ココでは、異伝として、天地開闢の初めに誕生していた+天御中主尊はじめ高皇産霊尊が誕生した場として伝えてました。
原初に遡るくらい尊い場として位置付けられてる高天原。それがここで天照大神の統治領域となる。ある意味、日本神話的伏線回収のワザ。むしろ、この瞬間は最初から想定されていたとも考えられて。伏線回収の細かいあれこれはコチラ↓で
そしてそして!
③同じ天にある太陽と月。神話が持つ「起源譚としての役割」につながる内容。
〔一書11〕では、天照大神が「高天原」、月夜見尊が「配日而知天事」としています。一応、第五段本伝、日神、月神としての誕生からの最終的な着地として、。
「日と並んで天を治める(原文:配日而知天事)」とは、月が太陽と同じく天にあるってことの起源譚的内容。この時点では、太陽と月は並んでいたんですが、この後の展開で昼と夜を分けて暮らすようになっていきます。
最後!
④勅任は律令用語。めっちゃ重い絶対命令。コレにて伊奘諾尊のお役目終了。主役は天照大神へ引き継がれる
伊奘諾尊による勅任。「伊奘諾尊は、三子に勅任した(原文:伊奘諾尊勅任三子)」とあります。
改めて、この「勅任」という言葉、律令用語であり、めっちゃ重い言葉としてチェック。基本、天皇しか出さないもので、組織上の伝達ラインとは別に、直接、個人や組織に下される絶対命令であります。コレ来たら、全員起立!謹んでお受けし即実行の巻。
ここでのポイントは2つ。
① 天照大神の高天原統治の根拠としての意味
伊奘諾尊が天照大神に「勅命として」高天原統治を任じているんです。
な訳ですから、この意味、超絶重要です。
神世七代の最後の世代、国を生み、神を生み、万物を生み出した創生神たる伊奘諾尊が勅任により命じた体(体裁)にすることで誰からも文句が出ないようにしている。一子相伝北斗神拳!
② 神話展開における主役交代としての意味
「勅任」を通して、物語のメインプレイヤーは伊奘諾尊から天照大神へ大きく転換します。
主役の天照は、そもそもは、第五段本伝で「日神」として誕生。天照大神としては〔一書6〕。それを承けての〔一書11〕。
主役交代は、物語の展開を大きく左右する超重要事項。なので、ココで、伊奘諾尊から勅任を受ける形式にすることでそれを根拠づけ・権威づけてる訳ですね。
次!
→いよいよ高天原に坐す天照大神が活動開始!!!
漢字の解説を少し。
「候」は、「横から見た人」の象形と「まとをうかがい矢を放つ」象形から、人が「うかがう」ことを意味。会意兼形声文字。ここでは、「さぐる」、「のぞく」、「様子を見る」意。斥候の候。
ポイント4つ。
① 神話の舞台は天上(高天原)へ。大きな場面転換が発生!
「こうしてすでに天照大神は天上にあり(原文:既而天照大神在於天上)」とあります。
これ、サラッと流すの禁止。日本神話的にも2回くらいしか発生しない大きなステージ転換なんです。
地上から高天原へ。
国生みから神生みへ、、今まで地上な感じだったのが、ここからしばらく天上。これ、素戔嗚降下と大蛇退治を挟みつつも、基本的には天孫降臨まで続きます。
メインプレイヤー交代と合わせて発生してる壮大な舞台転換、ってことでチェック。
そして!
②天照活動開始!経緯としては、光源を生み出し、力を与えて、役割を付与する←今ココ
本件、天照大神の「神としての形成過程」みたいな話で、、ワタシ何様?というのはありつつ、、これ、因数分解すると、大きく2つの解(側面)があると言えます。
天照大神で言うと、お日様・太陽が持ってる「光り輝く性質」というのが「自然現象表象」。で、これを表したのが「日神」。第五段〔本伝〕で登場。
一方、天にあって世界を照らし、特に、動植物の生存・成長を支える恩恵としての太陽、その「役割機能表象」。これを体現しているのが「天照大神」です。〔一書6〕〔一書11〕で登場。
つまり、第五段〔本伝〕で、そもそもが「自然現象表象」の光り輝く存在「日神」として誕生したものの、これだけでは、ただ輝いているだけなので、私たち人民にとってどんな恩恵があるのかよー分からん。それを補完するために「役割機能表象」的存在が用意される。まずは、第一段階として、〔一書6〕で「天照大神」として誕生。〔一書6〕では、黄泉(死)の穢れを祓うプロセス=超絶コントラストを効かせることで、超絶な神威を根拠付け、その上で、ここ〔一書11〕で、いよいよ「役割機能表象」の実像が描かれることになる。。。それは、恩恵をもたらす関わり方、つまり、地上世界を照らし、植物の成長を促し、私たち人民の食を支える存在であります。
光源を生み出し、力を与えて、役割を付与する。
こうして見てくると、相当念入りに準備されてきたと言えて、、なんせ主役の交代ですから。この意味の大きさ、そして神話としての構想力に震えが止まりません。。
そしてそして!
③天照大神の最初のお仕事は「食の確保」。天子がまず行うべき模範を示している
主役交代、みんなが固唾を飲んで見守ってる。。。何するの?どんなことやり始めるの??って、そんな中で、、、
「「葦原中国に保食神がいると聞く。月夜見尊よ、そこに行き様子をうかがってきなさい」と言った。(原文:聞葦原中国有保食神。宜爾月夜見尊、就候之)」とあります。つまり、天照の最初のお仕事が、食の神「保食神」の様子を探らせること。
コレ、天照的には食の確保が念頭にあり。この辺りの優先順位付けも流石。
天子は、人民の腹を満たしてこそ天子足りうる。
基本をしっかり実践。天照は分かってる。ってワタシ何様?というのはさておき、ここでは、天照大神の最初のお仕事は「食の確保」。それは、天子がまず行うべき模範を示しているってことでチェック。
最後!
④実体を伴う場=高天原ができたことで、その対比としての「葦原中国」という場ができ始めた
「葦原中国」について。実はココで初めて登場。天照大神が命名した言葉だったんすね。
とはいえ、これまでの経緯としては、第四段〔一書1〕の天神ミッションで「豊葦原千五百秋瑞穂之地」として前振り、概念としての提示はありました。
それを承けての「葦原中国」。
しかも、これは、これまで漠然とした天とか天上に、統治者が誕生し、実体を伴う場としての「高天原」ができたことが背景にあり。で、その対比として、同じく実体を伴う「葦原中国」ができ始めたと。天が固まれば地も固まる。
確かに、第四段や第五段を通じて国土ができて自然はじめ万物が生まれて人間も生まれてた。。だからこそ、いろんな国神も誕生していたと考えられて、保食神もその一環であります。
次!
→保食神、、、口から出すって、、ゲロで饗応??いや、まさか!!
ポイント3つ。
①「受勅」は、天照の高天原統治が確立している証として使われてる
「月夜見尊が勅命を受けて降り(原文:月夜見尊受勅而降)」とあり、「受勅」という言葉が使われてます。さらっと流すの禁止。コレ、超重要ワード。
つまり、天照大神が勅を出した、ってことで、これはつまり、天照大神が高天原の統治者になってるって事とイコールな訳です。
勅は、誰でも出せるわけではありません。統治者、それは、地上であれば天皇が出せる絶対命令。同様に、高天原であれば天照しか出せない絶対命令。
「勅」から読み取る高天原統治の確立。超重要事項としてチェックです。
次!
② 天神と国神の絶対的ヒエラルキー!エラい神が来たら下々の神はおもてなしで対応
降下する月夜見尊。保食神のところに至ると「保食神はさっそく〜 中略 饗応した(原文:保食神 〜 饗之)」とあります。
コレ、保食神が食の神だから食でもてなした、ってこと以上に、天神と国神の絶対的ヒエラルキーがあるから、ということでチェック。
エラい神様が天上から降りて来たわけですから、下々の、、国神としては当然、響宴をひらいて最高のおもてなしで対応すべき局面。国神(保食神)による天神(月夜見尊)へのおもてなし。これが神世界のヒエラルキー!
次!
③ 神様的おもてなし=地の幸、海の幸をとにかくたくさん取り揃える
神様的おもてなしの流儀。
「保食神はさっそく首を巡めぐらし、国に向かえば口から飯を出し、また海に向かえば大小さまざまな魚を口から出し、また山に向かえば大小さまざま獣を口から出した。(原文:保食神乃廻首、嚮国。則自口出飯。又嚮海則鰭広・鰭狭亦自口出。又嚮山。則毛麁毛柔亦自口出。)」とあります。
これ、実は、めっちゃロジカルに組まれてて。整理すると以下の通り。
まず、国。
コレは、領域・人民・主権の3要件が揃った「国家」ではなく、その前段的な「国」のイメージ。もちろん、ゆくゆくは統治者のもとで人民が生活する国になっていくことは想定されていて。だからこその、飯。つまり、ご飯。
次に、海。
鰭が広い魚、鰭が狭い魚、ということで、「大小さまざまな魚」という意味になります。神様的には魚は「鰭」で分類するのがいいみたいですぞ。
最後に、山。
毛が麁い動物、毛が柔らかい動物、ということで、「大小さまざまな動物」という意味に。こちらも、神様的には動物は「毛並み」が分類基準。。??
「それらの品物をことごとく備え、たくさんの机に積み上げて(原文:夫品物悉備。貯之百机而饗之。)」とあり、悉く&百個の机=数え切れないくらいたくさんの机に積み上げるのが、神様的おもてなしの流儀。
スゴイ光景です。ご飯、山の幸、海の幸が全て、悉く、果てが見えないくらいズラーっと並ぶ机に積み上げられてる、、、しかもそれ、全部口から出しました。。。
ちなみに、
保食神が口から出して食を用意した、というのは、実は重要な意味があって。2つ。
1つ目。
魚や鳥獣も飯と同じ「食」に当てるものだと示すねらい。口から吐き出すことによって、食用であることを、むしろ月夜見尊に演じてみせた。もちろん、それは天照大神の「勅」旨に応じるものでもあります。
2つ目。
地上世界の未成熟さを表象。
まだ葦原中国には「業」としての農業や漁業と言ったものが成立してないんです。てことは、文化的な営みとしての響宴もひらけるはずがなく。。仕方ないので、口から出してもてなした訳です。それはつまり、地上世界の未成熟さを表象していると言える訳です。
だからこそ、この後、天照大神が五穀を位置付け、農業を開始することに、とても大きな意味が出てくるようになる。ほんと、よく出来てる。素晴らしい神話構造です。
コチラも是非
次!
→口からゲロゲロ出す保食神も保食神だが、それにブチギレして殺す月夜見も月夜見だ、、、
先に漢字の解説を少し。
「忿然」は、激しく怒って心が落ち着かない様子。「憤然」とも書く。
「作色」は、色を作す=怒りのために顔が赤くなること。月夜見さん、かなりキレてます。。
先ほど解説したとおり、神世界には絶対的なヒエラルキーがございまして、、天神上、国神下。なので月夜見としては、口から出してもてなすなんて穢らわしいことをしてくる国神如きをブチ殺すのは当然の話で。これはこれでそういうもの。
一方で、構造論としては、こうした情動によって予想だにしない行動をとる人間モデル神によって神話に新たな展開が生まれてる、、てことであって。
むしろ解釈としては、保食神としては、口から吐き出すことで「食用」であることを月夜見尊に演じてみせた訳で。そうした保食神のはからいを、月夜見尊はまったく察知せず情動に任せてブチ殺した。そんな分かってない月夜見に今度は天照がブチギレをかまして昼と夜を分けるという展開へつながっていく。情動による想定外の展開をエンジンとする神話展開、とても良くできた構成であります。
次!
→天照大神に報告したら激オコされてエンガチョ、、、姉弟の仲やったんちゃうんかい??
ポイント2つ。
①「復命」は律令用語。「受勅」の義務として勅使が必ず行うべきもの。
勅を受けて使いをした結果、それは必ず報告する義務が発生します。コレ、律令世界の厳しい掟。だって、天皇が出した命令ですから。上司に報告するのは大事。
例えば、唐律では、「受勅出使」に付随して、使の「事訖、皆須返命奏聞」という結果報告の義務まで規定していたりします。この「返命」が、月夜見尊の「復命」に当たります。
『日本書紀』では他にも、、
と言った形で、「復命」の先は天皇もしくは朝廷。
つまり、月夜見尊が「復命」する先の天照大神を天上支配する神(地上で言う天皇)として位置づけている訳ですね。
これ、天照大神の高天原支配の確立、とも言えて。それは、新しい世界秩序・ルールが確立したってことでチェック。超重要。
そして!
② 太陽と月、昼と夜がある理由の明確化。神話の持つ起源譚的役割。
「月夜見尊とは日と夜とを隔てて住んだ(原文:乃与月夜見尊、一日一夜隔離而住。)」とあり、つまり、昼と夜に別れた起源譚として位置づけられてます。陽主導による陰との絶交、、、
日本神話は、やはり、太陽=天照大神を最高神として位置付けており、同じ天にありながら夜を照らす月はフィーチャーしてません。取扱い格差がスゴくて、、、
初めて、月夜見尊として活動したにも関わらず、天照の、統治者としての最初のお仕事(食の確保を念頭に置いた偵察業務)をぶち壊した神、、、そのままエンガチョ扱い。。
天には確かに2つの光源があるけれど、統治においては2つの頭(トップ)は要らないよ、統治者はあくまで天照だよ、と神話的に位置付けようとしてる。それは、農耕を主体とした国づくり、人民の、天子の食を支える中心は稲であり、その生育にはやはり、太陽の光が欠かせないわけで、そうした背景も感じられる神話構成だと思います。
以上、前半の部「天照大神の高天原統治」でした。