豊かで奥ゆかしい日本神話の世界へようこそ!
『日本書紀』をもとに、日本神話のディープなところを突っ込んで解説。最新の学術成果をもとに本格的神話講義。
今回は、
素戔嗚尊の「残忍さ」の違いから、根国追放処分の内実を探る
です。
日本神話の中でも割と有名なシーン。三貴神誕生と素戔嗚尊の追放。『日本書紀』神代上 第五段をもとにお届けします。
素戔嗚尊の残忍さの意味。根国へ追放処分になった理由をまとめて解説!
目次
素戔嗚尊の残忍さと追放処分。実は2パターンあって意味あいが違う
日本神話を代表する神キャラといえば、、、
素戔嗚尊
ですよね。昔も今も大人気の神様ですが。
ただ、、、この神様、実はその誕生からかなりの困ったちゃんでした。
勇ましく残忍。いつも哭いてばかり。この「哭き」、天地鳴動ビリビリと凄まじく、国内の多くの民が早死に、、、また、青々とした山を枯らしてしまう、、。
コレはヤバいということで、親から下された処分が
追放、、、
なかなか無いよ、コレ。日本神話史上初の追放処分。神話史に名を残したね。そんな素戔嗚尊であります。
その追放のされ方、実は、2パターンあって。
重要なのは、
追放の原因、根拠となった「残忍さ」の中身。
残忍さの中身が違う。
コレ、めちゃくちゃ大事で。
簡単に言うと、
ピュアかどうか、イノセンスかどうか
つまり、2パターンあるなかで
- 〔本伝〕の残忍さ:ピュア。生まれつきの神性としての凶暴性、無道
- 〔一書6〕の残忍さ:ピュアじゃない。自分の処遇に対する不平不満、不服従
といった「残忍さの中身」の違いがあるんす。
そんな中、今回特にピックアップしたいのが〔一書6〕のヒドい素戔嗚と追放処分。
まずは、2パターン確認。比較しながら違いをチェック。その上で、〔一書6〕の追放が他と違ってめちゃめちゃ重要な意味を持ってるって事、解説していきます。
『日本書紀』巻一第五段〔本伝〕:生まれつきの神性としての凶暴性、無道。ゆえに追放
まずは、第五段〔本伝〕の素戔嗚尊です。
経緯として、国生みからの神生みフェーズにあって、「天下之主者」を生もうとしてて、すでに日神、月神、蛭児を生んでる。そこからの続き。
次に素戔鳴尊を産んだ。(ある書には、神素戔鳴尊、速素戔鳴尊と言う。)この神は勇ましく残忍であった。そして、いつも哭くことをわざとしていた。このため、国内の多くの民を早死にさせ、また青々とした山を枯らしてしまった。それゆえ父母の二神は素戔嗚尊に勅して、「お前は、全く道に外れて乱暴だ。この世界に君臨してはならない。当然のこと、はるか遠く根国へ行かなければならない。」と命じ、遂に放逐したのである。
次生素戔嗚尊 【一書云 神素戔嗚尊 速素戔嗚尊】 此神 有勇悍以安忍 且常以哭泣爲行 故令國内人民 多以夭折 復使青山變枯 故其父母二神 勅素戔嗚尊 汝甚無道 不可以君臨宇宙 固当遠適之於根國矣 遂逐之
まず、物語に設定されてる大きな枠組みをチェック。
ココでのポイントは、
- 子の資質と、その資質に応じた処遇、という2軸で整理すること
こんな感じ。
| 尊卑 | 順番 | 誕生する神 | 性質 | 処遇 |
| 尊 | 先 | 日神、月神 | 光華明彩照徹於六合之内、其光彩亜日 | 天送 |
| 卑 | 後 | 蛭児、素戔嗚尊 | 雖已三歳脚猶不立、有勇悍以安忍 | 放棄、追放 |
と、
先に誕生した日神や月神と合わせて、こんなキレイに整理できるんすね。
- 「尊」を体現し、「先」に誕生する日神と月神
- 「卑」を体現し、「後」に誕生する蛭児と素戔嗚尊
ということで、
そもそも論として、
素戔嗚尊は「卑」を体現する存在として誕生してる。
ゆえに、「勇ましく残忍であった。そして、いつも哭くことをわざとしていた。このため、国内の多くの民を早死にさせ、また青々とした山を枯らしてしまった。」といった凶暴性や残忍さを発揮する訳です。
ここで重要なのは、
この凶暴性は神性によるもの、つまりピュアなもの
だということ。
「神性」とは、簡単に言うと神様のもともと持ってる性質とか性格、といった内容。
素戔嗚尊の神性である「凶暴性」や「残忍さ」は直ちに「悪」って事ではありません。それは、自然が時に、猛威を振るうことで人々に甚大な被害を与えるように、それ自体に罪はないし、悪でもない。そういうもの。「善悪」って価値判断だから、人間が勝手につけちゃうものですよね。神や自然はそんなの関係ないところにある。ってお話。
ココでのポイントが、
親の追放理由
素戔嗚の親である伊奘諾は「お前は、全く道に外れて乱暴だ。この世界に君臨してはならない。」と、つまり「無道」という言葉で追放根拠にしてるんです。
無道
道が無い。道理から外れてる、道理が無い、ということ。
だからと言って「悪」かどうかは別の話。よく考えたよね、、、この言葉。スゴいと思いませんか?
善悪の価値判断ではないところで、素戔嗚尊の凶暴性・残忍さをしっかり表現してます。
まとめます
第五段〔本伝〕の素戔嗚尊は、、、
- そもそも、「卑」を体現する存在として誕生した。
- ゆえに「勇ましく残忍であった。そして、いつも哭くことをわざとしていた。このため、国内の多くの民を早死にさせ、また青々とした山を枯らしてしまった。」といった凶暴性を発揮する。
- しかし、この凶暴性は神性によるもの、つまり生まれつきのものでありピュアなもの。
- なので、素戔嗚の親である伊奘諾は「無道」という言葉を使用して追放した。
ということで、まずはチェック。これが基本の素戔嗚尊です。
次!
『日本書紀』巻一第五段〔一書6〕:処遇への不満、不服従。寝返りゆえに追放
続いて、第五段〔一書6〕の素戔嗚尊。
経緯として、黄泉から還ってきた伊奘諾が、死の穢れを落とすために禊祓を行います@筑紫日向小戸橘之檍原が、そこからの続き。
そうして後に左の眼を洗った。これによって神を生んだ。名を天照大神と言う。また右の眼を洗った。これに因って神を生んだ。名を月読尊と言う。また鼻を洗った。これに因って神を生んだ。名を素戔嗚尊と言う。合わせて三柱の神である。
こういう次第で、伊奘諾尊は三柱の御子に命じて「天照大神は、高天原を治めよ。月読尊は、青海原の潮が幾重にも重なっているところを治めなさい。素戔嗚尊は天下を治めなさい。」と言った。
この時、素戔嗚尊はすでに年が長じていて、また握りこぶし八つもの長さもある鬚が生えていた。ところが、天下を治めようとせず、常に大声をあげて哭き怒り恨んでいた。そこで伊奘諾尊が「お前はどうしていつもそのように哭いているのだ。」と問うと、素戔嗚尊は「私は根国で母に従いたいのです。だから、哭いているだけなのです。」と答えた。伊奘諾尊は不快に思って「気のむくままに行ってしまえ。」と言って、そのまま追放した。
然後 洗左眼 因以生神 號曰天照大神 復洗右眼 因以生神 號曰月讀尊 復洗鼻 因以生神 號曰素戔嗚尊 凡三神矣 已而伊奘諾尊 勅任三子曰 天照大神者 可以治高天原也 月讀尊者 可以治滄海原潮 之八百重也 素戔嗚尊者 可以治天下也 是時素戔嗚尊 年已長矣 復生八握鬚髯 雖然不治天下 常以啼泣恚恨 故伊奘諾尊問之曰 汝何故恆啼如此耶 對曰 吾欲從母於根國 只爲泣耳 伊奘諾尊 惡之曰 可以任情行矣 乃逐之 (『日本書紀』第五段〔一書6〕より一部抜粋)
先の本伝と同様に、世界の分担統治について、枠組みをチェック。
ココでのポイントは、
- 子の資質は記載無し!なので「資質に応じた処遇」という整理ができない!
- 一方で、伊奘諾尊は「勅任」によって三子に命じている
要は、
資質に関する記述が無い=根拠が無いけど、勅任によって世界の分担統治を命じてる、って事。
先に「勅任」について言っておくと
令(巻第四)に「凡任官、大納言以上、左右大弁、八省卿、五衛府督、弾正尹、大宰帥勅任。」(選叙令第十二の3。日本思想大系『律令』269頁)とあり、
つまり、
国家の枢要な官職を任官するときに「勅任」という特別な言葉が使用される訳で、非常に重たい言葉。
ここで伊奘諾尊が「勅任」によって命じてるのは、
「本朝」の権威を前提とした、いわば国家意志の発動になぞらえる超重要命令として、ということ。
ところが、、、その勅任には根拠が無い、、
つまり、子の資質に関する記載が無い。。。。
無理やり表にするとこんな感じ。
| 尊卑 | 誕生する神 | 誕生方法 | 性質 | 処遇 |
| 尊 | 天照大神 | 洗左眼 | ? | 治高天原 |
| 月読尊 | 洗右眼 | ? | 治滄海原潮 之八百重 | |
| 卑 | 素戔嗚尊 | 洗鼻 | ? | 治天下 |
先ほどご紹介した、第五段〔本伝〕と比較してみ。
「子の資質」という根拠が無いので、「何故そういう処遇になったのか?」分かりませんよね。
なんとなく、、、左目から、、、先に、、、生まれた「天照大神」って、なんか輝いてる感じだから高天原をあてがった、、、???
っていうくらいしか言えない。てか、良く分からない。超重要任官命令なのに???
そう、
実は、、、
こういう曖昧な状態になっていることがポイント!
なんです。つまり、
資質に関する記述が無いということは、処遇の根拠が無いということ。
てことは、どんな立場からでも言えるってことですな!
これ、素戔嗚尊から見たらどうでしょうか?
理由あるいは根拠の明示もなく、世界の分担統治という重大任務を「勅任」によって振り分けるオヤジ。
ってなるよね。
強権発動オヤジの巻
一応、「尊卑先後之序」の枠組みを踏襲してる訳で、根拠を示さない、何も言わないってことは、そんならそれで、男であるオレ様「素戔嗚尊」が、たとえ「姉(第七段〔書三〕)」であろうとなんであろうと、女の「天照大神」より下位に立つなんてありえねー
しかも、
姉ちゃんは、天よりいっそう高い「高天」に対して、オレの任地は「天下」。
高さとか、尊さが全然違うけど。。。ちょ、ナニこの格差。。。?
しかも、この「天下」、はるか後でさえ統治がめっちゃ難しい「彼地(葦原中国)多有蛍火光神及蝿声邪神 。復有草木咸能言語 。」(第九段〔本伝〕)という有様。。。
この歴然たる差を、素戔嗚尊が容認するはずがないのです。
おかしい(怒)!
と。
ここにおいて、
父に冷遇された素戔嗚尊の心は
「恨」
キター!人間モデル神あるある。
●必読→:人間モデルの神による新たな展開|理から情による行動へ。これは日本神話的革命だ
だからこそ、「この時、素戔嗚尊はすでに年が長じていて、また握りこぶし八つもの長さもある鬚が生えていた。ところが、天下を治めようとせず、常に大声をあげて哭き怒り恨んでいた。」へつながる。
年が長じて=大人になっても、勅任された天下を治めず、いつも哭く、怒る、恨む、というブラック素戔嗚尊に変貌していくわけです。
コレ、先ほどご紹介した本伝パターンとは全然違う。神性とかではなく、素戔嗚的な「ちゃんとした理由」があっての凶暴性発揮、不服従。
人間モデルならではの「関係性」が前提になってる。
ちなみに、、、
国家意志の発動レベルの「超重要任官命令」である「勅任」に対して、従ってない(天下を治めようとしてない)訳ですから、、、この時点で組織論としてアウトです素戔嗚尊さん。
そんな中、
オヤジが追い打ちをかけるの巻。
そんな、理由あり絶賛反抗中の素戔嗚にオヤジが尋ねます。「なんでやねん」と。
いやいや、、、
素戔嗚尊からしてみたら、あほかオヤジ、と。
テメーの「勅任」のせいでこんなオレ様になってんのに、何言うとんねん、と。
いうことで、
素戔嗚尊の反応は、、、
オヤジに対する
強烈な「当てこすり」回答。
それが
「私は根国で母に従いたいのです。だから、哭いているだけなのです。」発言。
?
っと、ここで、ちょっとまて。
素戔嗚さん、アナタ「お母さん」っていらっしゃいましたっけ?
よーく思い出してくださいね。
そーなんです。ココ〔一書6〕で誕生した素戔嗚尊は、伊奘諾尊🚹の禊からでした。つまり、陽神単独による化出的誕生方法。つまり、、、
母不在。。。
お母さんいないのに、「母に従いたい、、、」って素戔嗚。
どっからどう解釈しても、当てこすり以外考えられませんよね。それはきっと第五段〔本伝〕を踏まえてのお話で。
ちなみに、ココ、学術世界でもフツーに間違いとか後代の付け足し説がまかり通ってます。
例えば、『全注釈』は「ここでスサノヲは母を慕って根の国へ行きたいと言っているが、これは黄泉の国(死者の世界)と根の国(現世の、生きている人の世界)を混同した杜撰な解釈で意味をなさない。さらに母(伊奘冉尊)に従って根の国に行きたい、というスサノヲの言葉は意味をなさない。彼は伊奘冉尊から生まれたのではない」と批判し、これらを「思い違い」さらには「後に付加されたもの」と断じてたりします。
でも、どうなんだろ? ま、それはさておき、
「私は根国で母に従いたいのです。だから、哭いているだけなのです。」
マザコン???
ココで重要なのは2つ。
- 生と死の対立構造を踏まえた「当てこすり発言」である
- 「従母」=「謀叛」。権威そのものを否定して寝返るという恐るべき重大犯罪である
てことで、ポイントまとめとく。
まず1つめ。
直前の黄泉往来譚で、生=伊奘諾尊、死=伊奘冉尊、という対立構図が提示されてました。さらに、生と死の断絶、死に対する生の優位、って事も確定。そんな中、ムスコが、お母ちゃんがイイって言うから、オヤジはブチ切れた。ざけんなと、そらそうだ、あんだけキョーレツな別れ方をしたわけで、なんであんなヤツ(伊奘冉のこと)の所がイイって言うんだと。イラつくぜと。だったら行っちまえ!
という流れ。まずはコレをしっかりチェック。
その意味で、黄泉の話の後に、何故こういう素戔嗚話が続くのか?っていうのは、まさに、この「母に従う」発言を導くためだった訳で。
スゴくない?この構想力。つながってくる、いろいろ。。。黄泉往来譚があるからこそ、母に従う発言が活きてくる。スゴい仕掛けです。古代日本人の構想力、創造性、素晴らしすぎる!
で、2つ目。
「従母」=「謀叛」。
コレ、該当する例が「唐律」という古代の法律条文にアリ。
唐から輸入された律(刑法)。その中に、凶悪犯罪について規定した「十悪」というのがあって、その第三に「謀叛」の罪状説明アリ。この罪状説明の注に「従偽」という言葉があるんす。コチラ。
第三に言うには、謀叛である。謀叛とは、国に背き偽に従うことである。
三曰謀叛。謂謀背国従偽 (唐律より引用)
ポイントは、「偽に従う(原文:従偽)」。
「偽」とは本朝とは別の政権の事。偽政権。敵国でもある。つまり、敵の国に従うってことで、要は「謀叛」の意味。
これ、権威そのものを否定して敵側に寝返るという恐るべき重大犯罪であって、、、
素戔嗚尊は、コレを踏まえて「従母」という言葉を使ってる、って事。母に従う。
これには、
- 父=伊奘諾尊=生=葦原中国・・・天照大神系
- 母=伊奘冉尊=死=黄泉国・・・素戔嗚尊系
といった設定、枠組みがあって。
母とは、伊奘冉尊であり、死であり、黄泉国であり。しかも、伊奘冉は、伊奘諾尊が統治する国の人民を毎日大量に殺すと宣告までしてる。
これは「本朝=葦原中国」に重大な脅威を与える敵対的な相手な訳で、素戔嗚よ、その伊奘冉尊=母に従うだと???
つまり、素戔嗚尊は謀叛を企てるのと同じレベルの発言をした、という事で。それが「従母」の意味の本質なんです。
- 置いておけないから追放(第五段本伝)
- 謀叛を企てたから追放(第五段一書6)
同じ追放でも、その内実や深刻度は全然違うんすね。
でもね、
ここが日本的というか、日本神話的というか、多様さを許容する価値観で。
実は、このあと、この「死を司る伊奘冉尊に連なる反逆者」としての素戔嗚尊が神話を大きく動かしていくことになるんです。
天照大神と皇孫による葦原中国統治、という本筋はありつつも、神話という物語を動かす原動力は素戔嗚尊。素戔嗚尊なくして日本神話は語れないくらいの大きな存在に。
つまり、単に謀叛人ですね追放ですね、終わりですね、以上。ってことではなく、メインプレイヤー神として活躍の場を与えてる。それを許容する広さと奥行きをもってるとも言える訳です。日本神話の豊かさは、実はこういうところにこそ、本質があるんじゃないかと思います。そして、そういう神話世界を創出した古代日本人の創造性、多様を許容する懐の大きさ、みたいなのがスゴイところなんですよね。
まとめ
素戔嗚尊の残忍性
根国へ追放処分になった理由をまとめて語ってまいりましたが、いかがだったでしょうか?
要は、
- 置いておけないから追放(第五段本伝)
- 謀叛を企てたから追放(第五段一書6)
ということで、同じ追放でも、その内実や深刻度は全然違うんすね。
日本神話的には、本伝の、神性としての無道性、残虐性からはストーリーとしてのオモシロい展開は生まれにくいんです。だって、神ってそういうもんだし、以上。みたいな感じで完結してしまう。
日本神話の豊かさ、おもしろさを生んでいるのは、やっぱり人間モデル神の素戔嗚尊であり。強権発動のオヤジに対する反抗や恨みがもとになるからドラマになる。
このあとの神話は、この〔一書6〕の素戔嗚尊と天照大神の関係を軸として展開していくようになる。
『日本書紀』編纂チームが必死に考え練り上げ創り上げた展開方法、その創意工夫度合いに改めてスゴい!という感嘆と敬意を送りたいと思います。日本ってスゴいよ、マジで。
ということで、本筋の神話解説シリーズへ戻りましょう。
参考文献
『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
[itemlink post_id=”13035″] [itemlink post_id=”13037″] [itemlink post_id=”13038″]



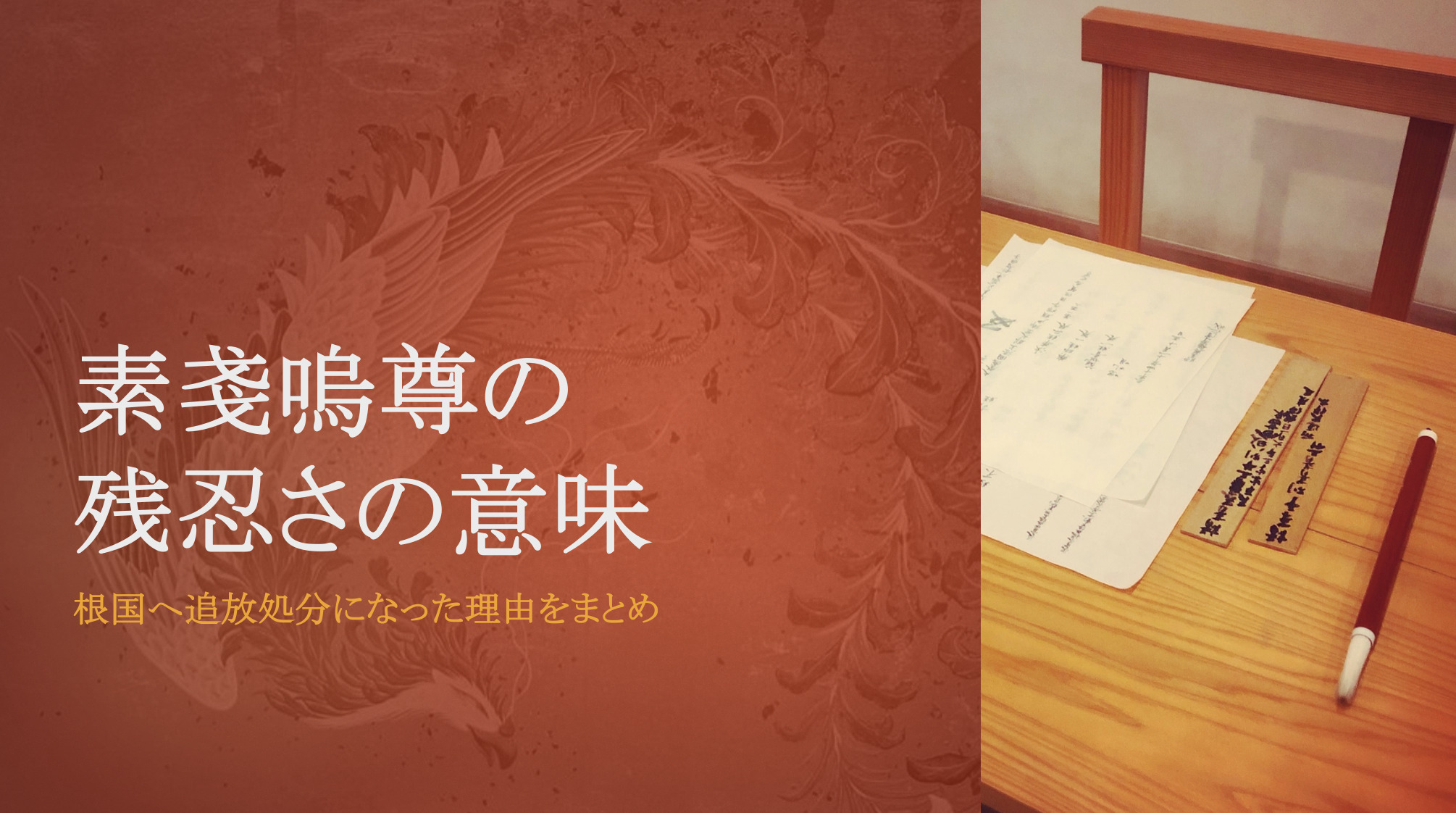







最後までお読みいただきありがとうございます。お気軽にコメントされてくださいませ。お待ちしております!