日本神話に登場する、重要ワード、重要エピソードをディープに掘り下げる「日本神話解説シリーズ」。
今回は、
陽神と陰神にみる日本神話的男女のあり方
陽神とは男の神様、陰神とは女の神様。正史『日本書紀』に登場する神の種類で、例えば、伊奘諾尊は陽神として、伊奘冉尊は陰神として位置づけられています。
今回は、「陽神と陰神」を通じて、神話世界における陰陽と男女形成の原理を探ります。
陽神と陰神にみる日本神話的男女のあり方|交じりあって化成するから、両方の性質を持ち合わせている
陽神と陰神:男女神化成の方法
まずは、陽神、陰神の誕生方法について現状認識。
コチラ、『日本書紀』神代上、巻一第三段〔本伝〕に伝えます。
陽の道と陰の道が互いに参じて化した。それゆえ男と女に成った。
乾坤之道、相参而化。所以、成此男女。(『日本書紀』巻一第三段より一部抜粋)
ということで。
ポイントは、「陽の道と陰の道が互いに参じて化した。」ということで、陰陽の道がお互いに参じて交じり合って化したことで男女の神が成るってこと。コレ、道本来がもつ運動としてチェック。
乾坤=陽の道と陰の道については、こちらも参考に。
さて、上記通り、
陽と陰の道がお互いに参じて交じり合って男女が化成した訳で、
これはつまり、
男も女も、それぞれ陰陽をあわせ持つってことです。その中で、陽が強く現れた方を陽神、つまり男と言い、逆に、陰が強く現れた方を陰神、つまりは女と言う、という次第。
神話世界における、男女の位置づけ、成り方の考え方はこんな感じで。
- 交じりあって化成するから、両方の性質を持ち合わせている。
- その中で特に強く現れた方が、男だったり女だったりする、というロジック。
この点をまずはチェック。
陽神と陰神:男女の結婚=陰陽の道の交わり
さて、そんなわけで、
神話世界において、男女神の結婚についても、この陰陽の道の交わり方がもとになります。立ち戻るイメージ。
陰陽の道の交わりによって男女が化成したと同じく、結婚すると、おのずから男女が生まれる。
ただ、
通常、出産自体は1子なので、男女のどちらか一方が誕生する。それでも、その誕生した男、または女は、陽だけ、陰だけの単純、純粋な性をもつものではありません。
要は、
両性を具有しながら、陽の強く現れた方が男、逆に陰の強く現れた方が女となる、ということです。
これは、最初に触れたとおり、互いに参じて交じり合うから両方の性質を持つ、ということがベースにあります。
伊奘諾尊と伊奘冉尊に代表される、陽神と陰神の結婚による神々の誕生にはこうした背景があるんですね。
近年、ジェンダー論が盛んになってますが、神話的に言わせると、男も女も、本来的に互いの性も兼ね備えているわけで、そもそも男女の性をそれぞれ一方だけから成り立つ固定的なものと見ることはできない、という話だったりします。
一方だけしかない、というのは、神話原理にもとる訳ですね。
男女はもともと交わりにおいて成り立つ。ゆえに、互いにもう一方の性とは親和的で、相互補完的なものです。
こうした考え方は、現代の男女の関係においても十分応用がきくとも言えそうです。
まとめ
陰と陽との道が交じり合って男女が化成=男も女も、それぞれ陰陽をあわせ持つ。
その中で、陽が強く現れた方を陽神、つまり男と言い、逆に、陰が強く現れた方を陰神、つまりは女と言う、というのが神話世界における、男女の位置づけ、作られ方。
これを基本に考えていくと、
男女はもともと交わりにおいて成り立つ=互いにもう一方の性とは親和的で、相互補完的なもの。
とも言えて。
こうした考え方は、現代の男女の関係においても十分応用がきくのではないでしょうか。
本エントリに関連する日本神話はコチラ!
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




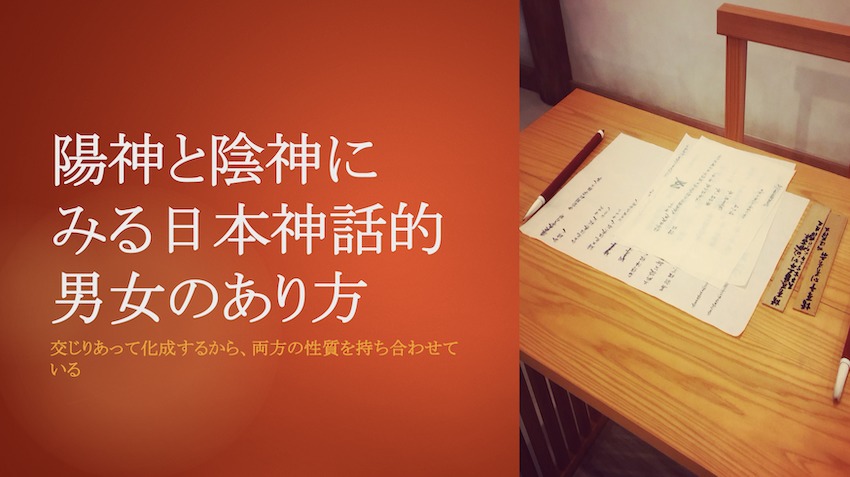














最後までお読みいただきありがとうございます。お気軽にコメントされてくださいませ。お待ちしております!