多彩で豊かな日本神話の世界へようこそ!
正史『日本書紀』をもとに、最新の文献学的学術成果も取り入れながら、どこよりも分かりやすい解説をお届けします。題して、おもしろ日本神話シリーズ。
今回は、『日本書紀』巻第一(神代上)第三段の本伝。
第一段から始まった開闢伝承の締め括り。内容的には「解説」に当たります。
概要で全体像をつかみ、ポイント把握してから本文へ。最後に、解説をお届けしてまとめ。
現代の私たちにも多くの学びをもらえる内容。日本神話から学ぶ。日本の神髄がここにあります。それでは行ってみましょう!
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
『日本書紀』巻第一(神代上)第三段 本伝 ~神世七代~
目次
『日本書紀』巻第一(神代上)第三段 本伝の位置づけ
前回、『日本書紀』巻第一(神代上)第二段の続き。
コレまでの経緯、登場する神様を把握してないと理解不能。なので先にコチラ↓をチェック。
で、
今回お届けするのは、下図、赤枠部分。

ポイントは、
神話全体の流れの中で読み解くこと。
詳細は今後順次解説、大きな流れ、枠組みは以下の通り。
| 大テーマ | 小テーマ | 内容 | 段 |
| 誕生の物語 | 道による化生 | 乾による純男神 | 第一段 |
| 乾と坤による男女対耦神 | 第二段 | ||
| 神世七代として一括化 | 第三段 | ||
| 男女の性の営みによる出産 | 国生み | 第四段 | |
| 神生み | 第五段 |
第一段から第五段までは、大きく「誕生」がテーマ。
この中で、第三段 は第一段、第二段の内容を踏まえた「締めくくり」「総括」。
乾と坤による神の化生ストーリーに区切りをつける位置づけになってます。
短く、あっという間に終わる神話ですが超重要テーマが存在するスポット。ポイントをしっかり押さえながら読み進めましょう。
『日本書紀』巻第一(神代上)第三段 本伝のポイント
天地開闢から、まず、「純男神」が三神誕生し(第一段)、さらに展開して「男女ペアの神様」が四組(計8神)誕生しました(第二段)。
第三段では、これらの神々を「神世七代」としてひとまとめ。非常に尊貴な神様ジェネレーション、神様カテゴリの誕生!
●必読→ 神世七代|天地開闢に次々と誕生した尊貴な神様カテゴリ。日本神話を伝える『日本書紀』『古事記』をもとに徹底解説します!
ポイント2つ。
①第二段で登場した男女ペア神は、実は「乾坤之道、相参而化」という「化生方法」だった
第三段は全体として、振り返り型カミングアウト。
第二段を振り返り、「実は、第二段の内容はこんなんでした~」という伝承になっとります。
神様の誕生の仕方について、神話的には「化生」という言葉ですが、
第三段で伝えてるのは、二段で誕生した男女ペア神は、乾と坤の道が、互いに参じて、集まって、混じり合って化生した、ってこと。
コレ、第一段の「乾道独化」による「純男神」とは別の誕生方法。革命的大事件。
詳細は後ほど。ココでは、乾と坤の、両方の道の働きによって男女ペア神が誕生した、ってことをチェック。
次!
②「純男」三神を三代、「男女」八神を四代とし、合計「神世七代」としてカテゴリ化
要は、3+4=7の計算式。世代=ジェネレーション、という概念で理解OK
分かりやすく
- 第一段:3世代。純粋な男の神様が3神。
- 第二段:4世代。男女一対の神様が4組、計8神。
- 第三段:解説部分。3(純男神)+4(男女神)=7代(神世七代)
といった流れ。
天地開闢、世界創世という原初に誕生した、非常に尊い神様ジェネレーション、神様カテゴリ。その全体を括る数字として奇数の7(=陽数)が設定されてます。
合理的で数学的にも美しい世界、それが天地開闢にまつわる神様誕生の神話観です。
まとめます。
- 第二段で登場した男女ペア神は、実は「乾坤之道、相参而化」という「化生方法」だった
- 「純男」三神を三代、「男女」八神を四代と算出、全部で「神世七代」としてカテゴリ化
以上2点を踏まえて以下、本伝をチェックです。
『日本書紀』巻第一(神代上)第三段 本伝
国立国会図書館デジタルライブラリより慶長4(1599)刊版 すべて八柱の神である。天の道と地の道が互いに参じて化した。それゆえ男と女に成った。国常立尊から、伊奘諾尊・伊奘冉尊に至るまで、これを神世七代と言う。
凡八神矣。乾坤之道、相参而化。所以、成此男女。自国常立尊、迄伊奘諾尊・伊奘冉尊、是謂神世七代者矣。 (引用:『日本書紀』巻一(神代上)第三段 本伝より)
『日本書紀』巻第一(神代上)第三段 本伝解説
改めて、第三段は、第一段から始まった開闢伝承の締め括りに位置。内容的には「解説」に当たります。
スゴい短いのに、わざわざ一段まるごと使用して解説に。
この重要感めっちゃ大事。
伝えたいことがあるんです。
てことで以下3つポイント解説。
最後に、総括として、
ココ第三段本伝が持つ意味を日本神話全体の構造論的に言うと、、
次の第四段=新時代へ向けた準備、つなぎとしての役割あり
ってことでチェック。
改めて、「第一段~第三段」と「第四段以降」は全然違う時代。
それは、
- 「神世七代」と「それ以外の神」との違い
- 「乾坤の道によって化成した神」と「それ以外の神(男女の営みによって生んだ神)」との違い
って、、すごいドギツイ事いうと、
「尊さ」が違うんす。
宇宙の、万物の根源である道から、道の働きによって誕生した神と、男女神の営みによって誕生した神では、尊さが、格が、違います。。。って、私は何様でしょうか??
第四段からは国生みが始まるわけで、ココ第三段=道による誕生の時代の最後に、次の時代へつながる物語をもってきた、とも言える訳です。
こうした時代の転換を織り込めばこそ、この神世七代という括りが重い意味をもちますよね。
改めてスゴすぎ。古代日本人が生み出した壮大な仕掛け。
『日本書紀』編纂当時の、東アジアの最先端知識、宇宙理論をもとに、単に真似で終わるのではなく、日本独自に組み合わせ、工夫し、新しく生み出している、超絶クリエイティブ発揮の巻。いつも言ってるけど、改めて。
まとめ
『日本書紀』巻第一(神代上)第三段 本伝
第一段、第二段の内容を踏まえた締めくくり、総括的解説の段。
①「乾道独化」と「乾坤之道、相参而化」という「神の化生方法」の違い
ベースには、乾道=天の道・・坤道=天に対する地の道、といった2項対立の根源とその働きあり。
日本神話的には、乾坤の道は「神を化生させる」という働きを持つ。
第一段で伝える「乾道独化」とは、「乾=天の道は単独で化す」という意味。乾道のみの働きによる化生の結果が「純男神」。それに対して、第二段で誕生した「男女ペアの神」は、「乾坤之道、相参而化」。乾坤が互いに参じて、集まって、混じり合って化生したのが男女ペア神。
いずれもジャパンオリジナルの概念。この創意工夫感がスゴイ。
②「純男」三神を三代、「男女」八神を四組のペア神四代と算出、「神世七代」とカテゴリ化
天地開闢→3(奇数=陽数)→4(偶数=陰数)→国生み8(たくさん!)といったイメージ、大きな流れのなかで理解。
第三段では、この3+4=計7世代を、「神世七代」として位置づけ。
天地開闢、世界創世という原初に誕生したとっても尊い神様ジェネレーション、神様カテゴリ。全体を括る数字(7)として奇数=陽数設定。
「神世七代」という神ジェネは、後の伊奘諾尊・伊奘冉尊の神生みによって誕生する神様たちとは違う、むしろ別格の、いや、超絶別格の神様たちとしてチェック。
③「神世七代」というカテゴリそのものが「尊卑先後の序」にもとづく
「神世七代」という神ジェネを、それ以降の神々、世代と区別する。そして、「神世七代」の中でも、純男三代と男女四代を区別する。
区別=尊と卑の別、優と劣の別。ココにある根本の概念が「尊卑先後の序」。
「尊卑先後の序」は、日本神話を貫く超重要な原理原則。この根底概念をもとに歴史観、神話世界が構成されてます。
分けることで、区別することで、価値を高めたい対象がどんどん尊くなっていく仕組み。
この世界の始まりの時代、そこで最初に誕生した神様を尊いものにしたい。「理想の世代(聖代)」としたい。
そのために、尊卑先後の序を活用、古代の歴史観をベースに3,4,7という数字を組み合わせて表現した、ってこと。
それをふまえて、第四段以降は、この道のはたらきにとって替わる形で、男女の営為・活動が展開。
道の働きから男女の営為・活動へ
大きな神話的展開をチェックです。
続きはコチラ↓で!オススメはこっち!
国生みが待ちきれない方はコチラで!
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ(S23)。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




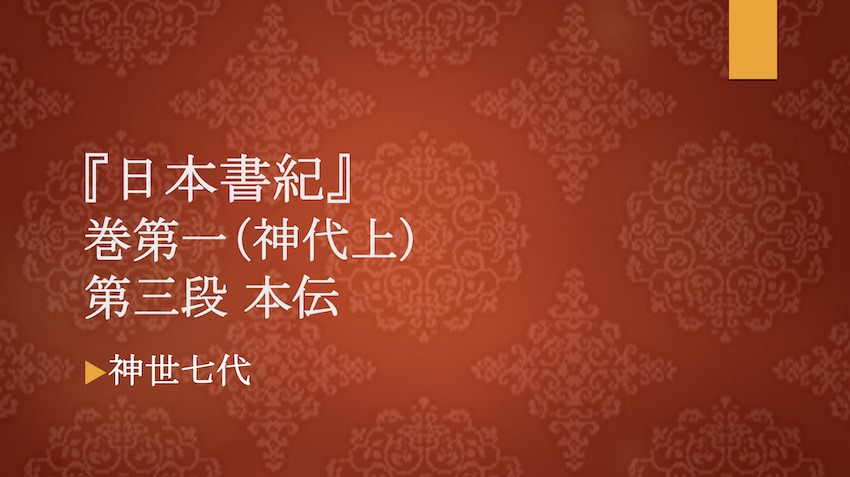



















→乾の道=天の道(≒陽)、坤の道=天に対して地の道(≒陰)といった意味。
まず押さえたいのは、
神の誕生=化生方法には、「乾道独化」と「乾坤之道、相参而化」の2つがあって全然違う!
ってこと。
コレ、そもそも、「道」や「易」の概念を理解しないと読み解けない、、、詳細コチラ↓で
ここでは簡単に。
万物の根源たる「道」は、
乾の道・坤の道、といった感じで、2項対立&働きアリ。
で、「日本神話的乾坤の働き」として重要なのが「神を化生させる」というもの。
第一段で伝える「乾道独化」とは、「乾の道は単独で化す」という意味。乾道の単独の働きによる化生の結果が「純男神」。純粋な男の神様。詳細は第一段解説にて。
それに対して、
第二段で誕生した「男女ペアの神」は、「乾坤の道、相参じて化す」。乾坤が互いに参じて、集まって、混じり合って、それによって化生したのが「男女ペア神」。
乾道単独の働きでは無く、乾と坤の、両方の道の働きによるものだ、てこと。
コレはこれで、実はジャパンオリジナル概念。中国では基本的に、乾は乾、坤は坤なので、参じて混じり合って、、といった感じでは無いんですよね。
いずれにしても、
というように、2項対立の対応関係がベースにあるわけで。これを理解してないと何のことやらサッパリ。。。
ま、とにかく、ココでは、
以上の3つ、しっかりチェックされてください。
次!
→国常立尊から伊奘諾尊・伊奘冉尊までを「神世七代」としてひとくくりにしてます。
「神世七代」の内訳は、「純男」三神を三代、「男女」八神を四代とする形。
3+4=7。世代=ジェネレーション、という概念理解でOK。
天地開闢の原初に誕生した、最も尊い神が、三世代。次いで誕生した男女ペア四組(ペア2×4組=計8神)の神が、四世代。
ということで、ここでも古代聖数概念が使用されてますね。
奇数と偶数の組み合わせ最少単位は5(3+2)ですが、最初に誕生する神が3なので、全体が5だと残り2しかなく、広がりが無くなります。
なので、組み合わせとして7を使用。
天地開闢→3(奇数=陽数)→4(偶数=陰数)→計7(奇数=陽数)→国生み8(たくさん!)
といったイメージ。だからこそ、理解としては、
「神世七代」という神ジェネは、後の伊奘諾尊・伊奘冉尊の神生みによって誕生する神様たちとは違う、むしろ別格の、いや、超絶別格の神様たち、としてチェック。
そら、道の働きによって、道から誕生した神様たちと、二神の結婚と神生みによって誕生した神様たちとでは格が違いますわな。。。って、私は何様でしょうか??
とにもかくにも、3(陽数)+4(陰数)=7(陽数)で「神世七代」、しっかりチェック。
ちなみに、、神様を一覧化すると、
(純男の神)
(男女一対の神)
ということでこちらもチェック。
次!
3つ目のポイント。実はこれが一番重要。
「神世七代」というカテゴリ分け、区別する考え方は「尊卑先後の序」にもとづいている。
本件、
というお話で。
コレ、実は、大きくは、
この世界の始まりの時代を、それ以降とは区別して「理想の世(聖代)」とする歴史観があるんです。この大きな歴史観、概念を理解しましょう。
例として以下。
三皇は道に依り、五帝は德に伏し、三皇は仁を施し、五覇は義を行う。~蓋し、優劣の異、薄厚の降なり(『太平御覧』巻第七十七「皇五部」所引「阮籍通老論」より)
『太平御覧』とは、中国宋代初期に成立した一種の百科事典の一つ。
要は、
三皇→五帝→五覇へ時代が下るにつれて、道→徳→仁→義(そして最終的には法律によって統治する)、というように「優」から「劣」に品下っていく、という考え方です。
道によって統治するのが究極、そっからレベルが下がっていって義になる。最終的にはルールで縛るようになる。。。
今風に言えば、人徳で治める聖人君主から、法律や刑罰によって治めるルール君主へ、といった感じ。「三皇」の時代を、理想化し、そっからだんだん時代が下るに従ってレベルが下がっていく、といった考え方になります。
時代が下るに従って、あり方・やり方も品質が下がっていく、
そんな概念が古代中国にはあったんすね。
で、
この概念をベースに、
ということ。
区別=優と劣の別、尊と卑の別
ココにある根本の概念が「尊卑先後の序」。
「尊卑先後の序」は、日本神話を貫く超重要な原理原則。やわらかく言うと、物事には優先順位があるよ、ということ。
この根底概念をもとに歴史観、神話世界が構成されてる、という訳。
分けることで、区別することで、価値を高めたい対象がどんどん尊くなっていく仕組み。
この世界の始まりの時代、そこで最初に誕生した神様を尊いものにしたいんです。「理想の世代(聖代)」としたいんです。
そのために、尊卑先後の序を活用、古代の歴史観をベースに3,4,7という数字を組み合わせて表現した、ということ。
コレ、あくまで相対的なものなので、「神世七代」が尊くてそれ以外の神様が卑しい、という意味ではないので注意。同様に、四世代が卑しい、という意味でもないです。
ということで、
冒頭の問い、
については、この世界の始まりの時代を、そこで最初に誕生した神様を、めちゃくちゃ尊いものにしたいから、ということになります。