日本神話に登場する、重要ワード、重要エピソードをディープに掘り下げる「日本神話解説シリーズ」。
今回は、
鬼と桃
をテーマにお届けいたします。
鬼と桃といえば、、、桃太郎。ですよね。
桃太郎が鬼を退治する
という、誰もが知る、この昔話ですが、実は、、、その元型、起源は、日本神話にあるんです!ド━(゚Д゚)━ン!!
桃太郎のお話。その核心部分を図式化すると、、、
桃が鬼を退治する、退散・払除する構図
ということになりますが、
日本神話でも、伊奘諾尊が追って来る八雷(鬼)に対して、桃の実を投げて退散させた。という伝承があり、まさに同じ構図!
いや、むしろ、神話こそが起源であり、桃太郎はその派生??くらいの勢いで。
スゴくない? 鬼と桃、神話で既に登場してるって、、、
今回は、そんな鬼と桃の繋がりを、その起源を!日本神話をもとにディープに深堀り、解説していきます!必読のエントリー!最後までしっかりチェックです!
なぜ?鬼は桃嫌い? 鬼を避らう桃、桃の持つ呪術的チカラの起源を日本神話から探る
目次
桃が鬼を退治する話が広く普及した経緯
まずは、馴染みのあるところから。桃太郎、「桃が鬼を退治する話」が、広く普及した経緯をチェック。
今でこそ、
桃太郎といえば、日本昔話の中でも知名度No.1的ポジションを獲得していますが、そもそも、広く世に知られる様になったのは、実は、江戸時代のことだったりします。
読本作家として活躍した曲亭馬琴が、『童蒙話赤本事始』のなかで「桃太郎・かちかち山・猿蟹合戦・舌切雀・花咲爺」を「五大昔噺」に選定した事がきっかけ。この功績が非常にデカい。これにより、親子で楽しむ昔話として、桃太郎が広まっていった訳ですね。
そして、明治になり、なんと、桃太郎話を「国定国語教科書」が採用したことで、その地位は不動のものとなりました。国が定めちゃった訳で。
1887(明治20)年、文部省が編纂した「尋常小学読本(巻一)」。ここに桃太郎が採り上げられます。この他にも、唱歌や図画などの教科でも用いられたりして。。。これにより、「国民童話」的な位置まで押し上げられ、全国津々浦々まで広く普及したんすね。
まず、このあたりの経緯をしっかりチェック。そうは言っても桃なんだけどさ。。
桃が鬼を退治する話の起源
広く普及した経緯は良いとして、当サイト的なる問題は、
その桃太郎話が、つまり、桃が鬼を退治する話の、その起源が、どこまで遡るのか、ということなんですが、、、
折口信夫『古代研究』(民俗学篇2。折口信夫全集第三巻)に「桃の伝説」という論考があり、桃太郎の話の成立を室町時代とする説もありつつ、、その詳細は、、、どうにも確かめようがありません!! だって記録がないんだもん。。。
しかし!
物語としての形、話型としては、桃太郎による鬼退治、そこに犬・猨・雉が加勢するという基本は、ほとんど変えることなく、江戸時代以前のはるか昔から伝えられていたのではないかと推測されます。
これ、なんでそう言えるかというと、、
手懸かりの一つとして、「構造が同じだ」という点があります。
桃太郎が鬼を退治する
という、この昔話を構成する核心部分。
これ、単純に図式化すれば、
桃が鬼を退治する、退散、払除する構図
であり、これは、『日本書紀』第五段〔一書9〕の「此れ、桃を用ちて鬼を避らふ縁なり」という一句、その図式そのものだったりします。
同じ構図が『日本書紀』で、日本神話で使用されていて、その後、江戸時代まで構図そのものが変わってないので、逆にいうと、桃が鬼を退治する話の起源は、日本神話に求めることもできる、ってことで。
なんなら、日本神話を起源として、桃が鬼を退治する話があるとも言える訳で。そうなると、、、俄然アツくなってきた!
ということで、早速、日本神話で伝える部分をチェックしてみましょう。

日本神話で伝える桃が鬼を退治する伝承
日本神話で登場するのは、『日本書紀』第五段〔一書9〕。殯斂訪問譚の中で伝えます。コチラ。
ある書はこう伝えている。伊奘諾尊は妻に会いたくなり、殯斂のところへ行った。すると伊奘冉尊は、まだ生きているかのように、伊奘諾尊を出迎え共に語った。そして伊奘諾尊に、「私の愛しい夫よ、どうかお願いです、私を決して見ないで下さい。」と言った。そう言い終わると忽然と姿が見えなくなった。このとき暗闇となっていた。伊奘諾尊は一つ火を灯してこれを見た。すると、伊奘冉尊の身は膨れあがっていて、その上に八色の雷がいた。
伊奘諾尊は驚き逃げ帰った。その時、雷達が皆起きあがり追いかけてきた。すると、道端に大きな桃の樹があった。伊奘諾尊はその樹の下に隠れ、その実を採って雷に投げると、雷達はみな退き逃げていった。これが、桃で鬼を追い払う由縁である。 (出典:『日本書紀』巻第一(神代上)第五段〔一書第9〕より)
ということで。
この〔一書9〕の伝承じたいは、伊奘諾尊が伊奘冉尊による見るなの禁を破り、その屍体を見て驚いて逃走したあとを八雷が追って来るのに対して、桃の実を投げて退散させた。という内容で。
構図的にも、
「道端に大きな桃の樹があった。伊奘諾尊はその樹の下に隠れ、その実を採って雷に投げると、雷達はみな退き逃げていった。」と、まさに、桃が鬼を退治する、退散・払除するカタチになってます。
桃が鬼を退治する。。。すごいよ、、その発想。
桃だぜ?
先ほど解説したように、この基本構造は、桃太郎による鬼退治の基本と同じであるため、恐らくですが、『日本書紀』が編纂された7〜8世紀当時から、ほとんど変えることなく伝えられていたのではないかと推測される訳です。
でだ、
ここで終わらないのが当サイトならではのディープなところ。ここからは、さらに、『日本書紀』編纂のベースとなった漢籍を元に、その起源を探っていこうとする訳です。

桃が鬼を退治する伝承の起源
中国の長い歴史の中でも、桃は「不老長寿の薬」や「魔除けの力」があるとされ、あるいは「仙果」仙人の食べる果物としても位置付けられてきた経緯あり。
まずは馴染みのあるところから。
『西遊記』では、孫悟空がまだ暴れん坊の頃、天界で管理人として任じられたのが、桃畑、桃の果樹園ですよね。
そこには桃の木が3,600本植えられており、手前の1,200本は3,000年に一度実をつけ、それを食べると仙人に、 真ん中の1,200本は6,000年に一度実をつけ、それを食べると不老不死に、 一番奥の1,200本は9,000年に一度実をつけ、 それを食べると天地があらんかぎり生き永らえる・・・と。
この、「桃」に象徴されるように、その桃を食べることで不老不死が得られるという、非常にめでたい話でもあるのですが、それ以上に重要なのは、桃の木そのものに宿る霊力によって、すべての災を避ける力があるとされていたこと。
さらに、桃が鬼を退治する。すなわち、鬼を避らう桃と、その実をつけた「大桃樹」とに関連する一節を探ってみると、、、ぶち当たるのが、後漢時代の漢籍、『論衡』。
『論衡』とは、中国後漢時代の王充(27年 – 1世紀末頃)が著した全30巻85篇(うち1篇は篇名のみで散佚)から成る思想書、評論書。
当時としては異例の、実証主義の立場から自然主義論、天論、人間論、歴史観など多岐にわたる事柄を説き、一方で非合理的と位置付けた先哲、陰陽五行思想、災異説を迷信論として徹底的に批判した、非常に革新的な書物です。
この『論衡』(巻二十二、訂鬼篇)の引く『山海経』(海外経)の佚文が次のように伝えています。
滄海の中に度朔の山有り。上に大桃木有り。其の屈蟠すること、三千里。其の枝の間の東北を鬼門と曰ふ。万鬼の出入する所なり。上に二神人有り。一を神荼と曰ひ、一つを鬱塁と曰ふ。万鬼を閲領することを主どる。悪害の鬼は、執ふるに葦索を以てし、而して虎に食はしむ。
おおお。。ありますやん、、「大桃木」。そして、鬼を退散させる桃、、、
で、
この伝承をめぐっては、後漢の応昭『風俗通義』(巻八。桃梗・葦交・画虎)や『斉民要術』(巻十)『漢旧義』などがほぼ同じ内容で採録する一方、『荊楚歳時記』(正月)の引く『括地図』では度朔山を「桃都山」としています。
桃都山に大桃樹有り。盤屈すること三千里。上に金鶏有り。下に二神有り。一は鬱と名づけ、一は塁と名づく。併せて葦索を執り、以て不詳の鬼を伺ひ、得れば則ち之を殺す。
と、やはり、
山に大桃樹がものすごい枝を広げていて、鬼を退散させる呪物的なものとして位置付けられているのが分かります。
さらに、
伝承の広がりは、『玄中記』(『芸文類聚』巻九十一「桃」所引)などの志怪小説にも及んでいて、、。
ま、要は、
これらの思想や概念を、日本では〔一書9〕が拾いあげたとみるべきで。当時の編纂チームメンバーが、当時の自然思想を根拠として盛り込んでいったのでしょう。これはこれで、ものすごい知識量だし、創意工夫です。なんせ神話的ドラマとして仕立て上げてる訳なので。
さらに、
桃の木を使った各種呪具・呪物についても記録が残っています。
鬼(疫鬼や疫神)を払う儀式「儺祭」では、桃の弓と棘の矢で邪鬼を払っていたようです。
「卒歳に大いに儺なし、群厲を殴除す。方相は鉞を秉り、巫覡は茢を操る。(中略)桃弧 棘矢の発する所に臬(弓の的)無し」 『文選』(巻三「東京賦」)より
ちなみに、
同じ儺祭でも、『後漢書』(礼儀志)は「葦戟・桃杖を公卿・将軍・特候・諸侯に賜ふ」という群臣に賜う「桃杖」をつたえてます。桃の杖!
他にも、『淮南子』(巻十四「詮言訓」)の「羿、桃棓に死す」に、許慎が注を付しているのですが、その内容が以下。
「棓は大杖、桃木を以て之を為り、以て羿を撃殺す。是れ由り以来このかた、鬼、桃を畏なり」
→訳:棓とは大きな杖のことで、桃の木で作った。これで羿が打ち殺された。これより以後、鬼も桃の木を恐れるようになった
「羿」とは人名で、天下に二人といない弓の名人で武将。それが家来の反逆にあって、狩りから帰ったところを、桃の木の杖で打ち殺されてしまう。強い武将でさえ、桃の木が持つ霊力に敵わなかった、というところから、鬼が恐れるようになった、、。
いずれも、
桃の持つ霊力、パワーが超絶!
ということで。
このほか、、、詳細は、王秀文氏の『桃の民俗誌』(朋有書店)にて、それこそ古今和漢の用例を博捜して詳細に論じてますのでチェックされてください。
おまけ:『古事記』に伝える桃と鬼
『古事記』版の日本神話もお届け。
実は、『古事記』での桃の位置付け、扱いは、ちょっと特殊。独自進化を遂げて新種の桃に??
ということで、以下チェック。黄泉国から逃げ帰る途中、最後に桃の実を投げつけて雷どもを退散させたあとの件。
伊耶那岐命は桃の実に「汝、吾を助けしが如く、葦原中国に有らゆる現青人草の、苦しき瀬に落ちて患ひ惚む時、助くべし」と告げ、「意富加牟豆美命」の名を賜わった。 (『古事記』上巻より一部抜粋)
ということで。
新種誕生!!!
なんと、、うつしき青人草、すなわち現世のあらゆる人の患いや惚みを助ける効能付与!
『日本書紀』第五段〔一書9〕は、あくまで「此れ、桃を用ちて鬼を避らふ縁なり」という鬼を避らう縁起、起源をもって結びとしていたのが、、、この歯止めを大きく踏み越えました。
追儺をはじめとする広汎な鬼に関連した用例に当たっても、『古事記』が伝える桃の実に直結する確かな例がないだけに!独自かつ固有な展開を遂げているとみるべきでしょう。
桃じたいに鬼を避らい、退散させる呪物の地位を賦与していたところから、新しい効能付与することで桃の呪力を強調したものとしてチェックです。
まとめ
日本神話に登場する、重要ワード、重要エピソードをディープに掘り下げる「日本神話解説シリーズ」。
今回は、
鬼と桃
をテーマにお届けいたしましたが、、いかがでしたでしょうか?
桃太郎に代表される、
桃が鬼を退治する、退散、払除する構図
は、実は、日本神話でも、伊奘諾尊が追って来る八雷(鬼)に対して、桃の実を投げて退散させた。という伝承があり、まさに同じ!
いや、むしろ、神話こそが起源であり、桃太郎はその派生??くらいの勢いで。
源流を辿ると、桃の持つ呪力に対する思想的なものまで行き着きます。
桃太郎の鬼退治も、こうした桃のもつ呪力が人々の苦患を救済するという思想・信仰の、長い時間をかけてひき継ぎ、かたちを成してきた物語の一つだったに違いないのであります。
ということで、本文に戻って神話世界をたっぷりご堪能ください!
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




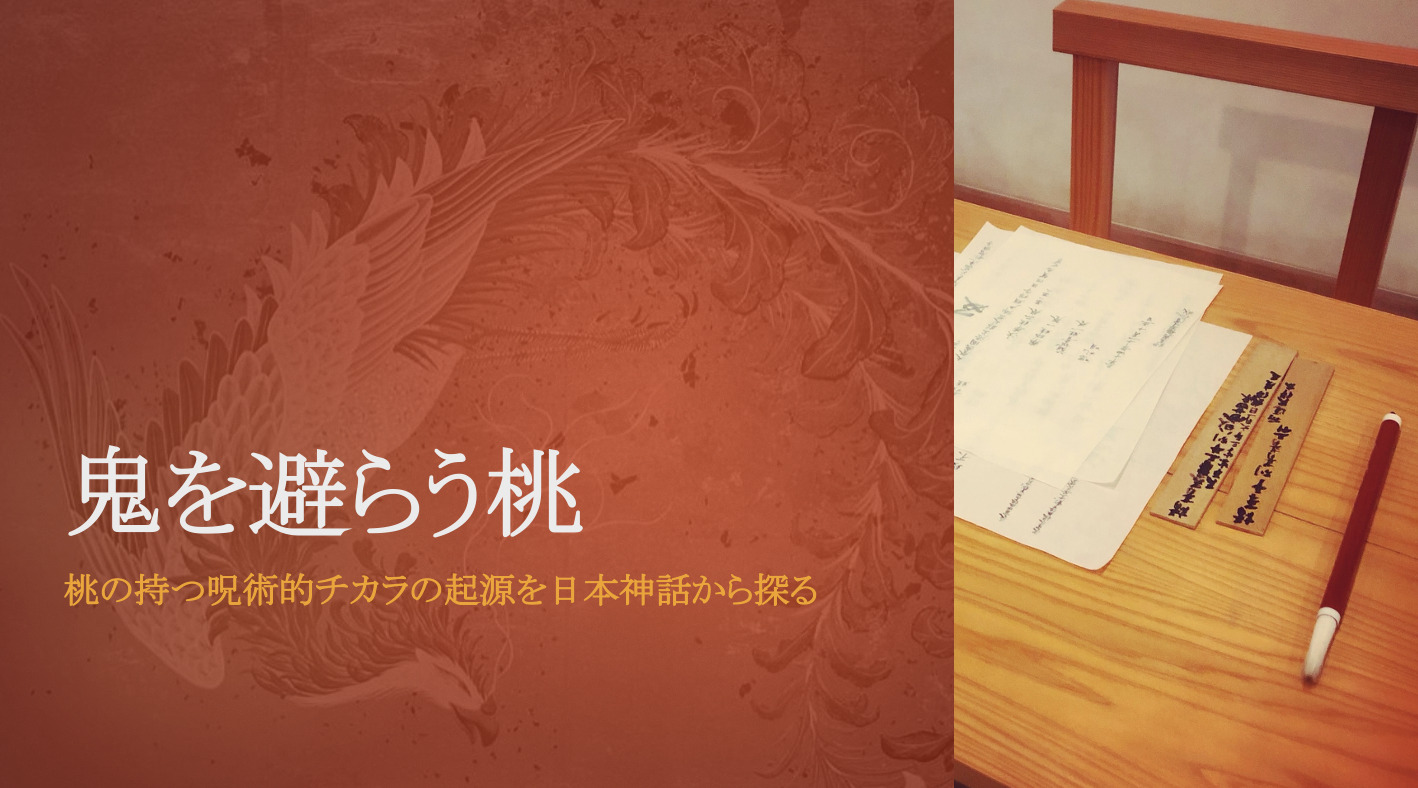














最後までお読みいただきありがとうございます。お気軽にコメントされてくださいませ。お待ちしております!