多彩で豊かな日本神話の世界へようこそ!
日本最古の書『古事記』をもとに、
最新の文献学的学術成果も取り入れながら、どこよりも分かりやすい解説をお届けします。
今回は、、
『古事記』序
現代語訳と分かりやすい解説付きでお届け。
『古事記』神話を読むとき、多くの場合、「序」を読まずに 「本文」から入ると思いますが、実はコレ、正しい読み方ではありません。『古事記』の編者である太安萬侶は、わざわざ巻頭に序文をつけていて、まずは序文から読めとしているんです。
今回は、その辺りの実際を、内容も含めて分かりやすく、ディープに解説していきます。
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
『古事記』序|現代語訳と原文|まずはココから読め!?太安萬侶が上表した『古事記』序文を分かりやすく解説!
目次
『古事記』序とは?
『古事記』の「序」とは、太安萬侶が元明天皇に言上した上表文。
『古事記』上巻の本文直前にあり、一般に、『古事記』序文として呼ばれてます。
「上表文」とは、君主に文書を奉る文書のこと。
『古事記』の一番最初、開巻第一行は「序」から始まり、そのまま「本文」に入る、という流れ。
『古事記』を読むとき、「序」を読まずに 「本文」から入ることが多いと思いますが、実はこれは正しい読み方ではありません!
『古事記』の編者である太安萬侶は、わざわざ、あえて、狙いを持って、巻頭に序文をつけてます。

『古事記』の巻頭、第一行は「古事記上巻井序」と記していて、これにより、
- 書名が『古事記』であること
- 上巻に「序」が井せられていること
が分かるようになってます。そう、『古事記』の書名は、実は序文冒頭の言葉から来てるんですね。
「上巻 序を幷す(上巻井序)」としてるのがポイントで。この時点で少なくとも上巻とは一体的扱い。
さらに、「序」は、『古事記』編纂の経緯や目的だけでなく、今日では一般に学術書が巻頭に掲げる「凡例」に相当する箇所として、本文の表記法、注記の原則等を明らかにしてます。
で、コレ、実際に確認してみると、この「序」の原則と「本文」とはしっかり対応しあってる。つまり、内容的にも『古事記』の「序」と「本文」は、一体不可分の関係にあることが分かるんです。
また、
応安4・5年(1371・2年) 書写の、現存最古の真福寺本『古事記』では、「序」の末尾の署名からそのまま「本文」が続いており、改丁(ページを改めること)どころか改行もしてない。
でも、この形式なら、「序」を省略してすぐ 「本文」に入ることは防げますよね。そうした配慮があったんじゃないかと感じられるほど「序」は大切だったりするんです。
ということで、
「序」は、飾り物としてあとから付けられたものではなく、なんなら、まず「序」から読んでほしい!これを読まないと「本文」が読みにくいし、正しい理解もしにくいぜ、と。そういう注意をするために、わざわざ巻頭にある。ココ、しっかりチェック。
で、
そんな『古事記』序ですが、大きく3つのパートから成ってます。
- 『古事記』の要約
- 天武天皇の業績と『古事記』編纂経緯
- 元明天皇の業績と『古事記』記述方法
ということで、
序文の位置付けと重要性、流れをチェックした上で、以下、順にお届けしていきます。
『古事記』序 ①『古事記』の要約
最初のパートは、『古事記』の要約です。天地初発から国土や神々の誕生を経て天皇の時代へ。崇神天皇や仁徳天皇の業績を讃えながら、人間の正道が絶えず続くように政治を行なってきたとしています。
古き事を記す 上巻 序を幷す
臣、安萬侶が申し上げます。
そもそも、混沌とした宇宙万物のもととなる気がすでに凝り固まりましたが、気が生み出す現象はいまだ現れておらず、その名もなく働きもなく、誰もその原始の形を知りませんでした。しかし、乾坤(天と地)が初めて分かれ、三柱の神が創造のはじめとなり、陰陽(男と女)がここに開かれ、二柱の神(伊邪那岐命と伊邪那美命)が万物の祖となりました。
こういうわけで、幽顕(見えない世界・幽冥・死者の世界と、見える世界・生の世界)に出入りして、日(天照大御神)と月(月読命)が目を洗ったことにより現れ、神々が海に浮き沈みして身を洗ったことにより現れました。
このような次第で、太素(天地万物の初め)は奥深く暗くてはっきりしないのですが、古い伝承により土を孕み嶋を産んだ時を知りました。また、元祖(天地万物の初め)は遥かに遠いのですが、先代の聖人の伝えにより神を生み人を立てた時を知りました。
まことに、次のことが分かります。
鏡を懸け珠を吐き、数えきれないほど多くの王(天皇)が皇統を継ぎ、剣を喫み大蛇を切って万の神々が繁栄したのです。そして、安河(高天原にある川)で議り、天下を平らげ、小浜(稲佐の浜)で論らい国土がすっきりしたのです。
これによって、番仁岐命が初めて高千穂の嶺に降り、神倭の天皇は秋津島(日本)を巡歴されました。化した熊が川を出て、天剣を高倉に得させ、尾の生えたものたち(吉野の先住民)が道を遮り、大烏(八咫烏)が吉野に導き、舞を列ねて賊を討ち払い、歌を聞き仇を平伏させました。
すなわち、夢のお告げにより神祇を敬祭し、賢后と申します(崇神天皇)。煙を望み見て人民を愛しみ、今に聖帝と伝えています(仁徳天皇)。国郡の境を定め国を開いて近淡海(琵琶湖)で制度をおさめられました(成務天皇)。姓を正し氏を選んで遠い飛鳥で整えられました(允恭天皇)。
歴代天皇の政治には緩急があり、華美と素朴の違いはありましたが、過去を振り返り、風教と道徳がすでに崩れているのを正しくし、現今の情勢を見定めて、人間の正道が絶えようとするのを補強しないことはありませんでした。
古事記上卷幷序
臣安萬侶言。夫、混元既凝、氣象未效、無名無爲、誰知其形。然、乾坤初分、參神作造化之首、陰陽斯開、二靈爲群品之祖。所以、出入幽顯、日月彰於洗目、浮沈海水、神祇呈於滌身。故、太素杳冥、因本教而識孕土產嶋之時、元始綿邈、頼先聖而察生神立人之世。寔知、懸鏡吐珠而百王相續、喫劒切蛇、以萬神蕃息與。議安河而平天下、論小濱而淸國土。
是以、番仁岐命、初降于高千嶺、神倭天皇、經歷于秋津嶋。化熊出川、天劒獲於高倉、生尾遮徑、大烏導於吉野、列儛攘賊、聞歌伏仇。卽、覺夢而敬神祇、所以稱賢后。望烟而撫黎元、於今傳聖帝。定境開邦、制于近淡海、正姓撰氏、勒于遠飛鳥。雖步驟各異文質不同、莫不稽古以繩風猷於既頽・照今以補典教於欲絶。
ということで。
「そもそも、混沌とした宇宙万物のもととなる気がすでに凝り固まりました」というのが、天地初発の部分。ちなみに、『古事記』本文では、「天地が初めて發った時に、高天原に成った神の名は~」とあり、これ細かく言うと
- 序文の天地初発はプロセス的内容=「気が凝り固まった」
- 本文の天地初発は結果スタート的内容=「高天原ありき」
ということで、序文と本文には若干の違いがあったりします。
なお、序文で伝える「混沌とした宇宙万物のもととなる気がすでに凝り固まりました」というのは、どちらかというと『日本書紀』の巻一(神代上)第一段〔本伝〕部分を踏まえたほうが理解しやすい内容になってます。
また、
「乾坤(天と地)が初めて分かれ、三柱の神が創造のはじめとなり」とあり、これが世に言う「造化三神」の箇所。これをうけて、『古事記』本文の冒頭で、高天原に三神(天之御中主神、高御産巣日神、神産巣日神)が誕生したと伝えていて、これにより、三神が造化のはじまり=高天原に誕生した三神=造化三神とされてる次第。
こんな感じで、『古事記』序文で概要を伝え、そのうえで本文で詳細を伝えるという構成になってるんです。
ちなみに、いわゆる「日本神話」と呼ばれる箇所は「また、元祖(天地万物の初め)は遥かに遠いのですが、先代の聖人の伝えにより神を生み人を立てた時を知りました。」まで。このあと、歴史の時代、天皇の時代へ入っていきます。
天皇の時代は、「過去を振り返り、風教と道徳がすでに崩れているのを正しくし、現今の情勢を見定めて、人間の正道が絶えようとするのを補強しないことはありませんでした。」ということで、つまり、歴代の天皇は人間の正道が絶えず続くように素晴らしい政治を行なってきたとしています。
『古事記』序 ②天武天皇の業績と『古事記』編纂経緯
2つ目のパートは、第40代天武天皇の時代。
なぜ、天武天皇なのかというと、『古事記』や『日本書紀』といった歴史書編纂事業が開始されたのが天武天皇の御世だったから。壬申の乱により超絶パワーをゲットし、神とも称された天武天皇、その業績を中心に『古事記』編纂経緯を伝えます。
飛鳥の清原の大宮に、大八州を統治された天皇の御世に至って、水底に潜み未だ雲を起こさない龍は天子の資質を備えられ、たびたび轟く雷鳴は好機に乗じて行動を起こされました。(濳龍、洊雷いずれも、天武天皇が皇太子の頃のことをいう。以下、皇子=大海人皇子のこと)
(天智天皇崩御の際に歌われた)夢の歌を占いで解き、天業を継ぐことを思われ、夜の水に到って基業(皇位)を継承することをお知りになったのです。
しかし、天運の開ける時がいまだ到来せず、セミのように南山(吉野山)に蛻られましたが、皇子に心を寄せる人たちが多く集まり、東国に威風堂々と進軍されました。皇輿(天子の乗る輿=皇子)はたちまちに少ない兵を起こし、山を越え川を渡り、皇子の六師軍は雷のようにとどろき、高市皇子の三軍は稲妻のように進軍しました。武器を手にして威を高らかにあらわし、勇猛な兵士は煙のように起こって加勢し、赤旗は兵士を輝かせ、賊軍(大友皇子軍)は瓦が崩れるように一挙に敗れました。
時を経ず、妖気は無くなり清くなったので、牛を放ち馬を休ませ、軍隊を整え帰し、大和国へ帰り、旗を巻き武器を収め、踊り舞い歌い飛鳥の都にとどまられました。
酉の年になり、二月、浄原の大宮(飛鳥浄御原宮)に昇殿され、天皇の位に即かれました。その政道は五帝である黄帝を超え、その聖徳は周王を上回るほどでした。天子たる”しるし”の乾符を握って世界をを統治し、天統を得て八方のはるか遠隔地までも統合なさいました。
二気(陰陽)の運行の正しさの通り政治が行われ、五行が天地の間に秩序をもって正しく流行循環するのは政治が良いしるしであり、神の道を復興して人民に奨め、すぐれた徳風を施してその及ぶ国の範囲を定められました。そればかりではなく、英智は海のように広大で、古い時代のことを深く究め、心は鏡のように明澄で、前の時代のことをお見通しになりました。
そこで、天皇は仰せられましたのは「朕が聞くところでは、『諸家(諸氏族)が持つ帝紀(帝の系譜)および本辞(神話や縁起などの伝承)は、もはや真実と違っており、多くは嘘偽りを加えられている』と聞いた。今日の時点で、その失りを改めなかったら、何年も経たぬうちに、その本旨はきっと滅びるだろう。この帝紀・旧辞は国家組織の根本であり、天皇政治の基礎である。そこで、帝紀を撰録し、旧辞を詳しく調べて、偽りを削り真実を定めて後の世に伝えようと思う。」
たまたま、舎人がいました。姓(氏)は稗田、名は阿礼、年は28。人となりは聡明で、ひと目見れば口で暗唱し、耳に聞けば記憶した。音訓も瞬間に判断して話し言葉に直し意味の分かる言葉で読み上げられることができました。
そこで、阿礼に勅して、歴代天皇の皇位継承の次第及び古代からの伝承を誦み習わされました。しかしながら、運は移り世は異り、未だその事業は行われませんでした。
曁飛鳥淸原大宮御大八洲天皇御世、濳龍體元、洊雷應期。開夢歌而相纂業、投夜水而知承基。然、天時未臻、蝉蛻於南山、人事共給、虎步於東國、皇輿忽駕、淩渡山川、六師雷震、三軍電逝、杖矛擧威、猛士烟起、絳旗耀兵、凶徒瓦解、未移浹辰、氣沴自淸。乃、放牛息馬、愷悌歸於華夏、卷旌戢戈、儛詠停於都邑。歲次大梁、月踵夾鍾、淸原大宮、昇卽天位。道軼軒后、德跨周王、握乾符而摠六合、得天統而包八荒、乘二氣之正、齊五行之序、設神理以奬俗、敷英風以弘國。重加、智海浩汗、潭探上古、心鏡煒煌、明覩先代。
於是天皇詔之「朕聞、諸家之所賷帝紀及本辭、既違正實、多加虛僞。當今之時不改其失、未經幾年其旨欲滅。斯乃、邦家之經緯、王化之鴻基焉。故惟、撰錄帝紀、討覈舊辭、削僞定實、欲流後葉。」時有舍人、姓稗田、名阿禮、年是廿八、爲人聰明、度目誦口、拂耳勒心。卽、勅語阿禮、令誦習帝皇日繼及先代舊辭。然、運移世異、未行其事矣。
ということで。
ココでのポイントは、やはり『古事記』編纂、より正確に言うと歴史書編纂事業開始の箇所です。
天武天皇の御代、すでに『諸家(諸氏族)が持つ帝紀(帝の系譜)および本辞(神話や縁起などの伝承)は、もはや真実と違っており、多くは嘘偽りを加えられている』状態だったようで。。。みんな言いたい放題、勝手な歴史が乱立していた模様。。
きっと、天皇家以外の氏族的には、「ウチはこんなにスゴイぜ!」を言わんがために、好き勝手な歴史を捏造、勝手に天皇家の神を登場させたり、都合の良い系譜をつくったりと、、、この辺りはロマンが広がるところで。
天武天皇的には、そうした状況に強い危機感を持っていたようで、、「今日の時点で、その失りを改めなかったら、何年も経たぬうちに、その本旨はきっと滅びるだろう。」と、本当のことが失われてしまうとしています。さらに、「この帝紀・旧辞は国家組織の根本であり、天皇政治の基礎である。」とあるように、まさに歴史は国家組織の根本であり礎であると、かなりの重要感をもって伝えてます。
そんなこんなの背景と危機感、さらに重要性の認識からスタートしたのが歴史書編纂事業だった訳で。
そこで登場するのが我らが「稗田阿礼」。28歳のスーパー舎人!?ちなみに、、稗田氏は、天宇受売命の子孫の猿女君の一族。大和国稗田の在とされてます。
で、
「阿礼に勅して、歴代天皇の皇位継承の次第及び古代からの伝承を誦み習わされました。」とありますが、ココで言う「誦み習わせた」というのは、帝紀・旧辞を解読し口誦(声に出して言う)させたということ。
それにより、天武天皇自ら撰録した定本、本来の歴史、正しい歴史ともいうべき帝紀・旧辞を、声に出して読める本にして後世に伝えようとした訳です。
一方で、、、阿礼への下命が天武10年(681)とすると、天武天皇崩御まで5年ちょっと。「運は移り世は異り、未だその事業は行われませんでした。」とあるように、結局、この時点での誦習事業は未完成となった訳です。
『古事記』序 ③元明天皇の業績と『古事記』記述方法
3つ目のパートは、第43代元明天皇の時代。
なぜ、元明天皇なのかというと、一度止まってしまった『古事記』編纂事業を再開させ、完成に至ったのが元明天皇の御世だったから。
前半は、とことん元明天皇を持ち上げ、その業績を讃えながら、後半は『古事記』編纂にあたっての記述方法や構成を伝えてます。
拝伏し考えますには、皇帝陛下(元明天皇)、天子の徳は天下に満ち、天地人の三才に通じて民を慈しみなさいます。紫宸(天子のいる場所=皇居)におられて、聖徳は馬の蹄の進みゆく極遠の地まで覆い、玄扈(黄帝がいた石室=皇居)におられて、皇化は船のへ先が漕ぎゆく果てまで照らされました。
日は浮かび輝きを重ね、雲が煙のようにたなびく(いずれも、吉祥のしるし)。柯を連ね(連理木。別々の木の枝が一つにくっついたもの)、穂を并す(嘉禾。一つの茎に多くの穂がついた穀物)吉祥のしるしは、史書として記すことが絶えませんし、貢使の到着を告げる烽火が列なり、僻遠の言葉の違う国々から次から次へと送られる貢により、宮廷の倉が空になる月はありません。その名声は禹王(夏を創始した王、治水の名王)よりも高く、その徳は成湯(殷の湯王。仁政の名王)よりも優れておられると申し上げるばかりです。
そこで、旧辞の誤り違っているのを惜しまれ、先紀の誤りが錯綜しているのを正そうとされて、和同4年9月18日に、臣・安万侶に詔し、「稗田の阿礼が誦んでいる勅語の旧辞を撰録して献上せよ」と仰されたので、謹んで、詔旨のまにまに細かに採り拾いました。しかし、上古の時代は、言葉もその意味する内容もみな素朴で、文章を作り句を構成する場合、漢字で書くとなるとそれは困難です。訓で述べたものは、詞(やまとことば)の意味と合いません。一方、すべて音をもって書き連ねたものは、見た目に長すぎます。こういうわけで、今、ある場合は一句の中に音訓を交えて用い、またある場合は全て訓を持って記録しました。その場合、文脈が分かりにくいのは「注」で明らかにし、意味の分かりやすいものは「注」をつけません。その上、姓の場合「日下」を「くさか」と読み、名の場合「帯」の字を「たらし」と読みます。このような見慣れた文字は、もとの通りとし改めません。
全て、記述した内容は、天地の開闢より始めて小治田の御世(推古天皇)で終わります。そこで、天御中主神から日子波限建鵜草葺不合尊より前を上巻とし、神倭伊波礼毘古天皇から品陀(応神天皇)の御世より前を中巻とし、大雀の皇帝(仁徳天皇)から小治田の大宮(推古天皇)より前を下巻とし、あわせて三巻を収録し、謹んで献上いたしますと、臣・安万侶、誠惶誠恐みも頓々首々す。
和銅五年(712年)正月二十八日 正五位上勳五等太朝臣安萬侶
伏惟、皇帝陛下、得一光宅、通三亭育、御紫宸而德被馬蹄之所極、坐玄扈而化照船頭之所逮、日浮重暉、雲散非烟、連柯幷穗之瑞、史不絶書、列烽重譯之貢、府無空月。可謂名高文命、德冠天乙矣。
於焉、惜舊辭之誤忤、正先紀之謬錯、以和銅四年九月十八日、詔臣安萬侶、撰錄稗田阿禮所誦之勅語舊辭以獻上者、謹隨詔旨、子細採摭。然、上古之時、言意並朴、敷文構句、於字卽難。已因訓述者、詞不逮心、全以音連者、事趣更長。是以今、或一句之中、交用音訓、或一事之內、全以訓錄。卽、辭理叵見、以注明、意況易解、更非注。亦、於姓日下謂玖沙訶、於名帶字謂多羅斯、如此之類、隨本不改。
大抵所記者、自天地開闢始、以訖于小治田御世。故、天御中主神以下、日子波限建鵜草葺不合尊以前、爲上卷、神倭伊波禮毘古天皇以下、品陀御世以前、爲中卷、大雀皇帝以下、小治田大宮以前、爲下卷、幷錄三卷、謹以獻上。臣安萬侶、誠惶誠恐、頓首頓首。
和銅五年正月廿八日 正五位上勳五等太朝臣安萬侶
ということで。
ここでのポイントもやはり『古事記』編纂事業の中身のところ。『古事記』編纂にあたっては、漢字を使って日本古来の言葉をどう表現するか?が大きな課題になってたようで。確かに、超絶ムズイコレ。
外国の文字体系である「漢字」は、漢文体には適しているのですが、日本の古語、古意を表す文字としては欠点があったんです。古くから伝わる日本独自の音の響きを持つ「やまとことば」は、漢字の訓読みで書いてもしっくりこない。一方、音のみでは文章が見た目に長すぎてしまう。。。
「上古の時代は、言葉もその意味する内容もみな素朴で、文章を作り句を構成する場合、漢字で書くとなるとそれは困難です。」とあり、安萬侶も非常に苦心した様子が伺えます。
そこで安萬侶が考え、提示した解決策が2つ。
- 1つ目は、音訓交用技法。
- 2つ目は、訓専用技法。
さらに、訓と音を区別するための「注」の活用。『古事記』ではいくつかの注の種類があるのですが、一番多いのが音注であり、これにより読みやすさや本来の意味をしっかり表現しようとした訳ですね。実はコレ、当時としては画期的なことで。イノベーションそのものであります。
詳しい解説はコチラで!
そして、最後のポイント。
『古事記』が完成したのが和銅5年(712)正月28日。一方、元明天皇が太安萬侶に下詔したのが和銅4年(711)9月18日なので、たった4ヶ月ちょっとで完成したことになります。
これは、阿礼が誦習していたからとされてますが、実際は、『日本書紀』がベースにあったからです。『日本書紀』をもとに、天皇家の歴史書として、国内の豪族氏族に配慮しながらそれらを神々の体系に組み込みながら一つの物語として編み出したのが『古事記』の実際だったりします。そして、『古事記』自体の編纂目的は、皇太子教育のテキストとして活用するため。これはこれで、皇位継承の歴史が絡む話なので別エントリで詳しくお届けします。
『古事記』序 まとめ
『古事記』序
太安萬侶が、元明天皇に言上した上表文。『古事記』上巻「本文」の直前にある序文。
『古事記』を読むとき、「序」を読まずに 「本文」から入ることが多いと思いますが、これは正しい読み方ではありません。『古事記』の編者である太安萬侶は、あえて巻頭に序文をつけてます。
『古事記』序は、大きく3つのパートで構成されてます。
- 『古事記』の要約
- 天武天皇の業績と『古事記』編纂経緯
- 元明天皇の業績と『古事記』記述方法
ということで、
1つ目、『古事記』の要約では、天地初発から国土や神々の誕生を経て天皇の時代へ。崇神天皇や仁徳天皇の業績を讃えながら、人間の正道が絶えず続くように政治を行なってきたとしています。
2つ目、天武天皇の業績と『古事記』編纂経緯では、壬申の乱により超絶パワーをゲットし、神とも称された天武天皇、その業績を高らかに讃えつつ、『古事記』や『日本書紀』といった歴史書編纂事業が開始された経緯、理由を伝えてます。
目的は、天武天皇自ら撰録した定本、本来の歴史、正しい歴史ともいうべき帝紀・旧辞を、声に出して読める本にして後世に伝えるため。一方、阿礼への下命が天武10年(681)とすると、天武天皇崩御まで5年ちょっと。結局、誦習事業は未完成となった訳です。
3つ目、元明天皇の業績と『古事記』記述方法では、『古事記』編纂に当たって、安萬侶が苦心した言葉の難しさを伝えてます。いわば、外国の文字体系である「漢字」は、漢文体には適しているのですが、日本の古語、古意を表す文字としては欠点があった訳です。
さらに、『古事記』が完成したのが和銅5年(712)正月28日。一方、元明天皇が太安萬侶に下詔したのが和銅4年(711)9月18日なので、たった4ヶ月ちょっとで完成したことになります。
この辺りの事情を伝えているのが『古事記』序なんですね。
続きは『古事記』本文!天地開闢はコチラです!!
序についての突っ込んだ解説はコチラで!必読です!
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
[itemlink post_id=”13035″] [itemlink post_id=”13037″] [itemlink post_id=”13038″] [itemlink post_id=”13039″]どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




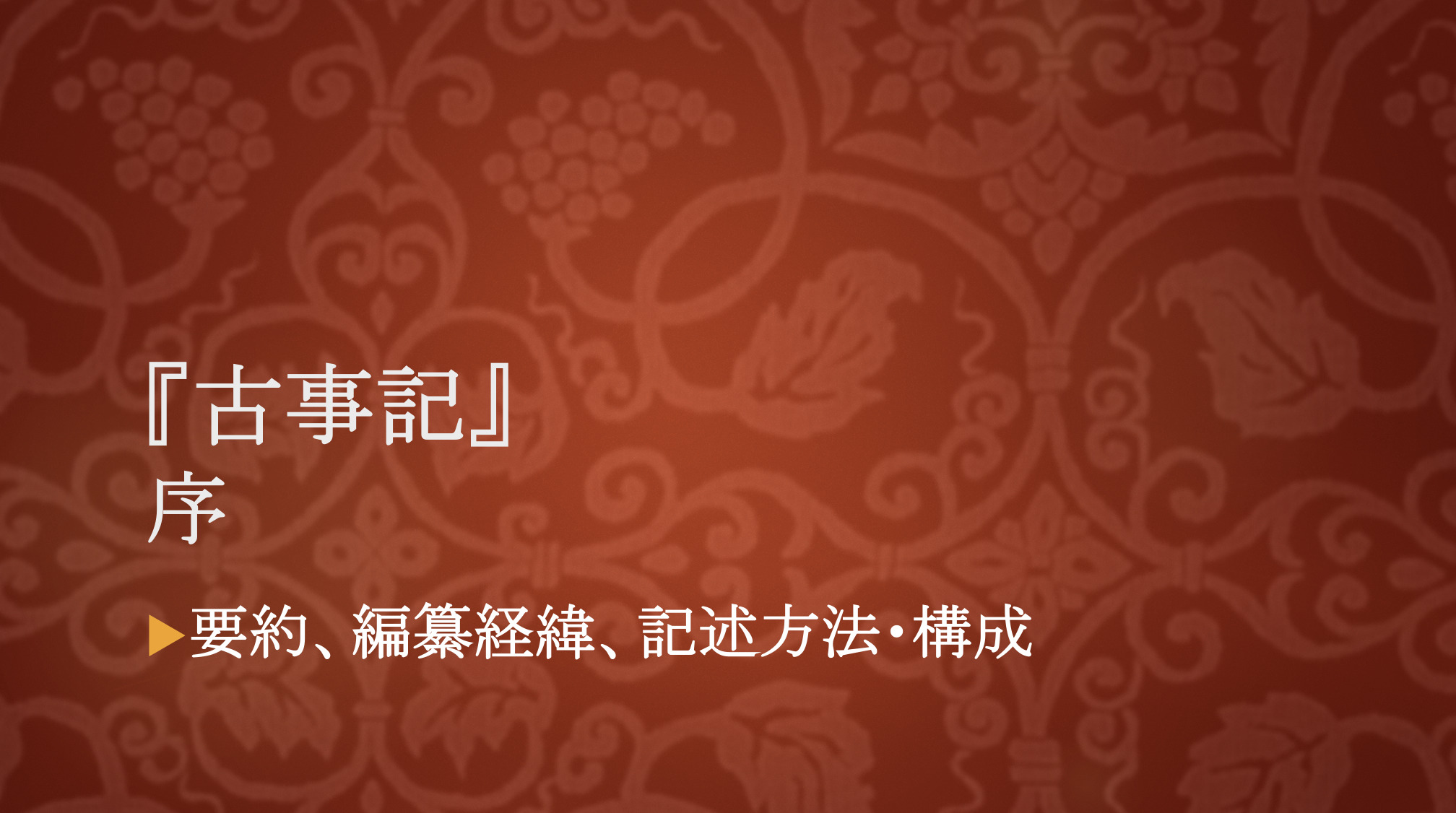



















最後までお読みいただきありがとうございます。お気軽にコメントされてくださいませ。お待ちしております!