多彩で豊かな日本神話の世界へようこそ!
日本最古の書『古事記』をもとに、
最新の文献学的学術成果も取り入れながら、どこよりも分かりやすい解説をお届けします。
今回は、『古事記』上巻から、
黄泉国訪問と生と死の断絶
『古事記』黄泉国訪問は、伊邪那岐命が愛しい伊邪那美命に会いに黄泉国へ行くお話。ポイントは、黄泉国の世界観(それは死生観と同じ)と、生と死の断絶(そして死に対する生の優位ロジック)。
今回も、概要で全体像をつかみ、ポイント把握してから本文へ。最後に、解説をお届けしてまとめ。
現代の私たちにも多くの学びをもらえる内容。日本神話から学ぶ。日本の神髄がここにあります。それでは行ってみましょう!
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
『古事記』黄泉国訪問と生と死の断絶|原文と現代語訳、分かりやすい解説付き
目次
『古事記』黄泉国訪問、生と死の断絶の概要
『古事記』上巻から。経緯としては、
伊邪那美命の神避りを嘆き悲しむ伊邪那岐命。人間さながらの激情発露、そして、我が子に復讐、斬断。激烈なシーンを通じて神威の強い神々が誕生しました。
↑経緯しっかり確認。
で、本文に入る前に、まずは押さえておきたいポイント、概要をチェック。
全部で4つ。
- 黄泉国行きは、人間モデル神誕生の伏線があってこそ。練りに練られた神話構造アリ
- 『古事記』的黄泉国は、国として成り立っている。国の体制上、役所があり、役所には長官=統治者がいる
- 見るなの禁に隠された深い意味。異類とは別れる他ない、、という「別れの必然」が物語に織り込まれている
- 黄泉往来譚の結末。。それは、生と死の断絶。そして、死に対する生の優位明確化
ということで、
以下、順に解説。
①黄泉国行きは、人間モデル神誕生の伏線があってこそ。練りに練られた神話構造アリ
今回お届けするのは黄泉国行きの神話ですが、コレ、単にそういう流れだからってことではなく、神話全体の流れの中で解釈する必要あり。
神話の持つ役割の一つに、起源を明らかにする、というのがあります。
中でも、死の起源は私たち人間にとって非常に重要な意味を持ってて。。なんで死ぬの?死ぬとどうなるの?って、このシンプルだけど深〜い問いに対して、日本神話的アンサーが今回の内容。
そもそもの伊邪那美の神避り≒死は、神話展開上必要なものとして、ある意味、予定されてたと言えるし、じゃあ、死んだあとどうなるの?という問いに対して、黄泉国行きの神話につながる。
ただし、単に、行くぜ黄泉国、だけじゃなくて、、しっかり動機づけ設定されてるとこに注目。それが、前段で登場した「人間モデル神」伊耶那岐命であります。
人間モデルなんで、感情をもとに行動する。(※神話的には、神が感情を持つので人間もそうなってる、という順番。神先人後。)。
それが、本文「(伊耶那岐命は)その妹伊耶那美命を見ようと欲って、」のところ。つまり、伊耶那岐命が欲してる訳です。愛しい妻、伊耶那美命に会いたいと。一目、もう一度見たいという動機をもって黄泉国へ行く。これにより、黄泉国行きが、とても自然な流れになってる。
国生みで布石を打って、段階的に人間モデルに移行、そのうえで黄泉国行きがある、非常に練られた構成になってること、このシーンだけで解釈するのではなく、神話全体の中でチェックです。
次!
②『古事記』的黄泉国は、国として成り立っている。国の体制上、役所があり、役所には長官=統治者がいる
『古事記』的黄泉国、コレ、『日本書紀』と比較するととても分かりやすくなるのですが、、
その最大の違いは
「国」として明確に位置づけられてる事。「黄泉国」。
コレ、、もう、「国」なわけで。当然、というか、前提的に、
- 統治者がいて
- 国民としての生活がある
- 軍隊もある
といった設定になっていきます。言葉一つなんですがとっても大事。
『古事記』的黄泉国は、国として成り立っていて、国の体制上、役所があり、役所には長官=統治者がいて、統治ルールがある。ここでいう「統治者」とは「黄泉神」。で、黄泉国を出るときには長官への相談と許可が必要、、、という訳です。
このあたり、日本の古代の人たちが創意工夫と想像力をめいっぱい広げて描いてるところであり、古代日本人の死生観にもつながる内容なんでしっかりチェック。
その他、黄泉国のポイントとしては以下。
- この世界とあの世(黄泉)はつながっていた。境界は「黄泉比良坂」。
- 黄泉国では、お互いの姿を確認できる「この世界と変わりない明るさ」があった。
- 黄泉国は、この世界とは非対称。時間の流れ方が違う。きっと黄泉の方が早い。
- 黄泉国では、黄泉の食べ物を食べる。「黄泉戸喫」。食べた者は「黄泉の神」となって元の世界には戻れない。
- 黄泉国は、死神とその腐乱した屍体によって汚れて穢れた国である。
- 尊貴な存在にはお付きの者が付く。ただし見た目はとても醜い。。。いや、猛烈である(雷神と黄泉軍)
こちらもあわせてチェックです。
次!
③見るなの禁に隠された深い意味。異類とは別れる他ない、、という「別れの必然」が物語に織り込まれている
「見るなの禁」とは、見ちゃダメの禁忌、タブーのこと。
コレ、古今東西の物語や伝承に共通した「型(話型)」で、
この世界の男性が、異界の女性と出会い、情を交わした後に、女が課す「見るなの禁」。それを男が破り、女の正体を見たことにより破局を迎える、、というのがパターン。
他にも、「鶴の恩返し」「浦島太郎」「見るなの座敷」、能の「黒塚」とかも同じ型(話型)です。
ポイントは、
- 異界の女が課すのは、女にとって見られたくないもの。それは通常、異類の本質とか本性。
- 一方の、男(人間)には感情があり、見るなと言われれば余計に見たくなる、、という人間の心理が働く
ってことで、、、こうした構造をもとに、結局、
異類とは別れる他ない、、という「別れの必然」が物語に織り込まれているんです。、深い、、、深すぎるぞ日本神話、。
次!
④黄泉往来譚の結末。。それは、生と死の断絶と、死に対する生の優位ロジック
神話の持つ役割、起源を明らかにする、とつながるお話ですが、今回の黄泉往来譚、最終的に何が言いたいのか?というのがポイントで。
それは、一言で言うと、
死とは断絶しました、しかも、死に対して生は優位である
ってこと。
最後、黄泉比良坂での伊耶那岐命と伊耶那美命の離縁宣言、泥仕合で、以下内容を伝えます。
- 死:伊耶那美命:伊耶那岐命の人民(人草)を1日1,000人絞め殺す
- 生:伊耶那岐命:1日1,500の産屋を建てる=産ませる
つまり、数字の大小で死<生であることを明確に伝えてる訳です。
死よりも生が優位にあるロジック。ここ激しく重要なのでしっかりチェック。
離縁の泥仕合いは、男女の離婚(離縁)や生と死の別離起源譚のみならず、人口増の起源譚でもある訳ですね。
まとめます。
- 黄泉国行きは、人間モデル神誕生の伏線があってこそ。練りに練られた神話構造をしっかりチェック
- 『古事記』的黄泉国は、国として成り立っている。国の体制上、役所があり、役所には長官=統治者がいる
- 見るなの禁に隠された深い意味。異類とは別れるほかないという「別れの必然」が物語に織り込まれている
- 黄泉往来譚の結末。。それは、生と死の断絶。そして、死に対する生の優位明確化
以上、チェックしたうえで、現場へゴー!
『古事記』黄泉国訪問、生と死の断絶の原文と現代語訳
古事記 : 国宝真福寺本 上 国立国会図書館デジタルコレクションより ここに、(伊耶那岐命は)伊耶那美命に会おうと欲って、黄泉国に追っていった。
そうして、(伊耶那美命が)御殿の閉じられた戸から出て迎えた時、伊耶那岐命は「愛おしい我が妻の命よ、私とお前が作った国は、まだ作り終えていない。だから還ろう。」と語りかけた。すると、伊耶那美命は答えて「残念なことです。あなたが早くいらっしゃらなくて。私は黄泉のかまどで煮炊きしたものを食べてしまいました。けれども、愛しき我が夫の命よ、この国に入り来られたことは恐れ多いことです。なので、還ろうと欲いますので、しばらく黄泉神と相談します。私を絶対に見ないでください。」と言った。
このように言って、その御殿の中にかえり入った。その間がとても長くて待ちきれなくなった。そこで、左の御美豆良に刺している神聖な爪櫛の太い歯を一つ折り取って、一つ火を灯して入り見たところ、(伊耶那美命の身体には)蛆がたかってごろごろ音をたてうごめき、頭には大雷がおり、胸には火雷がおり、腹には黒雷がおり、陰には拆雷がおり、左の手には若雷がおり、右の手には土雷がおり、左の足には鳴雷がおり、右の足には伏雷がおり、あわせて八つの雷神が成っていた。
そこで、伊耶那岐命は、その姿を見て恐れて逃げ還る時に、その妹伊耶那美命が「よくも私に辱をかかせましたね」と言って、黄泉の醜女を遣わして追いかけさせた。ここに伊耶那岐命は、黒御縵を取って投げ棄てると、たちまち山ぶどうの実が生った。(醜女が)これを拾って食む間に、逃げて行く。なおも追ってくるので、また、その右の御美豆良に刺していた神聖な爪櫛の歯を折り取って投げると、たちまち笋が生えた。(醜女が)これを拔き食む間に、逃げて行った。また、その後には、八種の雷神に、千五百の黄泉軍を副えて追わせた。そこで、腰に帯びていた十拳劒を拔いて、後手に振りながら逃げて来た。なおも追いかけて、黄泉比良坂のふもとに到った時、そのふもとに生えていた桃子を3つ取って、待ち撃ったところ、ことごとく逃げ返った。
そこで伊耶那岐命は、その桃子に「お前が私を助けたように、葦原中国に生きているあらゆる人々(青人草)が苦しい目にあって患い困る時に助けるがよい。」と告げて、意富加牟豆美命という名を授けた。
最後に、その妹伊耶那美命が自ら追ってきた。そこで、千人かかってやっと引きうごかせるくらいの岩をその黄泉比良坂に引き塞いで、その岩をあいだに置いて、おのおの向かい立って、離縁を言い渡した時、伊耶那美命が「愛しい我が夫の命よ、このようにされるならば、私はあなたの国の人草を、一日に千人絞め殺しましょう。」と言った。そこで、伊耶那岐命は「愛しい我が妻の命よ、お前がそのようにするならば、私は一日に千五百の産屋を建てよう。」と言った。
こういうわけで、一日に必ず千人死に、一日に必ず千五百人生まれるのである。ゆえに、その伊耶那美命を号けて黄泉津大神という。また言うには、その追って来たのをもって道敷大神という。また、その黄泉の坂に塞いだ石は、道反之大神と名付け、また塞ぎ坐す黄泉戸大神ともいう。ゆえに、其のいわゆる黄泉比良坂は、今、出雲国の伊賦夜坂という。
※音指定の「注」は、訳出を分かりやすくするため割愛。
於是、欲相見其妹伊邪那美命、追往黃泉國。爾自殿騰戸出向之時、伊邪那岐命語詔之「愛我那邇妹命、吾與汝所作之國、未作竟。故、可還。」爾伊邪那美命答白「悔哉、不速來、吾者爲黃泉戸喫。然、愛我那勢命那勢二字以音、下效此入來坐之事恐。故、欲還、且與黃泉神相論。莫視我。」如此白而還入其殿內之間、甚久難待、故、刺左之御美豆良三字以音、下效此湯津津間櫛之男柱一箇取闕而、燭一火入見之時、宇士多加禮許呂呂岐弖此十字以音、於頭者大雷居、於胸者火雷居、於腹者黑雷居、於陰者拆雷居、於左手者若雷居、於右手者土雷居、於左足者鳴雷居、於右足者伏雷居、幷八雷神成居。
於是伊邪那岐命、見畏而逃還之時、其妹伊邪那美命言「令見辱吾。」卽遣豫母都志許賣此六字以音令追、爾伊邪那岐命、取黑御𦆅投棄、乃生蒲子。是摭食之間、逃行、猶追、亦刺其右御美豆良之湯津津間櫛引闕而投棄、乃生笋。是拔食之間、逃行。且後者、於其八雷神、副千五百之黃泉軍、令追。爾拔所御佩之十拳劒而、於後手布伎都都此四字以音逃來、猶追、到黃泉比良此二字以音坂之坂本時、取在其坂本桃子三箇待擊者、悉迯返也。
爾伊邪那岐命、告其桃子「汝、如助吾、於葦原中國所有宇都志伎此四字以音青人草之落苦瀬而患惚時、可助。」告、賜名號、意富加牟豆美命。自意至美以音。
最後、其妹伊邪那美命、身自追來焉。爾千引石引塞其黃泉比良坂、其石置中、各對立而、度事戸之時、伊邪那美命言「愛我那勢命、爲如此者、汝國之人草、一日絞殺千頭。」爾伊邪那岐命詔「愛我那邇妹命、汝爲然者、吾一日立千五百產屋。」
是以、一日必千人死・一日必千五百人生也。故、號其伊邪那美神命、謂黃泉津大神。亦云、以其追斯伎斯此三字以音而、號道敷大神。亦所塞其黃泉坂之石者、號道反大神、亦謂塞坐黃泉戸大神。故、其所謂黃泉比良坂者、今謂出雲國之伊賦夜坂也。
※『古事記』上巻より抜粋

『古事記』黄泉国訪問、生と死の断絶の解説
『古事記』黄泉国訪問、生と死の断絶、、いかがでしたでしょうか?
最愛の人(神)を失った伊邪那岐命が、もういちど見たいと欲して黄泉国へ。ところが、、遅いって言われるし見るなって言われるし、、、で、結局見ちゃったんですけど、まースゴイ、、蛆がたかってるわ、雷神がいるわで、、、そりゃびっくりして逃げたくもなります?
その後の逃走劇、離縁の泥仕合含め、もはや、人間そっくりの二神。。人間に負けず劣らずのドラマ展開。
ポイントはまさにココで。
日本神話全体の流れの中で、今回の「黄泉国往来譚」の位置付け、意味としては、人間のように行動する神による多様なストーリー展開であり、人間っぽい反応がベースになってるからこそ突然発生するイベントも違和感なく織り込まれてる、ってこと。ココ、結構重要。
特に、今回は死がテーマ。神の話なんだけど、私たちと違いすぎる神の話だと、自分たちに引きつけて考えられない。人間っぽい神だからこそ、感情移入もできて、そこで展開される物語を自分事として理解できる訳で。死の話であれば尚更です。
て、考えると、本当によく出来てて、、、国生みで布石を打って、段階的に人間モデルに移行、そのうえで黄泉国行きがある、非常に練られた構成になってること、このシーンだけで解釈するのではなく、神話全体の中でチェックです。
ちなみに、、
今回も、ちょいちょい『日本書紀』と比較することで、重視しているポイント、伝えたいことを深堀りします。
「黄泉国訪問と生と死の断絶」と同じ流れを持つのは、『日本書紀』第五段〔一書6〕。
そっくりや。。。是非チェック。
ということで、
以下、詳細解説です。
- ここに、(伊耶那岐命は)伊耶那美命に会おうと欲って、黄泉国に追っていった。
- 於是、欲相見其妹伊邪那美命、追往黃泉國。
→感情表現に注目。
「伊耶那美命に会おうと欲って」とあります。「欲」という漢字が使われてる。サラッと流さないで。。コレ、まさに人間モデル神ならではの表現。
国生み神話の中で、結婚し交合し激しく愛しあってきたからこそ、天神指令の修理固成を一緒にやり遂げようとしてたパートナーだからこそ、、、神避った伊邪那美命に、もう一度会いたい感情が湧き上がる。それが「欲」に集約されてる。黄泉国行きを、神話のストーリー展開の中にナチュラルに織り込む技法がココに。。
ちなみに、、、今回の伊邪那岐命、リーダシップ論の一つ、PM理論で整理すると分かりやすくなったりします。。突然どうした?
- P:目標達成機能 →中断した修理固成をやり遂げる
- M:集団維持機能 →愛する伊邪那美命に会いにいく
ココでは、伊邪那岐命は、Mの機能が表出されてます。この後、Pが登場。ま、それはいいか、、、
続けて、
「黄泉国に追っていった」とあります。コレ、つまり、この世界と黄泉国とは繋がってるってこと。なので、死者を追っていくと辿り着ける!
って、スゴイ世界観ですよね。死生観に入りつつありますが、、、神の時代は、この世界と死の世界は繋がってたんすよ、、生の側から死の世界へ行ける、
コレってつまり、逆に言うと、死の世界からもこちら側へ来られるってことですよね。それでいいのか!? ということで、最後の絶縁に繋がっていく訳です。ある意味、絶縁に向けた伏線とも言えて、、よく考えられた設定であります。
ちなみに、『日本書紀』版の黄泉往来譚も同様の設定になってます。「こうした後に、伊奘諾尊は伊奘冉尊を追って黄泉に入り及びいたって共に語った。(『日本書紀』第五段〔一書6〕より)」こちらもチェック。
次!
- そうして、(伊耶那美命が)御殿の閉じられた戸から出て迎えた時、伊耶那岐命は「愛おしい我が妻の命、私とお前が作った国は、まだ作り終えていない。だから還ろう。」と語りかけた。すると、伊耶那美命は答えて「残念なことです。あなたが早くいらっしゃらなくて。私は黄泉のかまどで煮炊きしたものを食べてしまいました。けれども、愛しき我が夫の命よ、この国に入り来られたことは恐れ多いことです。なので、還ろうと欲いますので、しばらく黄泉神と相談します。私を絶対に見ないでください。」と言った。
- 爾自殿騰戸出向之時、伊邪那岐命語詔之「愛我那邇妹命、吾與汝所作之國、未作竟。故、可還。」爾伊邪那美命答白「悔哉、不速來、吾者爲黃泉戸喫。然、愛我那勢命那勢二字以音、下效此入來坐之事恐。故、欲還、且與黃泉神相論。莫視我。」
→『古事記』的黄泉国の世界観をチェック。
「(伊耶那美命が)御殿の閉じられた戸から出て迎えた時」とあります。黄泉国に、御殿がある!!??
って、実は、コレ、『古事記』では異界を象徴するものとして、非常に重要なアイテムなんです。
日本神話では、いくつかの異界が登場します。で、実は異界によってそれを象徴する建物が設定されてるんです。
- 黄泉・・・殿
- 根国・・・室
- 海神国・・・魚鱗のごと造れる客室
オモシロすぎる、、、
で、今回の、黄泉国の「殿」について言えば、実は、中国古代の志怪小説の世界が反映されてます。ま、黄泉譚の世界観やストーリー全体がココからインスピレーションを得てたりするんですが、、一番分かりやすいところでコチラ!
つまり、、、
志怪小説の「冥界往復譚」を一つの型として使用し、そこに、男と女のドラマや、生と死の断絶やらを盛り込んで、つまり、日本独自の創意工夫を入れて超絶オモロー!な世界観としてつくられたのが「黄泉往来譚」。ココ、激しくチェック。
単なる借り物ではない、独自の世界観への昇華、そして、読み物としても圧倒的にオモロー!なクオリティへ。古代日本人の創意工夫の結晶がココに。
で、その世界観とは、
死者の世界ながら、街があり、役所があり、貴人の住む住居「殿」がある。。。もちろん、従者も大勢いて、、、つまり、生きている時と同じように生活してるって世界観。ココしっかりチェック。
そして「閉じられた戸」。これ、原文でわざわざ「騰戸」とあり、元ネタとしては、『玉篇』(糸部)。「縢、緘也」とあり、「縢」は「緘」、つまり閉じる、しばるの意であるとしてるところから。なので「縢戸」は閉ざされた戸という意味になります。
死者の住む御殿の戸は閉じられてるってことなんで、生の側からすると安心できる内容ですよね。閉じられてるんだけど、愛する夫が来たので伊耶那美命は特別に出てきてお出迎えしたってことです。
次!
「伊耶那岐命は「愛おしい我が妻の命、私とお前が作った国は、まだ作り終えていない。だから還ろう。」と語りかけた。」とあります。ココも結構重要なポイント。
つまり、伊邪那岐命は、天神ミッションである「修理固成」が中断してるから、もう一度やり直すために黄泉国にやってきたってこと。先ほどのPM理論でいう、Pの目標達成機能が表出されてる。
↑リメンバー天神ミッション「修理固成」。そのさきに見据えているのは、「瑞穂の国」に仕上げていく土壌づくり、であります。
あと、「愛おしい我が妹の命」という呼びかけもチェック。
- 那迩妹(なにも)=「汝妹」男性から女性へ親愛の情を込めて呼びかける表現
- 那勢(なせ)=「汝夫」女性から男性へ親愛の情を込めて呼びかける表現
で、
- 伊耶那岐命から伊耶那美命へは「愛我那邇妹命」=愛おしい我が妻の命
- 伊耶那美命から伊耶那岐命へは「愛我那勢命」=愛おしい我が夫の命
というように対になって使われてます。以下、二神のかけあいにちょいちょい登場。
次!
「残念なことです。早くいらっしゃらなくて。」とあります。細かいけど、この世とあの世(黄泉)の非対称性、その違いがポイント。
伊耶那岐命は、伊耶那美命の神避り後、腹ばいになって哭いたり、息子を斬断したりしてたものの、直ぐに黄泉国入りしたはず。。ところが、愛する妻は残念、遅いと言う。。
コレ、つまり、この世とあの世では時間の流れ方が違う。なんなら、黄泉国の時間の流れ方が速い?ってことですよね。この世とあの世(黄泉)の非対称性、時間の流れ方が違うらしいの巻。
ちなみに、、そこに、伊耶那美命の「待ち望む気持ち」が入っていたってこともチェックしておきたい。人間モデル神なんで。待ち望む気持ちが余計に遅く感じさせた、、、てことで。
次!
「私は黄泉のかまどで煮炊きしたものを食べてしまいました。」とあります。原文「吾者爲黃泉戸喫」。ポイントは「黃泉戸喫」。「戸」=竈のこと。「喫」=口からのどを通して腹の中へと入れる。くう。くらう。たべる。なので、意味としては、黄泉のかまどで煮炊きしたものを食べる。
ポイント2つ。
「同じ釜の飯を食う」という言葉があるように、ある共同体への帰属、一員になるかどうかは、その共同体で食されてる物を食べるかどうかだったりする訳です。ということは、伊耶那岐命が「もう食べちゃったよ」と言ってるのは、私ってば黄泉の世界の一員になっちゃった、つまり元には戻れない、、、といった意味にもなるってことです。
2つ目。改めて、「竈(かまど)」があるって事は、生活があるってこと。つまり「死者の、死者としての生活がある」ってこと。先ほど解説した黄泉国の世界観のお話で。結構重要。
死んだら終わりではなく、死んでも死者としての生活が続いていく。古代の死生観としてチェックです。
次!
「しばらく黄泉神と相談します。」とあります。元の世界に還るには相談、許可が必要だってことですよね。めっちゃオモロー!な世界観です。
で、この相談する相手、「黄泉神」とは、黄泉国の統治者。長官であります。
コレ、実は、原型は「泰山府君」。唐代以降「裁き」が追加されて「閻魔大王」になっていくお話で。詳細はコチラで↓
古代中国の道教的死生観であり、市民レベルで普及していた一般的な思想、信仰として「泰山思想」てのがあって、その特徴とは、
- 統治者「泰山府君」を頂点とする役所があり、
- 死者は、死後もフツーに死者としての生活を続けていく
- 現世で善い行い→良い生活 悪い行い→苦役を受ける
といった内容。
特に、統治者を頂点とする役所の存在や、死後もフツーに死者としての生活が続く、といった世界観は『古事記』版黄泉の国に色濃く反映されてたりする訳です。
次!
「私を絶対に見ないでください。」と言った。」とあります。伊耶那美命が課す「見るなの禁」。日本神話では他にも、
- 鹿葦津姫の出産
- 豊玉姫の出産
でも同様に、見るなの禁が登場。ポイント4つ。
- 男(人間)に対して女(異類)が見るなと禁を課す。
- それは女にとって見られたくないものであり、通常は、異類の本質・本性である。
- また、それだけに、男としては余計に見たくなるという心理が働く仕掛けになってる。
- その結果、見てしまい、正体露見により、異類とは別れるほかないという必然を物語に織り込んでいる。
コレ、
古今東西の物語・伝承に共通した型(話型)なんです。
異界の女性とこの世界の男性が出会い、情を交わした後、女が課した「見てはならない」という禁忌・タブーを男が破ってしまい、女の正体を見たことにより破局を迎えるという展開。
ギリシャ神話には、オルフェウスが死んだ妻を取り戻すため冥界に行ったものの、地上に帰り着くまで彼女を振り向いてはならないというタブーを破り、結局は失敗するという類似した神話あり。このほかにも、「見るなの禁・タブー」のパターンを踏まえた神話があります。
日本の伝承でも、この「見るなのタブー」を中心的な話型とする多くの例があり、、
能の「黒塚」では、安達ケ原の老婆が課した「この奥の部屋をみてはならない」というタブーを、宿を借りた僧が破り、見ると白骨死体が山のようにあり、恐怖のあまり逃げ出した僧を、老婆(人喰い鬼)が追いかけるという展開あり。このほか、「鶴の恩返し」「浦島太郎」「見るなの座敷」とかもそうですよね。
いずれにしても、最終的には、生と死の断絶へ向かっていく訳で、そのための「きっかけ」づくりとして「見るなの禁」が設定されてる訳です。
次!
- このように言って、その御殿の中にかえり入った。その間がとても長くて待ちきれなくなった。そこで、左の御美豆良に刺している神聖な爪櫛の太い歯を一つ折り取って、一つ火を灯して入り見たところ、(伊耶那美命の身体には)蛆がたかってごろごろ音をたてうごめき、頭には大雷がおり、胸には火雷がおり、腹には黒雷がおり、陰には拆雷がおり、左の手には若雷がおり、右の手には土雷がおり、左の足には鳴雷がおり、右の足には伏雷がおり、あわせて八つの雷神が成っていた。
- 如此白而還入其殿內之間、甚久難待、故、刺左之御美豆良三字以音、下效此湯津津間櫛之男柱一箇取闕而、燭一火入見之時、宇士多加禮許呂呂岐弖此十字以音、於頭者大雷居、於胸者火雷居、於腹者黑雷居、於陰者拆雷居、於左手者若雷居、於右手者土雷居、於左足者鳴雷居、於右足者伏雷居、幷八雷神成居。
→待ちきれず見るなの禁を破って見てしまう伊耶那岐命。そこにいたのは、変わり果てた伊耶那美命の姿だった。。。
「その間がとても長くて待ちきれなくなった。」とあります。非常に人間的な表現ですよね。人間モデル神炸裂中であります。
「左の御美豆良に刺している神聖な爪櫛の太い歯を一つ折り取って」とあります。「御美豆良」とは、古代における男の髪型の一つで、髪を頭の中央で左右に分け、両耳のあたりで束ねて輪状に結んだもの。結び目に櫛を挿す場合もあったようで。今回、伊耶那岐命が使ったのもコレ。
「神聖な爪櫛」。原文「湯津津間櫛」。「ゆつ」は「斎つ」という連体助詞で「神聖な」。コレ、古代、櫛を聖なるものとしてみる価値観があったところから。男女の別なく櫛は挿してるし、例えば、八岐大蛇退治の際、素戔嗚尊は奇稲田姫を櫛に変えてたりします。
櫛の男柱とは、櫛の両端の太い歯の部分のこと。コレを折って松明とした。
で、伊耶那美命が帰り戻った御殿、コレ、実は、古代における殯の場=死体安置所が想定されてます。
殯とは、死者を埋葬するまでの長い期間、遺体を納棺して安置し、別れを惜しみ、死者の霊魂を畏れ、かつ慰め、遺体の腐敗・白骨化などの変化を確認することで最終的な「死」を確認する一連の儀礼のこと。
殯の場は暗いんすよ。だから松明を付けた。安置所なんで、当然、死体自体は腐乱してる。そんなイメージで読み解き。
「(伊耶那美命の身体には)蛆がたかってごろごろ音をたてうごめき」とあります。多分、、それまでは分からなかったんだろうな。。。櫛の松明の明かりによって初めてわかった。目視で確認。変わり果てた伊耶那美命の姿、、、こんなに汚れて穢れてるっ!なんてこった。。。って、このどうしようもない汚れっぷりがポイントで。
日本神話の展開的に言えば、ココでとことん汚れ・穢れへ振り切ることが、逆に、この後に続く禊祓の清浄さと、そこから誕生する神の神威・スゴさを支える根拠になっていく訳です。このコントラスト技法、激しくチェック。
怒りとか憎しみとか恨みとかは、その激しさ表現は比較的簡単で。でも、そこから誕生する神は主役にはなり得ない。だって、そもそもの出所がマイナスなエネルギーだから。
主役となる神、なんなら高天原の統治者たる神は、清浄さとか浄化といったプラスの、キラキラしたエネルギーを根拠とすべきで。神話的には、それが禊祓として位置付けられてるわけです。そして、その禊祓のスゴさ、清浄さのスゴさを最大に引き出すには、対極にある「半端ない汚れっぷり」が必要なのです。それが見事に物語の中で織り込まれてる。素晴らしい構想力です。
「あわせて八つの雷神が成っていた。」とありますが、コレ、『古事記』では、体を8つに分けるという共通の考え方アリ。前回のエントリでも、伊耶那岐命が迦具土神を8つに斬断し、それぞれの部位から神が成ってましたよね。
次!
- そこで、伊耶那岐命は、その姿を見て恐れて逃げ還る時に、その妹伊耶那美命が「よくも私に辱をかかせましたね」と言って、黄泉の醜女を遣わして追いかけさせた。ここに伊耶那岐命は、黒御縵を取って投げ棄てると、たちまち山ぶどうの実が生った。(醜女が)これを拾って食む間に、逃げて行く。なおも追ってくるので、また、その右の御美豆良に刺していた神聖な爪櫛の歯を折り取って投げると、たちまち笋が生えた。(醜女が)これを拔き食む間に、逃げて行った。また、その後には、八種の雷神に、千五百の黄泉軍を副えて追わせた。そこで、腰に帯びていた十拳劒を拔いて、後手に振りながら逃げて来た。なおも追いかけて、黄泉比良坂のふもとに到った時、そのふもとに生えていた桃子を3つ取って、待ち撃ったところ、ことごとく逃げ返った。
- 於是伊邪那岐命、見畏而逃還之時、其妹伊邪那美命言「令見辱吾。」卽遣豫母都志許賣此六字以音令追、爾伊邪那岐命、取黑御𦆅投棄、乃生蒲子。是摭食之間、逃行、猶追、亦刺其右御美豆良之湯津津間櫛引闕而投棄、乃生笋。是拔食之間、逃行。且後者、於其八雷神、副千五百之黃泉軍、令追。爾拔所御佩之十拳劒而、於後手布伎都都此四字以音逃來、猶追、到黃泉比良此二字以音坂之坂本時、取在其坂本桃子三箇待擊者、悉迯返也。
→日本最古のチェイス劇。
「伊耶那岐命は、その姿を見て恐れて逃げ還る時に」とあります。ポイントは、「見畏みて」という表現。
『古事記』版は、『日本書紀』版と比べると、黄泉国での目視による汚さや穢れ表現は、その数は少ないものの、内容的には強調してます。一言「見畏みて」だけなんだけど、コレ結構大事な強調ワードで。
類例として、同じ『古事記』から。
降臨した天孫「瓊瓊杵尊」に大山津見神が献上した石長比売を、天孫は「甚凶醜に因りて、見畏みて返し送りき」と、つき返す神話あり。醜いから、、、ってことで。これにより、石長比売のもつ「不動の生命」をもたらす呪力を獲得できませんでした。実は、その「不動の生命」をもたらす呪力こそ、醜の醜たる所以だったのですが、、。
で、ココでの「見畏」には、畏怖嫌厭の情を伴うものとして使われてるってことチェック。単に「畏まる」よりもっと強烈です。
これと同様に、伊耶那美命の姿を見た伊耶那岐命は、畏怖嫌厭して逃げ帰った、ということで。すんごい嫌そうな顔してる感じをしっかりチェック。
次!
「その妹伊耶那美命が「よくも私に辱をかかせましたね」と言って、黄泉の醜女を遣わして追いかけさせた。」とあります。「「よくも私に辱をかかせましたね」」って、こちらも非常に人間っぽい反応。正体が露見したことにより恥をかいたから。神が恥る。って、 あなた、、神でしたよね?
「黄泉の醜女を遣わして追いかけさせた。」とあり、原文「豫母都志許賣」。『日本書紀』では「泉津醜女」。「志許賣」と「醜女」。
「志許(シコ)」の意味は、2つあり、「醜い」という意味と、「威力のある、勇猛な」の意味。
「威力のある、勇猛な」については、例えば防人のうたう「醜の御楯」がわかりやすい。
「今日よりは 顧みなくて 大君の 醜の御楯と 出で立つ我は」(万葉集 4373番)
ココでは、「醜」は「威力が強い、屈強な」」という意味で使用されていて、「醜の御楯」とは「天皇の楯となって外敵を防ぐ者(スゴイ強いヤツ)」という意味。武人が、自分を卑下して表現。
「醜さ」と「威力があり勇猛」が「志許(シコ)」という言葉で連動してる感じがあり、古代日本人の感性をロマンとあわせて感じられる箇所です。
なので、「豫母都志許賣」。単に、黄泉の醜い女だね、キモいよね、じゃなくて、、非常に威力のある強い女、それはつまり、伊耶那美命を守る女兵士的な意味としてチェックです。
で、「八」は「多い」という意味、八人がどうのではなく、たくさんの猛女、といったイメージで整理。伊耶那美命、そうは言っても「神世七代」ジェネレーションですから。尊い神。スゲー猛女をどんだけ多く従えててもなんら不思議ではございません。
次!
「ここに伊耶那岐命は、黒御縵を取って投げ棄てると、たちまち山ぶどうの実が生った。(醜女が)これを拾って食む間に、逃げて行く。なおも追ってくるので、また、その右の御美豆良に刺していた神聖な爪櫛の歯を折り取って投げると、たちまち笋が生えた。(醜女が)これを拔き食む間に、逃げて行った。」とあります。
この逃避劇も、神話世界における物語りの一型式・話型。としてチェック。
異界から逃げる、異類に追われる、所持品を投げ異類が気に取られてるうちにさらに逃げる、、、日本でも「あおい玉あかい玉しろい玉」とかはその典型。海外でも「おこった月」とか。。。
なんで山ぶどうなの?タケノコなの?っていうと、投げるものと生えるものを対応させてるから。
| 投げるもの | 成るもの |
| 黒御縵(つる草の頭飾り) | 山ぶどう(古名:エビカズラの実) |
| 櫛 | たけのこ |
材料と成るものがしっかり対応してますよね。
次!
「その後には、八種の雷神に、千五百の黄泉軍を副えて追わせた。そこで、腰に帯びていた十拳劒を拔いて、後手に振りながら逃げて来た。」とあります。何度も申し上げますが「黄泉国」ですから。領域、人民、主権(統治者)があって、それらを守る軍隊(黄泉軍)が存在するのは当然であります。
次!
「なおも追いかけて、黄泉比良坂のふもとに到った時、そのふもとに生えていた桃子を3つ取って、待ち撃ったところ、ことごとく逃げ返った。」とあります。「黄泉比良坂」、『日本書紀』版は「泉津平坂」。表記はいずれにしても、この世とあの世の境界として坂が設定されてます。
坂=境。つまり、境界としてのスポット。
「そのふもとに生えていた桃子を3つ取って、待ち撃ったところ、ことごとく逃げ返った。」とあり、桃と鬼の話についてはコチラで詳しく↓
『論衡』(巻二十二、訂鬼篇)の引く『山海経』(海外経)はじめ古代漢籍に「大桃木」と鬼を退散させる桃の伝承あり。さらに追儺にも広がっていってます。これらの思想や概念がベースになってます。

次!
- そこで伊耶那岐命は、その桃子に「お前が私を助けたように、葦原中国に生きているあらゆる人々(青人草)が苦しい目にあって患い困る時に助けるがよい。」と告げて、意富加牟豆美命という名を授けた。
- 爾伊邪那岐命、告其桃子「汝、如助吾、於葦原中國所有宇都志伎此四字以音青人草之落苦瀬而患惚時、可助。」告、賜名號、意富加牟豆美命。自意至美以音。
→新種誕生!
なんと、、桃子にうつしき青人草、すなわち現世のあらゆる人の患いや惚みを助ける効能付与!
『日本書紀』の黄泉譚では、あくまで「此れ、桃を用ちて鬼を避らふ縁なり」という、鬼を避らう縁起、起源をもって結びとしていたのが、、、『古事記』では、この歯止めを大きく踏み越えました。
追儺をはじめとする広汎な鬼に関連した用例に当たっても、『古事記』が伝える「現世のあらゆる人の患いや惚みを助ける効能」を持つ桃の実につながる例がないだけに!独自かつ固有な展開を遂げているとみるべき。
桃じたいに鬼を避らい、退散させる呪物の地位を賦与していたところから、新しい効能付与することで桃の呪力を強調したものとしてチェックです。
ちなみに、、、
「葦原中国に生きているあらゆる人々(青人草)が」の部分。コレ、「葦原中國」「宇都志伎青人草」が登場する初の場面。
「葦原中國」は、日本、地上世界のこと。ココで初登場してるってことは、もとは、黄泉国と対比する意味合いが強かったってこと。
それまで、大八嶋国という嶋の集まりだった概念に、統治とか、生活とかを含む(ようになっていく)「葦原中国」という言葉が登場した意義は非常に大きい。日本神話全体の流れの中でも重要なポイント。
そして、「宇都志伎青人草」は人民のこと。詳しくはコチラで↓
『日本書紀』で伝える「顕見蒼生」を、『古事記』的に表現しなおしたのが「宇都志伎青人草」。その意味は、目に見えるこの世界に生きるたくさんの人々、民衆、人間のこと。
「葦原中国」という言葉が初登場し、黄泉国と対比的に使われてる中で、それとセットで「宇都志伎青人草」が使用されてるのがポイントで。
つまり、『古事記』的な「うつしき青人草」は、死の黄泉国に対して生の葦原中国に生きてる人々、という感じで、『日本書紀』よりは限定されてる訳です。あくまで、死の世界に対する生の世界「葦原中國」に生きる人々。それが「うつしき青人草」。
次!
-
最後に、その妹伊耶那美命が自ら追ってきた。そこで、千人かかってやっと引きうごかせるくらいの岩をその黄泉比良坂に引き塞いで、その岩をあいだに置いて、おのおの向かい立って、離縁を言い渡した時、伊耶那美命が「愛しい我が夫の命よ、このようにされるならば、私はあなたの国の人草を、一日に千人絞め殺しましょう。」と言った。そこで、伊耶那岐命は「愛しい我が妻の命よ、お前がそのようにするならば、私は一日に千五百の産屋を建てよう。」と言った。こういうわけで、一日に必ず千人死に、一日に必ず千五百人生まれるのである。
-
最後、其妹伊邪那美命、身自追來焉。爾千引石引塞其黃泉比良坂、其石置中、各對立而、度事戸之時、伊邪那美命言「愛我那勢命、爲如此者、汝國之人草、一日絞殺千頭。」爾伊邪那岐命詔「愛我那邇妹命、汝爲然者、吾一日立千五百產屋。」是以、一日必千人死・一日必千五百人生也。
→生と死の絶縁と黄泉譚の帰結。。。でも実態は、離婚の泥仕合。。
「千人かかってやっと引きうごかせるくらいの岩をその黄泉比良坂に引き塞いで、」とあります。『日本書紀』版も「千人所引磐石」。千人がかりで引っ張るくらい巨大な岩です。原文では「石」って書いてあるけど。。。石レベルの話ではございません。

次!
「その岩をあいだに置いて、おのおの向かい立って、離縁を言い渡した時、」とあります。巨岩を置いて言い合ってそれでも聞こえるってことは、よほどの大声だったのでしょう。。
ポイントは「離縁を言い渡した時」。原文「度事戸之時」。事戸を度す。事戸は、絶縁状のこと。それを渡すというこで離婚宣言てことなんですが、ココでチェックしたいのは、これ自体が、神様特有の言表行為であるってこと。詳しくはコチラで↓
言い立てることで言葉にした内容が実現されるという考え方。背景にあるのは、言霊の力にたいする信仰みたいなの。コレはこれで重要なのでしっかりチェック。
次!
「伊耶那美命が「愛しい我が夫の命よ、このようにされるならば、私はあなたの国の人草を、一日に千人絞め殺しましょう。」と言った。そこで、伊耶那岐命は「愛しい我が妻の命よ、お前がそのようにするならば、私は一日に千五百の産屋を建てよう。」と言った」とあります。ポイント3つ。
①お互いの呼びかけ方に注目
- 伊耶那岐命:愛しい我が妻の命よ
- 伊耶那美命:愛しい我が夫の命よ
お互いに親愛の情を込めた表現で言い交してますよね。
今まさに離縁しようとしている二神が、ここに及んでも尚、愛し合う形で呼びかけあってるところに胸キュン? 離縁することがあれば、こうありたいものです?
②伊耶那美命が1000人殺すと言った理由に注目
せっかくなんで、ふっかけた側、伊耶那美命の立場に立って考えてみましょう。コレも人間モデルならでは。
まず、伊耶那美命は、見ないでねって言ったのに見られた、恥をかいた、っていうところが起点。さらに、自分の姿を見た伊耶那岐命がびっくりして逃げ帰ったのも許せなかったはず。だって、「愛おしい我が妻の命、私とお前が作った国は、まだ作り終えていない。だから還ろう。」って言ってたやん、、あれも嘘だったの・・・?? なんなら、伊耶那美命としては、醜女を派遣して、追いかけさせただけだったかもしれず、、。それなのに、、それなのに、夫が一方的に巨岩で塞いでしまった。。。
こうした経緯をふまえると、伊耶那美命としては、自身が抱く愛情を無造作に踏みにじられたと感じてもおかしくない訳で。むしろ、そう受けとめたからこそ許し難く、だからこそ対抗手段に訴え出たと考えられるのです。
その意味では、人を殺したくて殺す訳ではないとも考えられて。。むしろ、「愛しい我が夫の命よ」と呼びかけながらも、「1000人殺す」と恨みをぶつけざるを得ない伊耶那美命の張り裂けんばかりの想いに、私たちは思いを致すべきでしょう。
そして、そうした対極の情動を一つのセリフの中にとても自然な形で同居させてる古代日本人の知恵と創意工夫に今更ながら圧倒される訳です。我らがご先祖はすでに、神話世界で文学の地平を切り拓いていた。。。スゴイですホント。
③生と死の断絶起源。死に対して生が優位に立つ日本神話的ロジック
3つ目のポイントが一番重要で。ここでの二神の掛け合いは
死に対する生の優位
が、枠組みとして設定されています。
- 死:伊耶那美命:伊耶那岐命の人民(人草)を1日1,000人絞め殺す
- 生:伊耶那岐命:1日1,500の産屋を建てる=産ませる
つまり、数字の大小で死<生であることを明確に伝えてる訳です。
死よりも生が優位にあるロジック。ここ激しく重要なのでしっかりチェック。
さらに、「こういうわけで、一日に必ず千人死に、一日に必ず千五百人生まれるのである。」とあり、離縁の泥仕合いは、男女の離婚(離縁)や生と死の別離起源譚のみならず、人口増の起源譚でもある訳ですね。
次!
- ゆえに、その伊耶那美命を号けて黄泉津大神という。また言うには、その追って来たのをもって道敷大神という。また、その黄泉の坂に塞いだ石は、道反之大神と名付け、また塞ぎ坐す黄泉戸大神ともいう。ゆえに、其のいわゆる黄泉比良坂は、今、出雲国の伊賦夜坂という。
- 故、號其伊邪那美神命、謂黃泉津大神。亦云、以其追斯伎斯此三字以音而、號道敷大神。亦所塞其黃泉坂之石者、號道反大神、亦謂塞坐黃泉戸大神。故、其所謂黃泉比良坂者、今謂出雲國之伊賦夜坂也。
→神名由来伝承の他、リアルな地名を伝えてます。
「黄泉比良坂は、今、出雲国の伊賦夜坂という。」とあり、この世とあの世の境である「黄泉比良坂」は出雲にあった!!!?
ということで、こちらをチェック。
あわせて、「伊賦夜」が起源になってる神社がコチラ。
「伊賦夜」が転じて「揖屋」になったそうで。この社周辺が「黄泉の入口」として神話的に関連づけられてた、てことです。
黄泉比良坂伝承地とあわせて地図でプロットすると以下の通り。

実際、揖夜神社の裏手の山、その向こうが「伊賦夜坂伝承地」になってて。また隣接する安来市の比婆山には「伊耶那美命」のご神陵があったりもします。
このあたりのエリアが『古事記』をベースにした黄泉とか伊耶那美命に関連してる訳ですね。この辺りは壮大な神話ロマン発生地帯であります。
黄泉の国の世界観まとめ
ということで、最後に、『古事記』版黄泉国の特徴的な所をまとめておきます。
- この世界とあの世(黄泉国)はつながっていた。境界は「黄泉比良坂」。
- 「黄泉戸喫」という黄泉の食べ物もあり。生活アリ。
- 見るなのタブーを異類の女神が課し、その本質を、この世の男神が見ることによって別離に至る。
- 尊貴な存在にはお付きの者(醜女)が付く。さらに、雷神と黄泉軍が漏れなく追加。
- 黄泉国は、国として成り立っている。国の体制上、役所あり、役所には長官=統治者がいて、統治ルールがある。ここでいう「統治者」とは「黄泉神」。黄泉国を出るときには長官への相談と許可が必要
といった感じ。
志怪小説の「冥界往復譚」を一つの型として使用し、そこに、男と女のドラマや、生と死の断絶やらを盛り込んで、つまり、日本独自の創意工夫を入れて超絶オモロー!な世界観としてつくられたのが「黄泉往来譚」。ココ、激しくチェック。
単なる借り物ではない、独自の世界観への昇華、そして、読み物としても圧倒的にオモロー!なクオリティへ。古代日本人の創意工夫の結晶がココに凝縮されてます。
『古事記』黄泉国訪問と生と死の断絶 まとめ
『古事記』黄泉国訪問と生と死の断絶
黄泉国訪問と生と死の断絶、いかがでしたでしょうか?
最後にまとめとして、日本神話全体の流れの中で、黄泉国登場の意味とは?というところをお届けです。
大きく3つ。
- 生と死の対立構造。そして死に対する生の優位を明確にすること
- 起源伝承として。天皇ですら免れない死とその後の世界を説明
- 穢れと清浄の対立構造。そして浄化プロセスからの高天原統治者の誕生
まず1つ目。
①生と死の対立構造。そして、死に対する生の優位を明確にすること
黄泉往来譚の結末。それは、伊耶那岐命と伊耶那美命の離縁・絶縁です。
神話的には、
- 伊耶那岐命・・・生であり陽
- 伊耶那美命・・・死であり陰
という対立構造があるため、これを踏襲した黄泉往来譚は、生(伊耶那岐命)と死(伊耶那美命)の断絶を伝える神話として位置づけられます。
さらに、泉津平坂での絶縁宣言には、
- 伊耶那岐命・・・1500人産む
- 伊耶那美命・・・1000人殺す
という対立構造があり、その意味は、生(1500)>死(1000)、つまり、生は死より優位であることを伝える神話でもあるってこと。
これなら安心ですね。
死は断絶されているものであり、簡単にはやってこない。しかも、生の方が優位であるというマウンティング感がサイコーの眠りをお約束します。
②起源伝承として。天皇ですら免れない死とその後の世界を説明
神話自体が持つ重要な機能として、起源譚があります。
人はなぜ死ぬのか、死んだらどうなるのか、それはいつの時代も重要な問いな訳で。
それに答えるのが神話。
日本神話風に言えば、伊耶那美命だって死ぬから。死んだら伊耶那美命のように黄泉国へ行って、死者としての生活が続くんだよ、ということになります。
③穢れと清浄の対立構造。そして浄化プロセスからの高天原統治者の誕生
こちら、次の展開につながるところとしてチェック。
黄泉国は穢れてるところなんです。その穢れ度合いと言ったら、、もうサイテーです。とにかく汚くて穢れてる。伊耶那美命の変わり果てた姿もそれを強調するための表現。
この、汚れっぷりがサイテーであればあるほど、キレイになったときのコントラスト、その清浄さはイヤでも引き立つ。これが狙い。
真逆・対極のものを置くことで、コントラストが冴えわたり、その清浄な浄化プロセスの中で誕生する神は物凄い神威を体現する、
黄泉往来譚はその意味で、このあとに続く、高天原統治者誕生のための壮大な前フリとも言える訳です。
以上、3点。しっかりチェックされてください。
続きはコチラ!ついに禊祓!三貴神の誕生です!
神話を持って旅に出よう!!!
日本神話のもう一つの楽しみ方、それが伝承地を巡る旅です。以下いくつかご紹介!
● 黄泉比良坂伝承地・伊賦夜坂伝承地
● 揖夜神社 「伊賦夜」が転じて「揖屋」に!?
● 花窟神社 千人かかってやっと引きうごかせるくらいの岩をその黄泉比良坂に引き塞いだとあり、これくらいは欲しい!
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
[itemlink post_id=”13035″] [itemlink post_id=”13037″] [itemlink post_id=”13038″] [itemlink post_id=”13039″]
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




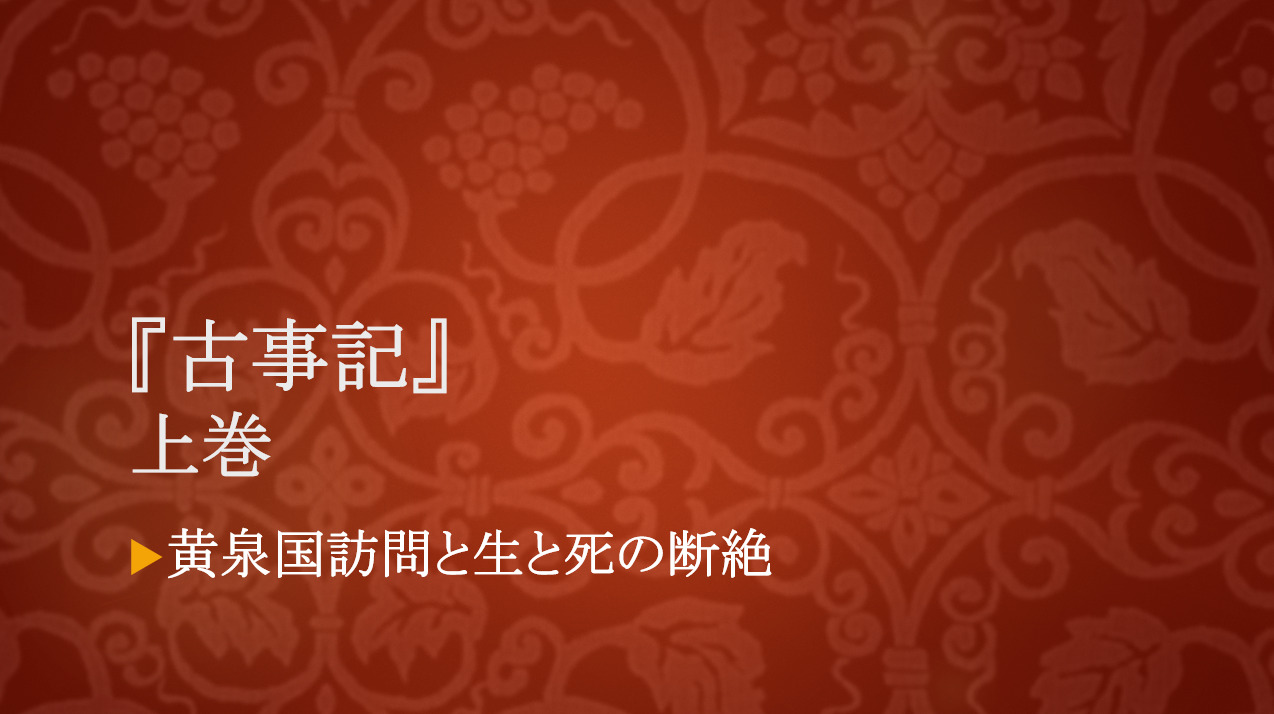
































初めまして。
日本神話でたどり着きました。
とても参考になる記事ばかりで
なるほど!っと手を打つほど
感動しています。
本題ですが、色んな神様がいるなかで
大祓詞にでてくる瀬織津姫のことも
気になりこちらにも記載しているのかなと
こちらのサイト内で検索しましたが見当たりませんでした。
また、神様が生まれた一覧にも
瀬織津姫の存在がどこにもなかったのですが
じっさいのところはどの位置に
いる神様なのでしょうか。
(見落としていたらすみません)
もしよろしければ瀬織津姫に関しての
記事を投稿していただけると幸いです。