日本神話に登場する、重要ワード、重要エピソードをディープに掘り下げる「日本神話解説シリーズ」。
今回は、
常世国
をテーマにお届けします。
常世国とは、海上遥か彼方にある理想郷。
日本神話に登場する異界の一つで、不老長寿を象徴。日本神話的には、多分、現在の三重県熊野灘のはるか向こう。
歴史の時代にも登場し、「不老長寿の実」である「非時香菓」を採ってくる伝承もあったりします。コレ、「橘」、つまりミカンのこと。
今回は、そんな「常世の国」について、日本神話や歴史伝承もふくめてディープに解説していきます。
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
常世の国とは?海上遥か彼方にある理想郷!日本神話的「常世国」を徹底解説!
常世国とは?
まずは、「常世の国」とはどんなところか?
についてご紹介。時系列てきには日本神話で登場する「常世国」が先なのですが、具体的に記述されてるのが歴史の時代なので、まずはコチラからご紹介。
登場するのは『日本書紀』垂仁天皇条。在位は垂仁天皇元年~99年。西暦に直すと、諸説ありますが紀元前後に相当。
このお方、第11代の天皇で、140歳まで生きたとか生きなかったとか。。この時点で歴史ながら神ってます。
晩年、
天皇は田道間守に、常世国に行って「非時香菓」をとってくるように命じます。
「非時香菓」とは「橘」のこと、つまりミカン。「不老長寿の実」として位置づけられていたようです。
- 天皇は知っていた。常世国があることを。
- そこには不老長寿の実である「非時香菓」がある。
- これを食べる事で永遠の命を。。。???
といった感じで、歴史の記述ながら、こちらもかなり神ってます。
その伝承現場がコチラ。
『日本書紀』巻六 垂仁天皇条
九十年の春二月の庚子の朔、天皇、田道間守に命せて、常世國に遣して、非時香菓を求めしむ。香菓、此をば箇倶能未と云ふ。今橘と謂ふは是なり。
九十九年秋七月の戊午の朔、天皇、纏向宮に崩りましぬ、時に年百四十歲。
冬十二月の癸卯の朔壬子に、菅原伏見の陵に葬りまつる。
明年の春三月の辛未の朔 壬午に 田道間守 常世國より至れり。則ち賚る物なるは、非時香菓八竿八縵。田道間守、是に、泣き悲歎きて曰す、「命を天朝に受りて、遠く、絶域に往り、萬里浪を蹈みて、遥に弱水を度る。是の常世國は、神仙の秘區、俗の臻らむ所に非ず。是を以て、往來ふ間に、自づからに十年に經りぬ。豈期ひきや、獨峻き瀾を凌ぎて、更本土に向むといふことを。然るに、聖帝の神靈に頼りて、僅に還り來ることを得たり。今天皇既に崩りましぬ、復命すこと得ず。臣生けりといえども、亦何の益かあらむ。」乃ち天皇之陵に向りて、叫び哭きて自ら死れり。群臣聞きて皆淚を流す。田道間守は、三宅連の始祖なり。
九十年春二月庚子朔、天皇命田道間守、遣常世國、令求非時香菓。香菓、此云箇倶能未。今謂橘是也。
九十九年秋七月戊午朔、天皇崩於纏向宮、時年百卌歲。冬十二月癸卯朔壬子、葬於菅原伏見陵。
明年春三月辛未朔壬午、田道間守至自常世國、則齎物也、非時香菓八竿八縵焉。田道間守、於是、泣悲歎之曰「受命天朝、遠往絶域、萬里蹈浪、遙度弱水。是常世國、則神仙祕區、俗非所臻。是以、往來之間、自經十年、豈期、獨凌峻瀾、更向本土乎。然、頼聖帝之神靈、僅得還來。今天皇既崩、不得復命、臣雖生之、亦何益矣。」乃向天皇之陵、叫哭而自死之、群臣聞皆流淚也。田道間守、是三宅連之始祖也。(『日本書紀』巻六 垂仁天皇条より一部抜粋)
●詳細解説コチラで→ 非時香菓(ときじくのかくのみ)|常世の国に生えるという不老長寿の実が奈良に!?田道間守が持ち帰った伝説の非時香菓(橘)を近鉄電車の傍で確認した!
先にポイントとなる語句解説を。
常世の国から持って帰ってきた「非時香菓八竿八縵」について。
これは、非時香菓が「八竿八縵」なので、たくさんの竿、つまり串刺し団子のような感じで串に刺した形のもの、&たくさんの縵、つまり干し柿のような感じでミカンを縄で括り付けた形のもの。
つまり、「ミカンをたくさんの串に刺した形のもの&たくさんのミカンを縄で括り付けた形のもの」のようです。常世の国の名産品???
常世の国へ渡るときに通る「弱水」について。
これは、鳥の毛すら浮いてしまうくらい比重がめちゃくちゃ軽い特別ゾーンのこと。漢籍『玄中記』には「崑崙には弱水があり、鳥の毛すら載せられない(有崑崙之弱水、鴻毛不能載)」と伝えます。フツーでは渡れない超特殊ゾーンであります。
でだ、
この伝承から言えるのは以下。
- 田道間守を常世国へ派遣して「非時香菓」を求めさせた。
- 10年後、ようやく帰還。その時、持って帰ってきたのは、非時香菓八竿八縵。
- 常世の国は海上の絶域にあり、多くの波を越え、さらに遥な弱水を渡る。
- しかも、神仙の「秘區」であって、フツーの人が行けるような場所じゃない
- 往復で10年かかる、遠いだけかもしれんけど、もしかすると流れる時間速度も違うかも
と。
ロマンだよね。
スゲーロマンだ。まずはこの世界観をしっかりチェックです。
日本神話における常世国とは?
常世の国のイメージをチェックしたところで、
ココからは、実際に日本神話で登場する「常世国」をご紹介。神話世界でどのような設定になっていたかを読み解きます。
神話世界で登場する「常世国」は2箇所。
国造り神話と建国神話。登場神は、少彦名神と三毛入野命。
ついでに、おまけとして、歴史時代ですが天照大神の伊勢神宮創始伝承もお届けします。
まずは神話世界から2つ。
『日本書紀』第八段〔一書6〕:国造り神話の中で伝える常世郷
大己貴神が少彦名命と力を合せて国作りの業を終えた後、少彦名命は「熊野の御碕」に行き、そこから「常世郷」に渡ったと伝えます。
その後、少彦名命は熊野の岬まで行き至ったところで、遂に常世郷に適ってしまった。またこれとは別に、淡嶋に至って、粟の茎をよじ登れば、弾かれて常世郷に渡り至ったという。
其後少彦名命行至熊野之御碕。遂適於常世郷矣。亦曰。至淡嶋、而縁粟茎者。則弾渡而至常世郷矣。(『日本書紀』第八段〔一書6〕より一部抜粋)

先にポイントとなる語句解説を。
「熊野之御碕」は、和歌山県熊野灘周辺にある岬。
淡嶋。この島を鳥取県米子市の上粟島や下粟島とする説(『釈紀』所引『伯耆風土記』)もあるのですが、日本海や瀬戸内海周辺で探すことができ、どれがどこと、比定できないようです。
ということで、
和歌山県熊野灘にある「熊野之御碕」から「常世郷」に往ったと。なので、常世の国は熊野灘からさらに海上方面に往ったところにあるってことですね。
『古事記』上巻の記述も、国を作り固めた後で少彦名神は常世の国に渡ったとあります。
『日本書紀』神武紀:建国神話の中で伝える常世郷
三毛入野命は神武天皇の兄。神武天皇は四人兄弟。三毛入野命は三男であります。で、東征に従軍していたのですが、熊野灘で暴風雨に遭い、嘆きごとを言いながら常世郷に往く、、、
三兄の「三毛入野命」 もまた、「我が母と姨とは共に海神である。それなのにどうして波濤を立てて溺らせるのか。」と恨み言を言い、波の先を踏んで常世の郷に往ってしまった。
三毛入野命、亦恨之曰「我母及姨並是海神。何爲起波瀾、以灌溺乎。」則蹈浪秀而往乎常世鄕矣。(『日本書紀』巻三(神武紀)より一部抜粋)
●詳細解説コチラで→ 熊野灘海難と兄の喪失|なぜ!?兄達は暴風雨の中で歎き恨み逝ってしまった件
暴風雨の中で往ってしまう訳で、その方向はやはり海上、太平洋方面になります。
『古事記』では何も伝えず上巻末尾の鵜草葺不合命の子を並べたところに、御毛沼命は波の穂を跳みて常世の国に渡ったとだけ伝えてます。
以上が、神代における常世の国の記述。なんか見えてきましたね。
おまけとして、以下。
『日本書紀』巻六 垂仁天皇条:天照大神の伊勢選択の理由
垂仁天皇条において、天照大神が伊勢の地を選んだ理由として、
この神風の伊勢国は、常世の浪の 重浪 帰する国なり。傍国の 可怜し国なり。是の国に 居らむと欲ふ。
「この神風が吹く伊勢国は、理想郷から打ち寄せてくる波が幾重にも重なって次々に打ち寄せる国。宮中から遠く離れた国だけれど、とても美しい国だ。この国に居ることにしよう。」

と伝えます。
「(伊勢は)常世の浪が幾重にも重なって次々に打ち寄せる国だ」と。「常世の浪」とは、「常世の郷から打ち寄せて来る波」。
ということで、
伊勢の国は、そんな理想郷からの波がおしよせる美しい国、だからここに住みます、と宣言した天照大神。コレも同じ場所を指してますよね。
日本神話的「常世の国」の場所
これまでご紹介した3つの伝承から、日本神話的「常世の国」がどこにあるのか?考えてみます。
- 少彦名命は「熊野の御碕=和歌山県熊野灘周辺の岬」まで行き至ったところで、常世郷に適ってしまった。
- 三兄の「三毛入野命」 は熊野周辺で暴風雨に遭遇、なんでやねんと恨み言を言いつつ、波の先を踏んで常世の国に往ってしまった。
- 伊勢国=三重県は、常世国からの波が押し寄せる所。
すべて、
紀伊半島の南東、熊野灘より海上遙か彼方を指している
ことが分かりますよね。
ということで、コチラ!

ここに、田道間守の伝承を重ねてみる。
- 田道間守を常世国へ派遣して「非時香菓」を求めさせた。
- 10年後、ようやく帰還。その時、持って帰ってきたのは、非時香菓八竿八縵。
- 常世の国は海上の絶域にあり、多くの波を越え、さらに遥な弱水を渡る。
- しかも、神仙の「秘區」であって、フツーの人が行けるような場所じゃない
- 往復で10年かかる、遠いだけかもしれんけど、もしかすると流れる時間速度も違うかも
ロマンだよね。
距離的には往復10年かかるらしいので、相当遠いイメージですが、理想郷としての位置づけになっていたことをチェックです。
まとめ
常世国
海上遥か彼方にある理想郷。日本神話に登場する異界の一つで、不老長寿を象徴。日本神話的には、多分、現在の三重県熊野灘のはるか向こう。
日本神話的には、
- 常世の国は海上の絶域にあり、多くの波を越え、さらに弱水という特殊ゾーンを渡る必要がある。
- 神仙の「秘區」であって、フツーの人が行けるような場所じゃない。
- 往復で10年かかる、遠いだけかもしれんけど、もしかすると流れる時間速度も違うかも
- 不老長寿をもたらす「非時香菓」がある。
- 伊勢の海岸には、この常世の国から波が押し寄せている。。。
ということで、
そんな世界感を是非チェックです。
常世国が登場する日本神話はコチラで!必読です!
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ(S23)。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
[itemlink post_id=”13035″] [itemlink post_id=”13037″] [itemlink post_id=”13038″] [itemlink post_id=”13039″]
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




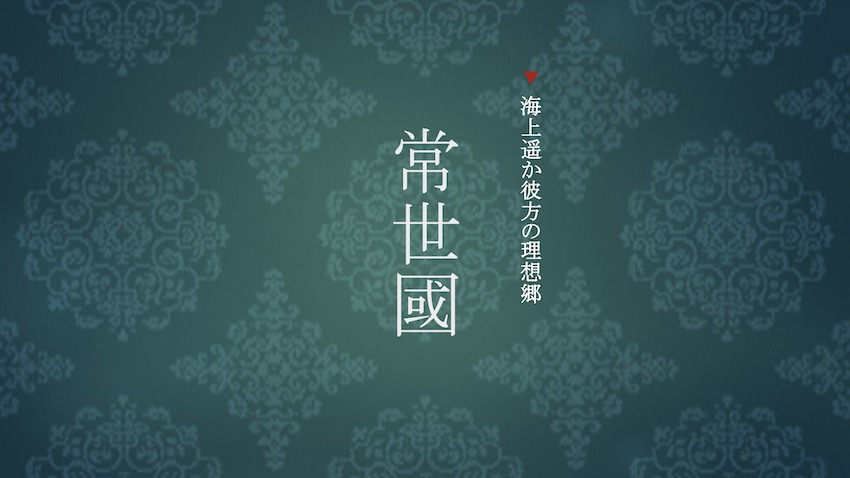




















最後までお読みいただきありがとうございます。お気軽にコメントされてくださいませ。お待ちしております!