『古事記』神話をもとに、日本神話に登場する神様を分かりやすく解説します。
今回は
「道敷大神」
『古事記』では、黄泉往来譚の最後に、伊耶那美神の別名として「道敷大神」を伝えます。
本エントリでは、「道敷大神」の名義、誕生にまつわる神話を分かりやすく解説します。
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
道敷大神|道で追いついた神&道を治める神!道敷大神の意味、活動を徹底解説!
目次
道敷大神の名義
『古事記』と『日本書紀』で名義の意味が微妙に違います。
『古事記』では、
「道敷大神」= 道を追いついた偉大な神
伊耶那岐命が黄泉国から逃走した時、伊耶那美命が黄泉比良坂で追いついたという伝承をもとに名付けられた神名。伊耶那美命の黄泉道の支配力の表象とも言えます。
「道」は、「道」の意。とくに黄泉平坂の道。
「敷」は、「及」の借訓。「追いつく、及ぶ」の意。
「大」は、「偉大な、大いなる」の意。
ということで
| 「道敷大神」=「道」+「追いつく、及ぶ」+「偉大な、大いなる」+「神」= 道を追いついた偉大な神 |
一方、『日本書紀』では、
「道敷大神」= 道道一面に力を及ぼし、その道を治める神
伊奘諾尊が黄泉から脱出する時、履を投げ捨てた時に化成した神。この履の投げ捨ては、伊奘諾尊の身に付けていたものを投げ捨てる一連の行為の中にあり、つまり、黄泉との断絶を図るための儀式の一つ。故に、黄泉から続く道を治める神として、黄泉からの影響を封じる意味が本質。
別の説では、「履が道一面に力を及ぼす」意味であり、履による歩行力の表象とされます。
道敷大神を伝える日本神話:『古事記』編
『古事記』では、
黄泉国で、伊耶那美命が課した「見るなの禁」を破り、伊耶那美命の正体が露見、伊耶那美の怒りから逃走劇に発展するところからです。
そこで、伊耶那岐命は、その姿を見て恐れて逃げ還る時に、その妹伊耶那美命が「よくも私に辱をかかせましたね」と言って、黄泉の醜女を遣わして追いかけさせた。ここに伊耶那岐命は、黒御縵を取って投げ棄てると、たちまち山ぶどうの実が生った。(醜女が)これを拾って食む間に、逃げて行く。なおも追ってくるので、また、その右の御美豆良に刺していた神聖な爪櫛の歯を折り取って投げると、たちまち笋が生えた。(醜女が)これを拔き食む間に、逃げて行った。また、その後には、八種の雷神に、千五百の黄泉軍を副えて追わせた。そこで、腰に帯びていた十拳劒を拔いて、後手に振りながら逃げて来た。なおも追いかけて、黄泉比良坂のふもとに到った時、そのふもとに生えていた桃子を3つ取って、待ち撃ったところ、ことごとく逃げ返った。 ~中略~
ゆえに、その伊耶那美命を号けて黄泉津大神という。また言うには、その追って来たのをもって道敷大神という。 (引用:『古事記』上巻の黄泉往来譚より一部抜粋)
伊耶那美命が黄泉比良坂で追いついたことを持って「道敷大神」とされます。
道敷大神を伝える日本神話:『日本書紀』編
『日本書紀』では、泉津平坂での絶縁宣言。その後の、伊奘諾尊が黄泉との断絶を図るための儀式の中で登場します。
この時には、伊奘諾尊はすでに泉津平坂に至っていた。そこで、伊奘諾尊は千人力でやっと引けるくらいの大きな磐でその坂路を塞ぎ、伊奘冉尊と向き合って立ち、遂に離縁を誓う言葉を言い渡した。
その時、伊奘冉尊は「愛しい我が夫よ、そのように言うなら、私はあなたが治める国の民を、一日に千人縊り殺しましょう。」と言った。伊奘諾尊は、これに答えて「愛しい我が妻よ、そのように言うならば、私は一日に千五百人生むとしよう。」と言った。
そこで「これよりは出て来るな。」と言って、さっと杖を投げた。これを岐神と言う。また帯を投げた。これを長道磐神と言う。また、衣を投げた。これを煩神と言う。また、褌を投げた。これを開齧神と言う。また、履を投げた。これを道敷神と言う。 (引用:『日本書紀』巻一(神代上)第五段〔一書6〕より一部抜粋)
ということで。
履の投げ捨ては、伊奘諾尊の身に付けていたものを投げ捨てる一連の行為の中にあります。
つまり、黄泉との断絶を図るための儀式の一つとしてあり、故に、黄泉から続く道を治める神として、黄泉からの影響を封じる意味が本質となります。
道敷大神を伝える文献
道敷大神・・・『古事記』上巻
道敷神・・・『日本書紀』神代上 巻1第五段〔一書6〕
参考文献:新潮日本古典集成『古事記』より 一部分かりやすく現代風修正
コチラも是非!日本神話の流れに沿って分かりやすくまとめてます!
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




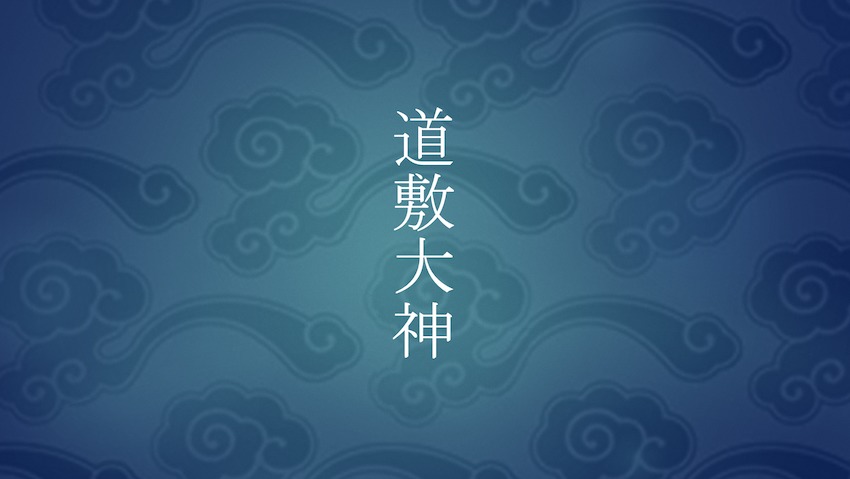

















最後までお読みいただきありがとうございます。お気軽にコメントされてくださいませ。お待ちしております!