神武天皇とはどんな人物(神)だったのか?
正史『日本書紀』をもとに、最新の文献学的学術成果も取り入れながら、神武天皇の人物(神)像をディープに解説します。
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
神武天皇とは?どんな人物(神)だったのか?『日本書紀』をもとに神武天皇を分かりやすく解説!
神武天皇とは?
まずは、神武天皇とは?という、根本のところをサラッと解説。
神武天皇とは、日本の初代天皇。日本という国を建国したお方です。
生まれは九州(諸説ありつつ、宮崎県高原町の皇子原神社とされてます)。四人兄弟の末っ子。15歳で立太子。45歳で東征発議し、6年かけて西から東へ東征。数々の苦難を経て、大和の橿原宮で初代天皇として即位。日本建国を果たす。天皇としての在位期間は、神武天皇元年1月1日 ~76年3月11日。崩御したのがこの日でした。
この東征の旅が、後に「神武東征神話」として伝えられてます。
その他、概要をまとめると以下の通り。
| 誕生年 | 庚午年(紀元前711年)1月1日 |
| 父 | 彦波瀲武盧茲草葺不合尊 |
| 母 | 玉依姫 |
| 兄弟 | 五瀬命(長兄)、稲飯命(次兄)、三毛入野命(三兄) |
| 諱 | 彦火々出見、狭野 |
| 出身 | 日向 |
| 地元のお妃 | 吾平津媛 |
| 地元で生まれた子供 | 手研耳命 |
| 東征ルート | 日向(宮崎) →宇佐(大分) →筑紫(福岡) →安芸(広島) →吉備(岡山) →浪速(大阪) →紀(和歌山) →熊野(和歌山・三重) →宇陀(奈良) →橿原(奈良) |
| 即位名 | 神日本磐余彦天皇、神日本磐余彦火火出見天皇 |
| 即位した場所 | 畝傍橿原宮 |
| 在位期間 | 神武天皇元年(紀元前661年)1月1日 – 神武天皇76年(紀元前585年)3月11日 |
| 正妃 | 媛蹈韛五十鈴媛命 |
| 正妃との間に生まれた子供 | 神八井耳命、神沼河耳命(綏靖天皇) |
| 崩御 | 神武天皇76年(紀元前585年)3月11日 |
神武天皇の活躍を伝える神武東征神話
続けて、神武天皇が何に、どこに登場するのか?基本的なところをチェック。
神武天皇の活躍を伝えるのは、『日本書紀』と『古事記』。いずれも冒頭部分で日本神話を伝える日本最古の書物、歴史書です。神の時代からそのまま神武伝承に流れ込むので、いろいろ神イベントが発生。
今回のエントリでは、日本の正史である『日本書紀』をもとにお届け。理由は、正史であること、多くの事蹟伝承が『日本書紀』をもとにしてること、『古事記』はかなり端折られていて、しかも最後は歌を歌って終わり、、的な感じでどうなのよ?状態だからです。
『日本書紀』をもとに神武天皇を深堀りすることで、神武天皇の全貌が見えてくることは間違いない!安心して読み進めてください。
ということで、
早速ですが、まずは、神武天皇が最初に登場するところをご紹介。
最初の登場は、『日本書紀』巻二(神代下)の第11段〔本伝〕。以下。
彦波瀲武盧茲草葺不合尊は、その姨の玉依姫を妃として、彦五瀬命を生んだ。次に稲飯命。次に三毛入野命。次に神日本磐余彦尊。併せて四人の男を生んだ。
ということで、この「神日本磐余彦尊」がのちの神武天皇です。
父「彦波瀲武盧茲草葺不合尊」と母「玉依姫」の間に生まれた4兄弟の末っ子として誕生。『日本書紀』巻二(神代下)の第11段〔本伝〕ではこれ以上は伝えてません。
具体的に、神武天皇の活躍を伝えてるのは、続く『日本書紀』巻三。通称「神武紀」と呼ばれる巻です。コレ、一巻まるっと使って、神武の生い立ちから、東征を経て日本の建国を果たし、崩御するまでを伝えてます。
今回のエントリで深堀り解説するのは『日本書紀』巻三。神武天皇とはどんな人物だったのか?以下6つのポイントをまとめます。
- モノスゴイ血筋と天神子
- 性格はクレバー&ストロング
- 構想力とプレゼン力がハンパない
- 挫折から学び成長する
- 天神とのつながりと加護
- 臣下を思いやる優れたリーダー
尚、『日本書紀』巻三、「神武東征神話」の概要はコチラでまとめてますのでチェックされてください。
神武天皇とはどんな人物(神)だったのか?モノスゴイ血筋と天神子
まずチェックすべきは、神武天皇の血筋。血統。
こちら、神武東征神話全体を通して、いや、なんなら日本神話全体を貫く激しく重要なテーマ。一言で言うと、
天照大神の直系。天神の直系。
『日本書紀』巻三(神武紀)では、以下のように伝えてます。
「神日本磐余彦天皇」は、「彦火火出見」を諱とし、彦波激武鸕鷀草葺不合尊の4番目の子である。母は玉依姫で、海神の娘である。
家系図を示すと以下の通り。

系図をさかのぼると、、父は「彦波激武鸕鷀草葺不合尊」、祖父は「彦火火出見尊(山幸彦)」、曾祖父は「瓊瓊杵尊」、、と最終的に「天照大神」に行きつく訳です。
さらに、祖母も「海神の娘」。もっと辿ると、ひいおばあちゃんは「山神の娘」。さらに、ひいひいおばあちゃんは「高皇産霊神の娘」。。。
父系を辿っていくと天照大神につながり、母系を辿っていくと海の神、山の神、高皇産霊神につながっていく、、、コレってつまり、
神武天皇は、天照大神の直系子孫であり、海神、山神、高皇産霊神の子孫でもある!
ってことです。
すごくない?コレ、、、
天上、いや世界の統治者の直系子孫であり、海や山という地上の支配神の血筋も持つ。果ては、東征を果たし大和の支配神の娘(媛蹈韛五十鈴媛命)とも結婚、、、文句なしのスーパー血筋であります。
神武東征神話的な解釈でいうと、これはつまり
天照大神の末裔にして、海と山、双方の支配神の血を引き継ぎ、地上の支配者として神の力と正当性とを体現する。まさに東征の主人公としてふさわしい出自、、てことになる訳ですね。
さらに、この出自、血筋は、『日本書紀』巻三(神武紀)では「天神子」として位置づけ、特別な言葉が使用されてます。明確に区別されてるんです。
以下、5つご紹介。
速吸之門に到り、珍彦、後の椎根津彦と出会ったときの件。
この時、一人の漁人が小舟に乗ってやって来た。彦火火出見はその者を招き、「お前は誰か」と問うた。その者が答えて、「私は国神です。名を『珍彦』と言います。湾曲した入江で魚を釣っています。天神子が来ると聞き、それですぐにお迎えに参りました。」と言った。
続けて、大和入りの際、最強の敵である長髄彦が脊髄反射するシーン。
その時、長髄彦がこれを聞きつけ、「天神子等がこの大和に来る理由は、我が国を奪おうとするためだろう」と言い、配下の兵をことごとく起こし、「孔舎衛坂」で遮り激しい戦闘となった。
さらに、東征神話後半、磯城彦攻略の際、帰順勧告するシーンでは、
烏は兄磯城の軍営に到り鳴き声をあげ、「天神子が、お前を召されている。さあ、さあ(招きに応じよ)」と言った。
そして
烏のあとに従って彦火火出見のもとに参上し、「私の兄の兄磯城が、天神子がいらっしゃったと聞き、八十梟帥を集めて武器を準備し、決戦を挑もうとしております。早急に手だてを講じなさいませ。」と言った。
と、、、ちょいちょい登場する「天神子」。
天神の中でも、天照大神の直系子孫を表現する言葉として使用されてるんです。
さらにさらに、細かい設定としては、「天神子」にはそれを証明する天神グッズなるものを所持してるようで。。東征神話終盤、彦火火出見=神武天皇と長髄彦の交渉のシーン。
彦火火出見は答えて「天神の子といっても大勢いる。お前の主君とする者が本当に天神の子ならば、必ずそのしるしとなる物があるはずだ。それを見せてみよ」と言った。長髄彦は早速、饒速日命の天羽羽矢一本と歩靫 とを取って彦火火出見に献上して見せた。彦火火出見はそれをよく見て「間違いない」と言い、今度は自分が身に付けていた天羽羽矢一本と歩靫とを長髄彦に下し示した。長髄彦はその天表を見て、いよいよ敬い畏まる気持ちを懐いた。
ココでは、
- 「天羽羽矢」・・・羽根で作った矢。空を飛行する鳥にちなんだ名称。
- 「歩靫」・・・背に負う矢を入れる武具。
の2つが登場。オモロー!なのは、この「証拠の品」、モノは同じなのですが、原文では実は、別の言葉が使われてるんです。
- 神武天皇(彦火火出見)のモノ=天表
- 饒速日命のモノ=表物
つまり、
- 天神子(神武天皇)の所持品=天表
- 天神の子(饒速日命)の所持品=表物
モノは同じでも、違うモノ。。「天神子」の証明品と「天神の子」の証明品とは別なんです!言い方だけかもしれんけど!
ということで、まとめると。
- 神武天皇は、天照大神の直系子孫であり、海神、山神、高皇産霊神の子孫でもある!
- 『日本書紀』巻三では、その尊い位置づけを「天神子」として表現していて、なんなら所持品も他とは区別する徹底ぶりである!
以上の2点をしっかりチェック。
次!
神武天皇とはどんな人物(神)だったのか?性格はクレバー&ストロング
神武天皇の血筋を通して、背景とか位置づけをチェックできたところで、次は、実際にどんな性格だったの?そのお人(神)柄的なところをご紹介。
まずは、神武天皇の性格について、『日本書紀』巻三(神武紀)で、具体的に伝えてるところがあるのでチェック。以下。
彦火火出見は生まれついて聡明で、何事にも屈しない強い心を持っていた。十五歳で皇太子となり、
とあり、原文では「生而明達、意礭如也」と伝えてます。
コレ、生まれながらにして英明、聡明。意志が「礭」の如し。「礭」とは、水が石に激しくあたるさま。また、その音の形容。かたくしっかりして揺るがないさま。確かなさま。意志堅固。要は、クレバー&ストロングな性格、ってことですね。
そんな神武天皇なんで、4兄弟の末っ子ながら、15歳で皇太子になる訳です。兄たちをさしおいて、、
で、
大事なのは、このクレバー&ストロング神武の性格、特性は、神武東征神話全体をとおして随所で発揮されてるってこと。
以下、主要な魅せ場をピックアップ。
①45歳という、中年、おっさんの域に突入してるのにもひるまず、兄たちや臣下を前に、東征して建国するぞ!というとんでもない構想をぶち上げるクレバー&ストロング神武。詳細は次のところで解説。
②最初の激戦「孔舎衛坂」で、兄が負傷するなど苦しい状況に追い込まれたとき、冷静に状況を分析し、解決策(神策)を導き出し即実行するクレバー&ストロング神武。素早い退却判断がナイスです。
③宇陀の高倉山に登ったときに、周りは敵だらけの絶望的状況の中、それでも東征成就、必勝の方法を見出そうと夢のお告げを引き寄せるクレバー&ストロング神武。そんな簡単にはヘコタレナイ。
④「孔舎衛坂」敗戦の学びを活かし、宇陀に入ってからは作戦変更。敵に対して、まずは帰順勧告・交渉を行い、それでも従わない場合は武力で討ち取るクレバー&ストロング神武。この学びは大きい。流石です。
と、、随所で「明達意礭如」を発揮されております。
一方で、、、そのストロングさゆえに、、一度恨みをもつと徹底的に追い詰める神武天皇の姿もあったりして。。
「孔舎衛坂」での戦闘で矢傷を負った長兄「五瀬命」が、和歌山市の竈山に至ったところで亡くなるのですが、この、長兄の薨去は、神武にとって、兄の無念を晴らす「仇討ち」の意味を東征に加えることになります。長髄彦ロックオン。
古代では、「報復」を「義務」として定めていて、殺されたのが父であれば「不倶戴天」の敵として、相手が死ぬまで報復を止めません。
五瀬命は長兄なので、弟の神武は「報復の義務」を負う。これは「兵(武器)を反さず」という言葉で伝えられ、武器を執って仇を討ち果たすまでは止めてはならない、という意味。有名な「忠臣蔵」も同じ考え方です。
実際、東征の最終局面で長髄彦を攻撃する時に、この五瀬命の薨去に思いを致し、断固とした決意をもとに、神武は「〜撃ちてし止まむ」「〜我は忘れず、撃ちてし止まむ」と来目歌を歌って戦いに臨みます。
と、、、まーかなり執念深いというか、ストロングな感じの神武天皇だったりします。
まとめます。
- 神武天皇は、生まれついて聡明で、何事にも屈しない強い心を持っていた。この性格は、神武東征神話の随所で発揮されている。
- 一方で、そのストロングさが、恨みの方に発揮されると、かたき討ちを果たすまでとことん追い詰める神武天皇の姿もあったりする。
以上2点、しっかりチェック。
次!
神武天皇とはどんな人物(神)だったのか?構想力とプレゼン力がハンパない
続けて、先ほど触れた、45歳という、中年、おっさんの域に突入してるのにもひるまず、兄たちや臣下を前に、東征して建国するぞ!というとんでもない構想をぶち上げるクレバー&ストロング神武、の部分について、詳しく解説。
こちら、東征して建国するぞ!と言い出した件、一般には「東征発議」と呼ばれてます。
で、この東征発議の内容、そのプレゼンがとにかくスゴイんです。神武天皇の人物像を語る時、これは外せないポイント。
以下、少し長いですが抜粋。日本最古の演説、プレゼンテーションであります。
(彦火火出見が)四十五歳になったとき、兄達や子供等に建国の決意を語った。
「昔、我が天神である高皇産霊尊・大日孁尊は、この豊葦原瑞穂の国のすべてを我が天祖である彦火瓊瓊杵尊に授けた。 そこで火瓊々杵尊は、天の関をひらき、雲の路をおしわけ、日臣命らの先ばらいを駆りたてながらこの国へ来たり至った。これは、遙か大昔のことであり、世界のはじめであって暗闇の状態であった。それゆえ諸事に暗く分からない事も多かったので、物事の道理を養い、西のはずれの地を治めることとした。 我が祖父と父は霊妙な神であって物事の道理に精通した聖であった。彼らは素晴らしい政により慶事を重ね、その徳を輝かせてきた。そして多くの歳月が経過した。 天祖が天から降ってからこのかた今日まで、179万2470有余年が過ぎたが、遠く遥かな地は、いまだ王の徳のもたらす恵みとその恩恵をうけていない。その結果、国には君が有り、村には長がいて、各自が支配地を分け、互いに領土を争う始末だ。 さて、一方で塩土老翁 からはこんな話を聞いた。『東に、美しい土地があって、青く美しい山が四方を囲んでいる。そこに天磐船に乗って飛びその地に降りた者がいる。』と。 私が思うに、かの地は豊葦原瑞穂の国の平定と統治の偉業を大きく広げ、王の徳を天下のすみずみまで届けるのにふさわしい場所に違いない。きっとそこが天地四方の中心だろう。そこに飛んで降りた者とは「饒速日」という者ではないだろうか。私はそこへ行き都としたい。」
諸々の皇子は、「なるほど、建国の道理は明白です。我らも常々同じ想いを持っていました。さっそく実行すべきです。」と賛同した。
と、、、まースゴイ。長い。
ポイントをまとめると以下の通り。
| 経緯 |
・遥か昔、神武の祖先である天神の「高皇産霊尊」・「大日孁尊」が、「豊葦原瑞穂の国」を神武の「天祖」である「彦火瓊瓊杵尊」に授けた。 |
| 現状認識 |
・遠く遥かな地は、いまだ王の徳のもたらす恵みとその恩恵をうけていない。その結果、争いが耐えない。→なんとかしなければならない。 |
|
目的 |
・「世界の中心」へ行き「都」としたい。 |
| 目標 (ゴール設定②) |
「世界の中心」=六合之中心 |
と、
ま、後付け整理になるかもしれませんが、それでも、自らの出自とあわせて、これまでの経緯、現状認識、建国によるメリット(王の徳による民が受ける恩恵)を分かりやすく語っていますよね。
当時の理想的指導者が「事を成す」必要性、必然性、適時性を丁寧に説明し、課題を明確にして一丸となって実行する。「日本最古の演説」ながら、そのレベルの高さにビックリです。
他にも、この発議を通して、、
①神武は、神代における二つの伝承を結びつけ、新たな神話を構想し、そのうえで、瓊々杵尊を起点とし、自らがその後継者であると位置づけた。
②神武は皇統を明らかにし、その始祖を天祖(瓊々杵尊)と位置づけることで、この世界を、天祖の天下り(天孫降臨)を直接の起源とする歴史の中に組み込んだ。
などなど、神武天皇が構想し、さりげなく入れ込んだ仕掛けとか戦略とかがとにかくスゴイ。詳しくはコチラで。
ちなみに、、、神武天皇の構想力、プレゼン力は、神武東征神話の終盤、橿原宮造営の発議でも発揮されます。以下。
3月7日、彦火火出見は命令を下した。「私が自ら東征に出発してからから、これまでに六年が過ぎた。この間、天神の神威を頼りとし、凶暴な賊どもは誅殺された。遠く辺境の地はいまだ静まらず、敵残党はなお残っているが、中洲の地はもはや兵乱に風塵がたつことはない。今まさしく、天皇の都を大きく広げ、大壮を規範として倣うのがよい。 しかるに今、時は世のはじめにあたり、民心は素朴である。彼らは穴に住み、未開の風習が常である。そもそも、聖人が制度を定めれば、大義は必ず時勢に叶うものである。いやしくも民の利益となることがあれば、聖人の業を妨げるものはないであろう。 今こそ、山林を伐り開き、宮殿を造営し、謹んで皇位に即いて、人民を安んじ治めなければならない。上にあっては天神がこの国を授けた徳に応え、下にあっては皇孫が正義を養育した心を広めよう。そして世界をひとつに合わせ都を開き、天下を覆ってひとつの家とするのだ。なんと素晴らしいことではないか。 見渡せば、あの畝傍山の東南の橿原の地は、思うに周囲を山に囲まれ、国の奥深くにある安住の地であろう。この地を整備しよう。」この月に、さっそく役人に命じて宮殿の造営を開始した。
コチラも、大きく4つのカタマリ。
| 現状認識 | ・東征に出発してからから、これまでに六年が過ぎた。 ・辺境の地はまだ静まってないが、中洲は平和になった。 |
| ベンチマーク | ・天皇の都を大きく広げ、聖人の行いを規範として倣うのがよい。 ・聖人が制度を定めれば、大義は必ず時勢に叶うものだ。 |
| 構想 | ・山林を伐り開いて宮殿を造営し、皇位に即いて人民を治めよう。 ・天神がこの国を授けた徳に応え、皇孫が正義を養育した心を広めよう。 ・世界をひとつに合わせ都を開き、天下を覆ってひとつの家としよう。 |
| 具体的内容 | ・畝傍山の東南の橿原の地は、周囲を山に囲まれ、国の奥深くにある安住の地。 ・この地を整備しよう。 |
と、まー良くできてる。
特に、都造営の意義を聖人の行いに重ねて組み立ててるのがポイント。ワイ聖人ロジック。詳しくはコチラで。
まとめます。
- クレバー&ストロング神武の中でも、東征発議や橿原宮造営発議では、その途方もない構想力、プレゼン力が遺憾なく発揮されている。
- なぜそれをする必要があるのか?理由を含めて説明することで、周りが納得して動けるような内容になっている。
以上2点、しっかりチェックです。
次!
神武天皇とはどんな人物(神)だったのか?挫折と成長
続けて、神武天皇を語るうえで、一番アツくなるお話をお届け。テーマは、、挫折と成長。
ビフォー・アフターをまとめると以下の通り。
| 1.ビフォー:東征発議~大和入り |
①自らのビジョンを熱く語り実行に移す。 ②頼もしい臣下を得る、行く先の皆さんも歓迎してくれる。 ③入念な準備。それをもって、一気に天下平定を目論む。 全般的に順調。建国ビジョンに基づき、賛同者も現れるし、入念な準備もして「コレでやったるで!」的なモード。 |
| 2.挫折:孔舎衛坂敗戦 |
ついに大和入りした初戦に敗戦。。主な理由は以下。 ①日の神の子孫の自覚を欠き、日に向かって戦った(天道に逆らう戦い)。 ②「天神子」でありながら、海から侵入し、長髄彦に自分の国を奪いに来たとの誤解を与えた。 ③いきなり戦闘に突入した。 敵を知らず、おのれのアイデンティティに無自覚のまま戦えば、敗北は必至。自分の出自やアイデンティティ的なところに無自覚なまま突っ込めば、相応の結果が返ってくる訳で、、それが孔舎衛坂敗戦の本質です。 |
| 3.アフター:宇陀入り~長髄彦最終決戦 |
失敗から学び、成長する神武天皇。それは戦い方に表れる。 ①背に日神の霊威を負い、前にできる影に従って賊を圧倒する。 ②天神神祇を礼祭する。 ③相手方に使者を派遣して、意向を確認する手順を踏む。 「天神子」というアイデンティティを自覚し、天神地祇とのつながりをもとに、敵の意思を把握しながら戦うことで、連戦連勝モードに突入。 |
ということで。
枠組みをもとに非常に良くできてます。
要は、日本神話、あるいは日本の正史『日本書紀』においては、神武天皇を完璧な人間として描いてないってことなんです。コレ、結構重要で。
そうは言っても、日本建国を果たしたお方。初代天皇です。それを、失敗なしの完璧な人物として描くのではなく、むしろ私たち同様、失敗し、そこから学び、成長する人物として描いてる。ココ、超重要。
まとめます。
- 神武天皇は、孔舎衛坂敗戦という挫折を乗り越え成長。それは戦い方の違いとして表れている。
- 失敗や挫折を通じて学び、苦難を乗り越えてビジョンを実現したからこそ、英雄になった。
以上2点、是非チェックされてください。それはそうと、神武天皇は成長しただなんて、、、私はいったい何様でしょうか??
次!
神武天皇とはどんな人物(神)だったのか?天神とのつながりと加護
続けて、神武天皇とはどんな人物だったのか?を語る上で外せない、天神とのつながりと加護のお話を。
コレ、結構深いお話で。。要は、天や神、あるいは宇宙??からの支援とか加護はどのように得られるのか?という話で。
最初に、神武天皇がこのことに気づくのが、孔舎衛坂で敗戦濃厚になったとき。以下。
東征軍は先に進むことができなかったので、彦火火出見は、この状況を憂えて、胸中に神策をめぐらした。
「今、私は日神の子孫でありながら、日に向って敵を攻撃している。これは、日を敵にまわしているのと同じで「天の道」に逆らうことだ。 ここは引き返して、かなわないと見せかけ、神祇を敬い祭り、日神の神威を背に負い、自分の前にできる影に従って襲いかかり、敵を圧倒するのがよいだろう。 こうすれば、少しも血を流さずに、敵は必ず自ら敗れるはずだ。」
ということで。
要は、
西から東へ攻め込む=日に向かって矢を向ける事であり、日神の子孫である神武にとっては天の道、道理に逆らう事。方向的に反目なので、天の加護は得られません。
逆に、東から西へ攻め込む=昇る太陽の威光を背に受けて戦う事なので、道理にかなってる。方向的に順目なので、天の加護が得られる。

↑こんな感じの大きな枠組み、それこそ天のサポートロジックがある訳です。
実際、この「神策」をもとに、大和に入るには東から西への方向転換が必要で、そのために、紀伊半島を南下、ぐるっと一周することにした次第。
そして、熊野荒坂津を起点に、東から西へ大きく方向転換。

熊野荒坂津から、大きく方向転換。東から西へ。昇る太陽の威光を背に受けて戦う事なので天の道に沿ってる。なので、さまざまな天サポート(天サポ)がつくようになるんです。例えば以下。
① 熊野の神が毒気を吹きかけ全軍昏倒の危機に瀕したとき、天照大神が救援の手を差しのべる。武甕雷神を通じて葦原中国平定のときに使用された神剣「韴霊剣」を使って、危篤状態に陥った東征一行を覚醒させる。
② 深く険しい熊野の山を越える道が分からず、進退窮まったとき、またもや天照大神が救援の手を差しのべる。今度は、「八咫烏」を遣わし、東征一行の道案内をさせる。
③ 宇陀で、周囲全部敵だらけの絶望的状況のとき、祈って寝た夢に「天神」が登場し必勝の方法を教えてくれる。天香山の土で祭器をつくり天神地祇を祀り、厳重な呪詛をすれば敵は平伏すると。実際やってみたら勝てました。
④ 長髄彦との最終決戦で、なかなか勝利を得られないとき、突然、金色の霊妙な鵄が飛来し、神武の弓の弭 に止まる。燃える火のように輝き、稲妻のように光を放つ。長髄彦の軍兵はみな目が眩み惑って反撃して戦うことができなくなる。
などなど。これらすべて、東から西へ大きく方向転換をしてから、天の道に沿うようになって得られた天サポートの事例です。
神武天皇も、神策どおり実行しつつも、最初は確信がもてなかったようですが、「八咫烏」飛来により天サポの存在を認識するようになりました。
果たして、八咫烏が空から飛んできて舞い降りた。彦火火出見は感嘆の声をあげ「この烏の飛来は、めでたい夢のとおりだ。なんと偉大なことよ、輝かしいことよ。我が皇祖の天照大神が、東征の大業を成し遂げようと助けてくれたのだ。」と言った。
ちなみに、、
こうした天照大神はじめ天神や天のサポートにより東征成就、建国を果たせた訳で。その多大なるご恩に対する奉公として、神武天皇は建国後、お祭りを行います。
4年(紀元前657年)春2月の23日、神武天皇は勅して仰せられた。「我が皇祖の神霊が天から地上をご覧になって、我が身を照らし助けてくださった。今、すでに諸々の賊は平定され、国内は平穏である。天神を郊祀って、大孝の志を申しあげねばならぬ。」そこで、鳥見山の中に斎場を設けて、その地を名付けて上小野の榛原・下小野の榛原といい、もって皇祖である天神を祭った。
「郊祀(郊外で天を祭る儀礼)」による「大孝(最大の孝行)」の実践。
東征中の数々の天サポート。その「恩」に対する「孝」としてお祭りした次第。天とのつながりを大切にする、忠義に厚い神武天皇であります。
まとめます。
- 孔舎衛坂で敗戦濃厚になった時めぐらした神策で、神武天皇は自らの出自と天とのつながり(天の道)を重視すべきことに気づいた。
- 東から西へ大きく方向転換することで、天照大神や天神や天のサポート、加護を得られるようになり、東征を成就することができた。
- いただいた天サポ(ご恩)に対するご恩がえし(孝)の実践として、鳥見山で祭祀を行った。忠義に厚い神武天皇の姿がある。
以上、3点チェックです。
次!
神武天皇とはどんな人物(神)だったのか?臣下を思いやる優れたリーダー
続けて、神武天皇とはどんな人物(神)だったのか?を語る上で、これまた外せない、臣下を思いやる優れたリーダーとしての神武天皇をご紹介。
臣下、つまり部下のモチベーション・コントロールはリーダーとしての重要なお仕事。神武天皇におけるその実践は3点。期待する、慰撫する、褒める。
まずは、「期待する」から。
国見の丘の戦いでは、彦火火出見は必ず勝つという志をもとに、東征の兵士たちに歌を詠むシーンがあります。
神風の 伊勢の海の 大石にや い這ひ廻る 細螺の 吾子よ 細螺の い這ひ廻り 撃ちてし止まむ 撃ちてし止まむ
(神風が吹く伊勢の海の大石に這いまわる細螺の如き吾が兵士よ、細螺のように国見丘を這いまわって、徹底的に(敵を)撃ちのめしてやれ。)
海辺の岩に無数にくっついてる巻貝のように、国見丘をびっしりと取り巻く東征軍の兵士たちが、強敵に執拗にまとわりついて攻撃する、撃ち平らげるまで徹底して攻めるのだと。
兵士の戦意を高めるべく「御謡」をつくり歌いかける。兵士達を鼓舞し思いのまま動かすリーダーとしての行動です。
次に、「慰撫する」です。
ところで、これより前のことであるが、東征軍は攻めては必ず敵の陣地を取り、戦っては必ず勝利してきた。しかし兵士たちが疲弊しないわけではなかった。そこで、彦火火出見は「御謠」をつくって、将兵の心を慰撫した。
楯並めて 伊那瑳の山の 木の間ゆも い行き見守らひ 戦えば 我はや飢ぬ 島つ鳥 鵜飼が伴 今助けに来ね
(伊那瑳の山の木の間を通って、敵がいつ襲ってくるかと見張りながら戦っていると、私はいよいよ腹が減ってしまったよ。鵜飼のものどもよ、今すぐ(うまい鮎をさし入れて)助けに来てくれ。)このように戦意を鼓舞した上で、ついに男軍を率いて墨坂を越え、先に出陣させた女軍と後方から挟み撃ちにして賊を破り、首領の兄磯城らを斬り殺した。
「伊那瑳の山」は、奈良県宇陀にある山とされてます。初めての土地、敵がどこから攻めてくるか分からない緊張状態の中で進軍する東征の兵卒たち。。その疲弊状態を神武天皇は敏感に感じとり、歌で慰撫した訳です。
部下たちのモチベーション、疲労度合いをきちんと見てる、現場重視の神武天皇の姿があります。
最後に、「褒める」から。
モチベーション・コントロールにおいて最重要課題。達成したこと、成し遂げたことを褒める。
例えば、コチラ。熊野の深く険しい山を突破するにあたって、臣下である「日臣命」が大活躍しました。
この時、彦火火出見は勅して日臣命を褒め称えて言った。「お前は、忠実で勇猛な臣下だ。その上、よく先導の功を立てた。この功績をもとに、お前の名を改めて『道臣』とする。」
褒め称えるほか、新しい名前を与えてます。険しい山々を突破する道を開拓したことにちなんで「道臣」。この辺りの配慮も素晴らしいですよね。
さらにさらに、宇陀を支配していた兄猾を討伐した際はこんな感じです。
彦火火出見はその酒肴を兵士達に分け与え、そこで「御謡」を詠んだ。
菟田の高城に 鴫罠はる 我が待つや 鴫は障らず いすくはし くぢら障り 前妻が 肴 乞はさば たちそばの 実の無けくを こきしひゑね 後妻が 肴 乞はさば いちさかき 実の多けくを こきだひゑね
(菟田の猟場である高城に鴫罠をかけた。獲物がかかるのを待っていると、鴫はかからず、なんと鯨がかかった。先に娶った妻が肴に欲しがったら、立木のソバの実のように肉の少ないところをいっぱいそぎ取ってやれ、新しい妻が肴に欲しがったら、サカキの実のように肉の多いところをいっぱいそぎ取ってやれ。これを来目歌と言う。
兄猾の弟である「弟猾」が献上したご馳走を、兵士たちに分け与える神武天皇。さらに!歌を詠む。で、この歌がまた、、、敵を討伐したことを受けての内容であり、その勢いにのるような感じで、きっとみんなでガッハッハと笑いあったに違いない内容になってます。そういう配慮ができるリーダーなんです。
最後に、東征成就、日本建国してから2年後。功績のあった部下たちに、褒賞を与えることもしてます。ま、これは当然といえば当然か。。
2年(紀元前659年)春2月2日、神武天皇は臣下の功績を評定して褒賞を行った。道臣命には、宅地を与え築坂邑に居所を与えられて、ことに寵愛された。また大来目には、畝傍山より西の川辺の地に居所を与えられた。今、来目邑というのは、これがその由縁である。そして、珍彦を倭国造とされた。また、弟猾に猛田邑を与えられ、それで猛田県主とされた。これは菟田主水部の遠祖である。弟磯城、名は黒速を磯城県主とされた。また剣根という者を葛城国造とされた。また、八腿烏も褒賞にあずかった。その子孫は葛野主殿県主部である。
まとめます。
- 臣下を思いやる優れたリーダーとしての神武天皇。その実践は、期待する、慰撫する、褒める、の3つ。
- 部下たちの気持ちに寄り添いモチベーション・コントロールするリーダーである。
以上、しっかりチェック。
次!
おまけ:前妻のほかに後妻も迎えたりしてます。。
本件、ほんとにおまけなのでサラッと。
神武天皇は、実は前妻として「日向国の吾田邑の吾平津媛」というお方がおりました。
彦火火出見は生まれついて聡明で、何事にも屈しない強い心を持っていた。十五歳で皇太子となり、さらに長じて、日向国の吾田邑の吾平津媛を娶って妃とし、手研耳命を生んだ。
ということで、「手研耳命」という男の子もいた模様。
ところが、、、
庚申の年、秋8月16日、彦火火出見は正妃を立てようとして、広く貴族の女を求めた。
その時、ある者がこのように奏上した。「事代主神が、三島溝橛耳神の女である「玉櫛媛」と一緒に生んだ子で、名を「媛蹈韛五十鈴媛命」と言う者がおります。この方は国中で一番麗しい娘です。」彦火火出見はこれを喜ぶ。
9月24日、媛蹈韛五十鈴媛命を宮中に召し入れて正妃とした。
とあり、前妻がおりながら新たにお妃をお求めになられております。
コレ、単に好色だったとかいう話ではなく、むしろ政略結婚的な意味合いが強いんです。
前妻の「日向国の吾田邑の吾平津媛」は、出身地である九州一帯の支配を盤石なものとする意味で、後妻の「媛蹈韛五十鈴媛命」も周りが納得する意味でそれぞれ結婚をされておられます。
ま、ここでは、ふーんという形で、一応、こんなこともしてまして的な形でチェック。
神武天皇とは?まとめ
神武天皇とは?
神武天皇とは、日本の初代天皇。日本という国を建国したお方。
生まれは九州。日向付近。四人兄弟の末っ子。15歳で立太子。45歳で東征発議し、6年かけて西から東へ東征。数々の苦難を経て、大和の橿原宮で初代天皇として即位。日本建国を果たす。天皇としての在位期間は、神武天皇元年1月1日 ~76年3月11日。崩御したのがこの日でした。この東征の旅が、後に「神武東征神話」として伝えられてます。
最初の登場は、『日本書紀』巻二(神代下)の第11段〔本伝〕。「神日本磐余彦尊」として登場。
具体的に、神武天皇の活躍を伝えてるのは、続く『日本書紀』巻三。通称「神武紀」と呼ばれる巻。コレ、一巻まるっと使って、神武の生い立ちから、東征を経て日本の建国を果たし、崩御するまでを伝えてます。
そこで伝える神武天皇像は以下の通り。
- 神武天皇は、天照大神の直系子孫であり、海神、山神、高皇産霊神の子孫でもある!
- 『日本書紀』巻三では、その尊い位置づけを「天神子」として表現していて、なんなら所持品も他とは区別する徹底ぶりである!
性格については、
- 神武天皇は、生まれついて聡明で、何事にも屈しない強い心を持っていた。この性格は、神武東征神話の随所で発揮されている。
- 一方で、そのストロングさが、恨みの方に発揮されると、かたき討ちを果たすまでとことん追い詰める神武天皇の姿もあったりする。
さらに、
- クレバー&ストロング神武の中でも、東征発議や橿原宮造営発議では、その途方もない構想力、プレゼン力が遺憾なく発揮されている。
- なぜそれをする必要があるのか?理由を含めて説明することで、周りが納得して動けるような内容になっている。
そして、
- 神武天皇は、孔舎衛坂敗戦という挫折を乗り越え成長。それは戦い方の違いとして表れている。
- 失敗や挫折を通じて学び、苦難を乗り越えてビジョンを実現したからこそ、英雄になった。
大事なのは、天神とのつながりも意識
- 孔舎衛坂で敗戦濃厚になった時めぐらした神策で、神武天皇は自らの出自と天とのつながり(天の道)を重視すべきことに気づいた。
- 東から西へ大きく方向転換することで、天照大神や天神や天のサポート、加護を得られるようになり、東征を成就することができた。
- いただいた天サポ(ご恩)に対するご恩がえし(孝)の実践として、鳥見山で祭祀を行った。忠義に厚い神武天皇の姿がある。
もちろん、部下への配慮もステキ
- 臣下を思いやる優れたリーダーとしての神武天皇。その実践は、期待する、慰撫する、褒める、の3つ。
- 部下たちの気持ちに寄り添いモチベーション・コントロールするリーダーである。
以上、是非チェックされてください。
コチラも是非!日本神話の流れに沿って分かりやすくまとめてます!
こちらの記事もどうぞ。オススメ関連エントリー
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)、他
[itemlink post_id=”13035″] [itemlink post_id=”13037″] [itemlink post_id=”13038″] [itemlink post_id=”13039″]どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




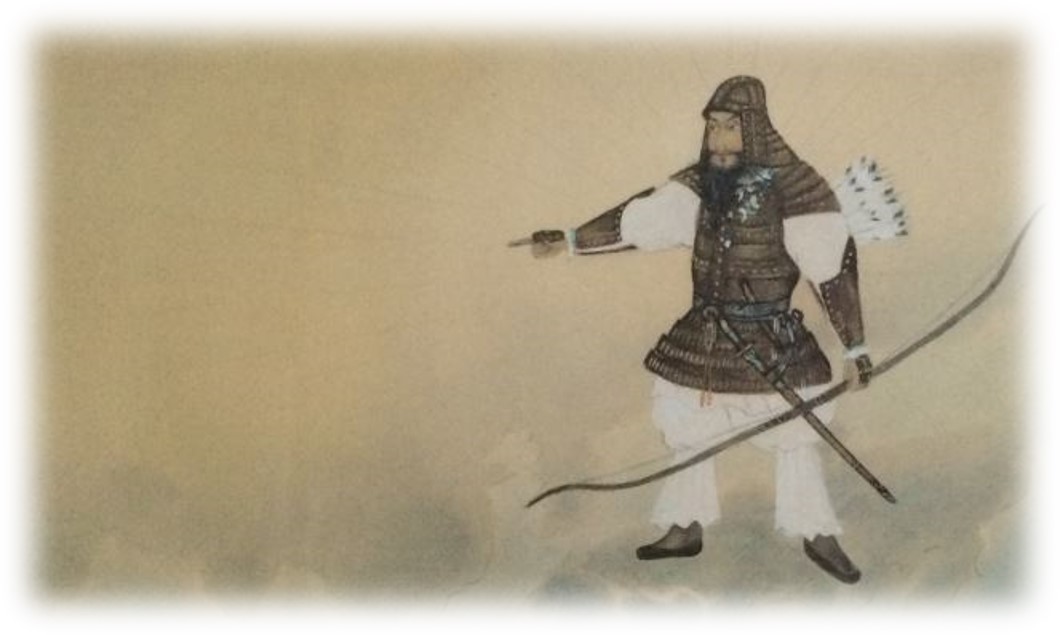































最後までお読みいただきありがとうございます。お気軽にコメントされてくださいませ。お待ちしております!