『古事記』神話をもとに、日本神話に登場する神様を分かりやすく解説します。
今回は、
「神産巣日神」
『古事記』では「神産巣日神」、『日本書紀』では「神皇産霊尊」として登場。
『古事記』では、天地がはじめておこったとき、高天原に誕生した三柱の至尊神(造化三神)のうちの一神。
独神として誕生するものの、すぐに身を隠す。
しかし、その後、高天原を追われた「須佐之男命」に手をさしのべ、また、その子孫の大国主神を支援し、さらにはこの神に「少名毘古那神」と共同して国造りを命じたりします。
一般に、この神を出雲系の祖神とみますが、あくまでもそれは出雲にかかわる神を支援、助力する役を担っていたにすぎません。
もとはと言えば、「造化三神」という位置づけからスタートしてるので、出雲に寄りすぎると「神産巣日の神」の実態から離れてしまいますので要注意。
今回は、天地がはじめておこったとき、高天原に誕生した出雲系の神の代表である「神産巣日の神」について徹底解説します。
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
神産巣日神|神々しく神聖な生成の霊力の神!造化三神の一柱!独神、別天神であり、生命体の蘇生復活を掌る神産巣日神を徹底解説!
目次
神産巣日神の名義
「神産巣日神」= 神々しく神聖な生成の霊力の神
「神」は、神の事物や行為につける接頭語。
「産巣日」の「産巣」は「苔が生す」などの「むす」で、「生成する」意味の自動詞。
用例としては、『万葉集』に大伴家持が「陸奥の国に金を出いだす詔書を賀く歌」。
「海行かば 水漬く屍、 山行かば草生す屍、 大君の辺にこそ死なめ、 かへり見はせじと 言立て」(4094番)と歌う「草生す屍」の例。
そして、『古今集』には、
「わが君は 千代に八千代に、細れ石の巌となりて、苔の生すまで」(賀)」という、「苔生す」の例、などがあります。
死体が腐ってそこに草が生えるのも、また苔が生えるのも、自然であり、条件や環境が整えばおのずから生じるもの、と考えられてた訳です。
ちなみに、この「生じる」条件や環境を提供しているのが、「高天原」という場だったりします。
もっと言うと、高天原に自然に誕生した神でもあって、その霊威、神威は抜群!と言うこともできます。
「日」は「霊的なはたらき」を意味する語で、神名の接尾語としてよく用いられます。
この、自動生成した、という意味と、霊的なはたらきをする(もちろん、超強力)、という意味は非常に重要です。
「神産巣日神」と「高御産巣日神」。
もともとは、「産霊・産日」の霊能をもつ一つの神であったのが、古代人の二元論的な思考方法から、修飾語を付けて「高御産巣日」と「神産巣日」の2つの神格として分離したものと考えられます。
以下、少々マニアックですが、論考をご紹介します。
「高御産巣日神」との対応からみると、「神産巣日神」の正式な名前は「神御産巣日神」であったと考えられます。
確かに、『日本書紀』神代紀上にも「神皇産霊」とあります。
ただ、「かむみむすひ」となると同じ音が重なるので「み」を脱落させて発音していたようです。それを文字化して「神産巣日」と書いたとすると、神名であることを踏まえると「御」を補って解釈する形になり、それが「神御産巣日神」になる、という訳です。このあたりはぐるぐるですが、へーという感じで押さえておいていただければと。
また、この神名の核が「日」にあるとする場合は、「産日むすひ」=太陽神と解釈できるため、「高御産巣日神」の霊能と同じになります。
いずれにしても、「生成・日=至上神」という「産霊・産日」の霊能をもつ一つの神であったのが、修飾語を付けて「高御産巣日」と「神産巣日」の2つの神格として分離したと考えられることはチェックしておいてください。
神産巣日神の活動と位置づけ
造化三神の一柱で、天之御中主神、高御産巣日神に次いで3番目に高天の原に化成した独神で、身を隠している別天つ神。
『古事記』ではその誕生を以下のように伝えてます。
天地初めて發りし時に、高天の原に成りませる神の名は、天之御中主の神。次に、高御産巣日の神。次に、神産巣日の神。此の三柱の神は、みな独神と成りまして、身を隠したまひき。
天地初發之時、於高天原成神名、天之御中主神。次高御產巢日神、次神產巢日神。此三柱神者、並獨神成坐而、隱身也。(『古事記』上巻より一部抜粋)
詳細解説はコチラで!
⇒「造化三神|天と地ができた原初の時に、初めて高天原に成りました三柱の神々」
⇒「独神|単独で誕生し、男女の対偶神「双神」と対応する神。」
で、
「神産巣日神」は、独神であり誕生してすぐ身を隠すのですが、その後、重要局面には登場し、生命体の蘇生復活を掌る至上神として重要な働きをします。
- 「五穀の起源」:「神産巣日の御祖の命」の名で、五穀の生みの御祖となります。
- 「大穴牟遅神の受難」:謀殺された大穴牟遅神を蘇生させます。これは、「産霊」の霊能によるものです。なので、冥界から顕界への転換を実現するくすしき神として位置づけられます。
- 「大国主神による国造り」:常世国の少名毘古那神の御祖として登場し、行き詰まる国造りに活を与えています。
- 「大国主神の国譲り」:「この、あが燧る火は、高天の原には、神産巣日の御祖の命の、とだる天の新巣の凝烟の」云々とあり、ここにおいても、この神を通じて高天の原が観念されており、「御祖の命」と呼ばれています。
と。
このように、地上の人々の回生を希求する心理が、この神を母なる「御祖の命」と表現させたのだと推測されます。
ちなみに、この神は、のちに女神として信仰されるようになります。一方、高御産巣日神は男神です。『古語拾遺』より。
神産巣日神を始祖とする氏族
- 「宿禰」姓:県犬養、間人、三島、滋野
- 「連」姓:委文、田辺、多米、竹田、爪工、天語、若倭部、屋。
- 「首おびと」姓:今木連、多米連、爪工連、物部連、和山守、和田、高家。
等々、、、この他にもあって非常に多い氏族展開。『新撰姓氏録』より。
神産巣日神の登場箇所
『日本書紀』神代上:神皇産霊尊
→「『日本書紀』巻第一(神代上)第一段 一書第1~6 体系性、統一性、系統性を持つ一書群が本伝をもとに様々に展開」
『古事記』上:神産巣日神
⇒ 『古事記』の天地開闢|原文、語訳とポイント解説!神名を連ねる手法で天地初発を物語る。
参考文献:新潮日本古典集成 『古事記』より 一部分かりやすく現代風修正
コチラも是非!日本神話の流れに沿って分かりやすくまとめてます!
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




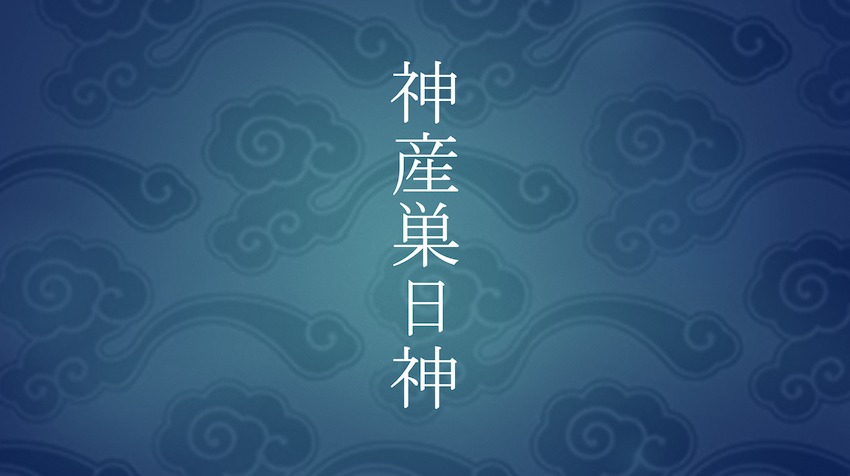















最後までお読みいただきありがとうございます。お気軽にコメントされてくださいませ。お待ちしております!