『古事記』神話をもとに、日本神話に登場する神様を分かりやすく解説します。
今回は、
高御産巣日神
造化三神の一柱で、天之御中主神に次いで二番目に高天原に成りました独神で、身を隠している別天神。
最高神の天照大御神と形影相伴うごとく活動し、皇祖神として重要なはたらきをします。
『古事記』では「高御産巣日神」、『日本書紀』では「高皇産霊尊」として登場。
今回は、「高御産巣日神」について、『古事記』を中心にディープに解説します。
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
高御産巣日神たかみむすひのかみ|高く神聖な生成の霊力の神!造化三神の一柱!独神、別天神であり「産霊」「産日」の霊能を発動。古事記、日本書紀をもとに高御産巣日神を徹底解説!
目次
高御産巣日神の名義
「高御産巣日神」 = 高く神聖な生成の霊力の神
「高」は、「高い」の意味の美称。この神の別名は「高木の神」(高い木を依代よりしろとして降臨する神)と言われてます。ここから、「高所から降臨する」という特徴に基づいた命名。
「産巣日」の「産巣」は「苔が生す」などの「むす」で、「生成する」意味の自動詞。
「日」は「霊的なはたらき」を意味する語で、神名の接尾語としてよく用いられます。
以上のことから、この神名の中核は、「産す」にあると言えます。一方で、「日」に中核があると考えることもでき、その場合は「高く神聖な、生成して止まぬ太陽」の意味となります。
ちなみに、この「産霊」としての霊能と、「産日」(太陽神)としての霊能とが『古事記』の文脈のなかで交錯するところがでてきます。
また、神産巣日神との対応関係もチェックです。
→参考:「神産巣日神|造化三神の一柱で3番目に高天の原に化成した独神。生命体の蘇生復活を掌る至上神」
高御産巣日神の活動と位置づけ
造化三神の一柱で、天之御中主神に次いで二番目に高天原に成りました独神で、身を隠している別天神。
『古事記』ではその誕生を以下のように伝えてます。
天地が初めて發った時に、高天原に成った神の名は、天之御中主神。次に、高御産巣日神。次に、神産巣日神。この三柱の神は、みな独神と成りまして、身を隠した。
天地初發之時、於高天原成神名、天之御中主神。次高御產巢日神、次神產巢日神。此三柱神者、並獨神成坐而、隱身也。(『古事記』上巻より一部抜粋)
詳細解説はコチラで!
⇒「造化三神|天と地ができた原初の時に、初めて高天原に成りました三柱の神々」
⇒「独神|単独で誕生し、男女の対偶神「双神」と対応する神。」
で、
「高御産巣日神」は
最高神の天照大御神と形影相伴うごとく登場し、皇祖神として重要なはたらきをします。
はたらきは、先ほども触れた通り2つ。
「産霊」としての「生成的霊能」と「産日」としての「司令者・至上神的霊能」です。
まず「天照大御神の天の石屋戸ごもり」の条では、その子「思金神」に命じて、衰えた太陽の蘇生復活をさせます。
これは「産霊」の発動によるもの。
次に、
「葦原の中つ国のことむけ」の段では、「天の安の河原」における会議の招集主催者となり、「天孫の誕生と降臨の神勅」の条では、娘の万幡豊秋津師比売命を「天の忍穂耳命」の妻にし、その子「邇邇芸命」を降臨させる司令者となります。
これは「産日」の霊能によるもので、皇祖神的地位にあることを示しています。
神武東征神話においては、「高倉下の献剣」の条では神剣を降し神武の危機を救い、「八咫烏の先導」の条においては、八咫烏を派遣し神武を大和に導かせています。
これは、「産霊」ならびに「産日」の発動でもあると言えます。先ほどの、交錯するとは、このことを言います。
ちなみに、、、
高天原を統治する天照大御神が「天の石屋」に籠り、「高天原皆暗く、葦原中つ国悉に闇し。これによりて常夜往きき。」という危機に際して、八百万の神がこぞって打開策を練りますが、このときに打開するための神事を統括するのが「高御産巣日の神」の子の「思金神」です。
「高御産巣日の神」自身は、天孫降臨に際して、子の「思金神」とともに葦原中国の平定に尽力する一方、天照大御神とともに降臨を命じてもいる。尚、降臨する天孫の「日子番能邇邇芸命」は、「高御産巣日の神」の外孫。
このあたりが、「高御産巣日の神」が高天原系代表と言われる所以です。
『日本書紀』で伝える高皇産霊尊
『日本書紀』では「高皇産霊尊」として登場。以下、『日本書紀』の記述より抜粋します。
〔一書4〕
ある書はこう伝えている。天地が初めて分かれ、初めに倶に生まれた(双生の)神がいた。名を国常立尊と言う。次に国狭槌尊。またこうも伝えている。高天原に生まれた神の名は、天御中主尊と言う。次に高皇産霊尊。次に神皇産霊尊。皇産霊は、ここでは「みむすひ」という。
〔一書1〕
ある書はこう伝えている。誓約の後に、稚日女尊が齊服殿に坐して神の御服を織っていた。素戔嗚尊はこれを見ると、生きたまま班駒を逆剥ぎ(尻のほうから皮を剥ぐこと)に剥いで、その殿内に投げ入れた。稚日女尊は、これに驚いて機から墜ち、持っていた梭で体を傷つけて死去した。それゆえ、天照大神は素戔嗚尊に対して「汝はやはり黒心がある。汝と会おうとは思わない。」と言い、そこで天石窟に入り、磐戸を固く閉じてしまった。ここにおいて天下は常に闇となり、昼と夜の交替も無くなってしまった。
それゆえ、八十万神を天高市(交易する市のように神の集う小高い場所)に会し(主語を明示しない)、善後策を問うた。この時、高皇産霊尊の子息の思兼神という者がいた。思慮の智があったので、思いをめぐらして「あの神の象をかたち造って、招き禱り奉るのがよい。」と申しあげたのである。それゆえさっそく石凝姥を鍛冶工とし天香山の金を採って日矛を作った。また真名鹿(愛子の愛で、愛らしい鹿)の皮を丸剥ぎにして天羽鞴(火を起こすさい風を送る道具、ふいご)を作った。これらを用いて天照大神の像を造り奉った神が、紀伊国に鎮座する日前神である。「石凝姥」は、ここでは「伊之居梨度咩」と云う。「全剥」、ここでは「宇都播伎」と云う。
『日本書紀』第八段 現代語訳
〔一書6〕
はじめ大己貴神が国を平定するに際して、行き巡り出雲国五十狹狹の小汀に到って飲食しようとした。この時、海上に忽然と人の声がした。そこで驚いて探し求めたけれども、全くなにも見当たらない。しばらくすると、一人の小男が白薟(カガイモまたヤブカラシ)の皮を舟として、鷦鷯(ミソサザイ)の羽を着衣とし、潮流に乗って浮かび到った。大己貴神はさっそく取り上げ掌中に置いてもてあそんでいると、飛び上がって頬を噛んだ。そこでその小男の形状を怪しんで、使いを遣わして天神に申しあげた。その時、高皇産霊尊はその報告を聞き、それで「私の産んだ児は全部で千五百座いる。その中の一児は最悪で、教え育てようにも従わない。私の指の間から漏れ墜ちたのが、きっとそのものだ。可愛がって養育すれば良い。」と云った。少彦名命がこれである。
『日本書紀』第九段 現代語訳
〔本伝〕
天照大神の子の正哉吾勝勝速日天忍穂耳尊は、高皇産霊尊の娘の栲幡千千姫を娶り、天津彦彦火瓊瓊杵尊を生んだ。そこで皇祖の高皇産霊尊は特に愛情を注いで貴んで養育した。こうして皇孫の天津彦彦火瓊瓊杵尊を立てて、葦原中國の君主にしようと考えた。しかし、その国には蛍火のように妖しく光る神や、五月ごろの蝿のようにうるさく騒ぐ邪神がいた。また、草や木さえもが精霊を持ち、物を言って不気味な様子であった。そこで、高皇産霊尊は多くの神々を召し集めて、問われるには「私は葦原中國の邪神どもを除き平定させようと思う。誰を遣わしたらよかろう。汝ら諸神よ、知っていることを隠さずに申せ。」と言った。皆は、「天穂日尊は傑出した神です。この神を使わしてみてはいかがでしょうか。」と言った。そこで、高皇産霊尊はこれら諸神の意見に従って天穂日尊を葦原中国の平定のために遣わせることにした。ところが、この神は大己貴神におもねり媚びて、三年たってもいっこうに報告しなかった。そこで、その子の大背飯三熊之大人――またの名は武三熊之大人――を遣わした。これもまた、その父に従って、とうとう報告に戻らなかった。
そこで高皇産霊尊は、さらに諸神を集めて、遣わすべき神を尋ねた。皆は、「天國玉の子の天稚彦は勇壮です。試してみるべきでしょう。」と言った。そこで、高皇産霊尊は天稚彦に天鹿児弓と天羽羽矢を授けて遣わした。だが、この神もまた誠実ではなかった。葦原中国に到着するや顕國玉の娘の下照姫<またの名は高姫。またの名は稚國玉>を娶って、そのまま住み着いて、「私もまた葦原中國を統治しようと思う。」と言って、報告に戻らなかった。
さて、高皇産霊尊は天稚彦が久しく報告に来ないことを不審に思い、無名雉を遣わして様子を窺わせた。その雉は飛び降って、天稚彦の門の前に植わっていた神聖な杜木の梢にとまった。すると、天探女がこれを見つけて、天稚彦に「不思議な鳥が来て、杜の梢にとまってます。」と言った。天稚彦は、高皇産霊尊から授かった天鹿児弓と天羽羽矢を手に取り、雉を射殺した。その矢は雉の胸を深く貫き通って、高皇産霊尊の御前に届いた。すると、高皇産霊尊はその矢を見て「この矢は昔、私が天稚彦に授けた矢である。見ると血が矢に染みている。思うに、これは国神と戦って血が付いたのだろうか。」と言った。そして、矢を取って下界に投げ返した。その矢は落下して、そのまま天稚彦の仰臥している胸に命中した。その時、天稚彦は新嘗の祭事をして仰眠しているところだった。その矢が命中してたちどころに死んだ。これが、世の人が「反矢恐るべし」と言うことの由縁である。
この後、高皇産霊尊はさらに神々を招集して、葦原中國に遣わすべき者を選定した。皆は、「磐裂・根裂神の子の磐筒男・磐筒女が生んだ子、經津主神がよいでしょう。」と言った。この時、天石窟に住む神である稜威雄走神の子に甕速日神がいて、その甕速日神の子に熯速日神がいて、その熯速日神の子に武甕槌神がいた。この神が進み出て、「どうして經津主神だけがひとり立派で、私は立派ではないのか」と言った。その語気は非常に激しかった。そのため、經津主神にこの神を副えて、葦原中國の平定に遣わした。
經津主神と武甕槌神の二神は、出雲國の五十田狭之小汀に降って来て、十握劒を抜いて逆さに大地に突き立てると、その剣の切っ先にあぐらをかいて座り、大己貴神に問うて「高皇産霊尊が皇孫を降らせ、この国に君臨させようと思っている。そこで、まず我ら二神を遣わし、邪神を駆除い平定させることとなった。あなたの考えはどうだ、国を譲るか否か。」と言った。すると大己貴神は「我が子に尋ね、その後で返事をしましょう。」と答えた。この時、その子の事代主神は、出雲國の三穂之碕にいて魚釣りを楽しんでいた。――あるいは、鳥の狩りをしていたとも言う。
そこで、熊野諸手船<またの名は天鴿船>に、使者の稲背脛を乗せて遣わした。そうして高皇産霊尊の勅を事代主神に伝え、その返事を尋ねた。そのとき、事代主神は使者に、「今、天神の御下問の勅がありました。我が父はお譲りするでしょう。私もまたそれと異なることはありません。」と言った。そこで、海中に幾重もの蒼柴籬を造り、船の舳先を踏み傾けて退去した。使者はそういう次第で、戻ってこのことを報告すると、大己貴神は我が子の言葉をもって二柱の神に、「私が頼りにしていた子もすでに国を譲りました。そこで、私もまたお譲りしましょう。もし私が抵抗すれば、国内の諸神もきっと同じように抵抗するでしょう。今私がお譲りすれば、誰ひとりとして従わない者はいないでしょう。」と申し上げた。そして大己貴神は、かつてこの国を平定した時に用いた広矛を二神に授け、「私はこの矛で、国の平定という功を成し遂げました。天孫がもしこの矛を用いて国を治めたならば、きっと天下は平安になるでしょう。今から私は、百足らず八十隈に隠れましょう。」と言って、言い終わるやとうとう隠れてしまった。
そして、二柱の神は帰順しない諸々の邪神たちを誅伐し、<一説には、二神はついに邪神や物を言う不気味な草・木・石の類を誅伐して、すっかり平定し終えた。唯一、従わない神は星神香香背男だけであった。そこで倭文神である建葉槌命を遣わして服従させた。そして二神は天に昇ったと言う>、ついに報告に戻った。
さて、高皇産霊尊は、真床追衾で皇孫の天津彦彦火瓊瓊杵尊を覆って降臨させた。皇孫は天磐座を押し離し、また天の八幾雲を押し分けて、威風堂々と良い道を選り分けて、日向の襲の高千穂峯に天降った。こういう次第で、そこから皇孫の出歩いた様子は、串日の二上の天浮橋から、浮島の平らなところ降り立ち、その痩せて不毛の国を丘伝いに良い国を求めて歩き、吾田の長屋の笠狭碕に辿り着いた、というものであった。
〔一書2〕
その時、高皇産霊尊は二神を出雲に戻し遣わして、大己貴神に勅して、「今お前が言うことを聞くと、深く通にかなっている。そこで、さらに条件を提示しよう。あなたが治めている現世の仕事は、我らの子孫が治めよう。あなた改めて一つ一つについて勅をしよう。そもそも、お前が治めている現世の政事は、我が皇孫が治めるのだ。お前は、幽界の神事をつかさどれ。また、おまえが住む天日隅宮は、今、造営してやろう。千尋もある長い𣑥縄で、しっかり結んで百八十結びに造り、その宮を建てるのに、柱は高く太く、板は広く厚くしよう。また、御料田を提供しよう。また、おまえが往来して海で遊ぶ備えのために、高い橋や浮橋、天鳥船も造ろう。また、天安河にも打橋を造ろう。また、繰り返し縫い合わせたじょうぶな白楯を造ろう。まら、お前の祭祀をつかさどる者は、天穂日命である。」と伝えた。そこで大己貴神は、「天神の申し出は、かくも懇切である。どうして勅命に従わないことがありましょうか。私が治めている現世の政事のことは、今後は皇孫が治めさてください。私は退いて神事を司りましょう。」と答えた。そうして岐神を二柱の神に推薦して、「この神が、私に代わって皇孫にお仕えするでしょう。私はここで退きましょう」と言って、瑞之八坂瓊を身につけて永久に隠れた。
そこで經津主神は岐神を国の先導役とし、周囲を巡りながら平定していった。反抗する者がいれば斬り殺し、帰順する者には褒美を与えた。この時に帰順した実力者が大物主神と事代主神である。そして八十萬神を天高市に集め、これらを率いて天に昇り、その柔順に至ったことを示した。
この時、高皇産霊尊は大物主神に、「おまえがもし國神を妻とするのならば、私はなお、おまえに迷いの心があると思うだろう。そこで今、私の娘の三穂津姫をおまえに娶わせて妻とさせる。八十萬神を率いて、永遠に皇孫を守って差し上げよ」と命じ、帰り降らせた。そして紀國の忌部の祖神の手置帆負神を笠作りと定めた。彦狭知神を盾作りとした。天目一箇神を鍛冶とした。天日鷲神を木綿作りとした。櫛明玉神を玉作りとした。そして太玉命の弱い肩に太い襷をかけ、代表者とした。このようにしてこの神を祭るようになったのは、これが起源である。
また、天児屋命は神事の根本を掌る神であったため、太占の占いによって仕えさせた。高皇産霊尊は、「私は天津神籬と天津磐境を造り立てて、皇孫のために祭祀をしよう。おまえたち、天児屋命と太玉命は、天津神籬を持って葦原中國に降り、また皇孫のために祭祀をしなさい」と命じ、二神を遣わして天忍穂耳尊に従わせて降らせた。この時、天照大神は手に宝鏡を持ち、天忍穂耳尊に授けて、「我が子よ、この宝鏡を見るのには、まさに私を見るようにしなさい。ともに床を同じくし、御殿をともにし、祭祀の鏡としなさい」と祝いを述べた。また、天児屋命と太玉命に、「おまえたち二神も、ともに御殿の内側に侍り、よくお守りをしなさい」と命じた。また、「私が高天原に所有する斎庭之穂を我が子に持たせなさい」と命じた。そして、高皇産霊尊の娘、名は萬幡姫を天忍穂耳尊に娶らせて妃とさせ、降らせた。そして、その途中に大空において生まれた子を天津彦火瓊瓊杵尊と言う。このため、この皇孫を親に代わって降らせようと考え、天児屋命と太玉命、及び諸氏族の神々をことごとく授け、また、衣服等の物もそれらと同様に授けた。そうした後に天忍穂耳尊は天に再び帰った。
〔一書4〕
高皇産霊尊は、真床覆衾を天津彦國光彦火瓊瓊杵尊に着せて、天磐戸を引き開けて、天の幾重もの雲を押し分けて降らせた。この時、大伴連の祖神である天忍日命が、来目部の祖神である天串津大来目を率い、背には天磐靫を背負い、腕には威力のある高鞆をつけ、手には天梔弓と天羽羽矢を取り、八目鳴鏑を取り揃え、また頭槌劒を帯びて、天孫の前に立って進み降り、日向の襲之高千穂の串日の二つの頂のある峯に辿り着き、浮島のある平らな土地に立ち、不毛の地を丘伝いに国を求めて通り、吾田の長屋の笠狭之御碕に辿り着いた。
〔一書6〕
天忍穂根尊は、高皇産霊尊の娘の栲幡千千姫萬幡姫命――または高皇産霊尊の子の火之戸幡姫の子、千千姫命と言う――を娶った。そして子の天火明命を生んだ。次に天津彦根火瓊瓊杵根尊を生んだ。その天火明命の子の天香山が尾張連等の祖神である。
皇孫の火瓊瓊杵尊を葦原中國に降臨させることになり、高皇産霊尊は多くの神々に、「葦原中國は岩の根や木の株、草の葉までがよく文句を口にする。夜は火の粉のようにやかましく、昼は蝿のようにわきあがる」と述べた――と、云々。
その時、高皇産霊尊は、「昔、天稚彦を葦原中國に遣わしたが、今に至るまで長く戻って来ないのは、國神に強靭な者がいるからだろうか」と述べ、無名雄雉を遣わして見に行かせた。この雉は降りて来るなり粟畑や豆畑を見て、そこに留まって帰らなかった。これが世に言う、雉頓使の発祥である。
そこで、また無名雌雉を遣わした。この鳥は降りて来るなり天稚彦に射られ、その矢に射上げられることで戻って報告をした――と、云々。
さて、高皇産霊尊は真床覆衾を皇孫の天津彦根火瓊瓊杵根尊に着せて、天の幾重もの雲を押し分けて、降らせた。そこで、この神を称して天國饒石彦火瓊瓊杵尊と言う。その時に降り立った所を日向の襲之高千穂の添山峯と言う。その進む時になり――と、云々。
〔一書7〕
高皇産霊尊の娘に天萬栲幡千幡姫がいた。――あるいは、高皇産霊尊の子の萬幡姫の子の玉依姫命と言う。この神が天忍骨命の妃となって、子の天之杵火火置瀬尊を生んだ。――あるいは、勝速日命の子の天大耳尊が丹潟姫を娶って、子の火瓊瓊杵尊を生んだと言う。――あるいは、神皇産霊尊の娘の栲幡千幡姫が、子の火瓊瓊杵尊を生んだと言う。――あるいは、天杵瀬命が吾田津姫を娶って、子の火明命を生んだ。次に火夜織命。次に彦火火出見尊。
2. 東征発議と旅立ち
(彦火火出見が)四十五歳になったとき、兄達や子供等に建国の決意を語った。
「昔、我が天神である高皇産霊尊・大日孁尊は、この豊葦原瑞穂の国のすべてを我が天祖である彦火瓊瓊杵尊に授けた。 そこで火瓊々杵尊は、天の関をひらき、雲の路をおしわけ、日臣命らの先ばらいを駆りたてながらこの国へ来たり至った。これは、遙か大昔のことであり、世界のはじめであって暗闇の状態であった。それゆえ諸事に暗く分からない事も多かったので、物事の道理を養い、西のはずれの地を治めることとした。 我が祖父と父は霊妙な神であって物事の道理に精通した聖であった。彼らは素晴らしい政により慶事を重ね、その徳を輝かせてきた。そして多くの歳月が経過した。 天祖が天から降ってからこのかた今日まで、179万2470有余年が過ぎたが、遠く遥かな地は、いまだ王の徳のもたらす恵みとその恩恵をうけていない。その結果、国には君が有り、村には長がいて、各自が支配地を分け、互いに領土を争う始末だ。 さて、一方で塩土老翁 からはこんな話を聞いた。『東に、美しい土地があって、青く美しい山が四方を囲んでいる。そこに天磐船に乗って飛びその地に降りた者がいる。』と。 私が思うに、かの地は豊葦原瑞穂の国の平定と統治の偉業を大きく広げ、王の徳を天下のすみずみまで届けるのにふさわしい場所に違いない。きっとそこが天地四方の中心だろう。そこに飛んで降りた者とは「饒速日」という者ではないだろうか。私はそこへ行き都としたい。」
諸々の皇子は、「なるほど、建国の道理は明白です。我らも常々同じ想いを持っていました。さっそく実行すべきです。」と賛同した。この年は、太歳・甲寅(紀元前667年)であった。
その時、彦火火出見は道臣命に勅して言った。「これから『高皇産霊尊』を祭神として、私自身が『顕斎』 を執り行う。お前を斎主として、『厳媛』の名を授ける。そして、祭りに置く埴瓮を『厳瓮』と名付け、また火を『嚴香來雷』と名付け、水を『嚴罔象女』、食べものを『厳稲魂女』、薪を『厳山雷』、草を『厳野椎』と名付けよう。」
高御産巣日神を始祖とする氏族
『新撰姓氏録』によれば、
- 「宿禰」姓:大伴、佐伯、弓削、大伴大田、斎部、玉祖、等。
- 「連」姓:忌玉作、家内、小山、等。
- 「直」姓:久米、葛木、役、荒田、等。
- 他:葛木忌寸、伊予部、恩智神主、波多祝、等。
高御産巣日神の登場箇所
高皇産霊尊 『日本書紀』神代上、神武紀
→「『日本書紀』巻第一(神代上)第一段 一書第1~6 体系性、統一性、系統性を持つ一書群が本伝をもとに様々に展開」
高御産巣日神 『古事記』上
⇒『古事記』の天地開闢|原文、語訳とポイント解説!神名を連ねる手法で天地初発を物語る。
参考文献:新潮日本古典集成 『古事記』より 一部分かりやすく現代風修正
コチラも是非!日本神話の流れに沿って分かりやすくまとめてます!
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




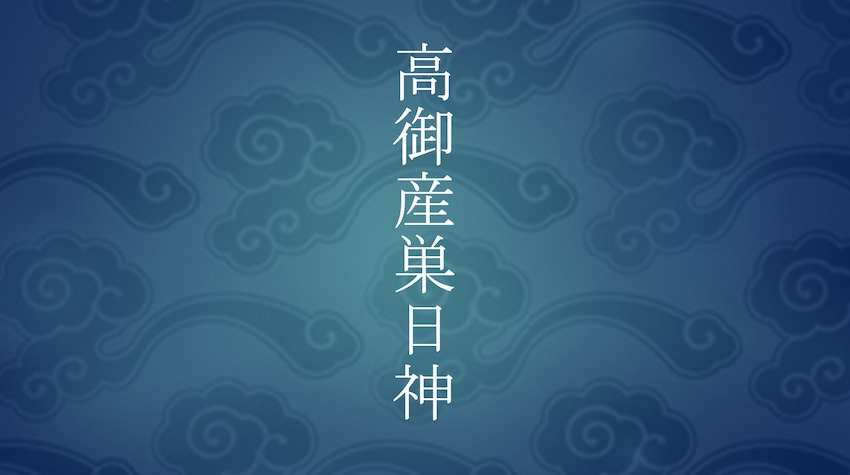
















最後までお読みいただきありがとうございます。お気軽にコメントされてくださいませ。お待ちしております!