『古事記』神話をもとに、日本神話に登場する神様を分かりやすく解説します。
今回は
「宇摩志阿斯訶備比古遅神」
『古事記』では天地初発に誕生した造化三神に続き、国が稚く浮いている脂のように海月なすただよえる時に成りました神として「宇摩志阿斯訶備比古遅神」を伝えます。『日本書紀』では「可美葦牙彦舅尊」として登場。
本エントリでは、「宇摩志阿斯訶備比古遅神」の名義、誕生にまつわる神話について、『日本書紀』もふまえて分かりやすく解説します。
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
宇摩志阿斯訶備比古遅神うましあしかびひこぢのかみ|立派な、萌え出る葦の芽の男神!国土浮漂のとき、葦芽のように勢いよく芽生え伸びてゆくものを依代として化成した独神で別天神
目次
宇摩志阿斯訶備比古遅神の名義
「宇摩志阿斯訶備比古遅神」= 立派な、萌え出る葦の芽の男神
『古事記』では、天地初発に誕生した造化三神に続き、国が稚く浮いている脂のように海月なすただよえる時に成りました神として、また、独神であり別天神として「宇摩志阿斯訶備比古遅神」を伝えます。
「宇摩志」は、良いものを心に感じて讃める語。
「阿斯訶備」は、春先に萌え出る葦の芽。
「訶備」は、「黴」と同源の言葉で、物が発酵すること、芽吹くこと。
「比古遅」は、男性への親称。
独神なので、男女の性別以前の神なのに、「比古遅」という男性への親称をつけるのはおかしいところがあるのですが、これは、葦芽の形態と勢いから、陽神として捉えたことによる命名と思われます。また、葦は元来、邪気を払う植物であったこと、また葦の生える土壌であれば稲が育つという信仰に支えられていたことも考えられます。
ということで、
| 「宇摩志阿斯訶備比古遅神」=「立派な(良いものを心に感じて讃める)」+「萌え出る葦の芽」+「男性への親称」+「神」= 立派な、萌え出る葦の芽の男神 |
宇摩志阿斯訶備比古遅神が登場する日本神話
「宇摩志阿斯訶備比古遅神」が登場するのは、『古事記』上巻、天地初発の神話。以下のように伝えてます。
次に、国が稚く浮いている脂のように海月なすただよえる時に、葦牙のように萌え騰る物に因って成った神の名は、宇摩志阿斯訶備比古遅神。次に、天之常立神。この二柱の神も、みな独神と成りまして、身を隠した。
上の件の五柱の神は、別天神である。
次、國稚如浮脂而久羅下那州多陀用幣流之時流字以上十字以音、如葦牙、因萌騰之物而成神名、宇摩志阿斯訶備比古遲神此神名以音、次天之常立神。訓常云登許、訓立云多知。此二柱神亦、獨神成坐而、隱身也。
上件五柱神者、別天神。 (『古事記』上巻、天地初発部分より一部抜粋)
ということで。
まず、天地初発に誕生する神々を整理するとこんな感じ。

▲「宇摩志阿斯訶備比古遅神」は、高天原に誕生した造化三神に続いて誕生し、五柱の別天神として位置づけられてます。
ポイント3つ。
①「宇摩志阿斯訶備比古遅神」の誕生タイミング
「国が稚く浮いている脂のように海月なすただよえる時に」とあり、天地初発の段階では、高天原(と、恐らく天も)は成っていましたが、それ以外はまだ稚く国土も水に浮く脂みたいにぷかぷか浮いている状態だったわけです。原始地球のドロドロっとしたイメージと重なる??とても想像力をかきたてられます。
次!
②「宇摩志阿斯訶備比古遅神」の誕生方法
「葦牙のように萌え騰る物に因って成った」とあり、まず「葦牙のように萌え騰る物」が誕生し、それを依代として化成したと伝えてます。この誕生方法、非常に独特で、めっちゃ日本的。
神は完全な形で誕生しません(造化三神は置いといて、、)。
まず一つの「物」として、「葦の芽の形」をして生まれる。それが神に成る。「成る」というのは「運動」です。神は完全な状態から生まれる訳ではなく、不完全な状態のモノから生まれ「変化して」神になっていくという事。ココがポイント。
「神様」というと、最初から最後まで「全知全能」や「完璧な存在」といったイメージがありますが、日本神話が伝える「神様」はそうではありません。最初は不完全な状態から生まれますし、西欧的な「全知全能」といった完璧さは持ち合わせていません。
自然から誕生する神のイメージ。それは、完璧ではない神。それは完璧ではない自然、刻々と変化していく自然の現れなのだと考えられます。この、古代日本人が描いていた世界観や価値観をしっかりチェック。
次!
③「宇摩志阿斯訶備比古遅神」の誕生場所
誕生場所については、、、これは諸説入り乱れる感じで。。。実はよく分かりません。『古事記』では国土のような気もするけどなんとも、、、
ということで、参考として、『日本書紀』で伝える「可美葦牙彦舅尊」をチェック。
『日本書紀』では、全部で3つの伝承があります。『日本書紀』巻一(神代上)第一段から、異伝である〔一書2〕〔一書3〕〔一書6〕に登場。
以下。
ある書はこう伝えている。昔、国も土地もできて間もなく幼かったころは、例えるなら水に浮かんだ脂の状態で漂っていた。そんな時、国の中に物が生まれた。その形は葦の芽が突き出たようであった。これにより変化して生まれた神があった。その名を可美葦牙彦舅尊と言う。次に国常立尊。次に国狭槌尊。葉木国は、ここでは「はこくに」という。可美は、ここでは「うまし」という。
一書曰、古、国稚地稚之時、譬猶浮膏而漂蕩。于時、国中生物。状如葦牙之抽出也。因此有化生之神。号可美葦牙彦舅尊。次国常立尊。次国狭槌尊。葉木国。此云播挙矩爾。可美、此云于麻時。 (『日本書紀』巻一(神代上)第一段〔一書2〕より)
ということで。
異伝のひとつめ〔一書2〕では、「国の中に物が生まれた。その形は葦の芽が突き出たようであった。これにより変化して生まれた神があった。その名を可美葦牙彦舅尊と言う。」とあり、国の中に生まれたと伝えてます。
続けて、
ある書はこう伝えている。天と地が混じり合って成った時、初めに神人(神である人、神そのものとも言うべき人)がいた。その名を可美葦牙彦舅尊と言う。次に国底立尊。彦舅は、ここでは「ひこぢ」という。
一書曰、天地混成之時、始有神人焉。号可美葦牙彦舅尊。次国底立尊。彦舅、此云比古尼。 (『日本書紀』巻一(神代上)第一段〔一書3〕より)
ということで。
異伝のふたつめ〔一書3〕では、「天と地が混じり合って成った時、初めに神人(神である人、神そのものとも言うべき人)がいた。その名を可美葦牙彦舅尊と言う。」とあり、詳細は不明。最初から「神人」がいたと伝えてるのが特徴です。
続けて、
ある書はこう伝えている。天地が初めて分かれ、物があった。葦の芽が空中に生じたようであった。これによって変化した神は、天常立尊と言う。次に可美葦牙彦舅尊。また、物があった。浮かぶ脂が空中に生じたようであった。これによって変化した神は、国常立尊と言う。
一書曰、天地初判、有物。若葦牙生於空中。因此化神。号天常立尊。次可美葦牙彦舅尊。又有物。若浮膏生於空中。因此化神。号国常立尊。 (『日本書紀』巻一(神代上)第一段〔一書6〕より)
ということで、
異伝のみっつめ〔一書6〕では、「天地が初めて分かれ、物があった。葦の芽が空中に生じたようであった。これによって変化した神は、 ~中略~ 次に可美葦牙彦舅尊。」とあり、天と地のあいだ、空中に誕生したと伝えてます。
以上の事から、
大きく2つ説があり、「国の中に誕生した」または「空中に誕生した」のいずれかということになります。
『古事記』に戻って。
そうは言っても、『古事記』的には「宇摩志阿斯訶備比古遅神」は「別天神」としてフォルダに入ってますから、天の側、つまり、空中に誕生したとするのが妥当。この神を天神としたのは、葦の芽が中空にあってなお、天を志向しているからとも言えて。その形態と萌え出る勢いがこの神の本質と考えられます。

宇摩志阿斯訶備比古遅神を始祖とする氏族
無し
参考文献:新潮日本古典集成 『古事記』より一部分かりやすく現代風に修正。
宇摩志阿斯訶備比古遅神が登場する日本神話の詳しい解説はコチラ!
宇摩志阿斯訶備比古遅神をお祭りする神社
● 出雲路幸神社 本殿の右裏手、結界の中に鎮座する陽石が御神体!
住所:京都府京都市上京区幸神町303● 物部神社 別天神 別天神の皆さんがそろってお祭り中!
住所:島根県大田市川合町川合1545● 間山豊富神社 弥生時代からお祭り中!?
住所:長野県中野市大字間山字宮上262
コチラも是非!日本神話の流れに沿って分かりやすくまとめてます!
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




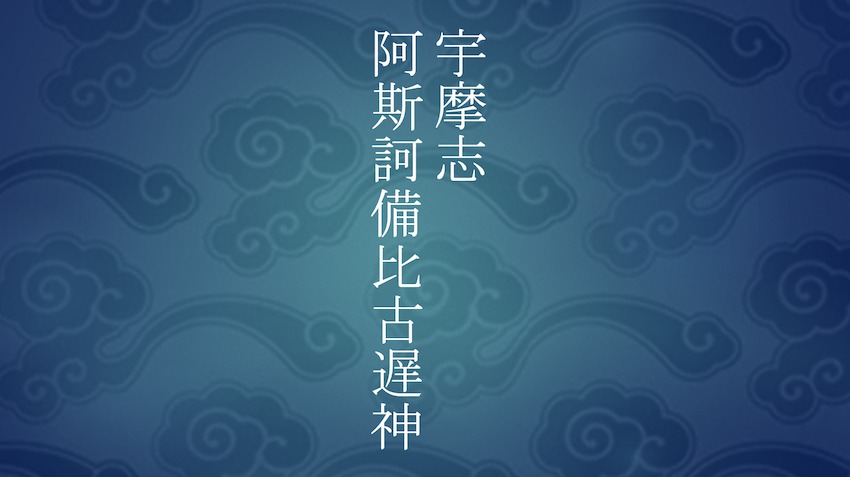

















最後までお読みいただきありがとうございます。お気軽にコメントされてくださいませ。お待ちしております!