多彩で豊かな日本神話の世界へようこそ!
正史『日本書紀』をもとに、最新の文献学的学術成果も取り入れながら、どこよりも分かりやすい解説をお届けします。題して、おもしろ日本神話シリーズ。
今回は、『日本書紀』巻第一(神代上)第一段の一書の皆さん。
本伝で伝える「天地開闢と三柱の神の化生」をもとに、計6つの一書=異伝がさまざまに展開していきます。
概要で全体像をつかみ、ポイント把握してから本文へ。最後に、解説をお届けしてまとめていきます。
現代の私たちにも多くの学びをもらえる内容。日本神話から学ぶ。日本の神髄がここにあります。それでは行ってみましょう!
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
『日本書紀』巻第一(神代上)第一段 一書第1~6 体系性、統一性、系統性を持つ一書群が本伝をもとに様々に展開
目次
『日本書紀』巻第一(神代上)第一段 一書第1~6の概要
前回、『日本書紀』巻第一(神代上)第一段の本伝、からの続き。
下図、赤枠部分。第一段〔一書〕の皆さん。

今回お届けする内容は、本伝を踏まえないとお話にならないので、
前回?本伝??という方は、まずコチラ↓をチェック!
- 『日本書紀』第一段の本伝は、構成上、大きく二つの部分から成りたつ。
- 前半は、「天地神の生成の原理(順番)の提示」がテーマ。
- 後半は、比喩表現を交えた具体的な描写と「純粋な男の神誕生」がテーマ。国常立尊、国狭槌尊、豊斟渟尊の純男三神の化生。
で、
今回の『日本書紀』最大の特徴である、一書の皆さん
本伝と一書の関係についてはコチラ↓をチェック。
- 本伝の内容をもとに多角的、多面的に展開する異伝、それが一書。
- 本伝があっての一書であり、一書あっての本伝というように、お互いにつながり合って、関連し合って、踏まえ合って、多様で豊かな日本神話世界を構築している。
ということで、
本伝の内容と、本伝と一書の関係、第一段全体の雰囲気、を踏まえてからの一書解説スタート。
日本神話における、世界の創生(異伝編)。
『日本書紀』巻第一(神代上)第一段 一書第1~6のポイント
現場をご案内する前に2つだけポイントを。
①一書1〜6は、本伝の内容をもとに、多角的多面的に展開している
第一段の一書群=異伝群6つは、それぞれ単体で読んでも断片でムムム状態。。でも、本伝を踏まえれば、あくまで本伝をもとに多面的に展開されてることが見えてくる。
一つひとつの意味理解というより、まずは、本伝と一書がお互いにつながり合って、関連し合って、多様で豊かな日本神話世界を構築している世界線で見ていただければと。
次!
②一書1〜6は、体系性とか系統性を持っている
第一段の一書群は、個別解釈よりも、構造理解の方が重要で。6つを全体的に扱うのが○。
すると、そこには体系性だったり、系統性が存在することが見えてきます。
例えば、こんな感じ。
| 化生して出現 | 化生によらず始めに出現 | 化して出現 | |
| 本伝前半対応 | 一書1 | 一書4 | 一書6 |
| 本伝後半対応 | 一書2 | 一書3 | 一書5 |
詳細は、後ほど解説。
ココでは、なんだかキレイに整理できる、つまり、そこには体系性・系統性がありそうだ、って事でチェック。
まとめます。
- 第一段の一書群は、本伝の内容をもとに展開している
- さらに、どうやら、体系性、系統性を持っているみたい、、
ということで、
『日本書紀』編纂当時の、東アジアの最先端知識をもとに、日本独自に組み合わせ、工夫し、新しく生み出しているのが第一段本伝のポイント。〔一書〕も同じく、超絶クリエイティブ発揮の巻。
では以下、一書の皆さんをどうぞ!
『日本書紀』巻第一(神代上)第一段 一書第1~6

第一段 一書1
ある書はこう伝えている。天地が初めて分かれ、一つの物がその虚空にあった。その物のかたちは言い表しがたい。その中に、自ら物が化生して生まれた神があった。名を国常立尊と言う。また国底立尊とも言う。その次に国狭槌尊。また国狭立尊とも言う。さらに豊国主尊。また豊組野尊とも言う。また豊香節野尊、浮経野豊買尊、豊国野尊、豊齧野尊、葉木国野尊、或いは見野尊とも言う。
一書曰、天地初判、一物在於虚中。状貌難言。其中自有化生之神。号国常立尊。亦曰国底立尊。次国狭槌尊。亦曰国狭立尊。次豊国主尊。亦曰豊組野尊。亦曰豊香節野尊。亦曰浮経野豊買尊。亦曰豊国野尊。亦曰豊齧野尊。亦曰葉木国野尊。亦曰見野尊。 (『日本書紀』巻一(神代上)第一段〔一書1〕より)
第一段 一書2
ある書はこう伝えている。昔むかし、国も稚く地も稚かったころは、水に浮かんだ脂のような状態で漂っていた。そんな時、国の中に物が生まれた。その形は葦の芽が突き出たようであった。これにより化生して生まれた神があった。その名を可美葦牙彦舅尊と言う。次に国常立尊。次に国狭槌尊。葉木国は、ここでは「はこくに」という。可美は、ここでは「うまし」という。
一書曰、古、国稚地稚之時、譬猶浮膏而漂蕩。于時、国中生物。状如葦牙之抽出也。因此有化生之神。号可美葦牙彦舅尊。次国常立尊。次国狭槌尊。葉木国。此云播挙矩爾。可美、此云于麻時。(『日本書紀』巻一(神代上)第一段〔一書2〕より)
第一段 一書3
ある書はこう伝えている。天と地が混じり成った時、はじめに神である人があった。その名を可美葦牙彦舅尊と言う。次に国底立尊。彦舅は、ここでは「ひこぢ」という。
一書曰、天地混成之時、始有神人焉。号可美葦牙彦舅尊。次国底立尊。彦舅、此云比古尼。(『日本書紀』巻一(神代上)第一段〔一書3〕より)
※神人:神そのものと言うべき人と考えられます
第一段 一書4
ある書はこう伝えている。天地が初めて分かれ、初めに倶に生まれた(双生の)神がいた。名を国常立尊と言う。次に国狭槌尊。またこうも伝えている。高天原に生まれた神の名は、天御中主尊と言う。次に高皇産霊尊。次に神皇産霊尊。皇産霊は、ここでは「みむすひ」という。
一書曰、天地初判、始有倶生之神。号国常立尊。次国狭槌尊。又曰、高天原所生神名、曰天御中主尊。次高皇産霊尊。次神皇産霊尊。皇産霊、此云美武須毘。(『日本書紀』巻一(神代上)第一段〔一書4〕より)
第一段 一書5
ある書はこう伝えている。天と地がまだ生まれていないとき、海に浮かぶ雲が根ざしつながる所がないような様だった。その中に一つの物が生まれた。葦の芽が初めて泥の中に生えたようであった。それが化して人となった。名を国常立尊と言う。
一書曰、天地未生之時、譬猶海上浮雲無所根係。其中生一物。如葦牙之初生泥中也。便化為人。号国常立尊。(『日本書紀』巻一(神代上)第一段〔一書5〕より)
第一段 一書6
ある書はこう伝えている。天地が初めて分かれ、物があった。葦の芽が空中に生じたようであった。これによって化した神は、天常立尊と言う。次に可美葦牙彦舅尊。また、物があった。浮かぶ脂が空中に生じたようであった。これによって化した神は、国常立尊と言う。
一書曰、天地初判、有物。若葦牙生於空中。因此化神。号天常立尊。次可美葦牙彦舅尊。又有物。若浮膏生於空中。因此化神。号国常立尊。(『日本書紀』巻一(神代上)第一段〔一書6〕より)

『日本書紀』巻第一(神代上)第一段 一書第1~6解説
第一段の一書=異伝の皆さん、、いかがでしたでしょうか?
6つそれぞれを単体で読んでも、やっぱり断片的で。。まー、色々言ってるね、、くらい?
でも、本伝を踏まえれば、一見とりとめもないような一書も、本伝をもとに多面的に展開されてることが見えてくる。
コレは、コチラ↓の記事をまずチェックいただくとして、
- 本伝の内容をもとに多角的、多面的に展開する異伝、それが一書。
- 本伝があっての一書であり、一書あっての本伝というように、お互いにつながり合って、関連し合って、踏まえ合って、多様で豊かな日本神話世界を構築している。
要は、
日本神話全体の構造として、そもそもこういうイメージなんす。

上記図で言うと、
- 縦軸が、本伝をもとに多面的、多角的に展開する動き=差違化
- 横軸が、先行する段の〔一書〕が、「布石」や「前フリ」として立ち、次段以降で展開する内容や語句などに繋がっていく動き=わたり
てことで、
これら、縦軸横軸の動きを通じて、本伝から一書へ、一書から本伝へ、お互いにつながり合って、関連し合って、踏まえ合って、多様で豊かな日本神話世界を構築している。という世界線。

▲ほんと、こんな感じなんですよね。。。繋がりあって関連しあって、一書(傍流)から本伝(本流)へ、本伝から一書へ。からみあってものすごい立体的で骨太な神話を生み出してる。
これを踏まえたうえで、
以下、大きく2点、縦軸(差違化)と横軸(わたり)に整理して構造論的にお届けします。
次!
2つ目は、
横軸の動き=わたり
について。ポイントは、一書第4。「又曰」の後。
コレ、、、実は『古事記』上巻の冒頭部分と同じ記述だったりしますが、コレはこれで別の話になるので別稿で。
ここでは、『日本書紀』の第一段以降の展開へ向けたわたりとしてのポイントを。
「わたり」とは、前フリのこと。布石のこと。
それでいうと、
この2点がポイントで。
まず、「高天原」が登場の件。
これは、第五段〔一書6〕、〔一書11〕、そして第六段への「わたり」として位置づけられます。
「高天原」は、天照大神の統治する最重要スポットなのですが、特に「本伝」で最初に登場するのは第6段!!!
てことは、本伝だけ読んでいると、「え?何この高天原、、、どこで出てきたん???」ってなる。。
でも、第一段の一書4(そして、第五段の一書6)を読んでおけば「あ、前に出てきた例のアレね(納得)」ってなる。←って、納得するかどうかはさておき、、、
これが学術用語でいう「わたり」。先行する段の一書が、次の段に展開する一節の内容や語句などの「先触れ」や「布石」として立つこと。
大事なのは、一書を踏まえないと、本伝は読み解けない、ってこと。逆も同じ。本伝を踏まえないと、一書は読み解けません。
で、
なんでこのタイミング、この場所で高天原が?って話で言うと、
天地が初めて分かれた原初のタイミング、というのが重要で。コレ以降、時代というか、後になればなるほど、尊貴性がなくなっていく訳です。
- 天地が開けたばかりのタイミング
- 純男の神々が誕生するタイミング
- それってつまり、乾道全盛の極めて超絶にガチで尊いタイミング
ってな訳で、、この絶好のタイミングを逃すわけにはいかぬと。でも、本伝で登場させるとそれはそれで説明がめんどい、、、てことで、一書という異伝の、さらに異伝という場所で、高天原を埋め込んできたわけです。
そして、それを今度は既成事実化し、第六段の本伝で堂々と登場させる。傍流が本流へ。でも、この時には、逆に、天地開闢の乾道全盛の極めて尊いタイミングに誕生したって伝わってたじゃねえかと、何が問題なんだと、そ知らぬ体(体裁)、、いや開き直りスタイル??
ポイント2つめの「高皇産霊尊」が誕生も同様で。
第8段で少彦名の親として、第9段で葦原中国平定で登場し活躍するのですが、8段、9段に先行する形で、ココで登場。
コレは、後になって、天地が初めて分かれた原初のタイミングに、高天原という尊い場に生まれた尊貴な神。その存在、身分が、葦原中国に対して絶大な力を持つ、という仕掛け、根拠付けになってるわけです。
スゴイ緻密なツクリ。。。わたり効果、しっかりチェック。
てことで、まとめると、、
これら、縦軸(差異化)と横軸(わたり)の動きや展開を通じて、本伝から一書へ、一書から本伝へ、お互いにつながり合って、関連し合って、踏まえ合って、多様で豊かな日本神話世界を構築している。という世界線。そのダイナミズムや創意工夫のスゴさを感じていただきたい次第。

▲繋がりあって関連しあって、一書(傍流)から本伝(本流)へ、本伝から一書へ。からみあってものすごい立体的で骨太な神話を生み出してるイメージ。。
最後に、第一段で誕生する神様たちをまとめておきます。
| 第一段 | 誕生する神 |
| 本伝 | 国常立尊、国狭槌尊、豊斟渟尊 |
| 一書1 | 国常立尊(亦名:国底立尊) 国狭槌尊(亦名:国狭立尊) 豊国主尊(亦名:豊組野尊、豊香節野尊、浮経野豊買尊、豊国野尊、豊齧野尊、葉木国野尊、見野尊 |
| 書2 | 可美葦牙彦舅尊、国常立尊、国狭槌尊 |
| 書3 | 可美葦牙彦舅尊、国底立尊 |
| 書4 | 国常立尊、国狭槌尊 「又曰」の後 天御中主尊、高皇産霊尊、神皇産霊尊 |
| 書5 | 国常立尊 |
| 書6 | 天常立尊、可美葦牙彦舅尊、国常立尊 |
「国常立尊」はおおむね共通して登場。ほか、国狭槌尊、可美葦牙彦舅尊が目立って登場。
それぞれの神様の名前がなんでこうなのか?という問いはあまり意味がありません。ただ、天地開闢の時に、その天地や国の状態、そしてそこに化生する、あるいは化生した物や神のありさまに即して、それぞれに名付けを行っている、くらいで留めておくことをオススメします。
神名の詮索は語源の探求と同じ。恣意的、または強引な解釈につなげないようにすることがめっちゃ重要です。巷にも結構多いのよホント。。。
まとめ
『日本書紀』巻第一(神代上)第一段 一書第1~6
第一段の異伝である一書は合計6つ。これら個別の一書を細かく取り上げて解釈しようとしても全体像が見えてこない。それよりも、全体の構成や構造を把握するのが◯。
第一段の一書群は、縦軸(差違化)と横軸(わたり)の展開運動として整理すると分かりやすい。
縦軸(差違化)では、
- 本伝の前半、後半をもとに展開している
- 体系性、系統性を持っている
の2点がポイントで、ここでの多面化・多様化の方法としての軸は2つ。一つが「神の化生方法にバリエーションを加える軸」、もう一つが「本伝の前半と後半で対応させてバリエーションを加える軸」。以下のように整理可能。
| 化生して出現 | 化生によらず始めに出現 | 化して出現 | |
| 本伝前半対応 | 一書1 | 一書4 | 一書6 |
| 本伝後半対応 | 一書2 | 一書3 | 一書5 |
横軸(わたり)では、
異伝である一書4の中にあるさらに異伝の箇所が重要。「高天原」と「高皇産霊神」がポイント。
天地が初めて分かれた原初のタイミング、それってつまり、乾道全盛の極めて超絶にガチで尊いタイミングな訳で、、この絶好のタイミングで後段の本伝へつながっていく布石として、高天原や高皇産霊神を埋め込むことで、権威付けや根拠付けを図ってる。
まとめると
『日本書紀』の一書群を通じて、縦軸(差違化)と横軸(わたり)の運動が展開されている世界線。その狙いは、多様で豊かな神話世界、そして最終的には日本という国のスゴさを伝えること。
そのために、日本書紀編纂チームが創意工夫により生み出したのが差違化&わたり展開技法、ということで。超絶ジャパーン的なるものとして要チェック。
『日本書紀』編纂当時の、東アジアの最先端知識、宇宙理論をもとに、単に真似で終わるのではなく、日本独自に組み合わせ、工夫し、新しく生み出しているのが第一段本伝のポイントでした。一書も同じく、超絶クリエイティブが発揮されてます。コチラも是非チェック。
続いて第二段!男女ペアの神々誕生!はコチラで!
『古事記』版の天地開闢はコチラで!
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
天地開闢まとめ、関連エントリはコチラで!
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!



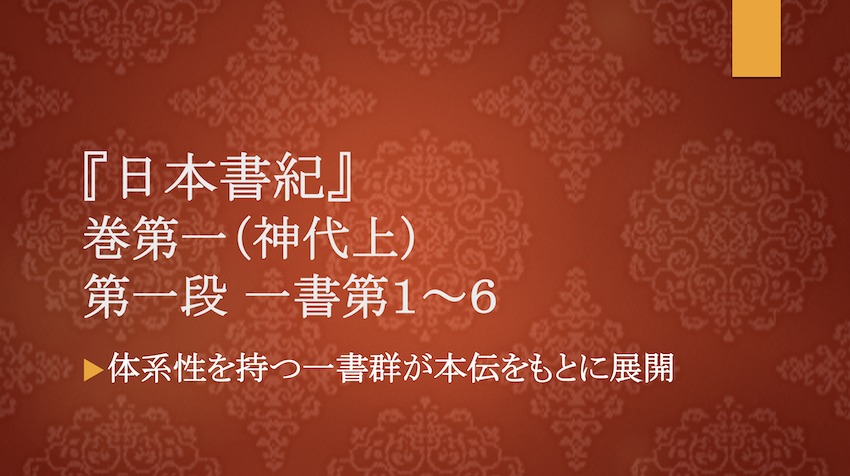






















構造理解の1つ目。
縦軸の動き=差違化
について。
結論を先にいうと、6つの〔一書〕は、2つの系統(軸)で整理できます。
つまり、
第一段の〔一書〕群において、多面化・多様化の方法として、その軸は2つあって、一つが「神の化生方法にバリエーションを加える軸」、もう一つが「本伝の前半と後半で対応させてバリエーションを加える軸」。
まずは、ひとつ目の「神の化生方法にバリエーションを加える軸」から。
化生方法についての軸は、
の3つに分類、グルーピングすることができる。実際に神の化生方法の箇所を抽出して並べてみると、、、
ということで、
別に、意図的にそういうふうに持っていってる訳じゃなくて、文献学的に徴証を尽くしていくと、こういうふうなグルーピング、系統が立ち上がってくるんです。
さらに!
〔書1〕〔書2〕ならびに〔書5〕〔書6〕は、神の誕生に「物」「化」がかかわる系列としてグルーピングでき、これが、実は本伝後半の「天地之中生一物。状如葦牙。便化為神」と対応してる訳です。
一方で、最初から神や人として出現する系の〔書3〕〔書4〕も一つのグループとして、神の誕生だけを伝える本伝前半「天先成而地後定。然後、神聖生其中焉」に対応してる。。
まとめると、、
「天先成而地後定。然後、神聖生其中焉」
「天地之中生一物。状如葦牙。便化為神」
ということで、
何が言いたいかというと、一書の皆さんは、本伝に即して多面展開されてる、しかもグルーピングあるいは系統化できる、ってことなんす。
これは、つまり、『日本書紀』編纂にあたっては、既にあった伝承を取りまとめたってことじゃなく、編纂チームによる創意工夫としてできあがったものなんじゃないか、ってことになる訳で。
もう一つ。
意味内容として「本伝の前半と後半で対応させてバリエーションを加える軸」について。
あらためて、冒頭表現を並べてみます。
と、
冒頭は「時+生まれたもの」の2つの要素でできてるんですが、、、似たような表現が並んでるなかで、やはり目につくのは同じ文言使用の一書1,4,6。
以下抽出。
と。前半「天地初判(天地が初めて分かれ)」で統一、後半ちょっと変えましたね的雰囲気、、、
で、実は、この「天地初判(天地が初めて分かれ)」は、本伝前半のまとめである「天先成而地後定(天がまず成りそして地は後で定まったのである。)」を踏まえ、これを集約した表現として対応してます。
第一段 本伝の前半のまとめ部分↓
天がまず成りそして地は後で定まったのである。しかるのち、神が天地の中に生まれた。
対応する、「天地初判(天地が初めて分かれ)」の一書群↓
ということで、
意味内容として、本伝前半のまとめである「天先成而地後定(天がまず成りそして地は後で定まったのである。)」を集約した表現として「天地初判(天地が初めて分かれ)」が対応、以下、生まれたものとして、本伝の「神」を、物とか倶に生まれた(双生の)神とかにしてる訳ですね。
さらに!
それ以外の一書2,3,5についても、
ちょっと、ココからは訳出で
と。
これはこれで、時系列にならんでるように見えます。前半の「時」表現だけ抽出し、時系列順に並び替えてみます。
と。
天地が生まれる前→天地が混じり合って→国も土地もできて間もないころ、と、、キレイに時系列配置???
この辺りで、やはり、一度、本伝に立ち戻って考えてみると、、、
この一書2,3,5。実は、第一段本伝の後半部分、具体的に伝えてる箇所と対応してる感じが、、、
第一段 本伝の後半部分↓
「それゆえに、天と地が開かれる初めには、のちに洲となる土壌が浮かび漂っていた。その様は、まるで水に遊ぶ魚が水面に浮いているようなものだった。まさにその時、天地の中に一つの物が生まれた。それは萌え出る葦の芽のようであった。そして、化して神と成った。」
時系列に並び替えた一書群↓
いかがでしょうか?
一言一句そのままとか、ココとここが厳密に対応してる、という訳ではありませんが、意味内容や表現として対応してる感はあるのではないでしょうか。
ということで、
以上の2点を整理すると、、
と、このように、
意味内容を追いかけることで、前半に対応する一書群、後半に対応する一書群、というように整理できる訳です。
ということで、
こうして整理してみると、『日本書紀』第一段の一書の皆さんには、基本の枠組みがまずあって、それをもとに、表現を変えることで違う伝承のように見せてる、とも言えて。
これが学術用語でいう「差違化」であります。
ちなみに、、
想定される編纂過程をめっちゃ分かりやすくすると以下。
①まずは本伝の前半と後半↓
②前半と後半に対応する異伝を生み出す↓
③それをシャッフルする↓
で完成。
私たちが現在見てるのは、差違化の結果なので、ぱっと見るとよー分からん、となるのですが、こうして記載事項を事実ベースで整理、まとめてみると、いろいろ分かってくる。
文献学において、『日本書紀』の一書群を「差違化」の結果として見た時に、なんのために差違化させてるかというと、、
多様で豊かな神話世界を提示すること。伝承の多様さ=文化や歴史の厚みそのもの。。。その先には、日本という国のスゴさを伝えるため。
ってな訳です。
差違化技法はそのために、『日本書紀』編纂チームが創意工夫により生み出したのであって、ひとつの超絶ジャパーン的なるものとしてチェック。