日本神話に登場する、重要ワード、重要エピソードをディープに掘り下げる「日本神話解説シリーズ」。
今回は、『古事記』をもとに
別天神
をお届けします。
『古事記』に独自な神であり、天地の始まりに誕生する5柱の神々。位置づけとしては、「神世七代」の神々に先立って誕生する非常に尊貴な存在。いずれも、独神であり、身を隠す。
「別天神」ついては、『古事記』単体で解釈するほか『日本書紀』と比較してみると、その存在意義やメッセージがより明確になります。
今回は、そんな「別天神」について、『古事記』文献をもとに、『日本書紀』との比較も盛り込みながらディープに解説します。
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
別天神(ことあまつかみ)とは? 天地のはじまりに誕生した独神で身を隠す五柱の神々!『古事記』をもとに別天神を徹底解説!
目次
別天神(ことあまつかみ)とは?『古事記』の登場箇所
まずは、「別天神」とはどんな神なのか?について、『古事記』の現場からチェック。
登場するのは、『古事記』上巻の冒頭。天地がはじめてできたところ。天之御中主神を筆頭に、5柱の神々が次々に誕生していく様を伝えます。
天地が初めて發った時に、高天原に成った神の名は、天之御中主神。次に、高御産巣日神。次に、神産巣日神。この三柱の神は、みな独神と成りまして、身を隠した。
次に、国が稚く浮いている脂のように海月なすただよえる時に、葦牙のように萌え騰る物に因って成った神の名は、宇摩志阿斯訶備比古遅神。次に、天之常立神。この二柱の神も、みな独神と成りまして、身を隠した。
上の件の五柱の神は、別天神である。
天地初發之時、於高天原成神名、天之御中主神訓高下天、云阿麻。下效此、次高御產巢日神、次神產巢日神。此三柱神者、並獨神成坐而、隱身也。次、國稚如浮脂而久羅下那州多陀用幣流之時流字以上十字以音、如葦牙、因萌騰之物而成神名、宇摩志阿斯訶備比古遲神此神名以音、次天之常立神。訓常云登許、訓立云多知。此二柱神亦、獨神成坐而、隱身也。上件五柱神者、別天神。 (『古事記』上巻より一部抜粋)
ということで、
天地のはじまりから5柱の神々が次々に誕生し、最後にそれらを一括して「別天神」として位置づけてます。みな独神であり、身を隠したと。
なお、神々についての詳細はコチラから。
⇒「天之御中主神|高天の原の神聖な中央に位置する主君。天地初発の時に高天の原に成りました最初の神。」
⇒「高御産巣日神|造化三神の一柱で天之御中主神に次いで2番目に成りました独神で別天つ神。」
⇒「神産巣日神|造化三神の一柱で3番目に成りました独神で別天つ神。生命体の蘇生復活を掌る至上神。」
⇒「宇摩志阿斯訶備比古遅神|葦芽のように芽生え伸びてゆくものを依代として化成した独神で身を隠した別天神」
⇒「天之常立神|天が恒常的に(永久に)立ち続けることの神!天地初発に造化三神のあとに誕生した独神であり別天神」
ということで、まず確認したい基本事項、
「別天神」が登場するのは『古事記』上巻の冒頭。天地のはじまりから5柱の神々が次々に誕生し、最後にそれらを一括して「別天神」として位置づけてる。みな独神であり、身を隠した神である。
てことで、チェック。
別天神(ことあまつかみ)とは?日本神話的に解釈する
「別天神」の登場場面をチェックできたところで、ココからは、「別天神」とは何か?どんな意味があるのか?について突っ込んで解説。
「別天神」を理解しようとするとき、大きく2つの視点からチェックする必要があります。
- 「別天神」の「記載内容」からの視点
- 「別天神」とそのあとに続く神々を踏まえた「位置づけ」の視点
ということで、
1つ目の「別天神」の記載内容からの視点とは、
- 「天地初めて發りし時に、高天原に成りませる神」と「次に、国が稚く、浮ける脂のごとくして、海月なすただよへる時に、葦牙のごとく萌え騰る物によりて成りませる神」とは位置づけが違う神々である。
- 独神であり、身を隠す神である。
の2つ。
さらに、「別天神」とそのあとに続く神々を踏まえた「位置づけ」の視点とは、
- 「別天神」のあとに誕生する神々を踏まえて位置づけを見てみる
- 『日本書紀』との比較を通じて解釈を深めてみる
てことで、
「ディープに解説シリーズ」なんで、以下、それぞれについてディープに分かりやすく解説!
1.「別天神」の「記載内容」からの視点
まずは、「別天神」について伝えてる内容から分かることをチェック。
まず1つ目。
①「天地初めて發りし時に、高天原に成りませる神」と「次に、国が稚く、浮ける脂のごとくして、海月なすただよへる時に、葦牙のごとく萌え騰る物によりて成りませる神」とは位置づけが違う神々である。
「天地初めて發りし時に、高天原に成りませる神」とは、「天之御中主神」「高御産巣日神」「神産巣日神」の三柱の神神であり、いわゆる「造化三神」と呼ばれる神様たち。
「次に、国が稚く、浮ける脂のごとくして、海月なすただよへる時に、葦牙のごとく萌え騰る物によりて成りませる神」とは、「宇摩志阿斯訶備比古遅神」「天之常立神」の二柱の神神。
まず理解したいのは、「別天神」の全5柱の神々は、3+2=5の構成になってるってこと。その違いは、高天原という至高の場所で生まれたかどうか。最初の三神は高天原で誕生し、それ以外は、恐らく天で誕生したと想定されます。
ここで、「造化三神」について。詳細コチラでチェック。
『古事記』では、他のどんな神よりも何よりも、「造化三神」を至高・至尊の存在として位置づけてるんです。コレ、『古事記』独自。
そもそも、『古事記』は国内向けの、天皇家の正当性を打ち出すために、恐らく、編纂当時の政治状況も踏まえて出雲に対して格別の配慮をしながら、それを大和勢力の中に組み込もうとしていた、、ことが伺える内容になってるんです。コレ、神話と歴史が交錯する超絶ロマン地帯。
このため、どこから生まれたかは知らないけれど、すでにある「高天原」という場を用意し、そこに「天之御中主神」「高御産巣日神」「神産巣日神」という3神を登場させてる。
中央・大和側代表の「高御産巣日神」、出雲代表の「神産巣日神」、そしてそれらを取り持ち、融和的に止揚する「天之御中主神」。絶妙な三角バランス。

これが「天地初めて發りし時に、高天原に成りませる神」ということ。わざわざ、「天地が初めてできる時」と「高天原という場」を限定して伝えてますよね。
一方、続けて登場する2神、「宇摩志阿斯訶備比古遲神」「天之常立神」は、「次に、国が稚く、浮ける脂のごとくして、海月なすただよへる時に、葦牙のごとく萌え騰る物によりて成りませる神」ということで、位置づけとしては、次順の存在になるわけです。
まとめます。
「別天神」の全5柱の神々は、「造化三神」と呼ばれる高天原で誕生した3神と、天で誕生した次順の存在たる2神の、2つに分かれる。5=3+2。
ということでチェック。
②独神であり、身を隠す神である。
「別天神」の伝承内容から分かること、その2。
「別天神」は、全て「独り神と成りまして、身を隠したまひき(独神成坐而隠身也)」とあるように、独神であり身を隠す神とされてます。
で、コレ、実は、「独神」は「隠身」とセットで使われる『古事記』独特の組み合わせなんです。ココがポイント!
「独神」については、単独で誕生し、男女の対偶神を指す「双神」と対応する神のこと。で、天地開闢においては、まず「独神」が誕生し、続いてその後に「双神」が誕生するという流れ・順番。
それを受けての、「身を隠す」という内容。
で、重要なのは、この「隠身」で。
「隠身」といえば、、、国譲りを迫られた大国主神が執った処身方法で。天孫に国を譲り、わが身は表の世界から立ち退くことを言います。
『古事記』ではこれを、
この葦原の中つ国は、命のまにまにすでに献らむ。ただあが住所のみは、 (中略) 底つ石根に宮柱太しり、高天の原に氷木高しりて治めたまはば、吾は百足らず八十坰手に隠りて侍らむ。 (『古事記』より一部抜粋)
と伝えます。
ちなみにこれは、『日本書紀』神代紀でも
天孫、若し此の矛を用て国を治めたまはば、必ず平安くましましなむ。今、我は当に百足らず八十隈に隠去れなむ。 (『日本書紀』より一部抜粋)
と共通する内容を伝えています。
このように、
大国主神の場合、天孫に国を譲り、わが身は表の世界から立ち退くことを「隠身」と言ってる訳で。そして、身を隠しながらも、天孫が治める国を陰からサポートする役割を担うってことでもあります。
これをもとに考えると、つまり、
「独神」として身を隠すとは、「双神」に、彼らの活躍する世界を譲り、自らは立ち退くこと、をいう訳です。
「双神」の代表格は、伊耶那岐と伊耶那美神。まさに世界を創生する2神。国生みも神生みも、この世界を形作ったのは双神の御業で。それだけでも十分すぎるほど尊い話なんですが、それよりさらに尊い存在がいるってなれば、、、これはもう、、、よく分からない感じが必要で。
独神のあとに続けて誕生する「双神」に、彼らが活躍する世界を譲り、自らは立ち退く立場を取っている、というのは、まさにこの激しく奥ゆかしく神秘的な雰囲気が必要だから、とも言えますよね。やはり、、尊い存在はなかなか表には出てこないのです。。。だからこそ、なんかスゲーってなるんです。
ということで、
「別天神」の記載内容からの視点で、2つ。
- 「別天神」の全5柱の神々は、「造化三神」と呼ばれる高天原で誕生した3神と、天で誕生した2神の2つに分かれる。
- 「独神」として身を隠すとは、「双神」に彼らの活躍するこの世界を譲り、自らは立ち退くこと。この奥ゆかしいスタンスは、非常に尊貴な神ならでは。
「尊貴」って言葉をテーマに、その意味をしっかりチェック。
続けて、チェックすべき2つ目。
2.「別天神」とそのあとに続く神々を踏まえた「位置づけ」の視点
記載内容だけでなく、その他の神や、なんなら『日本書紀』と比較することが分かることがあるんです。コレ、2つあって、
- 「別天神」のあとに誕生する神々を踏まえて位置づけを見てみる
- 『日本書紀』との比較を通じて解釈を深めてみる
てことで、
こちらも順に解説。
①「別天神」のあとに誕生する神々を踏まえて位置づけを見てみる
実は、『古事記』版天地開闢には、「別天神」の誕生の続きがありまして、、、それが「神世七代」と呼ばれる神様たちの誕生です。
で、これら、神世七代も含めた神様たちを一覧化したのがコチラ。

と、す、すごい世界観、、、
あとに誕生する神々を踏まえて、その位置づけを見てみると、「別天神」はかなーり尊い存在なんだな、、てことが分かりますよね。
少なくとも、神世七代よりも、上というか、尊貴というか。。
で、これが次の2つ目のポイントにつながります。
②『日本書紀』との比較を通じて解釈を深めてみる
『古事記』単体で「別天神」の位置づけを理解しようとしても、「神世七代より先だって誕生した尊貴な神々」としか言いようがないのですが、『日本書紀』との比較から眺めることで、奥行きや深みがでてくるんです!
まず、比較対象の『日本書紀』について。対応する箇所は、『日本書紀』巻第一(神代上)第三段 本伝。
『日本書紀』の神代紀では、天地の始まりに伴って最初に誕生した「純男」と、続いて誕生した「対偶神(男神と女神の一組)」とを一括して「神世七代」と称しています。
なので、
『日本書紀』から眺めると、『古事記』は「神世七代」のさらに前に「別天神」を置いていることになります。
ポイントはこの視点で、
「別」とは、まさしく「神世七代」に先立って特別に誕生したことを強調する表現である
ということ。
現に、最初の始祖神は、天の至尊・至高の場であり天照大御神が君臨統治する「高天原」で誕生するわけです。
『古事記』は、こうして『日本書紀』の神代紀が伝える神よりさらに尊貴な神としての「特別な地位」を別天神に与えている、とも言えて。
そこに、神代紀を向こうにまわして、いっそう尊貴な神々の体系を構築しようとした『古事記』のいわば野心的なものが見え隠れする訳です。
いずれにしても、
『古事記』単体で「別天神」のことを理解しようとしても、「神世七代より先だって誕生した尊貴な神々」としか言いようがないのですが、『日本書紀』との比較から眺めることで、その位置づけや解釈に奥行きや深みがでてくるのは間違いありません。
まとめます。
「別天神」とそのあとに続く神々を踏まえた「位置づけ」としては
- 『日本書紀』から眺めると、『古事記』は「神世七代」のさらに前に「別天神」を置いていることになる
- 「別」とは、まさしく「神世七代」に先立って特別に誕生したことを強調する表現である
の2点、その意味も含めてしっかりチェック。
3.「別天神」という神カテゴリ、序列を支える理論、思想
最後に、「別天神」や「神世七代」といった神カテゴリ設定、序列的なものを作ろうとする価値観、そのバックグランドとなる思想体系について補足解説。
『古事記』でも、全体を通して臭いたつ「スゲー区別したいぜ感」を支えている理論があるんです。
それが、
「尊卑先後の序」
コレ、実は、日本神話を貫く超重要な原理原則で。
やわらかく言うと、物事には優先順位があるよ、ということ。なんだかんだと、この基本概念をもとに神話世界が構成されてるんです。コレ、特に『日本書紀』との比較を通じて見えてくることだったりします。
区別してるところを列挙すると、、
- 「別天神」という神神を、それ以降の神々、世代と区別
- 「別天神」の中でも、造化三神と他2神を区別
- 「独神」という神神を、それ以降の神々、双神と区別
- 「神世七代」という神神を、それ以降の神々、世代と区別
- 「神世七代」の中でも、独神2代と双神5代を区別
と、まー区別の嵐。
『古事記』版天地開闢の実態は、神々の区別、区分けであり、すべて、原理原則をもとにした神様カテゴリになってる。
で、そこには、
この世界の始まりの時代を、それ以降とは区別して「理想の世(聖代)」とする歴史観がある。
コレ、しっかりチェック。
繰り返しになりますが、この世界をカタチ作ったのは双神であり神世七代カテゴリ。これ以降の神々とは区別して、この世界の始まりの時代を理想的な、非常に尊貴なものとして位置付けようとしたのが別天神という神カテゴリてことなんすね。まさに特別、格別、、
まとめ
「別天神」
『古事記』本文をもとに、『日本書紀』との比較も踏まえて「別天神」を解説してきましたが、いかがでしょうか?
改めて、「別天神」とは、「別天神」が登場するのは『古事記』上巻の冒頭。天地のはじまりから5柱の神々が次々に誕生し、最後にそれらを一括して「別天神」として位置づけてる。みな独神であり、身を隠した神である。
「別天神」を伝える内容から分かるのは、
- 「別天神」の全5柱の神々は、「造化三神」と呼ばれる高天原で誕生した3神と、天で誕生した2神の2つに分かれる。
- 「独神」として身を隠すとは、「双神」に彼らの活躍するこの世界を譲り、自らは立ち退くこと。この奥ゆかしいスタンスは、非常に尊貴な神ならでは。
の2点。
さらに、
- 『日本書紀』から眺めると、『古事記』は「神世七代」のさらに前に「別天神」を置いていることになる
- 「別」とは、まさしく「神世七代」に先立って特別に誕生したことを強調する表現である
の2つもしっかりチェック。
特に、位置づけについては重要で、『古事記』は、『日本書紀』の神代紀が伝える神よりさらに尊貴な神としての「特別な地位」を別天神に与えている、こと、しっかりチェック。
『古事記』版天地開闢の実態は、区別、区分けの嵐。つまり、神々の序列化を重要視してる訳ですね。
で、そこには、この世界の始まりの時代を、それ以降とは区別して「理想の世(聖代)」とする歴史観がある、ってこと含めてチェックされてください。
別天神の各神様の分かりやすい解説はコチラ!
⇒「天之御中主神|高天の原の神聖な中央に位置する主君。天地初発の時に高天の原に成りました最初の神。」
⇒「高御産巣日神|造化三神の一柱で天之御中主神に次いで2番目に成りました独神で別天つ神。」
⇒「神産巣日神|造化三神の一柱で3番目に成りました独神で別天つ神。生命体の蘇生復活を掌る至上神。」
⇒「宇摩志阿斯訶備比古遅神|葦芽のように芽生え伸びてゆくものを依代として化成した独神で身を隠した別天神」
⇒「天之常立神|天が恒常的に(永久に)立ち続けることの神!天地初発に造化三神のあとに誕生した独神であり別天神」
別天神の次に誕生する神様カテゴリもしっかりチェックしておかないと!
コチラも是非!日本神話の流れに沿って分かりやすくまとめてます!
天地開闢まとめはコチラで!
『古事記』版☟
『日本書紀』版☟
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ(S23)。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
[itemlink post_id=”13035″] [itemlink post_id=”13037″] [itemlink post_id=”13038″] [itemlink post_id=”13039″]
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




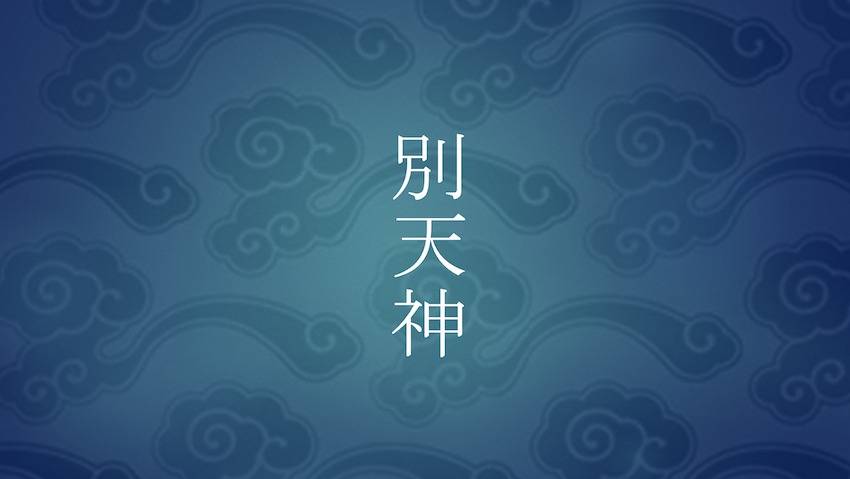

















コメントを残す