事代主神の子、媛蹈韛五十鈴姫命の出自について、『日本書紀』をもとに分かりやすく解説します。
媛蹈韛五十鈴姫命
このお方、、、実は謎深きお方であって、その麗しさも手伝って大いに惑わせてくれるお姫様であります。
一番の謎は、その出自。
誰の子やねん?
というところ。
本件、実は2つの伝承がありまして、、、
- 大己貴神の魂が三諸山に鎮まった、その神(大三輪の神)の子
- 事代主神がワニに化けて玉櫛媛のもとに通って生まれた子
と、大三輪神の子なのか、事代主神の子なのか、、よく分からない、、、
今回は、そのあたりのアレコレを『日本書紀』をもとにディープに解説します。
事代主神の子、媛蹈韛五十鈴姫命の出自|フツーではない交わり方で孕んだ子だからこそフツーではないお姫様になった件
目次
事代主神の子、媛蹈韛五十鈴姫命の出自
まずは、事代主神の子、媛蹈韛五十鈴姫命の出自について、元ネタとなるところからチェック。
このお方、神武紀(『日本書紀』巻三)の最後のところで登場し、神武天皇の正妃になるお姫様。なんですが、、実は、それより前、神代紀(『日本書紀』巻二)でその出自が語られてるんです。
『日本書紀』巻二、第8段〔一書6〕の後半。一般に、国造り神話と呼ばれる伝承の後半部分。現代語訳で抜粋します。
「どこに住みたいのか?」と大己貴神が問うと、「幸魂・奇魂」は「私は日本国の三諸山に住みたい」と言った。そこでその神の宮殿を三諸山に造営し住まわせた。これが大三輪の神である。この神の子は甘茂君等・大三輪君等、また姫蹈韛五十鈴姫命である。
又曰く、事代主神が八尋熊鰐に変化して、三島の溝樴姫の許にお通いになって〔ある伝えに、玉櫛姫という〕、御子姫蹈韛五十鈴姫命を生んだ。これが神日本磐余彦火火出見天皇の后である。 (『日本書紀』巻二 第8段〔一書6〕より抜粋)
ということで。
神代で「媛蹈韛五十鈴媛命」の出自が語られている次第。しかも、2つの伝承で!! 「又曰く」の前と後ろ。
- 「又曰く」の前:大三輪の神の子
- 「又曰く」の後:ワニに化けた事代主神と玉櫛媛の間に生まれた子
コレが
どっちやねん!?
と言いたくなる理由。媛蹈韛五十鈴媛命を謎めいた女性にしてる原因箇所であります。
事代主神の子、媛蹈韛五十鈴姫命の出自を深堀り
現状認識をいただいたところで、今回のエントリでは「又曰く」の後の伝承について解説していきます。
話は、神代紀から、神武紀へ。
『日本書紀』巻三、一般に「神武東征神話」を伝えるところから「媛蹈韛五十鈴媛命」の登場シーンをチェック。
庚申の年(紀元前661年)、秋8月16日、彦火火出見は正妃を立てようとして、改めて広く高貴な血筋の女を求めた。その時、ある者が「事代主神が三島溝橛耳神の女である玉櫛媛と生んだ子で、名を「媛蹈韛五十鈴媛命」と申します。この者は国中でもとりわけ麗しい美人です」と申し上げた。彦火火出見はこれを喜んだ。
9月24日、媛蹈韛五十鈴媛命を迎え入れて正妃とした。(『日本書紀』巻三 神武紀より抜粋)
橿原神宮で公開中の「神武天皇御一代記御絵巻」より
ということで。
東征を果たした神武天皇が、正妃を迎えようじゃないかと。広く求めたところ、媛蹈韛五十鈴媛命ってのがいてさ、めっちゃ美人なんすよ、と教えてくれた次第。って、誰ですか?こんなこと教えたのは。
ここで分かるのは、
神武紀は、神代紀の「又曰く」の後の伝承を引き継いでるってこと。
「事代主神が三島溝橛耳神の女である玉櫛媛と生んだ子で、名を「媛蹈韛五十鈴媛命」と申します」とありますよね。
日本神話的な流れを尊重すると、あくまで神代紀があって神武紀があって、という流れなので、神武紀の伝承は神代紀を引き継いでると見る訳ですが、一方で、神代紀にいきなり神武紀、歴史の時代の記述が登場する訳で、ある意味、「又曰く」以降は後で書き加えられたと見ることもできます。このあたり神話ロマンが広がるディープなエリアであります。
当サイトとしては、後で書き加えられたと解釈しており、なんなら、事代主神の位置づけが大きく変わっていると見ています。神代紀の「事代主神」と、神武紀の媛蹈韛五十鈴媛命伝承に関わる「事代主神」は別の神で、これ、実は「壬申の乱」が関係する壮大なお話になってくるので、詳しくは別エントリで。
話を戻して、、、媛の出自。
なんで事代主神が玉櫛媛と生んだ設定になってるのか? について、以下解説。
まず、確認いただきたいのは、
神武紀の、このシーンは、日本の初代天皇の妃を選ぶ重要局面だということ。
彦火火出見(=神武天皇)は、これから「天皇」になろうとする訳です。「天子」です。
ということは、
天子にふさわしいお方を妃にすべき
ということになります。※現妻がいるじゃないか!というのは置いといて!
そんな安直に選べない正妃チョイス。緊張感たっぷりの局面なんです。
- 誰がどう見ても「なるほどですね!」と納得するお方。
- なんなら、よそ者である神武と結婚することで地元の人たちに受け入れやすくなるお方。
- あの方が選ばれたということで逆に神武の価値が上がるようなお方。
そんな思惑がうごめくわけです。
そんな状況の中で選ばれたのが、媛蹈韛五十鈴姫命。(゚∀゚)キタコレ
当然、上記思惑を完璧なまでに満たすお姫様だった訳です。みんな黙りました。納得しました。あー、確かにね、って思った。
なぜって?
それは、このお姫様、尋常ではない親と通常ではありえない生まれ方をしてるから。
それが、
通い婚&異類婚
という設定。
あっちいったりこっち行ったりすみませんが、再度、神代紀の伝承をチェック。
又曰く、事代主神が八尋熊鰐に変化して、三島の溝樴姫の許にお通いになって、御子 姫蹈韛五十鈴姫命を生んだ。
ということで。要は、、
事代主神がバカでかいワニに化けて、三島の溝樴姫のところに通って、子供ができたんです。ワニが、夜な夜な通ってきて、いろいろ大人なコトがあって子供ができたんです。
コレ、尋常ではないやつ。
2点チェック。
- まず、神が通ってきて孕んだという事。つまり正式な結婚ではない中で孕んだ事。
- そして、ワニ、つまり異類と交わって孕んだという事。
これが「フツーではないやつ」。通い婚&異類婚。
その結果生まれたのが、媛蹈韛五十鈴姫命という事なんで、そら周りのみんな黙りますよ。。
その肌は、ワニ肌で、、、いえいえ、この世のものとも思われぬ麗しさだったはず。。。
ちなみに、神武紀に戻って、その原文では、
事代主神、共三嶋溝橛耳神之女玉櫛媛、所生兒、
「事代主神が、三嶋溝橛耳神之女玉櫛媛と一緒に生んだ子」とあり、「共」という漢字が使われています。
よく、この部分、「事代主神が玉櫛媛と結婚して」と訳してるのが多いですが、ハッキリ言って間違いです。し、コトの重要性を理解できていません。
初代天皇の御妃は、特別な方でなければならないのです!フツーではあかんのです!!
従って、単に結婚して生んだとかいう表現はダメで。通常の結婚ではない、通常の親ではない、どえらい背景から生まれてきたお方として、訳出にもそれを表現すべきなんです。
いやー、昼間は麗しくてまばゆいばかりに美しいあのお姫様が、なぜか夜になると水を飲みたがり、真夜中になるとあれ?なんだか肌がごつごつに?アレ?デカくなって。。。Σ(||゚Д゚)ヒィィィィ
なんて、
大いに惑わせてくれるお姫様です。
まとめ
事代主神の子、媛蹈韛五十鈴姫命の出自
正妃選びのとき、状況的には、彦火火出見が天皇になろうとしていたとき。
なので、それにふさわしいお方を妃にすべきであり、誰がどう見ても納得するお方であるべきでした。
そんな状況の中で選ばれたのが、媛蹈韛五十鈴姫命。
確かにこの御姫様、その出自は、
- 神が通ってきて孕んだ。つまり正式な結婚ではない中で孕んだ子だった。
- そして、親がワニ、つまり異類と交わって孕んだ子だった。
という2点で尋常ではありませんでした。
これは、神代の伝承、第8段一書6で伏線が張られており、その設定のなかで神武紀が引き継ぐ形式をとっています。
これを、伏線ととるか、後で書き加えられた、つまり事代主神の位置づけが大きく変わったことがあった、と見るかは、、、ああ、壬申の乱について書けなかったので、別エントリで!
神武東征神話の媛登場シーンの詳細解説はこコチラ!
東征神話の目次はコチラ!
本記事監修:(一社)日本神話協会理事長、佛教大学名誉教授 榎本福寿氏
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)、他
こちらの記事もどうぞ。オススメ関連エントリー
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




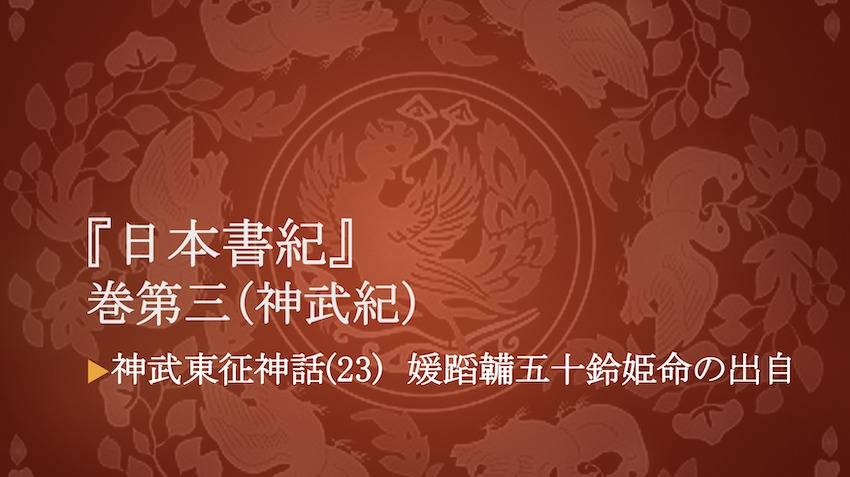




















[…] で、坂本氏情報の「五十鈴媛」って初耳ですが、日本書紀にちゃんと「ワニ顔の異類人・神と交わって生まれた子」だと記されてまして・・ワニ顔の宇宙人は坂本氏の記録にも出てます […]