多彩で豊かな日本神話の世界へようこそ!
正史『日本書紀』をもとに、最新の文献学的学術成果も取り入れながら、どこよりも分かりやすい解説をお届けします。題して、おもしろ日本神話シリーズ。
今回は、『日本書紀』巻第一(神代上)第二段の一書の第1,2。
第一段を引き継いで展開し、四組の「男女耦生之神」を列挙する第二段の本伝。これに併載されている異伝が2つ。それが一書の第1と2です。
概要で全体像をつかみ、ポイント把握してから本文へ。最後に、解説をお届けしてまとめ。
現代の私たちにも多くの学びをもらえる内容。日本神話から学ぶ。日本の神髄がここにあります。それでは行ってみましょう!
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
『日本書紀』巻第一(神代上)第二段 一書第1,2 親が子を生みなす新種が登場
目次
『日本書紀』巻第一(神代上)第二段 一書第1,2の概要
前回、『日本書紀』巻第一(神代上)第二段の本伝、からの続き。
下図、赤枠部分。本伝の下、一書の皆さん。

前段の第一段、天地開闢から「純男の神様」が誕生、続く第二段では、さらに展開して「男女ペアの神様」が登場。コレ、神話的に初!ニュージェネレーション!!
そして、今回の第二段一書の皆さん。
ココではさらに展開して
親が子を生みなす新種が登場!!
またまた出たっ!初のやつ!!生む世代!!!これはスゴイ。
一書第1,2は短く断片的な神話ですが、神話的大転換が発生する注目スポット。ポイントをしっかり押さえながら読み進めていきましょう。
ちなみに、第二段の一書は第三段の一書とあわせてチェック。詳細は第三段一書解説で。
『日本書紀』巻第一(神代上)第二段 本伝のポイント
ポイント2つ。
①本伝を元に差違化、親が子を生みなす新種が登場!
これまでの、神の誕生方法である
・物から化生したり(第一段本伝)、
・当初から「有」という存在のかたち(第二段本伝)
をとったりせず、それとは別の日本神話的ニュースタイル、
親が子を生みなす誕生!!
こ、これは、、神話世界では革命的なことで、、、((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
だって、これまで
道の働きにより神が生まれる(成り現れた)、って言ってたのに、
親神が子神を生む、って、すごい変化。。。
すごいものから生まれる、から、あいつがこいつを生む、へ。
この
自動詞(生まれる)から
他動詞(生む)への神話的大転換
が、なんと、ココ、第二段の一書で発生!
さらっと流したらあかん1個目。親が子を生みなす新種登場。要チェックです。
次!
②新種登場は、国生み・神生み神話への「わたり」
この新種、実は、第四段以降に登場する、伊奘諾尊・伊奘冉尊の結婚による、国生み・神生みへつながる「わたり」として位置づけられます。
「わたり」とは、繋がりをつけること。一書で前振り、後の本伝で既成事実化して再登場。詳しくはコチラ↓で。
要は、
ココ、第二段一書で「生む」という他動詞スタイルが先行登場してるからこそ、第四段以降、伊奘諾尊・伊奘冉尊が国や神を「生む」という神話がスムースに展開できるようになってる。
本伝でツッコまれても、だって前やってたし(生んでたし)って、言えるってこと。
この「わたり」の効果は単なる前振り以上に、異伝から本伝へ、傍流から本流へ的な、日本神話を「躍動するスゴイ神話」にしている原動力になってます。
まとめます
- 本伝を元に差違化、ついに、親が子を生みなす新種登場!
- この新種登場は、後段で展開する国生み・神生み神話への「わたり」
以上、2点を踏まえて以下、一書をチェックです。
『日本書紀』巻第一(神代上)第二段 一書第1,2

〈一書 第一〉
ある書はこう伝えている。この二柱の神は、青橿城根尊の子である。
一書曰、此二神、青橿城根尊之子也。 (『日本書紀』巻第一(神代上)第二段 〔一書1〕より)
〈一書 第二〉
ある書はこう伝えている。国常立尊が、天鏡尊を生んだ。天鏡尊が、天万尊を生んだ。天万尊が、沫蕩尊を生んだ。沫蕩尊が、伊奘諾尊を生んだ。沫蕩、これを「あわなぎ」と読む。
一書曰、国常立尊生天鏡尊。天鏡尊生天万尊。天万尊生沫蕩尊。沫蕩尊生伊奘諾尊。沫蕩、此云阿和那伎。 (『日本書紀』巻第一(神代上)第二段 〔一書2〕より)
え?これだけ?
はい、これだけです。

『日本書紀』巻第一(神代上)第二段 一書第1,2 解説
第二段の〔一書1〕と〔一書2〕はセットで読み解くのが◎
- 〔一書1〕が、系譜そのものの発生(親子一世代)を
- 〔一書2〕が、系譜の連続(四世代)を
伝えている、という流れアリ。
まず、〔一書1〕から。
続く〈一書 第二〉。
- 国常立尊が、天鏡尊を生んだ。天鏡尊が、天万尊を生んだ。天万尊が、沫蕩尊を生んだ。沫蕩尊が、伊奘諾尊を生んだ。
- 国常立尊生天鏡尊。天鏡尊生天万尊。天万尊生沫蕩尊。沫蕩尊生伊奘諾尊。)」
→コレ、国常立尊から連なる四代の系譜伝承。

先ほどの、一書1から系譜が増えとるやないか、、、
- 〔一書1〕が一代系譜
- 〔一書2〕が四代系譜
って事で。。つまり、〔一書1〕からさらに差異化してる訳ですね。
ちなみに、、
国常立尊は、前段、第一段本伝で「純男神」として登場。
天鏡尊から伊奘諾尊へは全4世代、ということで、これは第二段本伝の4世代誕生と同じ。
つまり、
- 〔本伝〕が、男女ペア神の4世代誕生
- 〔一書2〕が、純男神の4世代誕生
ということで。本伝と対応させてる感がスゴい。。
まとめると
〔一書1〕が、系譜そのものの発生(親子一世代)を、〔一書2〕が、系譜の連続(四世代)を、それぞれ本伝をもとに差違化することで伝えている、ということでしっかりチェック。
最後に、日本神話全体のなかでの、第二段〔一書1〕〔一書2〕の意味を解説。
まず、この系譜発生譚は、縦軸(差違化)の運動としてチェックです。
全体として2点。
そもそも、第一段や二段、三段の本伝では、
というように、
乾と坤、天と地といった世界を構成する根源である「道」という概念とその働きをもとに、神の化成・出現を物語ってました。
ところが!
ココ、第二段一書第1,2では、なんと「親が子を生む」ことで神が誕生すると。
「道の働きにより神が生まれる」から「親神が子神を生む」へ、
生まれる(自動詞)から生む(他動詞)への神話的大転換!!
が、ココ第二段の一書で発生してる訳です。
このことは、伊奘諾尊・伊奘冉尊の結婚による国生み・神生みへつながる「わたり」として位置づけられます。第四段以降に登場。
ココ第二段一書で、「生む」という他動詞スタイルが先行して登場しているからこそ、第四段以降の国生み・神生みがスムースに展開できるようになっている。
のちの本伝でツッコまれても、「だって前、やってたし(生んでたし)」って、言えるってこと。
その意味で、この場所に登場してるのは絶妙。
一書という、異伝での登場。
見方によっては、あくまで異伝=本伝ではない=突飛なことを言っても異伝ですから、で済んでしまう場所な訳で、めっちゃ便利な場とも言えます。
この便利な場所、位置づけを利用して、新しい概念を導入。しかも、それを既成事実化して本伝へ、神話の本流へ持って行ってしまう、、、ものスゴい構造を持っているわけです。
つまり、、
本伝をもとに一書(異伝)で差違化する=縦軸の運動と、差違化したニュースタイルを、後段本伝で使用する横軸の運動、これら縦と横の運動が絡みあい、繋がりあい、日本神話の立体的な構造を創り出している。

いや、むしろ、異伝で新登場した「傍流的ニュースタイル」が、「主流(メイン)」へ取って代わっていく、このダイナミックな縦と横の運動と絡み合いが日本神話の実態であって。。
「躍動するスゴイ神話」とも言えるその原動力が、差違化とわたりってことすね。
スゴすぎです。古代日本人が生み出した壮大な仕掛け。『日本書紀』編纂当時の、東アジアの最先端知識、宇宙理論をもとに、単に真似で終わるのではなく、日本独自に組み合わせ、工夫し、新しく生み出している、超絶クリエイティブ発揮の巻。

▲ほんと、こんな感じなんですよね。。。繋がりあって関連しあって、一書(傍流)から本伝(本流)へ、本伝から一書へ。からみあってものすごい立体的で骨太な神話を生み出してる。
最後に、第一段 一書1、2で誕生する神様たちをまとめておきます。
| 一書第1 | 青橿城根尊 |
| 第2 | 国常立尊 天鏡尊 天万尊 沫蕩尊 伊奘諾尊 |
全て純男の系譜としてチェック。詳細は別エントリ&第3段一書解説で。
まとめ
『日本書紀』巻第一(神代上)第二段の一書の第1,2。
第一段を引き継いで展開し、男女四組の「耦生之神」を列挙する第二段の本伝。これに併載されている異伝が2つ。それが一書の第1と2。
第一段、天地開闢から「純男三神」が誕生、続く第二段では、さらに展開して「男女ペアの神様」が登場。
一書ではさらにさらに展開して「親が子を生みなす新種」が登場。生む世代、神話的に初。
〔一書1〕が、系譜そのものの発生(親子一世代)を、〔一書2〕が、系譜の連続(四世代)を、それぞれ本伝をもとに差違化することで伝えている。
これまで、「乾道独化」とか「乾坤之道、相参而化」とか、「道」という概念をもとに「生まれる」という表現だったのが、ココ、第二段一書第1,2では「親が子を生む」ことで神が誕生する表現へ。
自動詞(生まれる)から他動詞(生む)への神話的大転換が、ココ第二段の一書で発生している、ということ。
また、ニュージェネ登場は、第四段以降に登場する、伊奘諾尊・伊奘冉尊の結婚による国生み・神生みへつながる「わたり」として位置づけられる。
異伝=一書という「便利な場所」を利用して、新しい概念を導入。しかも、それを既成事実化して、なんなら本伝へ、ある意味本流へ持って行ってしまう、すごい構造を持っている。それが日本神話。
このダイナミックな縦と横の運動が絡み合って日本神話という大きな物語を生み出している。その現場が一書第1,2ということです。
『日本書紀』編纂当時の、東アジアの最先端知識、宇宙理論をもとに、単に真似で終わるのではなく、日本独自に組み合わせ、工夫し、新しく生み出している、超絶クリエイティブ発揮の巻、是非チェックされてください。
続きはコチラで!
本シリーズの目次はコチラ!
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ(S23)。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




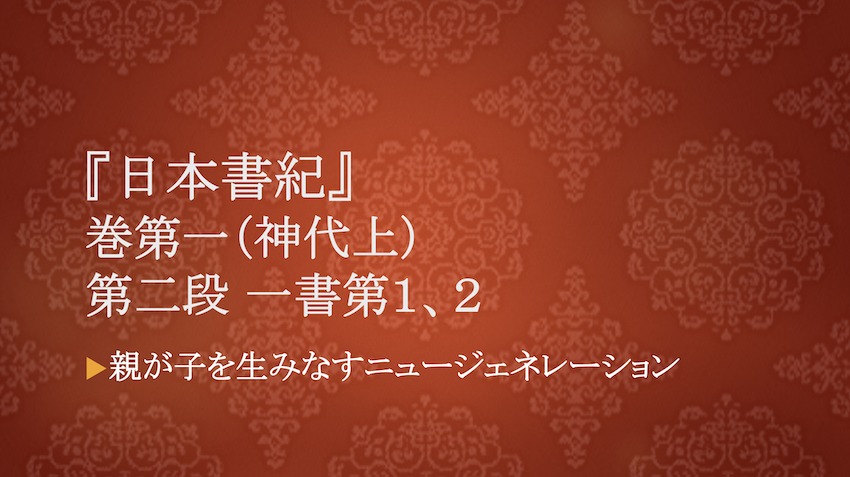

















とありますが、
ココで言う「此二神」とは、第二段〔本伝〕の最後に登場する伊奘諾尊・伊奘冉尊を指します。
なので、「伊奘諾・伊奘冉の二神は、青橿城根尊の子である」てこと。
青橿城根尊が親で、諾・冉2神を生んだと???
つまり、、ココでのポイントは、
「系譜」の発生!!
コレ!
日本神話史上初!!!
ちゃんとびっくりして!日本神話的に革命的事件が発生してるんで、まずはコトの重大性をチェック。詳細は後ほど。〔一書2〕と合わせて。
ちなみに、、、
「青橿城根尊」は、第二段本伝で「惶根尊」の別名として登場。
上記、「次に現れた神は、面足尊・惶根尊。」のところ、「男神・女神」の順番で記述されてるので、「面足尊」が男神、「惶根尊」は女神。という位置づけ@第二段本伝
なので、「惶根尊」の別名たる「青橿城根尊」は女神で、諾・冉2神の親=母、ってことだと。
この事からさらに
「二神が同母ならこれは兄妹となり、やがて結婚すれば当然に兄妹婚ということになる。」(山田宗睦氏『日本書紀史注巻第一』)というように、
伊奘諾・伊奘冉の兄妹説、からの、兄妹婚=近親相姦説、からの、原型は東南アジアの少数民族に伝わる兄妹相姦神話だー!といった説へつながっていったりするのですが、、流石にコレは飛躍しすぎかと。。同じような型を持つ伝承があるからといって、それが元になってるなんて立証しようがないですからね。。
いずれにせよ、第二段〔一書1〕では、系譜そのものの発生(親子一世代)を伝えてる、ってことでしっかりチェック。