多彩で豊かな日本神話の世界へようこそ!
正史『日本書紀』をもとに、最新の文献学的学術成果も取り入れながら、どこよりも分かりやすい解説をお届けします。題して、おもしろ日本神話シリーズ。
今回は、
『日本書紀』巻第一(神代上)第二段の本伝。
第一段で誕生した「純男の神」の流れを承けて「男女の対・ペアとなる神々」が誕生。
2(男女)×4組=計8神。イッツ・ニュージェネレーション!
概要で物語の全体像をつかんで、ポイントを把握してから本文へ。最後に、解説をお届けしてまとめ。
現代の私たちにも多くの学びをもらえる内容。日本神話から学ぶ。日本の神髄がここにあります。それでは行ってみましょう!
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
『日本書紀』巻第一(神代上)第二段 本伝 ~男女耦生の4代8神~
目次
『日本書紀』巻第一(神代上)第二段 本伝の位置づけ
今回お届けする内容は、前段である第一段を踏まえてから。コチラ↓を再チェック!
で、今回ご紹介するのは全体像で言うとココ(赤枠部分)

ポイントは、
神話全体の流れの中で読み解くこと。
詳細は今後順次解説、大きな流れ、枠組みは以下の通り。
| 大テーマ | 小テーマ | 内容 | 段 |
| 誕生の物語 | 道による化生 | 乾による純男神 | 第一段 |
| 乾と坤による男女対耦神 | 第二段 | ||
| 神世七代として一括化 | 第三段 | ||
| 男女の性の営みによる出産 | 国生み | 第四段 | |
| 神生み | 第五段 |
第一段から第五段までは、大きく「誕生」がテーマ。
誕生には2つあって、一つが「道による化生」、そしてもう一つが「男女の性の営みによる出産」。
「道による化生」は、第一段、第二段、第三段がひとまとめ。神世七代という最も尊い神さまカテゴリ誕生を伝えます。
そんな大きな流れの中で、
第二段は、前段の「純粋な男の神」誕生を承け、さらに展開。ついに「男女ペアの神様」が誕生!
コレ、神話的に初、ニュージェネレーション!!!
時代は大きく転換
純男神→男女対耦神へ。
この、大きなうねりを感じながら読み進めましょう。
『日本書紀』巻第一(神代上)第二段 本伝のポイント
ポイント3つ。
①「次有神」という言葉で前段を引き継ぎ、続く第三段へつなぐ
第二段〔本伝〕は、冒頭の「次に神あり(原文:次有神)」という言葉からスタート。
コレ、「次」の文字により、第一段をひき継いで展開することを明示。
そのあとも、男女四組の「耦生之神」を列挙するごとに、この表現を前置きしてます。
つまり、
第二段は、第一段の流れを引き継いでいて、それは続く第三段で「神世七代」と一括するところへつながっていく、、、
と、いうことで、このダイナミックな継承の流れをチェックです。
次!
②初登場!乾と坤から化生したニュージェネ「男女ペア神」!これは革命だ!
第一段では「純男神」だったのが、第二段になって初登場「耦生之神」!!!
「耦生」とは、「 二人(またはそれ以上)が同時に生まれる」という意味。つまり、「男女一組のセット神」てこと。コレって、、、
ニュージェネレーション!!!
か、革命だ。。。((((;゚Д゚))))ガクブル
第一段で「純粋な男の神」と強調してたのが、第二段になると「男女ペアの神神」へ劇的転換を果たす。これを革命と言わず何と言おうか?
第二段は、この大転換をビリビリ感じながら読み進めるのが◎
次!
③男女だから?結婚の物語?神の名前にストーリーらしきものアリ
誕生する男女ペアの神神には、どうやらストーリーらしきものが存在。それが
土台→家→互いに賛美→誘い合う
という「結婚の物語」。あるいは、「進化の物語」。これが、神名に設定されてるっぽい。。。
まとめます。
-
第二段は、冒頭の「次有神」という言葉からスタート。これにより、第一段をひき継いで展開することを表し、次の第三段へつなげる。
-
初めて、男女ペア神が誕生。男女で一組のセット神。コレ神話的大転換。さらっと流すのはNG!
- 神の名前にストーリーがある。土台→家→互いに賛美→誘い合う、という流れ。これは結婚を表象??
以上3点をチェックして本伝へゴー!
『日本書紀』巻第一 第二段 本伝 現代語訳と原文
▲国立国会図書館デジタルライブラリより引用。慶長4(1599)刊版 次に神があった。泥土煑尊(土、これを「うひぢ」と読む)、沙土煑尊(沙土、これを「すひぢ」と読む。またの名は、泥土根尊・沙土根尊)である。次に神があった。大戸之道尊(ある書では、大戸之辺と言う)、大苫辺尊(または大戸摩彦尊・大戸摩姫尊・大富道尊・大富辺尊とも言う)である。次に神があった。面足尊・惶根尊(または吾屋惶根尊・忌橿城尊・青橿城根尊・吾屋橿城尊と言う)である。次に神があった。伊奘諾尊・伊奘冉尊である。
次有神。泥土煑尊〈泥土、此云于毘尼。〉・沙土煑尊〈沙土、此云須毘尼。亦曰泥土根尊、沙土根尊。〉。次有神。大戸之道尊〈一云、大戸之辺。〉・大苫辺尊〈亦曰大戸摩彦尊、大戸摩姫尊。亦曰大富道尊、大富辺尊。〉。次有神。面足尊・惶根尊〈亦曰吾屋惶根尊。亦曰忌橿城尊。亦曰青橿城根尊。亦曰吾屋橿城尊。〉。次有神。伊奘諾尊・伊奘冉尊。 (『日本書紀』巻第一(神代上)第二段 本伝より)
って、短っ!
これだけ?
はい。これだけです。

『日本書紀』巻第一 第二段 本伝 解説
以下、3つ解説。一つ目
まとめ
『日本書紀』巻第一(神代上)第二段の本伝
第一段で誕生した「三柱の神」の流れを受けて、いよいよ男女の対となる神々が誕生。第二段では合計四組、計8神が誕生します。
ポイントは、
- 「次有神」という言葉によって、第一段を引き継ぐことを明示。本文では男女ペア神を一代として区切る役目発揮。
- 初めて「男女耦生之神」が誕生!コレ、男女で一組のセット神。神話的に革命とも言える大転換。さらっと流すのNG!
- 男女ペアで「神世の一代」に相当し、合計4代(計8柱)。さらに、第一段の純男3神=3代とあわせて「神世七代」(3+4=7)と一括化される@第三段〔本伝〕
- 「男女耦生之神」は、乾坤の道が互いに参じて、集まって、混じり合って、それによって誕生した。なので、神の名前に結婚ストーリーが。。。
- 土台→家→互いに賛美→誘い合う、という流れ、結婚ストーリーが第四段での国生みを導く。
ということで、
純男神→男女対耦神へ。時代が大きく転換してる、その革命的うねりを感じるのが◯!
『日本書紀』編纂当時の、東アジアの最先端知識、宇宙理論をもとに、日本独自に組み合わせ、工夫し、新しく生み出している感じ。ホントスゴイよジャパーン的超絶クリエイティブ。
続きはコチラで!
→第二段の異伝へ行く場合はコチラ!オススメ!
→次の段の本伝へ行く場合はコチラ!
『古事記』版の天地開闢はコチラで!
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
天地開闢まとめ、関連エントリはコチラで!
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




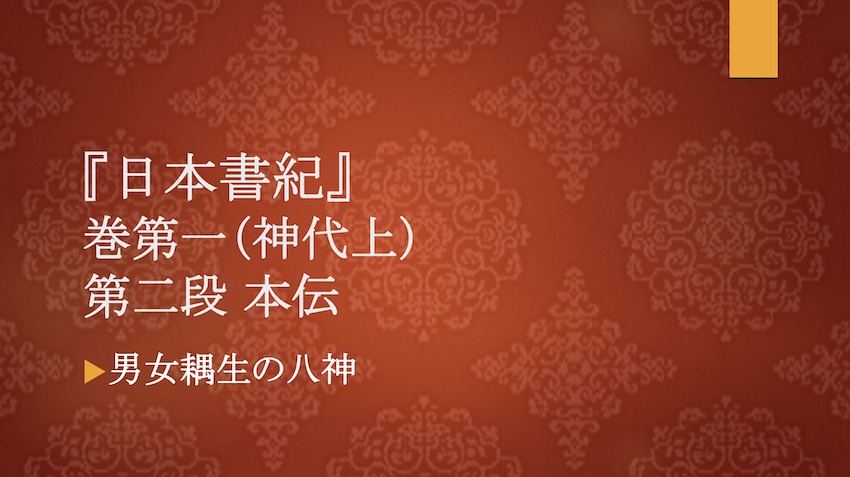






















→注を除くと上記。ポイント1つめ。
①「次有神」が引き継ぎと区切りの役目をもっている
第二段読み解きにあたっては、まず「次有神」に着目。
コレ、ポイント2つ。
そんな役目を「次有神」は持ってます。
第二段では登場しないのですが、続く第三段で、つまりあとになって、男女ペアの神は「神世の一代」としてカテゴリされることが分かるようになるんです。
てことで、「次有神」は引き継ぎ役と区切り役、2つの役割を持っていること、まずチェック。
次!
②男女一対の四世代、合計8神。あとで分かる、男女一対=一世代
第二段では、ただ単に男女ペア4組、計8神が誕生するだけの伝承。
ですが、これらの男女ペア神は、実は、
つまり、
後になって、次の第三段になって、「神世七代という尊い神様カテゴリの一部を構成」してた事が判明する。コレ、日本神話的後付け設定の巻。
分かりやすく
といった流れ。神様を一覧化すると、
(純男の神)
(男女一対の神)
と、まースゴイ合理的に組まれてる。
もともとあった伝承をまとめました的なものではなく、しっかり創られてる感じがしますよね。
「乾道独化」した「純男の神」は、最も尊い存在。なので「3」という陽数設定。一方の「男女ペアの神」は、次順の存在。なので「4」という陰数設定。
第一段をチェックいただければ、古代の聖数概念だとピンピンくるはず!
合理的で数学的にも美しい世界、それが天地開闢にまつわる神誕生の神話観です。
次!
③男女だからこそ、結婚の物語。神の名前にストーリーらしきものがある
ストーリーとは、「土台→家→互いに賛美→誘い合う」、要は「結婚の物語」。
先ほど、次の第三段になって神世七代という尊い神様カテゴリの一部を構成してた事が判明する、とお伝えしましたが、同様に、
「男女耦生之神」は、乾坤の道が互いに参じて、集まって、混じり合って、それによって誕生した(乾坤之道、相参而化)ことが分かります。
要は、乾道単独の働きでは無く、乾と坤の道両方の働きによるものだと。
この、集まる、混じり合う働きをベースにしてるからこそ、「土台→家→互いに賛美→誘い合う」、要は「結婚の物語」になってくる、と言える訳ですね。
以下。
①最初に「泥土煑尊、沙土煑尊」。
「泥土」と「沙土」が名に組み込まれていて、まず土壌の出現を表象。
②このあと「大戸之道尊、大苫辺尊」。
自然の土壌をかたどる表象から、人文の建造物、工作物をかたどる表象に転じます。要はお家を建てたわけです。
③そして「面足尊・惶根尊」。
こちらは、「おもだる(りっぱなお顔ね)」、「あやかしこね(かわいいね)」、と、たがいに称えあう関係にある訳です。盛り上がってきました。
④そして最後の「伊奘諾尊・伊奘冉尊」。
これは、「いざなふ」の語をもとに成りたつ神名とみるのが通例。要はベッドインへ向けて誘いあってるということです。
第四段でいよいよ国生みが登場する訳で、その前段として神名を通じて結婚ストーリーを表現したという訳ですね。
「土台→戸(家)→互いに賛美→誘い合う」結婚ストーリー。
すごいよくできた神話、、、((((;゚Д゚))))ガクブル
ポイント2つ。
1つ目は、神話世界の大きな大きな流れを、神名を通じて表現している!!ってこと。
土台→家に続き、二神がたがいに称えあうという表象を承け、まさにその称辞のとおり出現した二神(伊奘諾・伊奘冉)が誘いあう。それが、このあとに続く結婚や、国生み、神生みを導く、とも言えて、、
これはつまり、
神名を通じて、神話世界の大きな大きな流れを表現している!!
ってことすね。
2つ目は、最後の世代たる伊奘諾尊・伊奘冉尊は、男と女の本質的・根源的なありようを表象している。ってこと!
神名のプロセスは、最初は土台とか杙とか、表象内容は外観・外見にとどまっているのですが、
伊奘諾&伊奘冉の登場によって、男と女が互いに誘い合い、心を交わせ、お互いの存在を認め合うようになります。
男女が「いざ!いざー!!」って一体化しようと声を掛け合っている。。。
ポイントはここで。
男と女という、本来的にあい異なる性が、異なればこそ、互いに誘いあって一体化しようとする本質的・根源的なありようを表象している訳で。
言い方を変えると、日本神話的世界創生は「最終的に収斂していく事」にあるとも言えて。
土台→戸(家)→賛美→誘い合い、、、そして一体化。一体のものとして収れんする!
って、こんな世界創生を描いているところが他にあるのでしょうか。。いや、ない!
神の世の最後に、男女が互いに誘いあう本来的なあり方を表象する神が出現したことにより、神世七代という世界も完成をみる。
ココ、激しく重要なところなんで、しっかりチェック。