多彩で豊かな日本神話の世界へようこそ!
正史『日本書紀』をもとに、最新の学術成果も取り入れながら、どこよりも分かりやすい解説をお届けします。
今回は、『日本書紀』巻第一(神代上)第三段の一書の第1。
第一段、第二段を引き継ぎ、
天地開闢から誕生した純男神三代と男女耦生神四代を「神世七代」として一括する第三段の本伝。これに併載されている異伝が1つ。それが一書の第1です。
概要で全体像をつかみ、ポイント把握してから本文へ。最後に、解説をお届けしてまとめ。
現代の私たちにも多くの学びをもらえる内容。日本神話から学ぶ。日本の神髄がココにあります。それでは行ってみましょう!
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
『日本書紀』巻第一(神代上)第三段 一書第1 新しい時代へ向けた準備
目次
『日本書紀』巻第一(神代上)第三段 一書第1の概要
前回、『日本書紀』巻第一(神代上)第三段の本伝、からの続き。
下図、赤枠部分。本伝の下、一書。

これまでの流れが大事。
- 第一段、天地開闢から「純男三神」が誕生。
- 続く第二段では、さらに展開して「男女ペアの神様」が四組、計8神誕生。
- 第三段の本伝では、国常立尊から伊奘諾尊・伊奘冉尊までが七世代の神様「神世七代」でした、と「総括」してました。
天地開闢の時に誕生した、最も尊い神様ジェネレーション、神様カテゴリ、それが「神世七代」。
第三段の一書1は、この流れを受けて、差違化展開。さらに続く四段へ向けての「わたり」として位置づけられます。
参考:『日本書紀』の「一書」とは?『日本書紀』本伝と一書の読み解き方法を徹底解説!
これまで同様、この一書も短く断片的な神話。ポイントをサクッとチェックです。

『日本書紀』巻第一(神代上)第三段 一書1のポイント
ポイント2つ。
まず1つめ。
①第三段一書1は、、、コレ本来、第二段一書に入るべき内容では??
実は、第三段一書1は、第二段の本伝と近い、、てか、神名が一部違うだけで、そのまんまでは??とも言うべき内容で。むしろ、第二段を差違化したものとして、第二段の一書に入れるべきだったりします。
『日本書紀』構造論的には、第三段一書1は、本来であれば、第三段の内容(神世七代総括)の差違化としての一書が入るべきなんですが、、、そのような内容になってない、、
第三段なのに第二段の内容が入って。。。???ということで、何故そうなのか?を考えることが第三段一書1の読み解きにめっちゃ重要だったりします。詳細後ほど。
次!
②次の第四段=新時代へ向けた準備、つなぎとしての役割が??
ポイント2つめ。
第三段本伝解説でもお届けした通り、「第一段~第三段」と「第四段以降」は全然違う時代。
それは、
- 「神世七代」と「それ以外の神」との違い
- 「乾坤の道によって化成した神」と「それ以外の神(男女の営みによって生んだ神)」との違い
って、、すごいドギツイ事いうと、
「尊さ」が違うんす。
宇宙の、万物の根源たる道から、道の働きによって誕生した神と、男女神の営みによって誕生した神では、尊さが、格が、違います。。。って、私は何様でしょうか??
第三段一書は、この、道による誕生時代の最終地点。
第四段からは男女神の営みによる国生みが始まるわけで、この一番最後の場所に、男女ペア神の異伝があることで、次の時代へつながるようになっている、とも言える訳です。ま、ちょっと後付けかも知らんけど。。
まとめます。
以上、2点をチェックした上で本文をどうぞ!
『日本書紀』巻第一(神代上)第三段 一書第1の本文
第三段〈一書 第一〉
国立国会図書館デジタルライブラリより慶長4(1599)刊版 ある書はこう伝えている。男女が対になった神は、まず泥土煮尊、沙土煮尊があった。次に角樴尊、活樴尊があった。次に面足尊、惶根尊があった。次に伊奘諾尊、伊奘冉尊があった。樴は杭の意味。
一書曰、男女耦生之神、先有泥土煮尊・沙土煮尊。次有角樴尊・活樴尊。次有面足尊・惶根尊。次有伊奘諾尊・伊奘冉尊。樴、橛也。(引用:『日本書紀』巻一 第三段 一書1より)
『日本書紀』巻第一(神代上)第三段 一書1解説
先に細かいところを、次に構造を解説。

で、
実はココからが本題。ちょっと長くなるので、時間のあるときに是非。テーマは、、
「本来、第二段の一書にあるべき内容が、第三段の一書にあるのは何故なのか?」
てことで、、、以下思考実験的に解説です。
本件、そもそも、箱をイメージしてもらう必要があって、、
全部で6つの箱が、3行×2列で並んでます。
で、こんなルールがあったとする。
- それぞれの箱には、基本的には一つのテーマでしか物を入れることはできません。
- 1列目の箱は、ストーリーがあり、流れをもとに内容を入れていきます。
- 2列目の箱は、便利な箱。1列目の箱をもとに少し変えた物か、これまでにない新しい物、どちらかを入れることができます。

その上で、縦3×横2=6つの箱に中身(物語)を入れるとしたらどうなるか?
そんな思考実験的に以下。
まず、1つめのルール①をもとに、本伝を入れ込んでみる。
| 第一段 本伝 純男三神化成 | |
| 第二段 本伝 男女八神化成 | |
| 第三段 本伝 神世七代として総括 |
1列目、縦の箱に入れた本伝は、ストーリーがあり、流れをもとに入ってる。純男(3)→男女(4)→総括(7)。これはルール①の通り。
問題は、2列目、一書の皆さん。
| 第一段 本伝 純男三神化成 | 一書 差違化→? |
| 第二段 本伝 男女八神化成 | 一書 差違化→? |
| 第三段 本伝 神世七代として総括 | 一書 差違化→? |
どうなる???
ルール②をもとに考えると、、、
| 第一段 本伝 純男三神化成 | 一書 差違化→ 純男三神異伝 |
| 第二段 本伝 男女八神化成 | 一書 差違化→ 男女八神異伝 |
| 第三段 本伝 神世七代として総括 | 一書 差違化→ ??? |
と、
ここで問題発生。「???」の部分。
最後の、第三段本伝の差違化が難しい、、、
なぜなら、第三段本伝でコレまでの「総括」をしちゃってるから。区切りをつけちゃってるから。
この「総括」、「神世七代」という神様カテゴリ総括&設定であり、めちゃくちゃ重要。変な異伝はつくれない。。。
神世八代にするとか???いや、それはマズい。陽数=聖数観念をもとに構築した美しい神世界が崩壊してしまう。。。そもそも八世代も登場してないし、、、
そこで、、こうしてみた??
| 第一段 本伝 純男三神化成 | 一書 差違化→ |
| 第二段 本伝 男女八神化成 | 一書 差違化→ 純男三神異伝 |
| 第三段 本伝 神世七代として総括 | 一書 差違化→ 男女八神異伝 |
2列目の縦、1個ずつ下にズラしてみた、、、
で、
空白になった第一段本伝一書差異化の箱に、新たに別の異伝を入れてみた。
| 第一段 本伝 純男三神化成 | 一書 差違化→ 純男三神異伝①開闢誕生系 |
| 第二段 本伝 男女八神化成 | 一書 差違化→ 純男三神異伝②系譜系 |
| 第三段 本伝 神世七代として総括 | 一書 差違化→ 男女八神異伝 |
第一段本伝を2つに差異化。①開闢誕生系、②系譜系。
結果的に、本来、第二段の一書にくるはずの内容が、第三段の一書に。でもこれで完成。現在私たちが確認できる『日本書紀』第一段~第三段になりました。
ということだったんじゃないか、、、!!??m9( ゚Д゚) ドーン!
、、てことで
要はですね、第一段から第三段は、ひとつのカテゴリであり、伝えるべきミッションがある訳ですよ。伝えるべきミッションとは、「神世七代」を他の世代と区別すること。これ絶対。
しかも、
次の四段以降の国生み・神生みを導く結果を展開させる必要もある。
第四段以降の国生み・神生みとは、要は「男女の行為、営み」による「生む」作業。
そのためには、
- 純男→男女ペアという展開を導くこと
- 「生む」(≑系譜)という展開を登場させること
が必要で、
第一段~三段の本伝で、1つめの要件(純男→男女)は表現できた。残りの「生む=系譜」の登場を、どこでどう入れるか?というお話になり、、
今回の場合、それは第一段の一書ではなく、第二段の一書で入れた(②系譜系)、って事。1つの箱1テーマのルールあるし。総括の差違化は難しい、てか、できないので。
日本神話編纂チームはこうした課題とか、テーマとか伝えるべきミッションと向き合ってたんじゃないか、、、そんなように見える訳です。
でも、この登場させる箇所のズレ発生イベントによって、ズレてるんだけど、このズレちゃった、ズラしたことが、結果的に、次へ繋がる内容になっとるんす。
つまり、
第一段~第三段のカテゴリの最後、第三段一書に、耦生八神の異伝をいれることで、第四段の伊奘諾尊・伊奘冉尊の国生みへ自然とつながるようになってる、ってことで。
コレ、「物語をどう紡いでいくか?」という視点で。そこにこそ、日本ならではの創意工夫のスゴさが見えてくる。
くどいようですが、
「第一段~第三段」と「第四段以降」は全然違う時代。
「神世七代」と「それ以外の神」、「乾坤の道によって化成した神」とそれ以外の「男女の営みによって生んだ神」との違い。
とはいえ、全く別にしてしまうとそれはそれで問題で、、、神話世界の継起性で展開するルールをもとに、前段が次段へつながるように、つながっていくように、物語を設定していく必要あり。
区別は必要。だけど全く別にはできない。次々に展開していく流れをつくらないといけない。
そんな物語のルールのなかで、どうするのか?ということで、第一段~第三段のカテゴリの最後、第三段一書に、耦生八神の異伝をいれることで、第四段の伊奘諾尊・伊奘冉尊の国生みへ自然と、ナチュラルに、違和感なくつながるようになってるんす!
私たちが現在見てるのは、差違化の結果なので、ぱっと見るとなんでやねん状態なんだが、こうして記載事項を事実ベースで整理、まとめてみると、こういう見方もできますよねと。
文献学において、『日本書紀』の一書群を「差違化」の結果として見た時に、なんのために差違化させてるかというと、、
多様で豊かな神話世界を提示すること。伝承の多様さ=文化や歴史の厚みそのもの。。。その先には、日本という国のスゴさを伝えるため。
ってな訳で。そのために、あれこれ創意工夫しながら本伝、一書がつくられ、それぞれの箱に入れらてるという世界線。むしろ、その創造性にビリビリ震える訳で。一緒にビリビリしていただきたい!
まとめ
『日本書紀』巻第一(神代上)第三段 一書第1
冒頭、「男女耦生之神」からスタート。
コレにより、第三段本伝を引き継いでる事を暗示(「男女耦生之神」という言葉は、第三段本伝の総括のなかで登場)。
で、具体的な内容は、第二段本伝をもとに、一部神名を差し替えることで差違化。「大戸之道尊・大苫辺尊」の代わりに「角樴尊・活樴尊」。
登場する四世代計8神には、第二段本伝同様、「結婚の物語」、もっというと「進化の物語」がある。「土台→杭(家)→互いに賛美→誘い合う」
で、第三段一書1は、本来、第二段一書に入るべき内容。これは第一段~第三段の「神世七代」という枠内、限られた箱の中でいろいろ創意工夫した結果で。
ズラしたことで、結果的に次の四段へつながる内容として位置づけられるようになった。新しい時代へ向けた準備、あるいは、つなぎとしての役割がでてきている。
と、このように、「物語をどう紡いでいくか?」という視点が重要で。そこにこそ、日本ならではの創意工夫のスゴさが見えてくる。歴史書編纂チームがめっちゃ考えて創造した神話世界。その創意工夫の痕跡を追いかけていくことが日本のスゴさを理解していくことになる訳です!!!
次はようやっと第四段、国生み神話です!
続きはコチラ↓で!
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




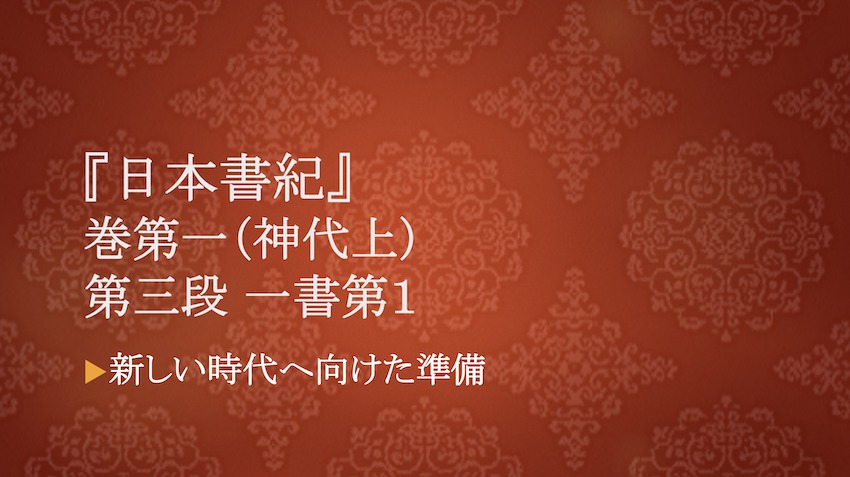
















→冒頭、「男女耦生之神」からスタート。
なんか、こう、、、強く刻んでる感じを、、、感じてもらいたいんすけど。。。
男女ペアの神ってね!!!こういう神様なんだよー
的な。
コレ、第三段本伝を引き継いでる事も暗示。「男女耦生之神」という言葉は、第三段本伝の「総括」で登場。「成男女」に根ざす言葉なので。
で、
肝心の中身はというと、、、なんと、、
第二段ソックリ!
第二段本伝をもとに、一部「神名」の差し替えで差違化してる!!
具体的には、第二段 本伝で伝える「大戸之道尊・大苫辺尊」の代わりに、第三段 一書1では「角樴尊・活樴尊」。一部差し替えでござる。
確かに、、そっくりさん一部差し替えや、、、
さらに、
第二段本伝での解説でお届けしましたが、男女耦生四世代の神名にはストーリーがあるってこと。「結婚の物語」であり、もっというと「進化の物語」で。。
と、まーキレイに並んでるし、一部だけ差し替えられてる感じですよね。
第二段本伝をもとに差違化。神名差し替え対応の巻。
ちなみに、、
話はズレますが、『古事記』はこれらを結びつけた神名列挙のかたちをとってます。
『日本書紀』第二段本伝「大戸之道尊、大苫辺尊」と、第三段一書1「角樴尊・活樴尊」を合体!盛り込んで、全5世代としてますね。
当てられてる漢字は違いますが、『古事記』では、意味的には、最初は泥砂状態の土台に杙を打ち込んで固め、その上に構造物を建造するという展開。『日本書紀』と比べて一世代増えてるので、そのぶん、その後の、お互いの賛美、誘い合い、、、の流れはナチュラルになってます。
コレはこれで記紀先後論争に入るのですが、ここから見ても、神代紀をもとに古事記が成り立ってるとみる方が自然なんですよね。神代紀の本伝と一書をつなげてできたのが『古事記』。ということで。
以上、話がズレました。
まとめると、
以上、一書1のポイントとしてチェック。