『古事記』神話をもとに、日本神話に登場する神様を分かりやすく解説します。
今回は
「天之常立神」
『古事記』では、天地初発に誕生した造化三神に続き、国が稚く浮いている脂のように海月なすただよえる時に成りました神として「天之常立神」を伝えます。
本エントリでは、「天之常立神」の神名の名義、誕生にまつわる神話について、従来の主な議論を踏まえ、実は神話的にはこう解釈すべき的なところを分かりやすく解説します。
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
天之常立神あめのとこたちのかみ|天が恒常的に(永久に)立ち続けることの神!天地初発に造化三神のあとに誕生した独神であり別天神
目次
天之常立神とは?その名義
「天之常立神」= 天が恒常的に(永久に)立ち続けることの神
『古事記』では、天地初発に誕生した造化三神に続き、国が稚く浮いている脂のように海月なすただよえる時に成りました神として、また、独神であり別天神として「天之常立神」を伝えます。
「天」は、「天」の意。高天原を含むより広義の意味での天。
「常立」=常に立つこと=恒常的に確立していることを意味。
そもそも、「常」は、独立した単語としては存在しません。ここで使われている「常」は、例えば「常し」(形容詞)「常しなへ」(形容動詞)などの「常」で、単語を構成する「語幹」です。「語幹」とは、語尾が変化する語の、変化しない(と見なす)部分のこと。で、この語幹「常」が、名詞と結びついた例が「常夏」「常宮」など。いろいろ結びつくわけです。
一方の、「立」は、「立つ」の名詞形の「たち」(動詞の連用形が名詞となる型。例:あそぶ→あそび、等)。
なので、「常立」とは、通常の用法である語幹「常」+名詞「たち」という組み合わせの形になります。
従って、常に立つこと、つまり、恒常的に確立していることを意味するのが「常立」。
「天之常立神」は、高天原に誕生した造化三神に続いて「宇摩志阿斯訶備比古遅神」のあとに誕生し、五柱の別天神の最後の神として位置づけられてます。
ということで、
| 「天之常立神」=「天」+「恒常的な確立(永久に立ちづけること)」+「神」= 天が恒常的に(永久に)立ち続けることの神 |
天之常立神が登場する日本神話
「天之常立神」が登場するのは、『古事記』上巻、天地初発の神話。以下のように伝えてます。
次に、国が稚く浮いている脂のように海月なすただよえる時に、葦牙のように萌え騰る物に因って成った神の名は、宇摩志阿斯訶備比古遅神。次に、天之常立神。この二柱の神も、みな独神と成りまして、身を隠した。
上の件の五柱の神は、別天神である。
次、國稚如浮脂而久羅下那州多陀用幣流之時流字以上十字以音、如葦牙、因萌騰之物而成神名、宇摩志阿斯訶備比古遲神此神名以音、次天之常立神。訓常云登許、訓立云多知。此二柱神亦、獨神成坐而、隱身也。
上件五柱神者、別天神。 (『古事記』上巻、天地初発部分より一部抜粋)
ということで。
まず、天地初発に誕生する神々を整理するとこんな感じ。

▲「天之常立神」は、高天原に誕生した造化三神に続いて、「宇摩志阿斯訶備比古遅神」のあとに誕生し、五柱の別天神の最後の神として位置づけられてます。
ポイント2つ。
①「天之常立神」は、別天神として天の側にいながら、独神として成りまし身を隠す
まず、「別天神」とは、「神世七代」に先立って特別に誕生したことを強調する神様カテゴリ。3(造化三神)+2=5の構成。とても尊い。
次に、「独神」として身を隠すとは、『古事記』独特の表現で、「双神」に、彼らの活躍する世界を譲り、自らは立ち退くことをいいます。
「双神」の代表格は、伊耶那岐と伊耶那美。まさに世界を創生する2神。国生みも神生みも、この世界を形作ったのは双神の御業で。
それだけでも十分すぎるほど尊い話なんですが、それよりさらに!尊い存在がいるってなれば、、、これはもう、、、よく分からない感じが必要で。
そのために、自らは立ち退くという、激しく奥ゆかしく神秘的なスタンスをとってる訳です。
やはり、、尊い存在はなかなか表には出てこないのです。。。だからこそ、なんかスゲーってなるんです。
いずれにしても、この特別感、自らは立ち退くという激しく奥ゆかしい雰囲気をチェックです。
次!
②「天之常立神」「国之常立神」の対応関係をチェック!
先ほどの神様一覧でやはり目につくのは、天之常立神と国之常立神。コレ、明らかに「天」と「国」との対応関係が組み込まれてます。
改めて、「天之常立神」は、造化三神に続く、別天神の最後の神。別天神や神名から、天の側に属すと考えられます。
一方、「国之常立神」は、対偶神の「宇比地邇神と須比智邇神」や「角杙神と活杙神」など、国土の側に属する神世七代の筆頭。
で、
この対応関係や立ち位置が重要です。
「天」の側に属する別天神の最後の神と、「地」の側に属する神世七代の最初の神という対応は、「天と地との対応」に根差している。
言い換えれば、
「天の常立」のあとに、これを引き継いで「国の常立」が成り、互いに対応する関係をかたちづくっているという事。
さらに、以下には、この国の恒常的な確立に引き続いて、国を構成する具体的な事物と神々が次々に継起的に誕生していく流れになってます。
これはつまり、
天や国の確立、そして世界を形づくる展開に道をつけるために、「天の常立の神」と「国の常立の神」を対応させ、引き継がせている、という事です。
非常にダイナミックな展開が神名を通じて埋め込まれている。ココ、是非チェック。
天之常立神にまつわる従来の議論:正訓字か借訓字か?
最後に、おまけとして、従来の議論というか、学説をご紹介します。論点は、
神名の核「常立」の「常」を
- 正訓字(「常しへ」などの常に変わらない意の漢字)とみるか、
- 借訓字(床の意の「とこ」を表すために借りた字)とみるか、
というもので、、
実は、「常立」の「常」には、こうした2つの見方があり、今もって決着がついてないんです。。。汗
ただ、、これまでは、上記確認した「2神の対応関係」を顧慮していない説が大半で。分かりやすく、従来の諸説を整理してポイントを解説したものがありますので、以下に引用します。
第一の問題は、このトコが「常」と表記されることの意味についてである。
確かに、「常」の意の「トコ」は、動詞を修飾した例を見ないから、「床」の意としたほうがよいであろう。しかし、単に「床」の意であれば、「天之床立神」と表記すればよいのであって、敢えて「常」字を用いたのは、その場のもつ恒久性を含意させたものと見るべきであろう。その意味で、正字か借字かと二者択一的に問うのは適切ではあるまい。
『古事記』注解2、上巻その一 山口佳紀氏説
ということで。
このあと、「第二の問題」とする「床」の解釈に移り、「神々生成の場がトコ(床)という語で捉えられた」と説きながら、「そのような場のもつ恒久性を表現するために、「常」の字が用いられたものと考えられる。」と結論づけています。
ただ、、、
結論付けている、場の「床」と恒久性の「常」は、両立するとは考えにくく、、、まして「常」がその両方の意味を表したというのは、後で盛り込みすぎなお話であります。。。
ここは、やはり常道にのっとって解くべきで。
「常」は、辞書の見出し語だけでも、「常し」「常しなへ」「常しへ」「常とば」「常夏」「常滑」「常宮」「常闇」「常世」「常夜」など、それこそ枚挙にいとまがありません。
動詞を修飾する例が「常」にないからといって、杓子定規的に「床立」を当てるだけでは、かえって本質を見失ってしまいます。本来の「常」の意味に立ち返り、前後の文脈と関係性を踏まえて解釈することが重要です。
なので、
常に立つこと、つまり、恒常的に確立していることを意味するのが「常立」としてチェックです。「天之常立神」の本質もそこにあります。
天之常立神を始祖とする氏族
無し。
ただ、、『新撰姓氏録』では「天底立命」があって、これが「天常立尊」の音変化であるとするならば、伊勢朝臣(左京、神別、天神)の始祖となる。という説もあり。
天之常立神 まとめ
「天之常立神」= 天が恒常的に(永久に)立ち続けることの神
『古事記』では、天地初発に誕生した造化三神に続き、国が稚く浮いている脂のように海月なすただよえる時に成りました神として、また、独神であり別天神として「天之常立神」を伝えます。
「天之常立神」は、別天神として天の側にいながら、独神として成りまし身を隠す。この特別感、自らは立ち退く立場をとるという激しく奥ゆかしい雰囲気をまずチェック。
続けて、「天之常立神」と「国之常立神」の2神の誕生は、
「天」の側に属する別天神の最後の神と、「地」の側に属する神世七代の最初の神という対応であり、大きく、「天と地との対応」に根差している。
さらに、
天や国の確立、そして世界を形づくる展開に道をつけるために、「天の常立の神」と「国の常立の神」を対応させ、引き継がせている。
非常にダイナミックな展開が神名を通じて埋め込まれていることもしっかりチェックです。
天之常立神が登場する日本神話の詳しい解説はコチラ!
天之常立神をお祭りする神社はコチラ!
● 春日大社の天神社 天の神ということで天神社!
住所:奈良県奈良市春日野町160● 總社大神宮 聖武天皇勅祭社 越前国に鎮座する国司所祭の神霊を一カ所に合祀!本殿で配祀されてます
住所:福井県越前市京町1-4-35● 駒形神社 日本最高神のほか、宇宙・地球を守護する神さまをお祀り中!
住所:岩手県奥州市水沢区中上野町1-83
コチラも是非!日本神話の流れに沿って分かりやすくまとめてます!
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




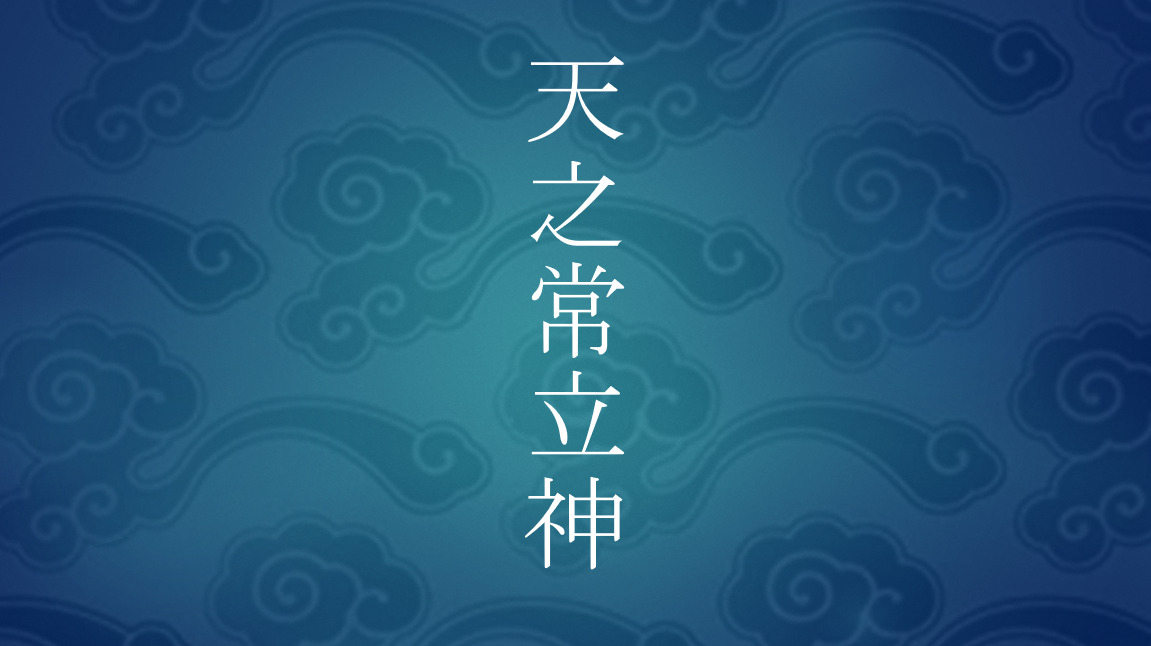

















最後までお読みいただきありがとうございます。お気軽にコメントされてくださいませ。お待ちしております!