『古事記』神話をもとに、日本神話に登場する神様を分かりやすく解説します。
今回は
「天両屋」
です。「両児嶋(現在の、五島列島の南の男女群島(長崎県福江市)」の名として、『古事記』上巻、国生み神話で登場。
本エントリでは、「天両屋」の神名の名義、誕生にまつわる神話を分かりやすく解説します。
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
天両屋あめのふたや|天空にある二つの屋根。大八嶋国を生んだ後、戻る途中で生んだ6嶋のひとつ両児嶋を神格化
目次
天両屋とは?その名義
「天両屋」= 天空にある二つの屋根
『古事記』では、大八嶋国を生み終えたあと引き返すときに6つの嶋が生まれたと伝えており、その6番目に生まれた嶋が両児嶋(現在の、五島列島の南の男女群島(長崎県福江市)。この嶋の名として「天両屋」を伝えます。
古代、東シナ海における要衝の島としてあり、その反映と思われます。
「天の」は、自然界の「天」。
「屋」は、屋根の形をした島。
五島列島の南の男女群島(長崎県福江市)で、男島と女島とが並んでいることからの命名。その形から「両屋」といい、海上遠く天空に見えるので「天の」を冠したもの。
天両屋が登場する日本神話
「天両屋」が登場するのは、『古事記』上巻、国生み神話。以下のように伝えてます。
その後、還り坐す時、吉備児嶋を生んだ。またの名は建日方別という。次に、小豆嶋を生んだ。またの名は大野手比売という。次に、大嶋を生んだ。またの名は大多麻流別という。次に、女嶋を生んだ。またの名を天一根という。次に、知訶嶋を生んだ。またの名は天之忍男という。次に、両児嶋を生んだ。またの名は天両屋という。吉備の児島から天両屋の島まで合わせて六つの島である。 (引用:『古事記』上巻より一部抜粋)
「然る後、還り坐す時(然後、還坐之時)」とあり、柱巡りして大八嶋国を生み終え引き返すときに6つの嶋が生まれたようで、その6番目に生まれた嶋が両児嶋(現在の、五島列島の南の男女群島(長崎県福江市)であり、この名として「天両屋」を伝えます。

▲青文字が、還り坐す時に誕生した6嶋。⑥が「天両屋」です。
『古事記』は、生んだ嶋に神名をつけることで神格化してるのがポイント。
この理由は、誕生した大八嶋国が、伊耶那岐と伊耶那美の子供であること、血縁関係にあること、生まれた島々が血脈によるつながりをもっていることを明確にするためです。
天両屋を始祖とする氏族
嶋の名なので、氏族の始祖とはなりません。
参考文献:新潮日本古典集成 『古事記』より一部分かりやすく現代風に修正。
「天両屋」が登場する日本神話はコチラ!
コチラも是非!日本神話の流れに沿って分かりやすくまとめてます!
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




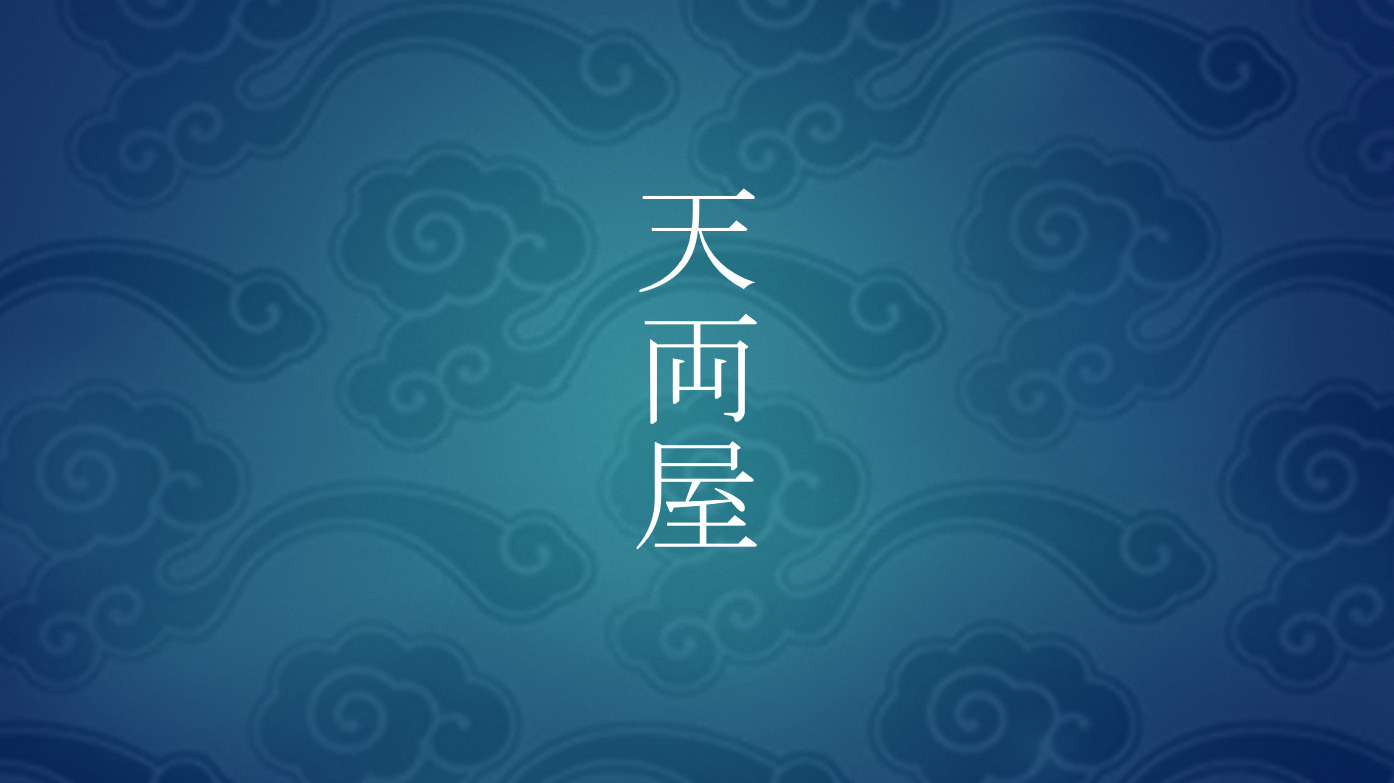
















最後までお読みいただきありがとうございます。お気軽にコメントされてくださいませ。お待ちしております!