『古事記』や『日本書紀』もとに、日本神話に登場する神様を分かりやすく解説します。
今回は
「大山津見神・大山祇神」
『古事記』では、伊耶那岐命と伊耶那美命の二柱の神が生んだ「山の神」として、神生み神話で登場。
『日本書紀』でも同じく、山の神として登場するのですが、伝承ごとに神名がさまざまに変化します。
今回は、『古事記』で伝える内容と、『日本書紀』で伝える内容を分けてそれぞれ解説します。
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
大山津見神・大山祇神おおやまつみのかみ|偉大な山の神霊!娘を皇孫に嫁がせることで重要な役割を担う神。日本神話をもとに大山津見神・大山祇神を分かりやすく解説します。
目次
大山津見神の名義
「大山津見神」= 偉大な、山の神霊
伊耶那岐命と伊耶那美命が、大八嶋国における自然物の生起プロセスで生んだ「山の神霊」。
「大」は、美称で、「偉大な」の意。
「山」は、そのまま「山」の意。
「津」は、連体助詞。
「見」は、「神霊」の意で、「精霊」よりも神格が高い存在。
ということで
| 「大山津見神」=「偉大な」+「海」+助詞+「神霊」= 偉大な、山の神霊 |
『古事記』で伝える大山津見神
「大山津見神」が登場するのは、『古事記』上巻、神生み神話。以下のように伝えてます。
次に風の神、名は志那都比古神を生み、次に木の神、名は久久能智神を生み、次に山の神、名は大山津見神を生み、次に野の神、名は鹿屋野比売神を生んだ。またの名は野椎神という。(志那都比古神より野椎に至るまで、幷せて四神ぞ)。
次生風神・名志那都比古神(此神名以音)、次生木神・名久久能智神(此神名以音)、次生山神・名大山上津見神、次生野神・名鹿屋野比賣神、亦名謂野椎神。自志那都比古神至野椎、幷四神。 (引用:『古事記』上巻の神生みより一部抜粋)
ということで。
系譜は以下の通り。

▲「大山津見神」は、大事忍男神から始まる10柱の神々のあとに誕生。あくまで、伊耶那岐命と伊耶那美命の2神が生んだ神として。
大八嶋国に生起する自然現象のような神だったのが、段階的に、より具体的な自然物を表すようになっていくプロセスで生まれます。さらに、「(志那都比古神より野椎に至るまで、幷せて四神ぞ)。」とあり、ひとつのカタマリとして位置づけられてる。
ポイントは、
『古事記』ならではの、壮大なストーリーらしきものがある!
てことで。
最初の風神は、大八嶋国を生んだ後だからこそ何もない状態、きっと生まれたての神々と朝霧が立ちこめてるだけの状態で、それを吹き払った気息が化して神(志那都比古神)となったイメージ。 そして、木の神(久久能智神)は、風神の存在を、木々の揺らぎによってそれと知らせるもの。 さらに、山の神(大山津見神)は、山林、豊かに木々の繁る山だから、国土が豊かに成長しているさまを表象。 最後に、野の神(鹿屋野比賣神(野椎神))は、山・野・原という大地を構成する3つの場の中間地帯。このあと、葦原中国の葦原が生まれることを予定する。そしてきっとそこには人間の姿も・・・
そのために、風、木、山、野という4柱の神が誕生してる。修理固成のための壮大なストーリーをチェック。
いずれの神も、大八嶋国に必要な神であり、それは、将来的には「瑞穂の国」になっていくために必要な神として生んでるんです。
ちなみに、、
『古事記』では他に「山津見」とつく八種の山の神が、伊耶那岐神の斬り殺した火神の死体から生まれてます。
それらは死体の各部位に成った神々で、山の特定の部位に関する名称を持つことから、山一般に関わる神格ではなく、山の一部や限定的な信仰の様態にまつわる山の神であると考えられてます。
一方の「大山津見神」は、そうした限定がなく、「大」という美称がついていることから、ひろく山一般に関わる、山津見の中の代表格のような存在とされてます。
山祇とは?『日本書紀』では山、あるいは山神
続けて、『日本書紀』で伝える「山の神」をご紹介。
『日本書紀』では、誕生シーンで5つ。その後の活動で2つの神話を伝えます。
『日本書紀』で伝える「山の神」の誕生
まずは、一番の基本形から。
『日本書紀』第五段〔本伝〕から。
次に海を生んだ。次に川を生む。次に山を生む。次に木の祖、句句廼馳を生む。次に草の祖、草野姫を生む。またの名を野槌と言う。 (引用:『日本書紀』巻第一(神代上)第五段〔本伝〕より)
ということで。
ここでは、神とか神霊とかでもなく、自然物としての「山」誕生を伝えてます。
続けて、、、第五段〔一書6〕から。
ある書はこう伝えている。伊奘諾尊と伊奘冉尊は共に大八洲国を生んだ。
その後に、伊奘諾尊は、「私が生んだ国は朝霧だけがかすんで立ちこめ満ちていることよ。」と言った。そこで吹き払った気が化して神となった。名を級長戸辺命と言う。また級長津彦命と言う。これが、風の神である。また飢えた時に子を生んだ。名を倉稲魂命と言う。また、海神等を生んだ。名を少童命と言う。山神等は名を山祇と言い、水門神等は名を速秋津日命と言い、木神等は名を句句迺馳と言い、土神は名を埴安神と言う。その後に、悉くありとあらゆるものを生んだ。 (引用:『日本書紀』巻第一(神代上)第五段〔一書6〕より)
ということで。
「山神等は名を山祇と言い、」とあるように、『日本書紀』的に初めて神化し、名を「山祇」というようになります。
続けて、、、
第五段〔一書7〕より。
ある書はこう伝えている。伊奘諾尊は剣を抜き軻遇突智を斬り、三つに刻んだ。そのうちの一つは雷神となった。もう一つは大山祇神と成り、一つは高龗と成った。 (引用:『日本書紀』巻第一(神代上)第五段〔一書7〕より)
ということで。
伊奘諾尊が火神「軻遇突智」を3つに切り刻むという非常に激しいシーンのなかで、「大山祇神」として誕生しています。火神を3つに刻んだうちの一つから成ったわけで、、火山の表象として見る説もあったり。
続けて、、、
第五段〔一書8〕より。
ある書はこう伝えている。伊奘諾尊は軻遇突智命を斬り、五つにばらした。これがそれぞれ五つの山祇に化成した。一つは首で大山祇と成った。二つは身体で中山祇と成った。三つは手で麓山祇と成った。四つは腰で正勝山祇と成った。五つは足で䨄山祇と成った。
この時、斬った血がほとばしり流れ、石や礫、樹や草を染めた。これが草木や砂礫がそれ自体に火を含み燃えるようになった由縁である。
麓は、山のふもとのことを言う。これを「はやま」と読む。正勝、これを「まさか」と読む。ある書では「まさかつ」とも読まれる。䨄これを「しぎ」と読む。音は烏含の反。
ということで。
同じく火神「軻遇突智命」を、今度は5つに切り刻んだときに成った神として五種類の「山祇」を伝えます。
『日本書紀』で伝える「山の神」の活動
第五段で誕生した「山の神」ですが、その後の活動は以下の通り。
その時、その国に美人がいた。名を鹿葦津姫と言う。<またの名は神吾田津姫。またの名は木花之開耶姫>。皇孫がこの美人に、「おまえは誰の子か」と尋ねると、「私は天神が大山祇神を娶って生んだ子です。」と答えた。 (『日本書紀』第九段〔本伝〕より)
別伝、第九段〔一書2〕では以下のように伝えます。
そこで、天津彦火瓊瓊杵尊は日向の串日高千穂峯に降り立ち、不毛の地を丘づたいに国を求めて通り、浮島のある平らな土地に立った。そして、國主の事勝國勝長狭を呼んで尋ねると、「ここに国があります。どうぞご自由に」と答えた。そこで皇孫は宮殿を立て、そこで休息した後、海辺に進んで一人の美人を見かけた。皇孫が、「おまえは誰の子か」と尋ねると、「私は大山祇神の子です。名は神吾田鹿葦津姫、またの名は木花開耶姫です」と答え、さらに、「また、私には姉の磐長姫がいます」と申し上げた。皇孫が、「私はあなたを妻にしようと思うがどうか」と尋ねると、「私には父の大山祇神がいます。どうかお尋ねください」と答えた。皇孫がそこで大山祇神に、「私はあなたの娘を見かけた。妻としたいと思う」と語ると、大山祇神は二人の娘に多くの飲食物を載せた机を持たせて進呈した。すると皇孫は、姉の方は醜いと思って招くこともなく、妹の方は美人であったので招いて交わった。すると一夜にして身籠った。そこで磐長姫は大いに恥じ、「もし天孫が私を退けずに招いていたら、生まれる子は長寿で、堅い岩のように長久に繁栄したことでしょう。今そうではなく妹だけを一人招いたので、生まれる子はきっと木の花のように散り落ちることでしょう」と呪詛を述べた。――あるいは、磐長姫は恥じ恨んで、唾を吐いて泣き、「この世の人々は木の花のように儚く移ろい、衰えることでしょう」と言った。これが世の人が短命であることの発祥であると言う。 (『日本書紀』第九段〔一書2〕より)
大山津見神を始祖とする氏族
なし
「大山津見神」が登場する日本神話はコチラ!
参考文献:新潮日本古典集成 『古事記』より一部分かりやすく現代風に修正。
「大山津見神」をお祭りする神社
● 大山祇神社 主祭神の大山祇神は「三島大明神」とも称され、当社から勧請したとする三島神社は四国を中心に新潟県や北海道まで分布
住所:愛媛県今治市大三島町宮浦3327
● 大山祇神社 一生に一度の願いは三年続けてお参りすれば、どんな願いもかなえてくれるの野沢の山の神様!
住所:福島県耶麻郡西会津町野沢大久保甲1445−2
コチラも是非!日本神話の流れに沿って分かりやすくまとめてます!
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




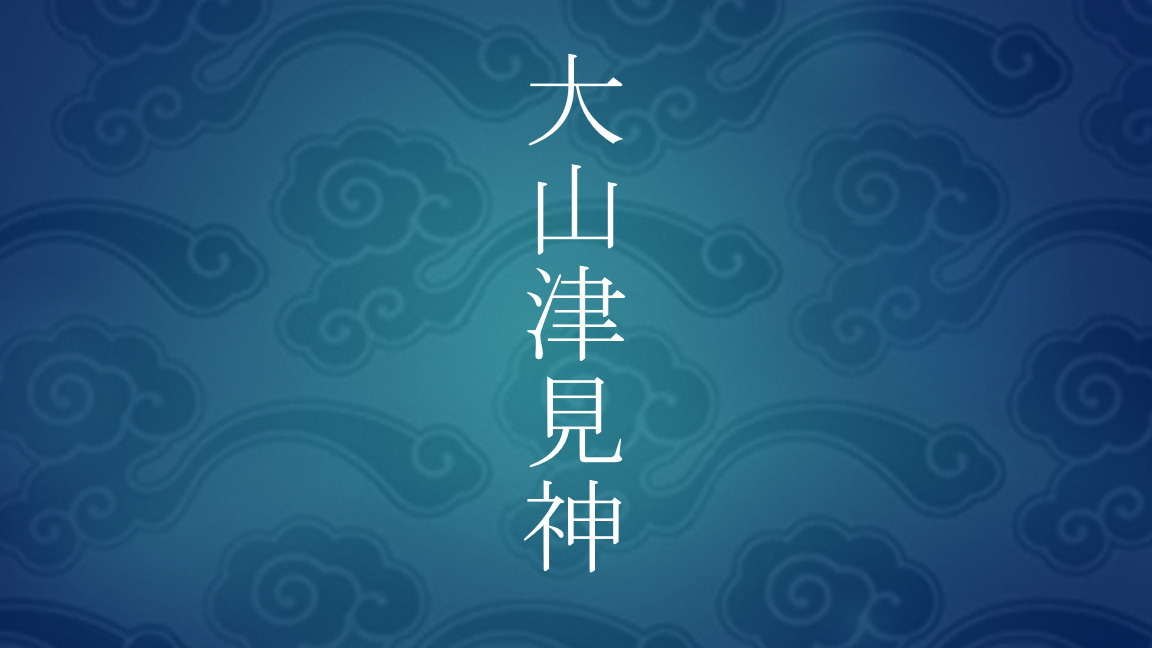

















最後までお読みいただきありがとうございます。お気軽にコメントされてくださいませ。お待ちしております!