多彩で豊かな日本神話の世界へようこそ!
正史『日本書紀』をもとに、
最新の文献学的学術成果も取り入れながら、どこよりも分かりやすい解説をお届けします。
今回は、神武東征神話を分かりやすく解説するシリーズ2回目。
テーマは、
東征発議と旅立ち
東征するにあたって、「彦火火出見」=神武は、兄達や子供、臣下を集め「発議」を行います。
壮大すぎる構想をどのように伝え、動機付けしたのか?
そんなロマンを探る事で、「東征発議と旅立ち」が伝える意味を読み解きます。
今回も、概要で全体像をつかみ、ポイント把握してから本文へ。最後に、解説をお届けしてまとめ。
現代の私たちにも多くの学びをもらえる内容。日本神話から学ぶ。日本の神髄がここにあります。それでは行ってみましょう!
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
神武紀|東征発議と旅立ち|東征の動機とか意義とか建国の決意とかをアツく語った件
目次
神武紀|東征発議と旅立ちの概要
『日本書紀』巻三「神武紀」をもとにお届けします。前回の内容、これまでの経緯はコチラ↓を確認ください。
そのうえで、、
東征するにあたって、彦火火出見=神武天皇は、兄達や子供、臣下を集め「発議」を行います。いきなりレッツゴーではなく、しっかり企画提案・動機づけを行なう訳ですね。
自身の生い立ちと、これまでの経緯をふまえて、東征の意義と建国の決意をアツく語ります。
この東征発議、実は「日本最古の演説」ながら、素晴らしい仕上がりになっております。現在のビジネスシーンでも十分活用できる内容であり、めっちゃ参考になる。後ほど詳しく解説。
ということで、さっそく現場をチェック。
神武紀|東征発議と旅立ち
(彦火火出見が)四十五歳になったとき、兄達や子供等に語った。
「昔、我が天神である高皇産霊尊・大日孁尊は、この豊葦原瑞穂国のすべてを我が天祖である彦火瓊瓊杵尊に授けた。そこで火瓊々杵尊は、天の関をひらき、雲の路をおしわけ、行列を駆りたて地上へ至った。この時、時勢は遥か遠い昔に属し、混沌として暗い時代だった。それゆえ、物事の道理に暗い者たちを正しい道に導きながら、西のはずれの地を治めた。
我が祖父と父は霊妙な神であり物事の道理に精通した聖であって、素晴らしい政により慶事を重ねその徳を輝かせ、そして多くの歳月が経過した。天祖が天から降ってから今まで179万2470有余年が過ぎた。しかし、遠く遥かな地は、いまだ王の徳のもたらす恩恵をうけておらず、果ては国には君が有り、村には長がいて、各自が支配地を分け互いに争い合っている。
さて、塩土老翁 からはこんな話を聞いた。『東に美しい土地があって、青い山々が四方を囲んでいる。そこに天磐船に乗って天から飛び降った者がいる。』と。私が思うに、かの地はきっと、王としての業績を広く大きくし、王の徳を天下のすみずみまで届けるのにふさわしい場所に違いない。そこが天地四方の中心だろう。そこに飛んで降りた者とは「饒速日」という者ではないだろうか。私はそこへ行き都としたい。」
諸々の皇子は、「なるほど、建国の道理は明白です。我らも常々同じ想いを持っていました。さっそく実行すべきです。」と賛同した。この年は、太歳・甲寅(紀元前667年)であった。
その年の冬10月5日に、彦火火出見は、自ら諸皇子や水軍を率いて、東へ進発した。
及年卌五歲、謂諸兄及子等曰 「昔我天神、高皇産靈尊・大日孁尊、舉此豐葦原瑞穗國而授我天祖彥火瓊々杵尊。於是火瓊々杵尊、闢天關披雲路、驅仙蹕以戻止。是時、運屬鴻荒、時鍾草昧、故蒙以養正、治此西偏。皇祖皇考、乃神乃聖、積慶重暉、多歷年所。自天祖降跡以逮于今一百七十九萬二千四百七十餘歲。而遼邈之地、猶未霑於王澤、遂使邑有君・村有長・各自分疆用相凌躒。抑又聞於鹽土老翁、曰『東有美地、靑山四周、其中亦有乘天磐船而飛降者。』余謂、彼地必當足以恢弘大業・光宅天下、蓋六合之中心乎。厥飛降者、謂是饒速日歟。何不就而都之乎。」 諸皇子對曰「理實灼然、我亦恆以爲念。宜早行之。」是年也、太歲甲寅。 其年冬十月丁巳朔辛酉、天皇親帥諸皇子舟師東征。 (『日本書紀』巻三 神武紀より一部抜粋) ※原文中の「天皇」という言葉は、即位前であるため、生前の名前であり東征の権威付けを狙った名前「彦火火出見」に変換。
※橿原神宮で公開中の「神武天皇御東征絵巻」より
神武紀|東征発議と旅立ちの詳細解説
リーダーとして、兄達や子供ら、そして臣下たちに東征の意義と建国の決意を語るシーンは、東征神話の中でも非常に重要な位置づけです。東征神話全体の起点になってる。
神武が語った東征発議、ポイントを整理すると以下の通り。
| 経緯 |
・遥か昔、天神の「高皇産霊尊」「大日孁尊」が「豊葦原瑞穂の国」を「彦火瓊瓊杵尊」に授けた。 |
| 現状認識 |
・遠く遥かな地は、いまだ王の徳のもたらす恵みとその恩恵をうけていない。 |
|
目的 |
・「世界の中心」へ行き「都」としたい。 |
| 目標 (ゴール設定②) |
「世界の中心」=六合之中心 |
ということで、
ま、後付け整理になるかもしれませんが、それでも、自らの出自とあわせて、これまでの経緯、現状認識、建国によるメリット(王の徳による民が受ける恩恵)を分かりやすく語っていますよね。
当時の理想的指導者が「事を成す」必要性、必然性、適時性を丁寧に説明し、問題を明確にして一丸となって実行する。
「日本最古の演説」ながら、そのレベルの高さにビックリです。1つの演説として、動機づけの方法としても非常に参考になると思います。そんなロマンに想いを致しながら、、、
以下詳細解説。
まとめ
東征発議と旅立ち
『日本書紀』巻第三(神武紀)からお届けしてきましたが、いがでしたでしょうか?
チェックしてきたポイントは以下の通り。
- 東征するにあたって、「彦火火出見=神武天皇」は、兄達や子供、臣下を集め「発議」を行います。いきなり出発しちゃうのではなく、しっかり企画提案・動機づけを行なう。
- 東征発議は「日本最古の演説」ながら、素晴らしい仕上がり。現在のビジネスシーンでも十分活用できる内容であり、参考になる。
- 内容について、冒頭、神武は、神代紀の二つの伝承を結びつけ、新たな神話を構想。コレ、豊葦原中国を瓊々杵尊に授けたことをめいっぱい権威づけるため。
- 東征神話的伏線設定あり。天孫降臨を再現することで回収を図っていく壮大な仕掛けが埋め込まれてる。
- ニニギによる西偏統治は『易』を手本としている。
- 神代から神武紀へ、「継起性で展開する世界」から「時間の世界」へ。時間表現は、神代のあとを引き継ぐ神武紀の重要な特徴の一つ。
- 歴史が天孫降臨に始まったとし、歴史経過の時間を具体的に179万年と明示。つまり、天孫降臨を境に、それ以前を、無時間の神代、それ以降を時間軸にもとづく歴史とする区分がここに成り立った、ということ。
- 東征は、この社会の混乱に終止符をうち、正しい秩序や教化をもたらす偉大な事業として始まった。
- 神武は「物知り爺さん」という偉大な側近を得ていた。
- 東征は、瓊々杵尊以来受け継いできた地上統治の「わざ」を広げていくこと、さらにその先には、豊葦原瑞穂の国の平定と統治が見据えられてる。そうした大業を成す場所こそが「六合之中心」。コレが東征の目的、その核心。
- 東征を発議し、実行に移す年を「歴史の始源」すなわち元年として位置づけてる。暦年の始まりは、同時に「四時」の始まりでもある。
今回ご紹介したのは、一部なのですが、深堀りすると、いろいろなオモシロ設定があって、非常に奥ゆかしい神話になってることが分かります。
『日本書紀』編纂チームの創意工夫の結晶、その構想力がスゴくて震える((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル 現代の私たちにも、多くの学びをもらえる内容だと思います。
つづきはコチラ!航海順風ガンガン行こうぜ!
神武東征神話のまとめ、目次はコチラ!
神話を持って旅に出よう!
神武東征神話のもう一つの楽しみ方、それが伝承地を巡る旅です。以下ご紹介!
● 皇宮神社:東征発議の場!??実は、15歳からこの皇宮屋に移って政治を行なっていたらしい、、
● 神武天皇御舟出の地:神武天皇が東征の航海に船出した地!?
● 立磐神社:船出の際に、航海の安全を御祈念、海上の守護神住吉三神を奉斎したことにちなむ
●磐船神社:饒速日命が天から降った時に乗ってた天磐船が御神体!?
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
こちらの記事もどうぞ。オススメ関連エントリー
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




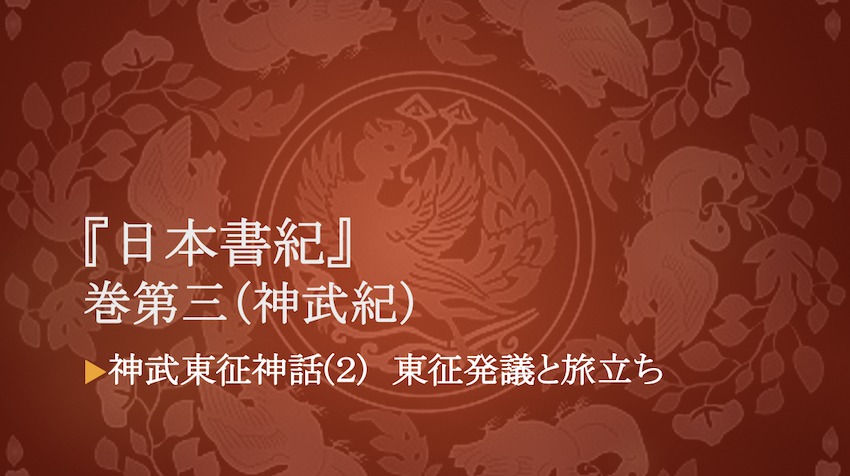


























→45歳になったときに東征発議。この時すでに中年のおっさんです。
でも、そんなのにひるまない神武天皇こと彦火火出見。生い立ちのところであった「生まれながらにして英明、意志堅固」を遺憾なく発揮。末の弟が、兄たちや子供たちに建国の決意を語る。。とんでもない構想をぶち上げる訳です。
次!
→いきなりですが、ココ、重要ポイント。東征発議の起点は天孫降臨から。
先に言葉の解説を少し。
「豊葦原瑞穂国」は、神代・国生みにて、天神が伊奘諾・伊奘冉に指令した「豊葦原千五百秋瑞穂之地」をふまえた言葉。
「すべてを(原文:舉)」の「舉」は、ことごとく、すべてをあわせて、という意味。徹底的な網羅的な感じ重要。
「我が天祖である彦火瓊瓊杵尊(原文:我天祖彥火瓊々杵尊)」について。
天祖=彦火瓊瓊杵尊としてる訳ですが、まず、直前の、高皇産霊尊・大日孁尊を「天神」と言ってるのとは敢えて別の言葉で表現してます。瓊瓊杵尊も天神なんだが。。これってつまり、神武的にはやはり、豊葦原瑞穂国のすべてを授けられた瓊瓊杵尊は別枠で重要だったってこと。それは、地上支配の起点、出発点、つまり祖たる位置づけなんで、「天祖」という言葉を使ってる訳です。
ちなみに、、本来、高皇産霊尊・大日孁尊に対しては「皇祖」という言葉が使われます。「皇祖」は、本来、天皇の血統に関わる特定の存在のみに用いられる特別な言葉で。巻二では、瓊瓊杵から見た高皇産霊尊や天照大神を指し、巻三では、神武から見た皇産霊尊や天照大神を指します。まさに皇統の祖。
実際、東征神話後半の頭八咫烏派遣救援シーンでは「皇祖の天照大神が、東征の大業を成し遂げようと助けてくれたのだ。」と叫ぶシーンがあったりします。つまり、神武としては皇祖=天照大神な訳です。
なので、
もともと神代から使われていた「皇祖」という言葉があって、高皇産霊尊・大日孁尊を指していたんだが、神武的にはやっぱり地上支配の起点、祖たる位置づけの瓊瓊杵尊は別枠で重要なんで、ここはやはり「天祖」という言葉を創造して言っておきたかった、ってことで、神武の瓊瓊杵推しとあわせてチェック。
その上で、
まず、なんで高皇産霊尊、大日孁尊(=天照大神)なのか?について。2つ。
①なぜ高皇産霊尊なのか?それは、国譲りや天孫降臨の際に、皇孫のために心を砕き、大変なご活躍をしていただいた天神だから。
これまでの経緯を言うと、『日本書紀』巻第二(神代下)第九段〔一書2〕では、
と、確かに、、ありがたいことこの上ない。。
特に、3つ目の「皇孫のために祭祀」、原文「為吾孫奉斎」は超重要で。
自らも皇孫のために祭祀をするし、二神にも祭祀をするように命じてる。。スゴくないすか?高皇産霊尊自ら皇孫のためにお祭りをしてたなんて、、、神武的には、これを踏まえて言ってる訳です。
そして、
②なぜ大日孁尊なのか?天照大神としていない理由は?それは、神武的には天照大神をあくまで「日神」として位置づけているから。
東征神話における重要イベント、中盤の孔舎衛坂敗戦の理由、神策の理論、熊野での天照大神の救援など、これらすべて天照大神が「日神」=太陽神として位置づけられてることに由来してます。
そして、神代において、日神として登場したのが『日本書紀』巻第一(神代上)第五段〔本伝〕。
ここでは、
「そこで、共に日神を生む。名を大日孁貴と言う。(大日孁貴、ここでは於保比屢咩能武智と言う。孁は、音は力丁の反である。ある書には、天照大神と言う。ある書には、天照大日孁尊と言う。)この子は、光り輝くこと明るく色とりどりで、世界の内を隅々まで照らした。」と伝え、まさに日神(太陽神)としての特性が強く打ち出されてました。これを踏まえてるんですね。
神武東征神話は、神代とのつながり、神代の設定が決定的に重要で。それらを踏まえるからこそ、東征に説得力や正当性が生まれるようになってる訳です。
だからこその高皇産霊尊、大日孁尊。このあたりもしっかりチェック。
ちなみに、、
この二神、東征神話中盤で絶体絶命の危機に陥ったときに再登場。ココではその布石、伏線としての意味もあり。
そして最後!!
③天孫降臨の二つの伝承を結びつけ、新たな神話を構想することで、瓊々杵とのつながりを根拠とした正統性を強化
改めて、神武が言ってることを整理すると、ポイントは、
高皇産霊尊・大日孁尊(天照大神)が、彦火瓊瓊杵尊に国を授けたとしてるってこと。
なんだが、
実はこれ、神武が構想した新たな神話とも言うべき内容だったりして。つまり、神代のことを再構成して語ってるんです。
細かく言うと以下の通り。
瓊々杵尊に国を授けたシーン、つまり、天孫降臨には2つの伝承があります。
で、ここでのポイントは、
神武は、両方の伝承を取り入れて一つにまとめた、ってこと。二つの伝承を結びつけ、新たな神話を構想したんです。
コレ、なんでかというと、瓊々杵尊に授けたことをめいっぱい権威づけるため。
伝承的にはアレコレあるけど、高皇産霊神も天照大神も、瓊々杵尊に授けたことは同じ。なので、それをまとめようと。そうすることで瓊々杵集約&推しをしてやろうと。
それは、そもそもが、神武の生前の名「彦火火出見」は、瓊々杵尊の子である山幸彦の名前であり、名前を通じて「瓊々杵尊の子」というつながりをつけてあるんで。ここで、さらに集約することで瓊々杵とのつながりを根拠とした正統性は強まりますよね。
すごい戦略的。。何かにつけて神武の瓊々杵リスペクト・瓊々杵エビデンスは徹底してる。これ、しっかりチェック。
次!
→瓊々杵尊が天孫降臨し、地上を治めはじめたときのことを言ってます。
先に言葉の解説をモリッと。
「天の関をひらき(原文:闢天關)」について。「天關」は天の関、関所。「闢」は、ひらく、ひらける意。門を左右に大きく開く、または力を込めて切り開く動作を指す。なので、天にある関所の門を大きく開くこと。きっと壮大・荘厳な門で、その巨大な扉が左右に押し開かれていく感じだったのだろう。。。
「雲の路をおしわけ(原文:披雲路)」について。「雲路」は雲の路。道。「披」は、ひらく、広げる意。なので、雲の路・道をおしわけ進むこと。
「行列を駆りたて(原文:驅仙蹕)」について。「仙蹕」は行幸の行列、天子の車駕の列のこと。「蹕」はさきばらい。前方の通行人や障害物を取り除き、安全を確保する役割を言います。天子の行列には当然、こうした先ばらいがいる訳で。天孫降臨時は、天忍日命らが担当。「驅」は駆り立てる意。
「地上へ至った(原文:戻止)」は、至ること、来ること。戻=来、止=至の意味あり。天孫降臨のことなので、地上へ至る。
「時勢は遥か遠い昔に属し、混沌として暗い時代だった(原文:運屬鴻荒、時鍾草昧」について。
「鴻荒」は、「鴻(おおきい)」と「荒(荒れ果てた、混沌)」で、非常に遠い昔、世界の始まりの混沌とした太古の時代を意味。「運」は、歴史的な「時勢」や「巡ってきた時代の局面」のこと。
「草昧」は、「草が茂って暗い」が原義で、転じて、まだ文化が発達しておらず、秩序がなく、混沌としている様子の意。『易経』の表現、「天造草昧」から。で、「鍾」は、当たる。なので、時は混沌として暗い状態であった。そういう時代だった。
「物事の道理に暗い者たちを正しい道に導く(原文:蒙以養正)」は、『易経』蒙卦に由来する言葉で、蒙昧=知識や学問がなく、物事の道理に暗いことや、愚かで判断力に欠ける状態な者たち、を教化して正しい道に導くこと。実は、『易経』蒙卦の「蒙以養正、聖功也」をそのまま引用してます。
ちなみに、、「蒙卦」は、易経(周易)の六十四卦の第4番目「山水蒙」を指し、山の下に水(泉)が湧き出る形を表し、物事がまだ幼く、暗く不明瞭な「啓蒙」や教えの時期を意味。蒙ってのはそういう意味な訳です。
その上で、、
ポイント2つ。
①東征神話的伏線?天孫降臨を再現することで回収を図っていく壮大な仕掛け
「火瓊々杵尊は、天の関をひらき、雲の路をおしわけ、行列を駆りたて地上へ至った。」とあります。コレ、まさに天孫降臨のことで。
ポイントは、降臨に際し行列の先ばらいを務めたのはどの神だったのか? 『日本書紀』神代紀第九段〔一書4〕では、次のように伝えてます。
ということで、
ここでは、天忍日命が天槵津大来目を率いてきらびやかに武装し天孫の先導を担ったことを伝えてます。神武の言う「行列を駆りたて」がまさにコレ。
で、重要なのは、東征神話中盤以降で活躍する「道臣」や東征の軍隊「大来目」が、実は天忍日命や天槵津大来目の子孫だったりする訳です。
なお、
臣下「道臣」の活躍が際立つのはコチラ↓
軍隊「大来目」が活躍するのはコチラ↓
これ、構造的にまとめると、、
てことで、これってつまり、
歴史記述のなかに神代伝承を引き継ぐ内容をいれることで、神代伝承が、つまり神話が歴史の中に組み込まれるようになる。。ってことなんす!スゴイよね、この構想力。発想力。
神代から仕掛けられた壮大な伏線と回収の仕掛けをチェックです。
さらに!
②瓊瓊杵降臨の時代は草昧。荒ぶる神々が跋扈する世界、人間は多分その辺の草状態??
「時勢は遥か遠い昔に属し、混沌として暗い時代だった(原文:運屬鴻荒、時鍾草昧)」とあります。これ、実際にどんな状況だったのか、神代、天孫降臨前後から拾ってみると、、、
とか、、、
まーヤバめな雰囲気プンプンな訳です。もちろん、武甕槌神と經津主神に平定はさせるんだが、、そして時代が下って少しはマシになったんじゃないか、、とは言え「草昧」、つまり混沌として無秩序で暗い感じの世界だったんじゃないかと推測される訳です。
だからこそ!「物事の道理に暗い者たちを正しい道に導く(原文:蒙以養正)」ことが必要だった訳です。この言葉だけで解釈すると、めっちゃ上からというかマウント感満載なんだが、背景や経緯をふまえると理解できるようになるのでは、、、
少なくとも、悪意をもって言ってる訳じゃないのだけは理解してほしい。。。
次!
→素晴らしい政治により徳を輝かせるプロセスを積み上げて179万年!!果てしない、、、
先に言葉の解説を少し。
「皇祖皇考」は、祖父と父のことで、火火出見尊と鸕鶿草葺不合のこと。瓊瓊杵を「天祖」と呼んだことに対応する形で設定されてます。
ちなみに、、先ほど解説したとおり、本来、「皇祖」という言葉自体は、高皇産霊尊や天照大神を指すんだが、ここでは、文脈整理から、祖父のことを言います。
「素晴らしい政により慶事を重ねその徳を輝かせ(原文:積慶重暉)」は、簡単にいうと、慶事を重ね、暉=輝きを重ねること。『文選』巻五八に由来し、代々家が繁栄することが原義。ここでは、素晴らしい政治を行い国に福徳を及ぼしてきた、という意味。
「以逮い」は、漢文訓読において「〜に至るまで」「〜に及ぶまで」という意味。主に「自り…以逮る」という形で、ある起点から終点までの時間や範囲を示す際に用いられます。つまり、「天祖降跡」から「今」に及ぶまで一百七十九萬二千四百七十餘歲!!
その上で、、
「天祖が天から降ってから今まで179万2470有余年が過ぎた」とあります。コレ、さらっと流してはいけません。
革命です。革命。
ポイント3つ。
①神代から神武紀へ。「継起性の世界」から「時間の世界」へ大転換
そもそも、、神武紀前の神話には「時間概念」が無く、「継起性」でもって物語が展開してきました。
継起性とは「次から次へと物事が続いて発生する事」。神の時代には「何年何月」といった時間概念は存在しません。
日本神話の最初の言葉も「古」という言葉から始まっている通り、遥か昔の話であって「いつ」という時間は存在しないのです。
●参考⇒「日本神話が伝える天地開闢|一番最初の言葉「古」から始まる世界のはじまりのお話」
そんな状態から、
神武紀以降は時間が導入されるようになります。
という内容がソレ。
これら時間表現は、神代のあとを引き継ぐ神武紀の重要な特徴の一つ。これ以降、編年体(出来事を年代順に書かれたもの)での記載が開始。
と、まースゴイ変化なんす。まさに革命だ。
神代から神武紀へ、
「継起性の世界」から「時間の世界」へ。
神武紀の最後は、橿原即位であり、以降、人の時代が続く展開になっています。
その意味で、神から人へ、時間概念の導入を通じてブリッジをかける役割を果たしているとも言えて。この点はしっかりチェック。
そのうえで、、、
②この世界を、天祖の天下り(天孫降臨)を起源とする歴史の中に組み込んだ
改めて、経緯確認。天祖が降臨しましたと、祖父と父が素晴らしい徳を輝かせてきたと、で、降臨してから百七十九万二千四百七十余年だと。
って、これ、神武の時代になっての後付けかもしらんが、意味合いとしては、天祖降臨(天孫降臨)を境に、それ以前は無時間の神代、それ以後は時間が存在する歴史の時代としてる、と言える訳です。そういう時代区分とか構造を前提とした話になっとる。
で、さらにいうと、降臨してから百七十九万二千四百七十余年経ったって言うことで、この世界を天祖降臨を起源とする歴史に組み込んだ、とも言えますよね。少なくとも、神の時代からいつ歴史の時代になったんすか?という質問に対しては、明確に、天孫降臨からです!という話になる訳です。
なので、多分、神武的には、天照や天忍穂耳は天上のお方であり、どこまでも神代の方々なんだろうなと。そこには時代の違い、距離感がある。でも、瓊瓊杵以降は、地上の方であり、歴史の時代の方々なんで、手触りのあるつながりを感じられる方々だったんじゃないかなと。こういうのも、時代区分とか時代認識から推測される訳です。
いずれにしても、、なんてすごいことを構想したんだろう、、『日本書紀』編纂チームの叡智、構想力に震えがとまりません、、((((;゚Д゚))))ガクブル
時間設定の詳細はコチラも参考にされてください。
そして最後!
③草昧の時代から、正しい道を養い、プロセスを積み上げてきた結果、機が熟してきた
先ほど解説したとおり、瓊々杵尊が天降った百七十九万二千四百七十余年前は「草昧」、つまり世の開き始めの無秩序の時代で、国をつくるなんて全然できない状態だった。言い方を変えると、機がまだまだ熟してない時代だった訳です。
なので、しょーがないので「物事の道理に暗い者たちを正しい道に導」きながら、足がかりとして「西のはずれの地を治めた」と。その上で、「179万2470有余年」という時間とプロセスを経てきた結果、今やっと、こうして建国を語れる状態になったという流れ。
この途方もない時間経過と壮大な積み上げプロセスに想いを致しつつ、しっかりチェック。
次!
→東征の理由や背景の部分。
先に言葉の解説を少し。
「遠く遥かな(原文:遼邈)」は、空間や時間が非常に遠く離れている、かけ離れている様子の意。「遼」は広々とした空間、「邈」は遠くかすかな時間(遠い昔・未来)。
「霑」は、濡れる、恵みを受ける。
「王澤」は、天子(天皇)の恵み、徳化、恩寵。
「疆」は、土地の「さかい」「はて」「かぎり」の意。特に国境や領域(疆域・疆土)を表します。
「凌躒」は、人をあなどって踏みにじる、干犯する、または圧力をかけて圧倒する意。
その上で、、
179万年余りに渡って素晴らしい政治を行ってきたが、遠くはるかな土地はまだ未開・野蛮な状態にある。各地がバラバラなまま小族長が勝手に支配し、境界争いが絶えない。。。
東征は、この社会の混乱に終止符をうち、正しい秩序や教化をもたらす偉大な事業として始まった訳です。コレも非常に重要なポイント。大義、やっぱ大事。
次!
→突然登場、塩土老翁!
「塩じい」こと塩土老翁は、実は、降臨した瓊々杵尊を出迎えた在地の首長、事勝国勝長狭の別名。しかも、瓊々杵尊に国を献上した経緯あり(神代紀第九段一書第四)。しかも、この塩土老翁は、続く海幸山幸譚で、山幸を海神の宮へと導く役割を担ったりします。
ちょっと待って、さっき天孫降臨から179万年以上経過したって言ってましたよね、、、てことは、それ以上の長生き爺さん、、謎すぎる!!
って、実は、
古代では、こうした長生きの老翁を「長人・遠人」と呼んでました。
仁徳天皇の偉大な事蹟をものがたる所伝(『日本書紀』仁徳天皇五十年条・古事記)では、天皇が武内宿禰に問いかけた次の詩を伝えてます。
時代を超えて生きてきた人であるからこそ「世の遠人」という。神武は「物知り爺さん」という偉大な側近を得ていたことになる訳ですね。
そして、
その「物知り爺さん」曰はく、「『東に、美しい土地があって、青く美しい山が四方を囲んでいる。」とのことで、流石、よー知ってるわ。。想定としては、大和、現在の奈良県橿原の地。
▲左の盆地が大和盆地。左端の細長い緑が生駒山。大和盆地の右が宇陀です。手前が熊野の山々。神様はきっとこんな世界を、、、ロマンだー!
「そこに天磐船に乗って天から飛び降った者がいる。」とあり、コレ、後ほど「饒速日」であると神武が推定しています。
つまり、目的地設定の根拠として、天神が降臨した場所を設定してる訳です。なんせ天皇の都を造るんで、どこでもいいって訳じゃない。
↑で、果たして「饒速日」は実際に、東征神話後半で登場します。
次!
→東征の目的、その核心が語られてます。かなり壮大な、そして重い言葉が使われてる。
言葉の解説を少し。
原文「恢弘大業・光宅天下」。
「恢弘」とは、広く大きくすること。 事業や制度、教えなどを世に広めること。
「大業」とは、帝王の業績のこと。
「光宅」とは、満ちゆきわたらせること。
なので、「恢弘大業・光宅天下」とは、王としての業績(事業、制度、教え等)を広く大きくしていくこと、天下にみちゆきわたらせることを言います。スゴイ、、、
そしてそれは、
広く、瓊々杵尊以来受け継いできた地上統治の「わざ」を広げていくこと、さらにその先には、豊葦原瑞穂の国の平定と統治が見据えられてる訳で。。結構壮大な、そして重い言葉なんですよね。もちろん、そこには人々が安心して豊かに暮らせる国をつくりたいという熱い想いがあったはず!
そして、
そうした大業を成す場所こそが「六合之中心」。
「六合」とは、天地(上下)+四方(東西南北)をいいます。いわば「世界の中心」であり、ここに都を置く事が想定されてます。
東征の目的、その核心がココで語られてるんです。超重要事項。しっかりチェック。
次!
→先ほどの、「そこに天磐船に乗って天から飛び降った者がいる。」の続き。
「饒速日」については、神武天皇の東征に先だって大和に天降った神様という設定あり。大和の地を支配する最強の敵「長髄彦」の妹を娶り、子供をもうけていたことが東征神話の後半になって判明。
最終的には、「長髄彦」を見限り「彦火火出見」に帰順。空気読める素晴らしい天神です。
で、なんでこんな神が登場してるか?
これが重要で。
要は、大和の土着の勢力に対して、天皇即位や日本建国の正当性を、天神との関わりにおいても示すため。ってこと。
東征はある意味、九州勢力が大和勢力を征伐する構図とも言えて。
大和在住の皆さんからしたら、ある日突然、部外者がやってきました的な話になる訳です。当然、脊髄反射する方々もいらっしゃったと思いますし、素直にお迎えする気持ちになれない可能性がある。そこで、武力を背景とした東征という構図に加えて、もともといた天神(大和の皆さんが受け入れていた天神)の支持、恭順という構図も加えることで、即位や建国の正当性を出そうとした、ってことなんす。
東征の最後、「長髄彦」との最終決戦でも、最終的には交渉と「饒速日」の寝返り的な行動によって勝敗が決するのですが、コレも、単に武力で征伐しました、という形で完結するのではなく、交渉やもともといた天神(饒速日)の恭順があったからこそ、という形にすることで、大和在住の皆さんのコンセンサスを取ろうとしてる訳ですね。
「饒速日」さん、その意味で、非常に重要な神ですし、別の言い方をすると、ダシに使われてるって雰囲気もしなくはないですが、、、 ( ̄Д ̄;;.
そうした、人民の気持ちにも配慮した、非常に奥ゆかしい伏線をいれてる神話になってる訳ですね。ホントに良く練られてます。古代日本人の叡智、創意工夫が凄すぎ。。
次!
→みんな納得、どうやら、みんな同じ思いでいたようで。これは忖度などではない!
ということで、さー出発だ!
ここで、先ほどの解説でふれた時間表現が登場。
「太歳」とは、木星の別称で、年を「太歳」+「干支」で記す方式。
これ以降、
各天皇代のはじめに「是年也、太歳(干支)」というように、「太歳」+「干支」で紀年を表示するようになっていきます。
多くは、即位の元年末尾にあるのですが、神武紀では特別。東征発議のこの場所で登場。つまり、橿原即位までのできごとの起点を示す形で使用されてます。
先に、「179万年余り」によって神代紀を歴史に組み込んだのですが、これをうけて東征を発議し、実行に移す年を「歴史の始源」すなわち元年として位置づけてる訳ですね。超重要事項。
「甲寅 」とは、「甲」が干支の最初に、「寅」が十二支の最初に於かれている事をいいます。
↑こちらの記事で解説してるように、結構ディープな暦年表記法があって。。。
「甲寅」自体は、十干の始めの「甲」と十二支の始めの「寅」との組み合わせなのですが、十二支の始めを「寅」とするのは、『爾雅』釈天によるもの。そこにはディープな革命理論説あり。
それが、「讖緯思想に基づいた古代中国の英雄的帝王像」を「我が国の七、八世紀における修史家の仕事」として造作したとする説(横田健一『日本書紀成立史論序説』)。
「讖緯思想」とは、漢代に流行した陰陽五行説に基づき、天変地異、または運命を予測するなどの予言説のこと。
この讖緯思想によれば、甲寅が元気始肇に当たり、辛酉は革命の年であり、神武の東征の発議・暦年の始めを前者に、東征の完遂後の橿原宮での即位を後者にそれぞれ当て、根拠づけ、権威化をはかったとするもの。
このあたりも非常に練りに練られた神話な雰囲気がぷんぷんしますよね。
時間表現、掘り出すと止まらなくなるオモローな世界が広がってます。
次!
→先ほどの時間表現に付随して、登場。「冬」という「四時」表現。
暦年の始まりは、同時に「四時」の始まりでもあります。
春(一、二、三月)
夏(四、五、六月)
秋(七、八、九月)
冬(十、十一、十二月)
で、
「その年の冬10月5日に、」という表現もコレを踏襲したもの。このあとの神武紀でもこの「四時」表現が登場。四季はほぼこれに重なりますね。
いやー、神武東征神話、深すぎです。どこまでも広がる神話ロマン。サイコーだ!