多彩で豊かな日本神話の世界へようこそ!
正史『日本書紀』をもとに、
最新の文献学的学術成果も取り入れながら、どこよりも分かりやすい解説をお届けします。
今回は、
神武東征神話を分かりやすく解説するシリーズ8回目。
テーマは、
熊野荒坂で全軍昏倒
「熊野荒坂津」から陸路を進む神武一行。
すると突然、熊野の神が現れ「毒気」を吐いて襲いかかります。この毒気の威力はすさまじく、彦火火出見はじめ東征軍の将兵はみな意識不明の重体に陥る。。。この危機を救ったのは、、、
なんと、天照大神!
「武甕雷神」を通じて東征一行の救援に当たらせます。
・なぜ熊野の神が襲いかかり意識不明の重体に陥るのか?
・なぜ天照が武甕雷神を通じて救援にあたらせるのか?
これらのロマンを探ることで、「熊野荒坂で全軍昏倒の意味」を考えます。
今回も、概要で全体像をつかみ、ポイント把握してから本文へ。最後に、解説をお届けしてまとめ。
現代の私たちにも多くの学びをもらえる内容。日本神話から学ぶ。日本の神髄がここにあります。それでは行ってみましょう!
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
神武紀|熊野荒坂で全軍昏倒|神の毒気にヤラレて意識不明の重体に!?天照による危機救援は「葦原中國平定」再現の意味があった件
目次
神武紀|熊野荒坂で全軍昏倒の概要
今回も『日本書紀』巻三「神武紀」をもとにお届け。ちなみに、前回の内容、これまでの経緯はコチラ↓をご確認ください。
そのうえで、
暴風雨で2人の兄を失った神武。身内は息子一人。。
「熊野荒坂津」に到り、陸路を進もうとすると突然、熊野の神が現れ「毒気」を吐いて襲いかかる!
この毒気により、神武はじめ東征軍の将兵はみな、意識不明の重体に陥る、、突然ですが、絶対絶命の危機!
この危機を救ったのが、、、天照大神!キタ――(゚∀゚)――!!
「武甕雷神」を通じて東征一行の救援に当たらせます。
神代・葦原中國平定時に使用された「韴霊剣」を使い、ようやく覚醒。危機脱出、という流れ。
- 陸路転換+東から西への転換の地で、
- 葦原中國平定の神話にちなむ神様とアイテムが登場し、
- 危篤状態だった神武が復活する、、
ということで、重要な意味が込められている臭いがプンプンする訳です。
東征ルートと場所の確認
東征の旅は、この「熊野荒坂津」から陸路を行くことになります。
「熊野荒坂津」は、現在の三重県熊野市の「大泊」。
東征神話的には、東征最東端の地が「熊野荒坂津」。コレ以降、逆方向への進軍、つまり東から西へ進むことになる。
これは大きくいうと、日神の威力を背に負う形になる訳で、神武に、東征一行に大きな支援の力を与えることになる訳です。コレ、激しく重要。

今回、天照大神が突然登場するのもコレ。天の道に沿う動きをしはじめるから。神策の具体的な効果が現れる訳ですね。
東征ルートは以下の通り。

東征一行は、大泊から42号線を通じて陸路を行き、309号線に入ってさらに北上、北山村で169号線と合流、吉野に到って370号線→166号線で菟田野(宇賀志)、さらに北上して宇陀に出るルートを辿ったと推定されます。
神武紀|熊野荒坂で全軍昏倒 神武東征神話現代語訳と原文
この時、神が毒気を吐き、この毒気により将兵はみな病み倒れてしまった。このため、軍は奮い立つことができなくなってしまった。
丁度そのころ、その地に熊野の「高倉下」 という名の者がいた。その夜、夢を見た。
(夢のなかで)「天照大神」は「武甕雷神」に伝えた。『いったい葦原中國は、まだ騒然として、うめき苦しむ声が聞こえてくる。(聞喧擾之響焉はここでは「さやげりなり」という)。武甕雷神よ、お前がまたかの国へ行き、征伐しなさい。』。すると武甕雷神は答えて、『私が行かずとも、私が国を平定した剣を下せば、国はおのずと平安をとりもどすでしょう。』と申し上げたところ、天照大神は、『よろしい。』と承諾した。(諾はここでは「うべなり」という)。そこで武甕雷神は、さっそく高倉下に伝えた。『私の剣は「韴靈」という。(韴靈はここでは「ふつのみたま」という)。今、これをお前の倉に置こう。これを取って天孫に献じるがよい。』。高倉下は「承知しました」と申し上げた。
そこで夢から醒めた。
その明け方、高倉下は夢に見た教えに従って「倉」をあけてみると、果たして天から落ちてきた剣が、倉の底板に逆さまに突き立っていた。
高倉下はさっそくこの剣を取って、彦火火出見に奉った。その時、彦火火出見は眠り臥していたが、たちまちに意識を取り戻し、「私はどうしてこんなに長く眠っていたのか。」と言った。続いて、毒気にあたっていた兵士たちもみな意識を取り戻し、目を覚まして起き上がった。
時、神吐毒氣、人物咸瘁、由是、皇軍不能復振。時彼處有人、號曰熊野高倉下、忽夜夢、天照大神謂武甕雷神曰「夫葦原中國猶聞喧擾之響焉。聞喧擾之響焉。宜汝更往而征之。」武甕雷神對曰「雖予不行、而下予平國之劒、則國將自平矣。」天照大神曰「諾。」時武甕雷神、登謂高倉下曰「予劒號曰韴靈。今當置汝庫裏。宜取而獻之天孫。」高倉下曰「唯々」而寤之。明旦、依夢中教、開庫視之、果有落劒倒立於庫底板、卽取以進之。于時、天皇適寐。忽然而寤之曰「予何長眠若此乎。」尋而中毒士卒、悉復醒起。 (『日本書紀』巻三 神武紀より一部抜粋)※原文中の「天皇」という言葉は、即位前であるため、生前の名前であり東征の権威付けを狙った名前「彦火火出見」に変換。
神武紀|熊野荒坂で全軍昏倒の解説
毒気って、、、どんな臭いだったんだろ、、、相当臭かったのか、、、紫色のヤバい感じだったのか、、、そんなロマンに想いを馳せながら、、、
以下詳細解説。
まとめ
熊野荒坂で全軍昏倒
今回の神話をまとめるとポイントは以下の通り。
- 陸路転換+東から西への転換の地で起こった物語である事。
- 葦原中國平定の神話にちなむ神様とアイテムが使用されている事。
- 危篤状態だった神武が復活する物語である事。
特に大きいのは、
東征最東端の地「熊野荒坂津」以降、これまでとは逆方向への進軍、つまり東から西へ進むことになったってこと。これは大きくいうと、日神の威力を背に負う形になり、神武に、東征一行に大きな支援の力を与えることになる訳です。
天照大神が登場し救援にあたるのもコレが理由。天の道に沿う動きに転換したからですね。神策効果発動!

ポイントは、天照大神の救援は、それまで個人レベルの決意だった「東征」に、天照大神による「お墨付き」を与える意味がある、ってこと。一種のギャランティー。コレ、非常にデカイ。
そして、この救援を「恩」として、東征が成就したとき、神武は鳥見山で天神を祭り「孝」を実践するという流れにつながっていく。。ある意味、東征神話的伏線設定。ココ、超重要事項なのでしっかりチェック。
そして、
今回の神話は、ある意味「葦原中國平定の再現」。
神代の神話と同じような設定を重ねることで、東征の正当性や権威付けを行っているのです。非常によく練られた物語ですよね。
さらに、
危篤状態の神武が「韴霊剣」で覚醒する、、非常にドラマチック。大げさにいえば、「神武は一度死に、復活した」という感じ?
西洋ではキリストの復活が伝えられていますが、まさにそれと同じか、もしくはそれ以上の意味があると思います。
この復活劇と神剣をゲットしたことにより、東征を果たし橿原即位・建国するというところにつながっていく、、、どこまでも広がる東征神話ロマン・・・サイコーだ!!
続きはコチラから!山で道に迷う・・??
神武東征神話のまとめ、目次はコチラ!
神話を持って旅に出よう!
神武東征神話のもう一つの楽しみ方、それが伝承地を巡る旅です。以下いくつかご紹介!
●熊野荒坂津(熊野市大泊港) ココ、大泊から伸びる42号線上で神が毒気を、、、((((;゚Д゚)))))))
●地元的にはココだとされる「熊野荒坂津神社」
●いやむしろココだと石碑が建つ「熊野荒坂津」
● 石上神宮 「武甕雷神が高倉下に下した神剣「韴靈」の霊威を祭る!!
● 鹿島神宮|御祭神は武甕雷神。神恩に感謝した神武天皇が、皇紀元年に大神をこの地に勅祭!!
●熊野についてのまとめ!
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
こちらの記事もどうぞ。オススメ関連エントリー
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




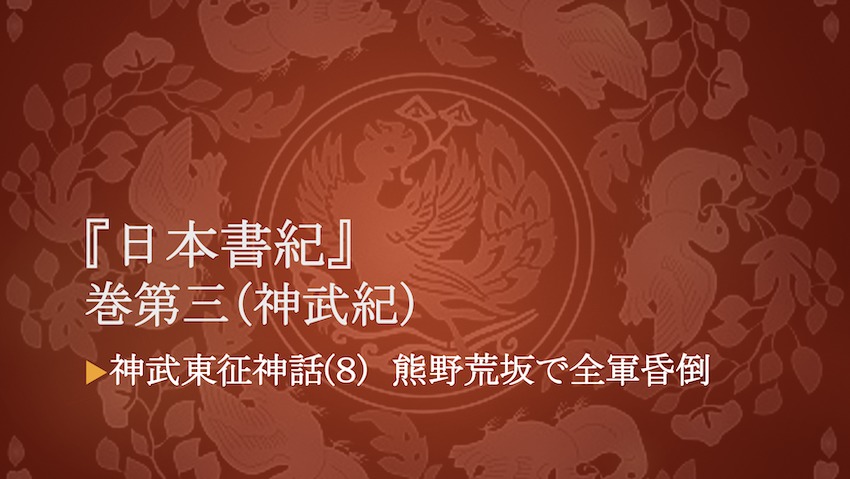























→突然すぎる。。。毒気って、、(;゚д゚)
ココで登場する「神」とは、熊野の神。
熊野といえば深く険しい山々が連なる人智の及ばない世界。日本神話的には、何をしでかすか分からない神々、あるいは魔物が棲む領域であります。そこに突撃したのは神武さん、アナタですよね??
で、実は、
前回の熊野灘の暴風雨以降、東征神話的には「自然(あるいは、何をしでかすか分からない神)が襲い掛かる試練の連続シリーズ」が始まってるんです。
熊野灘での海難は、兄たちの働きによって、兄を失ってしまったけれど何とかなった。。。でも!!ココからは独り。つまり、神武が自ら乗り越えていかないといけない状況に。そこに男のロマンがある。
とは言え、この自然が襲いかかる試練シリーズは、個人レベルではどないにもならん試練の連続で。。でも、神話的構造論からすると、あえてそういう試練が設定されてるとも言えるんです。
どういうことかというと、
個人レベルではどないにもならん試練だからこそ、誰かのサポートが必要になるってことであり、それを、東征神話では、天照大神の関与・救援を入れてきてる、ってことなんす。コレ、激しく重要で。
天照がサポートしてくれるってことは、
それまで個人レベルの決意だった「東征」に、天照大神による「お墨付き」を与える意味がある、ってことになる訳で。一種のギャランティー。これはデカイ。
天上における最高神であり、皇祖でもある天照大神が東征の成就を支援する。これほど大きな後ろ盾はありませんよね。
かといって、ハンパな試練では天照大神も関与できない。誰もが納得、今、ここでヘルプ入らないでどーする状態にならないとダメなんです。そのためには、人のチカラではどーにもならん絶体絶命の危機ってのを用意する必要があり、それが、今回の「神の毒気」。
コレ、どーすんの??流石に無理だよね(臭いにも程がある、、)、天照さん出番です!ってなる「仕掛け」なんです。しかも!さらに重要なのは、
最終的に、東征成就、天皇即位したときに、神武は鳥見山で天神を祭るのですが、コレはこの救援・援助に対する「孝」として行うのです。コレ、日本神話版「御恩と奉公」。
そしてそして、
これが現在、皇室が行っている祭祀の根拠になってる訳です。天皇がなぜ祭祀を欠かさないのか?その理由がコレ。
壮大すぎる、、((;゚Д゚))))ガクブル
数千年の時を経て継承されてきたロマンが、伝統が、そのきっかけが、、、
実は、、、
神の毒気!!(臭かったけど!)
次!
→突然登場、熊野の「高倉下」さん、、
高い屋根の倉を持つ地元の豪族? 高ーい倉ですから、相当な金持ちだったんじゃないか、、、いや、このころはまだ貨幣は流通してないか、、
なんで「高倉」かと言うと、あとで武甕雷神が神剣を地上に投げ落とすのですが、その時に目印になるから。天上から見ると、地上ににょきっと高い倉が突き出てるみたいに立ってるイメージ。あれ目がけて投げ落とす。そのための高ーい倉。
で、
「高倉下」さん、神武一行が毒気にヤラれてうんうん唸ってるまさにその時、夢を見る。
次!
→ついに登場、待ってました天照大神!!!
「いったい葦原中國は、まだ騒然として、うめき苦しむ声が聞こえてくる。」とあり、どーやら天照大神、地上の様子が音声として聞こえてくるらしい。。しかもその声は、うめき苦しむ自分の子孫。直ちに脊髄反射。
で、「武甕雷神よ、お前がまたかの国へ行き、征伐しなさい」とあり、、、流石でございます。その人選。いや、神選。武甕雷神!
確かに、この神をおいて他にどの神がいるというのか?
コレ、つまり、神代において葦原中國平定の際に、地上に降り立ち国譲りを迫り、国を平定した神。その神威、超絶です。
「またかの国へ行き、征伐しなさい」というのも、平定を踏まえてる。
で、「武甕雷神」は「『私が行かずとも、私が国を平定した剣を下せば、国はおのずと平安をとりもどすでしょう。」とあり、今回は、地上に降りては来ず、平定の際に使用した剣を落として対応します。たしかに、直接来ちゃったらそれで全部解決しちゃいますからね。。あんまり関与されすぎても神話的に破綻してしまうでござる。
で、この「韴霊剣」、葦原中國平定のときに使用された神剣なんで、危篤状態に陥った東征一行を覚醒させる力を持つ訳ですね。
次!
→明け方、、、高倉下が家の倉にいき、扉を開けてみると、、、
屋根破壊、、、2階以上のすべての床は破られボロボロ、、倉の底板に「韴霊剣」が逆さまに突き刺さってた、、、
おい!倉、壊すなよ!
と、言ったかどうかは伝えてはおりませんが、そういう状況だったようです。
この、「逆さまに突き立っていた」というも、葦原中國平定の際に、「経津主神と武甕槌神の二柱の神は、出雲国の五十田狭の小汀に降って来て、十握剣を抜き、逆さまに大地に突き立てて、その剣の切先に胡坐をかいて坐り大己貴神に間うた。(『日本書紀』第九段本伝より)」という内容を踏まえてます。
次!
→素直な高倉下。さっそく、神剣を神武一行に奉ります。
この神剣効果は絶大で、神武一行たちどころに意識を取り戻し、「私はどうしてこんなに長く眠っていたのか。」って、、、
寝てたんかーい!
ま、なにはともあれ起きてくれて良かった、、、