多彩で豊かな日本神話の世界へようこそ!
正史『日本書紀』をもとに、
最新の文献学的学術成果も取り入れながら、どこよりも分かりやすい解説をお届けします。
今回は、
神武東征神話を分かりやすく解説するシリーズ4回目。
テーマは、
大和上陸!難波碕から白肩の津へ
日向を出発し、瀬戸内を進んできた神武東征一行。岡山「高嶋の宮」で3年間準備したのち、いよいよ大和に入ります。
初めて上陸した大和の地。神武はどんな想いだったのか?
そんなロマンを探る事で「大和上陸」が伝える意味を読み解きます。
今回も、概要で全体像をつかみ、ポイント把握してから本文へ。最後に、解説をお届けしてまとめ。
現代の私たちにも多くの学びをもらえる内容。日本神話から学ぶ。日本の神髄がここにあります。それでは行ってみましょう!
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
神武紀|大和上陸!難波碕から白肩の津へ|生駒山の白い崖を目印にドキドキしながら進軍した件
目次
神武紀|大和上陸!難波碕から白肩の津へ の概要
今回も『日本書紀』巻三「神武紀」をもとにお届け。ちなみに、前回の内容、これまでの経緯はコチラ↓をご確認ください。
その上で、
日向を出発し、瀬戸内を進んできた神武東征一行。
岡山「高嶋の宮」で3年間準備した東征軍は、「難波の碕」から遡って河内国草香邑の「白肩津 」に上陸。「津」は港の事。ここから陸路で世界の中心へ入ろうとします。
『日本書紀』をもとに地名を辿ると、神武が「当初」目指した橿原への想定ルートは以下の通り。

「高嶋の宮」から大阪湾を抜け「難波の碕」へ、更に「白肩の津」に上陸し、そこから陸路で橿原へ進軍するルート。
以上のルートをイメージしながら本文をチェック!
神武紀|大和上陸!難波から白肩の津へ
戊午の年(紀元前663年)、春2月の11日に、東征軍は遂に東に向けて出発した。前の船の「とも」と、後ろの船の「さき」が互いに接するほど多くの船が続く。いよいよ「難波の碕」に到ると、非常に速い潮流に遭遇した。そこで、その国を名付けて「浪速国」という。(また「浪花」ともいう。今、「難波」と言うのは、訛である。)
3月10日に、その急流をさかのぼり、河内の国の草香の邑の青雲の白肩の津に到る。
戊午年春二月丁酉朔丁未、皇師遂東、舳艫相接。方到難波之碕、會有奔潮太急。因以名爲浪速國、亦曰浪花、今謂難波訛也。訛、此云與許奈磨盧。
三月丁卯朔丙子、遡流而上、徑至河內國草香邑靑雲白肩之津。 (『日本書紀』巻三 神武紀より抜粋)
▲橿原神宮で公開中の「神武天皇御一代記御絵巻」から。
神武紀|大和上陸!難波から白肩の津への解説
岡山で3年の準備のあと、初めて上陸した大和の地。神武はどんな想いだったのでしょうか?どこまでも広がる神話ロマンに想いを致しながら、、
以下、詳細解説。
まとめ
難波から白肩の津へ
いよいよ大和いりした「彦火火出見」こと神武。
「前の船の「とも」と後ろの船の「さき」が互いに接するほど多くの船が続く」という表現から、大軍を率いて進軍した様子が目に浮かびます。
一方で、2月11日に吉備を出発し、3月10日に河内国の「白肩の津」に着くまで、ほぼ一ヶ月を要したと伝えており、潮流の速さに難渋したことを伝えてます。
当時の地形が、現在とは全然違ったってところも興味深いですよね。広大なラグーンが広がっていたなんて。。。
潮流に阻まれた一方で、これによって、大船団は内陸まで入り込むことができたという事なんですね。良くできてます。現在の日下付近まで来たはずで、それはそれでビックリです。
つづきはコチラ!初戦で、、、??
神武東征神話のまとめ、目次はコチラ!
『古事記』版はコチラ!!
神話を持って旅に出よう!
神武東征神話のもう一つの楽しみ方、それが伝承地を巡る旅です。以下いくつかご紹介!
●「難波の碕」伝承地
●「白肩津」を実地調査してみた件
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
こちらの記事もどうぞ。オススメ関連エントリー
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




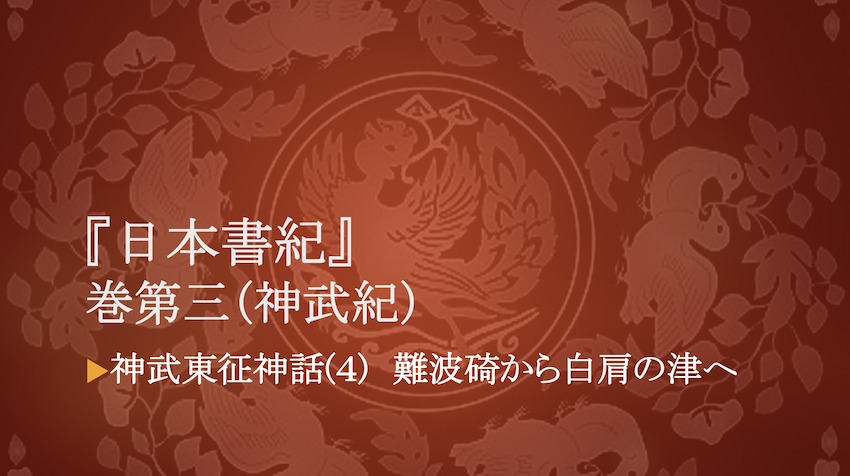

























→岡山の「高嶋宮」を出発。
「丁酉が朔にあたる丁未」は、2月11日のこと。
原文「皇師」は天皇の軍隊、東征軍のこと。「師」=軍隊。参考として、周代、軍隊の単位として「旅=500人」「師=五旅=2500人」「軍=五師=12500人」といったものがありました。てことは、その規模2500人??いや、もっといたような。。。いずれにしても、「前の船の「とも」と、後ろの船の「さき」が互いに接するほど多くの船が続く(舳艫相接)」とあるので、ひしめきあう大船団だったと考えられます。
ま、3年も準備したからね。船もたくさん作ったんじゃなかろうか、、、
次!
→難波の碕に到ったところで、はなはだ速い潮流に、行く手を阻まれる。
現在の、大阪府「浪速区」や「難波」の地名はこれが由来。つまり、とても速い潮流=浪が速い=浪速、という事。
ここでのポイント2つ。
①古代の大阪湾は、広大な潟湖が平野の奥深くまで入り込んでいた!?
なんと、現在の姿とは全然ちがっていて、この周辺は、大阪湾から東へ「生駒山」西麓までいたる広大な潟湖が広がっていたようです。
↑7世紀前後の古代想定地図(枚方市教育委員会主催「シンポジウム淀川流域の交通史」より)
潟湖とは、現在は「ラグーン」と呼ばれ、湾が砂州によって外海から隔てられて湖沼化した地形のこと。上町台地が半島のように突き出ており、「難波の碕」はこの潟湖の入口付近にある岬だった模様。
今回は神話の時代のお話。それでも、上記古代地図と重ねてみると以下の通り。
あくまで7~8世紀ごろの地形なので、神話の時代は別でしょ、てのが大前提。ですが『日本書紀』編纂前後の頃なんで、参考にはなると思います。
大阪湾から東へ「生駒山」西麓までいたる広大な潟湖が広がり、上町台地が半島のように突き出ていた、、、「難波の碕」はこの潟湖の入口付近にある岬だったようです。
潮流が激しく進軍に難儀したようですが、大軍を大和の地深くまで上陸させるために、このルートが選ばれたのだと推測されます。
ちなみに!完全に余談ですが、、
古代における海面の高さについて、、、地域により異なりますが、世界的な傾向としては、
ようで、、
神武天皇の即位年が、『日本書紀』の記述に基づくと西暦紀元前660年2月11日とされてるので、ざっくり紀元前1000年頃だとすると、海面は低下していった頃だけど現在よりは数メートル高かったと考えられ、、むしろ潟湖「草香江」どころか全部海〜な感じだったんじゃないかと。。。
さらにちなみに!!
②白肩の津」に着くまで、ほぼ一ヶ月かかったのは神のしわざだった!?
ひしめきあう大船団が潮の急流に難渋して進めない状態を伝えてるのですが、、、2月11日に吉備を出発し、3月10日に河内国の「白肩の津」に着くまで、ほぼ一ヶ月を要したということに。。どんだけ難渋したんだい?
コレ、岡山と大阪との距離の上ではやや不自然とも言えて、、
そこで、当サイトならではの文献学的考察を。
歴史の時代ですが、以下の伝承が参考になります。
実は、この難波の江(堀江)は、仁徳天皇が「茨田堤」を築いた所なんですが、築いてもすぐ崩れてふさぐことができなかった、と伝えてるんです。
その際、「河伯(川の神)」が天皇の夢にあらわれ、「武蔵人強首」と「河内人茨田連衫子」の二人を「人身御供」に求めます。天皇は二人を求めて河伯を祭ったところ、堤を完成させることができた、、ということで、。
ココから推測するに、、
すなわち、この難渋は神のしわざだった!?とも考えられます。大船団が草香江(潟湖)に入っていくにあたって、堤やら土手のようなものを築こうとしたが潮流が激しくなかなか築けなかった、、そこには、実は「河伯(川の神)」の存在が、、、?? って、このあたり、神話と歴史が交錯する超絶ロマン地帯であります。
次!
→「丁卯が朔にあたる丙子」は3月10日のこと。
「遡流而上」とは、流れに逆らって上ること。難波の碕からさらに草香江を遡上した先が白肩の津。
生駒山麓まで迫っていた潟湖「草香江」、その砂れきが海岸線を形成していたようで、コレ、実は『万葉集』でも歌われてたりします。
と歌われたように、
三津(難波の三津、難波津)は白砂の名所でした。こと生駒山の山麓から草香江に落ちこむ所に、船の着岸に適した場所があり、神武一行はそれを指したと思われます。草香江に入る船の目印ともなった訳ですね。
なお、
「青雲の白肩の津」という表現は、神武紀の最後に日本の国名をめぐって「玉牆の内つ国」「虚空見つ日本の国」と枕詞を冠して表わした例と同じく、「青雲」が枕詞として「白肩の津」の「白」にかかるもの。
古代では、白馬の節会(朝廷で白馬を庭上に引き出して天覧の後、群臣に宴を賜う儀式で、この日に白馬を見ると年中の邪気を祓うされた。古い風習による)を「あおうまのせちえ」と称するなど、「青」は「白」の色の領域に重なる色名でした。
万葉集にも、
と歌う「白雲」「青雲」「天雲」も意味的には互いに重なりあうものです。
神武にとって「大和」は右も左もわからない土地。そこで必要なのは「目立つ目標物」であり、生駒の白い崖は進軍するうえでの目印になったと思われます。
その他、実地調査の結果はコチラで。
神話と歴史の交錯するロマン発生地帯であります。コレがサイコー!