多彩で豊かな日本神話の世界へようこそ!
正史『日本書紀』をもとに、
最新の文献学的学術成果も取り入れながら、どこよりも分かりやすい解説をお届けします。
今回は、神武東征神話を分かりやすく解説するシリーズ3回目。
テーマは、
東征順風。臣下を得て戦闘準備
日向の地を出発した神武一行は、現在の大分県、豊予海峡から、瀬戸内海を経て岡山へ進軍します。
東征は実際、どんな旅だったのか?
そんなロマンを探る事で、「東征順風、臣下を得て戦闘準備」が伝える意味を読み解きます。
今回も、概要で全体像をつかみ、ポイント把握してから本文へ。最後に、解説をお届けしてまとめ。
現代の私たちにも多くの学びをもらえる内容。日本神話から学ぶ。日本の神髄がここにあります。それでは行ってみましょう!
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
神武紀|東征順風。臣下を得て戦闘準備|半年かけて岡山まで移動。3年じっくり準備した件
目次
神武紀|東征順風。臣下を得て戦闘準備の概要
今回も『日本書紀』巻三「神武紀」をもとにお届け。ちなみに、前回の内容、これまでの経緯はコチラ↓をご確認ください。
その上で、
日向の地を出発した神武一行は、
現在の大分県、豊予海峡から、宇佐、福岡、広島を経て瀬戸内を東へ。途上、有能な臣下を得たり、饗宴を受けたり等、順風満帆の旅。
そして岡山に到り「高嶋宮」を建て、3年の間、軍船の整備や兵糧の備蓄を行います。

このころは全てが順調で、建国の夢を胸に進軍する「彦火火出見」の姿が浮かびます。後に大活躍する「珍彦(椎根津彦)」が臣下として加わったり、地方の首長(国造)による饗宴を受けたり等、一切障害無し。みんなウェルカム。
しかし、この順風満帆がゆえに過信につながり、後に大きな災厄を引き起こしてしまう、、、って、このあたりも練りに練られた神話構成になってます。アゲるものがあるからサゲるものがある。落ちるからこそ学びがある。
神武紀|東征順風。臣下を得て戦闘準備
速吸之門に到る。
この時、一人の漁人が小舟に乗ってやって来た。彦火火出見はその者を招き、「お前は誰か」と問うた。その者が答えて、「私は国神です。名を『珍彦』と言います。湾曲した入江で魚を釣っています。天神子が来ると聞き、それですぐにお迎えに参りました。」と言った。彦火火出見が「おまえは私を先導することができるのか?」と問うたところ、「先導いたします。」と答えた。そこで彦火火出見は勅して、その漁師に椎の棹の先を授け、舟に引き入れ「海路の先導者」とした。そして、特別に名前を与えて「椎根津彦」とした。(椎はここでは「しひ」と言う。)これは倭直らの始祖である。
さらに進み、筑紫の国の菟狭に到る。
その時、菟狭の国造の祖先がいた。名を「菟狭津彦」「菟狭津媛」という。その者達は、菟狭川のほとりに一柱騰宮を建て、彦火火出見に饗宴を奉りおもてなしをした。そこで彦火火出見は詔をくだし、従臣の「天種子命」に「菟狭津媛」を妻として下された。(「天種子命」は中臣氏の遠祖である。)
11月9日に、筑紫国の岡水門 に到った。
12月27日に、安芸国に到り、埃宮に居住した。
乙卯の年(紀元前666年)春3月6日に、吉備国に入り、行館宮を建て居住した。これを「高嶋宮」と言う。3年の間、軍船を整備し、兵達の食糧を蓄え、一挙に天下を平定しようとした。
至速吸之門、時有一漁人乘艇而至、天皇招之、因問曰「汝誰也。」對曰「臣是國神、名曰珍彥、釣魚於曲浦。聞天神子來、故卽奉迎。」又問之曰「汝能爲我導耶。」對曰「導之矣。」天皇、勅授漁人椎㰏末、令執而牽納於皇舟、以爲海導者。乃特賜名、爲椎根津彥椎、此云辭毗、此卽倭直部始祖也。
行至筑紫國菟狹。菟狹者地名也、此云宇佐。時有菟狹國造祖、號曰菟狹津彥・菟狹津媛、乃於菟狹川上、造一柱騰宮而奉饗焉。一柱騰宮、此云阿斯毗苔徒鞅餓離能宮。是時、勅以菟狹津媛、賜妻之於侍臣天種子命。天種子命、是中臣氏之遠祖也。
十有一月丙戌朔甲午、天皇至筑紫國岡水門。
十有二月丙辰朔壬午、至安藝國、居于埃宮。
乙卯年春三月甲寅朔己未、徙入吉備國、起行館宮以居之、是曰高嶋宮。積三年間、脩舟檝、蓄兵食、將欲以一舉而平天下也。 (引用:『日本書紀』巻三 神武紀より一部抜粋)※原文中の「天皇」という言葉は、即位前であるため、生前の名前であり東征の権威付けを狙った名前「彦火火出見」に変換。
▲橿原神宮で公開中の「神武天皇御一代記御絵巻」から。
神武紀|東征順風。臣下を得て戦闘準備 解説
建国の夢を胸に進軍する「彦火火出見」こと神武。大船団の先頭、船の舳先に立って瀬戸内の海風を胸いっぱい吸い込みながら世界の中心を目指す、、、そんなロマンに想いを致しながら、、、
以下詳細解説。
まとめ
順風・戦闘準備(日向~高嶋宮)
このころの東征軍は順風満帆の一言に尽きます。
軍船の先頭に立ち、海の潮風を胸いっぱいに吸い込みながら建国の夢へ突っ走る「彦火火出見」。
また、「珍彦→後の 椎根津彦」を臣下として加えたのも大きいです。
東征の後半で出てきますが、椎根津彦、結構活躍します。彼の活躍無くして東征は果たせなかったんじゃないか?というくらい。スゴイんです。
このお方の登場も、非常に作り込まれた設定になってます。
太公望と同じような設定で登場し、同じように王たる者を助けて事を成す、というように古代の英雄と重ねている訳です。
東征の中では、
- 武勇に秀で「武官」に相当する「道臣」
- 太公望と同じように智略を持って貢献する「文官」としての「椎根津彦」
この対比構造も面白いポイント。
吉備の「高嶋宮」に3年居住し、軍船・食糧を整え、兵士を訓練するなど、天下平定をにらんで周到な準備を行ってます。
しかし、独力で天下を平定できると過信したことが、後に仇となり手痛い敗戦につながっていくのですが、、、
つづきはコチラ!いよいよ大和に進軍!
神武東征神話のまとめ、目次はコチラ!
『古事記』版はコチラで!!
神話を持って旅に出よう!
神武東征神話のもう一つの楽しみ方、それが伝承地を巡る旅です。以下いくつかご紹介!
●椎根津彦神社
●宇佐上陸の伝承地(柁鼻神社)
●菟狭津彦・菟狭津媛に饗宴を受けた伝承地(宇佐神宮)
●筑紫の国の「岡水門」伝承地(神武天皇社)
●安芸の「埃宮」伝承地(多家神社)
●高嶋宮伝承地(高島)
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
こちらの記事もどうぞ。オススメ関連エントリー
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




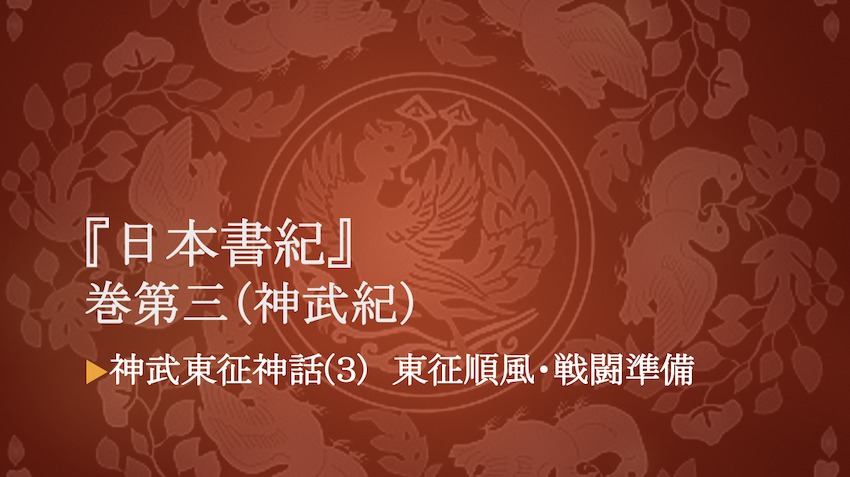




























→こちら、現在の豊予海峡。
豊予海峡は、大分県大分市の関崎と愛媛県伊方町佐田岬の間に挟まれる海峡。
海峡の両側、大分県と愛媛県の旧国名である「豊後国」及び「伊予国」から1字ずつ取って豊予海峡。最も狭い部分で海峡幅は約14km、最大水深は約195m。
ちょっと語ると、、
豊予海峡の海底はとても複雑で。。佐田岬と佐賀関を結ぶ線上には、馬の背のような尾根(海底山脈)が走ってて、水深60mから100mの浅い瀬が連なってます。
しかも、、この瀬の南北に、「海釜」と呼ばれる、すり鉢状に深く落ちくぼんだところがあり、瀬戸内海と太平洋の豊かな海流が、混ざり合ってスゴイ海流を引き起こしてるそうで。。。このダイナミックな動きが、海峡幅約14kmという超狭いところで発生してるから、そら速くもなるわと。
ちなみに、豊予海峡、現在では、関アジ・関サバで有名ですよね。
で、改めて、
「速吸之門」の「門」は関門のことで、海峡。日本神話的には、「速吸之門」は潮の流れが急な難所として位置づけられてます。
コチラ、実は神代にすでに登場。伊奘諾尊の禊祓のシーン。
黄泉の穢れを濯ごうと速吸名門に行ったけど、潮の流れが速すぎて洗えませんでした・・・の巻。
どうやら神の時代から、超速だったらしい。。。
そして、この設定がこの後登場する「珍彦」の出迎えにつながっていきます。
次!
→漁人(釣り人)、つまり「珍彦」は、神武の東征を聞き出迎えたと言い、神武を先導することを申し出る。そこで天皇は珍彦を海路の先導者として「椎根津彦」の名を与えます。
まず、
なぜ釣りなのか?
が、かなり重要で。単に、航海の途上だったから、という訳ではありません。
実は、この、釣り人である珍彦との出会いは、古代中国の「周」建国における功臣「太公望( 名は呂尚)」の、文王との出会いがベースになってるんです。
太公望と文王との出会い、コレ、めっちゃ有名なお話ですよね。
渭水の浜に釣糸を垂れて世を避けていた太公望。ところが、文王との出会いによって、文王に用いられ、武王を助けて殷を滅ぼす、、、てな訳ですが、この出会い方と同じ設定。珍彦も太公望も同じく、釣りをしている時に出会いがある。
要は、
太公望の出会いと同じような場面設定は、珍彦を智略をもって東征に貢献する側近として位置づけるための伏線、ってこと。
もっと言うと、
「珍彦」=太公望、てことは、神武=文王、てことも狙いとしてある訳で。文王と言えば、有能な人材を登用し、徳治を実践した古代の理想的な王、聖人とされている訳で、それを神武に重ねようとしてる、とも言えますよね。
このあたりも、非常に練りに練られた神話構成になってます。しっかりチェック。
ちなみに、武勇に秀で東征を導くのが道臣。こちらも、対称的に描かれてます。
でだ、
「私は国神です。名を『珍彦』と言います。湾曲した入江で魚を釣っています。天神子が来ると聞き、それですぐにお迎えに参りました」とあります。
ココで言う「国神」とは、その土地の土着の神のことで、だからこそ、海路に詳しい者として東征軍の先導者の役割を担う。神話の時代はこのように、初めての土地を訪れる場合には道案内をする者が登場する訳です。
ポイントは、「天神子」という言葉。
コレ、原文では「天神子」となってますが、実は、東征神話の中では、神武にだけ設定されてる特別な言葉なんです。
明確に使い分けが分かるのは、東征神話のクライマックス、長髄彦との最終決戦。その最後のところ。
ココ↑では、
東征より遥か昔、大和の地に天から飛び降りた饒速日命のことは、「天神之子」と表記。「之」という言葉が入るか入らないかだけの違いで、、
同じ「天神」の「子」なのですが、「天神子」と「天神の子」は全然違うものとして。本文でも明確に使い分けられてること含めてしっかりチェック。
「天神子」は、それだけ尊い、ということが言いたい。なので、知れ渡る訳です。
これは、前回のエントリで解説したとおり、
東征発議の中で、饒速日の天降りについて、神武が塩土老翁から聞いたとありましたが、これと同様に「天神の東征」も「珍彦(椎根津彦)」は聞いていたことになる訳です。天神クラスの動静は、下々の国神の皆さんには知れ渡るようで、、、
こうした背景があるからこそ、「天神子が来ると聞き、それですぐにお迎えに参りました」といった発言になってる。もっと言うと、潮の流れが急な難所「速吸の門」にさしかかったところで「珍彦(椎根津彦)」が登場したのも、危険を察知して出迎えた、国神としての当然の対応、という話になってくるのです。
ま、よく言えば「珍彦(椎根津彦)」流石、太公望と重ねられてるだけのことはある、空気読めるナイスガイ、ということなんですが、一方では、天神と国神の絶対的なヒエラルキーみたいなものも感じられて、、、このあとの宇佐もそうですが、天神子が来るわけですから、当然盛大にお出迎えするし、しなきゃいけないし、、、みたいな側面もあったりします。
その他、詳しくはコチラ↓で!
次!
→神武一行は、筑紫の国の菟狭 に至る。現在の大分県宇佐市とされてます。
なぜ宇佐なのか?
根拠となるのは『日本書紀』第六段〔一書3〕。
と伝えており、
宇佐は、海北道の中にあり、主宰神の所在地として位置づけられてるんです。つまり、九州の一大拠点。なので、ここで登場してるし、支配者であった「菟狭津彦・媛」が饗応し迎える訳です。
でだ、
「菟狭の国造の祖先がいた。名を「菟狭津彦」・「菟狭津媛」という。」とあります。
「国造」とは、古代の地方小国家の君主の称号。
その祖先である、「菟狭津彦」「菟狭津媛」がいたと。
コレ、実は「彦姫制」と呼ばれる古代の共同統治者のことで、「ヒコ」は政治、「ヒメ」は祭祀をそれぞれ司ります。
話が飛びますが、邪馬台国の卑弥呼も似たところで。『魏志倭人伝』では、邪馬台国では女性の卑弥呼が王に共立されて呪術的(祭祀的)支配を行い、男弟が卑弥呼を補佐して政治を執行していたと伝えてます。
話を戻して、
「菟狭川のほとりに一柱騰宮を建て、彦火火出見に饗宴を奉りおもてなしをした。」とあり、この「一柱騰宮」は、一時の饗応用に建てた特殊な構造の殿舎。一本の柱で支えられていたから「一柱」??
少々細かいですが、「菟狭川のほとり」について。コレ、原文「於菟狹川上」、上を「ほとり」と読みます。この「上」は、東征神話中盤での「丹生川上祭祀」につながる内容なのでチェックしておいてください。
そのうえで、
この饗応対応は、服属の意味が強い内容になってます。それこれも「天神子」という設定があるからこそ。
そのうえで、、
神武が、ヒメ(菟狹津媛)を近従の臣である天種子命にめあわせる訳ですが、この天種子命、実は、天岩戸神事に活躍した「天児屋根命」と同じ中臣氏の遠祖なんです。
ココでは、祭祀を司る女性首長を、祭祀の氏族である中臣氏に与えるという神武的な「はからい」としてチェックです。地味に激しく重要。
次!
→筑紫国の「岡水門」に至ります。
丙戌朔甲午=日付を干支で示す方式によるもの。月の「朔」にあたる干支(丙戊)を基準として、甲午が、何番目、つまり何日目にあたるか、で日付を設定。ここでは9番目にあたるので、9日ということになります。
「岡水門」は、福岡県遠賀郡遠賀川河口付近とされてます。
なぜ筑紫国の「岡水門」なのか?
しかも、、11月9日の到着日から、12月27日に安芸国に至るまでの1か月半、、、何してた??
まず、
位置的に、遠賀郡の西には宗像郡が接していて、さらに西、博多には大宰府があり、歴史の時代でありますが九州を統括する拠点がありました。
さらに、、筑前国風土記逸文には「筑紫国に到れば、先づ哿襲宮に参謁るを例とす。」と伝える香椎廟(現・香椎宮)があり、『古事記』ではこの宮で神功皇后が神懸りして新羅征討の託宣を得たことを伝えてます。
これらの神話、歴史の文献をつなげて考えると、、、
神武はここでの1か月半の多くを、この地の情勢を偵察させ、宗像はじめ在地の豪族たちが敵対、寝返りしないことを見極めていた、、と推測される訳です。そのうえで、九州を掌中に収めてから瀬戸内海へ航路をとった、、というのが東征的シナリオ。
そのための岡水門。そのための拠点として位置づけられてるってことでチェック。
次!
→安芸、つまり今の広島県に移動。
「埃宮」は、広島県安芸郡府中町付近とされてます。
この地が登場してるのは、もちろん、大和へ航行する順路として。安芸は古代より一大海運拠点でありました。
次!
→広島から吉備、つまり岡山県に移動。
天下平定に向けた基地を建設。「行館宮を建て(起行館宮)」とは、神武が東征の途中に、一時しのぎ的な仮の宿ではなく、天子行幸の宿舎に類する館を建てたことを言います。
用例は以下。
とあり、
行宮とは天子の仮御所として位置づけられてることが分かります。一時的なものでないのがポイント。
ここに3年居住し、軍船・食糧を整え、兵士を訓練するための基地とした訳です。天下平定をにらんだ、周到な計画によるもの。3年ですよ、、3年。結構長い時間ですよね。。私、3年前なにをしてたっけ。。。?