多彩で豊かな日本神話の世界へようこそ!
正史『日本書紀』をもとに、
最新の文献学的学術成果も取り入れながら、どこよりも分かりやすい解説をお届けします。
今回は、神武東征神話を分かりやすく解説するシリーズ5回目。
テーマは、
孔舎衛坂激戦、敗戦
「白肩の津」から上陸した神武一行は、世界の中心である「中洲」=大和平野(奈良盆地)に向けて進軍を開始。そこに、大和最強の敵「長髄彦」が行く手を遮り、孔舎衛坂で激しい戦闘に、、、ところが、初戦敗退。。。Σ(゚Д゚;マジデ!?
入念な準備を行ってきたにもかかわらず敗戦した理由はなんだったのか?
負けが確定したときの対処はどうだったのか?
そんなロマンを探ることで、東征神話における「孔舎衛坂敗戦の意味」を考えます。
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
神武紀|孔舎衛坂激戦、敗退|スネの長い関西人に初戦敗退。神策めぐらし日神の威を背に負うことにした件|分かる!神武東征神話No.5た件
目次
神武紀|孔舎衛坂激戦、敗退の概要、東征ルート
今回も『日本書紀』巻三「神武紀」をもとにお届けします。ちなみに、前回の内容、これまでの経緯はコチラ↓をご確認ください。
そのうえで、
「白肩の津」から上陸した神武一行は、いよいよ世界の中心である「中洲=大和平野(奈良盆地)」向けて進軍を開始します。徒歩にて。
まず、「龍田」を通って行こうとしますが、狭くて険しくて断念。「並んで行くことができなかった」と伝えてるので、相当狭かったのでしょう。。。これが「第一ルート」。
そこで、一度引き返して、生駒山を越えて行くルートを目指します。これが「第二ルート」です。
が、大和最強の敵「長髄彦」が行く手を遮り、生駒山の「孔舎衛坂」で激しい戦闘へ。
図示すると以下の通り。

「長髄彦」は、名前をそのまま解釈すると「スネの長い男」。大和一帯を支配し、先に天から降ってきた「饒速日命」を自分の妹と結婚させていたお方です。
東征軍は、この「スネの長い男」の軍に手痛い敗戦、撤退を余儀なくされます。
意気揚々と進軍し、岡山で3年も準備し、満を持して臨んだ初戦は完敗に終わったのです。
神武紀|孔舎衛坂激戦、敗退
夏4月9日に、東征軍は兵を整え、徒歩で龍田に向かった。しかし、その路は狭くて険しく、人が並んで行くことさえできなかった。そこで引き返し、改めて東へ胆駒山を越えて中洲に入ろうとした。
その時、長髄彦がこれを聞きつけ、「そもそも天神子等がやって来たのは、必ずや我が国を奪おうとするためだろう」と言い、ただちに配下の兵を起こし、孔舎衛坂で遮り合戦となった。この時、流れ矢が五瀬命の肘と脛に当たった。
東征軍は進んで戦うことができなくなった。彦火火出見はこれを憂慮し、心中に神策をめぐらした。「今、私は日神の子孫でありながら、日に向って敵を征服しようとしている。これは「天の道」に逆らうことだ。ここは退却して弱いと見せかけ、神祇を祭り、日神の神威を背に負い、自分の影を前にして、抑えつけるように敵を踏みつけるのがよい。こうすれば、少しも刃を血塗ることなく、必ずや敵は自ら敗れるだろう。」 皆は「まさにそのとおりです。」と言った。
そこで全軍に対し「しばらく停れ。これ以上、進軍してはならない」と軍命を下し、さらに軍を引いて引き返した。敵もまた、敢えて追ってはこなかったので、草香津まで退却し、盾を立てて雄誥をあげた。これにより、その津の名を改めて「盾津」という。今、「蓼津」というのは、訛りである。
はじめに、この「孔舎衛の戦い」において、大樹に隠れて難を免れ得た者がいて、その樹を指して「ご恩は母のようだ」と言った。(当時の人は、その地を名付けて「母木邑」といった。今、「悶廼奇」というのは訛りである。)
夏四月丙申朔甲辰、皇師勒兵、步趣龍田。而其路狹嶮、人不得並行、乃還更欲東踰膽駒山而入中洲。
時、長髄彥聞之曰「夫天神子等所以來者、必將奪我國。」則盡起屬兵、徼之於孔舍衞坂、與之會戰。有流矢、中五瀬命肱脛。
皇師不能進戰、天皇憂之、乃運神策於沖衿曰「今我是日神子孫而向日征虜、此逆天道也。不若、退還示弱、禮祭神祇、背負日神之威、隨影壓躡。如此、則曾不血刃、虜必自敗矣。」僉曰「然。」於是、令軍中曰「且停、勿須復進。」乃引軍還。虜亦不敢逼、却至草香之津、植盾而爲雄誥焉。雄誥、此云烏多鶏縻。因改號其津曰盾津、今云蓼津訛也。
初、孔舍衞之戰、有人隱於大樹而得兔難、仍指其樹曰「恩如母。」時人、因號其地曰母木邑、今云飫悶廼奇訛也。 (『日本書紀』巻三 神武紀より一部抜粋)※原文中の「天皇」という言葉は、即位前であるため、生前の名前であり東征の権威付けを狙った名前「彦火火出見」に変換。
▲橿原神宮で公開中の「神武天皇御一代記御絵巻」から。
神武紀|孔舎衛坂激戦、敗退の解説
意気揚々と進軍し、岡山で3年も準備し、満を持して臨んだ初戦は完敗に終わった、、、神武の悔しさ、無念はいかばかりか、、そんなロマンに想いを馳せながら、、
以下、詳細解説。
まとめ
孔舎衛激戦、敗退
地に詳しくなく、敵を知らず、日の神の子孫であるという己のアイデンティティに無自覚のまま戦えば、敗北は必至です。
初戦敗退の原因は、一言で言うと「情報不足と無自覚(≒おごり)」にあったと言えます。
この孔舎衛坂の戦いは、「彼を知らず己も知らず」の状態だったと言えますね。確かに勝てる訳がなく。。。
結果的にその代償は、この後に続く「兄の死」という形で払う事になります。
一方で、
敗戦が決定的になったときの「対処方法」も注目すべきです。
状況を客観的に分析し、「神策」をめぐらせ迂回ルートを決断しました。そして決めたら即行動。全軍に撤退を命令し、盾津で雄叫びをあげて士気を鼓舞します。
初戦敗退のショックは大きかったはずですが、くよくよしません。流石。
これはこれで神武の真骨頂とも言えて。試練や苦境におかれたときにリーダーはどう決断し行動すべきかを教えてくれます。
つづきはコチラ!兄さーん!!
神武東征神話のまとめ、目次はコチラ!
神話を持って旅に出よう!
神武東征神話のもう一つの楽しみ方、それが伝承地を巡る旅です。以下いくつかご紹介!
●気になる激戦の地の考察はこちら。
●孔舎衛顕彰碑はコチラ!
●雄叫びをあげたのはコチラ!
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
こちらの記事もどうぞ。オススメ関連エントリー
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




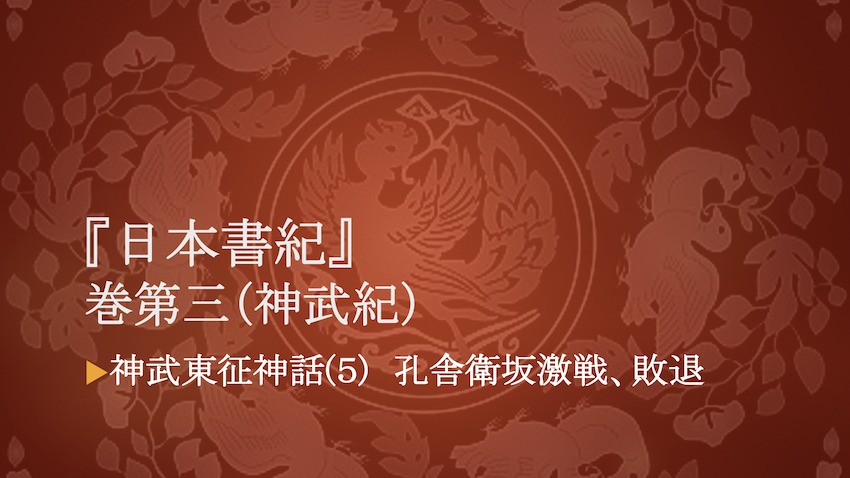


























→白肩津に上陸した春、から夏へ。
「丙申が朔にあたる甲辰」は4月9日のこと。
言葉の解説を少し。
「兵を整え(原文:勒兵)」の、「勒」は、原義は馬の口にかませる「くつわ(轡)」や頭にかけるひも(おもがい)のこと。転じて、兵を整える、心を引き締める意味。
そのうえで、
神武は大軍を率いて、まず龍田に向かいます。
この「龍田」は、現在の「竜田」、現在の奈良県生駒郡斑鳩町から西、大阪府柏原市の東付近。信貴山と明神山の間のところ。
古代、この付近には「竜田山」があったとされ、『万葉集』にこの山にちなむ歌をいくつか収載してます。例えばこちら。
この歌に詠む竜田山は、奈良朝の人々が難波(大阪)から大和(奈良)に向かう際に目印とした山。飛鳥藤原の時代には、すでに竜田道が難波と大和とを結ぶ大道として通じていたようです。
上記は歴史の時代の話ですが、逆に言うと、後世になって大道となっていくわけで。その意味で、竜田道は確かに、「中洲」をめざす最適のルートだったともいえるかも。
ちなみに、、、
この「竜田山」、その後、名前が失われ伝説と化しておりました。2016年、龍田大社と柏原市の協力のもと、龍田の祭神が降臨したと云われる、柏原市雁多尾畑地区にある「御座峰」に「龍田山伝承の地」石碑が建てられております(三郷町観光協会による)。
次!
→大軍が通るには狭く、険しかったと、、
進軍ルートイメージはコチラ。
狭く、険しかったって、、ホントに???
って疑問が残る雰囲気、、、実際、生駒山越えより良いような気がするのですが、、、コレ、後ほど解説。
「そこで引き返し、改めて東方、胆駒山を越えて中洲に入ろうとした。」とあり、生駒山を超えて大和平野(奈良盆地)に入るルート(第2ルート)を選択するわけです。
図示すると以下。
ちなみに、、
この第二ルートについては、現地調査を敢行!!
その詳細がコチラ↓!
実は、
「胆駒山を越えて中洲に入ろうとした」ルートには、2つの候補がありまして、、
現地調査を踏まえ、実際の地形をもとに考えると、恐らく、現在の暗峠だと推測されます。
▲現在の暗峠から大阪方面の図。大軍が進むには十分な広さがあり。孔舎衛「坂」というからには、山奥に入る手前、住宅地が広がっているあたりで激戦が繰り広げられたのだと思います。
あと、
「中洲に入ろうとした」の「中洲」についてはコチラ↓で
ポイント2つ。
ってことで、「葦原中国 >中洲 > 墺區」。大きさのイメージとあわせて、この地こそが、大業を成すに相応しい場所として位置づけられてること、しっかりチェック。
次!
→いきなり入ろうとするから、、、相手も脊髄反射やん、、
「長髄彦」は、名前をそのまま解釈すると「スネの長い男」。「髄」は、「スネ」の和名。膝から下が長い=敵対者の異形性を表現したもの。
ちなみに、、、
東征神話終盤では、以下のように伝えてます。
と言うことで、
もともと村の名前だった「長髄」。それにちなんで「長髄彦」。さらに、金鵄飛来というスーパーミラクル確変イベント発生にちなんで「鵄邑」と改名。それが訛って「鳥見」へ。『日本書紀』ではココまで。その後、歴史の時代に「鳥見郷」「鳥見庄」を経て、明治時代に富雄村の一部となり、昭和28年には富雄町が成立、その後奈良市に編入されて、現在、奈良県奈良市鳥見町。
話を戻して、
「長髄彦」は、長髄村のほか、おそらく大和一帯を支配していたと考えられ。さらに、神武より先に大和の地へ天から降ってきた「饒速日命」を自分の妹と結婚させていたお方です。
当然、情報網は構築されていた訳で、部外者が侵入してきたと聞けば兵を起こして迎え撃つ。地元民からしたら当然の反応であります。
次!
→五瀬命は、神武の長兄。
この戦闘で負傷。で、このあと、この傷がもとで亡くなってしまいます。。
次!
→神武の「神策」発動。神策をめぐらすのに「運」という漢字が使われてますね。運用する。
先に言葉の解説を少し。
「不若」は、「〜に若かず」と読み、「〜に及ばない」「〜には及ばない(〜のほうがよい)」という意味。「退還示弱、禮祭神祇、背負日神之威、隨影壓躡」に若かず。=の方がよい。
「抑えつけるように敵を踏みつける(原文:壓躡)」は、「壓(圧)」=押さえつける、鎮める、圧倒する+「躡(躡)」踏む、踏みつける。単に力で潰すだけでなく、神聖な力=日神の神威や圧倒的な存在感によって相手を征服・圧倒するというニュアンスが含まれます。
そのうえで、
ココで、神武の敗退理由を整理してみると、、以下の通りです。
(その一) 経路不適
生駒山越えの経路は、海岸から急峻な生駒山麓が迫る山越え。これは、大軍の進軍には不適。
(その二) 作戦ミス 全部で4つ。
①日の神の子孫の自覚を欠き、日に向かって戦う。(天道に逆らう戦い)
大阪方面から奈良盆地に向かって攻め込む事は、西から東へ進軍する事になります。東は太陽が昇る方角。これは、日に向かって矢を向ける事であり、日の神の子孫である神武にとっては天の道、道理に逆らう事だという事です。
▲生駒山を大阪方面から登る絵。午前中に登ったので、まさに上る太陽が目の前、まぶしーっ!ってなる。古代の戦いも午前中だったようで、東から西へ生駒山を登ると目の前がまぶしくて戦いになりません。。。まさに、日に向けて矢を放つ、、、天の道に背く行為ですよね。
②「天神子」でありながら地上から山越え侵入し、長髄彦に自分の国を奪いに来たとの誤解を与えた。
「天神子」である神武。であれば天降りしたらよかったのですが、、、地上から山を越えようとフツーに侵入。比較対象は「饒速日」。この神の場合、東征以前に、天から天磐船に乗って降ってきた訳で、それであればと、長髄彦は妹を嫁がせて受け入れてる訳ですね。ちなみに、子どもまでつくってる。。
フツーに攻め込んだ神武と、天から天降りした饒速日。同じ天神系の神でありながら、神武の場合、大和入り方法の違いが誤解を生み、戦闘に突入することになった次第。
自分の出自やアイデンティティ的なところに無自覚なまま突っ込めば、相応の結果が返ってくるという教訓です。
③攻撃するに当たり、事前に相手方に使者を派遣して、交渉・和睦・降伏勧告などを行わせることなく、いきなり戦闘に突入した。
このころは、戦い方も未熟でした。上陸、突っ込む、以上。という稚拙な内容。本来であれば、相手方に使者を派遣して、意向を確認する手順を踏むべきなのですが、、、なんでもそうですが、失敗から学び、教訓として活かす、という流れですよね。
ちなみに、東征神話の後半では、道臣らの侍臣を攻撃前に派遣し、交渉に当たらせてます。ココに神武の成長を見ることができる訳です。
④陸戦に対して兵の訓練・装備等が十分ではない。
吉備国の高嶋宮で3年を費やして準備したのは軍船と食糧だけ。。。陸戦用の装備を十分に整えていたか疑問。。
ということで、、
敵を知らず、おのれのアイデンティティに無自覚のまま戦えば、敗北は必至という訳です。
孫子の兵法(中国、呉の孫武が著したとされた兵法書)にも、「彼れを知り己れを知れば、百戦殆うからず。(中略)彼れを知らず己れを知らざれば、戦う毎に必ず殆うし。」と説いておりますよね、、
で、、
大事なのはココから!
敗北は敗北でいいとして、結果なので。大事なのはソコからの巻き返しです。これ、仕事でもなんでもそう。
話が飛びますが、、、
例えば、楚の項羽が漢の劉邦(高祖)の攻撃を受けて惨敗した際に、巻返しを期す周囲の勧めにもかかわらず、項羽は美姫の虞美人と共に自殺するという古代中国の著名な歴史上の伝承があります。コレ、捲土重来(一度敗れたものが、再び勢力をもりかえしてくること)の故事として知られますが、、
項羽とは逆に、神武は冷静に敗因を探り出して、巻き返しをはかります。その神策を次のように示してます。ポイント4つ。
①敗因を特定する。
日神の子孫でありながら、日に向って賊を討伐したことは天道に逆らうことであり、これを敗因と認定する。
②退却して、弱いように見せかける。
賊に油断させる作戦を立て、実行する。
③神祇を礼祭する。
天神や地祇の加護や援助を得る。具体的には、東征神話中盤、周囲を敵に囲まれたときに「天神」の教えとして登場。
④背に日神の霊威を負い、前にできる影に従って賊を圧倒する。
太陽を神格化した日神の威力、神助により、賊の打倒をはかる。つまり、東から西へ攻め込む事で、日の神の威光を背に勝ち進むことができるという事。昇る太陽の光を背に受けて、自分の影が前にできます。その影に従って進軍することで勝利できるというロジック。
この戦略による理想的討伐であれば、武力を行使するまでもなく、賊は必ず自滅すると全軍に示すと、誰もが賛同の声を挙げた訳です。
ここに全軍が団結し、巻返しに向けた行動を開始することになる。この巻き返しこそが神武の英雄たる所以。ウジウジしない!このスタンスは学びたいところですよね。
ちなみに、、
ココで登場する「日神の神威を背に負い(背負日神之威)」は、東征神話最後の宮都造営指令のときに、「天神の威光(皇天之威)」として再登場。
なので、
ココでは布石としての意味もあり。これ以降の東征神話は全て、この「背負日神之威」をもとに展開していきます。超重要事項。
次!
→即時に、撤退宣言。
損切りの判断は早ければ早いほど良い。傷口を無用に広げることになるので。コレ、運営や経営にとっては非常に重要な対応。現代のビジネスにも通じる内容です。
「始める」のは意外に簡単で、一番難しいのは「止める」こと。いろんな人が関わってくると余計に難しいのが世の常人の常。でも、決断する時はバシッとやる訳です。それが経営であり、責任者の務めであります。
次!
→神策発動中。退却し、船がある草香津まで戻る。ココから紀伊半島ぐるっと一周作戦へ。
「盾を立てて雄誥をした(原文:植盾而爲雄誥)」とあります。コレ、雄々しく声をあげ、戦意を鼓舞するということ。手痛い敗戦という逆境を、雄誥によって鼓舞しようとしたのです。
次!
→「恩 母の如し」の「母」とは、生みの母ではなく育ての乳母を言います。
古代では高貴な子女の養育にもっぱら乳母を当てていました。
その起源は、日本書紀の海幸・山幸の神話にまで遡ります。神武の祖父ホホデミ(山幸)は海神の娘・豊玉姫と結婚し、神武の父(ウガヤフキアエズ)を出産するが、「見るなの禁忌」を破って妻の出産を見てしまう。豊玉姫はなんと八尋のワニとなって出産の苦しみにもだえていた。その姿を見られてしまった豊玉姫はウガヤフキアエズを残して海へと帰ってしまう。困ったホホデミは婦人を取って、フキアエズを養育させます。
その婦人たちの役割は
など。すなわち、ここでいう「恩 母の如し」とは、自分を養育してくれた乳母の恩を想起して、命拾いさせてくれた樹を「乳母の樹よ」とたたえている訳です。自分を養育してくれた乳母の恩と、命拾いさせてくれた樹への恩を重ねているのです。