多彩で豊かな日本神話の世界へようこそ!
正史『日本書紀』をもとに、
最新の学術成果も取り入れながら、どこよりも分かりやすい解説をお届けします。
今回は、『日本書紀』巻第一(神代上)第四段の一書の第2~10。
第四段は、新時代到来の巻。
伊奘諾尊・伊奘冉尊の二神による「国生み」を伝える本伝。そして、そこに併載されてる異伝が全部で10!多彩な神話世界を展開してます。
今回はその中から、一書第2~10をざざざっとご紹介。
概要で全体像をつかみ、ポイント把握してから本文へ。最後に、解説をお届けしてまとめ。
現代の私たちにも多くの学びをもらえる内容。日本神話から学ぶ。日本の神髄が、魂がここにあります。それでは行ってみましょう!
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
国生み『日本書紀』巻第一(神代上)第四段 一書第2~10 多彩に展開する国生み
目次
国生み『日本書紀』巻第一(神代上)第三段 一書第1の概要
前回、『日本書紀』巻第一(神代上)第四段の一書第1
からの続き。
下図、赤枠部分。本伝の下、一書第1~10。

改めて、
第四段は、新時代到来の巻。
第三段までの、道の働きによる神の誕生から、第四段からは、男女の性の営みによる国や神の誕生へ。
国生み(第四段)→神生み(第五段)への流れは、国の土台づくり→国を統治する主者を生む という展開でもあります。
そんな第四段、本伝に併載されてる異伝は、なんと全部で10!
神代のなかでも2番目に多い異伝のみなさん。とにかく多彩。一歩間違うと訳分からん世界。でもご安心を。当サイトならではのガイドがあれば大丈夫!
コチラ!
| 1 | 本伝全体の流れ踏襲 天神に動かされる2神→『古事記』と同じ |
書1 |
| 2 | 磤馭慮嶋の形成 | 書2,3,4 |
| 3 | 唱和 | 書5 |
| 4 | 結婚、懐妊後の洲生み | 書6,7,8,9 |
| 5 | 陰神の先唱と積極性 | 書10 |
10の異伝も、整理すれば5つのタイプに分類可能。
今回は、ここから、一書第2~10を一気にお届けする強気な企画。
9つの異伝、全て断片伝承。本伝や一書1をもとに差違化。なので、第四段 本伝や一書1を理解してる必要あり。
一書1とは違い、断片的な物語群なので、固まりごとに読み進めていきましょう。

国生み『日本書紀』巻第一(神代上)第四段 一書2~10のポイント
第四段一書2~10は、本伝ならびに一書1を先にチェックしておいてください。
その上で、ポイント2つ。
①断片伝承の寄せ集め!?そうは言っても本伝の流れをもとに並んでます
第四段一書2~10。各伝承の内容は断片的で、それだけ取り出してもよー分からん状態。
寄せ集めですか!?
と、思いきや、実は「協議→結婚→出産」という本伝の流れをもとに並んでます。
こんな感じ。
| 1 | 協議 | 書2,3,4 |
| 2 | 結婚 | 書5 |
| 3 | 出産 | 書6,7,8,9 |
断片的伝承の寄せ集めに見えて、実は本伝の流れ通り。全部で8つの異伝も3つの固まりに。うん分かりやすい。
あれ?第10は?
それは、、、
②一書第10はめっちゃユニーク!原理を違えて成立する世界がある!
今回ご紹介する一書群のなかで、一書第10は特別。これ、
振り切ってる感じがスゴくて。
一書1をもとに差違化されてるんですが、伊奘冉尊の積極性が際立ってます。
本来であれば、原理原則からすると、伊奘諾尊、つまり陽神主導であるべきなんですが、この一書第10は最初から最後まで伊奘冉尊、つまり陰神主導。
これまでのように「やり直し」といった軌道修正がないので、これはこれで、原理を違えても成立しちゃう世界があるってことに。
この意味は神話展開上めちゃめちゃデカくて。。。続く第五段、天照大神による高天原統治の理由付けにもつながっていきます。詳細後ほど。
まとめます
- 断片伝承の寄せ集め!?そうは言っても本伝の流れ(協議→結婚→出産)をもとに並んでます
- 一書第10は非常にユニーク!原理を違えて成立する世界がある!
以上、
2点を踏まえて以下、一書群をチェックです。
国生み『日本書紀』巻第一(神代上)第四段 一書2~10 現代語訳

<第四段〔一書2〕>
ある書はこう伝えている。伊奘諾尊と伊奘冉尊の二神は、天霧の中に立って「私は国を得ようと思う。」と言った。そして、天瓊矛を指し下ろしてこれを探ると磤馭慮嶋を得た。そこで矛を抜き上げ、喜んで「良かった。国がある。」と言った。
一書曰、伊奘諾尊・伊奘冉尊二神、立于天霧之中曰、吾欲得国。乃以天瓊矛指垂而探之、得磤馭慮嶋。則抜矛、而喜之曰、善乎、国之在矣。(『日本書紀』巻第一(神代上)第四段〔一書2〕より)
<第四段〔一書3〕>
ある書はこう伝えている。伊奘諾・伊奘冉尊の二神は、高天原に座して「国があるはずだ」と言った。そこで天瓊矛でかきまわして磤馭慮嶋を成した。
一書曰、伊奘諾・伊奘冉尊二神、坐于高天原曰、当有国耶。乃以天瓊矛画成磤馭慮嶋。(『日本書紀』巻第一(神代上)第四段〔一書3〕より)
<第四段〔一書4〕>
ある書はこう伝えている。伊奘諾と伊奘冉の二神は、互いに「物があって、浮かんでいる油のようだ。その中に国があると思う」と言った。そこで、天瓊矛で探って一つの嶋を成した。名付けて磤馭慮嶋という。
一書曰、伊奘諾・伊奘冉尊二神、相謂曰、有物、若浮膏。其中蓋有国乎。乃以天瓊矛探成一嶋。名曰磤馭慮嶋。(『日本書紀』巻第一(神代上)第四段〔一書4〕より)
<第四段〔一書5〕>
ある書はこう伝えている。陰神が先に唱え「ああ、なんとすばらしい、いい少男でしょう」と言った。この時、陰神が先に言葉を発したので不吉とした。もう一度改めて巡り、陽神が先に唱え「ああ、なんとすばらしい、いい少女ではないか。」と言った。ついに交合しようとしたが、その方法が分からなかった。その時、鶺鴒が飛んで来て、その首と尾を揺り動かした。二神は見てこれを学び、すぐに交合の方法を得た。
一書曰。陰神先唱曰。美哉。善少男。時以陰神先言故、為不祥。更復改巡。則陽神先唱曰。美哉。善少女。遂将合交、而不知其術。時有鶺鴒飛来揺其首尾。二神見而学之。即得交道。(『日本書紀』巻第一(神代上)第四段〔一書5〕より)
<第四段〔一書6〕>
ある書はこう伝えている。二神は交合して夫婦となった。まず淡路洲・淡洲を胞として、大日本豊秋津洲を生んだ。次に、伊予洲。次に、筑紫洲。次に、億歧洲と佐渡洲とを双児で生んだ。次に、越洲。次に、大洲。次に、子洲。
一書曰、二神合爲夫婦、先以淡路洲・淡洲爲胞、生大日本豐秋津洲。次伊豫洲。次筑紫洲。次雙生億岐洲與佐度洲。次越洲。次大洲。次子洲。(『日本書紀』巻第一(神代上)第四段〔一書6〕より)
<第四段〔一書7〕>
ある書はこう伝えている。まず、淡路洲を生んだ。次に、大日本豊秋津洲。次に、伊予二名洲。次に、佐渡洲。次に、筑紫洲。次に、壱岐洲。次に、対馬洲。
一書曰、先生淡路洲。次大日本豐秋津洲。次伊豫二名洲。次億岐洲。次佐度洲。次筑紫洲。次壹岐洲。次對馬洲。(『日本書紀』巻第一(神代上)第四段〔一書7〕より)
<第四段〔一書8〕>
ある書はこう伝えている。磤馭慮嶋を胞として淡路洲を生んだ。次に、大日本豊秋津洲。次に、伊予二名洲。次に、筑紫洲。次に、吉備子洲。次に、億歧洲と佐渡洲を双児で生んだ。次に、越洲。
一書曰、以磤馭慮嶋爲胞、生淡路洲。次大日本豐秋津洲。次伊豫二名洲。次筑紫洲。次吉備子洲。次雙生億岐洲与佐度洲。次越洲。(『日本書紀』巻第一(神代上)第四段〔一書8〕より)
<第四段〔一書9〕>
ある書はこう伝えている。淡路洲を胞として大日本豊秋津洲を生んだ。次に、淡洲。次に、伊予二名洲。次に、億歧三子洲。次に、佐渡洲。次に、筑紫洲。次に、吉備子洲。次に、大洲。
一書曰、以淡路洲爲胞、生大日本豐秋津洲。次淡洲。次伊豫二名洲。次億岐三子洲。次佐度洲。次筑紫洲。次吉備子洲。次大洲。(『日本書紀』巻第一(神代上)第四段〔一書9〕より)
<第四段〔一書10〕>
ある書はこう伝えている。陰神が先に唱え「ああ、なんとすばらしい、いい少男でしょう」と言った。そこで陽神の手を握り、遂に夫婦となって、淡路洲を生んだ。次に、蛭児。
一書曰、陰神先唱曰、妍哉、可愛少男乎。便握陽神之手、遂為夫婦、生淡路洲。次蛭児。(『日本書紀』巻第一(神代上)第四段〔一書10〕より)

国生み『日本書紀』巻第一(神代上)第四段 一書2~10 解説
全部で9つの異伝、いかがでしたでしょうか?
一応、第四段 本伝の流れに沿って並んでましたよね。以下、3つの固まりごとに解説していきます。
協議 の部 解説
結婚 の部 解説
第四段本伝の「結婚」に対応する一書は、一書5。
- ある書はこう伝えている。陰神が先に唱え「ああ、なんとすばらしい、いい少男でしょう」と言った。この時、陰神が先に言葉を発したので不吉とした。もう一度改めて巡り、陽神が先に唱え「ああ、なんとすばらしい、いい少女ではないか。」と言った。ついに交合しようとしたが、その方法が分からなかった。その時、鶺鴒が飛んで来て、その首と尾を揺り動かした。二神は見てこれを学び、すぐに交合の方法を得た。
- 一書曰。陰神先唱曰。美哉。善少男。時以陰神先言故、為不祥。更復改巡。則陽神先唱曰。美哉。善少女。遂将合交、而不知其術。時有鶺鴒飛来揺其首尾。二神見而学之。即得交道。
→交合の方法を鳥に教わる、、だと???
ポイント2つ。
①「不祥」を地の文で使うことで、普遍性を持つものとして転換させてる
前半の先唱後和。陰神先唱による間違い。でも「不祥」としてやり直し。なんだけど、、本伝は陽神の発言の中での不祥でしたが、ここでは、「誰が」に相当する部分が抜け落ちてます。不祥としたのは誰なんだ?!
って、これ、地の文で「不祥」と伝えることにより、普遍的、一般的な性質をもつ評価に転換させてるってことで、これも差違化の一つだったりします。
2つ目。
②交合方法を鳥から学ぶのは、鳥は天の使いだから(日本神話的に!
再びの先唱後和、正しい順番で実行。ところが、、、
交合の仕方が分からない!∑(゚Д゚;)
で、なぜか鳥(鶺鴒)が登場。「鶺鴒」はセキレイのこと。長い尾を上下に振って歩く、スズメ目セキレイ科の鳥。

で、この鳥の動きを見て学んだと。。。それにしても、なぜ鳥???
実は、、鳥については、日本神話の中でも随所に登場。本件について、簡単に言うと
鳥=天の使い、天のメッセージを伝える役目 ってこと。
神武東征神話では「八咫烏」や「金鵄」として登場。
八咫烏は天照大神の使いとして。道案内を担当 →頭八咫烏の導きと熊野越え|山で迷って進退窮まる!?天照による2度目の救援は「天孫降臨」の再現だった件
金鵄は天からの瑞祥として登場。勝利の吉祥メッセージ →金鵄飛来=祥瑞応見|「瑞(みつ)」は王の聖徳に天が応えて示す「しるし」。古代にはそれなりのもんげー制度があった件
いずれも、天の使いとして、天のメッセージを伝える役目として位置づけられてるんす。
二神の交合方法不明の問題は、どうやって子を生むべきか?という側面以上に、どうやって国の土台たる洲を生むべきか?もっというと、どうやって国づくりを始めるべきか?という問題であって、、、そうなると、俄然、天が関与せざるを得ない、いや、天の意思的には重大事項になるわけです。だって、天は国をつくりたいから。
なので、天としては阻害要因を除去すべく動く。今回のケースでは、交合方法教える必要があり、鳥を通じてメッセージを伝達したってことなんす。これ、日本神話的な天の意思理論。
で、なんでセキレイなの?という話。
これは簡単で、この鳥は、水辺のあたりで尾を上下にゆり動かす習性をもつから。要は、交合の動きに似た行動特性を持ってるから、ってこと。ちなみに、、「鶺鴒」は、「ニハ(庭)」「クナ(尻)」「ブリ(振)」の意味、という説もあったりなかったり、、
ということで、まず、天の意思メッセンジャーとして鳥が選ばれ、その上で、交合と似た動きを持つセキレイが選ばれたってことでチェック。
出産 の部 解説
第四段本伝の「出産」に対応する一書は、一書6、7、8、9。
〔一書6〕の冒頭「二柱の神は交合して夫婦となった」を踏まえ、〔一書7〕以降どの一書も夫婦を前提として書き出してます。
〔一書6〕
- ある書はこう伝えている。二神は交合して夫婦となった。まず淡路洲・淡洲を胞として、大日本豊秋津洲を生んだ。次に、伊予洲。次に、筑紫洲。次に、億歧洲と佐渡洲とを双児で生んだ。次に、越洲。次に、大洲。次に、子洲。
- 一書曰、二神合爲夫婦、先以淡路洲・淡洲爲胞、生大日本豐秋津洲。次伊豫洲。次筑紫洲。次雙生億岐洲與佐度洲。次越洲。次大洲。次子洲。
〔一書7〕
- ある書はこう伝えている。まず、淡路洲を生んだ。次に、大日本豊秋津洲。次に、伊予二名洲。次に、佐渡洲。次に、筑紫洲。次に、壱岐洲。次に、対馬洲。
- 一書曰、先生淡路洲。次大日本豐秋津洲。次伊豫二名洲。次億岐洲。次佐度洲。次筑紫洲。次壹岐洲。次對馬洲。
〔一書8〕
- ある書はこう伝えている。磤馭慮嶋を胞として淡路洲を生んだ。次に、大日本豊秋津洲。次に、伊予二名洲。次に、筑紫洲。次に、吉備子洲。次に、億歧洲と佐渡洲を双児で生んだ。次に、越洲。
- 一書曰、以磤馭慮嶋爲胞、生淡路洲。次大日本豐秋津洲。次伊豫二名洲。次筑紫洲。次吉備子洲。次雙生億岐洲与佐度洲。次越洲。
〔一書9〕
- ある書はこう伝えている。淡路洲を胞として大日本豊秋津洲を生んだ。次に、淡洲。次に、伊予二名洲。次に、億歧三子洲。次に、佐渡洲。次に、筑紫洲。次に、吉備子洲。次に、大洲。
- 一書曰、以淡路洲爲胞、生大日本豐秋津洲。次淡洲。次伊豫二名洲。次億岐三子洲。次佐度洲。次筑紫洲。次吉備子洲。次大洲。
→ポイントは、胞の使用。
第四段 本伝での解説でも触れましたが、神の出産は、人間モデルと違い、胞、つまり膜は母体にはできない仕様のようで。母体の外にある嶋を「胞(膜)」として使用するらしい。
ここでは、「淡路洲(淡洲)」「磤馭慮嶋」が「胞(膜)」として使用され、出産へ。それぞれが、何でそれなのか?はあまり意味が無く、差違化の結果として理解するのが◯。
一応、一覧として以下まとめてみます。
| 一書6 | 一書7 | 一書8 | 一書9 |
| 大日本豊秋津洲 | 淡路洲 | 淡路洲 | 大日本豊秋津洲 |
| 伊予洲 | 大日本豊秋津洲 | 大日本豊秋津洲 | 淡洲 |
| 筑紫洲 | 伊予二名洲 | 伊予二名洲 | 伊予二名洲 |
| 億歧洲 | 億岐洲 | 筑紫洲 | 億歧三子洲 |
| 佐渡洲 | 佐渡洲 | 吉備子洲 | 佐渡洲 |
| 越洲 | 筑紫洲 | 億歧洲 | 筑紫洲 |
| 大洲 | 壱岐洲 | 佐渡洲 | 吉備子洲 |
| 子洲 | 対馬洲 | 越洲 | 大洲 |
※大日本豊秋津洲(本州)、伊予洲(四国)、筑紫洲(九州)、億歧洲(隠岐の島)、佐渡洲(佐渡島)、大洲(周防国大島/山口県屋代島か)、子洲・吉備子洲(備前国/岡山県の児島半島)、壱岐洲、対馬洲、越洲(北陸道一帯)
ユニークな一書第10
- ある書はこう伝えている。陰神が先に唱え「ああ、なんとすばらしい、いい少男でしょう」と言った。そこで陽神の手を握り、遂に夫婦となって、淡路洲を生んだ。次に、蛭児。
- 一書曰、陰神先唱曰、妍哉、可愛少男乎。便握陽神之手、遂為夫婦、生淡路洲。次蛭児。
→この〔一書10〕はめっちゃユニーク。
- 陰神が先に唱え(原文:陰神先唱曰)
- そこで陽神の手を握り、遂に夫婦となって(原文:便握陽神之手、遂為夫婦)
なんて、、、伊奘冉さん積極的すぎでしょ!??伊奘諾の存在感ゼロ。こんなのあり得ヘーん!
って、これはこれで、言い方を変えると、
原理を違えても成立する世界がある!
ってことで、、つまり、
- 原理原則からすると、陽神主導であり、陽が先になるべきなんですが、
- この段があることで、陰神主導で、陰が先になってもいい世界があり得る
- つまり、原理を違えても成立する世界がある、ということになる。
この意味はめちゃくちゃ大きくて。続く第五段で、日神(天照大神)誕生と高天原統治につながっていくんです。
どういうことかというと、原理からすると、陰が統治者となることはあり得ない訳です。ですが、実際には陰神である天照大神が高天原の統治者になっていく。これ、普通に考えるとおかしいじゃねえかと。
でも、
ココ、第四段〔一書10〕において、原理を違えた「あり得ない世界が成立する」って伝える事で、あり得なくない話に。いや、あり得る話になる!
さらにさらに、陰神が統治者になることで、陽神たる素戔嗚尊が反抗し、これが狂言回しの役割として機能し、物語が大きく、オモシロく展開していくようになる。。
これまでの「道」とか原理とかガチガチムキムキだと正解からはみ出せない。それってつまり、神話として多様に展開できなくなる。。そうした制約とか、神話的閉塞を打破するために、原理から外れた世界を一書で用意する。しかも、第五段へ続く直前、第四段の最後の一書で原理から外れてもOKな世界を入れることで、その後の展開に広がりが出てくるよう設計されてるんです。これもしっかりチェック。
国生み まとめ
『日本書紀』巻第一(神代上)第四段 一書第2~10
第四段は新時代到来の巻。
第三段までの、道の働きによる神の誕生から、第四段からは、男女の性の営みによる国や神の誕生へ。で、その営みの実態は、国生み(第四段)→神生み(第五段)という流れで展開。
国の土台づくり→国を統治する主者誕生 という展開でもある。
本伝に併載されてる異伝は全部で10!神代のなかでも2番目に多い異伝の数ですが、整理すれば5つのタイプに分類可能。
その中で、一書2~10は、本伝の流れ「協議→結婚→出産」をもとに差違化した物語。すべて断片伝承。
そのなかで、特に重要なのは一書第10。
原理を違えても成立する世界があるを提示することで、続く第五段以降の展開に合理性や納得性を付与する役目を果たしています。
日本神話の物語を構成する大きな装置、仕掛けがあって、そのために神話的な合理性を確保しつつ、狙いを定めて入れるべき内容を入れるべき場所に入れていく。
緻密に計算された、その積み上げとしての壮大な神話世界の展開へと繋げていること。その創意工夫のスゴさ、智恵をチェックされてください。
次は、いよいよ第五段、天下の主者誕生です!
続きはコチラ↓で!
神話を持って旅に出よう!
国生み神話の伝承地はコチラです!
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
[itemlink post_id=”13035″] [itemlink post_id=”13037″] [itemlink post_id=”13038″] [itemlink post_id=”13039″]
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




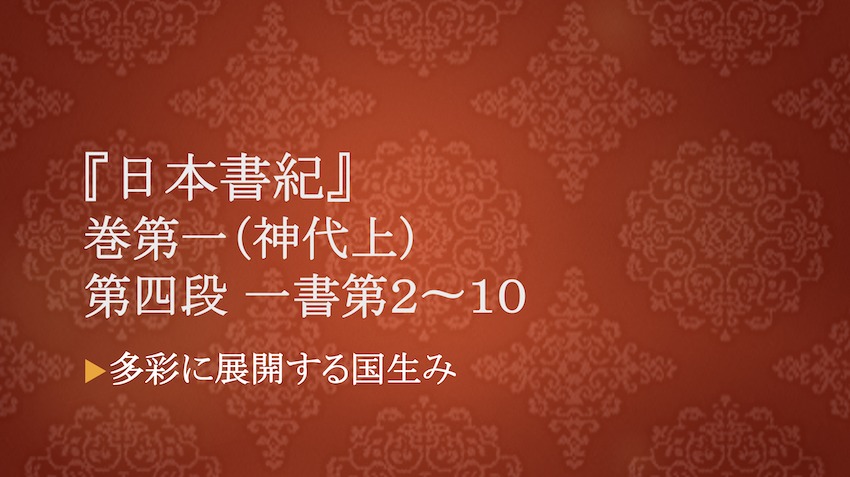






















第四段本伝の「協議」に対応する一書は、一書2、3、4。どの一書も、
と、3つの点でおおまかな共通性あり。
一方で、〔本伝〕に基づきながらも、本伝にある「滄溟」は登場しない。なので「其矛鋒滴瀝之潮」も無し。とにかく重視したいのは
「国」の取得、または存在想定
新しい時代が到来し、これから国家、つまり主権あり・人民あり・領土ありの三要件が整ったきちんとした国づくりが始まるわけで。「国があるはずだ」といった諾冉二神の言葉には、そうした予祝が込められている。コレ激しくチェック。
その上で、少し詳細解説。
<第四段〔一書2〕>
→「天霧」が地味に大事だったりして、、
「天霧」=天の霧。どうやら、天に霧が立ってるようで、、ポイントは、霧が立つってことは、湿地帯があるってことで、湿地帯があるってことは、そこに水田を作れるってことで。水田は豊かな秋の実りへ、つまり千五百秋瑞穂へ繋がっていく!!ってことなんす。
これ、類例として、第五段〔本伝〕では、
「私が生んだ国は、ただ朝霧だけがかすんで立ちこめてる(原文:我所生之國 唯 有朝霧 而 薫滿之哉)」と伝えており、ココでは地上の様子を言ってるのですが、それでも「霧」=湿地帯=水田=秋の実り、ということで、私が生んだ国=「大八洲国」が「豊葦原千五百秋瑞穂の地」となっていく事を象徴的に予告・約束する言葉、として使われてます。
さらに、
第五段〔一書11〕では、「(天照大神は)その稲の種を、天狭田と長田に始めて植えた。その秋には、垂れた稲穂が握り拳八つほどの長さにたわむほどの豊作であり、たいへん快よい(原文:即以其稲種、始殖于天狭田及長田。其秋垂穎八握莫莫然。甚快也。)」と伝えており、稲作が始まってる訳で。
これ、当然、天に湿地帯がないと稲作できませんから!その意味で、ココでの「天霧」は、第五段〔一書11〕への「わたり」として位置付けられる訳です。
その上で、
「私は国を得ようと思う」と言表し、天瓊矛を指し下ろして磤馭慮嶋を得る(言表と行為)。それを「良かった。国がある(原文:善乎、国之在矣。)」としています。
これ、意味としては、既に国は存在している=存在確定!ってことで。予祝でありつつも、かなり重要な意味を持たせてます。
次!
<第四段〔一書3〕>
→ココでは高天原が登場!
すでに第一段〔一書4〕で登場してますので、前振りは完了してます。
その上で、
ここで二度目の登場、俺たちの高天原。役割としては「国を尊貴化」すること。
二神は、至高な場である「高天原」にいて、そこから言葉を発する。「国があるはずだ(原文:当有国耶)」は、「まさに国あるか」→あるはずだぜ、間違いないぜ、といったニュアンス。高天原で発された言葉な訳で、重要な意味を持つ。
さらに、高天原から矛をかき回して将来の国(の一部)となるべき嶋を形成、これ、言い方を変えると高天原が関与ってこと。つまり、国生みに高天原が関与したって意味であり、これはこれで重要事項としてチェック。
次!
<第四段〔一書4〕>
→「物があって」って、懐かしい表現、、ってピンときたらあなたも神話ツウ。
これ、第一段の、天地開闢の時の表現ですよね。具体的には、「国常立尊」の化生に関連した表現を組み合わせて成立させてる。
第一段の一書のうち、冒頭が「天地初判」に始まる系統で、
二つの組み合わせ。いずれも「国常立尊」の化生に関連した所伝であります。
「一番最初に誕生した純男神」というめっちゃ尊い神。その誕生方法と同じ設定を、嶋の形成に使用することで「国の尊貴化」を図ってる。てことです。
ということで、3つの一書群。まとめると、
テーマは「将来、国となっていくための予祝的なメッセージ」&「国の尊貴化」で、そのために
と、まー、良くできてる。テーマをもとに差違化によって多彩で豊かな日本神話世界が展開されてます。