多彩で豊かな日本神話の世界へようこそ!
正史『日本書紀』をもとに、最新の文献学的学術成果も取り入れながら、どこよりも分かりやすい解説をお届けします。
今回は、『日本書紀』巻第一(神代上)第四段の一書の第1。
第四段は新時代到来の巻。
伊奘諾尊・伊奘冉尊の二神による州国生みを伝える本伝。これに併載されてる異伝が全部で10個。いずれも本伝をもとに差違化、多彩な神話世界を展開しています。
今回はその中から、一書第1をご紹介。
概要で全体像をつかみ、ポイント把握してから本文へ。最後に、解説をお届けしてまとめ。
現代の私たちにも多くの学びをもらえる内容。日本神話から学ぶ。日本の神髄がここにあります。それでは行ってみましょう!
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
国生み『日本書紀』巻第一(神代上)第四段 一書第1 天神ミッションと無知な二神
目次
国生み『日本書紀』巻第一(神代上)第四段 一書第1の概要
前回、『日本書紀』巻第一(神代上)第四段の本伝、
からの続き。
下図、赤枠部分。本伝の下、一書第1。

第四段は、新時代到来の巻。何が新しいって、
男女の営み
ってところ。
第三段までの、道の働きによる神の生成から、第四段からは、男女の営みによる洲国や神の誕生へ。男女の性の営みだからこそ、そこには責任が伴うわけで、これは続く第五段で主者生みへとつながって行きます。
第四段は州国というステージを用意、第五段はステージの主たる主者を用意していく。これら全て新時代ならではの展開であります。
そんな第四段、本伝に併載されてる異伝は全部で10!
神代紀のなかでも2番目に多い異伝のみなさん。とにかく多彩。一歩間違うと訳分からん迷宮ワールド。
でもご安心を。当サイトならではのガイドがあれば迷うことはございません!こんなのどうでしょう
| 1 | 本伝全体の流れ踏襲 天神に動かされる2神→『古事記』と同じ |
書1 |
| 2 | 磤馭慮嶋の形成 | 書2,3,4 |
| 3 | 唱和 | 書5 |
| 4 | 結婚、懐妊後の洲生み | 書6,7,8,9 |
| 5 | 陰神の先唱と積極性 | 書10 |
10の異伝も、整理すれば5つのタイプに分かれます。かつ、本伝の展開をなぞるように配列。
重点チェックすべきなのは、書1くらい。あと書10。他の異伝は、本伝をもとにした差違化の結果なので、ざっとみておいて大丈夫!
そんな中で、
今回は、激しく重点チェックの一書1。
本伝の伊奘諾尊、伊奘冉尊の姿とは全然違う二神の姿あり。しかも初登場「天神」。しかもしかも、蛭児などおかしな結果を生んでしまった原因をみんな分かってない珍事態発生。さらにさらにさらに、一書1は実は『古事記』の伝承と同じ内容。こ、これは一体、、、
ポイントは、第四段本伝をしっかりチェックしておくこと。一書1は、本伝の流れに対応する形で差異化展開、なので本伝を基準として捉えればスムースに読み解けます。
今回も非常にユニークな、それでいてめっちゃ重要なテーマが目白押しです!
国生み『日本書紀』巻第一(神代上)第四段 一書1のポイント
第四段一書1は、本伝のチェックが先。
くどいようですが、本伝の流れを押さえてないと読み解けません。是非。
で、以下、ポイント3つ。
①いきなり登場「天神」!二神に下された天神ミッションの行方を追え!
第四段一書1の冒頭、いきなりの初登場「天神」でござる。
コレ、詳細不明ながら、かなり尊い神様たち。神様群。そう、個体ではなく群体な感じ。複数存在。
で、そんな尊い神様群「天神」が、今回、伊奘諾尊、伊奘冉尊の二神に使命を与えます。通称「天神ミッション」!
二神に、地上に行って、その地に相応しい国の実現に向けた準備をしなさい、と。この天神ミッションが一書1の一番のポイント。その行方をチェックしていきましょう。
次!
②天神ミッション、、、とりあえずコンプリート!?無知な二神による若干残念なプロセス。大丈夫か伊奘諾・伊奘冉尊??
天神から与えられたミッションをもとに降下した二神ですが、、、途中までは良かったんだけど後半からいろいろやらかします。。。間違いばっかり。
第四段本伝では、二神の性質が明確に分かれていて、陽神と陰神の違いが際立ってました。陽神である伊奘諾尊は、理をわきまえており陰神の間違いに対しやり直しを指示。物語は陽神主導で展開。一方の、陰神である伊奘冉尊は間違い、過ちを犯す神として描かれてましたね。
ところが!
第四段一書1では、二神は常にセット。ことさら性質を強調する感じ無し。陽神主導な雰囲気も無し。一言でいうと、、、
無知な二神
間違いばかり、、どうしたみんな!?意識レベル下がりすぎ!??
でことで、2つ目のポイント、二神の描かれ方に注目しましょう。
次!
③本伝を差違化!本伝とは違う形で「大八州国」を尊貴な州国としている!
やらかしはあれど最終的に大八州国は誕生。
天神ミッションは、、、二神なりに一応のコンプリート。あくまで「準備」なので。第四段は国の土台をつくる、そして続く第五段では統治者を生む流れ。
で、本伝と同様に、大八州国を尊貴な国として位置付けたい動機あり。これは不変。
一書1では、その根拠を「天神」に集約させている。
天神というめっちゃ尊い神様の指令により、その大いなる関与を経て誕生した大八州国、うわーめっちゃ尊貴やん!と。
ここでは、別のアプローチ、天神指令&関与という「差違化」によって表現されてるってことでチェック。
まとめます。
- いきなり登場「天神」!二神に下された天神ミッションの行方を追え!
- 天神ミッション、、、とりあえずコンプリート!?無知な二神による若干残念なプロセス。大丈夫か伊奘諾・伊奘冉尊??
- 本伝の差違化、本伝とは違う形で「大八州国」を尊貴な州国としている!
以上、3点を踏まえて、本文をチェックです。
国生み『日本書紀』巻第一(神代上)第四段 一書1 本文、現代語訳

ある書はこう伝えている。天神が伊奘諾尊・伊奘冉尊に、「豊かな葦原で永久に瑞々しい稲穂が実る地がある。お前達はそこへ行き、その準備をしなさい。」と言って、天瓊戈を授けた。
そこで、二神は天上の浮橋に立ち、戈を投げて地を求めた。それで青海原をかき回し引き上げると、戈先から垂れ落ちた潮がまとまって島を為した。これを磤馭慮嶋と名付けた。
二神はその島に降り居て、八尋之殿を化し作った。そして天柱を化し立てた。陽神は陰神に「お前の身体は何か形を成しているところがあるか」と問うた。それに対して「私の身体に備わり成って、陰(女)の元というところが一ヶ所あります。」と答えた。陽神が言うには「私の身体に備わり成って、陽(男)の元というところが一ヶ所ある。私の身体の陽の元を、お前の身体の陰の元に合わせようと思う」と。そう言ったのである。
さっそく天柱を巡ろうとして、「お前は左から巡れ。私は右から巡ろう」と約束した。さて、二神が分かれて巡り出会うと、陰神が先に唱えて「ああ、なんとすばらしい少男でしょう」と言った。陽神はこれに和して「ああ、なんとかわいい少女ではないか」と言った。ついに夫婦となり、まず、蛭児を生んだ。そこで葦船に載せて流した。次に、淡洲を産んだ。これもまた子供の数には入れなかった。
そこで、再び帰り天に上り詣でて、こと細かに申し上げた。そのとき天神は太占で占いを行い、教えて言うには「女の言葉が先にあがったからである。もう一度、戻り行きなさい」と。そして、日時を占い定め、二神を降ろした。
そこで、二神は改めてまた柱を巡った。陽神は左から、陰神は右から巡り、出会った時に陽神が先に唱えて「ああ、なんとかわいい少女ではないか」と言った。陰神はその後に和して「ああ、なんとすばらしい少男でしょう」と言った。
このあと、同じ宮に共に住み、子を生んだ。その子を大日本豊秋津洲と名付けた。次に、淡路洲。次に、伊予二名洲。次に、筑紫洲。次に、億歧三子洲。次に、佐渡洲。次に、越洲。次に、吉備子洲。これにより、これを大八洲国と言う。
瑞、ここでは弥図と言う。妍哉、ここでは阿那而恵夜と言う。可愛、ここでは哀と言う。太占、ここでは布刀磨爾と言う。
一書曰。天神謂伊奘諾尊・伊奘冉尊曰、有豊葦原千五百秋瑞穂之地。宜汝往脩之。廼賜天瓊戈。於是、二神立於天上浮橋、投戈求地。因画滄海而引挙之。即戈鋒垂落之潮、結而為嶋。名曰磤馭慮嶋。 二神降居彼嶋、化作八尋之殿。又化竪天柱。陽神問陰神曰、汝身有何成耶。対曰、吾身具成、而有称陰元者一処。陽神曰、吾身亦具成、而有称陽元者一処。思欲以吾身陽元、合汝身之陰元。云爾。 即将巡天柱、約束曰、妹自左巡。吾当右巡。既而分巡相遇。陰神乃先唱曰、妍哉、可愛少男歟。陽神後和之曰、妍哉、可愛少女歟。遂為夫婦、先生蛭児。便載葦船而流之。次生淡洲。此亦不以充児数。 故、還復上詣於天、具奏其状。時、天神以太占而卜合之。乃教曰、婦人之辞、其已先揚乎。宜更還去。乃卜定時日、而降之。 故、二神改復巡柱。陽神自左、陰神自右。既遇之時、陽神先唱曰、妍哉、可愛少女歟。陰神後和之曰、妍哉、可愛少男歟。 然後、同宮共住、而生児。号大日本豊秋津洲。次淡路洲。次伊予二名洲。次筑紫洲。次億岐三子洲。次佐度洲。次越洲。次吉備子洲。由此、謂之大八洲国矣。瑞、此云弥図。妍哉、此云阿那而恵夜。可愛、此云哀。太占、此云布刀磨爾。 (『日本書紀』巻第一(神代上)第四段〔一書1〕より)
国生み『日本書紀』巻第一(神代上)第四段 一書1 解説
第四段一書1は、本伝の流れに対応する形で展開。本伝と比較しながら読むと、その違いがめっちゃ面白い。
で、まとめてみた
| 第四段 本伝 | 第四段 一書1 |
| - | 天神指令+矛下賜 |
| 天浮橋に立ち協議、矛を指し下ろし国を探る、滄溟を獲る | 天浮橋に立ち矛を投し、地を求める |
| 矛の鋒から滴瀝る潮が凝りて島を成す。磤馭慮島と名付ける | 矛の鋒から垂り落ちる潮が磤馭慮島に為る |
| 二神が降居、夫婦と為り洲国を産生もうとする | 二神が降居 |
| 磤馭慮島を国中柱とする | 八尋之殿を化作、天柱を化堅 |
| - | 身体問答 |
| 左旋右旋 | 左旋右旋(間違い) |
| 先唱後和(間違い) | 先唱後和(間違い) |
| 陽神悦ばず、やり直し指示、陽神主導 | 夫婦となり蛭児、淡洲を生む 蛭児は葦船で流す、淡洲は児の数に入れず |
| - | 天に上り詣で、天神に奏上 |
| - | 天神、太占し教示、日時占い再降下指令 |
| 左旋右旋 | 左旋右旋 |
| 先唱後和 | 先唱後和 |
| 身体問答 | - |
| 交合し夫婦と為る | 宮を同じくして共に住む |
| 淡路洲を胞となすが快ばず | - |
| 大八州国を生む | 大八洲国を生む |
| ポイント ・天神無し、二神の協議による国生み ・矛で探り獲たのは国 ・磤馭慮島を、国中柱とする ・間違い1回。先唱後和のみ ・陽神主導、男女性差強調 ・淡路洲は胞として使用するのみ |
ポイント ・天神の指令、関わりによる国生み ・矛で探し求めたのは地 ・磤馭慮島で、八尋之殿を化作、天柱を化堅 ・間違い2回。天神の教示により修正 ・二神無知、男女セット ・蛭児・淡洲を生むが、流す・子への不算入 |
これ、、、分かりやすいんじゃない???
最終ゴールは大八洲国の尊貴化、神聖化。これは不変。で、そのための結婚=儀礼=厳粛な手続き・ルールに則る、これも不変。しかし、ココ一書1では、そこに天神指令&関与&教示を入れてきたってこと。
これにより、別の観点からも大八洲国の尊貴化、神聖化が図られるようになってる。なんせあの天神様指令ですから!
第四段一書1は、前半後半の二段構成。
ポイントは、過ちのビフォーアフター。
過ちとは、陽神主導の原則を逸脱すること。その目印は、本文中の「云爾」。ここに断層あり。
- 「云爾」以前、天神ミッション受託、結婚準備。
- 「云爾」以後、間違いまくり、、、どうした?何があった??
過ちを犯す前、犯す後、そんな感じで整理して読み解きましょう。

前半解説 「云爾」以前

後半解説 「云爾」以後
- さっそく天柱を巡ろうとして、「お前は左から巡れ。私は右から巡ろう」と約束した。さて、二神が分かれて巡り出会うと、陰神が先に唱えて「ああ、なんとすばらしい少男でしょう」と言った。陽神はこれに和して「ああ、なんとかわいい少女ではないか」と言った。
- 即将巡天柱、約束曰、妹自左巡。吾当右巡。既而分巡相遇。陰神乃先唱曰、妍哉、可愛少男歟。陽神後和之曰、妍哉、可愛少女歟。
→後半は無知な二神の姿が際立ってきます。
ここでは2つミステイク。
1つ目。伊奘諾氏が「お前は左から巡れ。私は右から巡ろう(原文:妹自左巡。吾当右巡)」だと?オマ、、何を言ってるんだ??オマは左からだろう??
2つ目。続く「先唱後和」も、「陰神が先に唱えて(原文:陰神乃先唱曰)」、「陽神はこれに和して(原文:陽神後和之曰)」る。本伝同様、間違う伊奘冉は仕方ないとしても、伊奘諾氏!一緒になって和してどうする???
本来であれば、
- 陽神が左旋、陰神が右旋
- 陽神が先唱、陰神が後和
だし、それらを陽神たる伊奘諾氏が主導しないといけないんす。本伝の伊奘諾氏は分かってたのに、、一書になると別人、いや別神のようだ、、、過誤を犯しても(原理原則を違えても)、その自覚を全くもってない、、、ほんと、何があった???
なんですが、、、
でもね、、、
この間違いがあるからこそ、分かることがある。伝えられることがあるんです。掟を破るとどうなるか?それは、掟を破ってみないと本当のところは分からない。
本伝の伊奘諾尊は陽神として頼もしい。陰神の間違いを即座に指摘、やり直しを主導。ところが、これだけだとイマイチ分かりにくい。なんか知らんけどオコぷん&やり直しを命じる神、プライド高くてとっつきにくいかも、、、なんて、伊奘諾尊の言動の真意、本当に伝えたいことが伝わりづらくなってしまう。
それに対して、一書1。
ここまであからさまに間違ってもらえると非常に分かりやすい。しかも、その後の結果までついてくることで、間違えると大変なことになるんだ、、、というのが明確です。
むしろ、「間違い+結果(代償)」のセットは必須の展開、とも言えて。間違いがあるから学びがある。深く伝えられる。
物語を通じて、物語の展開だけしか使えないなかで、確かに、本伝だけでは十分に伝えきれない。少なくとも、「本来はこうあるべき」+「間違うとこうなるよ」という2本の物語がないとトータルで伝えられない。
となると、必然的に、現状の『日本書紀』のように、併載スタイルが答えになってくる。きっと日本神話編纂チームも夜通しこんな議論をしてたんだと思うんです。一本に絞るべきか、はたまた併載良しとするか、、、メリットデメリット並べて喧々諤々。そこには日本のスゴさや神世界の奥ゆかしさをどう効果的に伝えればいいか、対外的にも主張できる日本という国の立ち上がりをどう伝えるべきか、、アツい創意工夫の議論があったのではないか、、。私たちが今、学ぶべきはこの情熱であり、創意工夫の智恵だと思います。って、すみません話がズレました。
コチラもチェック
次!
- ついに夫婦となり、まず、蛭児を生んだ。そこで葦船に載せて流した。次に、淡洲を産んだ。これもまた子供の数には入れなかった。
- 遂為夫婦、先生蛭児。便載葦船而流之。次生淡洲。此亦不以充児数。
→原理を違えることで生まれた蛭児、淡洲の処遇に注目。
蛭児は、蛭(ひる)のように手足の萎えた子。ココでは、「不祥の子」として位置付けられてます。
まず、背景理解として、第四段本伝で伝える、先唱後和の間違い部分を再確認。
- その時、陰神が先に唱え、「ああ嬉しい、いい少男に会ったことよ。」と言った。陽神はそれを悦ばず、「私が男だ。理の上ではまず私から唱えるべきなのだ。どうして女が理に反して先に言葉を発したのだ。事はすでに不吉になってしまった。改めて巡るのがよい。」と言った。
- 時、陰神先唱曰、憙哉、遇可美少男焉。陽神不悦、曰、吾是男子。理当先唱。如何婦人反先言乎。事既不祥。宜以改旋。(引用:『日本書紀』巻一(神代上)第四段〔本伝〕より)
と言うことでした。ポイントは、「事はすでに不吉になってしまった(原文:事既不祥)」のところ。
道理上は「陽主導」であるべきで、先に唱えるべき。なんだけど、陰神が先に声を上げた。これは道理を違えることであり、不祥=不吉だと。
本伝では、この後、陽主導でやり直すのですが、ココ一書1では差異化され、左旋右旋も間違えるわ先唱後和も間違えるわ、、、道理を違えてしまった。だから「不祥の子」として蛭(ひる)のように手足の萎えた子になってしまう訳です。神話的にそういうロジックが組まれてるということで。。
で、「葦船に載せて流した。(原文:載葦船而流之。)」とあります。
葦船は、葦を編んで造った船。葦は邪気を払うという思想があり、葦船で蛭子の邪気を流し捨てる、、、的な意味あいとして説明されるのが多いですが、ココではもう少し深く解釈。
そもそも、日本神話的には、「不祥」の結果というのは「穢悪」な存在であり、「濯除」など水による除去を必要とする。そんな考え方があります。
用例を。第五段一書10では、黄泉国から戻ってきた伊奘諾尊が禊祓をするのですが、以下のように伝えてます。
- ただし、伊奘諾尊は自ら泉国を見てしまった。これはまったく良くないことであった。それで、その穢れを濯ぎ除こうと思った。
- 但親見 泉国 。此既不祥。故欲 濯除 其穢悪 。(引用:『日本書紀』巻一(神代上)第五段〔一書10〕より)
不祥=穢れてる、だから水で流す、除去する。
そういう概念があるからこそ、「葦船に載せて流した」と流す行為になる、そこには、水による穢れの除去、祓いの意味が込められてるってこと。しっかりチェック。
ちなみに、、、海に遺棄された蛭児ですが、例えば兵庫県の西宮神社では、蛭児はその後、西宮に漂着し、「夷三郎殿」と呼ばれ大事に育てられた、といった伝承あり。流されたものの、今では日本に約3500社ある、えびす総本社のご祭神として人々の崇敬を集めています。これはこれで良いお話かも。それはさておき、神話の話。
それ以上に重要なのが、
「流す」とか「子への不算入」といった対応の意味。
コレはこれで、神代における社会の未熟さということで解釈。神様だって社会を構成します。
天地開闢から国生みの時代はまだ色んなことが未成熟だった。だからこそ、二神は流したり認知しなかったりする。現代の感覚からすると違和感があるのは当然で。
社会の成熟度合いは、「個別的に長期生存が不可能な個体(弱者)」を生き延びさせる考え方や仕組みの出来具合に比例します。どれだけの個体が生き延びられるか、どれだけの「弱者」を生かすことが出来るかは、その社会の持つ力に比例する訳です。
神様の織りなす世界も、社会として機能してくるのは岩戸神話あたりから。それまでは、まだまだ未成熟な感じを引きずってたんす、って私は何様でしょうか??
蛭児や淡洲の「流す」とか「子への不算入」といった事、それ自体の良し悪しを議論するのは稚拙です。それよりも社会の成熟度合いといった観点から考えてみると深みがでてくると思います。
で、二神としては、生み損ないの原因が分からないままなので、命を下した天神を頼るほかない。。。てことで天上へ。天神ホウレンソウ(報告・連絡・相談)を実践だ!これはこれで仕事の基本??
次!
- そこで、再び帰り天に上り詣でて、こと細かに申し上げた。そのとき天神は太占で占いを行い、教えて言うには「女の言葉が先にあがったからである。もう一度、戻り行きなさい」と。そして、日時を占い定め、二神を降ろした。
- 故、還復上詣於天、具奏其状。時、天神以太占而卜合之。乃教曰、婦人之辞、其已先揚乎。宜更還去。乃卜定時日、而降之。
→天に上る二神。おそらく天柱を使って。
で、事細かく報告して、天神が対応策を教えてくれるかと思いきや、「天神は太占で占いを行い」と謎対応、、、天神さん分からんのかい!???
ポイント2つ。1つ目は、
①天神の太占は、最終的には大八洲国の尊貴化、神聖化につなげるための仕掛け
本伝は、もともと尊貴な伊奘諾尊・伊奘冉尊によって大八洲国が生まれたと。やっぱすごいよ大八洲国!という論法でした。
一書1では、ここからさらに、二神より尊貴な天神を登場させ、天神ミッションという形式、関わりによって大八洲国をさらに尊貴化しようとしてる訳です。
で、、この占いエピソードは、これをさらにさらに格上げしようとするためのもの。
つまり、二神より尊貴な天神、それよりさらに上位の宇宙的存在?があるんだと。このメッセージを卜占によって受信したんだと。それによって誕生したのが大八洲国!!!ダブルで尊いんだと。二神入れたらトリプル尊いんだ。という話。
より尊貴に、より高く、、、
この上方向へ一段ずつ上げていく指向性は、『古事記』の造化三神、別天神といった神様カテゴリの設定と共通するものがあります。
より尊貴に、より高く、、、なればなるほど説明は無くなっていく。よく分からない雰囲気。良くいえば、奥ゆかしい存在になっていく。まさに、「なにごとの おはしますかは 知らねども かたじけなさに 涙こぼるる (作:西行)」の境地。よー分からん、それがなんかスゴいんす。
で、占いの結果、「女の言葉が先にあがったからである(原文:婦人之辞、其已先揚乎)」とのことで、先唱後和の順序に問題があったことが判明。再降下を命じる流れに。
さらに!「日時を占い定め(原文:卜定時日而降之)」と、二神の降る日時までも天神は卜してます。またもや宇宙メッセージ。。。
コレ、後に神功皇后が新羅討伐を前に、「戦」に出陣するにあたり、事前に占いで吉日を選び、その吉日に出陣した内容に通じます(「爰卜吉日而臨発有日」『日本書紀』摂政前紀、仲哀天皇九年九月条より)。
2つ目は、
②天神の太占=天神さえ服従する「超絶的な働き=神意」を知るための儀式
「太占」については、『古事記』の一説を参照するのが例。天照大御神が天岩屋に隠れた際に行った神事のなかで
天香山の真男鹿の肩を内抜きに抜きて、天香山の天のははかを取りて卜合ひまかなはしむ(『古事記』より)
とあり、要は、鹿の骨を使って占いをすることを伝えてます。
これ、どうやるかというと、天香山の「ははかの木」の枝を採ってきて、先っちょを焼きます。オレンジ色に焼けた「ははかの木」の枝の先っちょを鹿の骨にぎゅーっと押しつけます。これを何度か繰り返すと、ポクってヒビが入ります。このヒビのでき方によって吉凶を占うという訳です。この割れる「ポクっ」という音をもとに「卜」という漢字ができてたりします。
占いというと、亀の甲羅のイメージが強いかと思いますが、神話世界では鹿なんすね。しかも、コレ、現代の大嘗祭関連の儀式でも行われているという、、、スゴ
二神の報告に際して天神の行った太占も、この卜占に通じる訳で。実際に天神がやってるところをイメージ。ポクって。
天神さえ分からないことがある、それは占いという儀式を通じてでないと分からない。でも絶対的に働いている法則であり、原理である。これは、言い方を変えると、天神さえ服従する超絶的な働きがある、ということでもあって。占いによって判明する神意を、そういう形で描いてるんですね。
この、天神を絶対視しない、あるいは、神を絶対者としない思想は、多神教的思想、またはアニミズム(自然界のそれぞれに固有の霊が宿るという信仰)に根ざす思惟とも言えて、すでにココに「兆し」として表現されてる!と言えます。
それにしても、、天神が占いをする、、、何度聞いても、スゴイ違和感。。。天神って何なんでしょうか?
次!
- そこで、二神は改めてまた柱を巡った。陽神は左から、陰神は右から巡り、出会った時に陽神が先に唱えて「ああ、なんとかわいい少女ではないか」と言った。陰神はその後に和して「ああ、なんとすばらしい少男でしょう」と言った。
- 故、二神改復巡柱。陽神自左、陰神自右。既遇之時、陽神先唱曰、妍哉、可愛少女歟。陰神後和之曰、妍哉、可愛少男歟。
→今度はうまく行った、、、
次!
- このあと、同じ宮に共に住み、子を生んだ。その子を大日本豊秋津洲と名付けた。次に、淡路洲。次に、伊予二名洲。次に、筑紫洲。次に、億歧三子洲。次に、佐渡洲。次に、越洲。次に、吉備子洲。これにより、これを大八洲国と言う。
- 然後、同宮共住、而生児。号大日本豊秋津洲。次淡路洲。次伊予二名洲。次筑紫洲。次億岐三子洲。次佐度洲。次越洲。次吉備子洲。由此、謂之大八洲国矣。
→同じ宮に共に住んで、次々に子を産んでいく。。
ポイント1つ。
①大八洲国の生み方=左旋右旋を踏襲、基本的に左回りに生んでいく
第四段本伝との違いを一覧でまとめてみます。
| 第四段本伝 | 第四段一書1 | |
| 1 | 大日本豊秋津洲(本州) | 大日本豊秋津洲(本州) |
| 2 | 伊予二名洲(四国) | 淡路洲(淡路島) |
| 3 | 筑紫洲(九州) | 伊予二名洲(四国) |
| 4 | 億歧洲(隠岐島) | 筑紫洲(九州) |
| 5 | 佐渡洲(佐渡) | 億歧三子洲(隠岐島) |
| 6 | 越洲(北陸道) | 佐渡洲(佐渡) |
| 7 | 大洲(周防国大島(山口県屋代島) | 越洲(北陸道) |
| 8 | 吉備子洲(備前児島半島(岡山県) | 吉備子洲(備前児島半島(岡山県) |
本伝の大洲(周防国大島(山口県屋代島)が抜けて、淡路洲(淡路島)がランクイン。
第四段本伝同様、二神の左旋右旋を踏襲、陽神の左旋を引き継いで、大きくは左回りに生んでいってます。
↓こちら、本伝より。ご参考に。

最後に、
冒頭の天神ミッション「豊かな葦原で永久に瑞々しい稲穂が実る地がある。お前達はそこへ行き、その準備をしなさい」。この重みを改めて噛みしめたい。
その上で、、まとめとして2点。
①第四段は、国をめぐるハードの整備とソフトの予定
第四段の〔本伝〕と異伝たる〔一書〕を通じて、基本は、国としての土台、ハードが整備されますが、それだけでなく、ココ〔一書1〕ではソフト面も予定されました。
〔本伝〕では、国のハード面重視。伊奘諾・伊奘冉尊を主体とし、「どうして国がないだろうか(きっと国があるはずだ)」と予祝し大八洲国を産む。ハードとしての国土形成。
で、〔一書1〕では、国のソフト面重視。天神を主体とし、「豊葦原千五百秋瑞穂之地」と予祝し大八洲国を生む。これは、本伝でハードたる国土形成を前提として、その中身の充実を伝えてる訳です。そういう役割分担。
本伝と異伝で「1伝承1メッセージ」のルールをもとに、ハード・ソフト両方から国の整いを伝えてるってことでチェック。
2つ目。
②天神ミッションは第五段の主者生みや第九段の天孫降臨へ向けた「わたり」
1つ目は、第五段へつながる流れがポイント。
- 第四段は、大八洲国の誕生という、いわば「国の土台づくり」がテーマ。ステージ用意。
- 続く第五段では、土台の主たる「主者」を生む神話へつながっていく。これが神生み。
第四段がステージ用意、第五段でステージの主を用意しようとする。この継起的な展開、流れのテーマに「豊葦原千五百秋瑞穂之地」があり、「わたり」として機能してる。
大きな神話展開、流れをチェック。
2つ目は、天神ミッションは、天孫降臨へむけた「わたり」として機能する、ってこと。
実は、第九段一書2で、天照大神が瓊瓊杵尊に神勅をくだすのですが、その神勅を支える根拠になっていく。具体的には、
- 第四段一書1で、天神が下した命
- 第九段一書2で、天照大神が下す神勅
が構造的に同じなんです。分かりやすく原文で比較してみます。
第四段一書1で、天神が下した命
- (A)天神謂 伊奘諾尊・伊奘冉尊 曰 「(B)有 豊葦原千五百秋瑞穂之地。(C)宜 汝往脩之。」(D)廼賜 天瓊戈
第九段で天照大神が下す神勅
- 天照大神 乃(D)賜 天津彦彦火瓊瓊杵尊、八坂瓊曲玉及八咫鏡・草薙剣、三種宝物。(中略)(A)因勅 皇孫 曰「(B)葦原千五百秋之瑞穂国、是 吾子孫 可王之地也。(C) 宜 爾皇孫就而治焉
上記、ABCDの構造をもとに整理すると以下
| 第四段 一書1 | 第九段 一書1 | |
| (A)誰が 誰に | 天神 謂 伊奘諾尊・伊奘冉尊 | (天照大神)因勅 皇孫 |
| (B) 対象の地 | 有 豊葦原千五百秋瑞穂之地。 | 葦原千五百秋之瑞穂国、是 吾子孫 可王之地也。 |
| (C)どうする | 宜 汝往脩之 | 宜 爾皇孫 就而治焉 |
| (D)与えたもの | 廼賜 天瓊戈 | 賜 天津彦彦火瓊瓊杵尊、八坂瓊曲玉及八咫鏡・草薙剣、三種宝物 |
キレイに対応させてあるのが分かりますよね。
第四段一書1は、後の第九段一書1の前振り。具体的には、第九段で天照が孫の瓊瓊杵尊を地上に降下させるときに下す神勅の「わたり」として機能してるってこと、しっかりチェック。
天照が下す「神勅」を支える根拠として、こうした伏線を張ってるところもスゴイ。つながりをつけてある、大きな仕掛けが組まれてるんです。
全体として、非常に練られた、緻密に設計、構築された神話世界が展開。一つひとつに当時の最先端知識をもとに創意工夫を盛り込んでつくられてる。多彩で豊かな日本神話は古代日本人の智恵の結晶なんだと思います。
国生み まとめ
『日本書紀』巻第一(神代上)第四段 一書第1
第四段一書第1の解説をお届けしてきましたが、いかがでしたでしょうか?
第四段は、新時代到来の巻。
その新しさは、男女の営みであるというところ。
第三段までの、道の働きによる神の誕生から、第四段からは、男女の営みによる国や神の誕生へ。男女の営みだからこそ、そこには責任が伴うわけで、第四段は州国というステージを用意、第五段はステージの主たる主者を用意していく。これら全て新時代ならではの展開であります。
ポイントまとめは以下。
- 初登場、天神。天神による天神のための一書第1
- 豊葦原千五百秋瑞穂之地=予祝メッセージてんこ盛り&天神ギャランティー
- 豊葦原千五百秋瑞穂之地をつくるための準備「脩」
- ミッション+グッズ=重要指令発令時の、神話世界の掟
- まさに神業!化作八尋之殿。又化竪天柱。
- 身体問答=男女の形状の違いを互いに言い合って確かめ合う
- 間違いまくり 左旋右旋が逆、先唱後和も逆。でも、それがイイ
- 原理を違えることで生まれた蛭児、淡洲の処遇=社会の成熟度という観点で解釈
- 天神による占いの意味=より尊貴に、より高く
- 天神の太占=天神さえ服従する「超絶的な働き=神意」を知るための儀式
- 大八洲国の生み方=左旋右旋を踏襲、基本的に左回りに生んでいく
- 第四段一書1の天神ミッションは第九段の天孫降臨へ向けた「わたり」
最終ゴールは大八洲国の尊貴化、神聖化。これは不変。で、そのための結婚=儀礼=厳粛な手続き・ルールに則る、これも不変。
でも、ココ一書1では、そこに天神指令&関与を入れてきたってこと。
本伝をもとにした差違化であると同時に、後段への「わたり」としても機能させている、非常に練られた、緻密に設計、構築された神話世界です。
一つひとつに当時の最先端知識をもとにした創意工夫を盛り込んでつくっている日本神話の世界。多彩で豊かな世界観は古代日本人の智恵の結晶。ぜひ隅々まで堪能いただければと思います。
続きはコチラ↓で!
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
神話を持って旅に出よう!
本エントリに関連するおススメスポットはコチラです!
国産みの伝承地と言えばココ!!
伊奘諾尊・伊奘冉尊の神話にちなむ&祭る神社はコチラ!!
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




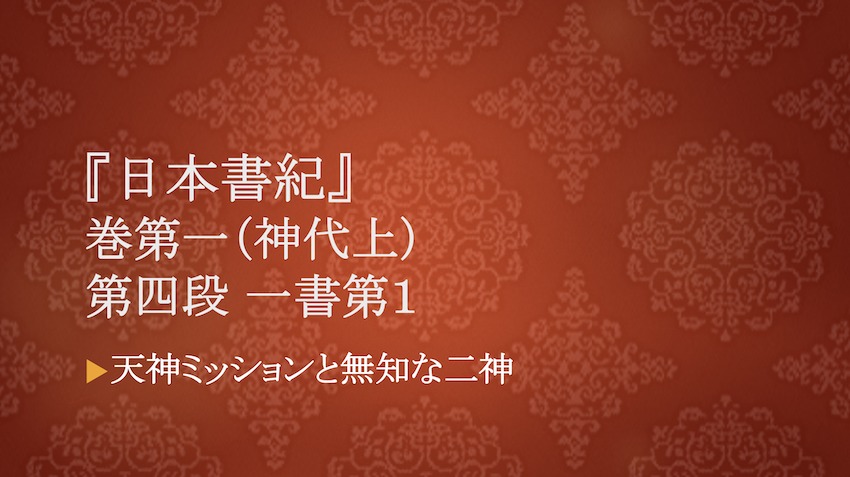

























→天神主語で始まる一書1。
ポイント4つ。1つ目。
①初登場の「天神」は諾冉二神より上位の存在。今後の神話展開を踏まえると、天照大神は同じくらい尊貴な存在。なんなら、天神の役割を天照大神が引き継ぐ
冒頭初登場の「天神」。コレ、さらっと流すの禁止。
本伝と一書の関係でも解説したとおり、一書は本伝の差違化スポット。新しい概念、言葉を導入するのに、めっちゃ便利な場所。コチラ↓で詳しく
新しい概念であり言葉として一書で登場した「天神」。
コレ、「天帝」と同じような言葉の作り方ですが、その実態は不明。第四段は第三段までの展開を引き継ぐので、純男神か、伊奘諾伊奘冉を除く神世七代の神全てか、どちらかを指すと思われます。
まずチェックしたいのは、この天神の位置づけ。ポイント2つ。
天神が伊奘諾伊奘冉に「準備をしなさい」と指令を出してるほか、「天瓊戈を授けた(原文:賜天瓊戈)」とあり、「賜」という漢字が使われてます。これ、上位のお方が下位の者に物を与える時に使われる言葉で。つまり、「天神」は諾冉二神より上位の存在であることが分かります。
さらに、諾冉二神より至高な存在、という位置づけ以上に、神話展開上重要なのが、この天神の国に対する関与が、天照大神に引き継がれていく、ってことなんす。
例を一つご紹介。原文で比較します。
ココ、第四段一書1では、天神が諾冉二神に「準備をしなさい」と指令を下す。
一方、第九段一書1では、天照大神が天稚彦に「(国を)平定せよ」と指令を下す。
簡略して並べます。
てことで、「豊葦原千五百秋瑞穂之地(葦原中国)+往○之」という同じ構造で伝えてますし、前者を後者が引き継ぐ関係になってます。
つまり、
てことで、これってつまり、
天神と天照大神は同じくらい尊貴。神話展開上、天神の役割を天照大神が引き継ぐ
そんな形で構想されてるってことなんす。この至高さとか尊貴さが全ての起点。この前提から一書1は構成されてます。ここ激しく重要なのでしっかりチェック。
そして!
②豊葦原千五百秋瑞穂之地=予祝メッセージてんこ盛り&天神ギャランティー
「豊かな葦原で永久に瑞々しい稲穂が実る地がある。(原文:豊葦原千五百秋瑞穂之地。)」とあります。ポイント2つ。
まず、予祝てんこ盛りについて。
日本の美称である「豊葦原千五百秋瑞穂之地」。とよあしはら の ちいほあき の みずほの地!
まとめると、豊かな葦の茂る原で永遠にくらいの勢いでずーっとみずみずしい稲穂が実るすばらしい地、といった意味。って、まースゴイ。これでもかってくらい予祝感満載。てんこ盛り。
次に、天神ギャランティー。
ポイントは、天神が発した言葉だってこと。
あの天神が言ったんすよ。天神が、豊かな葦の茂る原でずーっとみずみずしい稲穂が実るすばらしい地があるよと言ったんす。コレ、天神ギャランティー。要は、天神のお墨付き。保証付き。
以後、神話のさまざまな展開を経て、実際に「豊葦原千五百秋瑞穂之地」になっていく様子が描かれていく。その意味で、今後の神話展開の起点となる言葉でもあります。
ということで、まとめると「豊葦原千五百秋瑞穂之地」という言葉は予祝メッセージてんこ盛り&天神のお墨付き&今後の神話展開の起点という超重要な意味があるってことでチェック。
そして!
③「豊葦原千五百秋瑞穂之地」をつくるための準備「脩」
「お前達はそこへ行き、その準備をしなさい。(原文:宜汝往脩之。)」とあります。ポイントは「脩」。
「脩」は「おさむ」と読み、「治める、統治する」という訳語が当てられことが多いのですが、実はもっと奥深い重要な言葉。
もともとは祭祀演奏にあたって、鼓など楽器の手入れや練習、または本番に向けた整備の意。
『礼記』月令第六、仲夏之月では「この月は、楽師に命じて、鞀・鞀・鼓・均琴瑟・管・簫を修め、干・戚・戈・羽を執り、竽・笙・篪・簧を調え、鍾・磬・柷・敔を整えさせた。」とあります。これ、大雩の音楽を習うため。「大雩」とは雨乞いの儀式のこと。その祭祀演奏に向けた準備とか整備を楽師たちに命じたと。
この「準備、本番に向けた整備」を意味する「脩」は、実は『日本書紀』第三段の神武紀にも登場。
神武天皇が、岡山の高嶋宮で三年間居留。ここで近畿侵攻の準備をするのですが、ここで「脩舟、蓄兵食」と伝えます。つまり、軍船を整備し食料を蓄えた、ってことで。いよいよ本番、大和での本格的な戦闘が始まるんで、しっかり準備を行った、これが「脩」。
このことから、天神ミッションの本当の意味というのは、
将来「豊葦原千五百秋瑞穂之地」となる場所へ行って、「豊葦原千五百秋瑞穂之地」にしていくための準備作業をせよ、てことになります。ちょっとくどいけど。
よく見かける「治める」「統治する」という訳語にしてしまうと、結局二神は天神ミッションコンプリートならず、、、中途半端でしたね残念です無知ですからね、になってしまうのですが、本来の意味の「準備する、整える」ということであれば、二神は二神なりにコンプリートしたってことになるんです。これは、つづく第五段、天下の主者生みによって一応のケリをつけることになっていきます。コレ、文献学研究の現場。
そして!
④ミッション+グッズ=重要指令発令時の、神話世界の掟
「天瓊戈を授けた(原文:廼賜天瓊戈)」とあります。
実は、神話世界では、何らかの重要指令を下すときは「ミッション+グッズ」のセットがパターン。てか、掟。ここでもそのパターンが使われてます。
他にも例を挙げると、、
といった感じ。
ちなみに、天照ミッションによって下賜された「三種の神器」を引き継いでいるのが天皇で。神話を引き継ぐ天皇陛下。神話が今と繋がってる例でもあり。奥ゆかしい日本ならでは。
とにかく、ここでは、重要指令が出されるときは、ミッション+グッズのセットというのが神様世界の掟。今に繋がる重要テーマを含むことも合わせてチェックです。
次!
→本伝との差異化ポイントは、二神の協議がないこと、国を想定した言表が無いこと。これは、〔一書1〕の二神は、天神によって動かされる存在だから。
他は、ほぼ同じ内容で、ところどころ漢字表記を変換。
ここで特記しておきたいのは「投戈求地」。
本伝では、国を想定した上で「指下而探之」、つまり国を探してたのですが、一書1では「投戈求地」、つまり、地を求めていた。探す対象の違いをチェック。
これ、もちろん天神が諾冉二神に「豊かな葦原で永久に瑞々しい稲穂が実る地がある(原文:有豊葦原千五百秋瑞穂之地)」と指令していたから。それを受けて、「求地」と差異化されてる訳ですね。
そのほか、天浮橋はコチラで!
磤馭慮嶋についてはコチラで詳しく!
次!
→八尋之殿を作った??さらに、天柱を立てただと???
ポイント3つ。まず、1つ目。
①まさに神業??「化作」「化堅」は、二神の意欲ないし念慮のようなものが八尋殿や天柱を現出させたことをいう
「八尋之殿を化し作った。そして天柱を化し立てた。(原文:化作八尋之殿。又化竪天柱)」とあります。
この「化作」「化堅」、「作」は御殿を作るので作、「堅」は柱を立てるので竪(縄文時代の竪穴式住居の「竪」)、という漢字が使われてます。
で、ここでは特に、「化(かす)」という言葉が重要で。
「化(かす)」は、既に登場してましたよね。第一段本伝で、神の誕生=化生という方法。天と地の間に「もの」ができて、この「もの」が化すことで神が生まれる。つまり変化して生まれる、どろどろんと化け成るイメージ。最初は乾の道の単独変化なので男神が誕生。
さらに第三段では、総括の中で、「乾坤之道、相参而化。所以成此男女。」と、つまり、乾坤の道がお互いに参じて化すことで男女神になったんだよと。
これらは、道が化すことで生まれる、という自動詞用法のなかで使用されてました。
それに対して、今回は「化作八尋之殿」「化竪天柱」なので、目的語をともなう他動詞用法。
で、この「化」を他動詞的に使う例は、後段の第五段一書1にもあります。伊奘諾尊が三神(大日孁尊、月弓尊、素戔嗚尊)を生むのですが、それが「化出」。以下、大日孁尊化出の部分だけ抽出。
形式として整理すると、(A)の明確な意欲をもとに、(B)の象徴的な所作により、(C)にその結果が現出する、という形。
つまり、伊奘諾尊の「優れて貴い子を生もうと思う!欲す!!」といった意思というか念慮によって化し出る神があったと。。それが「化出」。どろどろんと現出。
なので、「化作」「化竪」も同様に、二神の意欲ないし念慮のようなものが八尋殿や天柱を出現させた、実体化させたと考えられる訳です。御殿を化し作った、天柱を化し立てた。どろどろんと現出。
まさに、、、神業。
こういうことが可能なのは、二神が「乾坤之道、相参而化。所以成此男女。」という出自をもってるから。「化す」という働きや運動を、自己存在の根源や本質に持っているから、と考えられる訳ですね。深い。。。深すぎるぞ日本神話。。
そして!2つ目。
②八尋之殿をつくったのは、新たに足を踏み入れた地に居住し、結婚し、出産する神様行動特性の一環から
なんで宮を建てた。。。?ってことなんですが、コレ、神様行動特性(神様コンピテンシー、略して神コン)によるもの。題して、「新たに足を踏み入れた地に居住し、結婚し、出産する一連の展開特性」。
他の例としては、
具体的には、
てことで、いずれも、同じ構造を持っているわけです。新たに足を踏み入れた地では、まず宮をつくる。そして住む。コレ、神様特有の行動特性。
今回も同様に、新たに踏み入れた地上で、二神が「同宮共住」しようと「化作」した訳ですね。いいじゃないですか、八尋之殿を現出させて共に住もうとしたわけですよ。新婚のラブホーム。盛り上がって参りました。
そして!3つ目。
③天柱を立てたのは、天上世界へ帰るための手段、経路を確保するためだった
一方の「天柱」。これは宮殿の柱ではありません。あくまで「天柱」。天や天神とのつながりを確保する柱です。
実際、第五段〔本伝〕では、「それで天柱を使って、天上に送り挙げたのである(原文:故、以天柱挙於天上也)」と、日神を天上に挙げる手段として使用してます。
これを考えると「天柱」を現出させたのは、このあと、天神への報告シーンがあるので、自分たちが天上世界へ帰るための手段、経路を確保するためだった、てことになります。そもそも天神指令から始まってますから。報告・連絡・相談は欠かせません!??
次!
→身体問答を左旋右旋の前に行ってる。。この時点で間違え始めてる??
身体問答とは、性別による男女のありかたの違いを、それぞれの形状をたがいに言表することによって確めあうこと。言表とは、言い表すこと。言表し行為に及ぶ。第四段本伝解説でご紹介した神様行動特性(神コン)でしたね。
本伝では左旋右旋のあと、交合直前に行ってましたので、順番が違う、、、って、この辺からです。二神が怪しくなってくるのは。。。御殿を作ってさー夫婦になるぞと、盛り上がってきましたねと、ラブが高まるにつれて男と女はおかしくなっていく、、、??
この最後、本文中の「云爾」。ここに断層があり。「云爾」以後、間違いまくり、、、どうした?しっかりするんだ!