多彩で豊かな日本神話の世界へようこそ!
正史『日本書紀』をもとに、
最新の文献学的学術成果も取り入れながら、どこよりも分かりやすい解説をお届けします。
今回は、
神武東征神話を分かりやすく解説するシリーズ10回目。
テーマは、
宇陀の兄猾と弟猾
八咫烏の道案内と「道臣」の活躍によって、熊野越えを果たした神武一行。奈良県宇陀市の宇賀志に到ります。ここから「中洲(大和平野)」をめざす訳で、以後、先住勢力=敵の制圧を中心に物語が展開。そこで登場するのが「兄猾」「弟猾」ブラザーズ。この両名、宇陀に勢力を張る在地豪族的存在で。
兄猾・弟猾の神話は何を伝えているのか?
そんなロマンを探ることで、「兄猾と弟猾」の意味を考えます。
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
神武紀|宇陀の兄猾と弟猾|弟は聡く帰順したが、兄は謀(はかりごと)を企んだのでさらして斬った件
目次
神武紀|宇陀の兄猾と弟猾 の概要
今回も『日本書紀』巻三「神武紀」をもとにお届け。前回の内容、これまでの経緯はコチラ↓をご確認ください。
試練の「熊野」越えを果たした神武一行。。ようやく、現在の奈良県宇陀市、宇賀志に到ります。
ココ、山から降った里というか野というか、平地とは違う、その手前の位置付け。それでも、自然や荒ぶる神が支配するのではなく、先住民、人間が支配する世界です。
ここから「中洲」(大和平野)をめざす訳で、以後、先住勢力=敵の制圧、そして軍事力と策謀が渦巻く人界ならではの展開になっていきます。
最初のターゲットは「兄猾」と「弟猾」兄弟。この両名、宇陀に勢力を張る在地豪族的存在で。
神武の召し出しに対して、兄の兄猾は反抗し、弟の弟猾は恭順します。
コレ、実は「兄の邪悪・劣弱、弟の善良・優強」という古代兄弟譚の類型によるもの。いつの時代も、兄は何をしでかすかわからない存在で。。弟はそんな兄の言動を見て空気読みながら冷静に対処する感じ。。。汗
彦火火出見は、将軍「道臣」を派遣し征伐。ここで「道臣」が大活躍。
東征神話自体は、天孫である「彦火火出見=神武」を主役として展開。これはこれで当然として、一方で注目すべきは、神武以外の臣下が活躍するところ。
これは、天孫(彦火火出見)以外の、国神あるいは人間にスポットライトが当たるという事でもあります。そういう意味でも大きな転換点として位置付けられます。
神武東征ルートと場所の確認
宇陀周辺の位置関係を整理。まず、敵布陣の図。コレ、後になって(高倉山に登って)分かるのですが、とりあえず、こんな感じだった、てことでチェック。

前回解説で、「菟田の下県にたどり着いた」とあり、現在の宇陀南半分のエリアに到着ってことでした。で、この中の一つの村が菟田の「 穿邑」。現在の宇賀志。想定として、166号線で宇賀志へ入るルート。
今回登場する「兄猾」と「弟猾」ブラザーズが支配していたのは「菟田県」。現在の宇陀盆地一帯であります。
「神策」に従い、東から西へ大和へ攻め込む、太陽を背に戦うためにも、この「菟田県」(宇陀)を攻略する必要があり、そのための前哨戦として今回のシーンが位置づけられます。
神武紀|宇陀の兄猾と弟猾 現代語訳と原文
秋、8月2日に、彦火火出見は、「兄猾」と「弟猾」という者を召し出させた。この二人は菟田県の首領である。
すると、兄の兄猾は姿を見せず、弟の弟猾はすぐにやってきた。
弟猾は軍営の門を拝してこう申し上げた。「私の兄の兄猾が反逆を企てております。天孫(彦火火出見)が今まさにこの地においでになると聞き、すぐさま兵を起こして襲おうとしていたところ、東征軍の威勢をはるかに望み見て、勝ち目のないことを恐れたのです。そこで企てを案じ、兵をひそかに伏せ、仮の新しい宮を建て、その建物の内に「人を圧殺するからくり機」を設け、饗宴に招待すると偽って誘い出し、罠にかけて討とうとしているのです。どうかこの偽りと企てを知り、よくお備えくださるようお願いします。」
彦火火出見はただちに道臣命を遣わし、その反逆の様子を窺わせた。
道臣命は、兄猾には確かに害意を抱いていることを詳しく察知し、激怒して責めなじり「卑しい敵め!うぬが造った宮に、うぬが自分で入ってみろ!」と荒々しい声で言った。さらに剣の柄に手をかけ、弓を強く引きしぼって追い立て、兄猾を建物に入らせた。
兄猾は、天によって罰を受けるのと同じようにどうにも言い訳ができなくなり、ついに自ら中に入りからくり機を踏み、押しつぶされて死んだのである。それから道臣命は兄猾の屍を引きずり出してバラバラに斬った。流れ出る血は踝まで達した。それゆえ、その地を名づけて「菟田血原」という。
弟猾は、大いに酒や肴を取り揃え、饗を催し東征の軍勢をねぎらいもてなした。彦火火出見はその酒肴を兵士達に分け与え、そこで御謡を詠んだ。
菟田の高城に 鴫罠はる 我が待つや 鴫は障らず いすくはし くぢら障り 前妻が 肴 乞はさば たちそばの 実の無けくを こきしひゑね 後妻が 肴 乞はさば いちさかき 実の多けくを こきだひゑね
(菟田の猟場である高城に鴫罠をかけた。獲物がかかるのを待っていると、鴫はかからず、なんと鯨がかかった。先に娶った妻が肴に欲しがったら、立木のソバの実のように肉の少ないところをいっぱいそぎ取ってやれ、新しい妻が肴に欲しがったら、サカキの実のように肉の多いところをいっぱいそぎ取ってやれ。
これを「来目歌」と言う。今、楽府 でこの歌を演奏するときは、手拍子や声の大きさに大小をつける。これは古式が今に残ったものである。
秋八月甲午朔乙未、天皇使徵兄猾及弟猾者。是兩人、菟田縣之魁帥者也。時、兄猾不來、弟猾卽詣至、因拜軍門而告之曰「臣兄々猾之爲逆狀也、聞天孫且到、卽起兵將襲。望見皇師之威、懼不敢敵、乃潛伏其兵、權作新宮而殿內施機、欲因請饗以作難。願知此詐、善爲之備。」
天皇卽遣道臣命、察其逆狀。時道臣命、審知有賊害之心而大怒誥嘖之曰「虜、爾所造屋、爾自居之。」因案劒彎弓、逼令催入。兄猾、獲罪於天、事無所辭、乃自蹈機而壓死、時陳其屍而斬之、流血沒踝、故號其地、曰菟田血原。
已而弟猾大設牛酒、以勞饗皇師焉。天皇以其酒宍、班賜軍卒、乃爲御謠之曰、
于儾能多伽機珥 辭藝和奈陂蘆 和餓末菟夜 辭藝破佐夜羅孺 伊殊區波辭 區旎羅佐夜離 固奈瀰餓 那居波佐麼 多智曾麼能 未廼那鶏句塢 居氣辭被惠禰 宇破奈利餓 那居波佐麼 伊智佐介幾 未廼於朋鶏句塢 居氣儾被惠禰。
是謂來目歌。今樂府奏此歌者、猶有手量大小、及音聲巨細、此古之遺式也。(『日本書紀』巻三 神武紀より一部抜粋)※原文中の「天皇」という言葉は、即位前であるため、生前の名前であり東征の権威付けを狙った名前「彦火火出見」に変換。
▲橿原神宮で公開中の「神武天皇御一代記御絵巻」から。
神武紀|宇陀の兄猾と弟猾 解説
兄と弟の扱われ方、その落差がスゴすぎて草、、、そんなロマンに想いを致しながら、、
以下詳細解説。
まとめ
宇陀の兄猾と弟猾
試練の「熊野」越えを果たした神武一行は、現在の奈良県宇陀市、宇賀志に到ります。
宇陀は、山から降った里というか野というか、平地とは違う、その手前の位置付け。それでも、自然や荒ぶる神が支配するのではなく、先住民、人間が支配する世界。
東征軍が目指す大和へ進軍するためには、宇陀の地を攻略する必要がありました。これは、東から西へ攻め込む、つまり太陽を背に戦い日神の力を受けて勝ち進める為。孔舎衛坂敗戦時にめぐらせた「神策」が根拠。
人が住む「人界」に入っていった先には、多くの在地豪族が勢力を張っている訳で。このシーン以後、戦闘に次ぐ戦闘。軍勢や策略がモノをいう人界ならではの展開になっていきます。
そんな展開だからこそ、彦火火出見自ら手を汚す事はせず、臣下の活躍を通じて敵を殺し制圧を進めていく。この結果、臣下の活躍が目を引くことになりますし、それほどの臣下を率いている彦火火出見の価値が上がっていく仕掛けになっています。
一方で、臣下=人間の活躍は、神代の流れを引き継いでいた神話に「神代から人代への転換」という新たな要素を加えていく。この転換は突然行われるのではなく、「必要性をもった経緯」から段階的に行われていく訳です。
最終的に橿原即位に至って、本格的な「人代」がスタートするときもスムースに移行されるようになっている。壮大な神話的仕掛けが入ってるってことでチェック。
ポイントをまとめると3つ。
- 本シーンは、これ以降、大和入りへ向けた「在地豪族の制圧」が主要テーマになる転換点である事。
- 制圧にあたっては、臣下が活躍。これは、「神代から人代への大転換」を象徴している事。
- 彦火火出見は、先の孔舎衛坂敗戦から学び、まずは使者を立てて恭順の意向を確認している事。
特に③。コレ、まさに彦火火出見の成長であって、、敗戦や兄の喪失などの試練を乗り越えてきたからこそ、深みとリアリティをもって読み取ることができる訳です。神武東征神話、練りに練られた素晴らしい内容になってる。日本書紀編纂チームの知恵、創意工夫の度合いがスゴくて震えが止まりません。。。
続きはこちらから!まずは南を制圧だ!
神武東征神話のまとめ、目次はコチラ!
『古事記』版はコチラで!!
神話を持って旅に出よう!
神武東征神話のもう一つの楽しみ方、それが伝承地を巡る旅です。以下いくつかご紹介!
をどの血原伝承地※古事記が伝えるスポット
● 菟田の高城
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
こちらの記事もどうぞ。オススメ関連エントリー
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




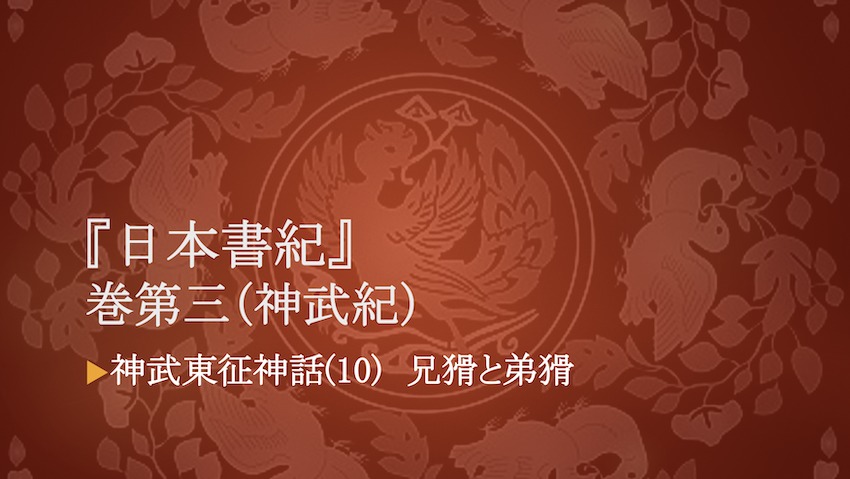


























→「八月甲午朔乙未」は、8月の「甲午が朔にあたる乙未」なので2日。
目指す大和へ進軍するためには、「菟田県」(宇陀)を攻略する必要がありました。これは、東から西へ攻め込む、つまり太陽を背に戦い、日神の威を負って勝ち進める為。孔舎衛坂敗戦時にめぐらせた「神策」が根拠。
宇陀進軍に向けた前哨戦、それが今回の「宇賀志攻略」であります。
「「兄猾」と「弟猾」という者を召し出させた。この二人は菟田県の首領である。」とあります。原文「魁帥」は、敵の首領を貶めて言う言葉。「菟田県」(宇陀)の首領、つまり、この地を支配していたのが「兄猾」「弟猾」ブラザーズってこと。
宇陀は、東征神話的には、山から野への転換点。
これまでの、自然(荒ぶる神)を相手にした戦いから、人を相手にした戦いへの転換。以後、「在地豪族の制圧」が主要テーマ。
人が相手ですから、これ以降は、軍事力の他、場合によっては「策略」がモノを言う人界ならではの展開に。ハメてイテこます。。。コレ、結構重要なポイント。
最初のターゲットが「兄猾」と「弟猾」。
神武はこの二人を「召し出し」ます(原文「徵」)。コレ、使者を立てて恭順の意向を確認したって事。実は、今までに無い行動、初めて出てくる言葉です。
このシーン以降、主要な敵キャラには、使者を立てて意向を確認する作業が入っていきます。これは、先の「孔舎衛坂の戦い」とは全く異なるやり方。
孔舎衛坂では、
右も左もわからずとにかく突っ込んでいった感じで、戦術として非常に稚拙でした。情報不足と己への過信・驕りもあって、見事に敗戦を喫した訳です。
それに対して本シーンでは、まず使者を立てて意向確認、それでも帰順しないのであれば徹底的に叩く、というやり方。ここに、彦火火出見の成長を見ることができます。(って私は何様でしょうか?)
敵の情報を把握せず突っ込んでいくやり方から、使者を立て相手の意向を確認した上で対応を決めるやり方へ。
大きな戦術の転換であり、東征神話全体としては彦火火出見の成長としてチェックです。
次!
すると、兄の兄猾は姿を見せず、弟の弟猾はすぐにやってきた。弟猾は軍営の門を拝してこう申し上げた。「私の兄の兄猾が反逆を企てております。天孫(彦火火出見)が今まさにこの地においでになると聞き、すぐさま兵を起こして襲おうとしていたところ、東征軍の威勢をはるかに望み見て、勝ち目のないことを恐れたのです。そこで企てを案じ、兵をひそかに伏せ、仮の新しい宮を建て、その建物の内に「人を圧殺するからくり機」を設け、饗宴に招待すると偽って誘い出し、罠にかけて討とうとしているのです。どうかこの偽りと企てを知り、よくお備えくださるようお願いします。」
→神武の召し出しに対して、兄の兄猾は反抗し、弟の弟猾は恭順。なんなら兄の企てを密告。。
コレ、実は「兄の邪悪・劣弱、弟の善良・優強」という古代兄弟譚の類型によるもの。
いつの時代も、兄は何をするか分からない存在で。。弟はそんな兄の言動を見て空気読みながら冷静に対処する。。。汗
「弟猾は軍営の門を拝して申し上げた。」とあり、コレ完全に臣下の礼です。
「天孫が今まさにこの地においでになると聞き、」とあり、神武が「天孫」であること、なんなら「天神子」であることも分かってた?。地に属する側から神武を天に由来する存在として位置づけてます。
だからこそ、空気読める人は恭順に切り替える。読めない人は我を通す、結果自滅する、、という大きな枠組み。
そして、兄猾の「逆狀」(謀)を全て、洗いざらい、タレ込む。。。
「兵を起こして襲おうとしていたところ、東征軍の威勢をはるかに望み見て、勝ち目のないことを恐れたのです。そこで企てを案じ、」とあり、元々は戦闘するつもりでいたようですが、謀略に変更したようです。ま、コレも神武の東征軍をティーアップする、軍勢やスゴさを伝える表現としてチェック。
「逆狀」(謀)の中身は、陽動作戦。新しい宮を造り、その建物の中に圧殺機を仕掛ける。その上で、神武一行を饗宴に誘い、何も知らずに入ってきた彦火火出見を圧殺してやろう、、って、なんて恐ろしい。。。
次!
彦火火出見はただちに道臣命を遣わし、その反逆の様子を窺わせた。道臣命は、兄猾には確かに害意を抱いていることを詳しく察知し、激怒して責めなじり「卑しい敵め!うぬが造った宮に、うぬが自分で入ってみろ!」と荒々しい声で言った。さらに剣の柄に手をかけ、弓を強く引きしぼって追い立て、兄猾を建物に入らせた。
→兄猾の「逆狀」を知った彦火火出見は、道臣命を派遣し対応にあたらせる。
改めて、ココは、神がすむ山ではなく、人が住む「人界」。軍勢や策略がモノをいう世界。だからこそ、彦火火出見は自ら手を汚す事はせず、臣下の活躍を通じて敵を殺し制圧を進めていく。
この結果、臣下の活躍が目を引くことになりますし、結果的に、それほどの臣下を率いている彦火火出見の価値が上がっていく仕掛けになっています。
「激怒して責めなじり」「荒々しい声で言った」とあり、非常に激しい表現が使われてます。原文「大怒誥嘖之」。大いに怒る、「誥」は上から下に申し渡す、「嘖」は怒り責める。これでもかと怒り表現連発です。
さらに、原文「案劒彎弓」。「案剣」は「撫剣」と同じ怒りの表現。コレ、五瀬命が亡くなる前にでてきた表現でした。「彎弓」は弓を引いて構えること。いずれも、道臣将軍の、力強さ、豪傑さが伝わってきますよね。
次!
→自ら仕掛けた「からくり機」で圧死する兄猾、、、さらに死体を引きずり出してバラバラに切るって、、、Σ(゚Д゚)
「天によって罰を受けるのと同じように」とあります。コレ、『論語』八佾から「罪を天に獲れば禱るところ無きなり」を踏まえた表現。簡単にいうと、罪を天に対して犯せば、いくら祈っても許されない、といった意味。
いきなり、「天」が登場してるように見えますが、実はコレも周到に設計された狙いがあるから。ここでいう「天」は、天神の血統をひく存在としての神武を意味するように使われてるんです。神武への反抗、反逆は、天に逆らうのと同じくらい重い罪であると、、スゴ(゚Д゚)
次!
→兄の悲惨な死に対して、弟のうまくやってる感がスゴイ、、、兄からずっと虐げられてたのでしょうか、、、
宴を催して神武一行をねぎらう弟猾。。原文「牛酒」とあり、牛いたの??? ま、それくらいのご馳走だったということで。
ポイントは、神武の歌った「御謡」。このあと、ちょいちょい登場します。
菟田の高城に 鴫罠はる 我が待つや 鴫は障らず いすくはし くぢら障り 前妻が 肴 乞はさば たちそばの 実の無けくを こきしひゑね 後妻が 肴 乞はさば いちさかき 実の多けくを こきだひゑね
(菟田の猟場である高城に鴫罠をかけた。獲物がかかるのを待っていると、鴫はかからず、なんと鯨がかかった。先に娶った妻が肴に欲しがったら、立木のソバの実のように肉の少ないところをいっぱいそぎ取ってやれ、新しい妻が肴に欲しがったら、サカキの実のように肉の多いところをいっぱいそぎ取ってやれ。
→この歌の解釈には2通りあります。
手がかりは歌の直前にある2つのイベント。
これまでの通説は、①に即しての解釈で、「くぢら」を兄猾とみなす内容。なんですが、、兄猾をもちあげすぎです。また、それだと「わが待つや」と神武軍が兄猾を罠でとらえようとしていた歌になるのですが、実際はそうではない(罠をしかけたのは兄猾であり、自分で死んだ)ので不成立。
どっちかというと②に即した解釈が〇。弟猾が全く思いもよらない大御馳走で慰労したことをたたえる歌とみなす内容で。神武は、その弟猾のもてなしを「くぢらが罠にかかったようなものだ」とほめあげて応じて見せた訳です。同時に、軍卒と共にしようと気遣いを示すもの。総じて、戦いの勝利を軍をあげて祝い楽しむ歌、そして神武の偉大さを、高らかに大笑いを交えて歌い上げてる内容なんです。
「前妻」「後妻」という言葉が登場してますが、コレ、特に誰というのは想定してなくて。勝利を祝い、ご馳走に浮かれたざれ歌、その場をもりあげたバカ騒ぎする「はやし歌」なので、意味的には、後妻の若い方にはいっぱいに、前妻の古女房には空っぽでもくれてやればいい的な、軍卒の労苦を慰め楽しませようとした歌として整理。コレ、古代の価値観なので悪しからず。。
次!
→「来目歌」とは、来目・久米部(熊野から大和へ入る際に、道臣が率いてきた戦士集団)に天皇が謳いかけた歌にちなむ名称。
「樂府」とは、宮廷の音楽・歌謡を司る役所の名。持統天皇元年正月朔条に「楽宮」の例があります。
「これは古式が今に残ったものである。」とありますが、これは、東征神話で語られたことが今に伝わってると示す、物語=歴史の真実性を確証するための表現。ちょいちょいこういうの差し込んできます。