多彩で豊かな日本神話の世界へようこそ!
正史『日本書紀』をもとに、
最新の文献学的学術成果も取り入れながら、どこよりも分かりやすい解説をお届けします。
今回は、
神武東征神話を分かりやすく解説するシリーズ6回目。
テーマは、
長兄「五瀬命」の死
孔舎衛坂での敗戦を受けて神策発動、紀伊半島を南下することになった神武一行。ところが、神武の長兄「五瀬命」が、戦闘で受けた傷が悪化し、竈山に到ったところで儚くなられる。。。
「長兄の死」が東征に与えた影響は何か?
こうしたロマンを探ることで、東征神話における「兄の死の意味」を考えます。
今回も、概要で全体像をつかみ、ポイント把握してから本文へ。最後に、解説をお届けしてまとめ。
現代の私たちにも多くの学びをもらえる内容。日本神話から学ぶ。日本の神髄がここにあります。それでは行ってみましょう!
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
神武紀|長兄「五瀬命」の死|「ますらお」なのに復讐できず無念すぎたので、東征に復讐を追加した件
目次
神武紀|長兄「五瀬命」の死 の概要
今回も『日本書紀』巻三「神武紀」をもとにお届け。ちなみに、前回の内容、これまでの経緯はコチラ↓をご確認ください。
そのうえで、
孔舎衛坂での敗戦後、東征軍は神策=日神の神威を背に負う(背負日神之威)べく海路を南下し、紀伊半島を迂回するルートを進みます。
途上、大阪府泉南市男里、男里川河口付近の「山城水門」に到りますが、ここへきて長兄「五瀬命」の傷が甚だしく悪化。五瀬命は雄叫びをあげ、敵に復讐もできずに死ぬ無念を口にします。
そして、和歌山市竈山に到ったところでついに薨じられ、そのまま竈山に葬られます。
東征ルート、場所の確認
ルートを確認。
生駒山の「孔舎衛坂」での敗戦により、神策をめぐらし日(昇る太陽)を背にして=日神の威を背に負って戦うため紀伊半島を大きく迂回して大和に入ろうとする。
その途上のお話。

紀伊半島迂回のため、草香津→ 山城水門→ 竈山の順で進軍。

↑上空から、和歌山市を望む。左上の突き出てる半島が加太の岬です。ここに神武の船団が、、、ロマンが広がりますっ!
五瀬命は和歌山市の竈山に到ったところでついに薨じられ、そのまま竈山に葬られることになるのですが、、ここでの「長兄の死」は、単に「お兄さんが傷を受けて死んでしまった」だけではありません。
このときの神武の無念は深く、以後、東征の目的に「仇討ち」が追加されることになります。
つまり、
「建国」という理想追求型の東征に、「報復」という個人的な目的が加わる訳で、その意味で、非常に重要なシーンなのです。
神武紀|長兄「五瀬命」の死 現代語訳と原文
5月8日に、東征軍は茅淳の「山城水門」 に至る。またの名は「山井水門」。(茅淳はここでは「ちぬ」という。)
この時、長兄「五瀬命」は、孔舎衛で受けた矢傷の痛みが甚だしく、そこで剣の柄に手をあてて押さえ雄誥をあげた。(撫劒は、ここでは「つるぎのたかみとりしばる」という)「なんといまいましいことだ!武勇に優れていながら、(慨哉は、ここでは「うれたきかや」という)敵の手によって傷を負い、報復もせずに死ぬとは!」当時の人は、それでこの地を名付けて「雄水門」といった。
さらに進軍し、紀国の竃山に到ったとき、ついに五瀬命は軍中にて薨じられた。よって竃山に葬った。
五月丙寅朔癸酉、軍至茅淳山城水門。亦名山井水門。(茅淳、此云智怒。)時五瀬命矢瘡痛甚、乃撫劒而雄誥之曰(撫劒、此云都盧耆能多伽彌屠利辭魔屢)「慨哉、大丈夫(慨哉、此云宇黎多棄伽夜)被傷於虜手、將不報而死耶。」時人因號其處、曰雄水門。進到于紀伊國竈山、而五瀬命薨于軍、因葬竈山。 (引用:『日本書紀』巻三 神武紀より一部抜粋)※原文中の「天皇」という言葉は、即位前であるため、生前の名前であり東征の権威付けを狙った名前「彦火火出見」に変換。
竈山神社@和歌山市
神武紀|長兄「五瀬命」の死 解説
必勝の神策、大和へは東から入って昇る太陽を背に受けて戦えば大丈夫作戦!の途上、、長兄が死んでしまう、、なんてこった。
兄の無念に想いを致しながら、、以下詳細解説。
まとめ
長兄「五瀬命」の死
孔舎衛の激戦と敗退。その原因は「情報不足と無自覚(≒おごり)」にありましたが、その代償を「兄の死」という形で払う事になりました。
神武の無念は非常に深く、以後、東征の目的に「仇討ち」が追加されることになります。考えようによっては、3年も準備したのに、自分の無自覚によって敗戦し、長兄が傷を負い死んでしまうわけで、、、ある意味私の責任です。
押さえておきたいのは、ここでの「長兄の死」は「報復」を東征に組み込む意味を持つという事。「建国」という理想追求だけでなく、「仇討ち・復讐」のための東征といった新たな段階に入る訳で、非常に重要なのです。
また、東征神話はその意味で「日本最古の仇討ち」として位置づけられるという事ですね。
つづきはコチラ!突然の暴風雨!??コレは、、、
神武東征神話のまとめ、目次はコチラ!
『古事記』版はコチラ!
神話を持って旅に出よう!
神武東征神話のもう一つの楽しみ方、それが伝承地を巡る旅です。以下いくつかご紹介!
●茅淳の「山城水門」伝承地:神武天皇聖蹟雄水門顕彰碑
天神の森公園の中。「水門」という名の通り、古代このあたりは海だった模様。。
●竃山伝承地
本殿の背後には彦五瀬命の墓と伝える「竈山墓」(宮内庁治定墓)があります。
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
こちらの記事もどうぞ。オススメ関連エントリー
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




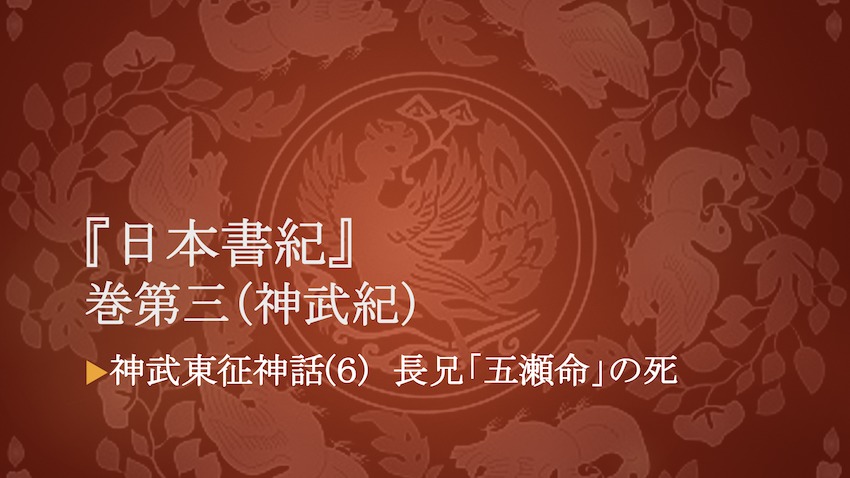
























→5月の「丙寅が朔にあたる癸酉」は8日のこと。
茅淳の「山城水門」は、現在の、大阪府泉南市男里、男里川河口付近とされてます。「茅淳」は、欽明天皇14年五月条に「河内国言、泉郡茅淳海中」と伝えており、河内国和泉郡の海を指す言葉です。その「水門」つまり河口付近。
敗戦が4月だったので、ここまで来るのにおよそ1か月ほどかかってます。その間、兄の傷は徐々に悪化していた。。?
次!
→報復もできずに死ぬ無念を雄叫び、、
いくつか注釈を。
原文「撫劒」。剣の柄に手をあてて押さえる。憤りの表現です。
参考として『孟子』(梁恵王章句下)に、斉の宣王の「自分は勇を好む」という言葉に対して孟子が答えて言う内容に、
勇敢なのは大いに結構だけどイキったところで匹夫の勇なんでやめとけと諭すのですが、ココでは「剣の柄に手をかけぐっと押さえつけ、目をいからして睨みつけ」という内容で伝えてます。非常に強い気持ちを体で表現している訳です。
同じ「撫劒」が使われてるってことは、剣の柄に手をあててぎゅーっと押さえる、のみならず、目をいからして睨みつけてる感もあったと解釈するのが◎。五瀬命の「匹夫の勇」を暗示する表現であります。
原文「慨」。腹立たしい、いまいましい、の意味。
参考として『万葉集』巻8「ここだくも 我が守るものを うれたきや 醜霍公鳥(中略)地に散らせば(1507番)」とあり、恋の歌ではありますが、憎らしいという意味で使われてます。
原文「大丈夫」。りっぱな男。勇気のある強い男の意味。
ということで、まとめると、、
剣の柄に手をあててぎゅっと押さえて(目をいからして睨みつけ)雄叫び。ますらおなのに、立派な俺なのに、敵から傷を受けて、しかも復讐もできず死ぬなんて!!!(死んでも死に切れないっ、、)
って、こと。
ポイントは、この無念さに深く思いを致すこと。コレかなり重要で。これをうけて、東征神話後半で「神武の仇打ち」につながっていく。神武の行動の根拠、原動力がこの「(兄の)無念さ」にある、という設定になってるすね。
最後の、「時人」とは、「当時の世間の人」の意味。神武紀では、事蹟にちなむ土地を名づける者として位置付けられてます。
次!
→さらに進軍。和歌山市の竈山に至ったところでついに亡くなります。「薨」という漢字が使用されており、これは、天皇の兄という身分に即した表現で、「死」を言います。
ココ、超重要なところ。長兄の薨去は、神武にとって、兄の無念を晴らす「仇討ち」の意味を東征に加えることになります。
古代では、「報復」を「義務」として定めていて、殺されたのが父であれば「不倶戴天」の敵として、相手が死ぬまで報復を止めません。
五瀬命は長兄なので、弟の神武は「報復の義務」を負う。これは「兵(武器)を反さず」という言葉で伝えられ、武器を執って仇を討ち果たすまでは止めてはならない、という意味。有名な「忠臣蔵」も同じ考え方です。
実際、東征の最終局面で長髄彦を攻撃する時に、この五瀬命の薨去に思いを致し、断固とした決意をもとに、神武は「〜撃ちてし止まむ」「〜我は忘れず、撃ちてし止まむ」と来目歌を歌って戦いに臨む訳です。
東征が、理想を追うだけではなく、報復をめざす新たな段階に入るという、極めて重要な意味を持つのが、この五瀬命の薨去なんです。