多彩で豊かな日本神話の世界へようこそ!
正史『日本書紀』をもとに、
最新の文献学的学術成果も取り入れながら、どこよりも分かりやすい解説をお届けします。
「神武東征神話を分かりやすく解説するシリーズ」今回は17回目。
テーマは、
橿原宮造営発議と八紘為宇
長髄彦誅殺により、東征神話における最大の山場を乗り越えた神武こと「彦火火出見」。残る課題は「建国・即位」へむけた「準備」。
大きく4つ。
- 中洲(=大和平野)平定
- 東征の事蹟にちなむ地名起源設定
- 宮殿造営
- 天皇にふさわしい嫁をもらう事
全3回に渡ってお届けしております。
前回、中洲平定と事蹟伝承をお届けましたので、今回は、3つ目「宮殿造営」をピックアップ!
概要で全体像をつかみ、ポイント把握してから本文へ。最後に、解説をお届けしてまとめ。
現代の私たちにも多くの学びをもらえる内容。日本神話から学ぶ。日本の神髄がここにあります。それでは行ってみましょう!
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
橿原宮 造営発議と八紘為宇|東征開始から6年が経過した今、天照から始まる神々の系譜や政治を踏まえ素晴らしい国をつくろうとした件
目次
橿原宮 造営発議と八紘為宇 の概要
今回も『日本書紀』巻三「神武紀」をもとにお届け。前回の内容、これまでの経緯はコチラ↓をご確認ください。
中洲は平定され、事蹟伝承も残したので、次はワイの住処をつくるんや。
そこで登場、橿原宮造営発議。
こちら、東征発議と同様、素晴らしいスピーチになっております。造営にあたっての経緯、意義、構想を、漢籍の膨大な知識とロジックを駆使しながら組み立て。『日本書紀』編纂チーム、古代日本人の知恵と創意工夫の結晶であります。
分かりやすく整理すると以下の通り。大きく4つのカタマリ。
| 現状認識 | ・東征に出発してからから、これまでに六年が過ぎた。 ・辺境の地はまだ静まってないが、中洲は平和になった。 |
| ベンチマーク | ・天皇の都を大きく広げ、聖人の行いを規範として倣うのがよい。 ・聖人が制度を定めれば、大義は必ず時勢に叶うものだ。 |
| 構想 | ・山林を伐り開いて宮殿を造営し、皇位に即いて人民を治めよう。 ・天神がこの国を授けた徳に応え、皇孫が正義を養育した心を広めよう。 ・世界をひとつに合わせ都を開き、天下を覆ってひとつの家としよう。 |
| 具体的内容 | ・畝傍山の東南の橿原の地は、周囲を山に囲まれ、国の奥深くにある安住の地。 ・この地を整備しよう。 |
と、まー良くできてる。
特に、造営の意義を聖人の行いに重ねて組み立ててるのがポイント。ワイ聖人。
さらに、天神がこの国を授けた徳に応え、皇孫が正義を養育した心を広めよう、ということで。これまでの背景理解が必須。
- 天照大神の直系子孫(=天孫)である神武が、
- 瓊瓊杵尊の子として位置づけるために、「彦火火出見」という名を名乗り、
- 天照大神はじめ天神が、この国を瓊瓊杵尊に授けた「徳」に対して応えるとともに、
- 瓊瓊杵尊の目指した「正しきを養う」という心を弘めることを、自らの政治の理想とした。
- そして、皇統の正統な後継者としての自覚に立ち、理想の政治の実現を目指した。
というのが、造営発議の背景にある考え方。極めてロジカルで、どこまでも奥ゆかしい内容となっております。
橿原宮 造営発議と八紘為宇 の現代語訳と原文
3月7日、彦火火出見は命令を下した。「私が自ら東征に出発してからから、これまでに六年が過ぎた。この間、天神の神威を頼りとし、凶暴な賊どもは誅殺された。遠く辺境の地はいまだ静まらず、敵残党はなお残っているが、中洲の地はもはや兵乱に風塵がたつことはない。今まさしく、天皇の都を大きく広げ、大壮を規範として倣うのがよい。 しかるに今、時は世のはじめにあたり、民心は素朴である。彼らは穴に住み、未開の風習が常である。そもそも、聖人が制度を定めれば、大義は必ず時勢に叶うものである。いやしくも民の利益となることがあれば、聖人の業を妨げるものはないであろう。 今こそ、山林を伐り開き、宮殿を造営し、謹んで皇位に即いて、人民を安んじ治めなければならない。上にあっては天神がこの国を授けた徳に応え、下にあっては皇孫が正義を養育した心を広めよう。そして世界をひとつに合わせ都を開き、天下を覆ってひとつの家とするのだ。なんと素晴らしいことではないか。 見渡せば、あの畝傍山の東南の橿原の地は、思うに周囲を山に囲まれ、国の奥深くにある安住の地であろう。この地を整備しよう。」
この月に、さっそく役人に命じて宮殿の造営を開始した。
三月辛酉朔丁卯、下令曰「自我東征、於茲六年矣。頼以皇天之威、凶徒就戮。雖邊土未淸餘妖尚梗、而中洲之地無復風塵。誠宜恢廓皇都、規摹大壯。而今運屬屯蒙、民心朴素、巣棲穴住、習俗惟常。夫大人立制、義必隨時、苟有利民、何妨聖造。且當披拂山林、經營宮室、而恭臨寶位、以鎭元元。上則答乾靈授國之德、下則弘皇孫養正之心。然後、兼六合以開都、掩八紘而爲宇、不亦可乎。觀夫畝傍山東南橿原地者、蓋國之墺區乎、可治之。」是月、卽命有司、經始帝宅。(『日本書紀』巻三 神武紀より一部抜粋)※原文中の「天皇」という言葉は、即位前であるため、生前の名前であり東征の権威付けを狙った名前「彦火火出見」に変換。

橿原宮造営発議と八紘為宇 の解説
宮殿造営令をくだしたとき、東征開始から6年が経過していました。
6年ですよ。。。。。6年。私、6年前って何してたんでしょうか?
1つの事を、壮大なビジョンを、6年もの歳月と様々な苦難を経て、ようやく実現しようというタイミング。このときの神武の心中やいかに?そんな神話ロマンに想いを致しながら、、、
以下詳細解説。
まとめ
橿原宮 造営発議と八紘為宇
中洲は平定され、事蹟伝承をも残したので、次はワイの住処をつくること。
そこで登場、橿原宮造営発議。
チェックしてきたとおり、東征発議と同様、素晴らしいスピーチになってますよね。
造営にあたっての経緯、意義、構想が、漢籍の膨大な知識とロジックを駆使しながら組み立てられてる。『日本書紀』編纂チーム、古代日本人の知恵と創意工夫の結晶(-_☆)キラーン
改めて、造営発議を整理すると以下の通り。
| 現状認識 | ・東征に出発してからから、これまでに六年が過ぎた。 ・遠く辺境の地はいまだ静まってはいないが、中洲の地は平和になった。 |
| ベンチマーク | ・今まさしく、天皇の都を大きく広げ、聖人の行いを規範として倣うのがよい。 ・聖人が制度を定めれば、大義は必ず時勢に叶うものだ。 |
| 構想 | ・山林を伐り開いて宮殿を造営し、皇位に即いて人民を治めよう。 ・天神がこの国を授けた徳に応え、皇孫が正義を養育した心を広めよう。 ・世界をひとつに合わせ都を開き、天下を覆ってひとつの家としよう。 |
| 具体的内容 | ・畝傍山の東南の橿原の地は、周囲を山に囲まれ、国の奥深くにある安住の地である。 ・この地を整備しよう。 |
と、ホントにロジカル。
特に、造営の意義を「聖人の行い」に重ねて組み立ててるのがポイント。ワイ聖人。
さらに、天神がこの国を授けた徳に応え、皇孫が正義を養育した心を広めよう、ということで。
- 天照大神の直系子孫(=天孫)である神武が、
- 瓊瓊杵尊の子として位置づけるために、「彦火火出見」という名を名乗り、
- 天照大神はじめ天神が、この国を瓊瓊杵尊に授けた「徳」に対して応えるとともに、
- 瓊瓊杵尊の目指した正しきを養うという御心を弘めることを、自らの政治の理想とした。
- そして、皇統の正統な後継者としての自覚に立ち、理想の政治の実現を目指した。
というのが、この造営発議の背景にある考え方。極めてロジカルで、どこまでも奥ゆかしい内容となっております。
ようやくたどり着いた「安住の地」。
この言葉には、これまでの戦闘や、苦難や、試練をふまえ、人民が安心して暮らせる国をつくりたいという想いが感じられ、心にぐっとくるのです。ほんと、どこまで奥ゆかしい神話なんだ。。。
と、いうことで、「建国・即位準備」の4項目。
- 中洲(=大和平野)平定
- 東征の事蹟にちなむ地名起源設定
- 宮殿造営
- 天皇にふさわしい嫁をもらう事
のうち、3項目を達成。続きまして、天皇にふさわしい嫁探しだ!
続きはこちらで!嫁カモン!
神武東征神話のまとめ、目次はコチラ!
神話を持って旅に出よう!
神武東征神話のもう一つの楽しみ方、それが伝承地を巡る旅です。以下いくつかご紹介!
●橿原神宮:橿原に造営した宮殿跡地に建立された神社!
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
こちらの記事もどうぞ。オススメ関連エントリー
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




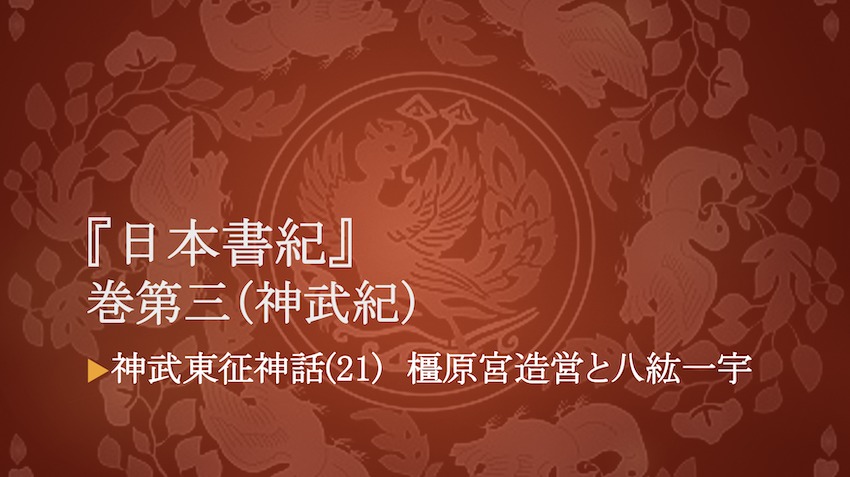






















→3月の、「辛酉」が朔の「丁卯」は7日。
神武は宮都造営の「令」を下します。東征発議と同様、これまでの経緯をふまえ意義とか理由を熱く語ります。
次!
→東征発議し出発したのが「太歳・甲寅(紀元前667年)」。造営令を下したこの年は「己未の年(紀元前662年)」。あしかけ6年が経過。
「天神の神威を頼りとし」とあり。「天神の神威」原文「皇天之威」。コレ、孔舎衛坂の戦いにて、神策を巡らせたときに登場「日神の神威を背に負い(背負日神之威)」をうけての内容。
元ネタは、
『後漢書』巻九・献帝紀。この中で「頼皇天之霊」とあり、「皇天」とは、大いなる天、あるいは、天帝のこと。これを応用し、ここでは天、とりわけ天照大神を指すものとして整理。
ちなみに、「天神」と神武の関係は東征発議で登場してました。コレを承けてます。
東征神話終盤ですから、、
前半に打っていた布石を、伏線をバシバシ回収しにかかってる。このあたりのつなぎも練りに練られて素晴らしい。。
「遠く辺境の地はいまだ静まらず、敵残党はなお残っているが、中洲の地はもはや兵乱に風塵がたつことはない。」とあり。「中洲の地」とは、東征の当初から目指してきた理想の地。世界の中心で天下統治を叫ぶ。
「風塵」は兵乱の比喩として。
原文「無復風塵」とあり、中洲は平定され、もはや兵乱が起こることはないとしています。平和な世の中が近づいてきてるモメンタムを感じて。。
次!
→だからこそ!今!都、つくろうぜ!
リーダーは、時を読むのも重要な役割。中洲に兵乱がなくなった今こそ、都をつくるのに相応しい時であると。。
「天皇の都を大きく広げ(恢廓皇都)」とあり。「恢廓」は、大いに空間を空け広げること。なので、皇都=天皇の都をめちゃくちゃデカく空間を空けて広げていくこと。想定してるスケール感重要。
「大壮を規範として倣うのがよい(規摹大壯)」とあり。コレ、超重要表現。
「規摹大壯」とは、『文選』魏都賦「搴大壮(大壮に搴す)」を取り込んだ表現。搴す=模す。なので、大壯を規範として模す。倣う。
「大壮」自体は、繋辞下伝で伝える易の卦のこと。「上古は穴居して野処す。後世に聖人之を易ふるに宮室を以てす。棟を上にし、宇を下にし、以て風雨を待す。蓋し、諸を大壮に取るなり。」とあり、要は、人民が穴で暮らしてたのを、聖人が宮室で生活するようにさせた、というもの。人民QOLの向上。君子の道が栄える象として位置づけられてます。壮大にするという字義からの連想も。
つまり、聖人の規範を手本に置き、易の大壮の卦を模範として、神武が宮室を建設して宮都を造営する、それが人民を利するものになるのだ!という内容。神武を聖人に重ね、正当性をこれでもか!と訴求してますよね。
一方で、現状認識。「時は世のはじめにあたり(運屬屯蒙)」。原文「屯蒙」は、『周易』の序卦伝から。「「屯」は物の始めて生ずるなり。物生じては、必ず蒙、故に之れを受くるに蒙を以てす。蒙は(中略)物のおさなきなり」。つまり、世はまだまだ始まりであり、おさない状態であると。
さらに「民心は素朴である。彼らは穴に住み、未開の風習が常である(民心朴素、巣棲穴住、習俗惟常)」と。穴に住む、コレ、先ほどの「大壮」を受けての表現。きちんと聖人文脈を踏まえてる。
「巣棲穴住」は、、イメージ的には、冬は穴に住み、夏は樹の上に住む、みたいな感じ。。。『礼記』礼運に「昔は先王に未だ宮室有らず。冬は即ち営窟に居り、夏は即ち檜素に居る」とあります。。未開にもほどがある!??
だかこそ必要なんだと。「聖人が制度を定めれば、大義は必ず時勢に叶うものである(夫大人立制、義必隨時)」。原文「大人」。コレ、中国古代の理想である聖人。これでもかとワイ聖人推し!
「義必隨時」は、『周易』随卦「時に随うの義、大なるかな」をふまえた表現。聖人が制度を定めるときはその大義は必ず時宜にかなうものだ、もっと言うと、ワイ=聖人がやることは時宜にかなってるんやで、と、コレが言いたい。
さらに!「民の利益となることがあれば、聖人の業を妨げるものはないであろう(有利民、何妨聖造)」と。。。「聖人の業」原文「聖造」。聖人が製造する、造る意味。聖人=神武による宮殿の造営を、聖人の業としてます。
と、、、まーすごい聖人ロジック、ワイ聖人推し。。漢籍の膨大な知識を踏まえ、聖人の行いを神武に重ねながら、あくまでも人民QOLの向上を念頭に、宮都造営の意義や時宜にかなってることを訴求してます。『日本書紀』編纂チームの創意工夫がスゴすぎて、、この時点でお腹いっぱいです。
次!
→壮大な造営ビジョン、スゴイですよね。ビリビリきます。
以下3つに分けて解説。
1つ目のカタマリ。
「今こそ、山林を伐り開き、宮殿を造営し(且當披拂山林、經營宮室)」とあり。原文冒頭の「且」は、当然~すべき、の意味。ワイ聖人、造営は時宜にかなう、人民QOL向上に資する、だからこそ当然、宮室を造営すべき。これ当たり前。そんなロジック。
「宮殿を造営し(經營宮室)」の、「経営む」とは、宮殿造営とその後の国家運営を念頭に置いた言葉。経常的に運営していく訳ですよ。造営はゴールじゃない。むしろ大事なのはその後の運営です。
「謹んで皇位に即いて、人民を安んじ治めなければならない(而恭臨寶位、以鎭元元)」は重要表現。
「皇位に即いて(臨寶位)」の「宝位」は皇位のこと。「宝位に臨む」とは「天皇として即位すること」をいう訳です。コレ、現在の皇位継承儀式にも登場する「高御座」の原型。。
思い起こせば神代。。
天照大神が、降臨する「彦火瓊瓊杵尊」に「天上無窮の神勅」を発動。
「皇孫に勅して、「葦原千五百秋之瑞穂國は、我が子孫が君主たるべき地である。汝、皇孫よ、行って治めなさい。さあ、行きなさい。天祚の栄えることは、天地とともに窮まることがないであろう。」と言った。(『日本書紀』巻第二 第九段〔一書1〕より)」
あのとき、火瓊瓊杵尊に予祝した「天祚」が今、「宝位」として結実しつつあるんすよ。この重要感、壮大な神話ロマンに震えが止まりません。。
「人民を安んじ治めなければならない(鎭元元)」の、「元元」とは「人民」のこと。どちらかというと、憐み慈しむべき対象としての人民、というニュアンス。
『後漢書』光武帝紀に、「上は天地の心に当たり、下は元元の帰す所と為る(上は天地の心にかない、下は人民の帰順するところとなった)」とあり。この李賢注に「元元は黎庶を謂ふなり。元元は言喁喁たるに由りて矜怜すべきの辞なり」とのことで、元元は黎庶=人民のことであり、言葉が喁喁=幼児のように片言でしゃべるので、矜怜=あわれむべきだとしています。。なんか、、、上から??
と、そんな憐み慈しむべき人民を「鎮める」ということで、「安心して暮らせる国をつくり治めよう」といった意味になります。
次、2つ目のカタマリ。。
「上にあっては天神がこの国を授けた徳に応え、下にあっては皇孫が正義を養育した心を広めよう(上則答乾靈授國之德、下則弘皇孫養正之心)」。コレも重要表現。
「天神」とは、高皇産霊尊・大日孁尊(天照大神)の2神のこと。「この国を授けた徳」というのは、降臨する瓊瓊杵尊に、地上つまりこの国を授けたことを言います。いずれも、東征神話冒頭、東征発議でしっかり触れられてました。
東征発議で、
神武自ら「昔、我が天神である高皇産霊尊・大日孁尊は、この豊葦原瑞穂国のすべてを我が天祖である彦火瓊瓊杵尊に授けた。」と言ってました。この限りない徳に応えていくことが天孫としての、天神子としての責務であります。
また、「皇孫が正義を養育した心をおしひろめる」というのは、皇孫=瓊瓊杵尊の目指した「正しきを養うという御心を弘める」と言う意味。
ポイントは、天照大神から始まる神々の系譜やこれまでの経緯を踏まえ、それを根拠・後ろだてとして、自らが実践者・体現者として皇位に即くのだと。その為の宮殿であると。ココ、超重要。
次、3つ目のカタマリ。。。
「そして世界をひとつに合わせ都を開き、天下を覆ってひとつの家とするのだ。なんと素晴らしいことではないか(兼六合以開都、掩八紘而爲宇、不亦可乎)」とあります。
「世界をひとつに合わせ都を開き(兼六合以開都)」の「六合」とは、天地四方のこと。神武が想定している空間の広がりを意識して。兼ねる=ひとつにあわせて、開都しようぜと。
「天下を覆ってひとつの家とするのだ(掩八紘而爲宇)」。これも超重要表現。原文「掩八紘而爲宇(八紘をおおいて宇となす) 」。
「八紘」とは、世界の八方の果てで天地を繋いでいる網。『淮南子』をもとにした世界の捉え方、その中の、かなりな世界の果てエリアを指します。
『文選』呉都賦の劉逵注に「『淮南子』に曰く、九州の外、八沢の方千里なる有り。八沢の外、八紘の亦方千里なる有り。蓋し八索なり。」とあり、要は、世界の果てくらいの勢いのめちゃくちゃ遠いところで天地を繋いでいるエリアが8つあり、それを「八紘」という訳です。まず、この「果て」な感じ、壮大な空間の広がりをチェック。
そのうえで、『文選』呉都賦より「古、先帝の代、曾て八紘の洪緒を覽る。六合を一にして光宅し、遐宇に翔集す。」とあり、古の聖王の時代には、世界の果て(八紘)まで見聞し、天下(六合)を統一して聖徳をあまねくし、巡守したことを伝えてます。要は、コレをなぞらえてる訳です。
「宇」は大きな屋根で蔽われた「いえ」のこと。なので、「掩八紘而爲宇」とは、それこそ古の聖王たちが実践していたように、世界の果てまでも覆ってひとつの家とするのだ、という意味になります。
よく「八紘一宇」という言葉が使われますが、これは大正時代に短縮して作られた言葉。もともとは「掩八紘而爲宇」。短縮しても「八紘爲宇」。当サイトとしてはこの原型をもとにチェックをいただきたい!
戦前の使われ方はさておき、世界を一つにして素晴らしい政治によって天下をおおい、一つの家族として安心して暮らせる国をつくろう、と宣言した訳で。このビジョン、構想は素晴らしいものがあると思います。
次!
→ついに登場、橿原!
思い起こせば、伊奘諾尊が禊祓をした聖地「筑紫日向小戸橘之檍原」で設定された伏線が、ココで、、、ついに、、ようやく回収された。。
「思うに周囲を山に囲まれ、国の奥深くにある安住の地であろう(蓋國之墺區乎)」とあり。原文「墺区」。『文選』巻一・西都賦「天地の墺区」による。そのなかに「説文に曰く、隩は四方の土、安居すべきものなり」とあり、奥深く安住に適した地をいいます。「中洲」の中心地にあたる。それ、橿原!
「安住の地」と伝えているところに、
が感じられて、心にぐっとくるのです。ほんと、どこまで奥ゆかしい神話なんだ。。。
「この地を整備しよう(可治之)」の「治」は、人手を加えてちょうどよい状態にすること、建設するときにも使われます。
そして、早速「帝宅」の造営を始めた訳ですね。