日本神話に登場する、重要ワード、重要エピソードをディープに掘り下げる「日本神話解説シリーズ」。
今回は、
イザナギとイザナミはなぜ国生みで失敗したのか?その意味とは?
をテーマにお届けします。
イザナギ=伊耶那岐命、イザナミ=伊耶那美命の国生みの失敗を伝えるのは『古事記』。または『日本書紀』第四段〔一書1〕。
今回は、『古事記』をもとに、伊耶那岐命と伊耶那美命の国生みの失敗とは?その意味するところは?についてディープに解説します。
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
イザナギとイザナミはなぜ国生みで失敗したのか?その意味とは?日本神話が伝える国生みの失敗を分かりやすく解説!
目次
イザナギとイザナミが失敗する場面
伊耶那岐命と伊耶那美命はなぜ国生みで失敗したのか?
その謎を探るべく、まずは、失敗の現場をチェック。どういった経緯で、どういう内容なのかを確認です。
ご紹介するのは『古事記』上巻。「国生み神話」と呼ばれる伝承箇所から。
経緯としては、
天神と呼ばれる非常に尊貴な神々によって、国の修理固成を命じられた伊耶那岐命、伊耶那美命。
二神は、淤能碁呂嶋に天下り、天の御柱を見立てます。そのうえで、身体問答で互いの体の形状確認をしてから、天の御柱を回り、交合して出産しようとするところから。
イメージは以下。

※陽=伊耶那岐命、陰=伊耶那美命
そこで伊耶那岐命は詔して「それならば、私と汝とでこの天の御柱を行き廻り逢って、みとのまぐはいをしよう。」と言った。このように期って、さっそく「汝は右より廻り逢いなさい。私は左より廻り逢おう。」と言い、約り終えて廻った時、伊耶那美命が先に「ほんとうにまあ、いとしいお方ですことよ。」と言い、その後で伊耶那岐命が「なんとまあ、かわいい娘だろうか。」と言った。
各が言い終えた後、(伊耶那岐命は)その妹に「女人が先に言ったのは良くない。」と告げた。しかし、寝床で事を始め、子の水蛭子を生んだ。この子は葦船に入れて流し去てた。次に、淡嶋を生んだ。これもまた子の例には入れなかった。
ここに、二柱の神は議って「今、私が生んだ子は良くない。やはり天神の御所に白しあげるのがよい。」と言い、すぐに共に參上って、天神の命を仰いだ。そこで天神の命をもって、太占に卜相ない「女の言葉が先立ったことに因り良くないのである。再び還り降って改めて言いなさい。」と仰せになった。
ゆえに反り降りて、更にその天の御柱を先のように往き廻った。ここに、伊耶那岐命が先に「なんとまあ、かわいい娘だろうか。」と言い、その後に妹伊耶那美命が「なんとまあ、いとしいお方ですこと。」と言った。
このように言ひ終わって御合して生んだ子は、淡道之穗之狹別嶋。 ~中略~ ゆえに、此の八嶋を先に生んだことに因って、大八嶋国という。
爾伊耶那岐命詔「然者、吾與汝行廻逢是天之御柱而、爲美斗能麻具波比此七字以音。」 如此之期、乃詔「汝者自右廻逢、我者自左廻逢。」約竟廻時、伊耶那美命、先言「阿那邇夜志愛上袁登古袁。此十字以音、下效此。」後伊耶那岐命言「阿那邇夜志愛上袁登賣袁。」各言竟之後、告其妹曰「女人先言、不良。」雖然、久美度邇此四字以音興而生子、水蛭子、此子者入葦船而流去。次生淡嶋、是亦不入子之例。 於是、二柱神議云「今吾所生之子、不良。猶宜白天神之御所。」卽共參上、請天神之命、爾天神之命以、布斗麻邇爾上此五字以音ト相而詔之「因女先言而不良、亦還降改言。」故爾反降、更往廻其天之御柱如先、於是伊耶那岐命先言「阿那邇夜志愛袁登賣袁。」後妹伊耶那美命言「阿那邇夜志愛袁登古袁。」如此言竟而御合生子、淡道之穗之狹別嶋。~中略~ 故、因此八嶋先所生、謂大八嶋國。 (『古事記』上巻より一部抜粋)

ということで。
| 失敗の内容 | 大八嶋国を生むはずが、水蛭子と淡嶋が生まれてしまったこと。 |
| 失敗の原因 | 天之御柱を廻ったあと、伊耶那美命(女神)が先に声をあげてしまったこと。 |
ということなんす。
水蛭子は葦船に入れて流し去て、淡嶋も子の例には入れなかった。とあり、生んだにも関わらず、流すか認知しないということになってます。
本文では2か所、失敗の原因を指摘するところがあり、
- 各言い終えた後、其の妹に「女人が先に言ったのは良くない。」とお告げになった。
- 天神の命をもって、太占に卜相なって「女の言葉が先立ったことに因り良くないのである。
と、伝えてます。
どうやら、結婚、いよいよ交合というときになって、女神が先に声をあげることはNG。先に男神が声をあげないといけないルールがあるようで。。
これを破ると、水蛭子と淡嶋が生まれてしまい、
逆に、きちんと手順を守ると、大八嶋国が生まれる、
という伝承になってる。
『古事記』の伝承、伊耶那岐命と伊耶那美命の結婚と国生みと、ステキなロマンス的なイメージがあるかと思いますが、実は全然違うくて、きちんとした手順やルールを守らないといけない、破るとおかしなことになる、という、ある意味、厳しい神世界の掟を伝えてるとも言えますよね。
イザナギとイザナミはなぜ失敗したのか?
と、いうことで、伊耶那岐命と伊耶那美命がどんなふうに失敗したのか?理解できたところで、ココからは、なぜ失敗したのか?について、さらにディープに掘り下げます。
なぜ失敗したのか?を探るためにも、じゃ、なにが成功なのよ?ってことを分かってないと話になりません。
てことで、以下、
まずは国生みにおける成功の定義を確認し、そのうえでなんで失敗したのか?について解説します。
国生みの成功の定義、国生みでの成功とは?
一言でいうと、
結婚=神聖な儀礼として、きちんとした手順、ルールのもとで行うこと。
コレ、国生みにおける大前提として押さえておきたいポイント。
ココでいう、結婚儀礼の手順、ルールとは、
- 身体問答
- 天之御柱を左旋・右旋
- 先唱後和
- 交合結婚
といった手順、流れのこと。儀礼なんで、踏むべき手順(①〜④)がある、、
しかも!
各手順で則るべきルール細目があって、、
そのルールとは
易の概念に基づく「陽主導」であること。
(陽=伊耶那岐命。陰=伊耶那美命。ただし、本文にはそこまで明確に陰陽理論は謳われておりません。)
●必読→ 日本神話的易の概念|二項対立の根源とその働きによって宇宙はつくられ動いている
なので、先ほどの手順に当て込むと、
- 身体問答・・・陽が先、陰が後
- 左旋右旋・・・陽が左旋、陰が右旋
- 先唱後和・・・陽が先、陰が後
- 交合結婚・・・ここは、、、特になし。二人で交合だから。
となるわけです。コレが成功パターン。成功の定義です。
結婚=神聖な儀礼であり、易の概念に基づく「陽主導」であること。
これがまず大前提としてあり、だからこそ、各手順で陰が先行することがNGとされる訳ですね。
なので、国生みでなんで失敗したの?ってことについては、つまり
陰先行は手順的に間違いでありダメだから、それをやっちまったから失敗なんだよ
というお話なんです。
なので、天神の是正指導を通じて正しい手順で国生みをしたよ、という流れにつながっていく訳です。

イザナギとイザナミの失敗が意味すること
ということで、なぜ失敗したのか?について理解できたところで、最後に、その失敗が意味するところはどういうことなのよ?について解説。
結論から言うと、2つ。
- 手順を間違えると、変なことになるよ
- 手順通りにやれば、ちゃんとした結果が生まれるし、それは神聖なものだよ
と。
一つ目の、間違えると変なことに、というのは淡嶋や水蛭子の誕生として伝えてます。そして、水蛭子は葦船に入れて流し去て、淡嶋も子の例には入れなかった。とあり、生んだにも関わらず、流すか認知しないということに。
二つ目の、ちゃんとやると良い結果が生まれる、というのは大八嶋国の誕生として。これは、子として認知できるものであったと。
それぞれ、きちんと分けて伝えてます。
全体にただよう手続き臭さは、そのためで。意味があってわざわざやってるんです。
その意味とは、
原理原則に基づく手順やルールに則る=神聖である
ってこと。つまり、最終的に成功として誕生する大八嶋国の神聖化が狙いとしてあるわけですね。
失敗があるからこそ、成功が引き立つ、
失敗があるからこそ、学びがある、
コントラスト的な技法を駆使して非常に分かりやすく伝えている訳です。
『古事記』は天皇家の私的な歴史書として、皇太子教育のテキストとして編纂された経緯があり。その目的に沿って、失敗事例と成功事例を並べることで、やっていいこととやってはダメなことを伝えようとしてるんです。その意味で、非常に良く練られた神話になってる。
古代の日本人が創意工夫によって生み出した構想力、知恵のスゴさに感動。現代の私たちも学びたいところですよね。
まとめ
イザナギとイザナミはなぜ国生みで失敗したのか?その意味とは?
をテーマにお届けいたしましたが、いかがでしたでしょうか?
国生みの失敗を伝えるのは『古事記』で、その内容とは、
| 失敗の内容 | 大八嶋国を生むはずが、水蛭子と淡嶋が生まれてしまったこと。 |
| 失敗の原因 | 天之御柱を廻ったあと、伊耶那美命(女神)が先に声をあげてしまったこと。 |
ということ。
水蛭子は葦船に入れて流し去て、淡嶋も子の例には入れなかった。とあり、生んだにも関わらず、流すか認知しないということになってます。
コレ、国生みの成功の定義が、
結婚=神聖な儀礼
ということであり、
結婚=神聖な儀礼であり、易の概念に基づく「陽主導」であること。
これがまず大前提としてあり、だからこそ、各手順で陰が先行することがNGとされる訳です。
原理原則に基づく手順やルールに則る=神聖である
つまり、最終的に成功として誕生する大八嶋国の神聖化が狙いとしてあるんです。
失敗があるからこそ、成功が引き立つ、
失敗があるからこそ、学びがある、
コントラスト的な技法を駆使して非常に分かりやすく伝えてます。
『古事記』は天皇家の私的な歴史書として、皇太子教育のテキストとして編纂された経緯あり。その目的に沿って、失敗事例と成功事例を並べることでやっていいこととやってはダメなことを伝えようとしてる。
その意味で、非常に良く練られた神話であり、古代の日本人が創意工夫によって生み出した構想力、知恵のスゴさに感動。現代の私たちも学びたいところです。
国生み神話の詳細解説!必読です!
神話を持って旅に出よう!
国生み神話のもう一つの楽しみ方、それが伝承地を巡る旅です。以下いくつかご紹介!
●上立神岩:伊奘諾尊と伊奘冉尊が柱巡りをした伝承地
●自凝神社(おのころ神社):伊奘諾尊と伊奘冉尊の聖婚の地??
●絵島:国生み神話の舞台と伝えられるすっごい小さい島。。
●神島:国生み神話の舞台と伝えられるこちらも小さな島。。
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
[itemlink post_id=”13035″] [itemlink post_id=”13037″] [itemlink post_id=”13038″] [itemlink post_id=”13039″]
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
ついでに日本の建国神話もチェック!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




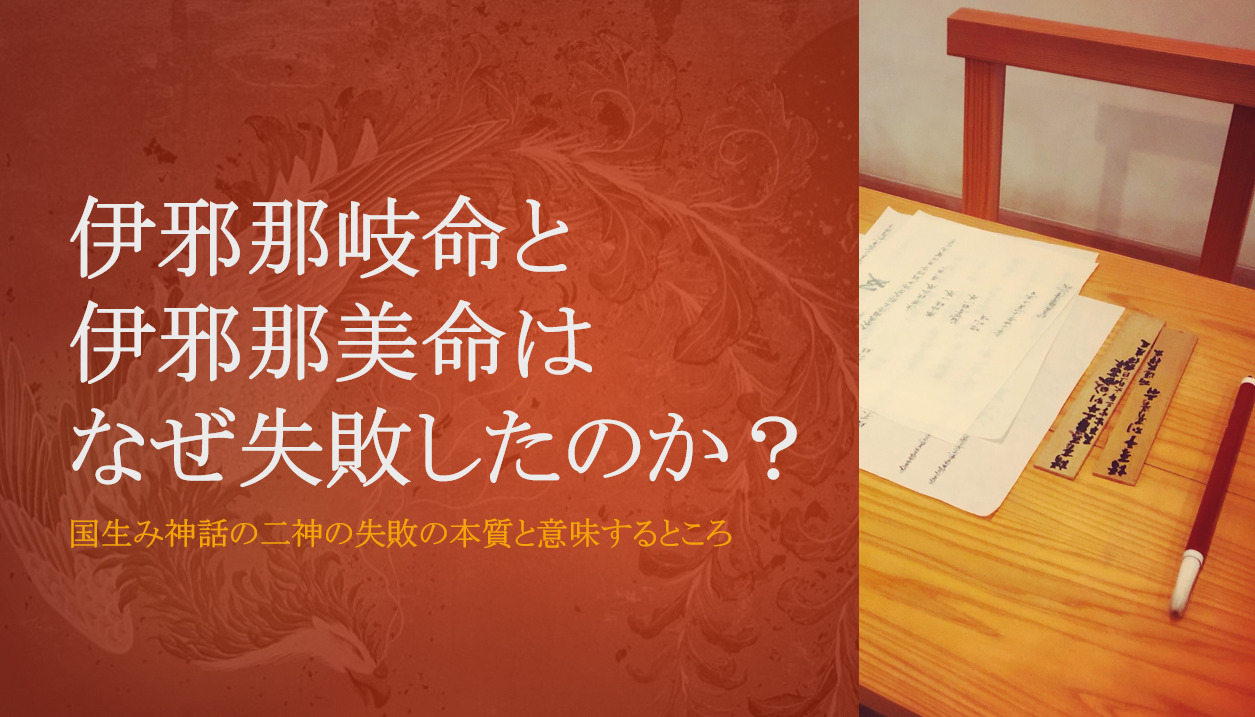





















最後までお読みいただきありがとうございます。お気軽にコメントされてくださいませ。お待ちしております!