日本神話に登場する、重要ワード、重要エピソードをディープに掘り下げる「日本神話解説シリーズ」。
今回は、
古事記と日本書紀の「国生み神話」の違い
をテーマにお届けいたします。
『古事記』と『日本書紀』、同じ「国生み神話」を伝える書物ですが、伝承の数や内容に違いがあります。
その中で、どれとどれを比較するかによって、同じだったり、違いがあったりするのが実際のところで。。
具体的には、『日本書紀』で国生みを伝えるのは巻一(神代上)「第四段」で。コチラ、実は、〔本伝〕のほかに異伝である〔一書〕が全部で10個もある、、、この、どれと『古事記』を比べるかによって答えが変わるんです。
今回は、その辺りの事情も含めて、『古事記』と『日本書紀』の「国生み神話」の違いについて日本神話をディープに掘り下げます。
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
古事記と日本書紀、国生み神話の違いを解説!
目次
『古事記』と『日本書紀』の伝える国生み神話の違い
まずは、『古事記』と『日本書紀』の伝える国生み神話の違いについて、前提となる部分を解説。
「国生み神話」を伝えるのは、『古事記』は上巻。天地開闢から別天神、神世七代の神々誕生の次に登場。
一方の『日本書紀』は、巻第一(神代紀上)の第四段、天地開闢からの神世七代の次に登場。
で、ココからが重要なんですが、
実は、『古事記』と『日本書紀』、どの伝承を比べるか?によって、違う!ってなったり、だいたい同じ!ってなったりするんです。
どういうことか?
分かりやすく、図解してみるとこうなる。

『日本書紀』第四段は、〔本伝〕のほかに異伝である〔一書〕が全部で10個あり、この中で、〔一書1〕の内容が『古事記』本文とほぼ同じになってる、ってことなんす。
なので、
『日本書紀』第四段〔本伝〕と比べると、違う!
ってなるのですが、
『日本書紀』第四段〔一書1〕と比べると、だいたい同じ!
ってなるんです。ココがポイント!
一応、『日本書紀』的には〔本伝〕が中心とされるので、以下、国生みの違いについては、第四段〔本伝〕と『古事記』を比べて解説していきますが、そもそも論、〔一書1〕と比較したときには共通点の方が多いことはチェックされてください。
本サイトでは、『日本書紀』の〔一書〕群は、〔本伝〕の差異化として文献学的に解釈してますので、その観点からすると『古事記』も差異化の一つとして位置づけられます。
ちなみに、これは、編纂当時の歴史的背景が絡む内容なので、詳細は別エントリで詳しく。要は、国家プロジェクトである『日本書紀』と、皇太子教育のために急遽作られた『古事記』の、編纂目的・背景の違いによるものです。
と、いうことで、前置きが長くなりましたが、以下、『日本書紀』第四段〔本伝〕と『古事記』を比べての国生み神話の違いをポイント解説。
『日本書紀』と『古事記』の国生み神話の違いは以下5つ。
①目的、狙いが違う
『日本書紀』と『古事記』の編纂動機、目的が違います。なので、同じ「国生み」なんですが違うところが出てくる。
目的の違いは以下、
| 『日本書紀』 | 『古事記』 |
| 国の歴史書。対外向けに日本という国のスゴさを伝えることが目的。 →最先端理論をもとに創意工夫によって独自の神話を構築。 |
天皇家の私的歴史書。皇太子教育用のテキストとして編纂。天皇家がこの地を統治する正当性を示すことが目的。 →一本の物語として分かりやすく神話を構築。 |
『日本書紀』がたくさんの異伝を併載してるのは、目的が「対外的に日本という国のスゴさを示すこと」であり、そのためにたくさんの伝承があったほうがいいから。多くの神話伝承がある=文化の厚み、国のスゴさ、なので。コレにより、『日本書紀』版国生みは、本伝+異伝10個、計11個の伝承が存在。
一方の『古事記』は、天皇家の私的歴史書として、皇太子教育用のテキストとして編纂されたため、物語としては一本。異伝なし。分かりやすいし、物語としても洗練されてる感じ。
まず、そもそもの、目的が違うところから編纂された日本神話的国生み、だから数もバリエーションも全然違う、てことをチェック。
次!
②国生みの出発点・起点が違う
| 『日本書紀』 | 『古事記』 |
| 伊奘諾尊と伊奘冉尊、二神の主体的な行動(道の働き)による国生み。 | 天神の指令による国生み。 |
国生み神話の冒頭、その出発点、起点が違います。
『日本書紀』は伊奘諾尊と伊奘冉尊という非常に尊貴な二神が、自らの主体的な意志・行動により国生みをしようぜ、というスタートになってる。
※二神の「主体性」の内実は、乾と坤が本来的に持つ道の働き。易をベースにした思想体系あり。→日本神話的易の概念|二項対立の根源とその働きによって宇宙はつくられ動いている
一方の『古事記』は、天神と呼ばれる、伊耶那岐命・伊耶那美命より格上の尊貴な神々が設定されており、この指令により国生みが開始される形。
天神は、最初の「国の修理固成」指令や、途中の是正指導など、国生みに深く関与。天神が起点となってるのが『古事記』です。
シンプルに、最初の出発点、起点が違うと、
- 『日本書紀』は、二神による国生み
- 『古事記』は、天神による国生み
ということになり、意味合いが変わってくるのです。コチラ、次の内容と合わせて後ほど詳細解説。
次!
③伊奘諾尊と伊奘冉尊の格が違う
| 『日本書紀』 | 『古事記』 |
| 伊奘諾尊と伊奘冉尊は至尊の存在。 | 伊耶那岐神と伊耶那美神は天神に次ぐ存在。 |
先程の続き的内容。
『日本書紀』はそもそも、「神世七代」というのが最高に尊い存在として位置付けられていて、その最後の世代、7代目である伊奘諾尊・伊奘冉尊も格上、至尊。
一方の『古事記』は、天神と呼ばれる、「神世七代」よりもさらに格上の、非常に尊貴な神々が設定されており、伊耶那岐命・伊耶那美命は次順の存在。指示命令される立場。
上記、②③をまとめると、
『日本書紀』が神世七代を至尊と位置付け、その最後の世代の伊奘諾尊・伊奘冉尊による国生みとすることで、誕生する大八洲国を神聖化しようとしてるのに対して、『古事記』は神世七代よりもさらに格上の天神を登場させ、その関与により『日本書紀』以上に大八嶋国を神聖化しようとしてる、ということなんです。
コレ、国生みに限らず、天地開闢からずっと『古事記』的には『日本書紀』より尊貴に、『日本書紀』よりスゴく、、という上に持っていこうとする力が働いてる経緯あり。
次!
④国生み途中の間違いの修正方法が違う
| 『日本書紀』 | 『古事記』 |
| 伊奘諾尊(陽神)主導による修正 | 伊耶那岐神は間違いを知りながら結局交合してしまう。修正は天神の占いを通じて。 |
国生みの途中、二神は手順を間違えるという過誤を犯すのですが、このミステイクの修正方法が違います。
『日本書紀』は、伊奘諾尊の陽神としての存在感、位置付けが絶対的。陰神である伊奘冉尊を指導、主導する役回り。途中の伊奘冉尊の過誤も、伊奘諾尊が自ら「それあかんやろ」と言ってやり直す形。
一方の『古事記』は、天神の位置付けが絶対。伊耶那岐命・伊耶那美命の二神を指導、主導する役回り。途中の伊耶那美命の過誤は、伊耶那岐命は「あかんような気がする・・・」と言ってそのまま交合してしまう。結果、淡嶋や水蛭子が生まれてしまう。そのことを天神に報告し、指示を仰ぐことでやり直しになります。
このように、国生み途中の間違いについて、その修正方法が全然違う、それはそもそも、二神の位置付けが違うところからきてること、しっかりチェック。
次!
⑤誕生する嶋がビミョーに違う
| 『日本書紀』 | 『古事記』 |
| 大八洲国 ※神名付与なし | 1回目:淡嶋・水蛭子 2回目:大八嶋国+6つの嶋 ※神名付与あり |
誕生する嶋についても多少違いあり。
『日本書紀』は、途中での間違いが修正されているので、産み損ない的な嶋は誕生しません。そのまま大八洲国が誕生。
『古事記』は、間違いのまま産んでしまうので水蛭子、で淡嶋、水蛭子が誕生。これらは流したり、子への不算入とします。その後、天神にお伺いを立て、正しい手順で産んだことで大八嶋国が誕生。プラスアルファで4つの嶋。
特に『古事記』の場合は、産んだ嶋に神名を付与してるのもポイントです。コレ、系譜を重視する『古事記』ならでは。
ということで、
『古事記』と『日本書紀』の国生みの違い、まとめます。
- 目的、狙いが違う
- 国生みの出発点・起点が違う
- 伊奘諾尊と伊奘冉尊の格が違う
- 国生み途中の間違いの修正方法が違う
- 誕生する嶋がビミョーに違う
ということで、5つチェックされてください。
ということで、以下、
『日本書紀』『古事記』の伝える国生み伝承をそれぞれご紹介します。各論の詳細は別エントリでチェックされてください。

『古事記』と『日本書紀』の伝える国生み神話の現場
ここからは、大きく2つ。『日本書紀』と『古事記』の国生み神話の現場をお届け。
これまでチェックしてきた違いに注目しながらチェックです。
続けて『古事記』をチェック。
『古事記』上巻 国生み
ここにおいて、天神諸々の命をもって、伊耶那岐命・伊耶那美命の二柱の神に詔して「この漂っている国を修理め固め成せ」と、天沼矛を授けてご委任なさった。
そこで、二柱の神は天浮橋に立ち、その沼矛を指し下ろしてかき回し、海水をこをろこをろと搔き鳴らして引き上げた時、その矛の末より垂り落ちる塩が累なり積もって嶋と成った。これが淤能碁呂嶋である。
その嶋に天降り坐して、天の御柱を見立て、八尋殿を見立てた。ここに、その妹伊耶那美命に「汝の身はどのように成っているのか。」と問うと、「私の身は、出来上がっていって出来きらないところが一つあります」と答えた。ここに伊耶那岐命は詔して「私の身は、出来上がっていって出来すぎたところが一つある。ゆえに、この私の身の出来すぎたところをもって、汝の身の出来きらないところに刺し塞いで、国土を生み成そうとおもう。生むことはどうだろうか」と言うと、伊耶那美命は「それが善いでしょう」と答えた。
そこで伊耶那岐命は詔して「それならば、私と汝とでこの天の御柱を行き廻り逢って、みとのまぐはいをしよう。」と言った。このように期って、さっそく「汝は右より廻り逢いなさい。私は左より廻り逢おう。」と言い、約り終えて廻った時、伊耶那美命が先に「ほんとうにまあ、いとしいお方ですことよ。」と言い、その後で伊耶那岐命が「なんとまあ、かわいい娘だろうか。」と言った。
各が言い終えた後、(伊耶那岐命は)その妹に「女人が先に言ったのは良くない。」と告げた。しかし、寝床で事を始め、子の水蛭子を生んだ。この子は葦船に入れて流し去てた。次に、淡嶋を生んだ。これもまた子の例には入れなかった。
ここに、二柱の神は議って「今、私が生んだ子は良くない。やはり天神の御所に白しあげるのがよい。」と言い、すぐに共に參上って、天神の命を仰いだ。そこで天神の命をもって、太占に卜相ない「女の言葉が先立ったことに因り良くないのである。再び還り降って改めて言いなさい。」と仰せになった。
ゆえに反り降りて、更にその天の御柱を先のように往き廻った。ここに、伊耶那岐命が先に「なんとまあ、かわいい娘だろうか。」と言い、その後に妹伊耶那美命が「なんとまあ、いとしいお方ですこと。」と言った。
このように言ひ終わって御合して生んだ子は、淡道之穗之狹別嶋。次に、伊豫之二名嶋を生んだ。此の嶋は、身一つにして顔が四つ有る。顔毎に名が有る。伊豫国を愛比売といい、讚岐国を飯依比古といい、粟国を大宜都比売といい、土左国を建依別という。次に、隠伎之三子嶋を生んだ。またの名は天之忍許呂別。次に、筑紫嶋を生んだ。この嶋もまた、身一つにして顔が四つ有る。顔毎に名が有る。筑紫国は白日別といい、豊国は豊日別といい、肥国は建日向日豊久士比泥別といい、熊曾国を建日別という。次に、伊岐嶋を生んだ。またの名は天比登都柱という。次に、津嶋を生んだ。またの名は天之狹手依比売という。次に、佐度嶋を生んだ。次に、大倭豊秋津嶋を生んだ。またの名は天御虚空豊秋津根別という。ゆえに、この八嶋を先に生んだことに因って、大八嶋国という。 (引用:『古事記』上巻より)

●詳細解説コチラ→ 『古事記』国生み原文と現代語訳と解説|伊耶那岐命と伊耶那美命の聖婚と大八嶋国誕生の物語
違いの1つ目。国生みの出発点・起点が違う、という点は、
「ここにおいて、天神諸々の命をもって、伊耶那岐命・伊耶那美命の二柱の神に詔して「この漂っている国を修理め固め成せ」と、天沼矛を授けてご委任なさった。」とあり、そもそも天神の命から始まってます。途中の過誤修正も天神が起点になってますよね。
違いの2つ目、伊奘諾尊と伊奘冉尊の格が違う、という点では、上記同様、二神が天神の下。二神より上の天神が非常に尊貴な位置付けで、その尊い神が主導して生んだ国は尊い、という体(体裁)になってます。
違いの3つ目。国生み途中の間違いの修正方法が違う点。コチラは、「各が言い終えた後、(伊耶那岐命は)その妹に「女人が先に言ったのは良くない。」と告げた。しかし、寝床で事を始め、、、」とあるように、伊耶那岐命が間違いを理解していながら誘惑に克てませんでした、、的な体裁。
そして、「そこで天神の命をもって、太占に卜相ない「女の言葉が先立ったことに因り良くないのである。再び還り降って改めて言いなさい。」と仰せになった。」とあり、天神が占いにより原因追求、その結果を持って二神に是正指導する形になってます。
違いの4つ目。誕生する嶋がビミョーに違う点については、コチラ。
| 1 | 淡道之穗之狹別嶋 | 淡路島 |
| 2 | 伊豫之二名嶋(伊豫国を愛比売、讚岐国を飯依比古、粟国を大宜都比売、土左国を建依別) | 四国 |
| 3 | 隠伎之三子嶋(天之忍許呂別) | 隠岐島 |
| 4 | 筑紫嶋(筑紫国は白日別、豊国は豊日別、肥国は建日向日豊久士比泥別、熊曾国を建日別) | 九州 |
| 5 | 伊岐嶋(天比登都柱) | 壱岐 |
| 6 | 津嶋(天之狹手依比売) | 対馬 |
| 7 | 佐度嶋 | 佐渡 |
| 8 | 大倭豊秋津嶋(天御虚空豊秋津根別) | 本州 |
誕生した大八嶋国のうち、淡道之穗之狹別島(淡路島)、伊岐島(壱岐)、津島(対馬)が、『日本書紀』と違う箇所です。
ということで、
以上、そのほかの細かい違いをまとめると以下の通りです。
| 第四段 本伝 | 『古事記』 |
| - | 天神指令+矛下賜 |
| 天浮橋に立ち協議、矛を指し下ろし国を探る、滄溟を獲る | 天の浮橋に立ち矛差し下ろしかき回す。 |
| 矛の鋒から滴瀝る潮が凝りて島を成す。磤馭慮嶋と名付ける | 矛の末より垂り落ちる海の水が、累なり積もって嶋と成った。これが淤能碁呂嶋。 |
| 二神が降居、夫婦と為り洲国を産生もうとする | 二神が降居 |
| 磤馭慮嶋を国中柱とする | 八尋之殿を見立て、天柱を見立てる |
| - | 身体問答 |
| 左旋右旋 | 左旋右旋 |
| 先唱後和(間違い) | 先唱後和(間違い) |
| 陽神悦ばず、やり直し指示、陽神主導 | 夫婦となり水蛭子、淡嶋を生む 水蛭子は葦船で流す、淡嶋は子の数に入れず |
| - | 天に上り、天神に奏上 |
| - | 天神、太占し教示、再降下指令 |
| 左旋右旋 | 左旋右旋 |
| 先唱後和 | 先唱後和 |
| 身体問答 | - |
| 交合し夫婦と為る | 御合いする |
| 淡路洲を胞となすが快ばず | - |
| 大八洲国を生む | 大八嶋国を生む |
| ポイント ・天神無し、二神の協議による国生み ・矛で探り獲たのは国 ・磤馭慮嶋を、国中柱とする ・間違い1回。先唱後和のみ ・陽神主導、男女性差強調 ・淡路洲は胞として使用するのみ |
ポイント ・天神の指令、関わりによる国生み ・矛をさしおろし、かき回す ・淤能碁呂嶋で、八尋之殿と天柱を見立てる ・間違い1回。天神の教示により修正 ・二神無知、男女セット ・水蛭子・淡嶋を生むが流す・子への不算入 |
これ、分かりやすいんじゃない???
最終ゴールは大八洲国/大八嶋国の尊貴化、神聖化。これは不変。
で、そのための結婚=儀礼=厳粛な手続き・ルールに則る、これも不変。
しかし、『古事記』では、そこに天神指令&関与を入れてきたってことですね。もちろん、最終ゴールである「大八嶋国の神聖化」が念頭にあり。
つまり、別の観点から大八嶋国の尊貴化、神聖化を図ってる、とも言えて。
なんせ、あの天神様が、、直接指令を下した訳ですから!尊くない訳がない!
ということでチェックです。

『古事記』と『日本書紀』の伝える国生み神話の共通点
違いだけでなく、逆に、共通するところは以下の通り。
①矛を使って嶋を形成するのは同じ
『日本書紀』版国生みも、『古事記』版国生みも、矛を使って最初の嶋(小野ゴロ島)を形成するのは同じです。
②結婚=儀礼として位置づけているのは同じ
『日本書紀』版国生みも、『古事記』版国生みも、いずれも結婚=儀礼として位置付けているのは同じです。
両方の伝承に共通する、手続き臭さはまさにこれで。
結婚=儀礼
儀礼には、きちんとした手順、ルールがあって、、ココでいう「結婚儀礼」とは、
- 身体問答
- 左旋右旋
- 先唱後和
- 交合結婚
のこと。ただし、『日本書紀』と『古事記』で若干の前後あり。
しかも!各手順で則るべきルール細目があって、、そのルールとは
易の概念に基づく「陽主導」であること。
なので、先ほどの手順に当て込むと、
- 身体問答・・・陽が先、陰が後
- 左旋右旋・・・陽が左旋、陰が右旋
- 先唱後和・・・陽が先、陰が後
- 交合結婚・・・ここは、、、特になし。二人で交合だから。
となるわけです。陽=伊奘諾尊・伊耶那岐命、陰=伊奘冉尊・伊耶那美命。
大事なのは、きちんとした手順に沿って行われた儀式は「正式なもの」であり、「神聖なもの」であり、その結果として誕生する大八洲国(大八嶋国)も正当なものであり、神聖なものであると言えるようになるってことですね。
ということで、
まとめます。
| 相違点 | ①目的、狙いが違う ②国生みの出発点・起点が違う ③伊奘諾尊と伊奘冉尊の格が違う ④国生み途中の間違いの修正方法が違う ⑤誕生する嶋がビミョーに違う |
| 共通点 | ①矛を使って嶋を形成する ②結婚=儀礼として位置付けている |
古事記と日本書紀の国生み神話の違い まとめ
古事記と日本書紀の「国生み神話」の違い
をテーマにお届けしましたが、いかがでしたでしょうか?
『古事記』と『日本書紀』、同じ「国生み神話」を伝える書物ですが、比較する伝承によっては、同じと言えたり、違うと言えたりします。
国生みを伝える箇所を図解してみるとこうなる。

要は、『日本書紀』第四段は、〔本伝〕のほかに異伝である〔一書〕が全部で10個あり、この中で、〔一書1〕の内容が『古事記』本文とほぼ同じになってる、ってことなんす。
なので、
『日本書紀』第四段〔本伝〕と比べると、違う!ってなるのですが、『日本書紀』第四段〔一書1〕と比べると、だいたい同じ!ってなるんです。ココがポイント!
その中で、『日本書紀』第四段〔本伝〕と比べた場合は、
| 相違点 | ①目的、狙いが違う ②国生みの出発点・起点が違う ③伊奘諾尊と伊奘冉尊の格が違う ④国生み途中の間違いの修正方法が違う ⑤誕生する嶋がビミョーに違う |
| 共通点 | ①矛を使って嶋を形成する ②結婚=儀礼として位置付けている |
ということで、チェックしておいてください。
神話を持って旅に出よう!
国生み神話のもう一つの楽しみ方、それが伝承地を巡る旅です。以下いくつかご紹介!
●上立神岩:伊奘諾尊と伊奘冉尊が柱巡りをした伝承地
●自凝神社(おのころ神社):伊奘諾尊と伊奘冉尊の聖婚の地??
●絵島:国生み神話の舞台と伝えられるすっごい小さい島。。
●神島:国生み神話の舞台と伝えられるこちらも小さな島。。
国生み神話の詳細解説!必読です!
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




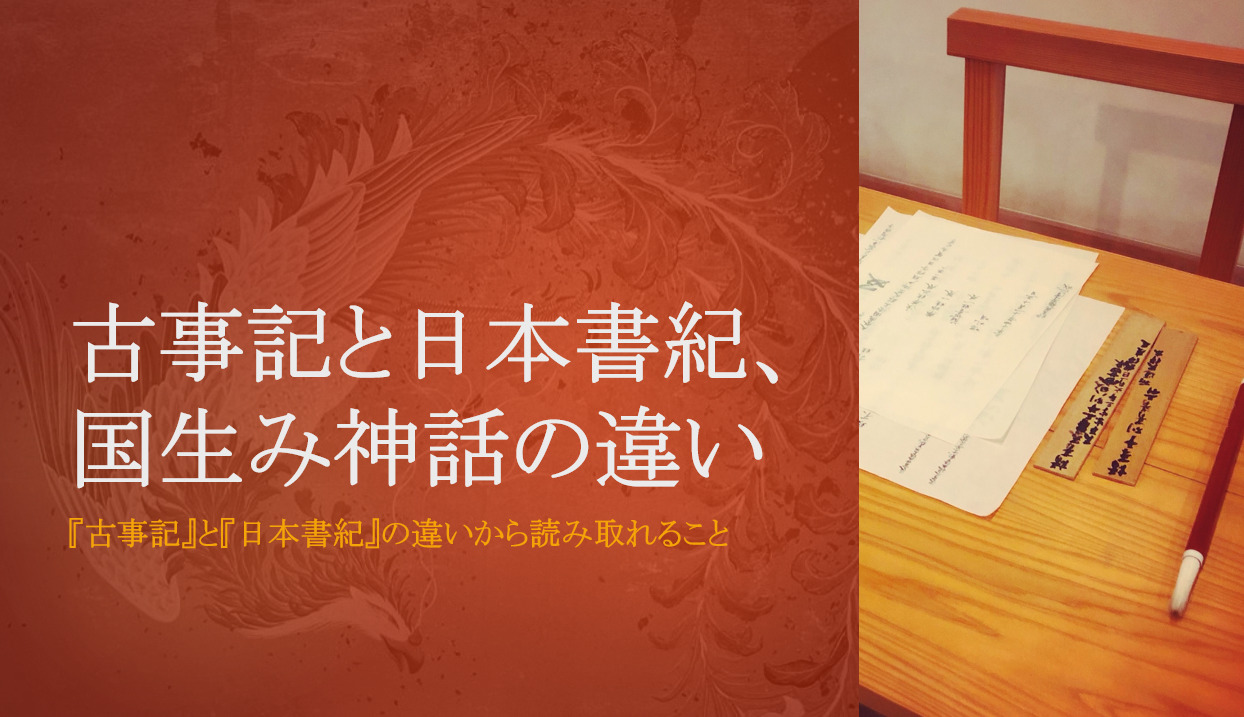



















『日本書紀』巻第一(神代上)第四段〔本伝〕
●詳細解説コチラ→ 『日本書紀』巻第一(神代上)第四段 本伝 ~聖婚、洲国生み~
なんか、、、スゴイ、、儀式っぽい、というか、説明くさいというか、、でも、実はコレがミソ。大事なところ。結婚=儀式として神聖化を図ってるんです。
協議から始まって、柱の獲得、柱巡り、先唱後和、身体問答、交合を経て、、、ようやく国生みという流れ。
違いの1つ目。国生みの出発点・起点が違う、という点では、
「伊奘諾尊と伊奘冉尊の二柱の神は、天浮橋の上に立って共に計り、「この下の底に、きっと国があるはずだ。」と言った。」とあり、伊奘諾尊と伊奘冉尊の協議が出発点。二神が主体的に国生みをしてます。
違いの2つ目、伊奘諾尊と伊奘冉尊の格が違う、という点では、上記同様、そもそも二神が非常に尊貴な位置付けになっており、その尊い神が生んだ国は尊い、という体(体裁)になってます。
違いの3つ目。国生み途中の間違いの修正方法が違う点。コチラは、「陽神はそれを悦ばず、「私が男だ。理の上では、まず私から唱えるべきなのだ。どうして女が理に反して先に言葉を発したのだ。これは全く不吉な事だ。改めて巡るのがよい。」と言った。」とあるように、陽神主導で修正を図ってます。
違いの4つ目。誕生する嶋がビミョーに違う点については、コチラをチェック。
誕生した大八洲国の8つの洲のうち、色付けをした、越洲(北陸道)、大洲(大島)、吉備子洲(児島半島)が『古事記』と違う箇所です。