多彩で豊かな日本神話の世界へようこそ!
日本最古の書『古事記』をもとに、
最新の文献学的学術成果も取り入れながら、どこよりも分かりやすい解説をお届けします。
今回は、
『古事記』の神武東征神話を分かりやすく解説するシリーズ、第2回目。「大和初戦敗退と五瀬命の死」をお届けします。
『古事記』中巻|神武東征神話② 大和初戦敗退と五瀬命の死
目次
『古事記』中巻|神武東征神話② 大和初戦敗退と五瀬命の死の概要
『古事記』中巻の神武天皇代をもとにお届けします。前回の内容、これまでの経緯はコチラ↓を確認ください。
そのうえで、、
ポイント3つ
①大和の地での敗戦には理由あり
日向の地を出てから岡田宮1年、多祁理宮7年、高嶋宮8年と計16年もの歳月を費やし、ようやく踏み入れた大和の地。だったんですが、「登美能那賀須泥毘古」が立ちはだかり兄の五瀬命が傷を負い大きな作戦変更を余儀なくされる、、
この大和の地での敗戦にはしっかり理由があり、それが「日神の御子なのに日に向かって戰ってる」というもの。日神=東から昇る太陽が前提としてあって、それに対して、神武たちの東征軍は大阪から大和盆地へ、方向的に西から東へ戦うってことなんで、太陽に向かって戦ってることになる。これ、日神の御子としては逆向き・反目になってるので加護を得られないというロジック。
今回の神話の大前提としてしっかりチェック。
次!
②作戦変更、結果的に紀伊半島ぐるっと一周へ
日神=東から昇る太陽の加護を得るには、背に日を負って撃つ必要があり、東から西へ、方向を逆にしないといけない。なので、紀伊半島を南下しぐるっと一周。熊野から宇陀を経て大和に入るという作戦へ変更することになります。
敗戦を機に自覚した出自=日神の御子であること、をもとにした作戦変更であることをしっかりチェック。
次!
③長兄の死により、東征の目的に敵討ちが追加されることになる
大阪湾を南へ、和歌山県和歌山市付近へ来たところで長兄の五瀬命が亡くなってしまいます。なんてこった。。この、敗戦からの長兄の死は、それまでの理想追求型の東征というプロジェクトに「報復(敵討ち)」という新たな目的を付与することになります。これ、東征神話的に非常に重要な転換点として位置付けられるのでチェックしておいてください。

↑上空から、和歌山市を望む。左上の突き出てる半島が加太の岬です。ここに神武の船団が、、、ロマンが広がりますっ!
以上、まとめると
- 大和の地での敗戦には理由あり
- 作戦変更、結果的に紀伊半島ぐるっと一周へ
- 長兄の死により、東征の目的に敵討ちが追加されることになる
の3点をしっかりチェック。
最後に、
当サイトとしては、是非、正史『日本書紀』と比較してチェックいただきたい!その方が、『古事記』の注力しているポイントがとっても分かりやすくなる。コチラ!
それでは本文をどうぞ!
『古事記』中巻|神武東征神話② 大和初戦敗退と五瀬命の死の本文
古事記 : 国宝真福寺本 中巻 国立国会図書館デジタルライブラリより その国より上りいく時、浪速の渡を經て、青雲の白肩津に停泊した。この時、登美能那賀須泥毘古が軍を興し待ちむかえて戰った。そこで船に入れていた楯を取って下り立った。ゆえに、その地を號て楯津という。今には、日下の蓼津と云う。
ここに、登美毘古と戰った時、五瀬命が手に登美毘古の痛矢串を負った。ゆえに、「私は日神の御子であり日に向かって戰うのは良くない。だから、賎しき奴から痛手を負った。今よりは行き廻って背に日を負うて撃とう。」と誓って、南の方より廻った時、血沼海に到って、其の手の血を洗った。それで「血沼の海」と謂う。其地より廻り、紀國の男之水門に到って、「賎しき奴の手を負って死ぬのか(死んでなるものか)」と男建して崩りなされた。その水門を號て「男水門」と謂ふ。陵は紀國の竃山に在る。
故、從其國上行之時、經浪速之渡而、泊青雲之白肩津。此時、登美能那賀須泥毘古自登下九字以音興軍待向以戰、爾取所入御船之楯而下立、故號其地謂楯津、於今者云日下之蓼津也。於是、與登美毘古戰之時、五瀬命、於御手負登美毘古之痛矢串。故爾詔「吾者爲日神之御子、向日而戰不良。故、負賤奴之痛手。自今者行廻而、背負日以擊。」期而、自南方廻幸之時、到血沼海、洗其御手之血、故謂血沼海也。從其地廻幸、到紀國男之水門而詔「負賤奴之手乎死。」男建而崩、故號其水門謂男水門也、陵卽在紀國之竈山也。(引用:『古事記』中巻 神武東征神話より)
※現代語訳について原文中の尊敬語は冗長になるため原義を損なわない範囲で通常の言葉に変換。また、口誦性の投影による接続語(爾、故、及、於是、など)の頻用も原義を損なわない範囲で簡略化。
『古事記』中巻|神武東征神話② 大和初戦敗退と五瀬命の死の解説
『古事記』版神武東征神話、冒頭部分、いかがでしたでしょうか?
日向の地を出てから計16年もの歳月を経てようやく辿り着いた大和の地だったのに、、いきなり戦闘になり、兄が死んでしまう、、神武の無念さたるやいかほどか、、そんなロマンに思いを致しつつ。。。
以下詳細解説。
『古事記』中巻|神武東征神話② 大和初戦敗退と五瀬命の死のまとめ
大和初戦敗退と五瀬命の死
日向の地を出てから岡田宮1年、多祁理宮7年、高嶋宮8年と計16年もの歳月を費やしようやく踏み入れた大和の地でしたが、、情報不足と無自覚(≒おごり)により、初戦敗退。しかも、その代償を「兄の死」という形で払う事になりました。
神武の無念は深く、以後、東征の目的に「仇討ち」が追加されることになります。「建国」という理想追求だけでなく、「仇討ち・復讐」のための東征といった新たな段階に入る訳で、その意味で、このシーンは非常に重要なのです。
続きはコチラ!熊野陸難と天照大神・高木神の救援
本シリーズの目次はコチラ!
『日本書紀』版東征神話の解説はコチラ!
神話をもって旅に出よう!
神武東征神話のもう一つの楽しみ方、それが伝承地を巡る旅です。以下いくつかご紹介!
● 盾津聖蹟顕彰碑|住宅地のなかに忘れ去られたように建っている碑
●茅淳の「山城水門」伝承地:神武天皇聖蹟雄水門顕彰碑
天神の森公園の中。「水門」という名の通り、古代このあたりは海だった模様。。
●竃山伝承地
本殿の背後には彦五瀬命の墓と伝える「竈山墓」(宮内庁治定墓)があります。
こちらの記事もどうぞ。オススメ関連エントリー
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




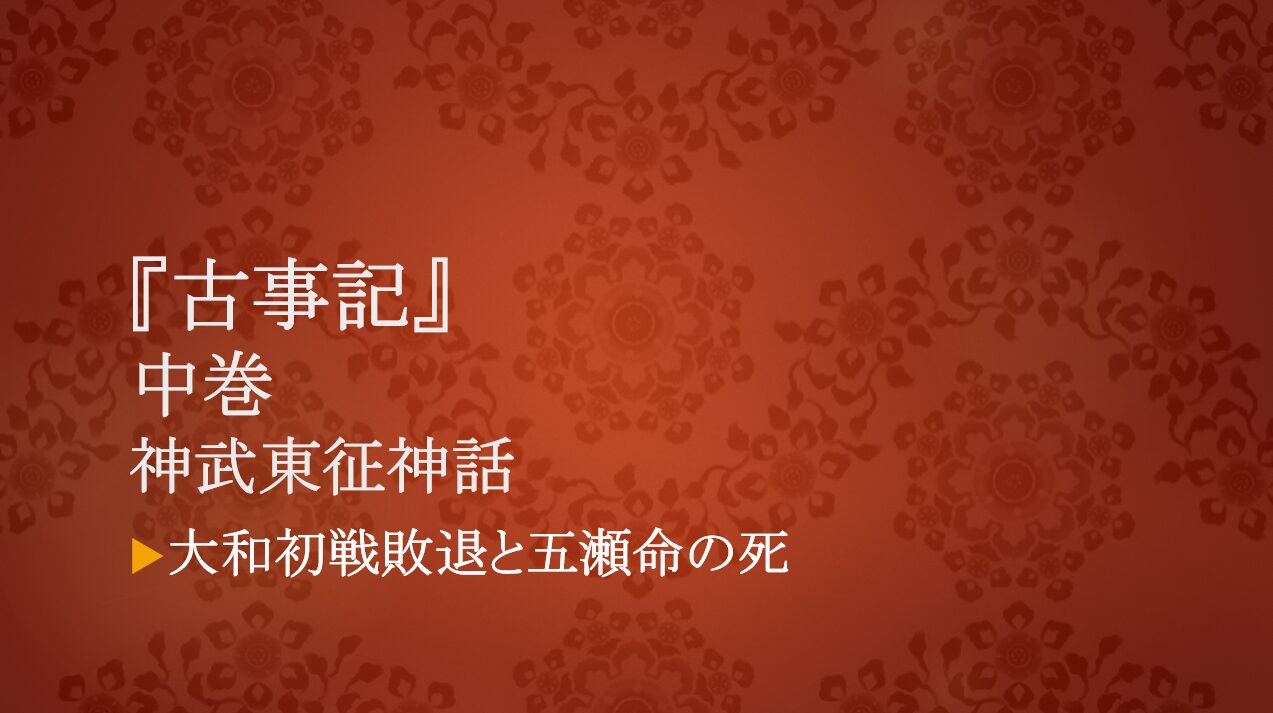


























先に言葉の解説を少し。
「浪速の渡」=大阪市東区上町台地の北端から北区天満付近にわたる地域とされてます。
「青雲の白肩津」=「青雲」は「白」にかかる枕詞。「白肩」は大阪府東大阪市日下町から枚岡町にかけての地とされてます。
ここでのポイント1つ。
①古代の大阪湾は、広大な潟湖が平野の奥深くまで入り込んでいた!?
古代の大阪湾は現在の姿とは全然ちがっていて、、この周辺は、大阪湾から東へ「生駒山」西麓までいたる広大な潟湖が広がっていたようです。潟湖とは、現在は「ラグーン」と呼ばれ、湾が砂州によって外海から隔てられて湖沼化した地形のこと。
↑7世紀前後の古代想定地図(枚方市教育委員会主催「シンポジウム淀川流域の交通史」より)
あくまで7~8世紀ごろの地形なので、神話の時代は別でしょ、てのが大前提。ですが『日本書紀』編纂前後の頃なんで、参考にはなると思います。
大阪湾から東へ「生駒山」西麓までいたる広大な潟湖が広がり、上町台地が半島のように突き出ていた、、、「浪速の渡」はこの付近と考えられます。
なお、『日本書紀』では、「難波の碕」として伝え、潮流が激しく進軍に難儀したとしています。とても速い潮流=浪が速い=浪速。からの、訛って「難波」だと。
そして、「青雲の白肩津」は、上記地図の「日下」付近。古代は「日下の入江」と言われ、船着場=津になっていた模様。
一応、軍船を率いていた訳で、大軍を大和の地深くまで上陸させるために、このルートが選ばれたのだと推測されます。
次!
→ついに登場、東征神話における最大の敵、那賀須泥毘古!
「登美能那賀須泥毘古」は、「登美」の「那賀須泥毘古」。
「登美」は、現在の奈良県奈良市鳥見町付近。
「那賀須泥毘古」は『日本書紀』では「長髄彦」と伝えていて、名前をそのまま解釈すると「スネの長い男」。「髄」は「スネ」の和名。膝から下(スネ)が長い=敵対者の異形性を表現したものと考えられます。
で、「とみ」とか「ながすね」について、『日本書紀』では以下のように伝えてます。
と言うことで、
もともと村の名前だった「長髄」。それにちなんで「長髄彦」→『古事記』で「那賀須泥毘古」。さらに、金鵄飛来というスーパーミラクル確変イベント発生にちなんで「鵄邑」と改名。それが訛って「鳥見」へ。『日本書紀』ではココまで。
その後、歴史の時代に「鳥見郷」「鳥見庄」を経て、明治時代に富雄村の一部となり、昭和28年には富雄町が成立、その後奈良市に編入されて、現在は奈良県奈良市鳥見町。
『古事記』では詳しくは伝えてませんが、「那賀須泥毘古」はこの辺りを本拠地として、大和一帯を支配していたと考えられ、当然、情報網は構築されていた訳で、部外者が侵入してきたと聞けば「軍を興し待ちむかえて戰った(原文:興軍待向以戰)」って、地元民からしたら当然の反応であります。
そこで神武は「そこで船に入れていた楯を取って下り立った(原文:爾取所入御船之楯而下立)」と。
この文脈からすると、最初の戦いの場所は船着場付近=白肩津となります。一方で、『日本書紀』の場合は「孔舎衛坂で遮り合戦となった」と伝えていて。かなり場所が違う、、、
そして、
「その地を號て楯津という。今には、日下の蓼津と云う。」とあり、「その地」とは先ほど登場した「白肩津」で、大阪府東大阪市日下町から枚岡町にかけての地。
神武が楯をとって下りたったところから「楯津」。からの(後に訛って)「日下の蓼津」へ。
次!
→ここで長兄「五瀬命」が負傷。なんてこった
とは言いつつ、どれくらいの激戦具合だったのかよー分からんので、とりあえず「痛矢串」とは痛手を負わせる矢のこと。
ちなみに、『日本書紀』では「流れ矢が五瀬命の肘と脛に当たった」と伝えてます。
次!
→文脈から、「私は〜」以下の言葉は五瀬命が発したことになるんだが。。それでいいのか?!
東征神話という物語観点からすると、ここで自覚する「私は日神の御子であり」というのは極めて重要で、その自覚をもとに「日に向かって戰うのは良くない」「行き廻って背に日を負うて撃とう」ということで紀伊半島ぐるっと一周する大きな作戦変更につながる訳です。これ、『日本書紀』的には「神策」として伝えていて、神武が自ら見出したものになってるんですが、、『古事記』では、その一番重要な「神策」に相当する内容を五瀬命が言ったことになってる。。
これ、『古事記』的には五瀬命は特別に天皇に準じた文字遣いになってることがあるので、
(例えば「詔」。ここでも「詔「吾者〜」と使われていますが、本来、天皇(天子)が発する命令や言葉を「告げる」「発する」という意味。主語は天皇の言葉なんだけど五瀬命に使われてるってこと)
そういう位置付けが反映されてるものと考えられますが、、やはり、神話的ドラマツルギーからすると、これは神武であって欲しいところであります。。
ちなみに、、
「血沼海」は、大阪府の泉北・泉南にわたる海とされてます。
一応、付近には「茅渟神社」があります。
次!
從其地廻幸、到紀國男之水門而詔「負賤奴之手乎死。」男建而崩、故號其水門謂男水門也、陵卽在紀國之竈山也。
→「楯津」付近で負った「痛矢串」による傷が元で五瀬命が死んでしまう、、なんてこった
「紀國の男之水門」は、和歌山市の紀ノ川の河口付近とされてます。
伝承地はコチラ↓
で、
「賎しき奴の手を負って死ぬのか(死んでなるものか)(原文:負賤奴之手乎死)」とあり、「負賤奴之手」=賎しき奴の手を負って=卑しいやつから受けた傷で。「乎死」=死ぬのか?いや死なない!反語表現によって強調されてます。きっと悔しさや無念さでいっぱいだったに違いない。
この辺りも、『日本書紀』では「撫劒」と伝え、剣の柄に手をあててぎゅっと強い力で押さえる憤りの表現が使われていて劇的な雰囲気が表現されてます。
その上で、
「崩りなされた(原文:崩)」とあり、五瀬命の死に「崩」という漢字が使われてます。
これ、先ほども解説した通り、『古事記』における五瀬命が特別に天皇に準じた文字遣いになってる例。「崩」は本来、天皇(天子)の死に対して使われる特別な言葉なんだが、五瀬命に使われてます。
そして、
東征神話の物語観点から押さえておきたいポイントは、長兄の薨去は、神武にとって、兄の無念を晴らす「仇討ち」の意味を東征に加えることになるってこと。
古代では、「報復」を「義務」として定めていて、殺されたのが父であれば「不倶戴天」の敵として、相手が死ぬまで報復を止めません。
五瀬命は長兄なので、弟の神武は「報復の義務」を負う。これは「兵(武器)を反さず」という言葉で伝えられ、武器を執って仇を討ち果たすまでは止めてはならない、という意味。有名な「忠臣蔵」も同じ考え方です。
実際、東征の最終局面では、この五瀬命の薨去に思いを致し、断固とした決意をもとに、神武は「〜撃ちてし止まむ」「〜我は忘れじ、撃ちてし止まむ」と来目歌を歌って戦いに臨みます。
東征が、理想を追うだけではなく、報復をめざす新たな段階に入るという、極めて重要な意味を持つのが、この五瀬命の薨去なんです。しっかりチェック。
なお、
「陵は紀國の竃山に在る」は現在の竈山神社。