多彩で豊かな日本神話の世界へようこそ!
正史『日本書紀』をもとに、
最新の文献学的学術成果も取り入れながら、どこよりも分かりやすい解説をお届けします。
「神武東征神話を分かりやすく解説するシリーズ」今回は16回目。
テーマは、
中洲平定と事蹟伝承
遂に大和最大・最強の敵「長髄彦」を倒した神武こと「彦火火出見」。長兄のかたき討ちを果たし、東征神話における最大の山場を乗り越えました。残る課題は「建国・即位準備」。
建国は一日にして成らず。最大の敵を倒したからと言って即建国という訳にはいきません。入念な準備、それなりの体裁を整える必要あり。
今回も、概要で全体像をつかみ、ポイント把握してから本文へ。最後に、解説をお届けしてまとめ。
現代の私たちにも多くの学びをもらえる内容。日本神話から学ぶ。日本の神髄がここにあります。それでは行ってみましょう!
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
中洲平定と事蹟伝承|大和平野各地の土蜘蛛さんを叩いて平定完了!あとは東征の事蹟を伝えておきたい件
目次
中洲平定と事蹟伝承の概要
今回も『日本書紀』巻三「神武紀」をもとにお届け。前回の内容、これまでの経緯はコチラ↓をご確認ください。
改めて、建国に向けた課題は以下4つ。
- 中洲(=大和平野)平定
- 東征の事蹟にちなむ地名起源設定
- 宮殿造営
- 天皇にふさわしい嫁をもらう事
今回は、そのなかで、①と②をお届け。
大和最大の敵「長髄彦」を倒したものの、中洲(=大和平野)にはまだ小規模な敵勢力が残っていた次第。この方々も残らず駆逐する必要あり。
今回登場するのは「土蜘蛛」のみなさん。この「土蜘蛛」は頑強に抵抗する先住民を蔑んだ表現で、地を這ってるようなイメージ、、、結構すごい表現を使わはるのね。。。汗
いずれも、抵抗するから徹底的にやっつける訳で、これをもって中洲平定&東征の総仕上げとした次第。
この後で出てくる「宮殿造営」時には、その結果として「中洲の地は少しも騒乱が無い」と言い、平定が成し遂げられていることが分かります。
大和平野のあちこちへ軍隊を派遣し、平定を進めているイメージをもって読み進めましょう。
そして、もう一つの「東征の事蹟にちなむ地名起源設定」。東征にちなむ土地を「地名の起源伝承」としてまとめて伝えてます。
古代において重視された考え方や価値観として、
歴史的事蹟や人々の関心を寄せる事物などを、後の世に語り伝えること
というのがあります。
神武東征神話は、建国譚でもある訳で。王朝として、国家として、その創設にちなむ地名を「起源伝承」として残すことは、当然やるべきことであります。一方で、やっぱ、(個人的にも)残しておきたいといった動機もあるかと。スゲーことやったらそれを後世に伝えていきたい。。。ワイのこと忘れんでや、、的な。このあたり、今も昔も変わらない価値観だと思います。
以上2点をしっかりチェック。
場所とルートの確認
土蜘蛛のみなさんは全部で4種。
- 「新城戸畔」 @層富県の波哆の丘岬
- 「居勢祝」 @和珥の坂下
- 「猪祝」 @臍見の長柄の丘岬
- 「侏儒に似た者たち」 @高尾張の邑
地図上にプロットしてみる。

「新城戸畔」は、これまでもちょいちょい登場した女性酋長さんの類。各地に跋扈されていたようで、大和平野にもいた!
「居勢祝」「猪祝」の「祝」は神官のこと。その地の神に仕える者、祭祀を司る首長をいった模様。
高尾張邑にいた「侏儒に似た者たち」は「こびと」のこと。中国では昔、俳優として位置づけられていたようで。本文では「身の丈が低く手足が長い」としています。
いずれも、頑強に抵抗する先住民(土蜘蛛)なんで、神武は大和平野のあちこちへ軍隊を派遣し、平定を進めていった次第。
中洲平定と事蹟伝承の現代語訳と原文
己未の年(紀元前662年)春2月20日、彦火火出見は将たちに士卒の訓練を命じた。
この時、層富県の波哆の丘岬に「新城戸畔」という者がいた。また、和珥の坂下に「居勢祝」という者がいた。臍見の長柄の丘岬には「猪祝」という者がいた。これら三か所の土蜘蛛は、みな己の勇猛さを恃みにし、あえて帰順しなかった。彦火火出見はそこで、軍勢を分けて派遣し、これらをことごとく誅殺した。
また、高尾張邑に土蜘蛛がいて、その体つきは、身の丈が低く手足が長くて侏儒に似ていた。東征の軍は、葛で網を結い、急襲して一挙に殺した。これにより、その邑の名を改めて「葛城」という。
さてまた「磐余」の地のもとの名は「片居」または「片立」といった。東征の軍が賊を打ち破ったとき、たくさんの兵が集まりその地に満ちあふれた。これにより名を「磐余」と改めたのである。
あるいはこうも言う。以前に、彦火火出見は厳瓮にそなえた神饌を食し、西方を征討しに軍を出陣させた。この時、磯城の八十梟帥らが、その地に大勢たむろしていた。果たして、彦火火出見と大きな戦いになり、ついに滅ぼされた。そこで、その地を「磐余邑」と名付けたのであると。
また東征の軍が雄叫びをあげた所を「猛田」といい、城をつくった所を「城田」という。また、敵の軍勢が戦死し倒れた死骸が、互いの臂を枕にして折り重なった場所を「頰枕田」という。
彦火火出見は、前年の秋九月に、ひそかに天香山の埴土を取り、それで八十平瓮を作り、自ら斎戒して神々を祭った。そして今、ついに天下を平定することができた。それゆえ、土を取った所を名付けて「埴安」という。
己未年春二月壬辰朔辛亥、命諸將、練士卒。是時、層富縣波哆丘岬、有新城戸畔者。又和珥坂下、有居勢祝者。臍見長柄丘岬、有猪祝者。此三處土蜘蛛、並恃其勇力、不肯來庭。天皇乃分遺偏師、皆誅之。又高尾張邑、有土蜘蛛、其爲人也、身短而手足長、與侏儒相類、皇軍結葛網而掩襲殺之、因改號其邑曰葛城。夫磐余之地、舊名片居、亦曰片立、逮我皇師之破虜也、大軍集而滿於其地、因改號爲磐余。
或曰「天皇、往嘗嚴瓮粮、出軍而征、是時、磯城八十梟帥、於彼處屯聚居之。果與天皇大戰、遂爲皇師所滅。故名之曰磐余邑。」又皇師立誥之處、是謂猛田。作城處、號曰城田。又賊衆戰死而僵屍、枕臂處、呼爲頰枕田。天皇、以前年秋九月、潛取天香山之埴土、以造八十平瓮、躬自齋戒祭諸神、遂得安定區宇、故號取土之處、曰埴安。(『日本書紀』巻三 神武紀より一部抜粋)※原文中の「天皇」という言葉は、即位前であるため、生前の名前であり東征の権威付けを狙った名前「彦火火出見」に変換。
中洲平定と事蹟伝承の解説
なんか、、ちょっと上から目線が強烈で、、、身体的な特徴を蔑みとして使ってるのがどうなんだろうと、、そんなロマンに想いを致しつつ、、、
以下詳細解説。
まとめ
中洲平定と事蹟伝承
大和最大の敵「長髄彦」を倒したものの、中洲(=大和平野)にはまだ小規模な敵勢力が残ってました。
今回登場した「土蜘蛛」のみなさん。いずれも、抵抗するから徹底的にやっつける訳で、これをもって中洲平定&東征の総仕上げとした次第。
この後で出てくる「宮殿造営」時には、その結果として「中洲の地は少しも騒乱が無い」と言い、平定が成し遂げられていることが分かります。
そして、東征の事蹟にちなむ地名起源設定。
歴史的事蹟や人々の関心を寄せる事物などを、後の世に語り伝えること。コレ超重要事項。
神武東征神話は、建国譚でもある訳で。王朝として、国家として、その創設にちなむ地名を「起源伝承」として残すことは、当然やるべきことであります。
中でも、「磐余」と「埴安」は超重要スポットとしてチェックです。
と、いうことで、「建国・即位準備」の4項目。
- 中洲(ちゅうしゅう=大和平野)平定
- 東征の事蹟にちなむ地名起源設定
- 宮殿造営
- 天皇にふさわしい嫁をもらう事
のうち、2項目を達成!続きまして、宮殿の造営だー!
続きはコチラ!ワイの宮をつくるのだ!
神武東征神話のまとめ、目次はコチラ!
神話を持って旅に出よう!
神武東征神話のもう一つの楽しみ方、それが伝承地を巡る旅です。以下いくつかご紹介!
●磐余邑顕彰碑:屈強な漢たちがあふれかえった伝承地?
●畝尾坐健土安神社:天香山の土採取に登場した土の神様をお祭りする神社!
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
日本神話の神様一覧|『古事記』をもとに日本神話に登場し活躍する神様を一覧にしてまとめ!
こちらの記事もどうぞ。オススメ関連エントリー
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
日本神話とは?多彩で豊かな神々の世界「日本神話」を分かりやすく解説!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




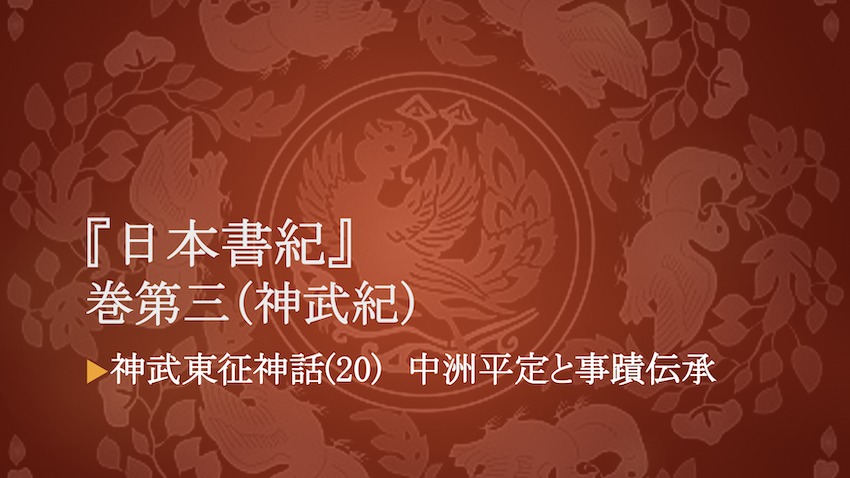























→年が明けて「己未の年」。紀元前662年に相当するとされてます。東征は5年目に突入。
春2月の「壬辰」が朔の辛亥は20日。神武は「将たちに士卒の訓練を命じ」ます。コレ、改めて、中洲平定へ向けた軍事教練としての位置づけ。
大和最大の敵「長髄彦」を倒したものの、中洲(=大和平野)にはまだ小規模な敵勢力が残っていた次第。この方々も残らず駆逐する必要あった次第。
あと、前回のエントリで「饒速日命」が長髄彦を殺して帰順したとありました。コレ、恐らく大軍勢を率いて帰順したはずで、この士(戦士)と卒(兵卒)を改めて東征軍に編入して調練する必要があったこと背景にあり。12月の戦いから年明けにかけて、「練」を通じて、元・長髄彦軍の動揺が収束し、東征の軍として戦える状態にしてた訳ですね。
次!
→土蜘蛛さん登場。
「層富県」は、現在の奈良県北部、奈良市・天理市・大和郡山市・生駒市・山辺郡にまたがる地域とされてます。
「波哆の丘岬」の「波哆」は、未詳ながら、添下郡赤膚山(唐招提寺の西にあったそうですが、、『通証』『集解』)または興福寺領波多庄(奈良市東南部『新編全集』)。「丘岬」は山の突端のこと。
「新城戸畔」は、女性首長。これまでにも登場した「名草戸畔」や「丹敷戸畔」と同じ。「新城」は、添下郡新木村で、現在の大和群山市新木町。
「和珥」は天理市和邇町周辺。崇神紀十年九月条に、「大彦命至於和珥の坂上」とあり、北陸道に通じる要衝だった模様。その「坂下」。
「居勢祝」の「居勢」は御所市古瀬(大和国葛上郡)とされますが、上記「和珥」と合わないので微妙、、、「祝」は神官のこと。その地の神に仕える者、祭祀を司る首長をいうか。。
「臍見の長柄の丘岬」は場所未詳。御所市名柄、または天理市長柄町か、、「猪祝」の「猪」は地名?「祝」は先ほど同様神官のこと。
「これら三か所の土蜘蛛は、みな己の勇猛さを恃みにし、あえて帰順しなかった」とあり、頑強に抵抗する先住民(土蜘蛛)がいた模様。
オモロー!なのは、これらの土蜘蛛さん、「丘岬」とか「坂下」とか、みんな平地じゃないところにいた訳で。平地=文明とすると、それ以外は未開。一応、枠組みをもとに整理されてます。
また、『摂津国風土記』に「土蛛」の注として「此の人恒に穴の中に居す。故に賤号を賜ひて土蛛と曰ふ」とあり、穴居の風俗ももっていたと推測されます。平地じゃないところで穴の中に住んでた方々、、、異質性の表現、その蔑み方がスゴイ、、、
いずれにしても、帰順しない方々は「ことごとく誅殺した」次第。
次!
→別タイプの土蜘蛛さんもいたようで、、、
「高尾張邑」は葛城地方、御所市西南部。
「その体つきは、身の丈が低く手足が長くて侏儒に似ていた。」とあり、「侏儒」とは「こびと」のこと。中国では昔、俳優として位置づけられていたそうです。
「葛で網を結い」とあり、「葛」はマメ科クズ属のつる性の多年草。確かにものすごいツルが生えるんで、網がつくれそう。それにしても、その網でこびとを一網打尽にした、って、、、こちらも蔑み感がハンパない、、、涙
ちなみに、「葛」はその根で食材の葛粉や漢方薬が作られます。 和名は、大和国吉野川上流の「国栖」が葛粉の産地であったことに由来。これはコレで東征神話でも登場してました。
ということで、、
以上で大和平定は終了。帰順しない者どもは徹底的に叩きましたという話。
後半は、事跡伝承です。
→東征の事蹟にちなみ「地名の起源伝承」として伝えてます。
コレ、古代において重視された考え方や価値観で。歴史的事蹟や人々の関心を寄せる事物などを、後の世に語り伝えるのって超大事。
例えば、『万葉集』にも、神功皇后による征韓伝承にちなむ「鎮懐石」に関連し、「天地の ともに久しく 言い継げと この奇し御魂 敷かしけらしむ」(814番)と歌ったり、
例えば、富士山を「~時じくぞ 雲は降りける 語り継ぎ 言ひ継ぎ行かむ 富士の高嶺は」(317番)と歌ったりして、ちょいちょい登場する重要事項であります。
神武東征神話は、建国譚でもある訳で。
王朝として、国家として、その創設にちなむ地名を「起源伝承」として残すことは、当然やるべきことであります。
特に注力しているのは2か所。「磐余」と「埴安」。
「磐余」は特に、神武が天皇として即位したときにその名に冠したくらい重要な地名。
↑即位にあたって「名付けて「神日本磐余彦火火出見天皇」と言う。」と伝えてます。
という、異なる地名起源伝承を併載。いずれの伝承であれ、神武の大和討伐にちなむ場所として「磐余」を伝えています。
次!
→別伝もあるぜと。先ほどの②部分。
「以前に、彦火火出見は厳瓮にそなえた神饌を食し、西方を征討しに軍を出陣させた。」とは、八十梟帥を国見丘で撃破した時を指します。
次!
→2か所登場。いずれも最後の戦いに関わる地と思われます。
「東征の軍が雄叫びをあげた」とありますが、該当する記述はなく、、、似たところでは盾津での雄叫び。
「猛田」は、現在の橿原市樋勝竹田町にあてる説がありますが未詳。
「頰枕田」も同様で場所未詳。
次!
→絶体絶命の危機的戦況をひっくり返した天香山土採取と丹生川上祭祀のこと。
これにより「遂に区宇を安定むること得たまふ」という平定にちなむ地名として伝えてる訳で、その意味で「埴安」は超重要。
ちなみに、奈良にはなんと、こちらの土の神様をお祭りしている神社があります!
ロマンだー。コレ、サイコーの神話ロマンです。