神武東征神話を分かりやすく解説するシリーズ
目次
日本神話.comでは、天地開闢から橿原即位までを「日本神話」として定義。東征神話は、その中で最大のクライマックスを彩るアツく奥ゆかしい建国神話であります。
言うと、
これを知らずして日本も神話も語れない!m9( ゚Д゚) メーン!
ということで、今回は14回目。テーマは、
兄磯城討伐と磐余制圧
宇陀、高倉山に登って判明した絶望的状況。周囲みんな敵だらけ。。そこで、天神からの教えにそって、丹生川上祭祀で賊虜の平伏を、つづく顕斎で高皇産霊尊の加護を祈願した神武。満を持して敵殲滅へ乗り出します。
殲滅にあたっては、大きく2段階で進行。
- まずは、国見丘を中心とした八十梟帥を殲滅
- その後、磐余にいる兄磯城らを殲滅
前回のエントリでは、ステップ①の「国見丘を中心とした八十梟帥殲滅」をお届けしました。今回はその②。
あふれるほど大勢いたと伝える磯城軍をどのように討伐したのか?
そんなロマンを探る事で、「兄磯城討伐と磐余制圧」が伝える意味を読み解きます。
今回も、概要で全体像をつかみ、ポイント把握してから本文へ。最後に、解説をお届けしてまとめ。
現代の私たちにも多くの学びをもらえる内容。日本神話から学ぶ。日本の神髄がここにあります。それでは行ってみましょう!
- 日本神話研究の第一人者である榎本先生監修。確かな学術成果に基づく記事です
- 日本神話全体の流れや構造を解き明かしながら解説。他には無い分かりやすい記事です
- 現代語訳のほか原文も掲載。日本神話編纂当時の雰囲気を感じてもらえます
- 登場する神様や重要ワードへのリンク付き。より深く知りたい方にもオススメです
兄磯城討伐・磐余制圧|戦う前に意思確認?臣下献策まま実行?それはきっと神武の成長と分かってきた感覚の件
兄磯城討伐・磐余制圧の概要
今回も『日本書紀』巻三「神武紀」をもとにお届け。ちなみに、前回の内容、これまでの経緯はコチラ↓をご確認ください。
今回のターゲットは、磐余の兄磯城。
「磐余」は地名。東征神話の最後で、「旧名を「片居」、または「片立」ともいう。東征軍が賊を打ち破ったとき、たくさんの兵卒が集まりその地に満ちあふれた。それにより地名を改め「磐余」とした。」と伝えます。
「兄磯城」はこのあたりの八十梟帥(屈強な敵兵士の意味)のドン。実は兄弟。弟に「弟磯城」がいます。二人合わせて「磯城彦」です。ヤンボー、マンボー、天気予報。
コレ、宇陀の宇賀志で登場した「兄猾・弟猾」と同じパターン。つまり「兄の劣弱、弟の優秀」という「兄弟譚」の類型。
例によって、兄は神武に抵抗し、弟は従順な態度を取ります。相変わらず、兄は良く分からない事をやり、弟はそんな兄を見て、状況を良く見て冷静に判断し、結果的に正しい選択をする。。。
流石だ、弟よ。兄はそんなお前をみて嬉しいぞ・・・ゴブッ←神武に討伐された
今回の重要ポイントは2つ。
- 兄磯城に勝利することで大和平野(奈良盆地)東側の制圧が完了すること。
- その上で、最大の敵「長髄彦」との最終決戦へ挑む流れであること。
しっかりチェックされてください。
場所とルートの確認
まずは、この地の重要性を確認。
ついに、、、ついに神武は大和の地を踏む。。
日向で東征発議し、東大阪の孔舎衛坂で打ちのめされて、さまざまな苦難を経てようやっとたどり着いた中洲=世界の中心地=約束の地。

イッツ大和平野!
もう何年経ったのか、、ずいぶん遠くまで来たもんだ、、、忍坂で残党を殲滅し、いよいよ大和平野に入った神武の胸に去来した想いとは・・・ ココ、神話ロマンを感じるポイントです。
ま、そんな感慨に浸る暇なんてなかったんですが、、、
目の前の敵、あふれんばかりの八十梟帥、兄磯城に集中する彦火火出見。決して負けられない戦いがそこにはある!
今回の、「兄磯城討伐と磐余制圧」は以下のような展開。

- まず、力の劣る女軍(小兵部隊)を進軍させ、敵主力部隊をおびき寄せる。
- 次に、男軍(主力部隊・精鋭機動部隊)を派遣し、墨坂の火を消す。戦意を喪失させる。
- その流れで、男軍は墨坂を越え敵の背後から攻撃し、先発の女軍と挟み撃ちで殲滅する。
と、、
特に、挟み撃ち部分、より詳細にみると、、、

という感じです。外山から忍坂周辺で兄磯城を殲滅したものと思われます。
高倉山で敵だらけの状況が判明したとき、その敵は主に2種類ありました。
- 山間部の八十梟帥・・・名前なし
- 平野部の八十梟帥・・・名前あり(兄磯城)
で、
山間部八十梟帥は、一気に「武力」で殲滅します。山の敵は文化レベルが低いという感じ。やや上から目線ですが、、。なので「武」の担当、将軍「道臣命」であります。
一方、平野部八十梟帥(磯城彦)は、武力は最後まで使いません。まず使者を派遣し降伏勧告から。平野の敵は文化レベルが高いから「文」の担当、「椎根津彦」が活躍します。
ということで、以下本文は、上記位置関係や、山と平野、武と文という対比構造をもとに読み進めると面白いと思います。
兄磯城討伐・磐余制圧の現代語訳と原文
11月7日に、東征軍は大挙して「磯城彦」を攻撃しようとした。
先ず、使者を派遣して「兄磯城」を召したが、兄磯城はその命に従わなかった。そこで、今度は八咫烏を派遣して召した。烏は兄磯城の軍営に到り鳴き声をあげ、「天神子が、お前を召されている。さあ、さあ(招きに応じよ)」と言った。兄磯城はこれを聞いて激怒し、「天圧神がやって来たと聞き、今まさに憤慨している時に、どうして烏めがこんなに嫌なことを鳴くのか。」と言い、弓を引きしぼって烏めがけて射ると、烏はすぐさま逃げ去った。
次に、八咫烏は「弟磯城」の家にやってきて鳴き声をあげて、「天神子が、お前を召されている。さあ、さあ。」と言った。この時、弟磯城は恐れ畏まって居ずまいを正し、「臣である私は、天圧神がやってこられたと聞き、朝に晩に大変かしこまっておりました。まったく素晴らしいことです、烏よ。あなたがこんな風に鳴いてくれたのは。」と言い、さっそく葉盤八枚を作って食べ物を盛り、烏をもてなした。
そして、烏のあとに従って彦火火出見のもとに参上し、「私の兄の兄磯城が、天神子がいらっしゃったと聞き、八十梟帥を集めて武器を準備し、決戦を挑もうとしております。早急に手だてを講じなさいませ。」と言った。
彦火火出見は、すぐさま将たちを集め、問うた。「今、兄磯城は、やはり反逆の意があり、召してもやって来ない。どうしたらいいだろうか。」 将たちは、「兄磯城は悪賢い賊です。まずは弟磯城を派遣してしっかりと諭し、あわせて兄倉下と弟倉下も説得させるのがよいでしょう。それでも帰順しないのであれば、その後に兵を挙げて戦いに臨んでも遅くはありません。」と申し上げた。
そこで弟磯城を遣わし、利害を明らかに示して分からせようとした。しかし、兄磯城らはなお愚かな謀に固執し、帰伏するのをよしとしなかった。
その時、椎根津彦が計略をめぐらせて言った。「この上は、まず我が女軍を遣わして、忍坂の道から出陣させましょう。これを賊が見れば必ずや精鋭部隊を残らずそこに向かわせるはずです。私は、勇猛な兵を馬で走らせ直ちに墨坂を目指し、菟田川の水を取って墨坂に置く炭火に注ぎ火を消し不意をつけば、敵の敗北は間違いありません。」
彦火火出見はその計略を「善し」とし、そこで女軍を出陣させて敵の動向をうかがった。果たして、賊は大軍がすでに押し寄せて来たと思い込み、全戦力を挙げて待ち受けた。
ところで、これより前のことであるが、東征軍は攻めては必ず敵の陣地を取り、戦っては必ず勝利してきた。しかし兵士たちが疲弊しないわけではなかった。そこで、彦火火出見は「御謠」をつくって、将兵の心を慰撫した。
[ 楯並めて 伊那瑳の山の 木の間ゆも い行き見守らひ 戦えば 我はや飢ぬ 島つ鳥 鵜飼が伴 今助けに来ね ] (伊那瑳の山の木の間を通って、敵がいつ襲ってくるかと見張りながら戦っていると、私はいよいよ腹が減ってしまったよ。鵜飼のものどもよ、今すぐ(うまい鮎をさし入れて)助けに来てくれ。)このように戦意を鼓舞した上で、ついに男軍を率いて墨坂を越え、先に出陣させた女軍と後方から挟み撃ちにして賊を破り、首領の兄磯城らを斬り殺した。
十有一月癸亥朔己巳、皇師大舉、將攻磯城彥。
先遣使者徵兄磯城、兄磯城不承命。更遺頭八咫烏召之、時烏到其營而鳴之曰「天神子召汝。怡奘過、怡奘過。」兄磯城忿之曰「聞天壓神至而吾爲慨憤時、奈何烏鳥若此惡鳴耶。」乃彎弓射之、烏卽避去。
次到弟磯城宅而鳴之曰「天神子召汝。怡奘過、怡奘過。」時弟磯城惵然改容曰「臣聞天壓神至、旦夕畏懼。善乎烏、汝鳴之若此者歟。」卽作葉盤八枚、盛食饗之。因以隨烏、詣到而告之曰「吾兄々磯城、聞天神子來、則聚八十梟帥、具兵甲、將與決戰。可早圖之。」
天皇乃會諸將、問之曰「今、兄磯城、果有逆賊之意、召亦不來。爲之奈何。」諸將曰「兄磯城、黠賊也。宜先遣弟磯城曉喩之幷說兄倉下・弟倉下。如遂不歸順、然後舉兵臨之、亦未晩也。」
乃使弟磯城、開示利害。而兄磯城等猶守愚謀、不肯承伏。
時、椎根津彥、計之曰「今者宜先遣我女軍、出自忍坂道。虜見之必盡鋭而赴。吾則駈馳勁卒、直指墨坂、取菟田川水、以灌其炭火、儵忽之間出其不意、則破之必也。」
天皇善其策、乃出女軍以臨之。虜謂大兵已至、畢力相待。先是、皇軍攻必取、戰必勝、而介胃之士、不無疲弊。故、聊爲御謠、以慰將卒之心焉、謠曰、
哆々奈梅弖 伊那瑳能椰摩能 虛能莽由毛 易喩耆摩毛羅毗 多多介陪麼 和例破椰隈怒 之摩途等利 宇介譬餓等茂 伊莽輸開珥虛禰
果以男軍越墨坂、從後夾擊破之、斬其梟帥兄磯城等。 (『日本書紀』巻三 神武紀より抜粋)※原文中の「天皇」という言葉は、即位前であるため、生前の名前であり東征の権威付けを狙った名前「彦火火出見」に変換。
兄磯城討伐・磐余制圧の解説
ついに、、、ついに、ワイ大和到達。。。
日向で東征発議し、孔舎衛坂で撃ちのめされてから、さまざまな苦難を経て、、ようやっとたどり着いた「約束の地」。
イッツ中洲!
あれから何年経ったのだろう?そうか、、4年か、、、ずいぶん遠くまで来たもんだ、、、その刹那、神武の胸に去来した想いとは・・・そんなロマンに想いを致しながら、、
以下詳細解説。
- 11月7日に、東征軍は大挙して「磯城彦」を攻撃しようとした。
- 十有一月癸亥朔己巳、皇師大舉、將攻磯城彥。
→十一月の、癸亥が朔にあたる己巳は7日のこと。
「磯城彥」とは、磐余一帯を支配していた磯城兄弟を一括した呼称。
9月、宇陀の高倉山に登ったとき判明した状況のうち、「また、磐余邑には「兄磯城軍」があふれるほど満ちていた(復有兄磯城軍、布滿於磐余邑)」と伝える内容に対応。
「あふれるほど満ちていた」と伝える通り、屈強な敵戦士「八十梟帥」がうじゃうじゃいた模様。

▲奈良県桜井市。磐余橋北詰交差点!橿原から宇陀方面へ向かう165号線上にあります。こんなところにも「磐余」がっ!ロマンだよね、コレ。すげーロマンだ。。って、交差点にロマンを感じる私って、、、
次!
- 先ず、使者を派遣して「兄磯城」を召したが、兄磯城はその命に従わなかった。そこで、今度は八咫烏を派遣して召した。烏は兄磯城の軍営に到り鳴き声をあげ、「天神子が、お前を召されている。さあ、さあ(招きに応じよ)」と言った。兄磯城はこれを聞いて激怒し、「天圧神がやって来たと聞き、今まさに憤慨している時に、どうして烏めがこんなに嫌なことを鳴くのか。」と言い、弓を引きしぼって烏めがけて射ると、烏はすぐさま逃げ去った。
- 先遣使者徵兄磯城、兄磯城不承命。更遺頭八咫烏召之、時烏到其營而鳴之曰「天神子召汝。怡奘過、怡奘過。」兄磯城忿之曰「聞天壓神至而吾爲慨憤時、奈何烏鳥若此惡鳴耶。」乃彎弓射之、烏卽避去。
→八咫烏を使者として派遣。デカいなオマ、、、てかカラスなのに しゃべるんかーい!
八咫烏、もとはと言えば、天照大神が派遣した経緯あり。推定、頭部約1m、翼開長約10mのカラス。まーデカい。。こんなのが「軍営に到り鳴き声をあげ」って、相当なデスメタル。
ココでのポイントは3つ
- 山の敵と平地の敵。そこには自然と文明という対比構造あり。それに沿って戦い方を変えてます
- 「天神子」は皇孫にだけ使う超特別なワード。他と区別するための周到な仕掛けあり
- 兄は抵抗、弟は従順。コレ「兄の邪悪・劣弱、弟の善良・優強」という古代兄弟譚の類型によるもの
まずは1つ目。
①山の敵と平地の敵。そこには自然と文明という対比構造あり。それに沿って戦い方を変えてます
「先ず、使者を派遣して「兄磯城」を召したが、」とあるように、大和平野に入っての戦いは、これまでの戦い方とはガラリと変わります。
| 山の敵 | 平地の敵 |
| 有無を言わさず叩く | まず帰順勧告、意思確認。その上で従わないなら徹底的に叩く |
| 例:国見丘の八十梟帥など | 例:宇賀志の兄猾、磐余の兄磯城 |
※ちょいちょい登場する戸辺の皆さんは「誅罰」。どちらかというと山の敵と同様に有無を言わさず叩くカテゴリ。
コレ、「山と平地」という大きな枠組みをもとにつくられてる。そして、これは「自然と文明」という対比でもあります。
山・自然の中にいる良く分からない敵は徹底的に叩き、文明・文化の中にいる、つまりコミュニケーションできる敵は交渉を入れてから対応を決めてるんです。
今回、3度にわたって使者を派遣。
- 使者を派遣し召す
- 八咫烏を使い帰順勧告 :天神子(神武)の召喚の命を伝達
- 弟を使い帰順勧告 :利害を開示して説得
まず、相手の意思を確認する。そのうえで対応を決める。平地(文明側)の相手だからこそのコミュニケーション。
ちなみに、、、
コレ、東征神話的には「神武の成長」としての意味もアリ。
東征神話における最初の戦闘である孔舎衛坂の戦い。この時の神武は、とにかく突っ込むだけの(ある意味)稚拙な戦い方でした。
一方、さまざまな試練を乗り越えた後の戦い方はガラリと変わってます。相手の意思を確認するなんて、、余裕すら感じる王道路線。いやホント、よくぞここまで立派になって、、って私は何様でしょうか??
2つ目。
②「天神子」は皇孫にだけ使う超特別なワード。他と区別するための周到な仕掛けあり
「天神子が、お前を召されている。」とあります。この「天神子」は天照大神直系の子孫(皇孫)にしか用いない特別な言葉。
設定としては、「天神」にはいろいろあって、天照大神直系子孫の場合は「天神子」、その他の天神の子孫は「天神之子」。本シーンに続いて長髄彦最終決戦に突入。このとき「饒速日命」が活躍するのですが、このお方は「天神之子」。同じ「天神」の「子」なのですが、「天神子」と「天神之子」は全然違う。しっかり区別して使われてるんです。
尚、兄磯城の言う「天圧神がやって来たと聞き、」にある「天圧神」は、「天神子」を「威圧する神」として言い換えた表現。地元民からしたら突然やってきて、巨大なカラスを派遣してくるなんて、、新手の圧迫面接以外の何物でもない、、、
最後、3つめ。
③兄は抵抗、弟は従順。コレ「兄の邪悪・劣弱、弟の善良・優強」という古代兄弟譚の類型によるもの
神武の帰順勧告に対して「兄磯城はこれを聞いて激怒し、~中略~ 弓を引きしぼって烏めがけて射る」とあり、兄磯城は徹底反抗。一方、この後で伝える弟磯城は従順。
コレ、実は「兄の邪悪・劣弱、弟の善良・優強」という古代兄弟譚の類型によるもの。いつの時代も、兄は何をしでかすかわからない存在で。。弟はそんな兄の言動を見て空気読む、冷静に対処する。。。汗 すでに登場した「兄猾・弟猾」兄弟も同じパターンです。
3度の帰順勧告に対して対抗する兄磯城。
- 使者を派遣し召す →従わない
- 八咫烏を派遣し召喚の命を伝達 →激怒し矢を射て追い返す
- 弟を使い利害を開示して説得 →愚謀を堅守し、聴き入れない
と。言い方を変えると、これだけ話し合いの場を設けようとしたにも関わらず聞き入れないのであれば、それはもう仕方ないよねと。それは潰されても仕方ないよねと。そういうロジックが成立する仕掛けになってる、とも言えます。その意味では、非常に良く練られてますし、よそ者が地元に受け入れられるような流れになってる。コレ、しっかりチェック。
次!
- 次に、八咫烏は「弟磯城」の家にやってきて鳴き声をあげて、「天神子が、お前を召されている。さあ、さあ。」と言った。この時、弟磯城は恐れ畏まって居ずまいを正し、「臣である私は、天圧神がやってこられたと聞き、朝に晩に大変かしこまっておりました。まったく素晴らしいことです、烏よ。あなたがこんな風に鳴いてくれたのは。」と言い、さっそく葉盤八枚を作って食べ物を盛り、烏をもてなした。
- 次到弟磯城宅而鳴之曰「天神子召汝。怡奘過、怡奘過。」時弟磯城惵然改容曰「臣聞天壓神至、旦夕畏懼。善乎烏、汝鳴之若此者歟。」卽作葉盤八枚、盛食饗之。
→巨大なカラスが今度は弟の家で鳴き声をあげる、、、コレもコレで結構なデスメタル。。
兄の徹底反抗に対して、弟は恭順。「弟磯城は恐れ畏まって居ずまいを正し、」「朝に晩に大変かしこまっておりました。」「さっそく葉盤八枚を作って食べ物を盛り、烏をもてなした」とあるように、非常に空気の読める弟です。だって「天神子」が来てるんだから、、兄と弟の対比構造、コントラストが効いた描写ですよね。
次!
- そして、烏のあとに従って彦火火出見のもとに参上し、「私の兄の兄磯城が、天神子がいらっしゃったと聞き、八十梟帥を集めて武器を準備し、決戦を挑もうとしております。早急に手だてを講じなさいませ。」と言った。
- 因以隨烏、詣到而告之曰「吾兄々磯城、聞天神子來、則聚八十梟帥、具兵甲、將與決戰。可早圖之。」
→恭順姿勢のみならず、兄を売る弟。。
コレ、思い起こせば、宇陀の宇賀志で登場した「兄猾・弟猾」と同じパターン。あの時も同様に、弟は兄を売り、神武に兄の秘策をバラしてたっけな。。
コレ、もちろん、古代の兄弟譚という話型の一つなんですが、、見方を変えると、地元民の中にも神武を迎え入れる勢力がいた、ってことでもあり。つまり、神武を単なる部外者、侵入者としてではなく、支配者として受け入れるための土壌づくりとして弟が登場してる、とも言えますよね。その意味では、非常に考えられてる神話ですし、日本神話編纂チームの創意工夫が素晴らしい訳です。
次!
- 彦火火出見は、すぐさま将たちを集め、問うた。「今、兄磯城は、やはり反逆の意があり、召してもやって来ない。どうしたらいいだろうか。」 将たちは、「兄磯城は悪賢い賊です。まずは弟磯城を派遣してしっかりと諭し、あわせて兄倉下と弟倉下も説得させるのがよいでしょう。それでも帰順しないのであれば、その後に兵を挙げて戦いに臨んでも遅くはありません。」と申し上げた。
- 天皇乃會諸將、問之曰「今、兄磯城、果有逆賊之意、召亦不來。爲之奈何。」諸將曰「兄磯城、黠賊也。宜先遣弟磯城曉喩之幷說兄倉下・弟倉下。如遂不歸順、然後舉兵臨之、亦未晩也。」
→神武が臣下に意見を聞いてる、、、、((;゚Д゚)); ガクブル
こんなの初めて。。。今まですべて背負ってきた神武が、、、すべて自分で決めてきた神武が、、、ここへきて臣下に献策させるなんて、、、不安だった?どうしていいか分からなかった?いえいえ、そんな話ではございません。部下を活かすのがリーダーの務めであります。これこそまさに神武の真骨頂。神武の成長なのであります。。って私は何様でしょうか?
臣下の献策は以下
- まずは弟磯城を派遣してしっかりと諭す
- あわせて兄倉下と弟倉下も説得させる
- それでも帰順しないのであれば、その後に兵を挙げる
と。
やっぱ、運用をしっかり踏まえてます。運用=統治。なんでもかんでも武力でどーん!はダメなんです。必ず地元民の反感を生んでしまうので。それでは統治がうまくいくはずがない。みんなが受け入れてくれないと。みんなが神輿を担いでくれないと、、うまく行く訳がない。そのための、説得。コミュニケーションです。コレ、非常に重要なポイントなのでしっかりチェック。
ちなみに、、「あわせて兄倉下と弟倉下も説得させるのがよいでしょう。」とあり、いきなり登場「兄倉下と弟倉下」。コレ、恐らく、兄磯城の仲間で、八十梟帥の一種。兄弟で登場。こいつらも大きな勢力をもっているので説得してこちら側に引き入れとけ的な意味合い。
それでも納得しないなら、いよいよ兵を挙げて潰しましょうと、
次!
- そこで弟磯城を遣わし、利害を明らかに示して分からせようとした。しかし、兄磯城らはなお愚かな謀に固執し、帰伏するのをよしとしなかった。
- 乃使弟磯城、開示利害。而兄磯城等猶守愚謀、不肯承伏。
→弟を派遣して説得に当たらせる。説得には「利害を明らかに示して」とあるようにメリット・デメリットをロジカルに因数分解。。
結果は、、、
解けません、解りませんでしたー!!
ということで、剣を持ってこーい!
- その時、椎根津彦が計略をめぐらせて言った。「この上は、まず我が女軍を遣わして、忍坂の道から出陣させましょう。これを賊が見れば必ずや精鋭部隊を残らずそこに向かわせるはずです。私は、勇猛な兵を馬で走らせ直ちに墨坂を目指し、菟田川の水を取って墨坂に置く炭火に注ぎ火を消し不意をつけば、敵の敗北は間違いありません。」
- 時、椎根津彥、計之曰「今者宜先遣我女軍、出自忍坂道。虜見之必盡鋭而赴。吾則駈馳勁卒、直指墨坂、取菟田川水、以灌其炭火、儵忽之間出其不意、則破之必也。」
→出ました。平地の敵は計略駆使。将軍・椎根津彦の登場です!
計略の内容は陽動作戦。女軍、つまりサブ部隊(力の弱い部隊)を派遣し引き付ける。その間に、墨坂に向かい、菟田川の水で墨坂に置く炭火を消し不意をつく!

ちょっと引いて大局でみると、、、

ということで、挟み撃ちにしてやっつけるという極めて巧妙な作戦であります。
ここで、なんで墨坂の炭火を消すのか?についてロマン解説を。
一言で言うと、墨坂に置いてあった炭火は敵の勢いを象徴するものだから、なんなら敵パワーの源泉ということ。うん、ロマンだね。
初登場は、宇陀の高倉山シーン。
ココで、「国見丘には八十梟帥がいて、女坂 には「女軍」を、男坂には「男軍」を配置し、墨坂には真っ赤に焃っている炭を置いていた。」とあり、要は、敵の勢いを象徴するものとして「墨坂」の「真っ赤に焃っている炭」を伝えてる訳です。
「墨坂の炭火」というとキャンプとかで使う炭レベルを想起しがちですが、とんでもない! 敵勢力の勢い、なんならパワーを象徴する訳ですから、その勢いたるや、カンカン轟轟、とんでもない勢いだったはず。
それを、「菟田川の水を取って墨坂に置く炭火に注ぎ火を消し」ちゃう訳なんで、された側からしたら「不意」を突かれること間違いなし。なんならパワーの源が消されちゃう訳なんで、テンションはガタ落ち間違いなし。非常に巧妙な作戦なのであります。しかも、それが敵勢力に分かるくらいなんで、そもそもの炭火の巨大さたるや、、、

▲磐余と墨坂の距離は165号線経由で9.5km。不意を突かれた!と兄磯城たちが確認するためには、相応の巨大な炭火が必要だが。。??
コレ、神話ロマン。
次!
- 彦火火出見はその計略を「善し」とし、そこで女軍を出陣させて敵の動向をうかがった。果たして、賊は大軍がすでに押し寄せて来たと思い込み、全戦力を挙げて待ち受けた。
- 天皇善其策、乃出女軍以臨之。虜謂大兵已至、畢力相待。
→この計略、いいのね!??
ということで早速実行。このあたりが素晴らしい訳です。部下の献策に対して、良いものは良いとして実行する。素晴らしいリーダーであります。成長したな・・・
で、兄磯城の軍は陽動作戦にひっかかり、「大軍がすでに押し寄せて来たと思い込み、全戦力を挙げて待ち受けた」訳ですね。こっちはちょっとしか兵を出してないのにっ(ざまあ的な・・)。
次!
- ところで、これより前のことであるが、東征軍は攻めては必ず敵の陣地を取り、戦っては必ず勝利してきた。しかし兵士たちが疲弊しないわけではなかった。そこで、彦火火出見は「御謠」をつくって、将兵の心を慰撫した。
- 先是、皇軍攻必取、戰必勝、而介胃之士、不無疲弊。故、聊爲御謠、以慰將卒之心焉、謠曰、
→突然の振り返りシーン。挿入。
連戦連勝を誇る東征軍、その兵卒といえど、疲労蓄積は否めず、、ただよう疲労感を敏感に察知した神武が歌で愛撫、いや「将兵の心を慰撫」する。
なんて素晴らしいリーダーなんだ!部下に寄り添える、気持ちを察することができるリーダー!サイコーです!
ということが言いたい。
- [ 楯並めて 伊那瑳の山の 木の間ゆも い行き見守らひ 戦えば 我はや飢ぬ 島つ鳥 鵜飼が伴 今助けに来ね ] (伊那瑳の山の木の間を通って、敵がいつ襲ってくるかと見張りながら戦っていると、私はいよいよ腹が減ってしまったよ。鵜飼のものどもよ、今すぐ(うまい鮎をさし入れて)助けに来てくれ。
- 哆々奈梅弖 伊那瑳能椰摩能 虛能莽由毛 易喩耆摩毛羅毗 多多介陪麼 和例破椰隈怒 之摩途等利 宇介譬餓等茂 伊莽輸開珥虛禰
→
「楯並めて」は枕詞。ある言葉を導くために、その直前に置かれ、句調を整えたり、情緒的な 意味を添えたりする語。通常は五音で訳しません。で、楯を並べて射ることから、「伊那瑳の山」の「い」と、「い行き見守らひ」の「い」にかかります。技巧的な表現。
「伊那瑳の山」は、宇陀の南にある伊那佐山とされてます。
宇陀高倉山から眺めたときに判明した周囲敵だらけの状況。見慣れぬ土地。いつ襲ってくるかも分からない極限の緊張状態の中で、木々の間を見張りながら進む。。降りしきる雨、ずぶ濡れになりながら一歩一歩進んでいく兵士たち、、、ロマンだ。。そりゃお腹も空くよね。。
「島つ鳥」は、鵜にかかる枕詞。島にいる鳥の意味。「鵜飼」とありますが、コレ、8月に吉野巡幸したときに出会った「苞苴担」の子を阿太の養鵜部の始祖と伝えてました。「苞苴」は天皇に奉る「御饌」のこと。
ということで、この「御謠」は、慰労が趣旨。さしもの武きもののふも、連戦連勝とはいえ疲弊した。そんな兵士たちに美味な鮎でも食べさせて慰労したいという意味なんです。コレ、国見丘の戦いでも登場してましたね。あわせてチェックです。
次!
- このように戦意を鼓舞した上で、ついに男軍を率いて墨坂を越え、先に出陣させた女軍と後方から挟み撃ちにして賊を破り、首領の兄磯城らを斬り殺した。
- 果以男軍越墨坂、從後夾擊破之、斬其梟帥兄磯城等。
→神武が兵士たちに寄り添い、歌を歌ってくれた・・コレはやるしかない!!!!!
ということで、大いに乗せられた、いや鼓舞された兵士たち。椎根津彦の計略どおり、主力部隊である「男軍」を率いて墨坂へ。10km離れても見えるくらい巨大な炭火を消し不意打ち!さらに、ぐるっと回って挟み撃ち!!


無事、「首領の兄磯城らを斬り殺した。」とのことです。現場からは以上です。
まとめ
「兄磯城討伐と磐余制圧」
大和平野へ入っての戦いはこれまでの戦い方とはガラリと変わります。
| 山の敵 | 平地の敵 |
| 有無を言わさず叩く | まず帰順勧告、意思確認。その上で従わないなら徹底的に叩く |
| 例:国見丘の八十梟帥など | 例:宇賀志の兄猾、磐余の兄磯城 |
コレ、「山と平地」という大きな枠組みをもとにつくられてる。そして、これは「自然と文明」という対比でもあります。
山・自然の中にいる良く分からない敵は徹底的に叩き、文明・文化の中にいる、つまりコミュニケーションできる敵は交渉を入れてから対応を決めてるんです。
実際、彦火火出見は平野に入って戦い方を大きく変えてました。
3度にわたって使者を派遣し、帰順勧告を行います。
- 使者を派遣し召す →従わない
- 八咫烏を派遣し召喚の命を伝達 →激怒し矢を射て追い返す
- 弟を使い利害を開示して説得 →愚謀を堅守し、聴き入れない
まず、相手の意思を確認する。そのうえで対応を決める。平地の相手だからこそおこなう「交渉」という訳です。
さらに、この「自然と文明」という対比構造を土台に、「彦火火出見の成長」というビフォー・アフター構造が重ねられています。
- ビフォー:まだよく分かっていなかったころ。あのころは若かったねの頃
孔舎衛坂の戦いで分かる通り、戦い方はとにかく突っ込むやり方。敵や地形の情報を十分に持たず、部下の意見も聞くことなく、とにかく自分の思い先行で突っ込めば負けるのは必定ですよね。 - アフター:いろいろ分かってきたこと。なんか最近大人になったねの頃
兄猾討伐、兄磯城討伐、長髄彦討伐で分かる通り、まず意思確認から入る。その上で従わないので叩く。また、部下の献策を戦術に採りいれる。自分だけでなく、相手の意思や部下の案といった情報を様々に加味しながら行動するようになってる。結果として負けることが無くなり、連戦連勝の展開へ。
単に、山と平地という対比構造で終わらせず、そこに神武の成長も重ね合わせる事で重層的な深みを持たせています。
部下を適材適所で活躍の場を提供、的確な判断・指揮、兵士たちへの心配りなど、全てが彦火火出見の名将ぶりを際立たせています。まさに理想的な指導者として描かれているわけですね。それもこれも重大な試練を一つ一つを懸命に乗り越えるなかで得た気づきと成長によるものだった、と言えます。
単なる「敵征伐」の話ではなく、こうした重層的な構造をもって組まれてるので、非常に深いし、解釈が豊かになります。やっぱり東征神話、タダモノではありません。古代日本人の叡智と創意工夫がスゴすぎです。学びたいのはココ。
神話を持って旅に出よう!
神武東征神話のもう一つの楽しみ方、それが伝承地を巡る旅です。以下いくつかご紹介!
●神武天皇聖跡磐余邑顕彰碑:敵どもがあふれかえっていた地!
●墨坂伝承地:敵勢力のパワーを象徴する地!
●伊那佐山:ドキドキしながら兵士たちが見張った地!
●外山(とび):挟み撃ちにしたのはきっとこのあたり!
続きはコチラ!いよいよ最終決戦へ!
神武東征神話のまとめ、目次はコチラ!
 佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
佛教大学名誉教授 日本神話協会理事長 榎本福寿
埼玉県生まれ(S23)。京都大学大学院文学研究科博士課程国語学国文学(S53)。佛教大学助教授(S58)。中華人民共和国西安外国語学院(現西安外国語大学)文教専家(H1)。佛教大学教授(H6)。中華人民共和国北京大学高級訪問学者(H13)。東京大学大学院総合文化研究科私学研修員(H21)。主な書籍に『古代神話の文献学 神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む』がある。『日本書紀』『古事記』を中心に上代文学における文献学的研究成果多数。
参考文献:『古代神話の文献学』(塙書房)、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館)、『日本書紀史注』(風人社)、『日本古典文学大系『日本書紀 上』(岩波書店)
[itemlink post_id=”13035″] [itemlink post_id=”13037″] [itemlink post_id=”13038″] [itemlink post_id=”13039″]
こちらの記事もどうぞ。オススメ関連エントリー
どこよりも分かりやすい日本神話解説シリーズはコチラ!
日本神話編纂の現場!奈良にカマン!




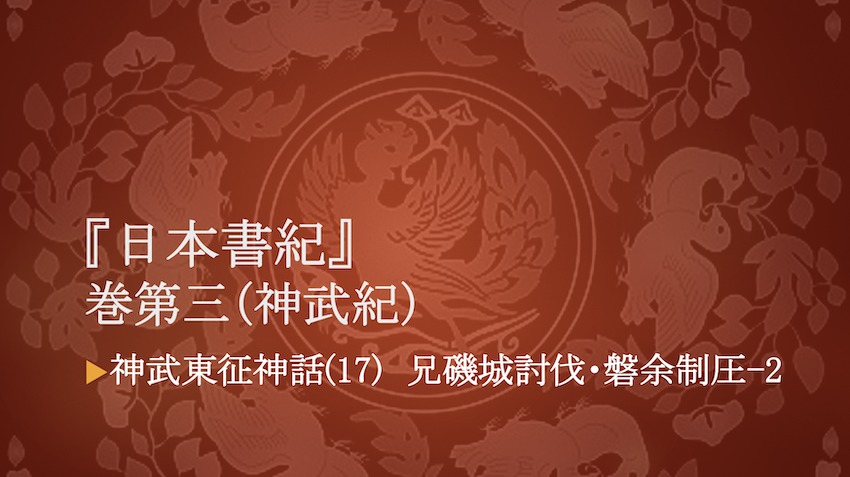































お気軽にコメントされてください。お待ちしております!